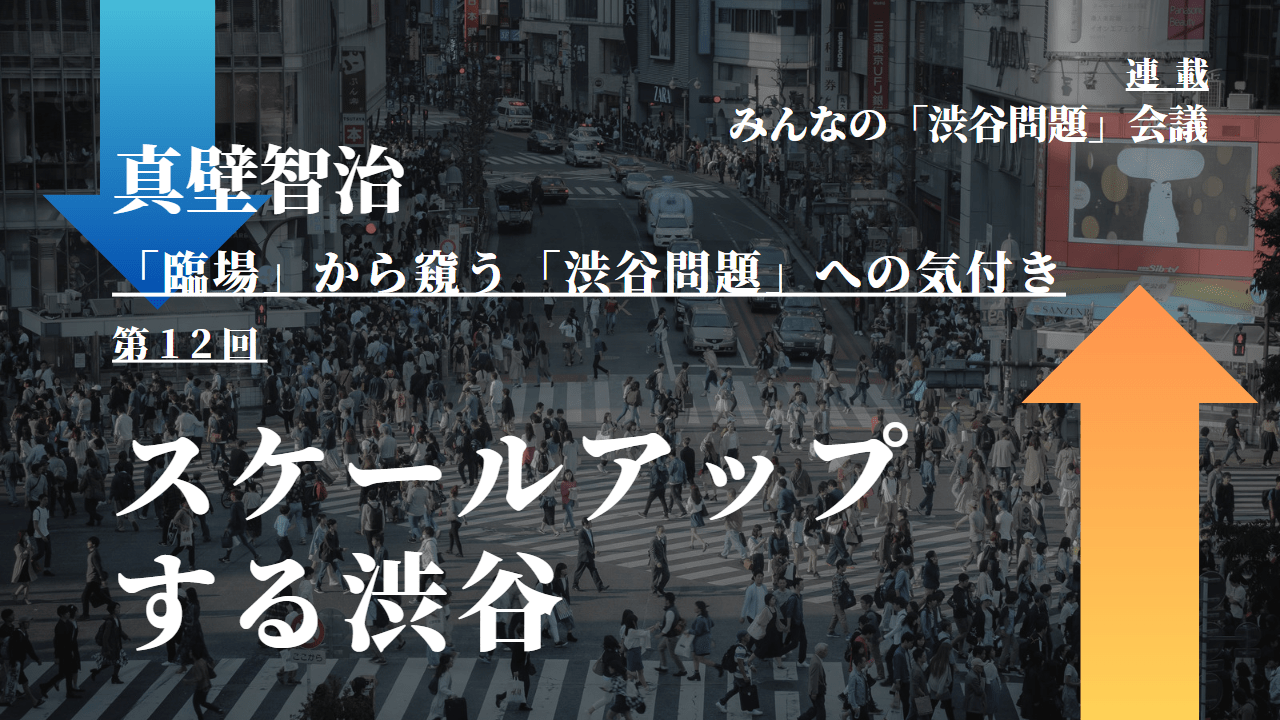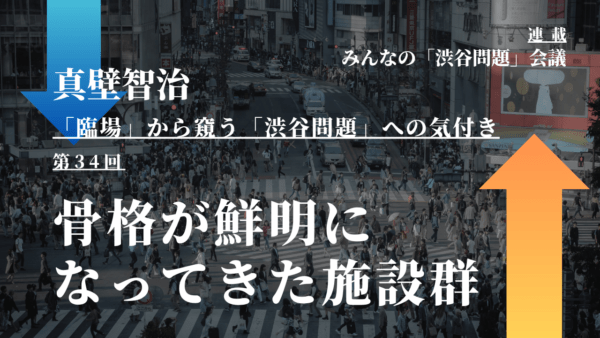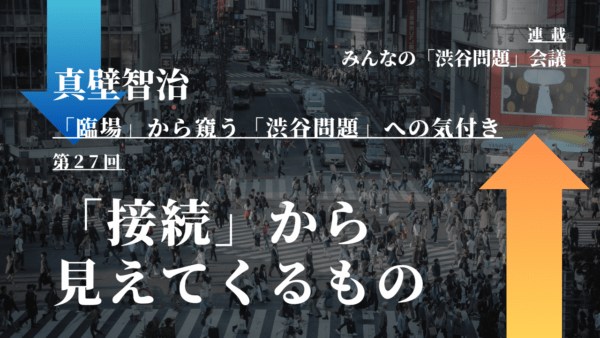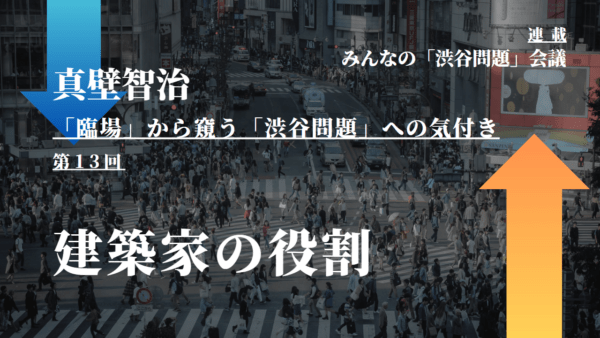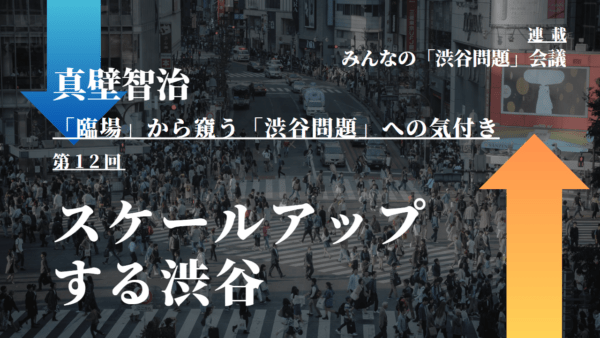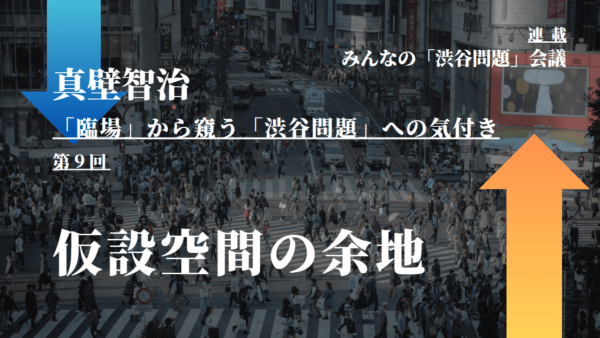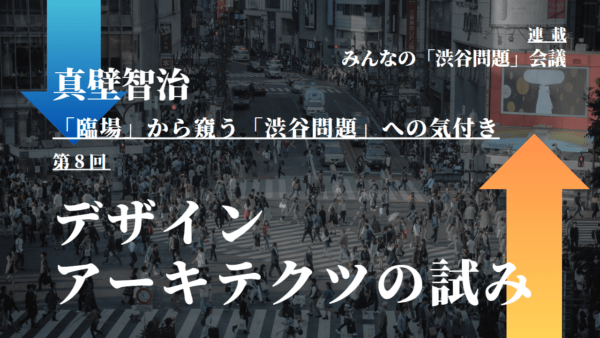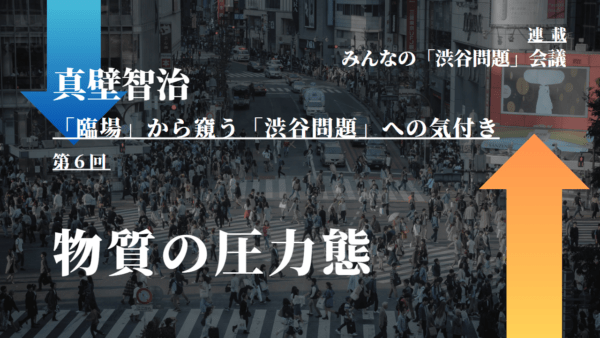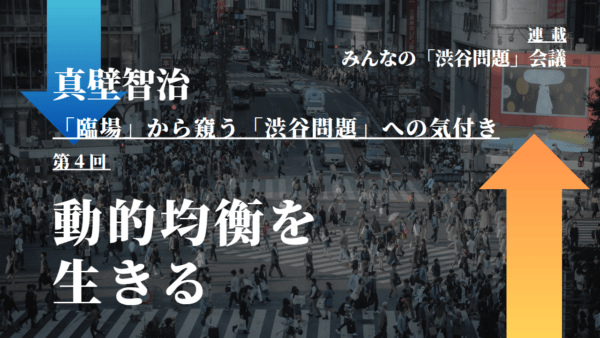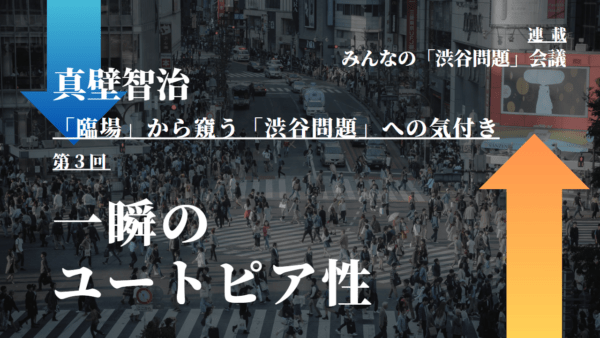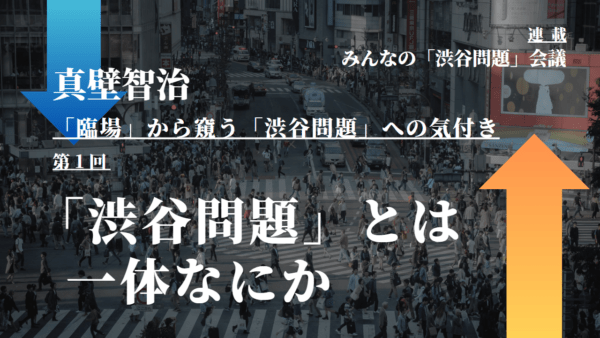スケールアップする渋谷
– 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第12回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。


≪横にスクロールしてお読みください≫
スケールアップする渋谷
二〇一九年一月二〇日、「渋谷スクランブルスクエア」東棟と「渋谷ヒカリエ」へ通じる「ヒカリエブリッジ」とがいよいよ接続・開通した。
再開発工事現場のステージにおいては大きな局面を迎えたことになります。
実際には、これまでそれらを隔てていた仮設壁が取り外され、東棟の外部に面した一部分が接続されただけなのですが、そこに突如出現したのが「街に開かれた」巨大な垂直空間「アーバンコア」だったのです。
あのひしゃげた破調部分のファサードの内側に息を潜めていた大空間がそれだった。
「アーバンコア」からの渋谷の躍動感のある眺望体験が初めてだっただけにそのインパクトは大きかった。たった仮設隔壁の一枚向こうにこんなスペクタルが準備されていたなんて、と驚きました。デザイン・アドバイザーの建築家・内藤廣の工事の過程を面白くさせたい、との発言を一瞬私は思い出した。まさにこれこそが、私がこれまで劇場型工事としてきたものの最大級の演出効果になっていた。小さな部材が織り上げるノイジーな巨大垂直ヴォイド空間の体現である。
この体験を含め、「渋谷スクランブルスクエア」東棟と地上及び地下の東急東横線・メトロ地下鉄線との移動を円滑にしようと図った「アーバンコア」での体験が一気に渋谷のスケールの印象を大幅に変えてしまった。
特に、地上から地下へ、地上から上階へのエスカレーターに依る大量円滑移動を可能にするタテのヴォイド空間の存在が渋谷のまちのスケールアップの印象を強く作り替える要因になっている。
基本的には近景としての「渋谷スクランブルスクエア」東棟接地階の階高とメトロ銀座線渋谷ホームスラブ床裏と地上との高さとがその場のスケールアップ感を生んでいるのだが、その上で「アーバンコア」のタテのヴォイド空間が渋谷のスケールアップの印象に一層の拍車を掛けている。
大型建築群そのものが駅前中心部に与えるスケールアップ感は、近景でよりもむしろ、中景での光景から強く感じられるものになっている。
「渋谷ヒカリエ」・「渋谷ストリーム」・「渋谷スクランブルスクエア」東棟の三棟は、スリバチ地勢の谷底よりもそこから少し外れた「通り」や「坂」からの方が、そのスケールアップ感をリアルに体感できるのです。スケールアップ感を感じさせる要件には、目前の圧倒感に加えて全体のヴォリュームが把握出来ることが肝心になります。渋谷再開発では足元からの施設全体のヴォリュームが把握し易い。
つまりは、渋谷のまちのスケールアップ感は、駅を起点にその移動と共に現われる渋谷駅中心部の近景・中景、そして遠景との関わりから三様のスケールアップ感が体感され、それらの像のコラージュとして渋谷のスケールアップ感が認識されることになる。
近景でのスケールアップを感じさせる「アーバンコア」のタテのヴォイド空間もそこにグランドフロア、大地の存在が介在してのものになるのです。身近に感じる街のスケール感は大地に立つことで得られるものが基本、地上を離れると感じにくくなる。大地は常にそこに立つ人のリアルなスケール感を刻んで周囲との照応を可能にし、更に人のふるまいもまさに地に足の着いたものにしてくれるのです。
「渋谷スクランブルスクエア」東棟の接地階はこうした大地が裸の状態で躯体下に形成されていて、そこから直接的に「アーバンコア」にアプローチすることになる。渋谷のスケールアップ感の体感はこの近景に組み込まれたタテのヴォイド空間から全て始まる、と言っても過言ではないだろう。
中景で把握される渋谷の新たなスケール感は「通り」や「坂」を往来している折の「アイ・ストップ」や「エッジ」として実感されて認識されます。「歩行のまち・渋谷」だからこそ思わぬ場所で駅前中心部の中景に出会うことになり、改めて渋谷のスケールアップ感をグラデーショナルに認識することになる。
その際、中景が描き出す中心部の「エッジ」に向ってそれぞれの場所から補助線を軸として引いてみると、見事に地勢の谷底に軸がフォーカスしてゆくのが分かる。これは奇しくも中景を介しての渋谷でのスリバチ底部の顕在化となっているものでもあります。
渋谷駅前中心部のスケールアップが遠景としても眺望出来るようになり、それは渋谷再開発のアイデンティティとして映る。
それまでの遠方から渋谷駅前が識別出来る建物は「渋谷マークシティ」と「クロスタワービル」ぐらいしかなかったが、いずれも建物の識別には際立った特徴は見当たらない。つまりは誰にも分かる充分な「ランドマーク」の遠景として認識されるものでは在りえなかったのです。
やはり遠景としてのランドマーク効果が圧倒的に高いのは「渋谷ストリーム」になる。建物の表皮に施したフラクタルなオプティカル効果が遠方から極めて有効に、渋谷駅前中心部のスケールアップの様を「位置」として示すようになった。これは言葉を換えれば、渋谷駅前中心部の大型建築群によるスケールアップ化の象徴として遙かな「遠景」で誰にでも分かるものとして「渋谷ストリーム」が機能していることになる。
こうして渋谷のスケールアップは渋谷駅前中心部の「近景」、「「中景」そして「遠景」からそれぞれに体感されたそれらのスケールの感覚と光景の姿がコラージュとして織り重なって認識されるものになってゆく。
その感覚と姿でコラージュされた渋谷のスケールアップ像の中心に近景で体感されるあのタテに大きなヴォイド空間が、闇の様に鎮座しているのである。スケールアップしたタテ軸のヴォイド空間が渋谷の地勢の寄り代になっている。
私にはこのスケールアップ化の「構造」が渋谷のスリバチ底部の地霊への鎮魂のように想われるのです。
一方、南街区の大型建築「渋谷ストリーム」の外皮のデザインは、タテ長のパネルがランダムに鉛直方向に張られている構成となっていて、私は「フラクタル・スキン」(自己相似的表皮)と呼んでいる(デザインアーキテクト、シーラカンスアンドアソシエイツ小嶋一浩+赤松佳珠子)。
ここでは「渋谷スクランブルスクエア」東棟のファザード・デザインと異なり、むしろ中景や遠景の見え方を意識したランドマーク的なファサードの破調デザインとなっており、国道二四六号線・明治通り・青山通りからの建物の視認性を意識してのものだろう。
二棟の大型建築のファサード・デザインに見るオプティカル効果の役割分担は理に適っていると思えます。こんなにも近接して建つ二棟の大型建築のファサード・デザインに「破調」が全面的に主題化している事例は、これまでのモダニズム建築の歴史の上からもあまりなかったように思う。『錯乱のニューヨーク』ですら、「破調」は見当たらない。
なぜ、渋谷再開発で、デザインアーキテクトたちは大型建築のファサード・デザインに「破調」を自覚的に選択したのだろうか。そこにデザインアーキテクトたちの見識と反骨の一部が見え隠れする。
単純に「ノイズ」をファザード・デザインに投与するのではなく、渋谷が持つ固有な谷底地勢の中で、谷地の底に建つ「渋谷スクランブルスクエア」東棟は圧倒的に「見上げストレス」を生み出す。近目での壁面の圧迫感の緩和化がテーマになったのだろう。
また谷底に建つ「渋谷ストリーム」の遠目からの「レジビリティ」(分かりやすさ)、「イメージアビリティ」(イメージのしやすさ)もファサード・デザインのテーマとして自覚されたはずです。
その上で、ファサード・デザインのオノマトペを誘導しやすい「ユラ・ユラ」(「渋谷スクランブルスクエア」東棟)や「パタ・パタ」(「渋谷ストリーム」)が均一性を打ち破る「破調」としてデザイン・モチーフになった、と考えられる。
このように、オプティカル効果としてのオノマトペ感覚を大型建築に「破調」として投与したのはデザインアーキテクトの極めて限られたデザイン関与の内で成し得た良識であったのではないか。
又、「渋谷フクラス」でもファザード・デザインに「ノイズ」投与の試みがみられた(デザインアーキテクト手塚貴晴・手塚由比)。
「渋谷フクラス」は「ヒカリエ」・「渋谷ストリーム」・「渋谷スクランブルスクエア」東棟とはその規模感が異なります。従って、そこに多少違う問題意識からのデザイン・トライアルが散見される。
ここで注目したいのは建物の「正面性」の資質についてです。
「渋谷フクラス」のファサードは大きく上下二層で等分に分割され、接地階を含む八階分ほどの下層とその上層とのシンプルな構成となる。接地性が強い下層の部分に、よりインパクトのあるデザイン性を持たせ、上層にボンヤリとした浮遊感の漂うオプティカルな表象を与えていて、建物ファサード全体としてノイズ感のある表情を創出しています。その裡でも、「アーバンコア」の取り込みが建物ファサードの下層部分に人の動きと流れとを視覚化させていて、通りの街並みに活気のある様相をもたらしている。
このように「渋谷フクラス」は接地性の強いノイズとしての建物の正面性を示していて、開発されたどの施設よりも「猥雑さ」を創出し、街の賑いと共振している。これも重要なデザインアーキテクトの判断であった。
見て来たように、デザインアーキテクトには担当する施設デザインが限定されていた裡で、「デザイン会議」が示す「お題」への試みを図ったものになっていた。
しかし、その「お題」への試みも、デザインアーキテクトのデザイン関与に限界があり、踏み込んだ「ディテール」や現場でのデザイン管理に支障を来している場面には多く出会った。「渋谷スクランブルスクエア」東棟の「アーバンコア」に至ってはデザイン領分の分断が顕著に現れていた。これらも当然「渋谷問題」として検証されるべきことだ。
これから竣工する「桜丘口地区」施設や渋谷駅「中央棟」などにどの様なデザインアーキテクトたちのデザイン・トライアルが図られたのか丁寧に読み解いてゆく必要が強くあろう。そこに、デザインに依る公共性の在り方を「渋谷問題」の大事な部分に加えることになるのであるから。
従ってこの様な局面からのデザインアーキテクトのデザイン・トライアルには注視してゆきながら狼煙を立ち昇らせてゆくことになる。
(つづく)
連載記事一覧