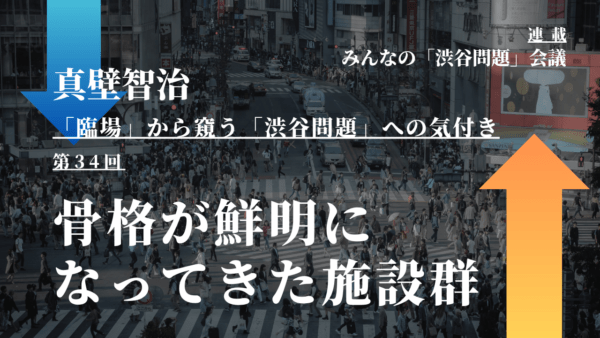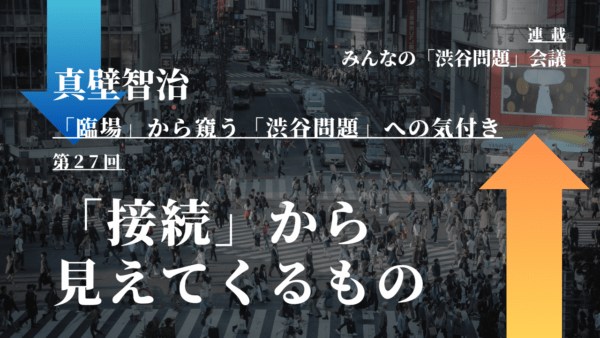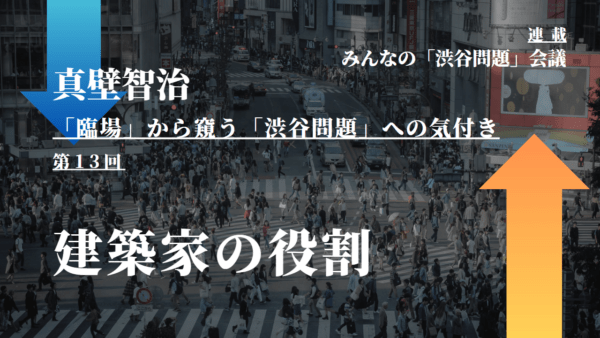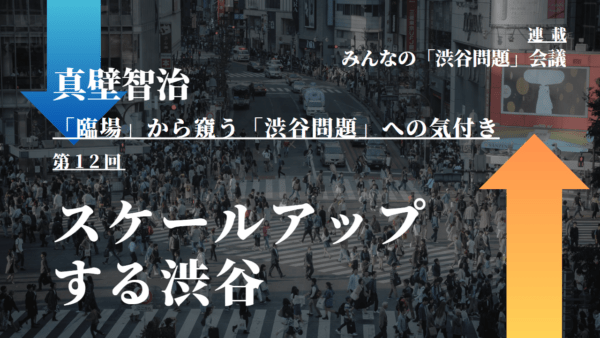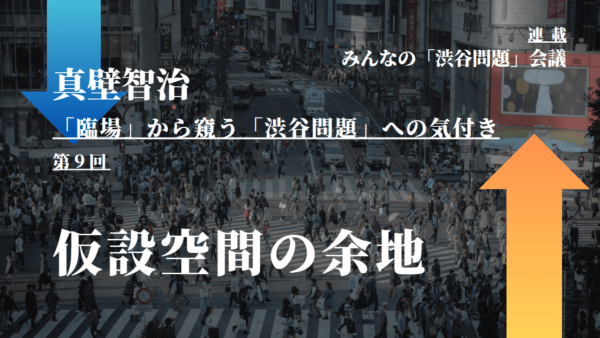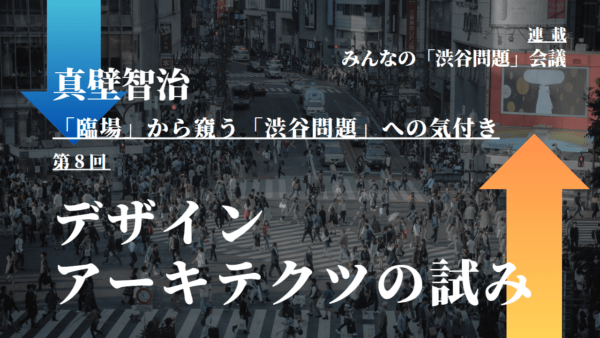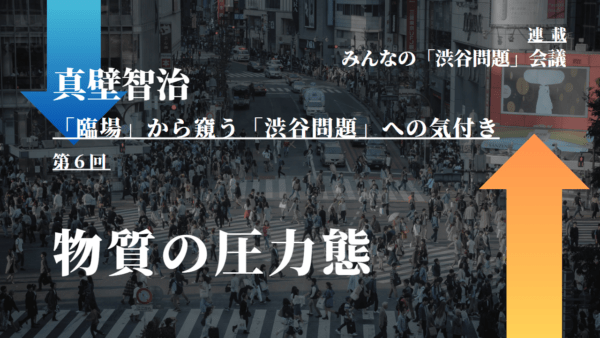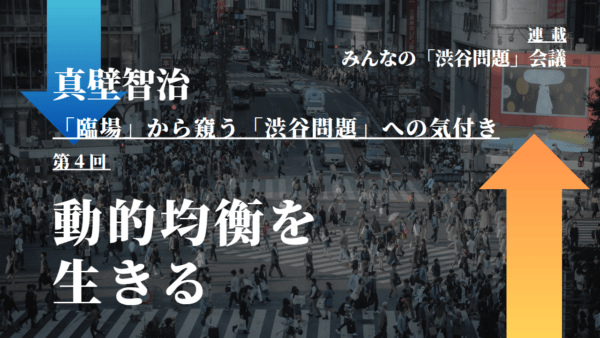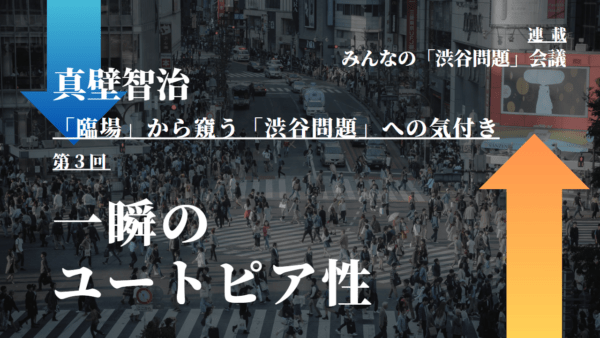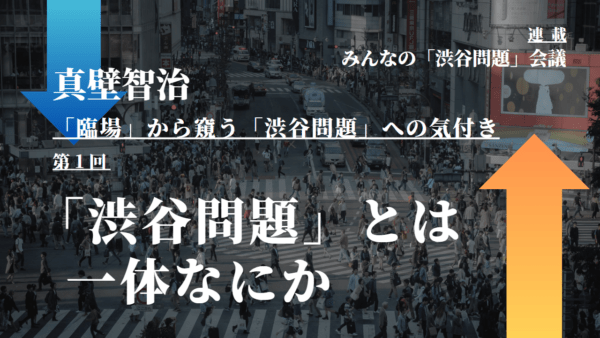対比的な場所 – 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第25回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。


≪横にスクロールしてお読みください≫
対比的な場所
都市の魅力を生むものに場所の対比的なコンテンツがある。対のコンテンツとして把握されるもので、様相としての表と裏、明と暗、良場所と悪場所などがそれで、その対比のコントラストが強ければ強い程、都市の魅力が深まり、謎めく。
この対比的な様相は互いにアンビバレンツな位相を示し、絶対的な表とそれに拮抗する絶対的な裏とが併存する。更に絶対的な表にも裏が潜み、絶対的な裏にも表が現われる。表と裏とがセミラティスな構造を示す様相の力学的動態が都市の魅力を生むのです。
郊外の街の退屈さは過半こうした場所の対比性が感じられないことに起因するもので、細やかな表だけで、対比される裏もない。裏がないから表が際立たず、そこに場所の対比的な力学的動態が生じない。
渋谷再開発は巨大開発となるものだが、この開発が結果として生み出すであろう場所の様相のコンテンツにはどの様なものが想定されるのか。そのことが街としての深さの印象を決定付けるからだ。
今からそれを観相することが批評としての「渋谷問題」にも連なることになろう。
まず予測されるのは当該開発が巨大であるが為に生まれてくる「スケール」の文脈、つまりメガスケールとミニスケールとの対比がどの様に体験されるのか、であろう。
ここでの「ミニスケール」を私たちの身の丈スケール、ヒューマンスケール、と規定しておく。
私たちが日々体験する渋谷再開発での場所の印象は建物自体の圧倒的な巨大さから来るエッジとしてのスケール感と、低層部(FOOT)で体感されるヴォイドのヴォリューム感や部材・メンバーの大きなサイズ感などの相乗的メガスケール感覚から形成されるものになる。
はたして、私たちの場所の印象の裡にミニスケールは介在し、更にそれがメガスケールとの対比性を感じさせるまでに拮抗し合うような緊張感は、そこに伴ってくるのだろうか。
皮肉なことに二つのスケールの拮抗する対比性が場に強く感じられたのは、建物が竣工する前、ブリコラージュな仮設空間が存在した時点までであったことです。そこには確かなスケールの対比性が感じられ、アンビバレンツな位相を露出していたものだった。
建設中の建物内に仮設空間が設定され、挿入されていた時には、エンジニアリングが生み出すスケール感とブリコラージュが生むミニスケール感とが対比し合って、豊かで密度感のある場所の仮象的印象を形成していました。
それがいざ竣工し仮設空間が除去されるや、それまでの対比されるスケール感が拮抗するスリリングな場所の印象は消失した。
しかし、当該開発に関わるデザインアーキテクトたちは自覚的に屹立するメガスケールに対比されるミニスケールを建物に植え付けようと試みて来たのです。デザインアーキテクトの一人隈研吾はそれを「ノイズ」として、全面化されるメガスケールに挑んだ。
結果的にはそこにスケール対比から生じる場所の感覚を充分に生むには至っていないのだが、メガスケールに些かでも「ノイズ」が陰りとして対比効果を与えているのだけは読み取れる。
しかし、再開発事業全体が必然的に「華やかさ」を全面指向している裡で、ノイズが生み出す「陰り」はあまりに微力だった。
「華やかさ」は人の意識や行動を外へと向かわせる。渋谷再開発の上位コンセプトとなる「エンターテインメントシティ渋谷」を体現する上からも、「華やかさ」は必須の要件であったろう。なによりも「華やかさ」は消費意欲を扇動し、人びとの関心をどんどん外延化させるからです。ここでのエンターテインメントは当然、人の外延化を梃子に刺激と欲望の消費の上に成立するものであり、それが都市の国際競争力を持つとされて来ていた。
結局、渋谷再開発事業からは場所の対比性を窺うことは出来ず、なによりもその必要性や必然性が全く求められていなかったのである。「華やかさ」の一極主義が都市再生特区開発の本意・本音なのが今さらの様に頷けるのです。
一方、「陰り」は人の意識や行動を内へと導く。「陰り」は人間が生きてゆく環境の内に必要なもので、人は「華やかさ」に心が引かれる反面、「陰り」も強く求めます。人が疲れた時、一人無心になりたい時などに「陰り」が優しく包み入れてくれるからだ。そうしたアンビバレンツな場所の対比性のバランスの中に私たちの生の営為が在るのです。
「華やかさ」が外向への資質を持つのに比し、「陰り」は飽くまで内向に開かれる入口となるものだ。都市の健全さとはこの二様の資質を備えることに尽きる。
渋谷再開発事業に動員されたデザインアーキテクトたちが共通に抱いた密やかなコミットメントは華やかさを要件とする再開発事業に「陰り」の根拠となる接地性をデザインしようとしたことだった。
それはこのままでは街は面白くならない、渋谷がダメになる、と言う強い危機感からのコミットメントであっただろう。
巨大施設の接地性に「ノイズ」(「渋谷スクランブルスクエア」東棟)や「猥雑さ」(「渋谷フクラス」)や「記憶」(「渋谷ストリーム」)などの陰りを、華やかさに抵抗するものとして投企されたものだった。
しかし、些かでも細やかな「陰り」の投企は、巨大な渋谷再開発の様相に在って、人びとの足を一瞬止めさせる効果は担えているのかもしれない。
ところで、渋谷の街中の陰りのある特異な場所の一つに「ガード下」が在る。
私たちは渋谷の華やかな場所と対比して、この陰りのある暗い場所の存在を心に刻み、街のダイナミックな面白さを享受しているはずです。
渋谷の駅周辺には大小合わせて八か所程の「ガード下」を見ることが出来る。
JR・京王井の頭・メトロ各線の「ガード下」が七か所、内、「ガード下」に幹線道路が通る大きなものが四か所、井の頭線の小さな「ガード下」が一か所。残りの二か所がJR線路の「ガード下」で、しかも共に小さなトンネル状になっている。
それにJRから井の頭線への大きな連絡通路の「ガード下」一か所が加わり、都合八か所。
渋谷の街へのアクセスは過半駅を起点とします。従って街へのアクセスは駅周辺の各々の「ガード下」の陰りを取り込んで、幾つもの華やかさの体験は生まれて来た。
都市の成熟にはこうした、一方での生きられた陰りの場所が不可欠なものになるのです。
特にここではガード下の「トンネル」を観相してみたい。その存在感が渋谷には重要な場所の対比性となっているからだ。
都市に在って「トンネル」は、単なる機能から意味的公共性としても私たちの生活に関わってくる存在なのではないか。
一定の状態が均質に続く「パス」としてトンネル体験は理解されるが、存在論的には、明かりと闇の濃淡がグラゼーションを帯びる意味的な胎内空間として感知され、ただ暗いだけの「パス」ではなく、表情を伴った都市の陰りを表出する貴重な場所になっているのです。
都市のトンネルはそこに陰りが付帯するから恐怖心を与えがち、が、意味的公共性としての発見をそこに見出すと途端にトンネルの存在が一気に変ってきます。
トンネルが私の皮膚に迫り、私の身体がトンネルの陰りに放り出される。それまでのシ-クエンシャルに体験されていた街の感覚コードとは全く異質な体験感覚へスウィッチが切り替わる。
表情のある暗さを帯びる小さな場所は人を内に向かわす資質を持つ。これも都市の「ノイズ」となろうか。
乾いた温湿度感、包み込む様な体温のある圧力感、鈍く身体を震わす残響音、壁に施された祝祭感のあるグラフィティ、冷気を含む都市の澱の様な臭い、壁を舐める様に走る闇のグラゼーション、汗をかいた様な黒々とした床、身を潜める自転車の群れの息遣い、などが暗さの中に息衝く。
私に開かれた内向世界がそこに広がっているのです。
都市の中を流れるだけでなく、場所に留まり、その場を感じる機会を持ちたい。都市に群れるだけでなく、独りの時を見つめられる場所を持ちたい。
そんな内向する動機に応えてくれる場所の一つが都市の小さなトンネルなのです。そこに身を置くとトンネルと私との感応が自然に起動し、身体の陰りと一体となるのが分かる。場所との一体化は都市との身体化の感覚を伴うもので、そこに安堵感の様なものが満ちてくる。この陰りを生む小さな場所が建築ではなく土木であることも暗示的だ。
建築は前提にその施設用途が特定されている。しかし、土木には担う機能が設定される以外、その存在についての解釈には規制がない。
これは建築家青木淳が「遊園地」と「原っぱ」のメタファーで問題提起したものとも重なります。
施設用途が定まる「遊園地」と用途が自在な「原っぱ」とが建築と土木の存在と重なり、都市の土木に「原っぱ」を見、内に開かれる入口の可能性が感じられるのも故あること
ではないか。
都市の土木やオープンスペースが生む都市の陰りは、独りのための文化を育む資質を持つ。
都市の孤独を楽しむ、自分に向き合う、身体を静かに休める、などの穏やかなふるまいを育むこと、又その都市の陰りが弱者にこそ豊かに開かれるもので在ることを強く望みたい。
それらはいずれも、都市の意味的公共性から派生する余地としての権利的公共性や、自生的公共性を獲得してゆく道筋を必要とするものなのです。
こうした都市の生きられた「陰り」の場所が一方に存在してこそ、「華やかさ」とアンビバレンツな対比性がそこに生じることになる。
都市の意味的公共性の内にはこうした場所の対比性が潜んでいるから深く、面白い。
ここで忘れてはならないことが在る。
都市の陰りとなるものは人びとに依り発見されるものだ、と言うことなのです。デザインアーキテクトたちが投企として試みた陰りも、人びとに発見されなければ気付かれることがない。
都市の陰りは「原っぱ」の如く非用途設定な場所にこそ見出されることになる。
従って、都市の陰りは予定調和的な計画からは生まれ難く、まずは都市の内に発見されること、その上で場所の穏やかなふるまいが想像されることからしか始まらない。
果して渋谷再開発事業から生み出される華やかさに拮抗する陰りのバランスを私たちはどこに見出すことになるのだろうか。
見出せなければ、渋谷の深さは遠のくばかりだ。
このことも重大な「渋谷問題」の一角を担うものになろう。

(つづく)
連載記事一覧