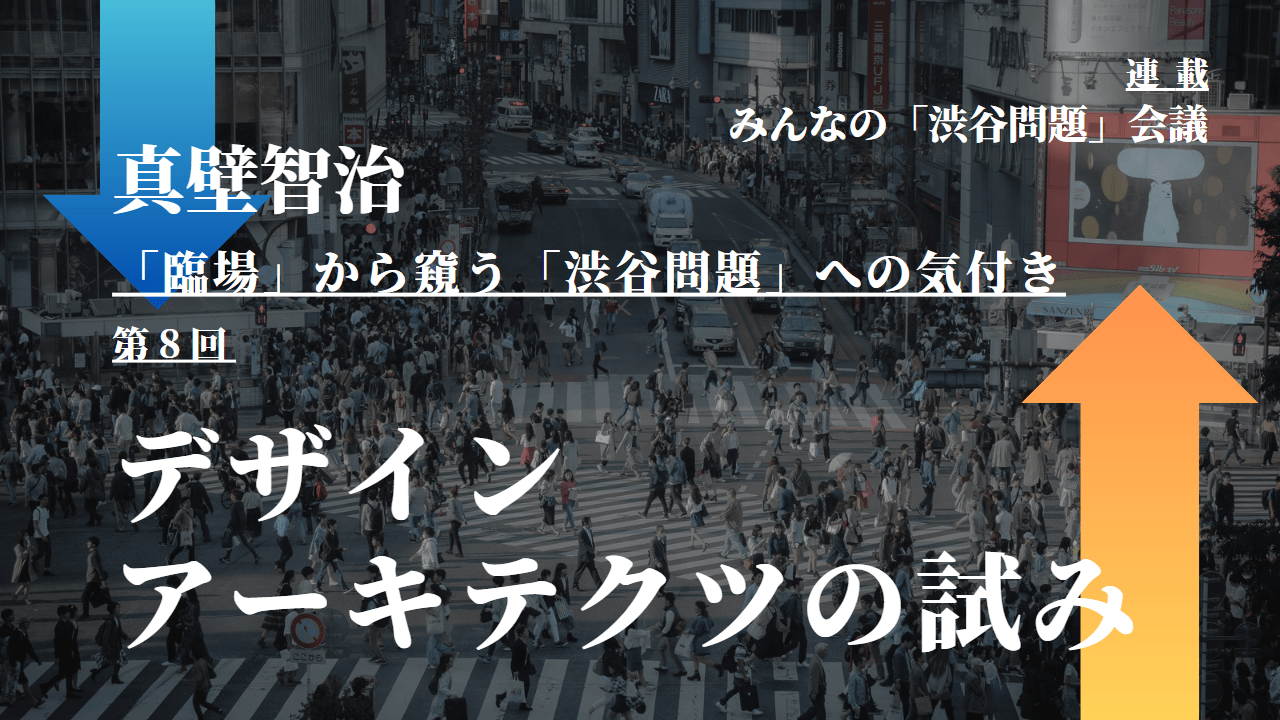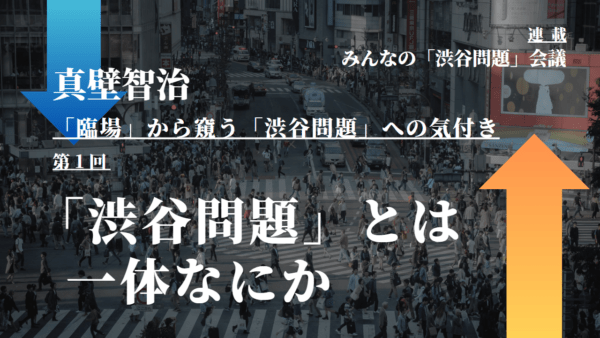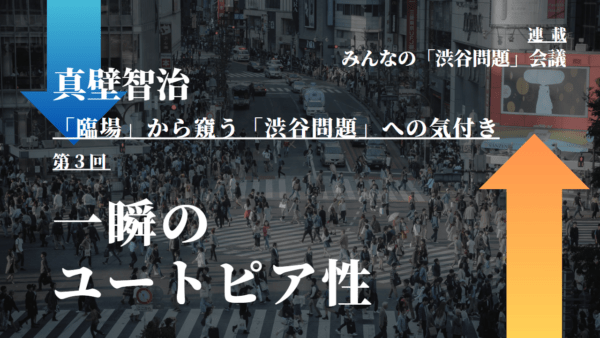デザインアーキテクツの試み
– 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第8回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。


≪横にスクロールしてお読みください≫
デザインアーキテクツの試み
渋谷再開発推進に際しての特徴の一つに「デザインアーキテクツ」方式が挙げられる。
「デザイン会議で合意し、各街区にはそれぞれデザインアーキテクトを採用してもらうことにしました。この仕組みの導入は、何よりも『超高層ビルを建てるだけのビジネス』ではだめになると思ったからです。容積だけが価値となる安易で経済的な超高層ビル事業の潮流に抗いたかった。どうせ建つなら渋谷らしく多様な建物が建つようにしたかったのです。デザインアーキテクトが関われるのは設計の一部なので、建築家としては必ずしも本意な立場ではないと分かっていましたが、蓋を開けてみると各街区に建築家が参画してくれました」(内藤廣)
内藤は渋谷には「ノイズ」が必要だと考えていた。開発を整理し過ぎると、人の心が入り込む隙間が失われる。特にこの渋谷では、大規模開発だからこそ新たなノイズを創出すべき、と思ったと言う。
その為にも「できるだけ隣と違う形」をデザインアーキテクトに求めた、とのこと。
その結果、垂直移動都市装置となる「アーバンコア」はそれぞれに施設担当するデザインアーキテクトによるデザイン競演の体を成している。
とは言え、「アーバンコア」は極めて公共性の強い人びとの往来・移動の場となる為、単純に「隣と違う形」を作り出せば済むことではない。
「アーバンコア」デザインの最大の問題は、その場の公共性と私たちの身体性とをどの様に関係付けて新たな都市体験の創出にコミット出来るか、に掛かっていたはずだ。ところが、デザインアーキテクトたちの関わりの限界か、「形」は生み出し得ても、肝心の私たちの身体性との接触を生む「ディテール」が不足している。例えば階段一つ取っても、新たな公共性を身体が感応するものは一切成っていない。「デザイン」の分割が招く欠陥である。ディテールがお粗末な「デザイン」は最終的に評価に値しない。
私はむしろ、デザインアーキテクトたちのデザイン上の試みについては各個の「アーバンコア」よりも、各施設の「外装デザイン」での試みに注目してきた。
渋谷再開発での超高層ビル群は隣棟間隔が狭く高密度化を呈してくる。
こうした容易に推察出来る事態に対してどの様な超高層ビルの表皮デザインを試みるのか。建物の形態操作(アイコン)ではなく、表層操作である。「渋谷スクランブルスクエア」東棟の外装デザインには垂直方向のタテの揺らぎが確認される。
これはファサードのパターン構成によるオプティカル効果から生まれるもので、圧倒的な垂直壁面への視覚的ストレスを緩和する狙いが推測されます。特に、「ヒカリエブリッジ」の往来時、対面する「渋谷スクランブルスクエア」東棟の壁面は少し揺らぐようで楽しく、気持ちが静まる。
一方、南街区の「渋谷ストリーム」のファサードも垂直方向に白い金属パネルが二層・三層分にランダムに掛け渡され、巨大な垂直壁面の均一で退屈な表情にリズム感を作り出している。
ここでも、壁面のオプティカル効果への意図が明瞭に読み取れよう。
いずれの大型建築のファサード・デザインも建築の表面の「均一」を回避し、「破調」を主題にしているのが分かる。これも偶然であろうか。それとも渋谷再開発のデザイン・コードに「破調」が設定されていたのであろうか。これも「ノイズ」(内藤廣)発想から誘導されたものと理解できるのではないか。
「スクランブルスクエア」東棟の外皮デザインは、タテの細いストライプ(幅が均質でなく、次第に細くなったり太くなったりしている)がガラスの表面に等間隔に施されている構成で、微かな鉛直の揺らぎが外皮から感じ取れます(デザインアーキテクト隈研吾)。ストライプのタテ方向の微妙な破調が重力感を伴う緩い揺らぎを誘い、建物の外装の表皮がタテに緩く波打つように上下に波動していて「フラジャイル・サーフェイス」と呼んでもいいものだ。
繰り返しと僅かな変調がファサード・デザインの構成上のモチーフになっていて「バーチャル・デザイン」の実践になっている。
これはデザインアーキテクト、隈研吾が独自に開発してきたフラジャイルなファサード・デザインの流れに含まれるものだが、ここでは特に、大型建築の外装表現が建物の近景としての見え方を意識したものになっているのです。
建物を見上げる際のオプティカルな効果が狙いとする、極めて意図的なデザインとなるもので、同時に谷底を挟んで向き合う「ヒカリエ」のファサード・デザインとの調和やシナジーも、意図されてのものだろう。


一方、南街区の大型建築「渋谷ストリーム」の外皮のデザインは、タテ長のパネルがランダムに鉛直方向に張られている構成となっていて、私は「フラクタル・スキン」(自己相似的表皮)と呼んでいる(デザインアーキテクト、シーラカンスアンドアソシエイツ小嶋一浩+赤松佳珠子)。
ここでは「渋谷スクランブルスクエア」東棟のファザード・デザインと異なり、むしろ中景や遠景の見え方を意識したランドマーク的なファサードの破調デザインとなっており、国道二四六号線・明治通り・青山通りからの建物の視認性を意識してのものだろう。
二棟の大型建築のファサード・デザインに見るオプティカル効果の役割分担は理に適っていると思えます。こんなにも近接して建つ二棟の大型建築のファサード・デザインに「破調」が全面的に主題化している事例は、これまでのモダニズム建築の歴史の上からもあまりなかったように思う。『錯乱のニューヨーク』ですら、「破調」は見当たらない。
なぜ、渋谷再開発で、デザインアーキテクトたちは大型建築のファサード・デザインに「破調」を自覚的に選択したのだろうか。そこにデザインアーキテクトたちの見識と反骨の一部が見え隠れする。
単純に「ノイズ」をファザード・デザインに投与するのではなく、渋谷が持つ固有な谷底地勢の中で、谷地の底に建つ「渋谷スクランブルスクエア」東棟は圧倒的に「見上げストレス」を生み出す。近目での壁面の圧迫感の緩和化がテーマになったのだろう。
また谷底に建つ「渋谷ストリーム」の遠目からの「レジビリティ」(分かりやすさ)、「イメージアビリティ」(イメージのしやすさ)もファサード・デザインのテーマとして自覚されたはずです。
その上で、ファサード・デザインのオノマトペを誘導しやすい「ユラ・ユラ」(「渋谷スクランブルスクエア」東棟)や「パタ・パタ」(「渋谷ストリーム」)が均一性を打ち破る「破調」としてデザイン・モチーフになった、と考えられる。
このように、オプティカル効果としてのオノマトペ感覚を大型建築に「破調」として投与したのはデザインアーキテクトの極めて限られたデザイン関与の内で成し得た良識であったのではないか。
又、「渋谷フクラス」でもファザード・デザインに「ノイズ」投与の試みがみられた(デザインアーキテクト手塚貴晴・手塚由比)。
「渋谷フクラス」は「ヒカリエ」・「渋谷ストリーム」・「渋谷スクランブルスクエア」東棟とはその規模感が異なります。従って、そこに多少違う問題意識からのデザイン・トライアルが散見される。
ここで注目したいのは建物の「正面性」の資質についてです。
「渋谷フクラス」のファサードは大きく上下二層で等分に分割され、接地階を含む八階分ほどの下層とその上層とのシンプルな構成となる。接地性が強い下層の部分に、よりインパクトのあるデザイン性を持たせ、上層にボンヤリとした浮遊感の漂うオプティカルな表象を与えていて、建物ファサード全体としてノイズ感のある表情を創出しています。その裡でも、「アーバンコア」の取り込みが建物ファサードの下層部分に人の動きと流れとを視覚化させていて、通りの街並みに活気のある様相をもたらしている。
このように「渋谷フクラス」は接地性の強いノイズとしての建物の正面性を示していて、開発されたどの施設よりも「猥雑さ」を創出し、街の賑いと共振している。これも重要なデザインアーキテクトの判断であった。
見て来たように、デザインアーキテクトには担当する施設デザインが限定されていた裡で、「デザイン会議」が示す「お題」への試みを図ったものになっていた。
しかし、その「お題」への試みも、デザインアーキテクトのデザイン関与に限界があり、踏み込んだ「ディテール」や現場でのデザイン管理に支障を来している場面には多く出会った。「渋谷スクランブルスクエア」東棟の「アーバンコア」に至ってはデザイン領分の分断が顕著に現れていた。これらも当然「渋谷問題」として検証されるべきことだ。
これから竣工する「桜丘口地区」施設や渋谷駅「中央棟」などにどの様なデザインアーキテクトたちのデザイン・トライアルが図られたのか丁寧に読み解いてゆく必要が強くあろう。そこに、デザインに依る公共性の在り方を「渋谷問題」の大事な部分に加えることになるのであるから。
従ってこの様な局面からのデザインアーキテクトのデザイン・トライアルには注視してゆきながら狼煙を立ち昇らせてゆくことになる。
(つづく)
連載記事一覧