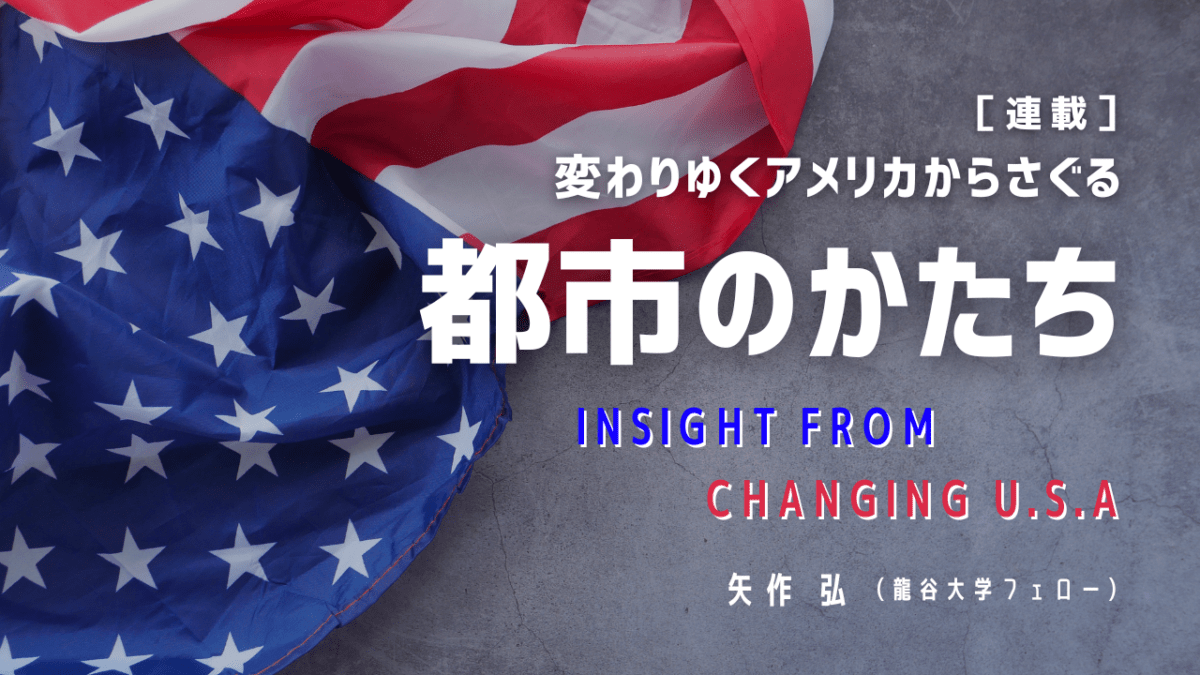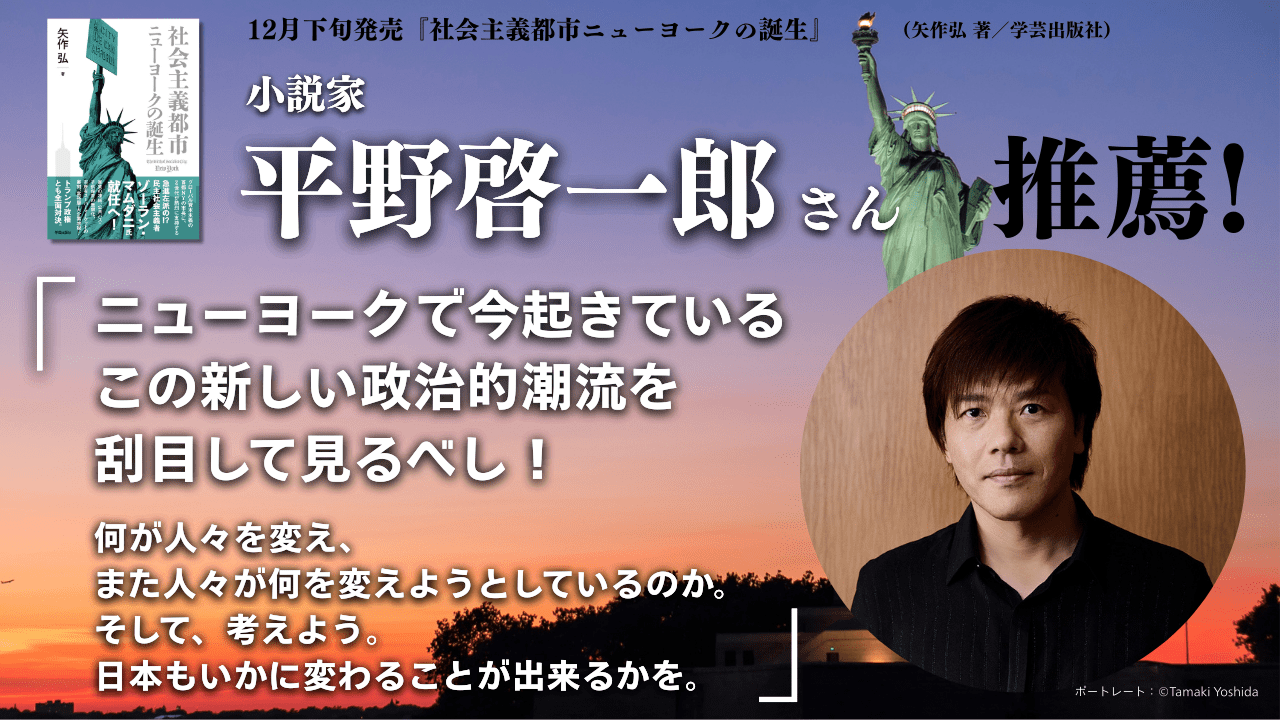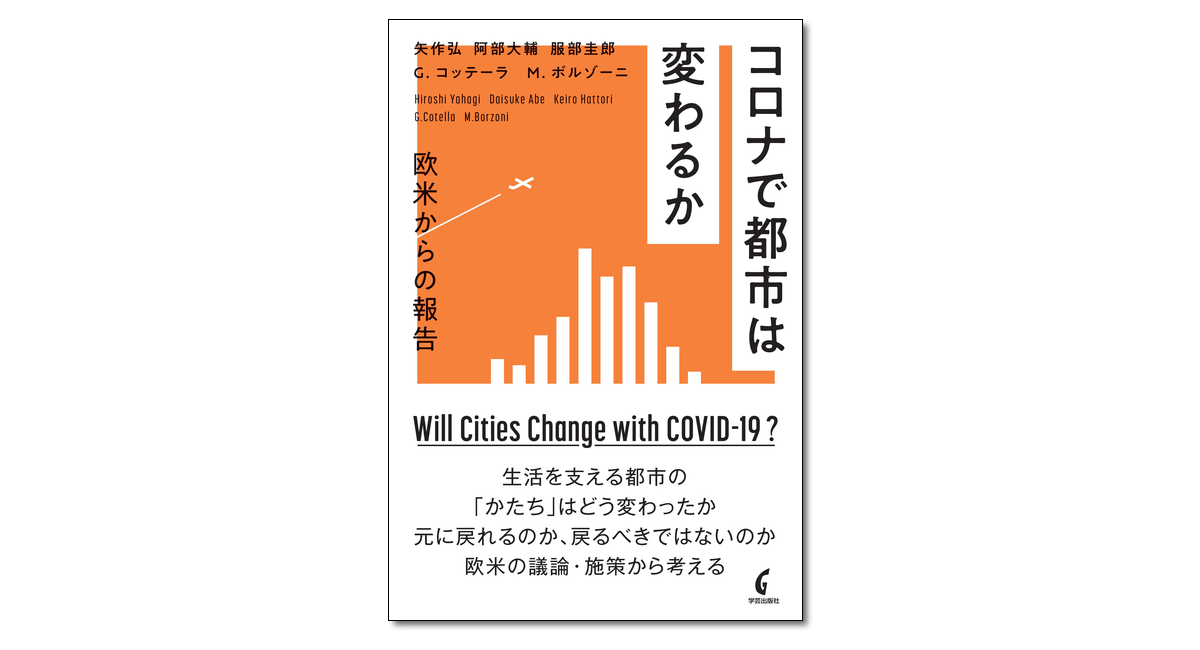第1回「戸建て住宅専用地区の廃止と郊外の変容」連載『変わりゆくアメリカからさぐる都市のかたち』
アメリカで展開されている都市政策の最新事情から注目の事例をひもときつつ、コロナ禍を経て変容するこれからの都市のありよう=かたちをさぐります。
筆者
矢作 弘(やはぎ・ひろし)
龍谷大学フェロー
「戸建て住宅専用地区」とは
アメリカでは、都市計画の戸建て住宅専用地区(single-house-zoning)を廃止する動きが広がっています。都市計画は基礎自治体に権限委譲されていますが、州政府が法律を改正し、州内全域で戸建て住宅専用地区の規制を緩和する事例も増えています。
戸建て住宅専用地区は、一戸建て住宅以外の建物を認めない、というゾーニングです。玄関口が幾つもある連棟型の住宅やアパート、あるいは商店などの立地を認めない。最低敷地面積規制(小規模敷地を認めない)や、複数台止まれる駐車場を附設することを義務付けている場合もあります。したがって見映えのよい高級住宅地になっています。
都市計画で最初に戸建て住宅専用地区を決めたのは、バークレー(カリフォルニア)で1916年でした。以来、100年余の歴史があります。「戸建て住宅専用地区は、居住の自由を制限する」という主張がなされ、裁判になりましたが、連邦最高裁が1926年、「合憲」の判断を下しました。
戸建て住宅専用地区の廃止に最初に動いた州は、オレゴンです。以後、リベラルな、民主党の強いブルー州を中心に同趣旨の法改正に動く州政府、基礎自治体の都市政府が増えています。
オレゴンは2019年に法改正しました。戸建て住宅専用だった地区に、ほかのタイプの住宅開発を認める、という内容です。具体的には、それまでの戸建て住宅専用地区に、
- 人口25,000人以上の都市、及びポートランド都市圏内では、2-4連棟型住宅の建設を認める。
- 人口10,000人以上の都市では、2連棟型住宅を建てることができる。
ことが定められました。
“これぞ、アメリカ”という風景の変容
「超高層ビルが林立するニューヨークの摩天楼街がアメリカを象徴する風景か」と問われれば、決してそうではない。建築空間的にも、社会/文化空間としても、ニューヨークはアメリカの異端です。
「これぞ、アメリカ」という風景をワンショット撮るとすれば、青芝の繁る、前庭付きの戸建て住宅が延々と並び建つ郊外の風景を置いてほかにない。各家に2、3台の車が止まっています。
移動はもっぱら車です。家内には、大型冷蔵庫、食器洗い機、最新の大型スクリーンテレビなどの耐久消費財が並び、広いリビングルームには、ソファーセットが置いてあります。豊かな、もっぱら白人/中間所得階層の住区です。

そこに1950年代後半以降、ショッピングセンターが出現しました。1970年代には、ビジネスパークが開発され、治安の悪化したダウンタウンを逃避して来るオフィスの受け皿になりました。
戦後のアメリカに拡散したこの「郊外の“かたち(建築的、可視的な意味に止まらず、人々の暮らし方/働き方を含む)”」は、古今東西、それに比肩するものはなく、都市学的な意味で「アメリカ例外主義」を具現した時空と言われています。
半面、営まれている日々の暮らしは、近所付き合いが希薄です。むしろ孤立しています。郊外暮らしの人々の間には、「周囲と違うこと」を嫌う中間所得階層に独特の生活観が漂い、同質性を競い合う性癖があります。そこには、桐島洋子『淋しいアメリカ人』、D.リースマン『何のための豊かさ』が活写した、凡庸で刺激の乏しいコミュニティが広がっています。
人口動態の変化とマイノリティの郊外居住
戸建て住宅専用地区の廃止は、この風景を塗り替えます。アメリカ例外主義の終焉です。アパートなどいろいろなタイプの住宅が混在することになります。母屋の隣に小規模建物(コテージや小商店、カフェなど、ADU=Accessory Dwelling Units)を建てられます。
戸建て住宅専用地区の廃止をめぐっては、賛否両論があります。その間で厳しい論争があります。それぞれの論点については、次回、紹介することとし、ここではなぜ、戸建て住宅専用地区の廃止が広がっているのか、その事情について記述します。
1.人口動態の変化
第一に人口動態の変化が、その背景にあります。ベビーブーマーは80%弱がマイホームを所有しています。次にマイホームの取得に動くのは、ミレニアムです。その半分(49.5%)は貸家住まいでこれから住宅を買うことになります(RentCafe)。
次の次に家庭を持つのはゼネレーション〈Z〉です。この世代は、74%がアパートか、親元暮らしです。
若い世代には、ダウンタウンにあるコンドミニアムは高額で手が出ない。郊外に新居を探すことになります。しかし、アメリカでは、2008年の経済危機が終わると住宅価格が高騰しました。
コロナ禍が沈静し、住宅はさらに値上がりしています。頭金を親に頼って購入する場合も、小規模な住宅を郊外に探すことになります。アパート暮らしを続けるにしても、結婚し、子供が生まれれば、郊外の、広いスペースのアパートに引っ越さなければならない。結婚年齢を迎え、郊外を目指すミレニアム、さらにはZ世代の住宅需要が戸建て住宅専用地区の廃止を後押ししています。また、ベビーブーマーも子育てが終わって高齢化し、小さな住宅か、集合住宅での暮らしを希望しています。
2.マイノリティの郊外居住
マイノリティの郊外居住が進展しています。歴史的に黒人はインナーシティ(都心と郊外の間の住工混在地)に集住していましたが、昨今は郊外暮らしの黒人が急増しています。
海外からの移民も、以前は大都会の、韓国人は韓国人の――移民コミュニティを最初の着地先にしていましたが、近ごろは郊外に直接やって来ます。エッジシティ(職住、娯楽機能などが集積する自己完結型の郊外都市)が発達し、そこに社会インフラ労働(ホテルや飲食店、病院などのサービス労働など)が生まれているためです。
結果、郊外に低賃金労働者が増え、その住宅需要を満たすためにアパートの建設を認める――などの動きにつながっています。
揺らぐ郊外の“かたち”の輪郭
人口動態の変化は、既に「郊外の“かたち”」に影響を及ぼしています。アメリカ例外主義として語られて来た「郊外の“かたち”」は、その輪郭が揺らいでいます。
白人中間所得階層の住区が、マイノリティ、低所得階層も暮らす多様性のある住区に変わっています。もっぱら車で買い物に来る、郊外暮らしの金字塔になっていたショッピンセンターが相次いで破綻し、跡地がアパート/コンドミニアム、オフィス、商店街などが並ぶ混合用途に転換されています。ビスネスパークにも、タウンハウスが併設されるようになりました。郊外でも、歩いて暮らせるまちづくり(徒歩か自転車で移動)が推奨されています。
戸建て住宅専用地区を廃止する動きは、こうした「郊外の“かたち”」の変容と伴走して進行しています。
(つづく)
連載記事一覧