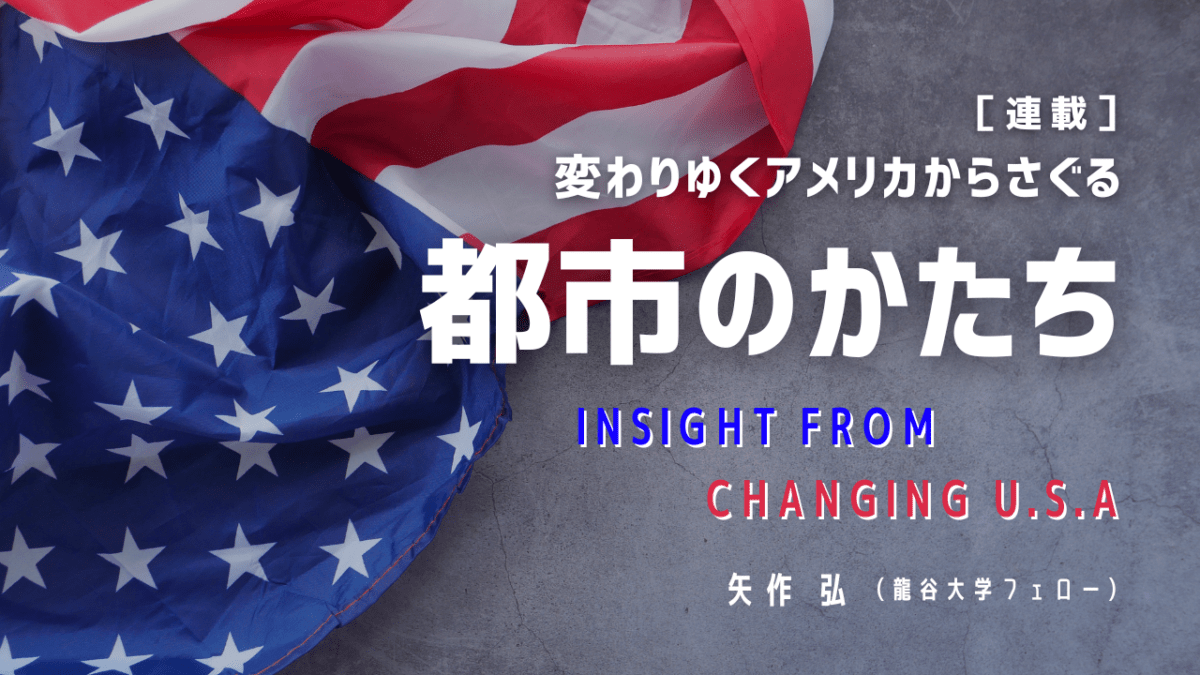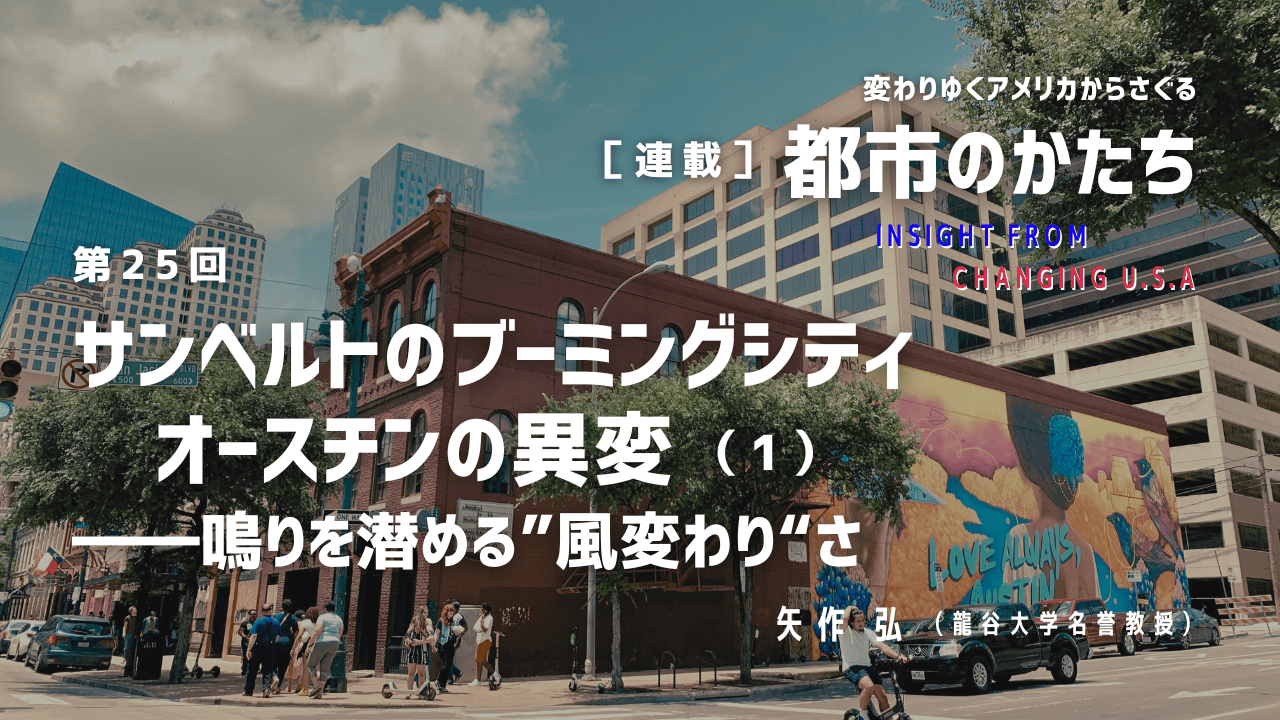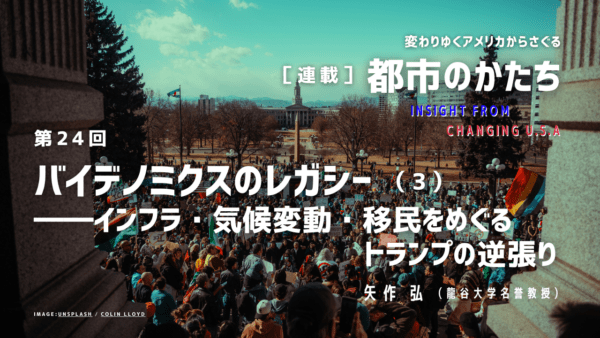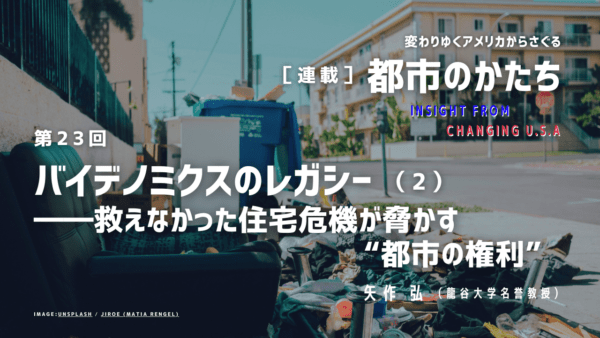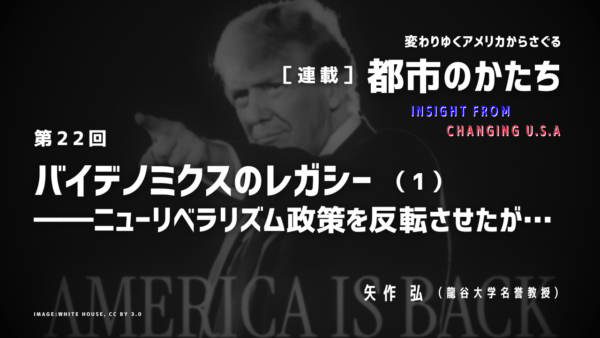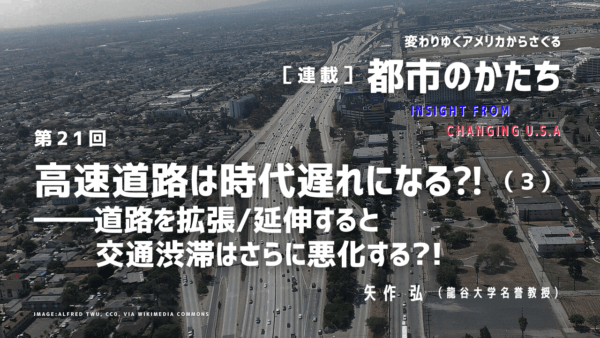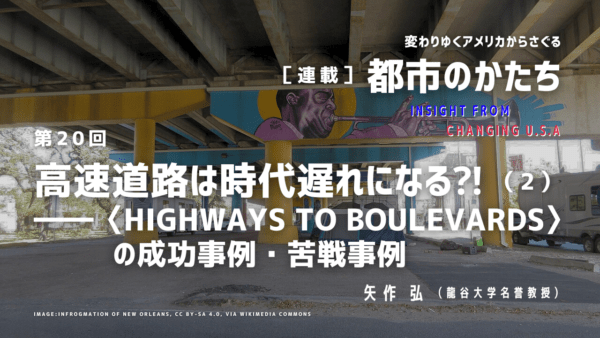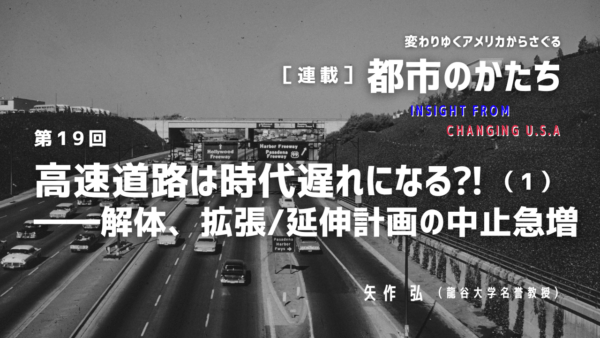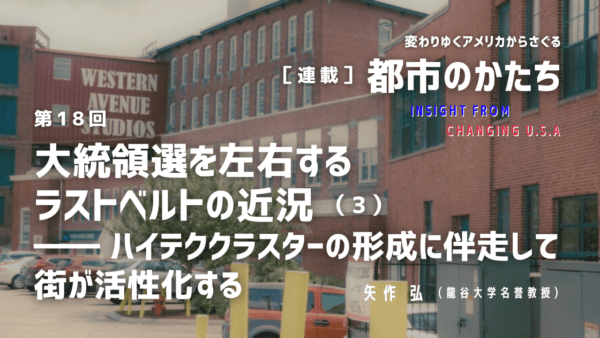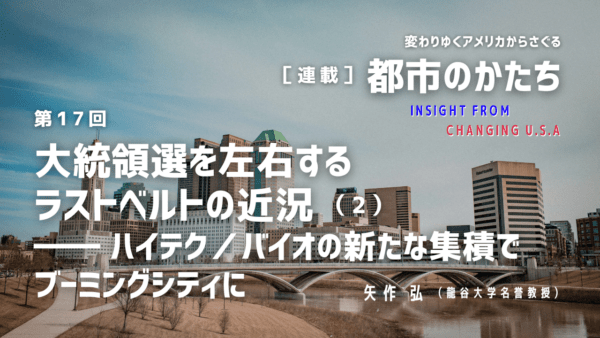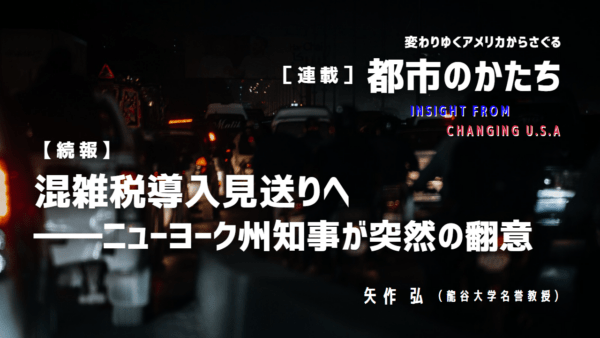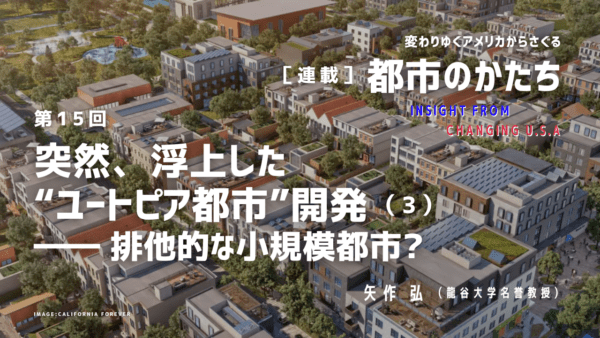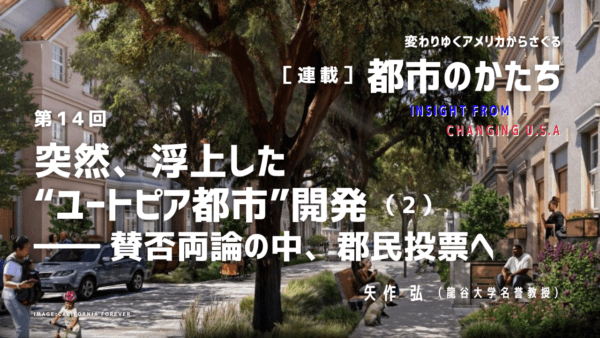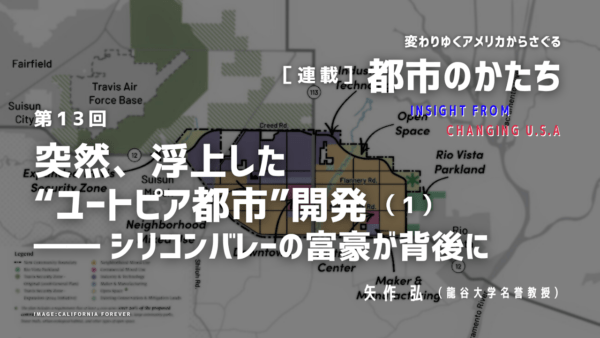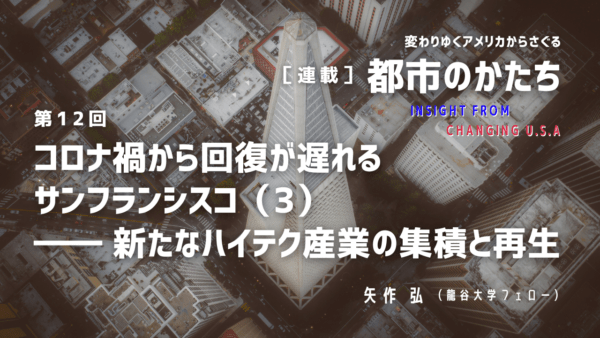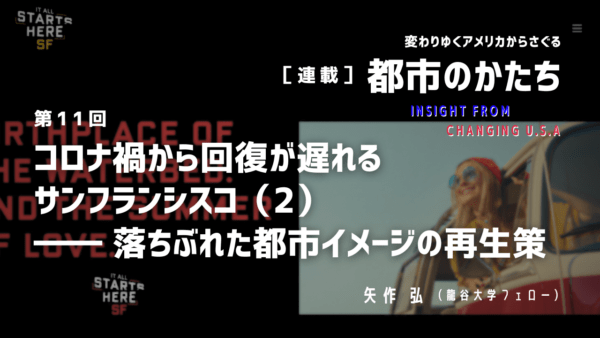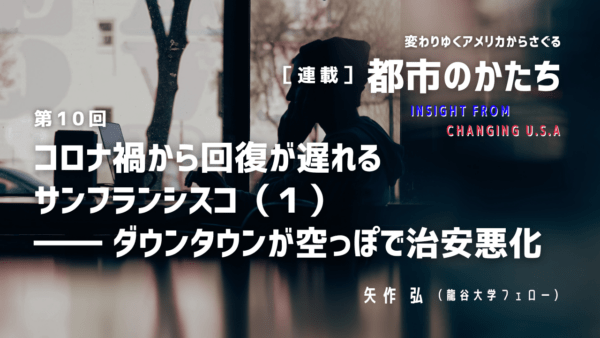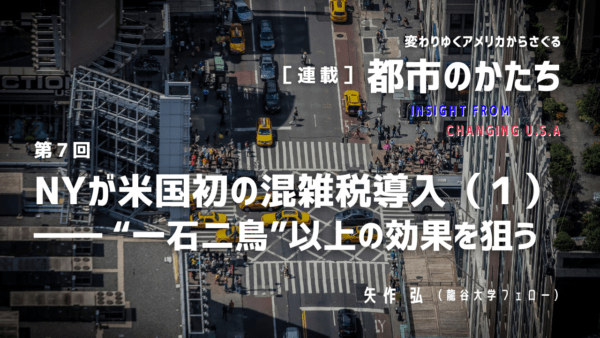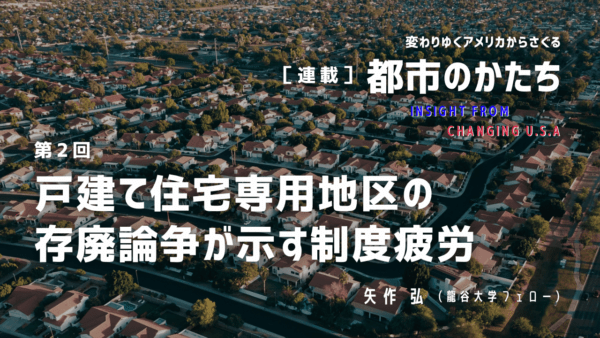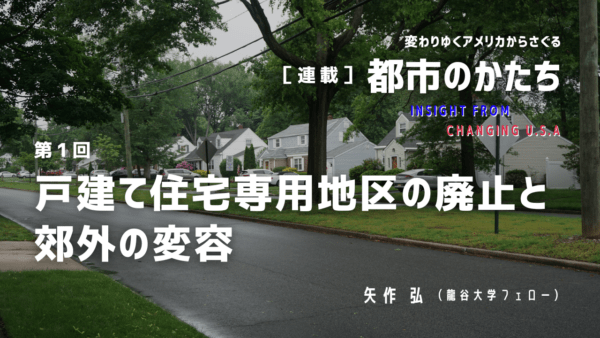第25回「サンベルトのブーミングシティ オースチンの異変(1)―― 鳴りを潜める”風変わり“さ」連載『変わりゆくアメリカからさぐる都市のかたち』
アメリカで展開されている都市政策の最新事情から注目の事例をひもときつつ、変容するこれからの都市のありよう=かたちをさぐります。
筆者
矢作 弘(やはぎ・ひろし)
龍谷大学フェロー
前回の記事
「オースチンを風変わりのままにしておけ!」
「オースチンを風変わりのままにしておけ!(Keep Austin weird !)」 がオースチン(テキサス)の非公式なモットーになっています。ギターのボディや車のバンパー、カフェの窓ガラスなどにそう書かれたステッカーが貼ってあります。Tシャツのデザイン文字にも使われています。

オースチンのルポルタージュ記事やオースチンに関する研究報告書などでも、「オースチンを風変わりのままにしておけ!」から書き始め、その意味するところを解説しているものに出合います。
しかし、そう言われるようになったのは、それほど昔ではなく、精々、ここ数十年のことのようです。それ以前のオースチンが「風変わり」だったことは、言わずもがなだったのです。
敢えてモットーにする必要がなかったのでしょうが、どうやらオースチンの「風変わり」が危うくなっている、失われつつある、ということで、このモットーが使われるようになったのです。
「しておけ(keep)」と命令形になっているところからも、そうした事情を憶測することができます。この命令形には、「風変わり」が希薄になってきていることに対するオースチンっ子の心配というのか、苛立ちが含まれている、と読み解くことができます。
ハイテクとエリートが牽引した急成長都市
オースチンは、サンベルトにある代表的な急成長都市です。20世紀末からこの間、可視的、建築的な意味に加え、雇用や産業構造など経済社会面でも〈都市の「かたち」〉を急激に変貌してきました。
変化を牽引したのは、IT系ハイテク企業とそこで働く高学歴のパワーエリート(ハイテクプロフェショナル)集団です。その集積が急ピッチに進展し、オースチンは国内屈指のブーミングシティになりました。
引越し先人気上位10位都市ランキング
- No. 1 – Dallas-Fort Worth, Texas
- No. 2 – Charlotte, North Carolina
- No. 3 – Phoenix, Arizona
- No. 4 – Lakeland, Florida
- No. 5 – Austin, Texas
- No. 6 – Nashville, Tennessee
- No. 7 – Raleigh, North Carolina
- No. 8 – Palm Bay, Florida
- No. 9 – Houston, Texas
- No. 10 – Greenville, South Carolina
おかげでオースチンの郊外都市も急成長しました。オースチンのダウンタウンから20kmほどのマノールは、2014-2023年に180%の人口増を記録しました(Austin’s suburb soars among fastest-growing U.S. cities in past decade, Austin Cultural Map, April 14, 2025)。アメリカ全体で人口増加が急な郊外都市ランキングで6位でした。100位までにオースチンの郊外の5都市がランクインしていました。
ところがブーミングシティの成長に〈揺らぎ〉が出ています。急成長都市にしばしば孕む経済的、社会的矛盾が積み重なって臨界点を越え(?)、それらがいよいよ成長の足かせになってきた、という指摘があります。
本稿では、オースチンの今昔を以下の順で紹介し、その将来を探ります。
- 大学と州政府が主要雇用主でそれ以外にこれといった産業がなく、静かで落ち着いた、しかし、「風変わりな」町だったオースチンが、20世紀末から21世紀に入ってITブームに沸き、ブーミングシティに変容した。その道程で「風変わり」に由来するオースチンの魅力が失われつつある!?
- さらに住宅費の高騰とホームレスの増加、交通渋滞、麻薬関連の犯罪の増加――などの都市問題を抱え込み、ブーミングに〈陰り〉が指摘されるようになった。「成功の代償」の表出です。その現況を報告します。
- そうした議論を踏まえ、「明日のオースチン」、さらにはオースチンに代表されるサンベルト都市の将来をめぐる議論――楽観論、悲観論を紹介します。
テキサスの個性的な都市圏
テキサスには、オースチンと並び、ヒューストン、ダラス、サンアントニオの主要4都市があります。それぞれの都市に個性があります。いずれも郊外に幾つかのエッジシティ(職住遊機能を備えた自己完結型の郊外都市)を抱え、大きな都市圏を形成しています。
ヒューストンには、石油/化学工業関連産業が集積しています。エネルギー関連産業が活況だった1980年代に、ダウンタウンに超高層ビルが林立しました。
ダラスには、連邦準備銀行があります。アメリカ南西部の金融都市です。同時にIT系企業が集積する「シリコンプレーリー(草原)」の中心都市になっています。

ユナイテッド航空のハブ空港になっているヒューストン空港とアメリカン航空のハブ空港になっているダラス-フォートワース空港は、メキシコ、さらには南アメリカとの都市間を結ぶ航空便の、アメリカ側の、空の玄関口になっています。
ダラスには、サウスウエスト航空の本社があります。
サンアントニオは観光に強みがあります。アラモの砦、それに水路をボートで巡るツアーに人気があります。「テキサスのベニス」と称されることがあります。

オースチンは州都です。州政府とその関連機関があります。アメリカの州都は、しばしば中小規模の地方都市です。州内に並び競う同格レベルの都市がある場合、どちらの都市にも与せず、中小都市に州都を置く、という賢明な政治的判断です。
そうした州都は政治都市ですから、一般的に経済、社会、文化のいずれの活動も乏しく、しばしば「都会的な刺激がなく、退屈でつまらない都市」のレッテルを貼られています。
テキサスも、同じような事情からオースチンが州都になったのでしょうか。
ただ、幸いなことにオースチンは、歴史的にも「退屈でつまらない都市」のレッテルには無縁でした。本稿のテーマになっている昨今のオースチンは、激動するブーミングシティですから何事も忙しく、「退屈」どころの話ではないのですが、ハイテク都市になる以前の、往年のオースチンも、他州の、類似の規模の州都とは様子がだいぶ違っていました。
それは州立のテキサス大学(テキサス大学システムの本部校)があるおかげです。大学ランキングでは、文理両分野で上位に並ぶ総合大学です。
また、先端科学技術に力を入れています。最近、デル・テクノロジーズの創業者の寄付を基礎にメディカルスクールを開学しました。ノーベル賞受賞者を多く輩出しています。そうした優れた大学の恩恵を受け、以前から街には知的、文化的な香りがあります。

変貌する〈音楽の街 オースチン〉
アフリカ系黒人の音楽活動が活発でした。テキサスは共和党支配の「レッド州」で保守的ですが、オースチンは伝統的に民主党が強く、リベラルです。総合大学がある、文化的多様性がある、政治的に自由な気分が漂う――そうしたことがオースチンを「風変わり」な州都にしてきました。
ところが、昨今、例えば音楽家が暮らしにくくなっています。家賃が高騰し、スタジオなどを借りられなくなっています。〈音楽の街 オースチン〉の現況を憂いて討論会が開催されました(DIY urbanism: SXSW and panel discuss making Austin for musicians, Austin Cultural Map, March 3, 2025)
オースチン在住のジャーナリストが、雑誌New Yorkerにオースチンの変貌を活写するエッセーを書いています(The astonishing transformation of Austin, Feb. 6, 2023)。そこでは、1980年ごろのオースチンを、「風変わりな」に加え、「呑気な」「お茶目な」「自発的な」などの修飾語を並べて描いていました。
エッセーの副題は、「かつてはのんびりの、少々、風変わりな町だったのに、今やシリコンバレーなどからの逃亡者が殺到し、メガロポリスに激変中」です。
筆者は1980年にオースチンに移住し、以来、オースチン暮らしをしています。それまでにナッシュビル、デンバー、ダーラム、それにNY、LAなどを転々とし、また、地球のあちこちで放浪暮らしをし、その経験に照らしてオースチンの、激しい、それも短期間の変貌に驚いています。
1970年の人口は25万人でした。それが2022年には、都市人口が97万人を超えました。半世紀の間に、およそ4倍の急増です。もう少し詳しい人口動態の説明は次回に譲りますが、ダラス都市圏人口は、同じ時期におよそ8倍に増えました。
中都市から大都市に変化すれば、当然、都市の気質は変わります。それまでの中間所得階層に代わってハイテクで富を成した大金持ちや、同じくハイテク企業で働き、高額所得を稼ぐ専門職集団が街を闊歩し始めれば、都市の外形や風情が変わるのは必至です。
件のジャーナリストは、1980年当時のオースチンについて以下のように書いています。
人口は30万人を少し超えた程度だった。人口の13%が大学生、5%が大学の教職員、それに州政府の職員が数%。
車は何処にでも駐車し、そのまま放置できた。
ダウンタウンのカフェやレストランの数は限られ、そこでは顔見知りによく出会った。
高層ビルはわずかしかなかった。過半が銀行の建物だった。市内の一番高いビルの最上階(26F)からは、視界を遮る建物はなく、威風堂々とした州議事堂ビル、大学キャンパスに点在する様式建築の校舎群、ダウンタウンの商店街などを一望できた。
大学、州政府に加えて市役所、地元銀行、新聞社やテレビ局、学校、美術館などの文化施設で働く職員とその家族――元来、第3次産業の、それも高学歴層の多い都市でした(最近は25歳以上の52%が大卒以上)。
中小都市の特典で、行きつけのカフェでは、知り合いの教授やジャーナリスト、アーティストなどに出会うのも珍しくなかったようです。
街の変化を象徴するスカイライン
オースチンの急な変貌は、ダウンタウンのスカイラインの変化に具現しました(The evolution of Austin’s skyline, MOUNT BONMEL)。
20世紀初めまで市内で最も高いビルは、石造り建築の州議会堂でした。現在の議事堂は、アメリカ50州の州議会堂で最大規模です。この州議会堂を超える高さのビルを建てることについては、常々、論争が起き、実際のところ20世紀半ばまでそうした建物が建てられることがなかったのです。
1920-30年代には、オースチンでもアールデコ様式が普及し、16階建てのオフィスビルが出現しました。
20世紀半ば以降は、ガラスと鉄骨の近代建築が主流になりました。1970年代に2棟の高層ビルが建ちました。前述したように特段の産業はなく、高層ビルの建築主は、いずれも銀行でした(American Bank Plaza、Austin National Bank Tower)。それでもダウンタウンの街並みは、中低層ビルが中心でした。
1980年代に30階を超える超高層ビルが2棟建ちましたが、15階を超える高層ビル/超高層ビルの新築は、1980年代は13棟に止まっていました。
半面、1980年代には、高さの記録を更新する高層ビル、超高層ビルの建設をめぐってその先導役が代替わりしました。IT系のビッグビジネスが主役になりました。IT系企業をキーテナントに迎えたオフィスビル、そこで働き、高額所得を稼ぐパワーエリートの暮らすコンドミニアム/アパート、それにオフィス/住宅/ホテル・レストランアが入居する複合ビルが50階超の超高層ビルとして建設されました。
オースチンのダウンタウンでは、今後、数年の間に80階建ての超高層タワービル(Wilson Tower、複合ビル)を含めて20棟余のタワービルの建設が計画されています(Exploring dynamic Austin TX skyline 2023, MOUNT BONMEL)。その強気な建設需要を引っ張っているのは、ハイテク産業のさらなる成長予測です。
とめどなく続くハイテク企業の集積
ダウンタウンのスカイラインを大きく変容させたハイテク企業の集積は、1980年代以降、急ピッチでした(The rise of Austin’s as a tech hub, MOUNT BONMEL)。
デル・テクノロジーズの創業者マイケル・デルは、テキサス大学時代に学生ビジネスとしてパソコンの修理会社を設立しました。それが1984です。以降、急成長して情報技術分野でグローバル企業になりました。後日、デルは、オースチン北方の郊外都市(ラウンドロック)に本社を移転しましたが、それでもオースチンを基盤に大きな投資を続け、業容を拡大してきました。
デルに先行して1970年代には、IBMやテキサスインスツルメント、モトローラがオースチンに拠点を構えていました。1980年代に世界規模で情報通信革命が起き、オースチンでもIBM、テキサスインスツルメントが事業規模を急拡大しました。マイクロエレクトロニクスとコンピューターテクノロジーが統合されて新たな研究開発コンソーシアム(MCC)を形成したのは1982年です。MCCはハイテク企業の誘致、あるいは育成で威力を発揮し、オースチンのIT系ハイテク都市化をリードしました。
テキサス大学も、情報通信関連の学部、大学院を拡充し、研究施設を新設し、産学連携研究に傾注しました。おかげでMCCやテキサス大学は、そこからスピンオフし、スタートアップするハイテク小企業の温床になりました。
21世紀を迎え、IT系ビッグビジネスの進出、その巨大投資が加速しました。「シリコンヒルズの奇跡」です。Apple、Amazon、Google、Facebook(Meta)、Teslaなどの国内資本と同時に任天堂、東京エレクトローン、サムソン電子などの海外資本も進出し、大型投資を重ねました。その一部が超高層ビル群のキーテナントになっています。
また、オラクルがカリフォルニアのシリコンバレーから本社をオースチンに移転し、「シリコンバレーの凋落?! シリコンヒルズの台頭!」を象徴するニュースとして注目を集めました。EVsのテラスもオラクルに続き、カリフォルニアから本社を移転しました。
オースチンのハイテク関連雇用は、2015-2020年に41.4%増加しました。現在は、製造業部門を含めてハイテク産業がオースチンの主要雇用主になっています。
昔ながらのオースチンっ子が抱く郷愁
New York Timesは、記者が「ある都市に36時間」滞在し、街中を徘徊する旅行記を連載しています。そのオースチン版(36 hours in Austin, Feb. 29, 2024)は、「このライブミュージックの首都、そして個性的な州都では、〈オースチンを風変わりのままにしておけ!〉が過去数十年のマントラ(真言)になっている」と書き始め、続けて「しかし、今や、アメリカ第10位の都市である」「この大学町はひたすら成長し、(マントラとは)大いに違って見える」と書いていました。「風変わり」が失われている?!
記事は、記者がコロラド川を堰き止めた貯水湖のレディー・バード湖に小舟を浮かべ、そこからダウンタウンの摩天楼を遠望した後、パワーエリートによってジェントリファイされつつある黒人/ラテン系の街区(6番街=「汚い6番街」の愛称がある)などにあるタコレストランや音楽バーを探索して歩く、という感じのルポルタージュです。
ハイテク都市に変容するオースチンを敢えて避け、隅に追いやられ、それでもオースチンっ子がこだわり守ろうとしている界隈に、〈風変わりで個性的な〉飲食店や皮革製品店、民芸品ショップなどを探し求め、足を踏み入れています、
New Yorkerに寄稿したジャーナリストは、最近のオースチンについて以下のように書いています。
昔からのオースチンっ子は、小さな町だったころのオースチンに郷愁がある。小さいことから来る不便は、我慢できた。
私はダウンタウンに建てるビルの高さを制限し、「オースチンが摩天楼街にならないようにしたらいいのに」と思っていた。人間的な規模の街のままでいて欲しかった。超高層ビルのないパリやワシントンD.C.のように。
それが今は、高層ビルの窓辺から一方向を眺めただけでも、建設用のクレーンが10本も連棟している。さらにテキサスで一番高いビルなることを競って2棟の超高層ビルの建設計画がある。
アメリカでオースチンほど激変した都市は他にない。わずか10年の間に、市域の1/3が都市化した。都市圏レベルでは、人口が毎日355人増えている。しかし、住宅費が高騰し、暮らし難くなって毎日239人が域外に追い出されている。
ジャーナリストは、最近のオースチンに対して疎外感を抱いています。エッセーの最後に、大方、以下のように書いています。
遠方から眺めるオースチンのダウンタウンのスカイラインは、太陽光を反射して美しいが、冷たく、気が滅入るほど均質で、その風景は思い描いていた「明日のオースチン」からはかけ離れ、かつてよく知っていた場所も、日々、ますます不可知な、際限のないところに変容し、私はそこでは、市民(citizen)ではなく、単なる居住者(resident)になってしまったように感じる。
JETRO(日本貿易振興会)から「オースティン報告」が出ています(2022年4月)。その報告書も、〈オースチンを風変わりのままにしておけ!〉のモットーに言及し、オースチンが「違い」を認め、「違い」受け入れる――その気質がこの都市の革新性につながっている、という市長の発言を引用していました。
しかし、「風変わり」が薄まってきたオースチンは、モットーを、あらゆる機会、あらゆるところで発し続けなければ革新性が失われる、という段階にきたのでしょうか。
(つづく)
連載記事一覧