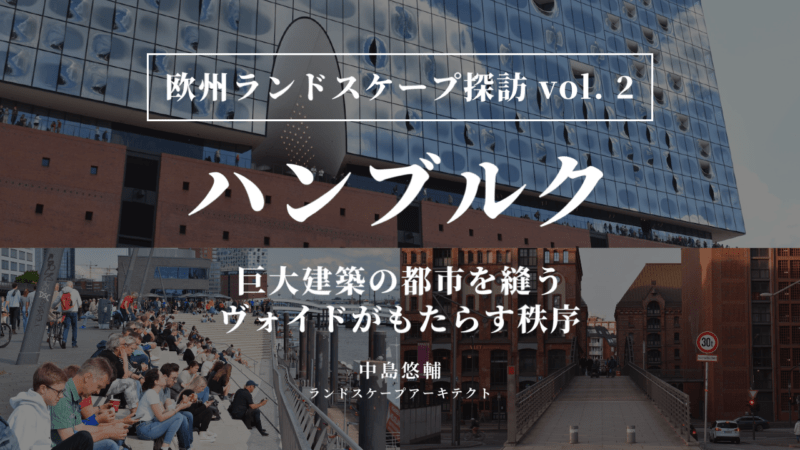連載「欧州ランドスケープ探訪」vol. 5|ミラノ:所有する緑に感じるルネサンス
ベルリンでランドスケープアーキテクトとして働き始めた私は、一体なぜランドスケープが必要なのか、ランドスケープはどういう設計思想にもとづいているのか、といった問いについて、まだはっきりとした答えが出せていない。
ランドスケープアーキテクチャが対象とする庭、広場、公園が生まれ、発展した地であるヨーロッパの各地を巡ることで、その答えが出るのではないか。そんな期待をもって、ランドスケープを巡る旅に出ることにした。これは、ヨーロッパ各都市のランドスケープの傑作を訪れる中で見えてきた、ランドスケープの設計思想に関する備忘録である。
筆者/中島悠輔(ランドスケープアーキテクト)
公園が少ない国 イタリア
イタリア人の同僚とミラノでの旅の話をしていた時、イタリアは他のヨーロッパの国々に比べて公園の数が少なく、憩いの場として公園を求める意識が薄いことに話題が及んだ。
イタリアの多くの都市は他の国の都市と比べると小さく、街のすぐ隣に山や海などの自然があることが多い。特にシチリアなどの南部では主要産業が農業や漁業等の一次産業であり、日頃から自然に触れる生活が定着している。わざわざ都市内の公園で人工的な自然に触れる必要がないのだ。

また、イタリアの貴族が都市の中に城や宮殿を建てなかったことも、公園の少なさの背景にあるといってよいだろう。
以前の記事でも書いたが、16~18世紀頃、パリやロンドンでは王や貴族が都市内に〈ルーブル宮殿〉、〈テュイルリー宮殿〉や〈バッキンガム宮殿〉等の宮殿と庭園を造った。17~18世紀頃、パリやロンドンで市民革命が起き、それらの宮殿は政府の施設や図書館や美術館などの公的な建物となり、庭園は公園として公開された。


一方で、5世紀にローマ帝国が滅亡して以来、イタリアはローマやミラノ、ヴェネツィアなどの都市が国家として分裂し、14~16世紀頃のルネサンス期、メディチ家やエステ家、ヴィスコンティ家等の貴族が力を持ってそれぞれの都市を支配していた。
ルネサンスとは、それまでキリスト教により弾圧されていた古代ギリシャ・ローマの文化を研究し、自由に科学や芸術を探求する文化的な運動であるが、メディチ家やエステ家はこの運動を支持し、科学者や芸術家を支援した。
さかのぼること紀元前4世紀頃、ギリシャでプラトンがアテネの郊外の森に「アカデメイア」という学園を開設したように、イタリアの貴族達もまた郊外にヴィラを建て、自然の中に人が集まり学問について議論する場を作ろうとしたのである。

その後、19世紀中頃になると、イタリアでもいわゆる「イタリア統一運動」を通して支配階級が排除されたが、都市内には支配階級が所有する宮殿や庭園は少なかったことから、それらを元にした公園はほとんど生まれなかった。
こうした歴史的な流れから見てもイタリアの都市に公園が少ないことは必然と言える。
古代ローマに倣った広場
ミラノには先にも触れたヴィスコンティ家の庭園であった歴史を持つ〈センピオーネ公園〉や、ドゥニャーニ家の庭園であった〈インドロ・モンタネッリ公共庭園〉が、イタリア統一運動後に公園として開放されている。それでもやはり、他のヨーロッパの都市と比べて公園の数が少ない。

その一方で、〈ドゥオーモ大聖堂広場〉や〈スカラ広場〉、〈フランセスコ・バラッカ広場〉といった街中の広場は、行き交う観光客、観光客相手に商売する人、階段やベンチに座って談笑する人、駆けまわって遊ぶ子供たちで賑わっていた。
これらの広場の多くは中世に造られたものもあるが、19世紀に造られたものもある。
ミラノの都市整備が進められたのは、イタリア統一運動が活発だった19世紀中頃である。イタリアの文化を象徴する都市・建築の在り方が模索され、イタリアの文化の基となっている古代ギリシャ・ローマの文化の研究が再度、盛んになった。そうした中で、新古典主義の建築が増え、古代ローマの都市にあった公共広場「フォルム」を参考にミラノでも広場が多数造られたのだ。
具体的な特徴としては、中央にモニュメントが置かれた石畳の舗装のシンプルな広場が多い。パリやロンドンの貴族の庭園をベースとした公園とは違うイタリアらしいオープンスペースだ。



中庭・バルコニーで楽しまれる私的な緑
また、中庭とバルコニーが多いこともミラノの特徴だ。どちらも古代ローマの文化の影響を受けている。
古代ローマの都市部に住む富裕層の家「ドムス」には、列柱で囲まれた中庭「ペリスタイル」が造られた。ペリスタイルは表通りから離れた居室に光と外気、生活用水のための雨水を取り込む場所であったと共に、彫像や絵画や美しい花々が飾られ、学術・芸術の場として建物の中で重要視された空間だ。
一方、多くの市民は「インスラ」と呼ばれる高層の集合住宅に住んでおり、2階以上の階にバルコニー「マエニアーヌム」が設けられた。インスラは木造や泥レンガで造られた簡素なもので居室は狭く、高層階は水道も整備されていない劣悪な環境であったが人々はマエニアームに植物を置き、ささやかな自然を楽しんだ。
中庭は5世紀頃に権力が少数の人に集中する中で少なくなっていき、バルコニーは4世紀頃に戦争時に都市を防御するために造られなくなったが、どちらもルネサンス期に再度発展し、19世紀の新古典主義の影響を受けた近代的な都市開発の中でも取り入れられていった。
現在のミラノの旧市街地に位置するアパートの1階には、プラダやフェラガモといったハイブランドの店舗が並ぶ。店に入ると内側に向いた窓から中庭が垣間見える。窓に映る緑は美しく店の展示を飾っていた。
ミラノを訪れたのは、ミラノサローネ国際家具見本市の期間であったが、街中にある中庭は人を道路から建物に引き入れ、窓から見える美しい景色で展示を飾り、時には中庭自体が展示場所となっていた。生活に潤いを与え、芸術や技術について議論する私的な屋外空間「ペリスタイル」が、資本主義的な経済体制とも上手く結びつき、結実しているように思えた。






旧市街地では、石造りの支えや装飾的なフェンスなど、クラシカルなバルコニーを見ることもできる。現代的なアパートでも、モダンなバルコニーが窓などの開口部に対してバランス良く配置されており、イタリアの建築においてバルコニーがファサードを構成する重要な建築要素と捉えられていることがわかる。
2014年に国際高層ビル賞の最高賞を受賞した〈ボスコ・ヴェルティカーレ〉は、バルコニーに植えられた木々が夏季にビルを冷やしてエネルギー消費を抑え、大気汚染から人を住民を守るなど、環境に対する取り組みが評価されているが、その背景には古代ローマから続くイタリアの所有する緑の文化がある。





所有する緑への意識に見出す日伊の相似
文化や歴史的な点で、イタリアと日本のオープンスペースへの意識は似ている。
日本でも江戸時代は国民の8割強が農民であり、城壁の中で生活をしていた北ヨーロッパの大都市生活者とは違って、人々の生活と自然が密接に繋がっていた。また、明治維新では封建制度が廃されたが、武士の城や庭園は政府の管理下に置かれ、公園という文化は浸透しなかった。
一方で、神社の境内などはお祭りなどで使われるオープンスペースとして人々の生活に浸透している。この点、古代ローマの政治・祭事・商業の場であった「フォルム」とよく似ている。
日本はイタリアと同じく、農業の歴史が長いことから、土地を所有することに対する意識が強い。
街中でも、長屋の中庭や生活道路まではみ出て置かれる鉢植えのような私的な緑の文化こそ、日本らしいオープンスペースの在り方なのかもしれない。

連載記事一覧
筆者紹介

中島悠輔(なかしま・ゆうすけ)
1991年生まれ、愛知出身。ベルリンのランドスケープ設計事務所Mettler Landschaftsarchitektur勤務。
幼少期にシドニーに住んでいた経験から自然に近い生活空間に興味を持ち始め、東京大学・大学院にて生態学・都市計画学を学びランドスケープという言葉に出会う。大学院卒業後1年間、設計事務所等でインターンをし、留学準備を進め、18年より渡豪し、2020年にオーストラリア メルボルン大学Landscape Architecture修士課程を修了。ヨーロッパ、特にドイツの機能美のデザインを学ぶために、2021年に渡独。2020年より400人が参加する国内外のランドスケープアーキテクチャに関する情報交換のためのFacebookグループ「ランドスケープを学びたい人の井戸端会議」を運営。