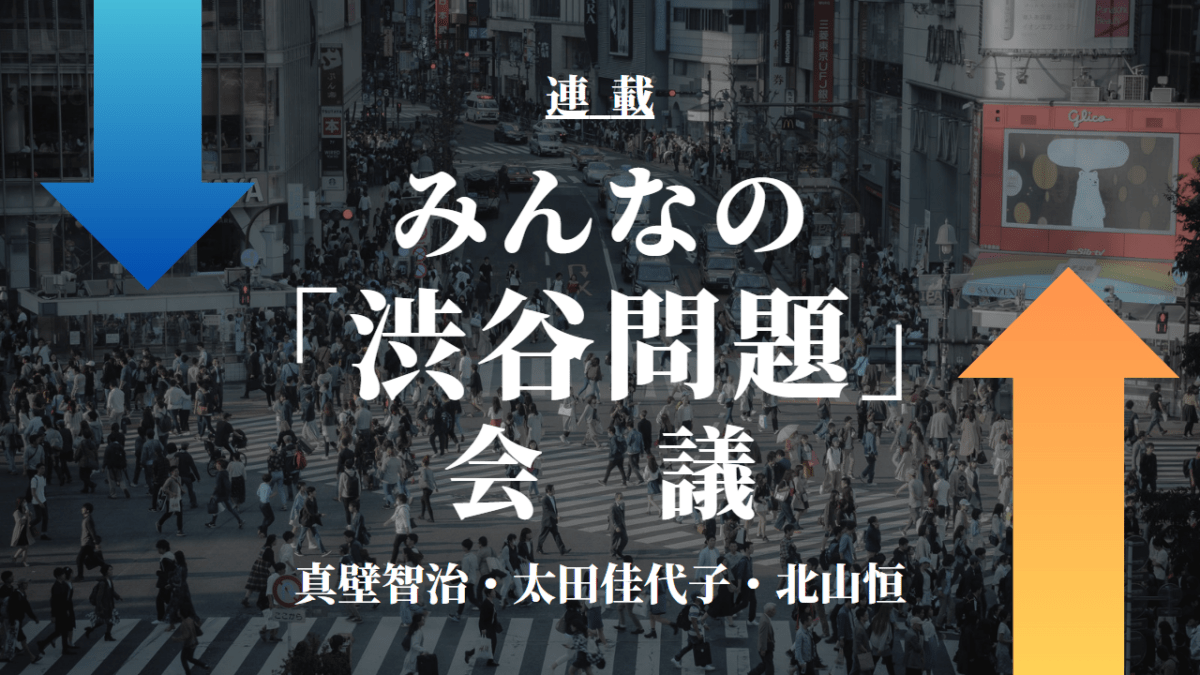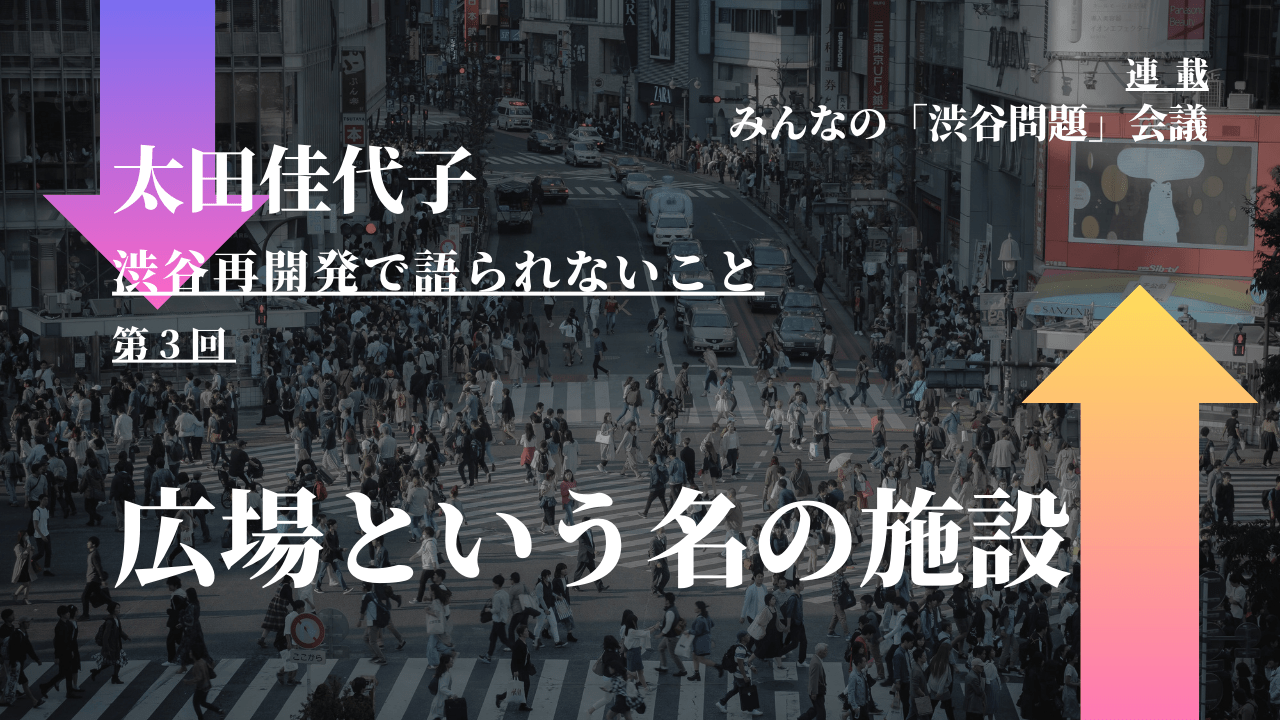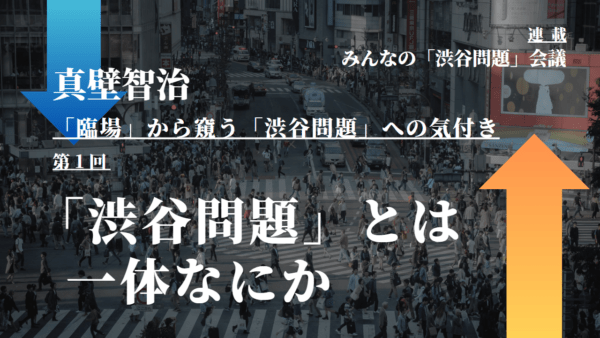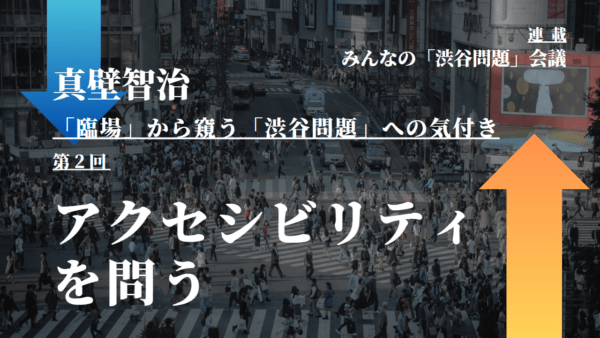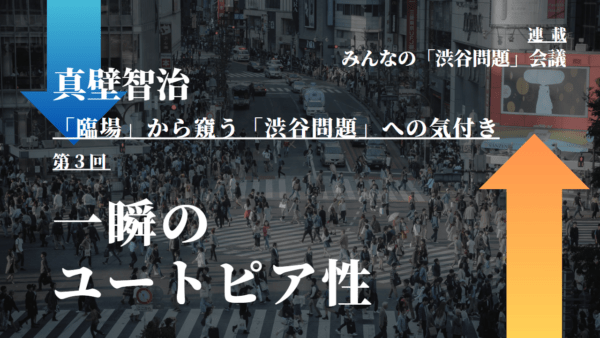広場という名の施設 – 太田佳代子「渋谷再開発で語られないこと」(第3回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
太田佳代子(おおた・かよこ)
建築キュレーター、編集者。NPO法人建築思考プラットフォーム理事。ハーバード大学デザイン大学院特任研究員。2018〜21年、カナダ建築センター(CCA)特任キュレーター。2014年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館コミッショナー。2004〜06年雑誌「DOMUS」副編集長・編集委員。おもな編著に『SHIBUYA! ハーバード大学院生が10年後の渋谷を考える』(共著)など。
はじめに
渋谷の街が都市再生特区のシステムで大きく生まれ変わり、新しい「広場」がいくつか誕生した。規制緩和との引き換えとして作られ、市民に開放された「広場」は、さて本当に広場たり得ているのだろうか。
≪横にスクロールしてお読みください≫
再開発で生まれる都市の余白
再開発によって渋谷川は復活した。この川をまたぐ稲荷橋は拡張され、オープンスペースができた。渋谷ストリームの玄関となる大きな穴は、稲荷広場と呼ばれるこのオープンスペースに向かって開き、大階段によって人々を2階のメインストリートへ、そしてJR渋谷駅へと導く。原広司が京都駅のコンコースで階段を巧みに使い、いわば新しい都市の地形を建築の内部に作り出したのに対し、稲荷橋に面した大階段はむしろ屋外の谷と丘(稲荷広場と渋谷駅)を巻き込み、建築を渋谷の地形と同化させた。
大階段がつくる新しい地形は、都市生活を豊かにしてくれる装置として喜んで受け入れることができる。だが、前面の「広場」に差し出された「公共性」の、トゥルンと滑らかに調整された形を手放しで歓迎することはできない。
稲荷広場は居心地がよく、映えるポケットパークであり、スポーツイベントやファッションショー、青空マーケットなど、様々なイベントの舞台にもなる。大階段を埋め尽くす観客たちが一斉に身を乗り出して広場と一体となっているのを見ると、有効空地や公開空地(*1)のありようが開拓されたことを実感する[写真]。
ただ、この広場に設定された使用料を知ると、少し見方が変わってくる。一日の料金は35万円以上(*2)。とてもじゃないが、個人のグループや非営利組織が出せる金額ではない。渋谷ストリームから少し離れた渋谷キャストの広場も同様で、50万円以上かかる(*3)。ふつうに高級レンタルスペースである。
広場の経営サイクルと公益性
大規模再開発でできる広場は、誰もが自由に過ごせる場所として設計されているものの、集まって何かを行うとなると、高額な使用料が発生する。特定の目的のためにこの都市空間をシェアすることは、金銭的な余裕のある企業や団体だけに許されているのが現状だ。
再開発の空地のイベント使用について、何か共通の運営ポリシーがあるのか調べてみた。渋谷駅周辺再開発には早くからエリアマネジメント組織が作られたが、その報告書によれば、「まちを盛り上げ、使いやすくする財源」(*4)として広場などの公共空間で収益を得ることになっているという。稲荷広場の管理は渋谷ストリームが行なっているが、やはり使用者から徴収した使用料を「良好な水辺空間の保全、創出」(*5)のために使うことが、渋谷区に義務付けられている。つまり、イベント主催者が支払う使用料で広場を維持・運営し、より良くしていくという経営サイクルになっているわけだ。
私が抱く疑問は、規制緩和で含み利益を得た再開発事業者自体は、公益をもたらす場として作った「広場」で、一体どのような公益をもたらしているのだろう、というのが一点。もう一点は、「にぎわい創出」を目的の一つとするエリアマネジメントの考え方として、広場の使用者や来場者の消費に頼るだけでなく、自治とか社会の寛容性とか教育といった、消費に結びつかないが地域社会に貢献する活動を育んでいく試みも加えていくべきではないか、というものだ。
再開発の空地を使い倒す
少なくとも、一定の条件をクリアした人々や組織には、もっと手頃な料金で「広場」を提供する枠を設けるべきである。公益の名の下に生まれた都市の新しい余白は、消費や広告とは無関係の交流を促し、多様性を育む場所でもあってほしい。収益とは別の基準で公共貢献をもたらすことのできる人や活動にも門戸を広げれば、再開発によってできる広場は、新しい都市空間としての価値を高めるはずだ。
一つのヒントになるのが、東京都のヘブンアーティスト・プログラムである。審査を経てライセンスを得たアーティストには、都内73箇所で屋外の公共スペースがパフォーマンスの場として開放されている(*6、7)。消費サイクルから自立して公共スペースを使うシステムが、わずかながら存在しているのである。こうした試みを広げて、地域の人々の自発的な活動や都市の自治を支える場所を作っていく試みが、自治体にも市民にも求められていると思う。
規制緩和と引き換えにつくりだされる新しい広場の使用者を「消費者」から「市民」へと近づけるために、市民も交えて議論し、アイデアを探り、実験に移すといった展開が必要だ。エリアマネジメントの組織やまちづくり団体には、市民参加やアイデアを提案する場を作る姿勢を求めたい。再開発で生まれる都市空間は、弾力的なまちづくりの発想と多様な人々の参加によって、もっと魅力的な場になると思うのである。
[写真]週末の稲荷広場と渋谷ストリームの大階段(筆者撮影)

*注
- 有効空地は、都市の環境改善や防災のために有効とみなされる道路や公園、駐車場などをいう。公開空地は、再開発でできた空地のうち、一般に開放され自由に通行・利用できる区域。
- 渋谷ストリーム
https://stream-hall.jp/square/ - 渋谷キャスト
https://eventspace.shibuyacast.jp/garden/ - 渋谷駅前エリアマネジメント「渋谷駅前エリアマネジメント活動レポート 2013-2020」、2020年10月発行。
- 渋谷区ホームページ「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定/許可条件」2023年3月17日。
- 東京都生活文化スポーツ局
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/heavenartist/ - 渋谷キャストの広場と大階段も指定スペースとなっているが、実際この目的で使われている日はごくわずかのようだ。
(つづく)
連載記事一覧