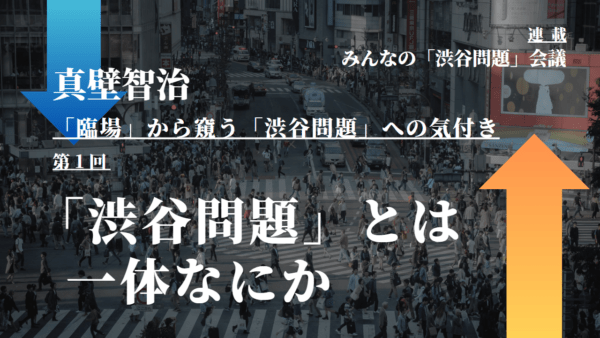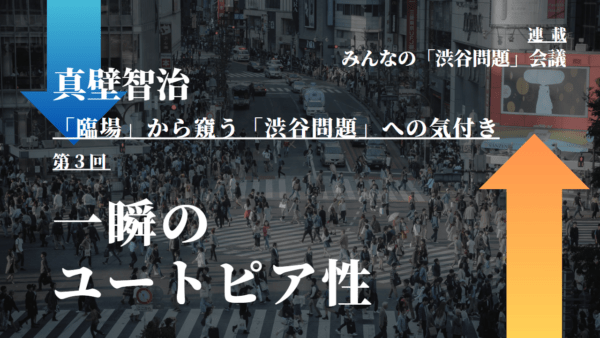広大に開かれるスリバチ底部 – 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第35回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。


≪横にスクロールしてお読みください≫
広大に開かれるスリバチ底部
スリバチ地勢底部の拡がりの様が再開発工事開始以前とは比べようもなく広大に映るようになってきた。このスペクタルを、実は私は待ち望んでいたのだった。
なによりも、JR渋谷駅東口と「ヒカリエ」との間の広大な「抜け空間」が、その印象の要因をつくり出している。
嘗てのメトロ銀座線を支えていた高架橋の列柱が無柱化され、スリバチ底部をまたぐ形で二本の「チューブ」(「ヒカリエブリッジ」とメトロ銀座線渋谷駅ホーム)の空中を走るエッジの様態が、一層強いホリゾンタルな「抜け空間」を印象付けたのだろう。
これは渋谷再開発が生み出す新しいアーバニティを備えた光景の一つになるに違いない。広大に開放されたスリバチ底部は新たな渋谷の表象空間になることを意味し、これこそが都市(渋谷)の空間構造の一つとして体験され、身体化して記憶されてゆき、「都市のイメージ」となってゆくものだろう。
このスリバチ底部からはJR渋谷駅の微妙な勾配を持つ建設中「空中広場」のスラブ躯体が目に入る。
この全く人工的な構造躯体である「空中広場」のオープンな基盤(平面)も、アスファルト舗装のスリバチ底部の地勢(平面)と呼応し出している。
小さな空中基盤の存在がより一層スリバチ底部の広大な拡がりを演出しているようで、二つの平面が呼応・共振し合っている。
そして、ここで忘れてはならないのが、スリバチ底部を解放した空中を走る二本の「チューブ」の存在を生んだデザイン(構造も無論含まれる)の力である。
それらは建築と土木の要素を合せ持つ「建土築木」(内藤廣)を体現しているもので、都市デザインと規定しても良いかと思える。「都市デザイン」の力を持ってこそ谷底底部が解放されたのだ。
恐らくここに隣接するJR渋谷駅「空中広場」は、スリバチ底部の地勢と人や車の移動様態を観光するのに最適なアーバン・スポットになるであろう。
再開発当初からもう一つ私が持っていた重大な関心に、スリバチ底部の在り様があった。
それはスリバチ底部に立地する建物施設の接地階での様態(主要には平面計画)に関わってくる。
再開発される前まではJR渋谷駅構内も東横百貨店東館・西館接地階も共に、スリバチ底部を自在に通り抜けたり、全体としてのスリバチ底部の「空間」領域を感覚したりすることがとても困難だった。
従って、本来から備わる「地勢」の様態を把握することが難しかったし、それに気が付きにくかった。
そのいずれの要因も、それまでの建物施設の接地階が閉じられたもので、スリバチ底部の地勢に開かれ、繋がる意図を全く持っていなかったことに起因する。
対して現段階のJR渋谷駅は、接地階構内の様態はいまだ仮設状態に在るものの、明らかに改札口から南口方面、東口方面への移動の為の通路が大幅に拡幅され、通り抜け感が格段に高まってきた(その状態がいつまで保たれるかは不明だが)。
それにつれて、渋谷駅東口と南口とに渡る広大なスリバチ底部のアウトラインが繋がって全体がイメージされるようになる。
これまでも、渋谷駅東口とハチ公口とは高架線路を介してスリバチ底部が比較的ボンヤリと繋がり、そこに拡がりを幾分かは感じさせていたものだが、渋谷駅東口と南口とはそのスリバチ底部が繋がるイメージは完全に持ちえなかったものだった。
それが現在の渋谷駅接地階構内は、仮設段階ではあるもののすっかり整理され、東口と南口方面への移動が分かり易くなったので、そのスリバチ底部の連続性が増大し、拡張感が実感出来るようになってきたのです。これも「渋谷問題」として吟味されるべきだ。
多少通路が直線的なクランク状であるとは言え、「渋谷フクラス」前と「渋谷スクランブル」東棟前(下)とが一気に繋がった感覚も強くします。
これから二〇二七年完成に向って、JR渋谷駅のフロア構成は以下の様になることが示されている。
山手線・埼京線・湘南新宿ライン等のホームは二階、全ての改札は三階に集約される。JR渋谷駅三階こそが公共貢献とされる「フリーウェイ」の独壇場となる、と言うわけなのだ。そして東西南北に向け自在なアクセシビリティが可能な様態になることが期待されるものだ。
「歩行のまち・渋谷」はまさにスリバチ底部を起点に、東西南北に布置される豊かな地勢と界隈に向けて歩き出すことが一層出来易いような感覚を持つことになろう。しかし、これも一階からの起点(スタート)が原則になる。三階スタートではこの感覚は得られない。スリバチ底部を〇メートル水位とすると、駅接地階構内から四方どの辺りまでが一メートル未満水位ゾーンなのだろうか。
こんな様態を想い浮かべると、クリスト「囲まれた島々」マイアミ州フロリダビスケーン湾プロジェクトが頭をよぎる。「湾内に点在する一一の島々を水に浮く、ピンク色の布で取り囲んだ作品」(「surrounded islands」一九八三年)。
「渋谷ストリーム」でも東急東横線渋谷駅ホームなどの「記憶」が新しい施設開発に上書きされた感もあるが、渋谷のスリバチ底部は遙か太古からの記憶なのだ。
渋谷スリバチ水位一メートルをピンク色に染め上げる、スリバチ学会監修インスタレーションプロジェクトを提案したい。これも「臨場」在ればのものになる。
渋谷のまちの接地性・地上性・大地性への強烈な気づきを生むインスタレーションとしての充分な意味を担うに違いない。
それは同時に、渋谷の新たなアーバニズムを一瞬の内にイメージさせる「地勢」と「空間」とのふるまいのスタートライン(出発点)として、人びとに問いかけるものになろう。こうしたイマジネーションを胚胎させるのも「渋谷問題」の深さの中に組み込みたい、と考えているからだ。
「歩行のまち・渋谷」や「地勢のまち・渋谷」の魅力を損う都市開発であってはならないはず。
民間主導型都市再開発を検証する「渋谷問題」の根底には、この「歩行」と「地勢」の資質の保全も設定することにならざるを得ないのではないか。
渋谷再開発では最低限、この二つの視点を欠く、あるいは破壊する都市開発の営為は渋谷にとって取り返しのつかない事態を招くことを私たちは自覚しなくてはならない。
渋谷のアーバニティは、この歩行と地勢とをより豊かにシンクロさせることに依って創出されるべきものなのではないか。
たとえそれが、公共貢献として一定の公共性を求められていたとしても、「快適な移動」が歩行と地勢とを歪めていないか、影響を及ぼしていないか精査する視点が重要になってくるだろう。 そのことへの気付きとして、広大に拡がりだした渋谷スリバチ地勢底部と対面してみることも身体性としての「渋谷問題」の領域に分け入るには不可欠な検証となるものなのです。
(つづく)
連載記事一覧