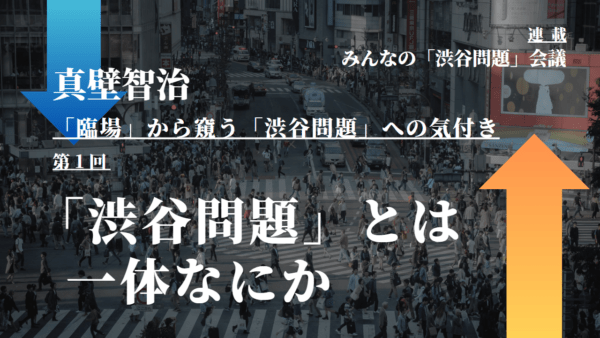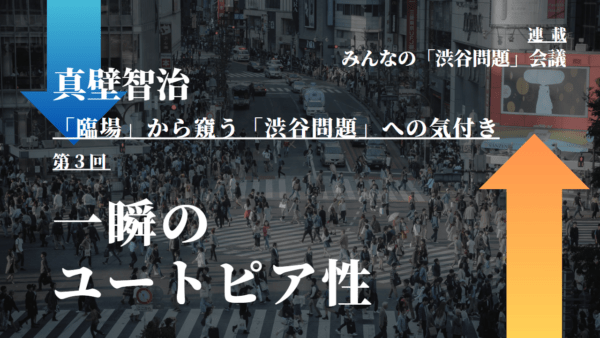光景の臨界 – 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第33回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。


≪横にスクロールしてお読みください≫
光景の臨界
都市の光景の記憶の像は、ボンヤリとしたシルエットと共にヴォリュームが重なり、周囲(環境)との相対的なバランスの体制化として定着される。
記憶の対象フィールドを構成する視覚要素がシルエットとヴォリュームという上位的な抽象化からまずは整理され、それらは周囲との視覚的力学を介して体制化が施される。
因って、都市の光景の記憶の底には絶えず周囲との相対的なバランス、動態的な均衡が潜む。
一方、日々目にする光景はアングルやプロポーションなどの「フレーム」を手掛りに感覚され、微差な光景の変化は私たちの能動的な感性を介してキャッチされる。
その分かり易い証左として、スマホをかざして光景を撮る時、スマホのフレーム越しに光景を取り込んでいるだろう。スマホを身体に密着させず、より離して、私と光景との間にフレームを差し挟んで光景を定着させるあの所作こそ、日々の光景への接し方を示すものになろうか。
すっかり私たちは脇を固めて一眼レフカメラで光景に密着することを忘れてしまっていて、際疾いのはフレームをツールとして設定しないと光景に接すことが出来ず、微差な光景の変化にも疎いことだ。
問題は、都市の光景の記憶の像と、日々の光景の感覚との乖離・ズレとなる。
つまり、日々の目前の光景が、記憶の像の内に収まらなくなってくる時に問題が起こる。
記憶の像の内に在る動態的な均衡が目の前の光景を介して崩れ出すと、途端に記憶(あるいは認識)が混乱をきたす。現在の渋谷で日常的に進行している事態である。
そうした記憶(認識)の構造(体制化)が混乱する際(きわ)を「光景の臨界」とするものなのです。
二〇一一年三月一一日、東日本大震災時に襲来した壮絶な津波が日常的な光景の記憶を一切奪ったことを忘れるわけにいかない。
記憶の構造が一切消失した荒涼とした大地を前に茫然とするしかなかった。記憶が混乱する間もなく、「光景の臨界」を察知する間もなく、光景とその記憶が一瞬にして壊滅してしまったのだった。それは想像を絶する恐怖であったろう。
いよいよその「光景の臨界」が始まり出した。
東急百貨店東横店西館の解体工事が目に見えて新たなステージに入ってきたのが分かる。同時にその建物に対する私たちの記憶に混乱が生じだしたのも自覚される。
元来、東急百貨店東横店西館・東館は、明確な正面性を特に持たない建物・施設であった。
嘗ての「東急文化会館」や「東急プラザ」と比較すると、建物のファサードの印象が極度に薄く、建物のマスだけが駅舎と一体になって記憶されていた。いやむしろ百貨店が駅舎を飲み込んだ建物のマスとして認識されていただろうし、都市の光景としてはシルエットを描きづらく、ヴォリュームのみの記憶が強い。それがターミナルデパートの宿命であったのであろう。
そのヴォリュームが減退し、「光景の臨界」が始まり出したのです。当初から建物のシルエットは覚束ないものだった。なによりも建物のヴォリュームの減退は防護壁の高さの減少から窺えた。
完全に解体工事が完了する手前のこの段階で、私たちは解体の臨界を察知することになる。
丁度二〇二〇年一〇月辺りから着工された解体工事も一年四か月程を経過して、解体の臨界を迎えたことになり、これから急速に解体の事態が動き出してゆくだろう。
合わせて低層部に在ったJR玉川口からの連絡通路や接地階での通り抜け通路などの身体化されていた「道」の記憶も光景の臨界と共に消えてゆく。
漸くは西館解体の「光景の臨界」ショーからは目が離せない。どんな劇場型工事の展開になるのか予測がつかないからだ。
特に光景の記憶の像がどの様に混乱し、光景の臨界と共に、目の前にどんな光景が姿を見せるのか。そのヴォリュームの減退がそれまでの光景の記憶を消去させてゆきながら、現われる新たな光景の動態がどの様なものなのか。つまり、「光景の臨界」が示す相貌の逐一を感応しておきたい。
シルエットもヴォリュームもかき消えた虚空に向って「光景の臨界」が進んでいくだろう。
ここからは、一切のこれまでの記憶よりも、目の前での様態・様相への新たな感知とそこからの記憶の像が積み上がってゆくことになる。
それが光景の記憶の更新・塗り替えだ。
ここに見られるものは決して記憶の上書きではなく、臨界を契機とする光景の記憶のリセットと考えた方が良い。その先に新たに生起する光景への序章として記憶化が作動するのです。
光景の臨界を自覚させるものが気配である。光景の臨界は私たちの内なる記憶の構造の混乱が切っ掛けになるものだが、環境の内にも光景の臨界を伝える気配が滲みだしている。
気配は、次に来る事態への予兆を微かに伝える貴重な役割を担う。
新しいJR渋谷駅の「空中広場」の計画に気付かせてくれたものは、躯体の微かな勾配の動きが示した気配であった。それ自体が微かなだけに、積極的で鋭敏な感性の存在も、気配の感知には不可欠になるのです。
生来、場所には多くの気配が潜みます。気配を介して場に備わる意味領域と交信したり、場に生起する事態への気付きを得たりと、場に対応してゆく私たちの全身感覚と場が発する気配とが呼応し合って、環境を理解し、一体となることが出来る。
謂わば場所との感応とはこうした気配の授受を前提にして行われるべきものなのだ。
「光景の臨界」を示す気配を探索してみよう。
JR渋谷駅埼京線・湘南新宿ラインホームからも「光景の臨界」の気配が覗けた。
隣接する解体現場の防護壁がすっかり低くなり「もう一つの時間」として進行している駅ホーム更新工事の躯体と馴染む様態から、明らかにこれまでとは異なる「光景の臨界」が映し出されている。気配はもっぱら斑状に低くなった防護壁から中の空虚さを直感させるものとして放出されていて、解体完了が近いことを気配と共に空の高さが察知させるのです。
JR渋谷駅南口から桜丘へ向う新設歩道橋の上から、東横店西館の解体現場と対面する。
解体現場としているが、解体工事の様態・様相は防護壁が在り、一切可視化されない。従って、解体の様は防護壁を介在させてそこからの気配の感知しか敵わない。工事を隠すことから窺えるものを感知しようとすることを意味します。
ここからの眺めの最大の特徴は、防護壁を施して解体を進めている現場と、防護パネルを一切設置せずに少しずつ上方からのクレーンを駆使して解体しているJR施設との連続的対比性が際立つことだ。これは隣接し合う対象物への解体手順とその工法とが異なることで生じている連続的対比性で、これを受け止め、向き合う様に「渋谷フクラス」の意味濃度の濃い「ファサード」が在る。こうした非意味濃度と意味濃度の二つの表象世界が対面し合う所で、隠されている解体現場を察してゆく。ここでは解体されてゆく物質の旺盛な気配が防護壁越しに滲んでくる。
更に歩道橋を「渋谷フクラス」側へ進み、外部通路「バルコニー」からすっかり低くなった解体の現場の「光景の臨界」が確認される。
ここからは連続的対比性を示す二か所の解体現場の背後に「渋谷スクランブルスクエア」東棟と「渋谷ストリーム」が聳え立ち、迫りくる。同時に、桜丘口地区再開発工事の躯体の建ち上がりも工事の進捗につれ視野に入る。
こうした二様の超高層施設表層の「オプティカル効果」と、建設中の「エンジニアリング」が現す架構体とが織り重なる圧倒的なスペクタクルが背景となって、解体現場の「光景の臨界」が一層鮮明に感知出来る。気配はなによりも環境の布置の中で固有に生起してくるものですから。
徐々にクレーンを使って解体を進めているJR施設の切り取られた壁面の先端部の「染み」からは、施設としての役割を放棄した様態が物質の気配として伝わってくる。
そして、JR渋谷駅ハチ公口前からも解体現場の「光景の臨界」を検証してみる。
解体工事の為の防護壁からはすっかりヴォリューム感も圧迫感も弱まり、低くなったシルエットだけが浮遊している様に映る。
薄くなったヴォリュームと浮遊するシルエット。斑状の防護壁から覗ける陽光と空。
ここにはもう完全に、光景の記憶の像の面影はどこにもなく、光景の臨界域に突入していることが一層良く分かる。西館解体の「光景の臨界」の進行が最も感知されるのが、このハチ公口前になる。
気配も旺盛で、なによりも防護壁の存在が全く別物の軽いスクリーンにトランスしていて、実体感の無いもの離れ感の在る気配が漂っている。物質性を感じさせない気配なのです。
光景の記憶の像が崩れ出すのもむしろ心地良く感じられる。これから生まれるであろう光景への期待を鼓舞する様な、穏やかな気配の存在のせいでもあろうか。
更に、解体現場を少し引いて対面してみる。そこからどの様な気配を感知することになるのか。
JR渋谷駅東口の宮益坂入口附近から解体現場を遠望する。
少し解体現場の全体がシルエットとして覗ける。エッジ感は無く、固有のシルエットが小さなスカイラインを映し出している。ヴォリューム感は極めて薄く、圧倒感も全く無い。
スリバチ底部のオブジェクトに相応しい姿が先見的にそこに出現しているようだ。
解体工事の最中に「未来」を垣間見る想いがした。
こうした様態から、実に穏やかな気配が都市に立ち昇っている。こんな穏やかな都市の光景はあまり体感した印象が無い。解体前に抱いていた光景の記憶、つまり、シルエットに固有性が無く、唯ヴォリュームが圧倒していた記憶と全く逆転した光景がそこに映し出されている。
この光景も一瞬の幻視になるのであろう。
解体が完了し、更地化してそこから放出される穏やかな気配とは異なるものだろう。
更地から生まれる気配とは、嘗て在った建物の影をひきずり、謎めくものがその穏やかな気配の裡に棲むものだが、目の前の気配には影や謎は感じられない。
これは明らかに解体現場が生起させる「光景の臨界」を、正に示唆するものだ。「光景の臨界」は確実に次のステージを告示するものになっているのです。
ここまで、西館解体現場を異なる場所から眺め、その「光景の臨界」の様を観察してきた。
周囲の環境をバックに「光景の臨界」がそれぞれに見せてくれたものは、新たな光景への記憶のリセットであった。そして「光景の臨界」をそれぞれに自覚させてくれた気配が、異なるバックに応じてニュアンスを違えたのは新鮮な発見でもあった。
この視点は都市の「光景の臨界」を理解してゆく上で、その幅とダイナミズムへの想念を拡張してくれるだろう。こうした光景の移ろいに身を寄せてみることも「渋谷問題」に出会ってゆく方途となるものだ。
(つづく)
連載記事一覧