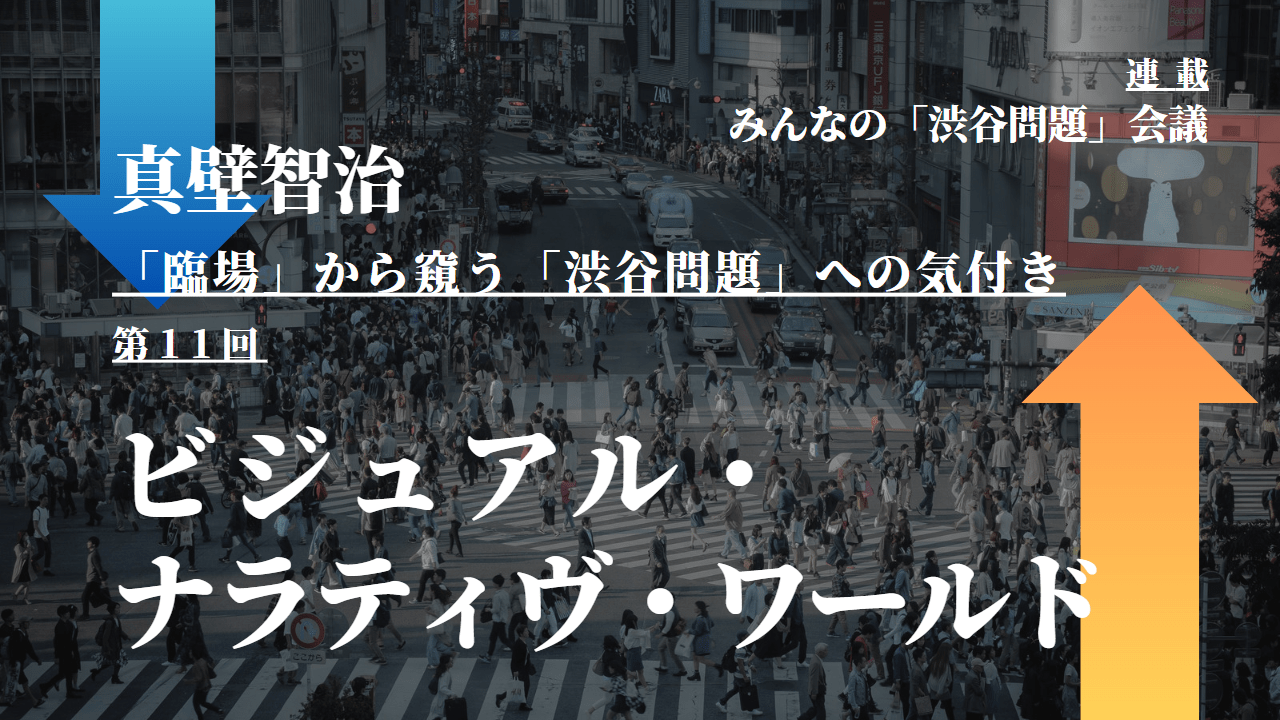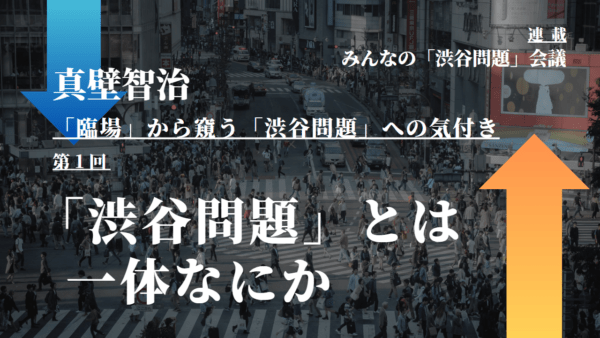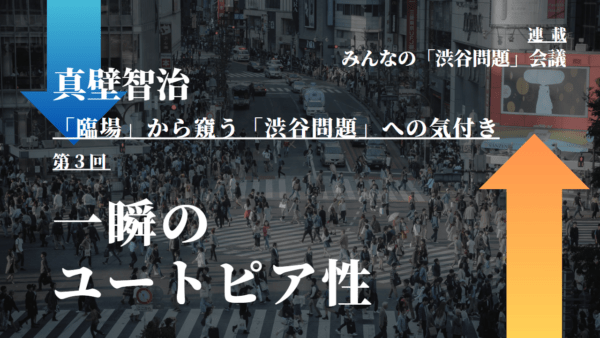ビジュアル・ナラティヴ・ワールド
– 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第11回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。


≪横にスクロールしてお読みください≫
ビジュアル・ナラティヴ・ワールド
渋谷再開発工事期間中に現われる物質世界の様相は寡黙なモノの集積体であるが、それらが生む視覚イメージによって多くの言葉がそこから発せられる。これが「ビジュアル・ナラティヴ」の世界とされるものだ。
モノが語り出す世界と呼応することもこの長きにわたる工事期間中で私たちが身に付けたい都市との応答の復権なのではないか。
モノが語り出すものに耳を傾ける、そうしたプロセスから醸成されてくる感性が都市の日常を生きてゆく上では不可欠になる、と私は常に思って来た。その感性が極度に衰退している。
しかし、工事が完了すると世界はモノから一気に商品や消費のコードで埋め尽くされ、モノの世界からとは全く異なる「ビジュアル・ナラティヴ」の世界が横溢し、際限のない欲望の再生産システムと向き合わなければならなくなる。それらは目の前の世界が語り出す「ビジュアル・ナラティヴ」の話法と文脈とが全く異なるものであることを意味します。
なによりもモノの世界での「ビジュアル・ナラティヴ」には「私」と「モノ」とが共に在る、共に気付いている事態を生み、その中でモノが語り出すのである。その局面から建築や都市を語り出す人たちが現われても不思議ではない。それに比べ商品の世界での「ビジュアル・ナラティヴ」には多くの「私」が穏やかに照応することが出来づらく、「商品」だけが饒舌に語るものとの共存は難しい。この「商品」には映像情報も無論含まれ、一方的に押し付けられ、見せられる「ビジュアル・ナラティヴ」は次第に脅威に映り始める。これが「商品」からの「私」の疎外と言ってもいい。
「商品」は「私」をコントロールしようとする。それが華やかであれば在る程、「私」と「商品」とが共に在る感覚は遠いものになったり、異常な接近を生んだりもする。
資本が誘導する生産と消費の循環の渦の中に「私」を幽閉させるのに「商品」に依る「ビジュアル・ナラティヴ」の世界が極めて有効に働くことになる。資本と商品に私たちが囚われる構造をそこに見ることができる。
私が六〇年代末から都市演習(アーバン・プラクシス)として行って来た「フロッタージュ」は都市に表出する「モノ」に紙を当て、擦り採った擦像あるいは擦象となるものです。
しかし、この擦像には微妙に「商品」の世界の気配や余韻のようなものが滲み込む。都市の表層を示す「モノ」がモノクロームの凸凹の擦像に置き換わる瞬間に「商品」が間接的に入り込むのだが、まだ「モノ」の「ビジュアル・ナラティヴ」の大勢の裡なので、一定の安心感が湧き、モノと共に在る感覚を持つことが出来るのです。
都市の表層が擦像に依る「モノ」の「ビジュアル・ナラティヴ」としてまるで海のような拡がりを見せ始め、「モノ」から擦り採られたモノクロームの白地が限りない都市の闇を暗示し出す。
実はこうした擦像の擦り残された白地部分には闇の奥に潜む「商品」が織り込まれているのが、アーバン・フロッタージュを長年にわたり実践してくると、その間の「擦像」に浮かび上がってくるものの変化を把握することが出来るのです。
六〇年代末から七〇年代までのアーバン・フロッタージュが描き出す擦像の白地部分からは国家権力の影とそれに抗う異議申し立てとが拮抗する緊張感が闇のように感じ取られた。
擦像に擦り採られたモノクロームの世界は白地と墨とのコントラストが鮮明で、ハーフトーンの表出は殆ど見当たらなかった。ある意味で都市が分かり易く力の拮抗として健全に映っていた様に強く感じていた。
それが二〇〇〇年に入ると、都市の表層の擦像にそれまでとは違う異質性が浮かび上がってくる。
擦像に現われるコントラストがボケ出し、白地と墨地とが曖昧になってくる。俄然、ハーフトーンの表出の増大化。
そこから映し出されるのは新自由主義経済下での格差や貧困そして排除の影が「モノ」の表層の「ビジュアル・ナラティヴ」の世界から染み出してくる。
それらを直截に身体が受け止めていた様に思う。
六〇年代末でのフロッタージュに向う私の身体にはリンとした直立性が貫かれていて、モノクロームのコントラストが鮮明な擦像には向うべき対象も感じとられていた。
対象が巨大で圧倒的で在ればある程、擦り採る筆圧とタッチが強く、激しくなっていったのが読み取れもした。
それが二〇〇〇年に入るや、擦り採られる擦像からのモノクロームのコントラストが曖昧になるにつれ、フロッタージュに向う私の身体も次第に直立性を欠き、融解し、溶け出す様な感覚が擦る行為に添うように表出してきた。
二つの時代のアーバン・フロッタージュが示した擦像が映し出す二様の「ビジュアル・ナラティヴ」からは明らかにその社会に潜み、根付くものの差異を浮き出させていると同時に、私の「身体」の様態の差異も暗示的に示しているのが分かる。
渋谷再開発の工事現場が極めて劇場型であるからこそ、モノの世界が語り出す「ビジュアル・ナラティヴ」に応答出来る様態やモノが商品(記号)に置換され、そこから生じる「ビジュアル・ナラティヴ」様態の移行などを見極めて狼煙を上げたい。「渋谷問題」の所在に気付いてもらいたいからである。それらを比較実感する所からも「渋谷問題」にアプローチし、切り込むことが出来る。こうした視点こそが「渋谷問題」の一角をその工事現場の渦中から探る基本的態度となるものなのだ。
呉々も「渋谷問題」は頭でっかちな構えだけでは立ち行かないものなのを識るべきなのです。なにより「渋谷問題」には多くの「私」を介在させたものでなければならない。
一〇〇年に一度の一大都市更新事業であるだけに、そこから派生する問題群には、これまでの都市更新では検討されえなかった様な領域や局面に出会うであろうことは覚悟しなければなりません。その為にも新たな問題群の所在を特定することが必要となり、そのチャンスの一つとなるのが誰も踏査せず、手付かずであった再開発工事現場なのです。
(つづく)
連載記事一覧