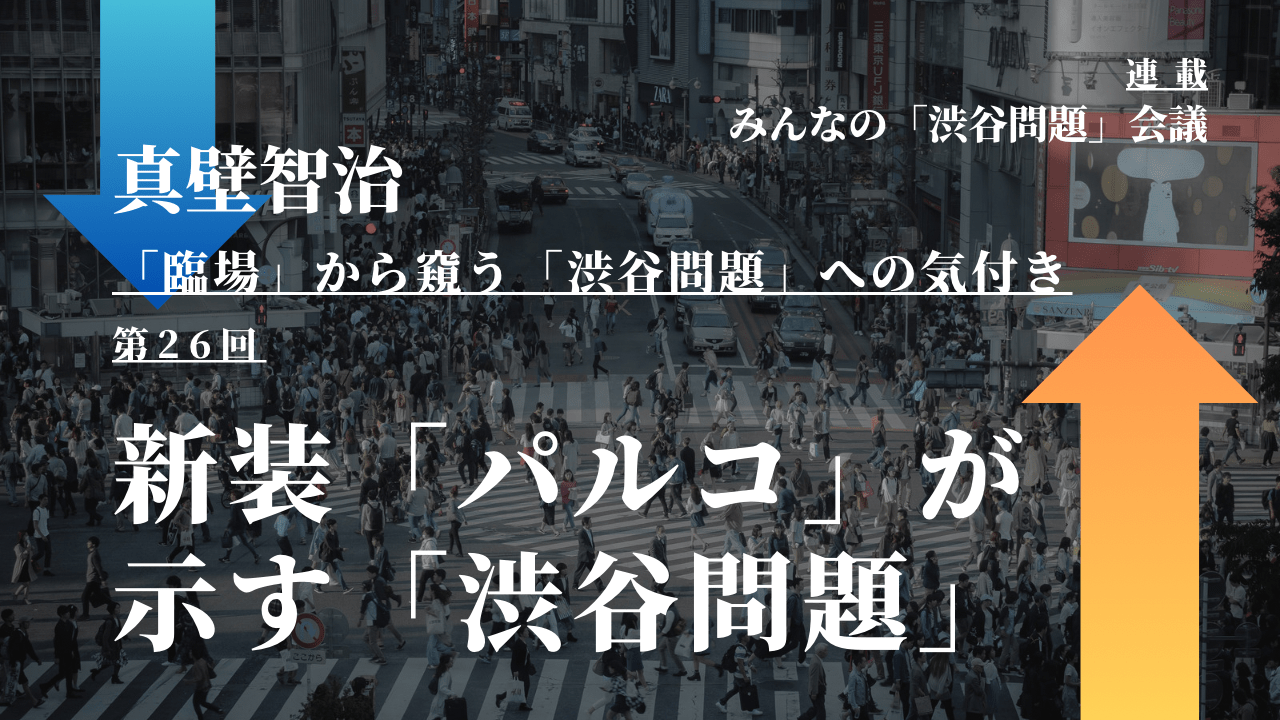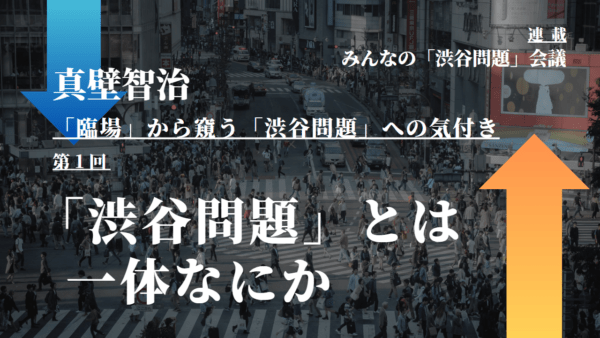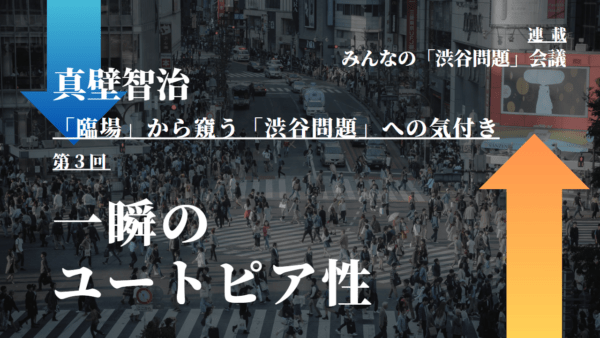新装「パルコ」が示す「渋谷問題」 – 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第24回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。


≪横にスクロールしてお読みください≫
新装「パルコ」が示す「渋谷問題」
これまで渋谷再開発の動向に対峙しようと進行する工事現場を臨場して来たが、私の脳裏から常に離れることなく、抱いて来た懸念があります。
果して、この再開発が本当に都市生活文化を豊かに生みだしうるのだろうか、一体「エンターテインメントシティSHIBUYA」とはどの様な様態と事態とを渋谷に招来してくるのだろうか。
再開発の内にどの様な公共性(公共空間)が育まれうるのか、そしてなによりも再開発が渋谷全体にどの様な再生効果を及ぼすのだろうか。
このような私の懸念・疑惑は臨場を重ねれば重ねる程尽きるどころか、益々増大して来ていたのです。
そこで五〇年を経た「パルコの第2章」(牧山浩三パルコ代表執行役社長)とされる渋谷「パルコ」の新装された再デビュー(二〇一九年一一月二二日)をこのタイミングで検証してみようと思った。
それはいたたまれない想いからで、渋谷再開発に対しての一方の西武「パルコの第2章」
を検証せずにはいられなかったのが実直な想いだった。
「渋谷スクランブルスクエア」東棟のグランドオープン(二〇一九年一一月開業)と軌を一にして、新装「パルコ」は三年の時を置いてオープンしたことになる。当然西武は東急を強く意識しての一手であることは間違いない。
渋谷「パルコ」はパート1(一九七二年)以来、パート2、パート3と増館し、新しい業態・複合ファッションテナントビルとして、華やかに渋谷の七〇年代、八〇年代の文化シーンを牽引し、名実ともに都市文化を醸成して来た。
しかし、バブル崩壊から始まる長い景気低迷と共に「パルコ」の業績も落ち、一気に渋谷の文化の創造・発信の力が稀薄になり、都市文化の前線から後退して随分と間が空いていた。
私の意識からも渋谷「パルコ」は遠い存在となっていたものでした。
いつ以来だろうか、久し振りの「パルコ」である。
白くヴォリューム感のあるキュービックで端正な外観の新装「パルコ」の第一印象は、知的でセンスのいい建物と映り、往時の「パルコ」と重なった。
新装「パルコ」をどの様に解読するのか。
私の関心は、飽くまでも長い低迷からの脱却策として、どの様な構えの施設を街に向けようとしているのか、更には東急が展開する駅前再開発への対抗がどの様なものなのか、を探る一点に在る。
それは、これからの渋谷に於ける「建築の資質」という観点から「パルコ」を検証してみよう、と言うことになります。
新装「パルコ」は都市再生特別地区制度を基にこれまでの三館体制を「一街区」として集約し、三〇〇パーセントの容積割増を取得しての再編デビューとなるものだ。
目立った特徴はそれまでのパート1、3の二つの建物を一つの施設に統合し、その間の道路を「ナカシブ通り」として施設内歩行者専用通路に生まれ変わらせたことです。
同時に、建物回りの外構もこれまでの「パルコ」とは異なる表情の設えになった。建物の外周を全くのシームレスな床仕上げを図っているのです。これらを「通り」と「外周」からも新装「パルコ」が街への接地性を最大のポイントにしていることが窺えよう。
外構の床のシームレスな仕上げ、としたが、単に機能的なバリアフリー・デザインを示しているだけではなく、それを遙かに越えた街に関わる構えとしてのデザインとなるもの、と認識した方が実態に相応しく、更にそれは建物の足元の接地性から施設自体や施設と街との関係性を捉え直そうとしている、と認識できる。
何故なら、坂道に沿って立つ建物の足元の外構処理は、単に街路と建物外構と建物入口とをフラットに整えるだけなら、バリアフリーに充分配慮した床デザインの域だけなのだが、渋谷「パルコ」は更にその先をデザインの主題にしているからだ。
建物の四方が坂の微地勢に接して立つ特性がデザインの主題の基になっているのが分かる。
床面の微妙な勾配を合せ、コーナー(角)と勾配の取り合い、建物と街路との余白、隣接する施設と街路との動線、建物への引き込みと勾配の具合い、そして象嵌の様な床材の切替え、滑らかな床材仕上げ、公道と民地との馴染ませ、などが建物外構デザインの穏やかな構成要素となっています。
勾配は一方向だけではない。
街路に沿った勾配と建物に向っての勾配との二方向がここの床では錯綜し、交差し合って実に繊細で微妙な「微地勢」をデザインとして作り出しているのです。
「微地勢」を含んだ建物を囲む余白は広場の様な感覚を私たちに与えます。「微地勢」が私たちの身体と感応する。
これは明らかに前「パルコ」からは感じ得なかった感覚で、新たに生み出された「微地勢」の床の身体化により創出された「広場感覚」は新装「パルコ」が持つ新たな建築資質となってゆくに違いない。
都市に多く目に付く、形ばかりの「広場」ではなく、どこにも広場と謳っていないのに、誰もが一様に、そして一瞬に感覚として「広場」を感知出来るニュアンスがここには在るのです。
そこでは自然と人がアフォードされ、溜まり、流れ、賑わいが予感される。
それこそが街の中に生まれる「公共空間」としては一つの在りうべき所在だ、と思う。そこでは公道も民地もルーズに収まっていて、緩く広場感覚が周辺に浸透している。
しかも、ここで面白い体験は、建物の外構・外周を巡ってもこの広場感覚が実感されることだ。施設を時計回りに巡るのと反時計回りに巡るのはその広場感覚が多少異なるのも、新鮮な発見です。こうした「パルコ」の外周を巡る回遊歩行から生まれる広場感覚は、まさに街への接地性の創出に由来してのものだろう。そこで肝心なのは、生まれ始めた広場感覚に規制を加えてはならないことだ。規制とは、広場感覚を損う管理行為を指す。
私はこの「パルコ」の微地勢を活かす広場感覚に、渋谷再開発への西武の対抗に読み取れるのです。
実際、「渋谷スクランブルスクエア」東棟2Fのメインエントランス前の場所(「アーバンコア」)からは一向に通路以上の広場感覚は感知されない。「パルコ」の広場感覚は誰もが楽しめる公共空間として育ち、定着していって欲しい。
新装「パルコ」の建築資質として「ナカシブ通り」にも注目したい。施設を貫通させ、南北の微地勢の調整を図るだけでなく、「公園通り」に面した「広場」と共に「通り」を作り出したことは、渋谷にとって小さな都市資源の一つを加えてゆくことになろう。ここにも通り抜けたり、溜まったりする楽しさを見出すことができる。
「公園通り」から「ナカシブ通り」へ、あるいは「スペイン坂」から「ナカシブ通り」へと、微地勢感やスケール感、街並みの様相が異なる「坂」と「通り」のシークエンス体験は「歩行のまち」を目指す渋谷にとっても固有のコンテンツになるはずだ。
こうしたデザインされた都市の余白が全面に強く感じられるのが新装「パルコ」の建築資質の大きなポイントになっていて、街と連なる豊かな公共空間を形成し始めていることが早くも窺える。
街に開かれた余白を生み出してゆくことは、一定以上の施設開発では需要な取組み要件とならなければならないし、都市に新たなアーバニズムを生み出す為にも必要不可欠な視点とならなければならない。
改めて、新装「パルコ」の接地性を今の渋谷の事態から考えてみよう。
銀座・表参道に建ち並ぶスーパーブランドのアイコン建築への道を安直に選択しなかった「パルコ」は賢明であった。
アイコン建築は場所を選ばず、どこにでも建つインパクトの強い印象を作り出すことを意図した建物のことです。そこでの最大の要請は他との強力な差別化が図れ、偏に目立つこと。従って、それは立地性を咀嚼しない非立地主義が前提になり、スター・アーキテクトの利己的作品主義の独壇場となってきたものです。
「パルコ」が選択した接地性とは言うまでもなく立地性に依拠するもので、地勢を含む立地性を丁寧に読み解いて大地の上に広場感覚を生み出し、そこに実感しえる賑わいのある公共空間を体現させている。そこの場所でしか創りえない建築が生まれた。
一方、巨大再開発となる渋谷駅前が露わにしている事態はどうか。「アーバンコア」と「スカイウェイ」の動線の装置化で地勢、本来のグランドライン(GL)を蹂躙している事態を生んでいて、それを「快適な移動と美しいデザイン」にその公共性を担保させようとしているのだ。
大地から離れた地に足の着かない場所の公共空間に対して私たちは直感的、生理的に、際疾い場所だと思うのはどうしてか。これらを「公共貢献」と言うのだとしたら、それは公共性の意味と可能性を極度に限定させてはいないか。つまりは流すだけの機能性のみの公共貢献ではないか。
こうして見てくると、西武と東急との間にある対照的な開発視点が露わになるはずです。
グランドから離れることを加速させる「渋谷スクランブルスクエア」東棟、「渋谷ストリーム」、「ヒカリエ」の東急勢に「MIYASHITA PARK」の三井不動産を加えた離陸派。グランドから乖離し、空中を制覇しようとする立場。
グランドこそ施設開発の立脚点であり、よりそれに依拠しようとする渋谷「パルコ」の西武接地派。グランドに依拠して、グランドを解放しようとする立場となるものだ。
そこには開発の規模・課題・戦略の絶対的な違いがあるけれども、少なくとも規模が大きければ大きい程、一概に皆が良くなる開発とは限らないことだけは確かなことでしょう。
それに地面から離れれば離れる程、街が死ぬことも皆が気付きだしているはず。
地面から離れることと、地面を開放しようとすることとはその前提が丸っきり別物であることを私たちは見抜いてゆかなければなりません。
離陸思想は非立地主義と極めて相性がいい。それに比べ、接地思想は立地主義を遵守する。
この二つの視点の所在が施設開発の在り様を大きく左右することになるのです。
今後の渋谷は、地勢・地面を巡っての離陸派と接地派との対比的せめぎ合いが結果的に街の魅力を生み出してゆくことになるかもしれない。
「歩行のまち・渋谷」の面白さとはその矛盾こそがなるべきで、渋谷の歩き方の提案が渋谷全体の活況へと繋がるかもしれないと私は考えています。どんな渋谷の歩き方が望ましいのか、を問うことからこそ、みんなの「渋谷問題」の本質も始まらなければならないのではないか。
新装「パルコ」の建築資質を見てきた。
外観デザインはどうか。
建物の外観デザインも外構デザインも共に地勢に沿って移動する裡からの見え方を配慮する場所に棲みつくデザインがスタディされていた、と思える。つまりいずれもが接地性をデザインの根拠にしているものです。
そこでは「移動とデザイン」がテーマとなるシークエンシャル・デザインを課題とし、人の移動から生まれる光景と地勢の感触を留めることを試みたことになります。
そうして「場所」を新たに刻もうとしたことが新装「パルコ」の建築資質を結果として映し出していた。
「公園通り」を登ってゆくと緩く道がカーブする。この坂道の登りとカーブの効果から「パルコ」の外観デザインがシークエンシャルに楽しめるのです。
石切り場の様な大きく分割された白い外壁面の構成は、移動につれて表情を静かに移わせてゆく。圧巻なのは微妙に壁の小口を見せてハングする外壁面で、「パルコ」の前から大きく右に折れ曲がる通りの彼方を指している様な振り(ムーブマン)は建物に生命感を与えていて、通りと共に棲む情景をつくり出していることだ。
これまで述べてきたように、移動とデザインは渋谷再開発の公共貢献を担保する上での必須の要件でした。
「快適な移動と美しいデザイン」がセールストークとされ、それを達成する具体的な設置として「アーバンコア」と「スカイウェイ」がデザインされてきた背景を持ちます。
そこで移動とデザインの価値指標となった「快適さ」と「美しさ」は感覚としては厳密なものではありません。従ってその感覚が何を保証し、何を確認し合えるかは極めて曖昧にならざるを得ない。だからこそ、開発のセールストークに公共感があり、大義な感覚としてそれらが織り込まれたのであろう。それに引き替え、新装「パルコ」が都市に現象として生み出している「移動とデザイン」は人の心に映し出されるものなのです。
人の心に映し出されたものを介して街との関わりを確かな実感として掴むことができる。それは必ずしも「快適さ」や「美しさ」が漠然と示そうとするものでは敵わない、小さな確かな実感として体験されるものになります。
都市は与えられた言葉ではなく、自らが実感し得た言葉でこそ生きられるべきものなのである。
新装「パルコ」の建築デザインが示したものは、その外観にしろ、外構にしろ、場所の地勢と立地を遵守し、どこまでも大地との接地性を建築デザインの土台とする設計態度でした。そこに人々の確かな実感をもたらし、場所と人との感覚とふるまいの循環を生み出そうとしているのが分かる。
地勢のまち・渋谷にはこうした思想に依る建築デザインが不可欠なのは言うまでもないことなのです。
新装「パルコ」は建物・まちづくり・都市制度の三位が一体となって「次なる渋谷の文化を創造・発信する街の拠点」を目指すものなので、「都市再生特区」としての拠点の動向を私たちはこれからシビアに見届けてゆく必要がある。
「パルコ」の建築資質を活用したソフト展開がどんな「渋谷」を創出するのか、それがなによりもの都市再生特区の役割と評価に繋がるのですから。
新装「パルコ」の在り様も「渋谷問題」として充分に議論するに足る余地を持つ。
(つづく)
連載記事一覧