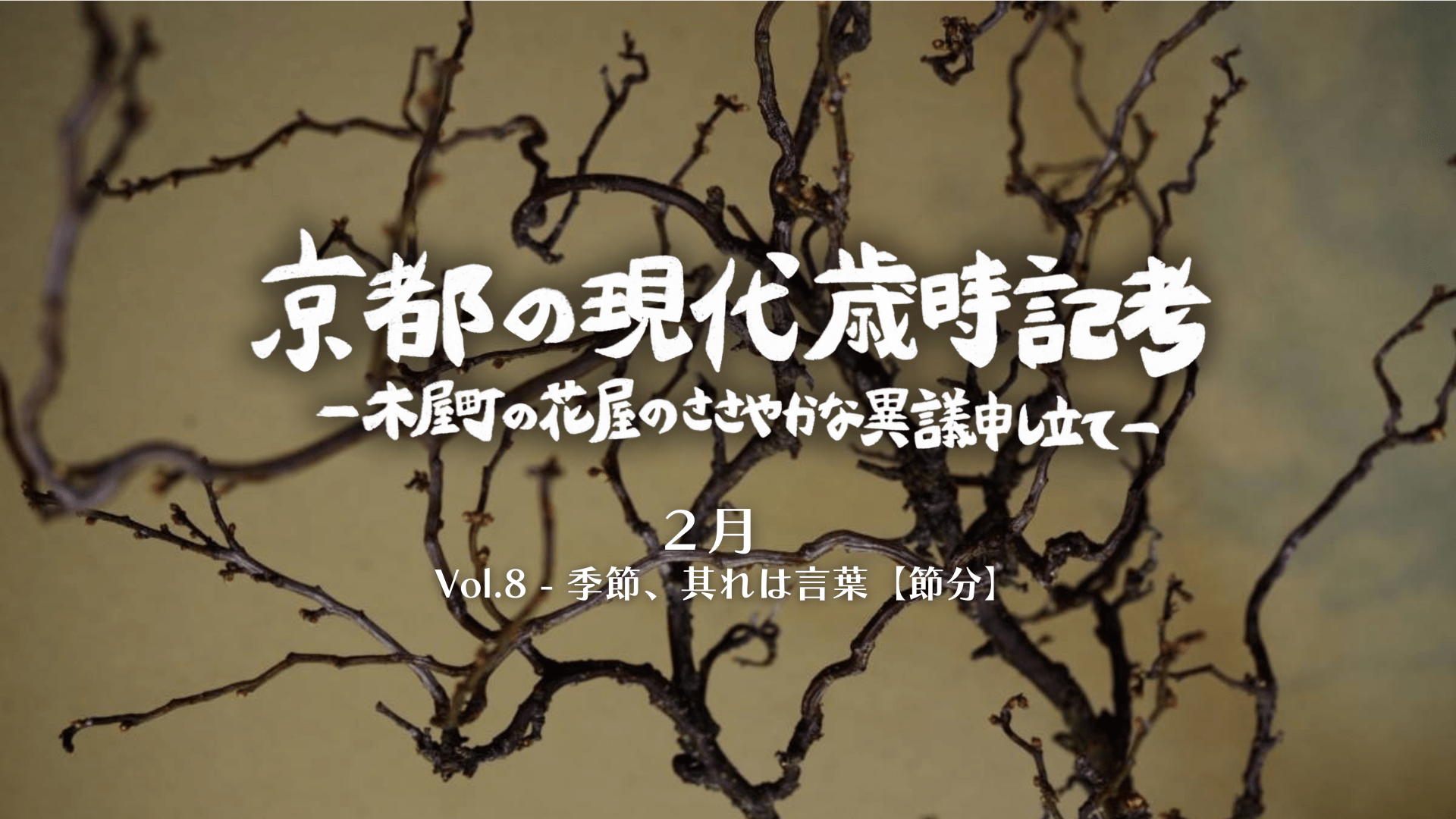季節、其れは言葉【節分】|連載「京都の現代歳時記考 -木屋町の花屋のささやかな異議申し立て-」
先人たちが日本の気候から見つけてくれた、
美しいもの・儚いもの・恐いもの、その中で生きていく知恵と工夫。
そんな季節特有の本来の暮らしぶりと、現代の暮らしぶりを結び、歳時記を再解釈する。
松尾芭蕉は言った。「季節の一つも見つけたらんは、後世のよき賜物」
私たちは、100年後の人々に、どんな贈り物をできるだろう。
なんかわくわくして、めぐる季節を感じて、余裕があれば祝えばいい。
ちょっと変わった視点から、京都・木屋町に店を構える花屋の主人が現代の暮らしにすこしだけ反抗します。
執筆者プロフィール
西村良子
京都木屋町の花屋「西村花店」店主、華道家。1988年京都府生まれ。2010年関西大学卒業。先斗町まちづくり協議会事務局兼まちづくりアドバイザー。2017年に花店を開店し、現代の日本での花と四季の楽しみ方を発信し続けている。木屋町の多くの飲食店や小路は西村さんの生け込みで彩られている。

節分とは、立春の前日のことである。季節の分かれ目で、節分。だから立夏の前日も立秋の前日も立冬の前日もみんな節分なのだけれど、いつの頃からか立春節分だけが祝われるようになり、いつの頃からか節分だけが祝われるようになった。
天気予報では今でも変わらずこの二十四節気にのっとった季節を伝えてくれるけれど、立春の日のレポートは、必ず「暦の上では春ですが」から始まり、「でも今は冬真っただ中です」と続く。節分は冬の行事として定着し、立春はその存在が忘れられつつある。
二十四節気が今でも生きているのは日本だけなのだけれど、世界の暦と共通する部分がある。春分、秋分、夏至と冬至である。地球が傾いて自転しているために光が見える時間(昼)と見えない時間(夜)が一日ごとに違い、その長さがちょうど半分ずつになる日が春分と秋分、一年で最も昼が長くなる日が夏至、短くなる日が冬至である。これは事実であり、文化や信仰に関わらず世界中に共通している。イエスキリストの誕生日が12月25日なのは、冬至のすぐ後、つまり太陽が力を取り戻し始める頃だからだという説がある。
世界にはいろいろな気候や季節が存在する。約束された真実は、地球の自転による日照時間の変化、それしかない。私たちは「季節」を現実に存在するものだと思いがちだけれど、実際にはそうではない。四季なのか六季なのか二季なのか、二季ならば夏と冬なのか、雨季と乾季なのか。決めたのはその国の人々である。その証拠に、日本は科学的にいうと四季の国ではない。紛れもない雨季が存在する五季の国である。しかし日本人はその雨季を「梅雨」と名付け夏とした。「季節」は人間が恣意的に作り上げた記号なのだ。ちょうど言葉と同じように。
世界の多くの国で、夏至と冬至に重要な意味を持たせていることが多い。その場合冬とは冬至から春分までの期間をいい、春とは春分から夏至までの期間ということになる。しかし二十四節気は春分より一か月以上も前、多くの国が冬と定めた時期を、春の始まりとしたのである。
言葉が国によって違い、同じ国であっても時代によって通じないことがあるように、立春という季節は、現代の日本人にとって意味を失いつつある。現代語の「春」は、どんな色や温度なのだろう。

ぱっと思いつくのはやはり桜だろうか。桜のつぼみが膨らみ始めることにその兆しを見つけ出し、「開花宣言」はまるで決められた春の始まりである。現代では桜は並木に植えられていることが多く、つぼみがどんどん咲き進み空が桜色に覆われて行く様はまさに春、である。視界だけでなく、共有された写真でスマホの画面も瞬く間に同じ色に染まって行く。その頃には気温も湿度もすっかり上がり、私たちは疑いようのない春を疑う術もなく祝う。
花が極端に少ない立春の時期に、お茶室でもいけ花で重宝されるのは、「雪中花」の異名を持つ水仙である。その名の通り12月~1月頃に咲き始める。水仙は、いけ花の伝統的な形「生花」という古典いけ花の中でも特に技術が必要な形に用いられる。とりわけ水仙は葉っぱを外し組み替える「葉組み」というテクニックを必要とする、技巧が際立つ花だ。
その中に、「早春のいけ方」という特別な形がある。葉っぱが先に育ちその間から花芽を伸ばす水仙は、咲き始めた頃の花は葉より低く、すっと伸びた細長の葉の合間に白い花が覗くという姿になる。やがて時が進むと花茎が伸びて行き、年が明ける頃には葉の丈を超える。
葉組みの際、わざと花の方を伸ばし、成長した年明けの姿を表現したものが「早春のいけ方」である。ただでさえ組み替えた葉と花をもともとそうであったように自然に見せつつ、生花の形に整え立たせるのが難しい水仙なのに、花だけ伸ばすにはさらなるテクニックが必要となる。そこまでの技巧を凝らしてまで、この形が求めたものは何なのか。
それはきっと、春を待つ気持ちではないだろうか。水仙は基本的には冬に咲く花である。それでも、早春のいけ方は季節が間違いなく春に向かって進んでいるのだということを表現することができる。少なくとも、いけ手がそう想っていることを。「まだ寒いけれど、春はすぐそこです」だろうか、「寒くつらい時期はいつまでも続きません」だろうか。春を待つ気持ちを「望春」という。立春とは、そんな日だったのではないだろうか。


一年で最も寒い時期に定められたこの国の春の始まり。気候的にはとても春と言えない、目にも肌にも春を感じられない「春」は、私たちに、想像し伝える余白を残してくれていた。待つ春も過ぎる春も春に数えることで、この国の春は長くなり精神的な深みを帯びた。桜という花とそれが咲く気候というあまりにも限られた短すぎる春は、季節を思い描き作り出すことのできなくなった現代社会を浮き彫りにしているように思えてならない。
「暦の上では春ですが」。その言い回しは、さも誰か知らない人が作った現代には通用しない暦を押し付けられているように聞こえるけれど、作ったのは日本人である。日本にしかない暦である。日本語という考え方や伝え方で構成された社会を日本というならば、日本の暦に基づいた考え方や伝え方が、日本の暮らしと言えはしないだろうか。それは、どんなに便利で効率の良い生活が当たり前になったとしても、異常気象が増えたとしても、忘れてはならないことである。
季節の花

南天(メギ科)
桜が咲くころには他の花たちも合図をされたように咲き乱れる日本ですが、2月頃まではほとんど椿と水仙くらいしかない、花好きには寂しい季節です。
そんな中、冬につく赤い実は格別です。クリスマスのサンキライ、お正月の千両に続き、節分の南天とまるでバトンのように季節に応じた赤い実を飾っていきます。
南天の葉は深い緑ですが、一部紅葉し赤銅色の葉が混ざり、お正月から立春にかけて花瓶に1本いけるとなんとも格調高い雰囲気が出ます。
南天が節分の花とされているのは、季節の変わり目である節分には魑魅魍魎が移動するので、魔除けを願った人々に「難を転ずる」に通じる名前が好まれたからです。
小噺
本連載の執筆者が構える「西村花店」であるが、実はこの花屋何やら企んでいるらしい。
小噺として、今後の「西村花店」の行く末も紹介。
毎話の再解釈が花屋の空間にどう昇華されていくのか、そんな様子もお楽しみください。
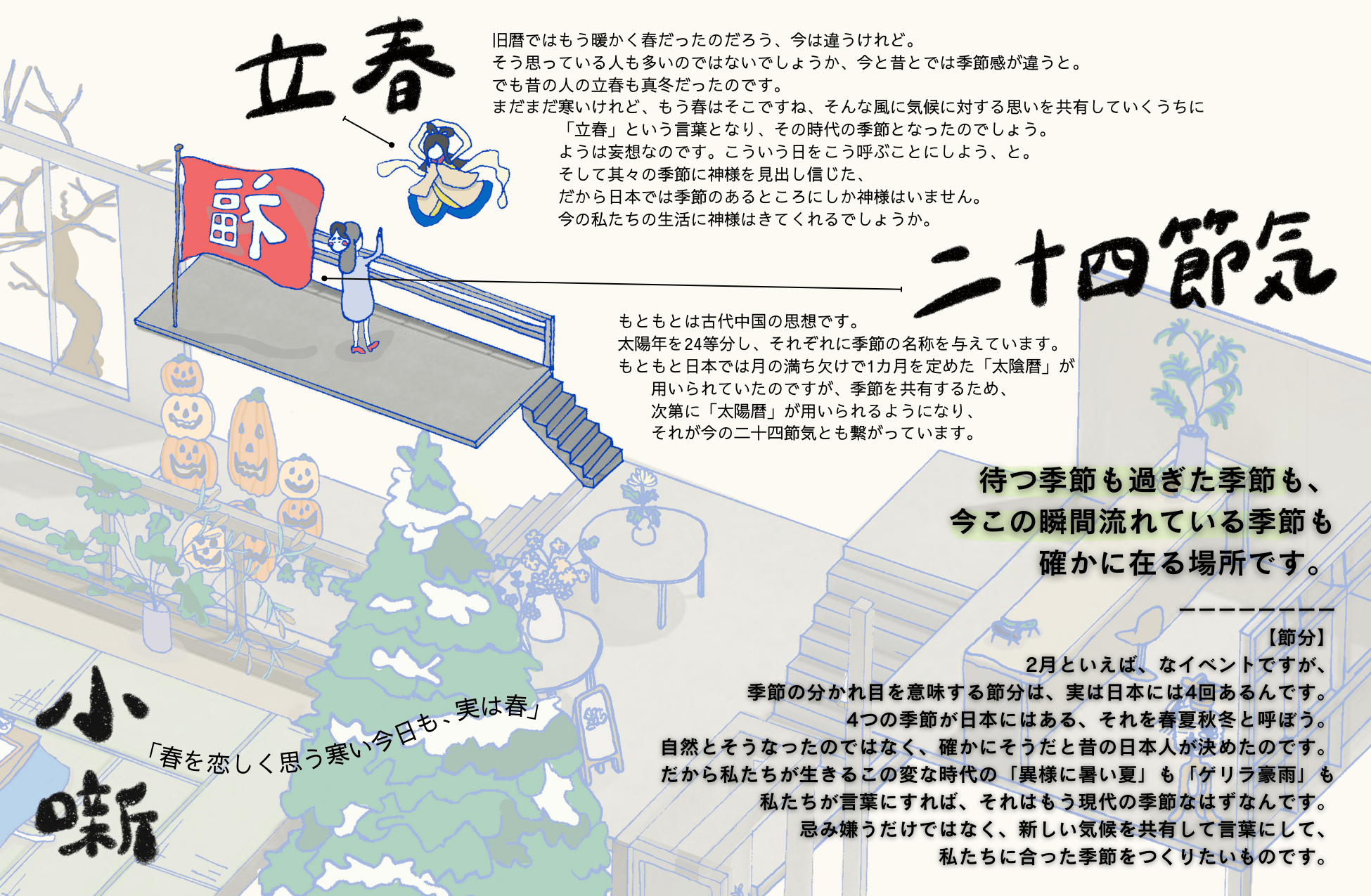
二十四節気
もともとは古代中国の思想です。太陽年を24等分し、それぞれに季節の名称を与えています。日本では昔こうした、地球が太陽の周りを一回転する時間を一年とした「太陽暦」ではなく、月の満ち欠けで1カ月を定めた「太陰暦」が用いられていました。統一されたカレンダーというものがない時代に、空を見上げるだけで日付を読めたこの暦は、昔の人にとっては便利だったに違いありません。
しかし月の動きは、日照時間や気温を司る太陽の動きとはなんら関係がないので、実際の季節と暦が年々ずれていくという特徴がありました。
季節を共有するため、次第に「太陽暦」が用いられるようになり、それが今の二十四節気とも繋がっています。
立春
旧暦ではもう暖かく春だったのだろう、今は違うけれど。そう思っている人も多いのではないでしょうか、今と昔とでは季節感が違うと。でも昔の人の立春も冬だったのです。
まだまだ寒いけれど、もう春はそこですね、そんな風に気候に対する思いを共有していくうちに「立春」という言葉となり、その時代の季節となったのでしょう。
ようは妄想なのです。こういう日をこう呼ぶことにしよう、と。
そしてそれぞれの季節に神様を見出し信じた、だから日本では季節のあるところにしか神様はいません。
今の私たちの生活に神様はきてくれるでしょうか。
企画・編集・小噺イラスト:安井葉日花(学芸出版社)
題字:沖村明日花(学芸出版社)
撮影:生駒竜一