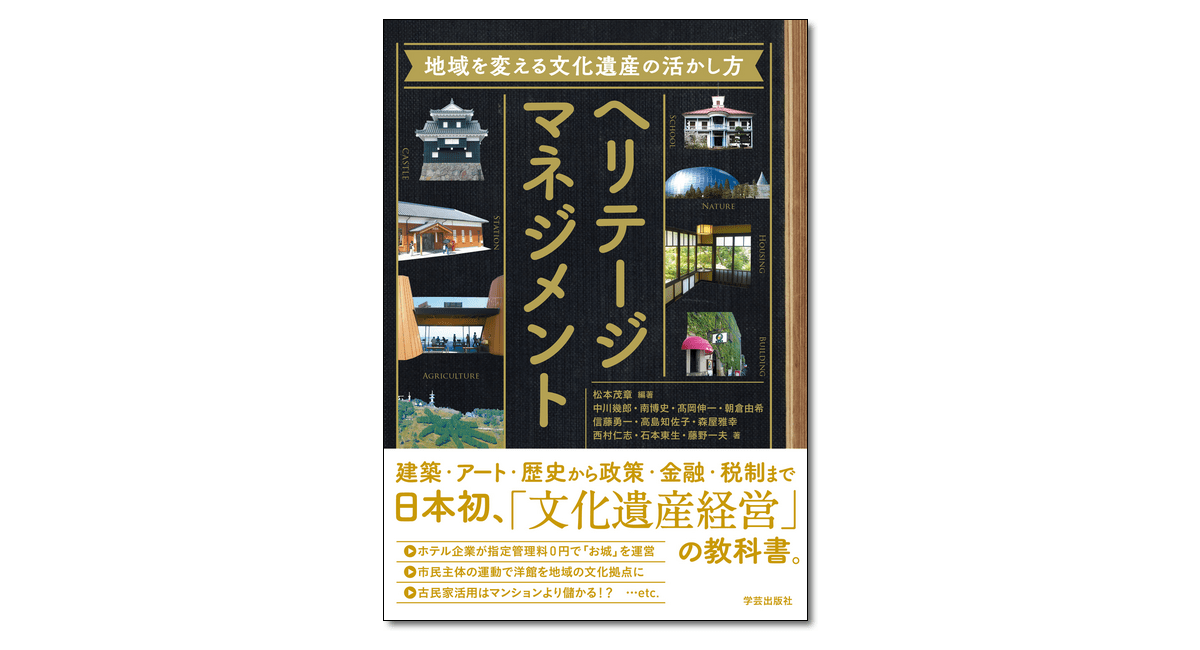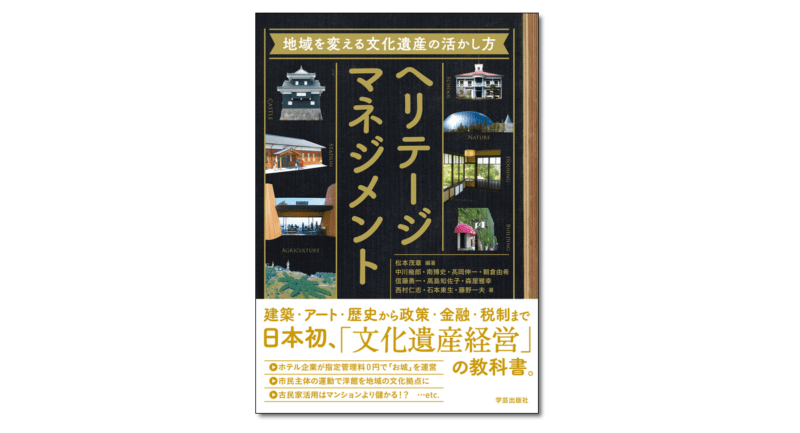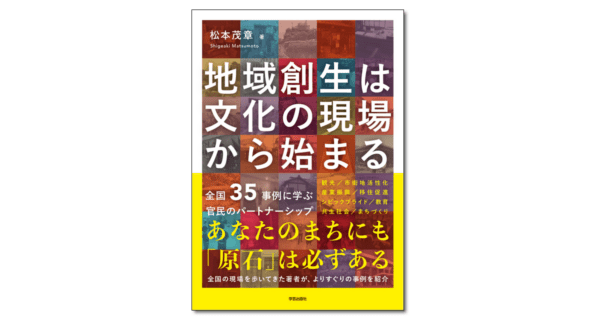【受付終了】妖怪の名前は、なぜ、爆発的に増えたのか?-25年10月からのNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に寄せて、妖怪博士をお招きする-|第19回文化と地域デザイン講座
| 主催 | 文化と地域デザイン研究所 |
|---|---|
| ※詳細は主催団体等にお問い合わせください。 | |
- 日時:2025年9月7日(日曜) 午後2時~午後4時すぎまで
- 会場:アカデミックスペース「本のある工場」 (大阪市此花区西九条5-3-10)
- 参加費:無料
- 詳細・申込:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBmQ1fzSiAzVZk9z4SPj4FCIGNZxH_-mNF94YsigW2b0AybQ/viewform
内容
2025年10月から、小泉八雲の妻「セツさん」を主人公にしたNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」が放映されます。
これを機に、総合研究大学院大学にて、日本で初めて妖怪研究で博士号(学術)を取得された香川雅信先生(兵庫県立歴史博物館学芸課長)をお招きして、妖怪の名前について語っていただきます。
日本の妖怪は、中世まで、ごく限られた種類にとどまっていたそうです。なぜ、江戸時代の17世紀に至って、急激に増加したのか? 香川先生は、妖怪の「名前」に注目し、俳諧の俳人たちが全国各地の「化けもの話」の収集に励んだことを解明されました。<鬼魅の名は>の視点から語られます。妖怪という地域文化資源に関心のある方! 松尾芭蕉がひらいた俳人の情報ネットワークに関心のある方! 民俗学に関心のある方! 「文化×地域×デザイン」に関心のある方! お越しください!