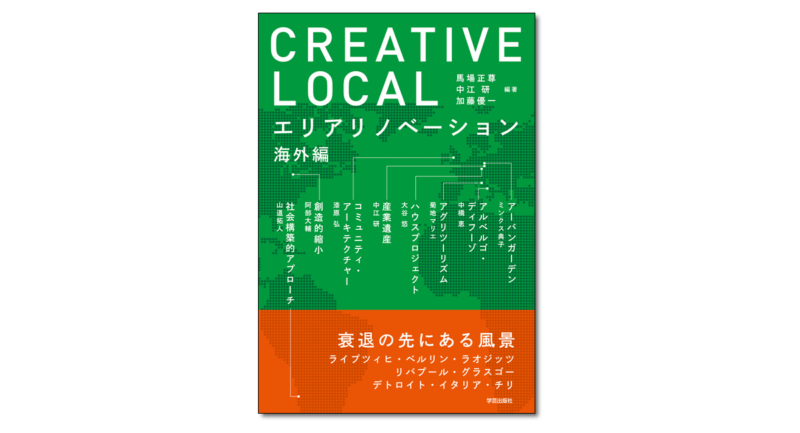[レポート]パブリックをどう動かすか|馬場正尊×藤村龍至

新著『PUBLIC DESIGN』やウェブサイト「公共R不動産」で新しい公共空間の扉を開こうとする馬場正尊。埼玉県鶴ヶ島市、川越市、大宮地区で公共施設マネジメントに取り組む藤村龍至。まったく異なる方法論で「パブリック」に対峙する2人が語る、硬直したパブリックの動かし方、人口減少時代の建築家の役割とは。


どうすれば人は動くか
馬場 今度『PUBLIC DESIGN 新しい公共空間のつくりかた』という本を出しました。この本の中でリアルなパブリックスペースをつくったり運営している人を6人ピックアップしてインタビューしているのですが、その6人が全員僕より若かった。この世代はどのようにパブリックを捉えているか、そこに新しい社会のシステムや空間の運営の方法論が眠っていると考えて、建築業界なら藤村さんにお話をお聞きしたいと思い、対談をお願いしました。
藤村さんは僕と世代もアプローチも違うわけですが、ストラテジー(戦略)はすごく似ている。僕もそうですが、藤村さんもプロジェクトを動かす時に、場で発表すること、メディアを使うことをきわめて意識的にやっていますよね。
藤村 以前、五十嵐太郎さんが「メディアの人はメディアに興味を持つ」と言っていたんです。たとえば新人が雑誌に取り上げてもらうには、まずメディアの人に関心を持ってもらう必要がある。地方都市で建築家と議論すると、彼らは目の前にあるコミュニティの人たちに向かって発信すれば物事は動いていく。一方、東京のような大きなパブリックでは、メディアを介してでなければつながれない。
私が東洋大学の学生たちと埼玉県鶴ヶ島市で公共施設マネジメントに取り組んでいるプロジェクトは、最初は地元のメディアにしか取り上げてもらえませんでしたが、渋谷のヒカリエで展覧会をしたら全国メディアで「先進的な事例」として紹介されるようになり、それまで消極的だった行政職員や住民たちの意識も変わっていきました。
馬場 僕は本やウェブといったマス的なメディアを媒介にして物事を動かそうとしていますが、藤村さんは事件のような展覧会やワークショップを起こして、それをマスにつなぐという、もっと小さいポーションで物事を仕掛けようとしている点が面白いですね。行政を動かそうとするとそのくらいのサイズから仕掛けていった方がよいという感覚があるんですか。
藤村 そうですね。ただ、情報発信の手段や速度は進化していますが、既存の制度・組織・地域社会といった「レガシーシステム」がついてこれるスピードはあまり変わっていないというのが現状です。
たとえば、「鶴ヶ島プロジェクト」でも、鶴ヶ島市に公共施設マネジメントを提案して、東洋大学のプロジェクトとして取り組み始めてから実際に行政が動くまでに5年くらいかかっています。鶴ヶ島市の人口はおよそ7万人です。7万人の市の組織というのはそれなりに大きいわけですが、最初の頃は市役所のロビーで展覧会をしても役所の人たちは素通りでした。公共施設マネジメントが自分たちの組織にとって将来的には重要だと言ってはいても、実際にはその問題意識は全然共有されていなかったわけです。ですが、5年が経ち、ようやく役所の人たちも動きだす雰囲気になってきました。
馬場 行政のレガシーシステムを動かすにはやはり「5年」かかるんですね。
僕はこれまで民間の仕事が多かったんですが、民間だと物事を動かすのに「3年」という感覚ですね。たとえば「東京 R 不動産」 というメディアを立ち上げて、新しいプロジェクトが生まれるまでに大体3年くらいなんです。
藤村 たしかに民間に比べれば時間はかかりますが、逆にそれくらいかければ行政も意外と動くんだなとも感じています。
さらに行政の仕事の場合、政策とつなげることが大切です。公共施設の再配置を、総務省の公共施設利用計画や財政論、国土交通省のコンパクトなまちづくりや立地適正化計画といった政策メニューの間に位置づけて実行することが重要です。でなければ、行政組織はついてきません。逆に言えば、そこを突破口にすれば一つ一つのポーションは小さくても動いていくのです。
公共と民間の境界線を引き直す
藤村 私は人口減少社会で皆が弱ってきているのは実は素晴らしいことだと思っています。開発の時代だと、たとえば鉄道会社と沿線自治体は、開発許認可の問題を巡って敵対しあう関係になりますが、人口減少が激しくて乗降人員がすごく減っている地域では、鉄道会社と行政が協調してどうやって人口を誘導しようか、都市機能を補完しようかという話しあいが必要になってくる。人口減少やお金がないということを入り口にして共通の戦略を持つような場面が徐々に生まれてきた。少し前なら信じられないことが起こっているのです。お金がないという状況は何か新しいしくみを生みだしていく突破口になるという気がしています。
馬場 今後は都市間競争が否応なく起こりますよね。これからの行政は生き残りをかけてほとんど民間と同じ感覚で地域を経営していかざるをえない状況になっていくと思います。
藤村 成功すればポートランド、失敗すればデトロイトというように、すでにアメリカでは結果がはっきりと出ています。日本でもデトロイトみたいになるところがどんどん出てくるかもしれませんが、そういう状況下で重要になってくるのが、「今持っているストックをどう使うか」ということです。たとえば中心市街地の道路は非常に貴重なストックです。道路使用を規制する道路交通法を柔らかくする、あるいは都市公園法を拡大解釈をして、道路や公園を広場みたいに使えるようにしていくと、札幌市のように人が集まる道路ができるわけです。このような取り組みができるかできないかが「都市の差」になって表れてくる。
馬場 ニューヨークがブルームバーグによって一気に変わったのは、まちを経営するスタイルを行政から民間団体に切り替えたからです。荒れ果てていたタイムズスクエアでは、ビルのオーナーたちが連合して会社を立ち上げ清掃・警備などを司るようになり治安が改善して、人が戻り不動産の価値も上がっていった。ブルームバーグは上手な民間開放を短期間に行ったことで都市を復活させたわけです。ポイントは都市を細かい経営のネットワーク体、集合体として捉え直したことだと思います。
藤村 ニューヨークでは、ブルームバーグがゾーニングの40%を書き換えたといわれています。歩行者空間を拡大するとか、工場をホテルに替えるなどさまざまな規制が緩和できた背景には、「世論を啓発する」「行政と住民の間に専門家を入れる」といった、メディア出身のブルームバーグならではの戦略がありました。ガチガチの官僚組織で、多様な人種を抱えるニューヨークですら、10年かければ動くのです。
馬場 日本でもそうせざるをえないことはわかっているはずですよね。内閣府の規制緩和委員会で僕も建築基準法の改正に対する意見を述べたりしているんですが、国交省の抵抗は大きそうです。
藤村 公共施設マネジメントで気をつけなくてはならないのは、耐用年数を迎えたこの施設とこの施設を統合して少し面積が減りましたというような場当たり的な統廃合です。実際には50年くらいの単位で全体を見渡して残すところと廃止するところを計画する必要があるはずですが、長期的な視点を持たずに場当たり的にやってしまい、どんどんお金が足りなくなっている事例が散見されます。
これは丹下健三の時代とすごく状況が似ています。戦後、戦地から大量に引き上げてきた人を受け入れるために炭鉱労働者住宅がたくさんつくられました。石炭産業が終わるのは目に見えていたにもかかわらず、炭鉱労働者住宅に予算がどんどん使われていたわけです。それに対して、丹下は、それでは絶対財政破綻する、将来的な産業の転換を見越してどこに投資するべきかきちんと考えるべきだと主張し、統計的なリサーチを行いました。それが、その後の日本の国土計画につながっています。
現在はそれとは逆で、人口が減少していく状況下でどこに投資するかをきちんと計画することが求められている。そういう意味では、計画論が逆説的に意味を持ちはじめているとも言えます。
たとえばニューヨークのブロードウェイでは交通シミュレーションなどの社会実験を行って、技術的な与件をきちんと組み立てた上で、ここを道路から広場にしようと計画を立てていったそうです。そこでは、計画がまず重要で、その後にプレイヤーが出てくる。ニューヨークの再生では、民間の経営者といった主体がたくさんいたことも成功の要因ではありますが、そのような行政によるきちんとした計画があったからこそ経営が可能になったという視点も重要な気がしています。
トップアップとボトムアップ
藤村 先日、都市計画家の人たちとの議論の中でこんな話をしました。地籍が厳密にあるヨーロッパでは公的なもののあり方を皆で議論して決めることに対する責任感が非常に強いのに対し、地籍のないエリアが多い日本ではまちへの関心がかなり低いと。ですが、その一方で、果たして関心のない人たちを本当に喚起する必要があるのかという話もあります。自由に移動して暮らせる人たちや、お金がありサービスを買える人たちは基本的には関係ないわけです。ですから、サービスを買えない人たちが教育や福祉の問題に対してきちんと参加できるしくみさえ組み立てればよいのです。
馬場 藤村さんは社会のインフラシステムに興味があって、そこのボトムをどう担保しながら新しい時代の枠組みをつくっていくかという目線で物事を考え、進めているんですね。それに対して、僕はどちらかと言えば盤石なボトムを時間をかけてつくることよりも、トップアップで変えた方が手っ取り早いと考えるタイプなのかもしれません。
自分は、象徴的に変わるためのエンジンのようなものを提示することで、興味のある人から徐々に真似してもらおうというトップアップ作戦をやっているんだなと気づきました。「R不動産」のサイトもその価値がわかる人にだけわかってもらえばいいというスタンスでつくっていますし、『PUBLIC DESIGN』という本も象徴的に変化した事例を見せることから変えていくことを意図してつくりました。藤村さんと僕は見ている方向はすごく似ているけれど、アプローチはまったく逆なんですね。
藤村 しかし、トップアップというのは本当にパブリックと言えるのか?という疑問があります。パブリックには「すべての人に開く」という論理があって、つまりボトムを考えざるをえない。とはいえ、ボトムアップで公平性にこだわりすぎるあまり硬直している社会に対しての批判として、トップアップももちろん必要です。
最近は「リノベーションまちづくり」というのがすごく流行っています。閉塞した状況のなかで突破口をつくっていることはすごく素晴らしいことだとは思いますが、その事例を見ていると肝心の構造改革ができているのか時々疑問に思うことがあります。
私が最近の馬場さんの活動ですごく興味を持っているのは、点からの刺激を面にしたり、山を動かす意識を打ち出しておられるところです。そこが「リアルなパブリック」なんでしょうね。「新しいパブリック」は確かに動きだしているんですが、「リアルなパブリック」「レガシーのパブリック」をどう動かすか。
馬場 レガシーのパブリックに初めてぶつかり、怒りに近いものを感じる時もあります(笑)。行政の制度やルール、資金の流れなどがあまりに粘着質すぎて。どうやってそれを少しずつ壊していくか、試行錯誤しているところです。
たとえば最近、どんどん余っていく公共空間をうまく活用するシステムを構築できないかという問題意識から「公共 R 不動産」というウェブサイトをスタートさせました。地元では見向きもされない公共空間でも、全国的に紹介すれば東京の企業などが買ってくれて再流動化するのではないかという楽観的な感覚でつくり始めたんです。
でも実際にやってみると、公共空間が売りに出せない。「市民の反対が怖い」「将来の調整がついていない」「議員から何を言われるかわからない」といったさまざまな障害があって、「公共空間を売りに出したくても出せない」という地方の課題が浮き彫りになったんです。ほとんどの自治体で、行政資産を売買するフローがしっかりできていないし、資産価値を判断することもできない。スタートさせたものの、いきなり問題噴出という状況に直面したわけです。
鶴ヶ島市では、スムーズに公共空間の再配置を進めていける実感はありますか。
藤村 既存のレガシーシステムの中だけではなかなか動かないのかもしれません。鶴ヶ島でも大学という実験場が行政の横にあって、そこで世論をつくっていってようやくゆっくりと山が動きだした感じです。
私はオランダに1年間留学していたんですが、オランダの合意形成は本当にリニアで、意思決定はやたらと早い。その代わりに雑と言うか、あまり細かいことにこだわりません。それに対して、日本の場合は何でも時間をかけるというか、昔の寄合の意思決定のように三日三晩酒を飲んで騒いで後は長老に任せますみたいなリズムの違いがあるように思います。都市計画家の蓑原敬さんが仰るには、「あと10年」と言うと物事はなかなか動きませんが、「あと1000日」と言うと大体動くそうです(笑)。
これからの建築家の役割
馬場 これまでの話から、「計画」という行為のあり方が少しずつ変わってきているような感じがしますね。これからの計画というのは、ハード的な計画というよりも、「新しい枠組みをどうデザインするか」という方向へシフトしつつある。その枠組みは事業者が自由度をもって入れる枠組みであり、そのような枠組みの集積でこれからの都市は成立していくように思います。ですが、その枠組みのデザインに建築家が長らく参画していない状況にある。藤村さんは、その枠組みのデザインに僕ら建築家がきちんと参加していかなければならないというスタンスなんですね。
藤村 そうですね。かつては建築家が国の枠組みをデザインする時代がありました。60年代までの丹下健三と日本の政策は一致していましたが、70年代からはどんどん離れていきました。丹下は、工業地帯を集中配置することで投資が集中し経済発展が起こるということを主張していました。それに対して、自民党は農村の支持を得るために全国に工業都市をばらまきたい。すると、丹下の主張は論理的には正しいけれども政治的には正しくないということになり、そこでずれが生じてしまった。それ以降の丹下は国の行政からも遠ざけられ、建築家と政策との関係は、それ以降50年ほど切れてしまったわけです。
ですが現在、再びアカデミズムが役割を取り戻しつつある状況にあります。コミュニティと行政の間に入ったり、企業と地元の間に入ったりといろいろなケースがありますが、第三極としての大学や建築家協会、建築士会のような専門家の職能集団が果たす役割は大きいはずです。
馬場 建築家が中間的役割を果たすべきだというのが、藤村さんの大きなメッセージだということですね。でも、それは結構煩雑な作業ですよね。空間をつくるという職業的なゴールに辿り着くまでに膨大な労力がかかり、それに対する報酬も担保されにくい。ただ、コミュニティデザインといったやり方では社会に対してゴールを見せるという点で弱いと感じるところがあります。それに対して、最終的に物をつくるという僕ら建築家の職能であれば、そこをクリアしやすい。
藤村 こういう作業は時間がかかるものですが、いったん動きだすと一斉に動きだすという感覚があります。公共施設の再配置に関しては、2020年頃から全国的に一気に動き始めると思います。その時に建築家がきちんとノウハウを持っていなければ乗り遅れてしまいます。逆に、ノウハウを持っていればリードできるわけです。
私は鶴ヶ島プロジェクトを2011年、35歳の時に始めましたが、10年間くらいは大宮や川越市等でケーススタディをして、その後はいろいろな地域でそのノウハウを活かすようなフェーズに入っていきたいと思っています。
今後、行政も変わらないと生き残れませんから、民間のセンスで建築をつくったり、発注の条件を変えたり、いろいろな方法が試行錯誤されています。こういう状況下では大学や専門家集団が力を発揮します。建築家は大学で教えるようになると設計ができなくなってパワーダウンすると言われますが、むしろ大学でやることはたくさんあると感じています。「パブリックを考える」こともその一つですし、建築家にとって大きな可能性が広がっている時代なのではないでしょうか。
2015. 4. 21 『PUBLIC DESIGN 新しい公共空間のつくりかた』出版記念トーク、東京・co-lab西麻布にて
馬場正尊
Open A 代表/東京 R 不動産ディレクター/東北芸術工科大学准教授。 1968 年佐賀生まれ。早稲田大学大学院建築学科修了後、博報堂入社。早稲田大学大学院博士課程へ復学、雑誌『 A 』編集長を務める。 2003 年建築設計事務所 Open A を設立し、建築設計、都市計画まで幅広く手がけ、ウェブサイト「東京 R 不動産」「公共 R 不動産」を共同運営する。建築の近作に「佐賀市柳町歴史地区再生プロジェクト」「道頓堀角座」「雨読庵」「観月橋団地再生計画」など。近著に『PUBLIC DESIGN 新しい公共空間のつくりかた』『RePUBLIC 公共空間のリノベーション』など。
藤村龍至
藤村龍至建築設計事務所代表/東洋大学理工学部建築学科専任講師。 1976年東京生まれ。東京工業大学大学院博士課程単位取得退学。2005年より藤村龍至建築設計事務所主宰。2007年よりフリーペーパー『ROUNDABOUT JOURNAL』発行。建築設計やその教育、批評に加え、公共施設の老朽化と財政問題を背景とした住民参加型のシティマネジメント等に取り組む。建築の近作に「鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設」「APARTMENT N」「家の家」「小屋の家」「倉庫の家」など。近著に『批判的工学主義の建築 ソーシャル・アーキテクチャをめざして』『プロトタイピング 模型とつぶやき』など。
※登場する人物・名称等の情報はイベント当時のものです。