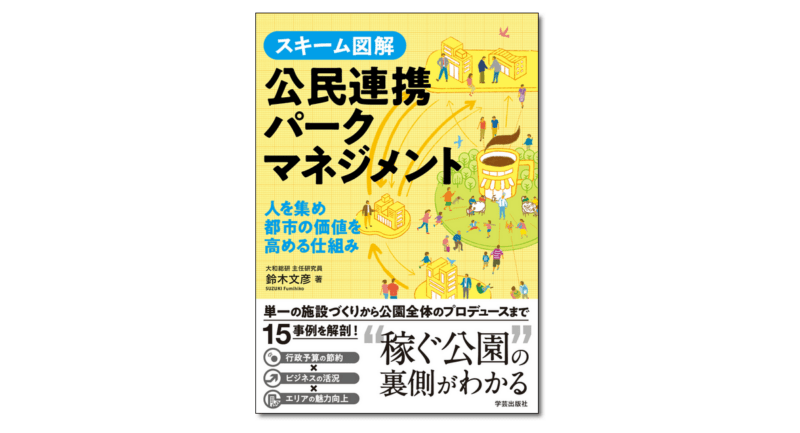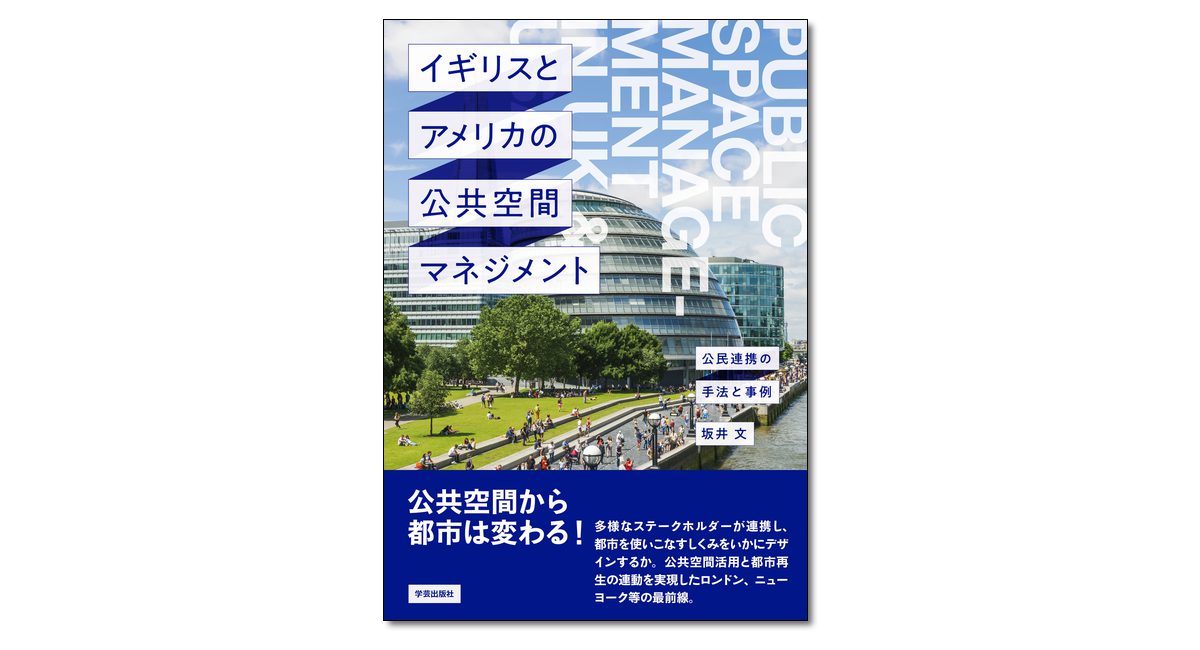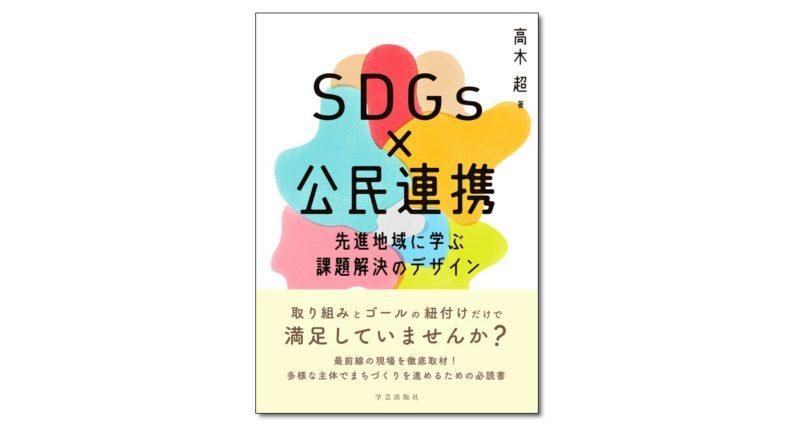【受付終了】公民連携手法による公的不動産の利活用と公的サービス創造
| 主催 | 比較住宅都市研究会 |
|---|---|
| ※詳細は主催団体等にお問い合わせください。 | |
- 日時:2025年9月19日(金)18:30〜20:30
- 会場:東京都立大学同窓会 八雲クラブ ニュー渋谷コーポラス10階 1001号室 渋谷区宇田川町12-3
- 参加費:1000円(学生は500円)
ネット参加600円(学生は無料) - 詳細・申込:http://home.g08.itscom.net/ebizuka/
内容
報告者:
矢部 智仁氏(合同会社RRP/RRP LLC代表)
要旨:
総務省の要請により各自治体が策定した「公共施設等総合管理計画」は、その策定要請から11年目となります。そもそも公共施設等総合管理計画は、社会構造の変化に伴って各自治体の財政制約に対応するための費用抑制や総量抑制を意図した計画です。しかしながら現実には大幅な施設面積の削減や抑制が実現できているとは言えない状況であり、例えば公共施設統廃合の結果、保有施設の総面積が増加する状況すら散見されます。
国内には建築物やインフラに加え公有地をはじめとする公共部門が保有する「不動産」が多く存在します。例えば土地については所有主体別の面積割合(令和3年度土地所有・利用概況調査報告書(国土交通省))は全国ベースで28.3%と約3割に上り、建物についても非住宅建築物の床面積の総床面積に対する公共の保有割合は約3割と考えらます(建築物ストック統計(国土交通省、推計値を含む)。このように公的不動産の総量が日本のストックに占める割合は決して小さくはなく、いわば公共部門は地域の大地主とも言えるわけです。大地主である以上、保有する資産の利活用とその効果が地域社会に与える影響が小さくないことを自覚すべきであり、同時に不動産を「資産」として捉え、公的不動産の利活用に関するマネジメントという視点に立った公共部門の取り組みが求められるはずだと考えます。
公共施設等の維持管理に関わる行政負担は、扶助費負担・公債費負担・人件費という義務的経費に新たに加わる「第四の義務的経費」と一部では言われ始めています。いずれにしても今後の自治体の行政サービス提供に必要な経常的費用使途の裁量にマイナスの影響を与える分野になる可能性があります。
将来のより良い行政サービスの実現のためにも、すでに余剰となっている、あるいは余剰になることが予測される遊休公的不動産の利活用検討の際に、地域の将来像を描き将来像を実現させる政策を進める手段として公的セクターには民間的な「資産を使った経営」を理解する進化が求められる、同時に民間セクターにも地域課題の解決というパブリックマインドを自らの内に醸成することが求められると考えています。遊休公的不動産の活かし方を官民が連携して考えることの是非や有用性についてご参加の皆様と意見交換をしたいと考えます。
講師のプロフィール:
大学卒業後、株式会社リクルート(住宅情報部門)において広告企画営業に従事。大手不動産会社、建設会社の販促支援に携わったのち、リクルート住宅総研 所長として建設・不動産業界の動向調査や業界団体・行政機関へのロビー活動に従事、国土交通省をはじめ行政設置委員会の委員等も歴任。
リクルート在職時の2013年、公民連携 (PPP)によって地域課題を解決するという未来志向の考え方に出会い、PPP型事業は建設・不動産業が地域に貢献し、期待される産業であり続けるために力を発揮する場面であると考え、東洋大学大学院 公民連携専攻でPPPに関する専門的な学びを得ました。
社会人大学院修了後、経営コンサルタント会社を経て2021年から現職。習得した知見を活かして建設・不動産事業者のPPP事業の導入支援や事業への協働、行政機関等主催の公民連携施策関連の委員会参加や事業検討支援などでの協働や啓発活動に取り組んでいる。
東洋大学 大学院 公民連携専攻 客員教授(PPPビジネス担当)、横浜市立大学 都市社会文化研究科 非常勤講師(都市ビジネス論担当)、公益社団法人 日本不動産学会理事、国土交通省 PPPサポーターなど産官学をつなげるポジションで活動中。