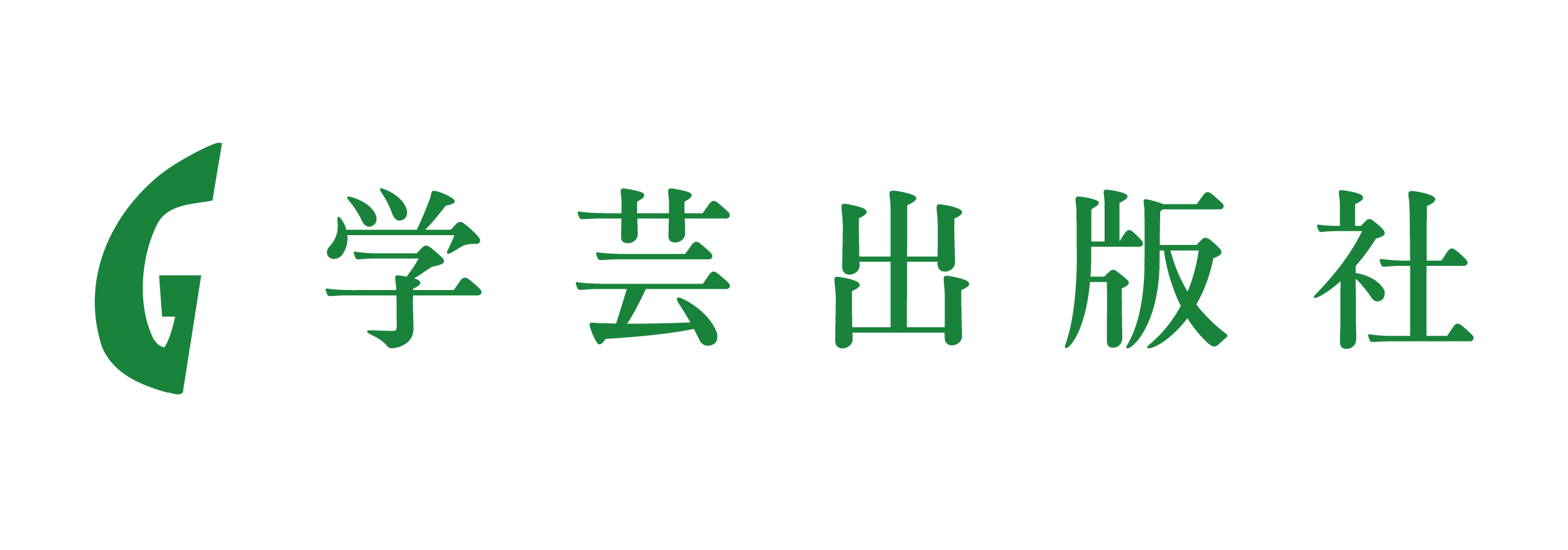[ブックレビュー]プロフェッサー・アーキテクトのポテンシャル 大学 研究室のオフィス化にいかに抗うか|藤村龍至
こども関連施設の研究者である仲綾子氏が早稲田大学・古谷研究室に潜入し、主宰する建築家・古谷誠章が研究室での活動を糧にして建築家としての活動をパワーアップさせてきた具体策を解き明かす。大人数の研究室のマネジメントは大変そうだけれどとても楽しそうというのが第一印象。
そもそも大学の研究室を組織とみて研究対象とする、あるいは大学教員が研究室をマネジメントするイメージが湧かないという人もいるかもしれない。「自分の頃は酒ばかり飲んでいた」「先生は研究室にほとんどいなかった」「学生は社会の制約から離れてのびのびと自らのテーマを探求するべきだ」などの声が聞こえてきそうである。
産学の接点としての大学研究室像は、この20年ほど繰り広げられた教育と労働をめぐる議論のなかで大きく変化した。大学で実施プロジェクトを進めるのであれば、役割や対価などについて事前に明示し、労働者性の高いと考えられる作業には対価を払う姿勢が求められるようになり、さらには退構時間の厳守や飲酒の禁止など、より厳格な管理を課す大学も増えた。大学研究室は教育の場としてよりは労働の場として見做されるようになり、オフィス化が進んでいるのである。
そのようになると、建築家にとっては大学研究室は創作の拠点として決して有利な場所であるとは言えなくなる。プロフェッショナルとしての訓練期間が短く、知識も足りず、労働者としては未熟な集団を大量に抱え、社会で競争に勝っていかなければならないからである。
それを乗り切る策のひとつが「ポジティブ・フィードバック」であると本書では切り取っている。古谷研では「怪しい不動産屋の話」以外は、持ち込まれた話は全て研究室活動に取り込むという。そこから廃校再生の「月影プロジェクト」が生まれ、その知見は建築家の古谷が公共施設として設計する「鋸南町道の駅プロジェクト」に応用される。
他方、次々とプロジェクトが持ち込まれ、メンバーの満足度が高められるように組織を運営していくと、方向性が散逸し、輪郭の見えない組織になってしまう可能性もある。ポジティブ・フィードバックとボトムアップが古谷研究室の活動の型であるとすると、創作論的な一貫性はどこから生まれてくるのだろうか。
ひとつの工夫は古谷が苦心しているという異学年交流の導入であろう。演習課題はもちろん、卒論、修論という共通の作法の中で自らの関心や発見を体系化していく体験では、経験で長じる先輩が後輩を指導する際に「縦の関係」が発揮され、強化される。
本書では助手という中間管理職の存在にも着目する。助手の宮嶋が、プロポーザルの締め切り前に変更を提案した古谷に「いまさら?」と語気を強める場面が描かれる。宮嶋のSNSでの呟きが流れてくると時々心配になるが、実際にリアル空間でお会いすると古谷との絶大な信頼関係を感じる。宮嶋をある部分で擁護し、ある部分で解放させることで「下から上へ」の動きをつくるのもまた古谷の力量のうちなのであろう。
仲氏は環境デザイン研究所の出身であるということで東京工業大学のプロフェッサー・アーキテクトであった仙田満との比較も期待してしまう。仙田はデビューしたての頃、商業施設のメイン施設の設計を年長者が務め、若手であった自分には外構の設計依頼が多かったことをきっかけに子どもの遊び場研究を始め、その過程で「遊環構造」を導き、その知見を「Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島」などの設計に反映し集客に成功する、というようにポジティブ・フィードバックを旨としたプロフェッサー・アーキテクトであった。結果として日本建築学会の学会長を経験するところも古谷と共通点がある。
このように本書は大学研究室を組織として対象化し、産学連携が強く言われると同時にオフィス化が進行する昨今にあってキーパーソンとなる「プロフェッサー・アーキテクト」の役割を描き直す。プロフェッサーの作法を無批判にトレースするだけでもなく、ボトムアップと称して学生の想像力の内側で停滞するでもなく、大学という柔らかな実験の場の可能性を理解するためにも、広く読まれたい一冊である。
藤村龍至