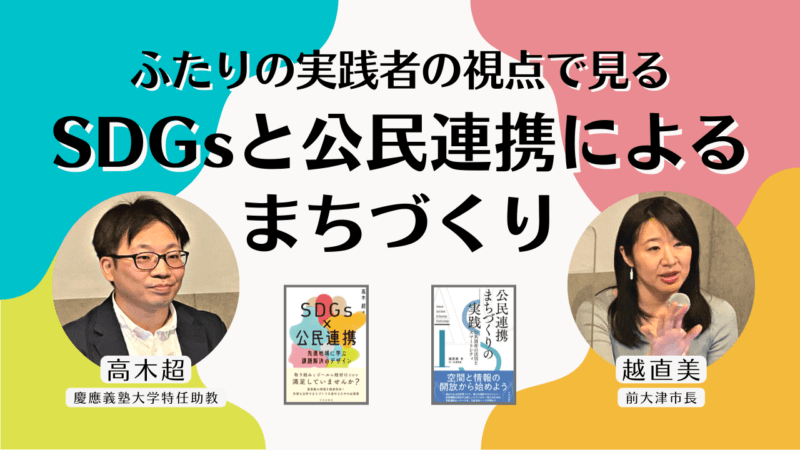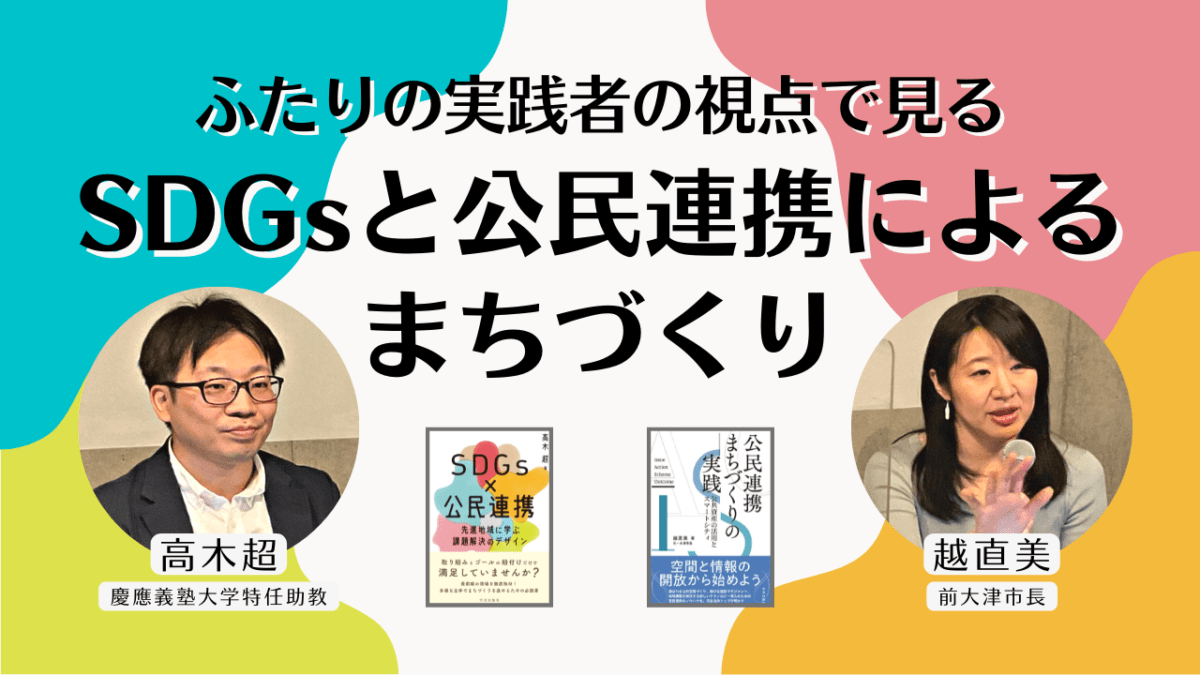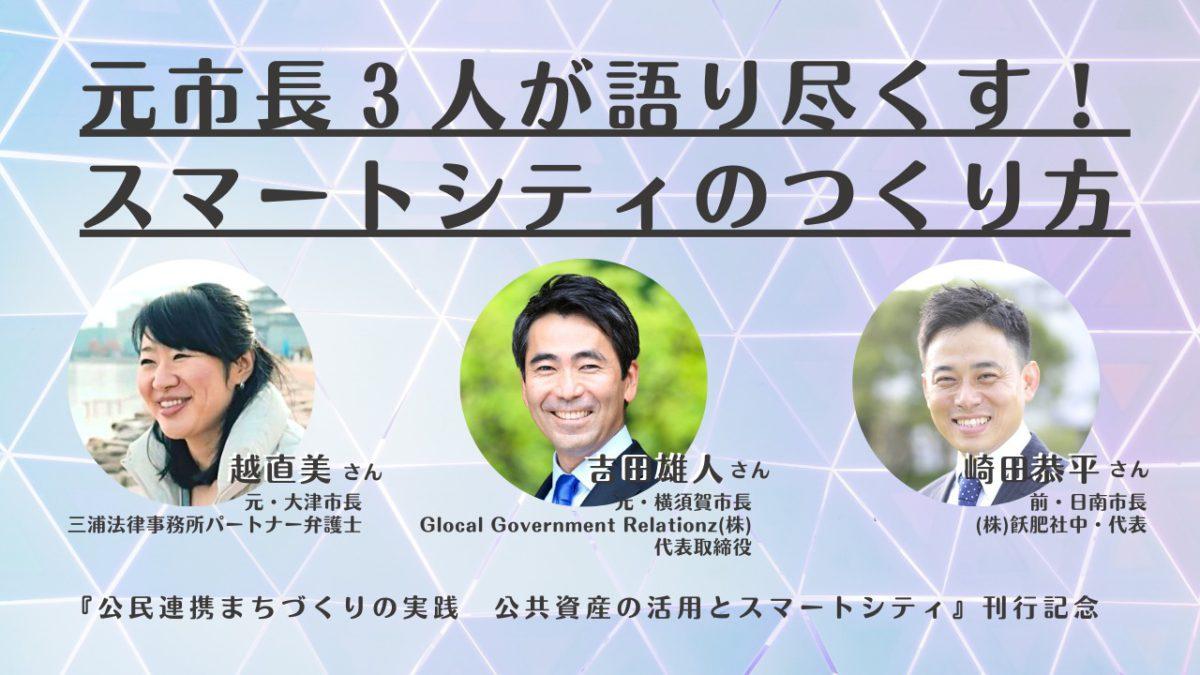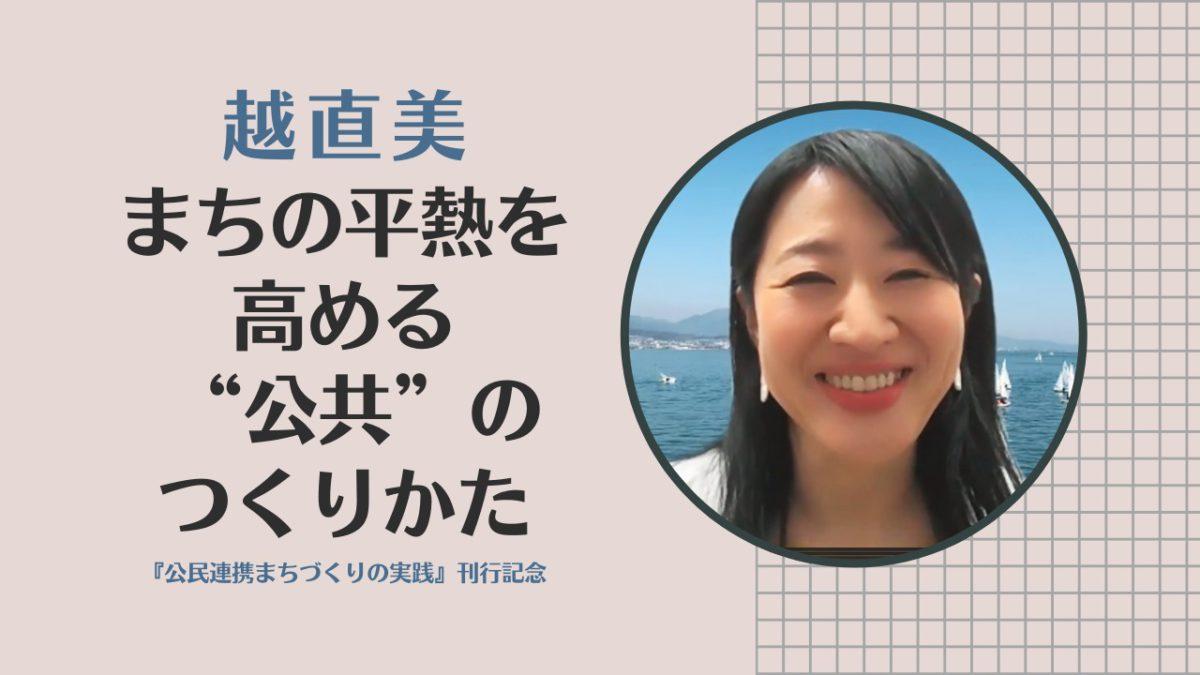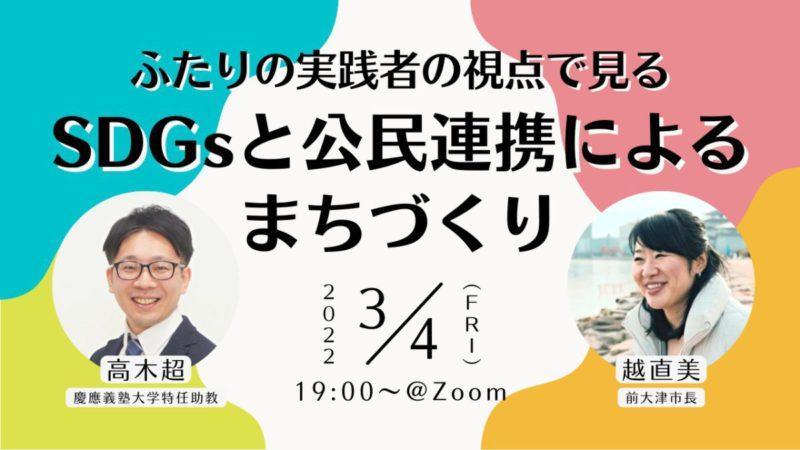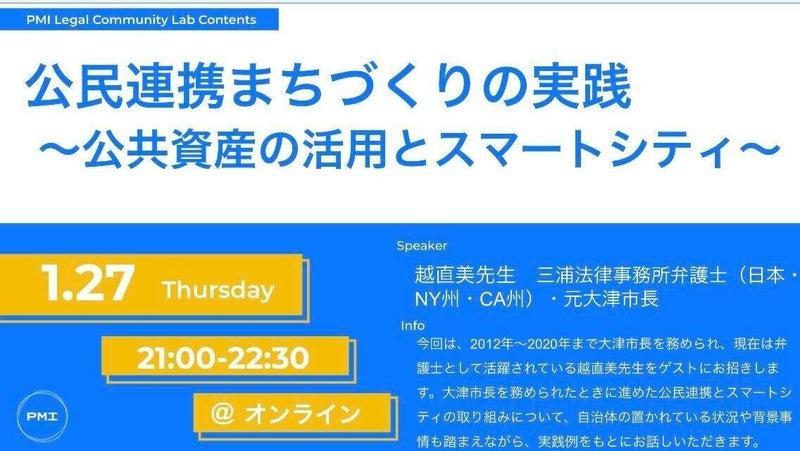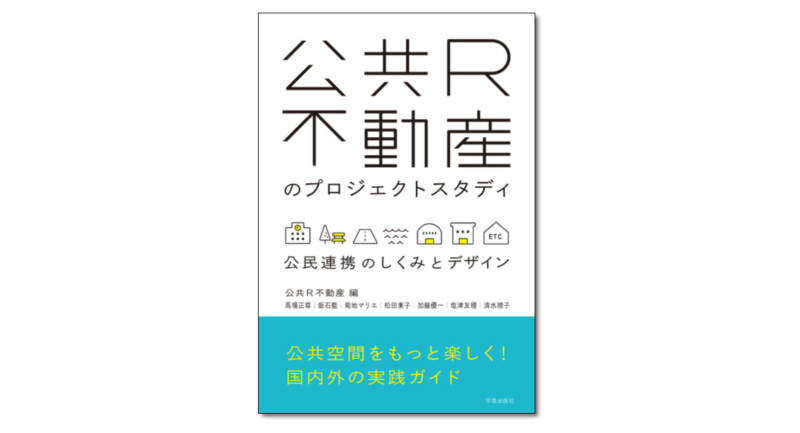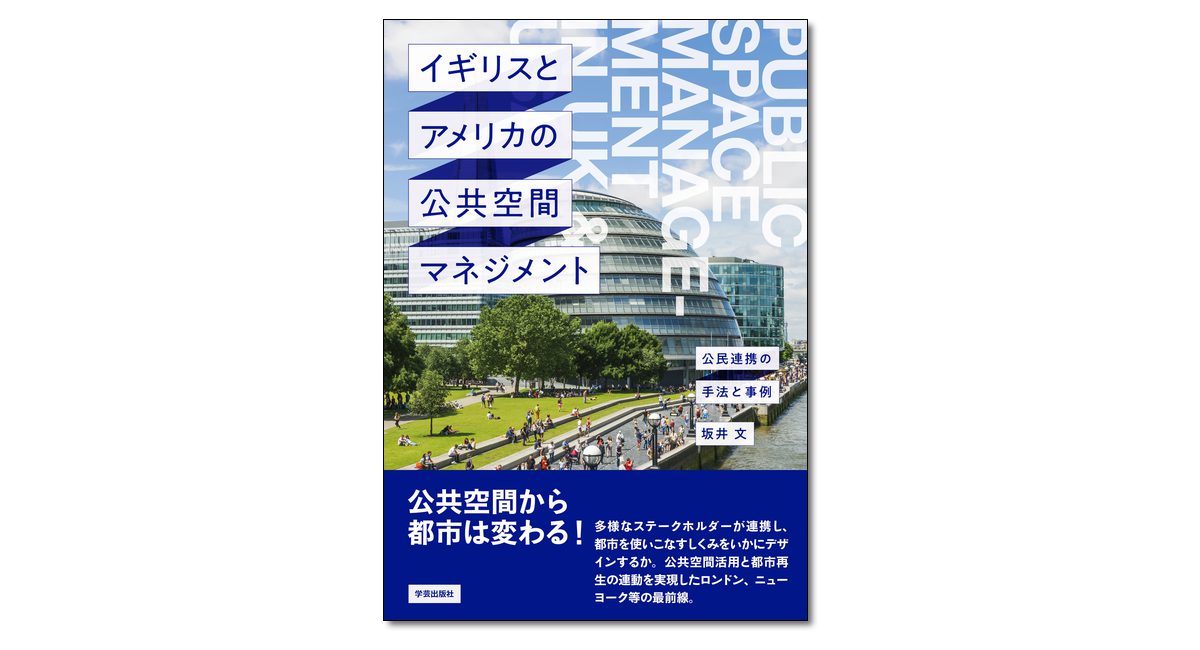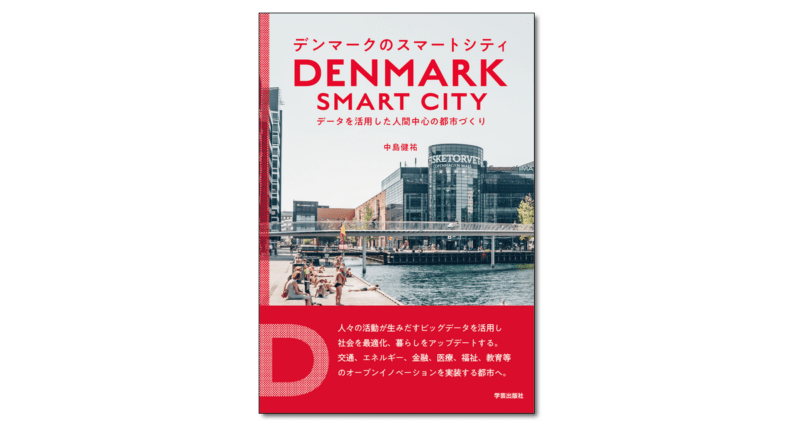公民連携まちづくりの実践 公共資産の活用とスマートシティ

実務的ノウハウを元自治体トップが徹底解説
自治体が公民連携に取り組む際の実務的なノウハウを元・大津市長が徹底解説。選ばれる公共空間づくり、稼げる施設マネジメントへの転換、テクノロジー導入による課題解決などを目指した事業のプロセスを、当初課題の実態(Issue)/採られた対応策(Action)/事業者との連携の仕組み(Scheme)/得られた成果(Outcome)に分けて紐解いた。
越直美 著
| 体裁 | A5判・200頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2400円+税 |
| 発行日 | 2021-09-25 |
| 装丁 | 中川未子(紙とえんぴつ舎) |
| ISBN | 9784761527891 |
| GCODE | 5616 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| 関連コンテンツ | 試し読みあり レクチャー動画あり(全3件) |
| ジャンル |
ログイン
新規登録
開催が決まり次第、お知らせします。
終了済みのイベント
Introduction:今求められる公民連携とは
Case 1:ランドマークを役割分担で再生する
――JR大津駅ビルのリノベーション
- [Issue]駅ビル新築構想と交通結節点ではない立地のギャップ
- [Action]駅ビルの運営管理からの撤退
- [Scheme]民間によるテナント誘致と改修費の一部負担
- [Outcome]既存建物を活かしたリノベーション誘致と若年層の利用者の増加
Case 2:負の公共資産を賑わいの場に変える
――大津びわこ競輪場跡地の利活用
- [Issue]公有地の活用を阻む莫大な施設解体費
- [Action]市・市民・事業者の「三方よし」の利活用方針
- [Scheme]定期借地による民間事業者主導の施設・広場整備
- [Outcome]公園と一体化した複合商業施設の開業
Case 3:インフラのあり方を合理化する
――公営ガス事業のコンセッション
- [Issue]インフラの持続可能性とガスの自由化による厳しい競争環境
- [Action]コンセッション方式の民営化
- [Scheme]料金上限維持等を含む運営権契約
- [Outcome]持続的なインフラ維持と市民サービスの向上
Case 4:ニーズを汲み取った規制緩和を実行する
――琵琶湖沿いの企業保養所の転用促進
- [Issue]空き保養所の増加と市街化調整区域という制約
- [Action]規制緩和のためのニーズ調査
- [Scheme]開発許可制度の弾力的な運用
- [Outcome]観光振興に役立つ宿泊・飲食施設の誘致
Case 5:遊休不動産の活用を促す
――大津宿場町構想
- [Issue]中心市街地の空洞化と伝統的な街並みの悪化への懸念
- [Action]町家ホテルの開業を契機にした宿場町構想の立ち上げ
- [Scheme]都市再生課のまちなか移転とリノベーションスクール
- [Outcome]若者による町家活用の広がり
Case 6:スマートシティをつくる
――自動運転・MaaS・デマンド型乗合タクシー・カーシェアリング
- [Issue]高齢化による公共交通の危機
- [Action]新しいモビリティの導入に向けた実証実験の展開
- [Scheme]新技術を実用化するための連携・検証体制
- [Outcome]「住民の足」の確保に向けた試行錯誤と課題
Case 7:行政DXを推進する
――AIいじめ深刻化予測を中心に
- [Issue]行政課題解決のためのエビデンスの必要性
- [Action]AIによる分析の開始
- [Scheme]AI分析のプロセスと結果
- [Outcome]AI分析結果のさらなる活用と他分野への応用の可能性
はじめに―本書の構成
私は、2012年から2期8年、大津市長をつとめた。本書は、その間に、職員とともに進めた公民連携とスマートシティの実践例である。
厳しい財政状況を出発点として始めた公民連携の取り組みであったが、その結果生まれたのは、単なる経費削減ではなく、市民が楽しめる空間だった。本書で述べるいずれの事例も、Issue では取り組みの背景となる問題、Action では問題解決のために大津市が起こした行動、Scheme では具体的な手法や手順、Outcome では取り組みの成果という内容に沿うように記載している。
公民連携を進めるためには、自治体と民間事業者の役割を整理して再構築するとともに、事前の調査やスキームの組み方に工夫が必要である。本書では、スキームを組む際の実務上のコツを紹介した。
また、現在、私は弁護士として民間事業者へのアドバイスを行っているが、民間事業者からは自治体の仕組みが見えにくいことも多い。そこで、自治体の置かれている状況や背景事情についても言及した。
全国で公民連携やスマートシティを進める自治体の方、そして民間事業者の方に、お手に取っていただければ幸いである。
2021年8月吉日
越直美
おわりに
本書を読んでくださった皆様、誠にありがとうございました。
私は、2012 年、当時全国最年少の女性市長として大津市長に就任し、子育て支援、行財政改革およびいじめ対策に取り組んできました。厳しい財政状況の下、まちづくりについては何をするにしても「お金がない」というところから出発せざるを得ず、職員と悪戦苦闘しながら辿りついたのが、公民連携という道でした。
そして、公民連携の結果できあがった大津駅ビルやブランチ大津京を見て、公民連携の真の価値に気付きました。それは、市民の笑顔でした。公民連携は、単なる経費削減ではなく、市民が楽しいワクワクする空間をつくるためのものだったのです。私自身、何かを言葉で説明しなくても、その空間に来るだけで市民に変化を感じてもらえることの素晴らしさに気付きました。その感動は、私をまちづくりの面白さの虜にしました。
私がスマートシティに取り組み始めたのは、2 期目になってからです。地域での様々な困りごとをテクノロジーで解決できないかと思ったのです。
市民生活を便利にしたい、もっと効率的な行政にしたいという思いが、スマートシティを進める原動力となりました。
私は、まちづくりについては素人でしたが、だからこそ、市民感覚で市民が喜んでくれる空間をつくりたいと思って取り組んできました。テクノロジーについても素人でしたが、自動運転バスに乗るときは、いつもワクワクしました。そこには、未来への期待がありました。まちが変わったときの市民の笑顔と感動を、忘れることができません。
私は、当時、まちの将来像として、「琵琶湖の上に浮かびながら仕事をする」という絵を自分で書いていました。それは、人が働く場所にとらわれず、自分の好きな場所で時間を過ごすという理想を示したものでした。新型コロナウィルス感染症の流行でリモートワークが進み、思っていたよりも早くそのような日が近づいてきました。
私は市長としてやり残したことはないと思っているのですが、公民連携とスマートシティについては、これからも弁護士として、関わっていきます。本書で述べた様々なスキームを組む際にも、M&A 弁護士としての知識と経験が助けてくれました。これからは、民間事業者と自治体を結びつける接着剤のような存在として、全国の公民連携とスマートシティの取り組みを応援していきたいです。特に、自治体を知る者として、困っている民間事業者やスタートアップの力になれればと思っています。
本書で述べたそれぞれの取り組みを進めるにあたり、そして、本書を執筆するにあたり、お世話になった全ての皆様に心から御礼申し上げます。
いずれの取り組みが進んだのも、大津市職員の皆様のおかげです。新しい挑戦には苦労がつきものですが、それを乗り越え、新しい取り組みを実現してくださった皆様に心から感謝申し上げます。
様々な取り組みに参加し支えてくださった全ての市民の皆様、本当にありがとうございました。皆様の日々の活動に重ねて御礼申し上げます。また、二元代表制という制度の下、まちづくりについて議論し、ともに大津市をよくしようと歩んでくださった市議会の皆様に、厚く御礼申し上げます。
そして、大津市の夢をともに実現してくださった民間事業者の皆様、誠にありがとうございました。公民連携やスマートシティの素晴らしさを教えていただきました。
さらに、お世話になった大学の先生や専門家の皆様、そして、国土交通省、経済産業省、警察庁、滋賀県や滋賀県警をはじめとする関係機関の皆様に、御礼申し上げます。皆様のお力がなければ、取り組みを進めることはできませんでした。全ての関係者の方々に心から感謝申し上げます。
最後に、本書を執筆するにあたりお世話になりました松本優真様をはじめとする学芸出版社の皆様、三浦法律事務所の皆様、ご協力いただいた全ての皆様、本当にありがとうございました。
多くの方々のお力でできあがった本書が、全国の自治体で公民連携やスマートシティが進む一助となれば幸いです。
2021年8月吉日
越直美
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。