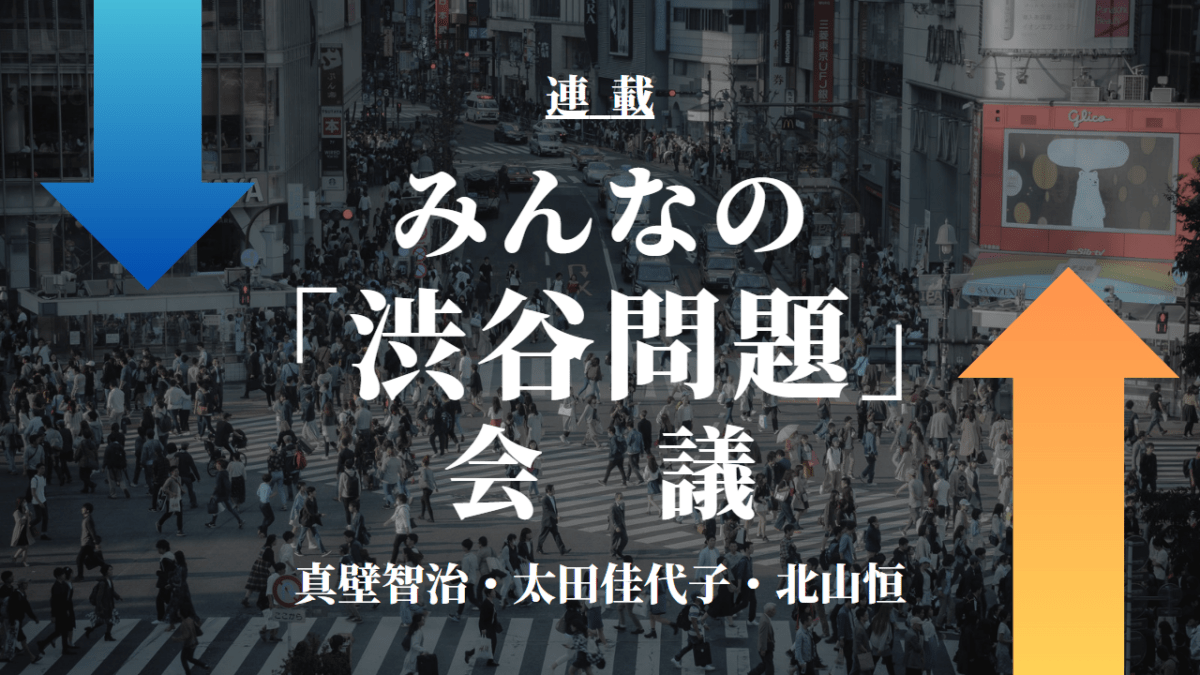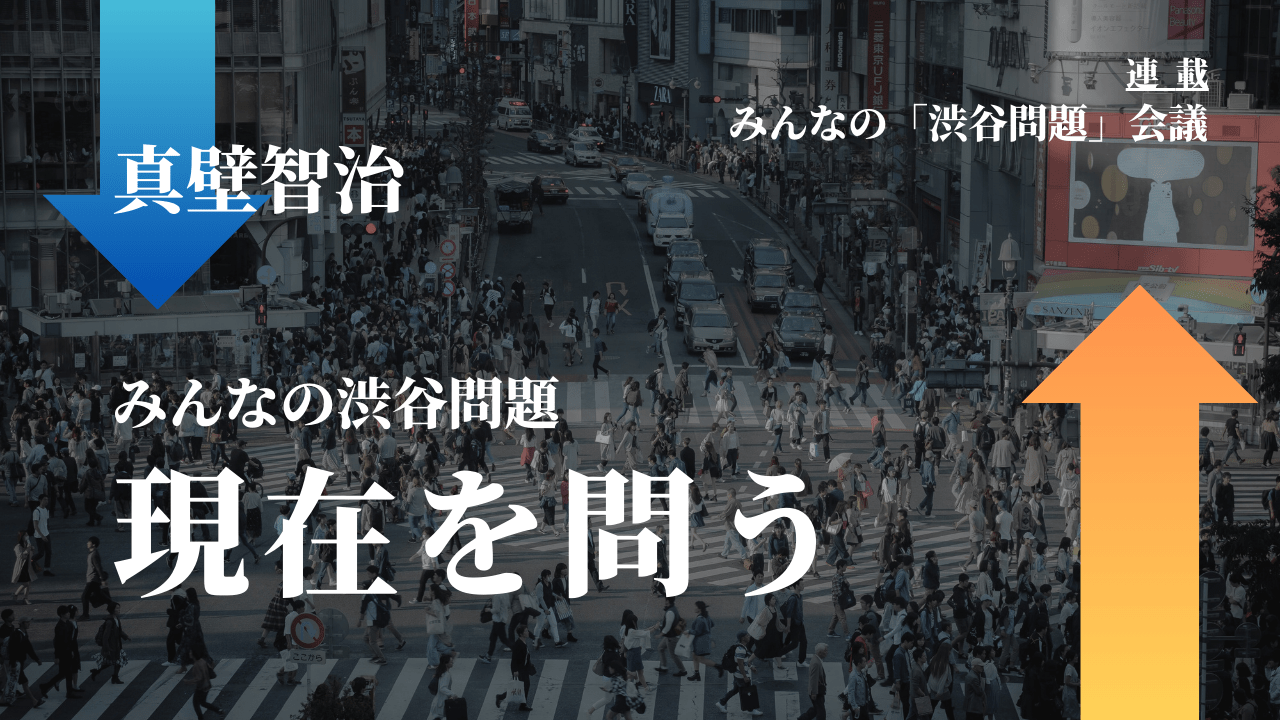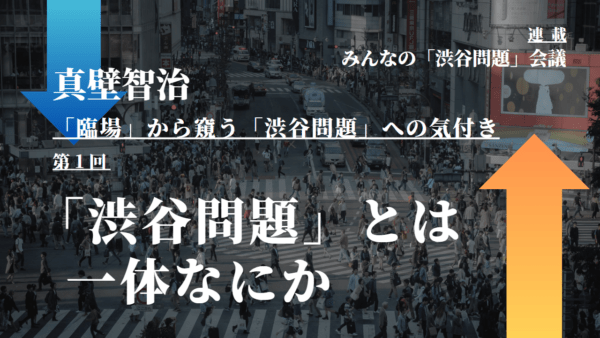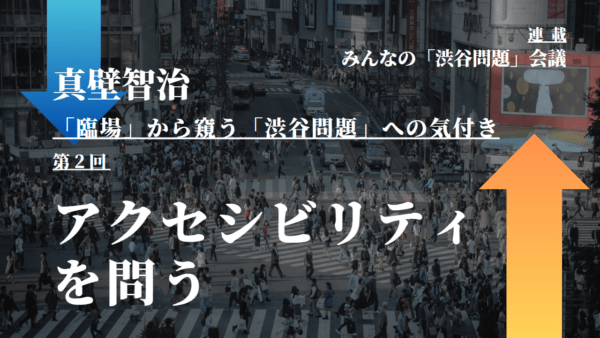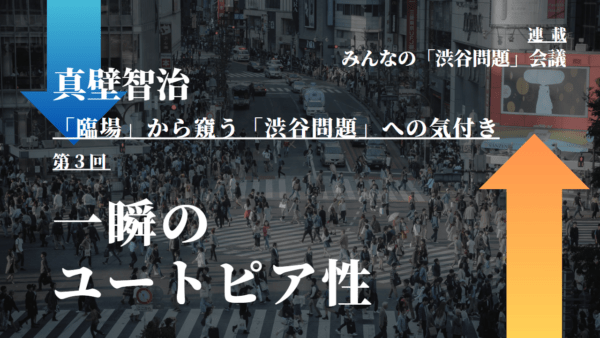みんなの渋谷問題 現在を問う|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。
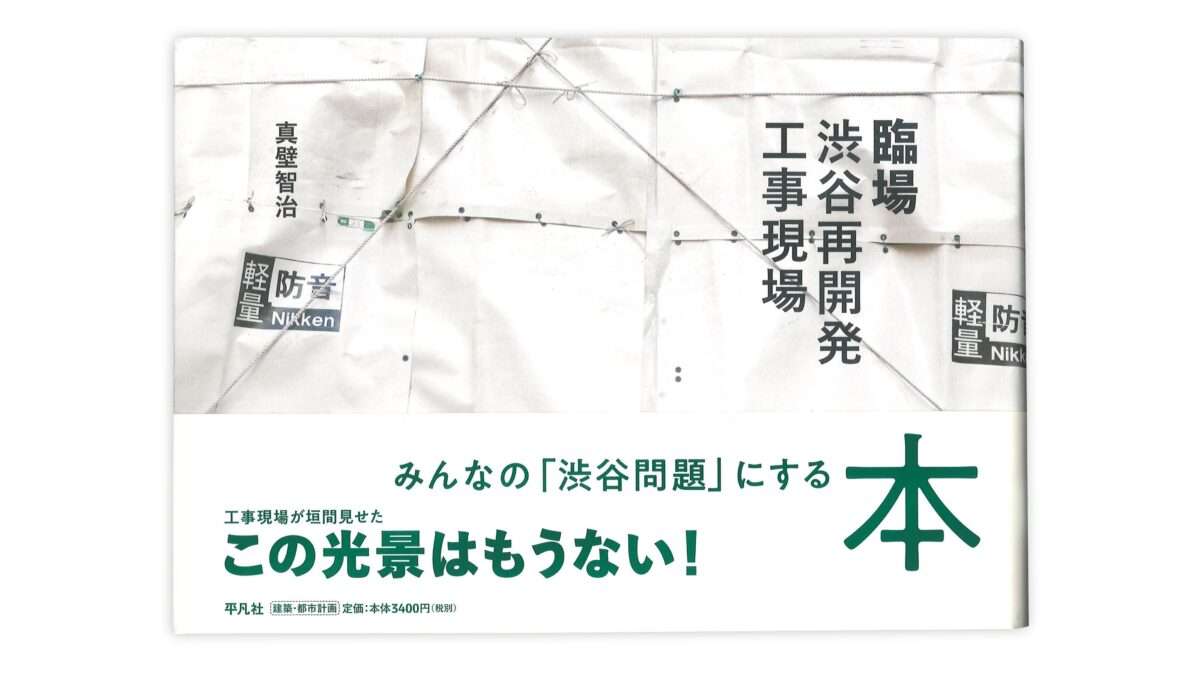
≪横にスクロールしてお読みください≫
軋む都市の亡霊(ビッグネス)と
野生(カオス)の相克 1
現在(二〇二五年初頭)の渋谷再開発の様態は
「ジェネリックな光景に渋谷が沈んでいる」
「ビッグネス群を前に渋谷が縮んでいる」と、映る。渋谷がどんな方向に進むのだろうか。
渋谷が沈み、縮むのはビッグネスが生む均質なメガスケールの他に、ビッグネスが生み出す実体感のない野心に満ちた不明なコードを備える亡霊の様な存在も大きい。それらはもう建築のコントロールの域を越えている。そんな特性を持つ民間(ディベロッパー)主導型渋谷再開発を正面から広く、議論し合うことが端からとても危うく、曖昧だと感じてきた。一方でオープンスペースも公開空地も全く寛容さを欠く。どうしてなのだろう。これまでの官主導型再開発とはどこか違う。
議論する主題に当事者意識が持てずに踏み込めないのか、あるいは議論の対象が私たちの手の届かないものだからであろうか。このジレンマはディベロッパーが主導する都市再開発が増えるにつれ、大きくなっている。
いずれにしても議論の取っ掛かりが見えづらく、大上段な議論は挑めそうにない。
逆に言えば、民間主導型渋谷再開発はどこから議論を始めてもよいのである。だとしたら私たちの日常生活批判として主張すべき共通利益から渋谷に向き合うのが議論の起点になるべきではないか。公共性の議論も私たちの使い勝手からの日常生活批判レベルから始めることになる。
民間主導型都市再開発に私たちの日常性から対峙するとはどの様なことになるのか。
私たちの日常としてこれまで育まれてきた当該地への記憶や想いや振る舞いから今の渋谷に向き合う、そこに明らかな断絶が浮かび上がる。この断絶をしっかり見つめる所から日常生活批判を始め、断絶を前提に再開発が進む現実に向き合うことだ。
民間主導型都市再開発では計画が承認されれば、後は計画情報を開示する必要がない、とばかりに計画遂行の一方通行が常態化してきて、私たちとの断絶の溝は深まる。この民間主導型都市再開発の固有な体質自体を問題視することも私たちの日常生活批判からのラディカルな問いにもなろう。
都市再開発事業が公から民への移譲が活発になるにつれ、開発主体が示すこの事態が次第に露骨化し、都市生活者は常にカヤの外になる傾向を感じるのは私だけではないだろう。
開発計画からどんどん都市生活者が疎外されてゆく現状が在り、これも深刻な断絶となる。
多くの民間主導型都市再開発の場合、その開発事業としての収支性、収益性の構造が不透明なのは無論、開発計画をめぐる公(おおやけ)の説明の場や開かれた討議の場が設定されることは少なく、もし在ったとしてもそれは一般的なパブリシティやニュース・リリース程度の情報伝達に過ぎない。更に姑息なのは再開発地域近隣住民のみを対象とするディベロッパー主催の「説明会」である。ここでも多くの都市生活者はカヤの外に置かれ、断絶感を味わう。この様に民間主導型都市再開発では説明を受けるにも「関係者」と「部外者」と言う線引きが露骨に行われ、再開発にとってのこっち側とあっち側の意識付けが進み、そこに分断化が図られる。そこには当事者意識が広く育つ土壌が元々存在しないのである。これこそが大問題ではないか。
多様性が求められ、尊重される時代に在って、ディベロッパーによる都市再開発の進め方については自由経済原理と市場第一主義の実践とはいえ、絶えず広く、多くの議論に晒す、言わば開発計画検討や理解の為の開かれた養生期間が必要なのではないだろうか。つまりは、ここには市民の知る権利と開発主体の伝える義務が共に不在だからこその一策なのだ。
また、ディベロッパーによる都市再開発の情報発信の在り方での偏りも顕著に見られるように思う。まずは開発計画は世界に向けて投資、出資者へ第一義に開示される。
そこでの開発計画情報は「建築」ではなく「物件」に終始する。都市再開発が一旦「物件」としての必要情報に翻訳され、それが世界に向けて発信される。今日、ディベロッパーによる都市再開発が露わにしている事態は建築と都市をすべからく「物件」に変換させていることではないか。本来的に建築や都市は存在するだけでそこに公共性やアーバニズムが問われるものなのだが、そうしたことへの討議の為の情報化もなしに、世界に向けて「物件」が一人歩きをしている現況に在る。物件情報は絶えず差別性や新奇性を訴求するレベルを示し、都市が一体誰のものかは不明のままだ。
都市生活者に向けられる開発情報は「物件」の後回しになり、建築と都市についてのセグメントされた情報(都市生活者が消費者として把握された開発イメージ)でしかない。
民間主導型都市再開発事業ではグローバルエコノミーに向けての開発計画をアナウンスしても、多くの都市生活者に向けての情報発信・開示についてはあまりにも疎くなってはいないか、ここへも私たちの日常生活批判を向けてゆくべきだ。
都市再生特区の指定を得た民間主導型渋谷再開発の基本スタンスは開発可能容積率を全面化して描く収益開発事業に他ならない。
従って、再開発の前提フレームで計画全体が超高層(ビッグネス)群による開発事業スキームがその骨格となってもそれはディベロッパー発想としては否めず、この段階での計画検討でグローバルエコノミーを念頭に置く「世界のSHIBUYA」としての渋谷再開発像を描出することになるのであろう。
この時から渋谷再開発は増床化を図りたいディベロッパーによる「ビッグネス」との蜜月計画としてスタートし、この段階での計画と私たちの日常生活との乖離は決定的になる。
渋谷再開発を牽引してきたデザイン部会座長の内藤廣は民間主導が必然的に計画の基盤として誘導するビッグネス自体には全く興味を示さず、その低層部にこそ渋谷の質(渋谷らしさ)の創出を期待する、としていた。それは渋谷再開発に在ってはあれは建築ではないという諦念と共にビッグネスの足元(低層部)にしか可能性がないことを当初から示唆するものであった。
言うまでもなく「ビッグネス」はレム・コールハウスが『錯乱のニューヨーク』(一九九四年)に続く『S・M・L・XL+』(一九九五年)で指摘した通り、それはそれまでの「建築」という枠組みには到底収まらない新種の建築としたものだった。「ビッグネス」の定理の概要を示しておく。
ある臨界量を超えると、建物は「ビッグな建物」になる。そうした量塊(マッス)はもはやひとつの建築的身振りでコントロールできるものではなく、複数組み合わせても無理である。
そして、そこでは空間どうしを建築的にではなく機械的に繋ぐエレベーターと、そこに関連する一連の発明により、建築の古典的レパートリーは無効となる、としている。更に単に大きいというだけで、建物は善悪を超えた道徳と無関係の領域に入る。建物のインパクトはもう質と関係がない。こうしてスケール・建築構成・伝統・透明性・倫理性から一挙に離脱するということは究極の、根本的な訣別を意味する。ビッグネスはもう都市を織り成す構成要素ではない、という訣別だ。ビッグネスはアーバン・ファブリックの対象にはなり得ないのである。
内藤廣が期待したビッグネスの低層部への建築的対応策としてデザインアーキテクトが登用され、渋谷の質の創出がデザイン・ミッションになっていたが、現況の結果はどうであろうか。
結論から言うと、内藤のビッグネスへの興味のなさと諦念が、ビッグネスシンドロームに打ち勝つ対応としての構造的ロジックを不明にさせてしまっている。つまりはレム・コールハウスのビッグネスの定理を打ち砕く明解な反力的(カウンター)対抗策のイメージが見当たらないのだ。内藤の最大の見誤りは、ビッグネスの足元(低層部)も実は建築的コントロールの活かない素地を充分に持っていることへの認識不足であった。
その低層部に歩行インフラ都市装置となる「アーバンコア」や「スカイウェイ」を建築的身振りとして持ち込んだ程度ではビッグネスの呪縛から逃れ、渋谷の質を創出しているとはとても言えない。公共貢献とされる「アーバンコア」も垂直動線幇助が主機能で、アメニティを共通利益として実感して新たな公共性を感じるまでには至っていない。開発側からの公共貢献と都市生活者がそこに公共性を感じ取る、とは同一レベルでは全くないのである。その矛盾はディベロッパー主導都市再開発の至るところに散見されるものだ。
ビッグネスの低層部で唯一、建築的コントロール対応が試みられているのが「渋谷ストリーム」(デザインアーキテクト小嶋一浩、赤松佳代子)であろうか。
近隣地域と繋がる開放的な通り抜け通路や階段が小さな構造としてビッグネスの大きな構造の足元に差し込まれている。又、渋谷川沿いの散策路に面した路面店感覚の店舗構成にはビッグネス群の内で稀少な接地性を活かし、賑わいを発揮している場となっていて、小さな界隈を形成し得る余地を感じる。いずれもが都市生活者やインバウンドの多彩なアクティビティを誘導して、渋谷の新しいアーバニティスポットを予感させる。
またビッグネスの外装処理にデザインアーキテクトが問題意識を持ち、パターンの破調によるオプティカル効果を施す試みが見られる。レム・コールハウスが指摘したビッグネスに在っては内部と外部とは全く別物のプロジェクトでそこに一切の関係がないことを根拠に、外部に破調のパターン構成による「ノイズ」をビッグネスに与えていて、それは同時に外部が物体として安定していることを周囲に伝えるものとなっている。
軋む都市の亡霊(ビッグネス)と
野生(カオス)の相克 2
実は内藤がビッグネス低層部に渋谷の質を新たに植え付けようとするヒントは既に皮肉にも再開発工事現場の内に在ったのである。それが次に述べるカオスの世界観とその構造なのである。
片や、建設中のビッグネスの足元(低層部)ではどの様な事態が生起してきていたのか。
再開発工事の進行と共に、ビッグネス建設への既存建物の解体とその後の建設敷地への統合化の為の整地が進み、多くの小さな敷地が大きな敷地へと改編されてゆく事態を見せてきた。
特に桜丘口地区での再開発工事でこのスぺクタルが大展開される。ビッグネスが実感としてその巨大さの実体が感じられるのは低層部での更地の敷地規模や基礎工事、躯体の建てかた工事の場面までで、そこから上層への建設進展ではどんどん建築としての実在感が消失する。そして、マネーゲームそのものとしての「ビッグネス」が亡霊の如く空中を埋め尽くしてゆく。
ここに至るまでの事態は、ビッグネス建設に入る為の前段階としてその場所の記憶を消去させ、建設の為の大きな敷地に集約してゆく作業で、これはビッグネスのベースメントの漂白作業以外の何ものでもない。ビッグネスは土地の大規模な漂白を基に成り立つのである。
ベースメントの漂白化とはビッグネスという欲望の構造物を構築する為に、それまでその場所に備わっていたコンテキストを白紙化することを意味していて、そこの場所性と記憶性が一気に消滅する都市代謝を私たちは体験してきた。同時に、ビッグネスはその土地のコンテキストを映し出すことも一切しない。
そして、もう一つビッグネスの足元で生起してきた特筆すべき事態が挙げられる。
それはビッグネスの足元だからこそ展開される「解体」と「新設」の全く逆の生成ベクトルの工事進行現場が必然的に表わす新たな工事様態となるものだ。往来者の安全を第一に工事現場の養生も兼ねた仮設空間がスポンテイニアスにビッグネスの足元を埋め尽くす。
特に渋谷再開発工事の過半は都市生活者を工事現場に巻き込む劇場型工事となるものなので、そこに絶えず工事と生きる私たちの日常性が強要されてくる。つまりは工事を私たちの日常が身体化させている、と言うことが出来るだろう。
この再開発工事の身体化も新種の都市体験・建築空間体験となっているのではないか。
再開発建設工事を技術的に支えているものは「エンジニアリング」(培養された技術)と「ブリコラージュ」(野生の技術)の二つの技術世界である。
特にビッグネスの足元に自在に立ち現われる仮設空間はブリコラージュな技術秩序から生まれるものになる。
この様に、ビッグネスの足元には「解体」と「仮設」というこれまでの建築の概念や規範から全く遠方のものらがからまるように生息していた。それらはこれまでにも充分に建築的討議が成されることはなかったものだ。
言うまでもなく、「解体」と「仮設」は建設と常設に対しては不定形となるもので、それ自体は極めて脱構築な営為になり、そうした不定形を受容してゆく都市生活者の態度に内に「カオス」を体験することになるのである。
同時に私たちはビッグネスの足元にからまるカオスを介して都市と建築の野生を垣間見ることになる。脱構築な営為としてのブリコラージュな技術世界が都市の渦中に培養とは異なる野生を注入していたのであった。
亡霊のような不在のビッグネスに対して、足元=低層部に生起しているリアルな野生の表出は劇場型工事中の往来者には、フッと我に返ることが出来る生命感に包まれるものとなるものだった。
仮設はこれまでの用途と機能をアプリオリに整合させて成立してきた「完全な建築」を生む建築計画論では手に余る対象だった。
どこまでも不完全形であり、常にそれらは暫定的であり、その様相や様態は工事進行に対応して可変する自在形であり、その施工に関わる作業者のスキルに応じて按配される手仕事に依る一回きりの作品性も獲得している。
見方を変えれば、「ビッグネス」を建設させる為に「カオス」が一定期間に渡って、その足元(低層部)に生息していた、とも言えるのである。
つまりはビッグネスとカオスとの一時的な共存となり、それは同時に亡霊と野生との共演を表わすことにもなっていた。
これこそが渋谷再開発での特異性のコアとなるもので、ビッグネス建設が都市生活者に与える恐怖、不安などのストレス(ビッグネスシンドローム症候)が工事進行と共に増大してくるのを一定癒そうとするのが低層部でのカオスの世界となっていて、そこでは絶えずビッグネスとカオスとのアンビバレンツな相克運動として感じられてきた。
しかも、これまで示してきたようにカオスをもたらしていたビッグネスの足元に展開される解体と仮設の世界はブリコラージュな秩序を持ち、全くの脱構築となるもので、それらのカオスは絶えず現在進行形なダイナミズムを生む。渋谷の質を保証することとカオスの存在は無縁ではない。渋谷の質とは絶えず変転するダイナミズムと共に在るものなのであるから。
カオスには雑多な不完全さが備わるからこそ都市生活者は救済され、ビッグネスが肥大すれば、カオスの増大・拡張が都市の躍動のバランスとして必要なのだ。カオスはビッグネスに対する免疫力のようなものになる。
ビッグネスはレム・コールハウスが新種の建築空間と指摘したものだが、私は仮設空間もまたビッグネスと共に現われた新種の建築空間と規定しておきたい。仮設空間は渋谷再開発計画の内から生じてきた想定された存在ではなく、再開発工事の対応の中から必然化されてきただけの非計画的な脱構築空間だったのである。
それだけに仮設空間が生み出すカオスは結果的に都市生活者に感覚されるものになり、カオスは不定形で極めてアナーキーな躍動感を伴うものになる。
ここでカオスの特性を示しておこう。
・カオスは不定形化を受容する脱構築的な営為から誘導されるもの。
・プログラム(計画)の対象にはなりづらく、そこに旺盛な人間の振る舞いが関与することによって浮上するシナリオのない様相世界となる。
・カオスは一瞬の統合と分離との飽くなき不連続な連続性を体現する場所を生む。
・カオスはどこまでも完全になり切らない一回性を保持する現象である。
・カオスはオルタナティブな中心性を志向する。
・カオスは近代主義・モダニズムとは馴染みにくい辺境の美学。
・カオスは矛盾し合うもの、相対し合うものを包摂し受容する。
・カオスは理解されるものではなく、感覚され、共感されるものになる。
・カオスは大地を母とする場所の生命現象で、接地性を失うとカオスは消滅する。
・カオスは反権力・反権威の象徴となり、絶えず無場所性を発揮する。
・カオスはどこまでも人間が主役のリアルな世界で、都市に生命感をもたらす。
しかし、このカオスティックな建築空間はビッグネスの竣工と共に用無しになり、一斉にその姿を隠してしまった。解体や仮設がビッグネスの足元にからみつくように存在したカオス世界はビッグネスの竣工と共に潮が引くように消失し、もう渋谷にはビッグネスとカオスの緊張した相克の構図はない。そこにはビッグネスの大味で圧倒的な物量感に支配されるジェネリックな渋谷の姿が映し出され、渋谷らしさが全く影を潜めている。
現況の渋谷再開発での最大の問題点(読み間違い)はビッグネスの躯体構造のスケール、スパンピッチがそのまま低層部を支配し、包み込んでいる躯体制約から逃れられずにいることだ。
内藤は当初からビッグネスの低層部にしか興味がなく、渋谷の質を保証する可能性は低層部にしかないと断言したが、構造的にビッグネスの高層部と低層部との躯体構造が切り替わるわけではない。ビッグネスの躯体構造の規制・枠組みの内で低層部を建築的に表層のみをいじってみた所で、渋谷の質を保証する可能性は生まれないことは自明である。脱構築的な発想による「小さな構造」群がビッグネスの低層部を活かすには必要なのである。
ビッグネスの欲望の亡霊が漂うジェネリックな世界の低層部にどうしたら人間の振る舞いの気配と活気と尊厳の溢れた新たな「カオス」を創生し続けてゆくことが可能になるのだろうか。ビッグネスとカオスの新たな相克、これこそが渋谷の次のステージへの命題となってゆく。ビッグネスと新たなカオスとの共存こそが渋谷の描くべき都市ビジョンなのではないか。
軋む都市の亡霊(ビッグネス)と
野生(カオス)の相克 3
「ビッグネス」と「カオス」が相克し合う世界の上下二層構造の建築像について少し触れておく。ジェネリックなXLの相貌を示すビッグネスに対して、カオスはどこまでもヒューマンスケールを示すXSの世界となる。あくまでもビッグネスを成り立たせる大きな一次的な躯体構造の低層部に都市(渋谷)の質を保証する脱構築的な「かた」(典型)を許容する小さな二次的な構造を埋め込む入子型上下構造となるもので、それはこれまでの工事現場で幾度も体現してきた仮設の不定形さを映し出した小さな構造がそれらへの建築的ヒントとなるものだ。こうした低層部の小さな構造をスタディするのが本来のデザインアーキテクトの役割でなければならなかった、と私は思う。
しかし、竣工後のビッグネスの低層部には渋谷の質を保証する「かた」を抱えた「小さな構造」が絶対的に欠落している。どの低層部からもカオスが期待できる脱構築的な構造の素地が見当たらないのだ。これが今後の大問題。
内藤が低層部で力をかけた公共貢献とされる歩行インフラ都市装置「アーバンコア」や「スカイウェイ」を誘導したがそれらはいずれもデザインの差異性にこだわった「かたち」に過ぎず、インフラ都市装置の利便体験だけでは渋谷の質を保証しえるカオス体験は生まれてこない。
なによりも渋谷再開発で重要となる建築的課題はビッグネス低層部の接地性(大地性)をどの様に渋谷に再現させ、解放するか、そして、そこにどの様なアーバニズムを生み出せるのか、に尽きるが、その基本課題と大地から離れた新たな都市装置との関係性が不明なのが致命的なのである。渋谷の質の保証には低層部での接地性が絶対に不可欠になる、と私は考える。
「渋谷サクラステージ」(デザインアーキテクト:古谷誠章)の低層部はどう映るのか。「渋谷サクラステージ」は多くの解決すべき課題が山積みされたプロジェクトである。桜丘口地区再開発工事は敷地内を貫通するブラインド状態の仮設通路の往来時に、「計画」をアレコレ洞察してきた。工事現場への洞察は計画への期待もこもる。仮設通路はブリコラージュな魅力があり、通路の両側からは仮設パネルを介して進行する工事様態がイマジナリーに推察することが出来た。ここでの洞察が極めて肝心で、片やビッグネスの低層部、片や桜丘地域との接続部。それを媒介するのが仮設通路部分なのであった。そこは渋谷再開発に在って接地性が最も長い低層部を形成する重要な場所となるはずのものだった。しかし完成した姿に私は愕然とした。仮設通路から洞察した街と繋がる小さな構造(カタ)が見られず、そこに在るのは他のビッグネスとを繋ぐ都市装置と車の為の貫通道路でしかなかった。嘗ての桜丘が織り上げていたまちの密度感を生み出す余地はそこにはない。
要は一番肝心なビッグネス低層部(それも長い接地性をもつ特性)に渋谷の質を創出する新たな構造的建築提案が無いのが気掛かりだ。「渋谷サクラステージ」低層部に強く求められるものは小さな商売へのインキュベーティブな対応の集積に答えられる「小さな構造」なのではないか。
そうしたビッグネス低層部の目論見違いに比べて、期待の持てそうなものにJR渋谷駅の改造・更新開発が挙げられる。渋谷駅の改造は計画当初から低層施設が設定されていたものだが、私がずっと気に掛けて注視してきた渋谷駅に計画される「空中広場」(デザインアーキテクト:SANNA)の存在である。「空中広場」の梁躯体がキャンティレバー状にJR線路上にハングし出した時からこの工事経緯が気になっていた。
この架構体は私の見誤りなのかもしれないが、微かな下り勾配の梁躯体と映った。これは明らかに「事件」である。もし、それがそうで在ったならば空中広場としては異例的で、実験的な試みとなろう。
それは完成すれば線路上に浮かぶ下り勾配のデッキ状「空中広場」となるもので、床の微勾配が作用するアフォーダンスが内蔵された脱構築的な「かた」の小さな構造の出現で、それがどの様な人びとの出会いや憩いや集いを生むのかが大変興味を抱かせる。建築としてのアフォーダンスを主題化する「空中広場」の試みは渋谷再開発低層部に新たな「カオス」を作り出し、都市の見え方を変える都市資源となるかもしれない。そんな妄想も膨らむ。
それがジェネリックな光景と化す渋谷にアフォードされた「カオス」の場を創出し、渋谷に新たなパブリックライフが根付くのを期待したい。都市への希望とはこうした未完成な構造が示す余地に出会った時に感得されるものなのではないか、と思う。
いずれにしてもこれからの渋谷再開発の残りの推移はJR渋谷駅の改造・更新開発も含む「渋谷スクランブルスクエア」中央棟・西棟の工事進行の如何に関わってくるだろうから、その進行を見守るしかない。
これまでの低調な渋谷再開発施設低層部の様態に新たな渋谷の質がどの様に加わるのか、そこには渋谷の希望が見出せるのか、その一点への注視になる。
恐らくそのことが渋谷再開発への評価を左右する大きな「都市現実」になるのではないだろうか。



JR渋谷駅・空中広場の工事現場
(おわり)
連載記事一覧