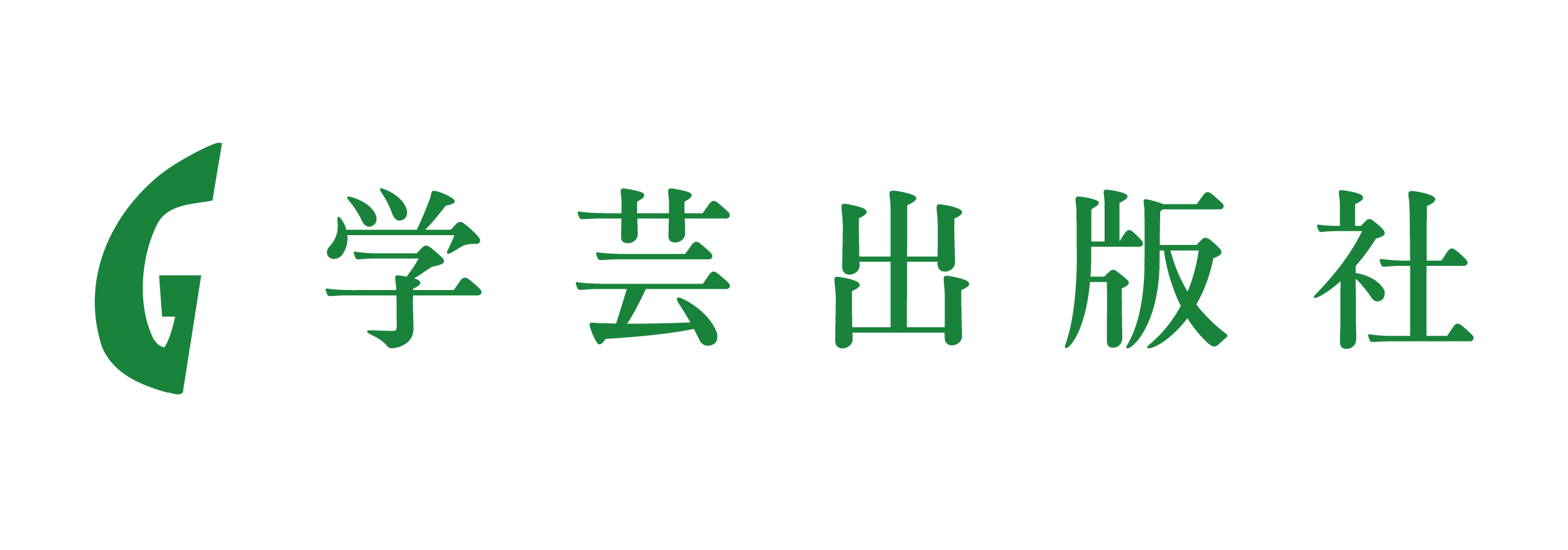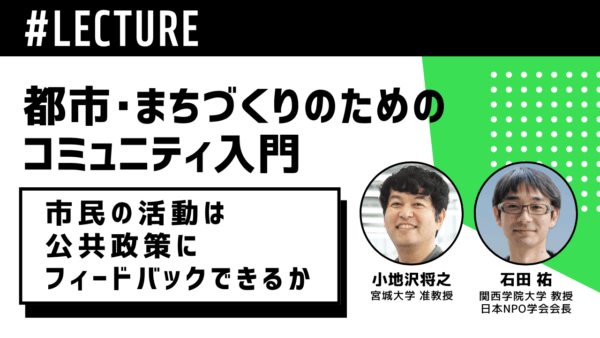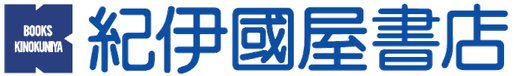都市・まちづくりのためのコミュニティ入門

内容紹介
空間のあり方と地域社会の仕組みを横断する
人々の関係性や行動の場となる都市・農村空間のあり方を構想する都市計画学と、空間的な世界の背景にある地域社会の仕組みを探る都市社会学。両者の融合を図る本書では、都市の成り立ちや地域社会の歴史、地縁組織・NPO等の担い手をめぐる課題、公共性の概念や公民連携の諸制度、交通政策や公共施設再編等の事例について解説
小地沢 将之 著

| 体裁 | A5判・240頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2700円+税 |
| 発行日 | 2024-05-15 |
| 装丁 | 北田雄一郎 |
| ISBN | 9784761528911 |
| GCODE | 5688 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| 関連コンテンツ | レクチャー動画あり |
| ジャンル | 都市・地域の計画 |
| 教科書分野 | 都市 |
■1. 住み続けられるまちを目指す社会の指針
1.1 世界共通の3つの目標
1.2 温暖化を抑制する~1つめの目標:パリ協定〜
1.3 持続可能な社会をつくる~2つめの目標:SDGs~
1.4 災害に強い社会を実現する~3つめの目標:仙台防災枠組~
■2. 都市の成り立ち
2.1 都市の誕生
2.2 コミュニティの定義
2.3 コミュニティの同一化・同質化
2.4 共有する生活
2.5 思想とコミュニティ
■3. コミュニティの単位
3.1 統治のための「閉じた社会」
3.2 町内会の登場:
3.3 郊外に広がる社会
3.4 防犯のための「閉じた社会」
■4. 閉じた社会から開いた社会へ
4.1 NPOの登場
4.2 強いつながりよりも弱いつながりを
4.3 人と人の間にある見えない力
4.4 外へとほとばしる課題解決の力
■5. 現代の都市政策の視点
5.1 都市のビジョンを定める
5.2 適正な都市の規模を定める
5.3 移動手段を確保する
5.4 公共施設を持続可能にする
■6. コミュニティ目線での都市政策の解法
6.1 コミュニティのビジョンも定める
6.2 生活機能の中心を定める
6.3 地域の隅々まで移動手段を確保する
6.4 公共施設をリニューアルする
■7. コミュニティの主体性
7.1 旧来的な集落組織
7.2 さまざまな主体の連帯
7.3 まちなかの活性化
7.4 エリアマネジメント
■8. 郊外住宅地の再生
8.1 都市は中心から外側へ
8.2 ロードサイド化する社会
8.3 大量生産から価値の創造へ
8.4 過疎化する郊外
■9. 多様な生活と安全安心
9.1 住民運動から市民活動へ
9.2 災害とコミュニティ
9.3 犯罪とコミュニティ
■10. 成熟社会の公共意識
10.1 下請け型のコミュニティからの脱却
10.2 住み慣れた地域で迎える高齢期
10.3 公民連携の時代
10.4 市民が支える公共
■11. 移りゆくコミュニティの中心
11.1 コミュニティの中心はどこか
11.2 学校
11.3 商店街
11.4 コミュニティ施設
11.5 街路と公園
■12. 住み続けられるまちの創造へ
12.1 基本ルールは「誰ひとり取り残さない」こと
12.2 地勢に逆らわない都市づくり
12.3 参加や意思決定のバージョンアップ
12.4 政策づくりのバージョンアップ
我が国は、町内会などの地縁組織を核としたまちづくりが伝統的に盛んである。しかし、担い手の高齢化や町内会加入率の減少などの背景から、これらの活動の持続が困難になりつつある。阪神・淡路大震災を契機に、NPOなどの新たなセクターが課題解決型まちづくりの担い手として注目され、東日本大震災においても延べ数百万人の人たちが被災地で活躍したといわれている。東日本大震災の翌年に開催された世界防災閣僚会議では、NPOなどによる支援の事例が多数報告された。しかし、地縁組織が主導した取組みの事例報告は、第9章でも紹介している仙台市内の1事例のみであった。地縁組織による課題解決型の活動、あるいはNPOと地縁活動の融合による活動は、平時でも災害時でも実際にはあまり行われていない。
一方、地方自治体における都市政策は公民連携の時代を迎えている。「民」は従来、企業などの経済セクターを指すが、我が国の歴史的な社会構造を鑑みると、「公」にとってのもっともふさわしい連携パートナーは地縁組織であろう。すなわち、地域に暮らす私たち一人ひとりが課題解決力を備えたまちづくりの担い手になる方法を検討しなければならない。
ところで、従来は都市の成り立ちなど空間的な都市構造に関する学問は、建築・土木学分野の一領域である都市計画学が担ってきた。公民連携や都市政策に関する内容もここに含まれている。一方で、町内会やNPOなど、社会の非空間的な側面については、社会学の一領域である都市社会学の守備範囲である。この両者が融合すれば、我が国特有の都市や社会の成り立ちをふまえ、その特性を最大限に活かした課題解決が実現可能となるだろう。近年は公共施設等総合管理計画や立地適正化計画など、新しい行政運営や都市経営の考え方も出てきており、これらの新制度を適切に運用していくためには、都市計画学と都市社会学の双方の専門性を有しながら取り組むべき時にある。
本書は、ハードの都市を扱う都市計画学と、ソフトの社会を扱う都市社会学の双方について、基本的な視点を押さえながら、それぞれを個別の学問の知識として修得するのではなく、双方の関わり合いを理解できるようまとめた教科書である。すなわち本書の狙いは、建築・土木学分野の学生たちにとっては、その空間的な世界の背景にある社会の仕組みを意識することができ、社会学分野の学生たちにとっては、人々の関係性や行動のフィールドである都市空間や農村空間の成り立ちやあり方を知ることができることにある。
世界の人口は80億人を超え、2050年代後半には100億人を超えるとの推計があり、こういったトレンドをふまえながら、世界中では持続可能な社会のあり方を追究している。それは、地球温暖化や貧困などの克服に関する目標であるため、私たちの遠いところで起きているような錯覚をしていないだろうか。
現実にはこういった課題は、世界が直面している形とは異なる形で、極端な人口減少が進もうとしている我が国にも襲いかかってくる。地球温暖化に伴う洪水が増えれば、私たちが河川流域に形成してきた都市の安全さは損なわれる。猛暑が続けば、栽培ができなくなる農産物が増加し、私たちの食糧調達に危機が到来する。すでに都市部と郊外や地方都市の間では、教育・医療・福祉サービスへのアクセスの格差が生じているが、この格差はますます拡大する。
こういった課題に対して、これまでの私たちは限られた専門性のみに身を委ねながら正解を追究しようとしてきた。たとえば、都市計画学では土地利用などの規制は全体論の理屈を持ちつつも、場当たり的に地区レベルでの例外を許容し続けてきた。都市社会学では社会構造を過度にモデル化してしまうため、生活者一人ひとりの息遣いが見えにくくなることも多かった。結果として、社会が抱えた諸課題を解決できないまま、人口増加のピークを折り返し、到来することが予見できていた人口減少への対応策を持たないまま現在に至っている。
そこで本書では、建築・土木学分野の都市計画学と社会学分野の都市社会学の双方の知識の修得に向け、それぞれの学問の基本的な考え方を網羅するとともに、現行の諸制度を紹介しながら、さらにその先にある持続可能な地域社会の構想をするための視座の獲得の一助となることを目指している。本書を最後まで読み解いていただければ、これらの学問が融合したその先に、持続可能な社会の未来がみえるはずである。
第1章では、世界中が共通の目標としているパリ協定、SDGs、仙台防災枠組について紹介している。これらは世界の最末端に暮らす私たちをも包含する目標であり、地域社会の持続可能性を検討するうえで、もっとも尊重しなければならない目標である。
第2章と第3章では、都市の成り立ちやコミュニティの構造について理解する。建築・土木学分野の初学者が扱う空間的な都市の成り立ちと、社会学分野の初学者が学ぶコミュニティの構造を横断的に理解することで、現代の社会構造がつぶさにみえてくるようになる。
第4章では、古典的な都市や社会の閉鎖性が現代の社会では限界を迎えていることについて、弱い紐帯(Weak Tie)やソーシャル・キャピタルなどの概念とともに紹介していく。
第5章と第6章では、都市政策、都市計画、交通計画、公共施設の再編のそれぞれについて、我が国の諸制度とその事例を紹介している。地方自治体ごとにその扱いがまちまちではあるが、先進的な取組みには持続可能な社会を実現するためのヒントが内包されている。
第7章では、新しい地域社会の担い手や課題解決型のまちづくりの方向性について理解していく。併せて、まちなかの活性化の必要性について紹介している。
第8章では、世界的に進んだ都市の郊外化の歴史に着目する。ソフトの社会の成り立ち、ハードの都市空間の変遷の両面からみると、現代の郊外住宅地が抱える課題がみえてくる。
第9章では、安全安心をめぐる課題が多様化するなか、これらに対応している担い手、仕組み、その実践例について紹介している。激甚化する災害からの復興においても、コミュニティスケールでみていくと、その対応方法が明らかになってくる。
第10章では、公共性とは何かを理解しながら、私たち自身が社会の担い手であるべき理由を探求している。
私たちの社会が変容するにつれ、コミュニティの中心も移ろいゆく。第11章では、これからの時代において中心性を担う場所がどこであるか、それぞれの場所をめぐる最新の制度などとともに掘り当てていく。
第12章は、本書のまとめである。これまでに紹介した社会の成り立ちや現行の制度などをふまえつつ、持続可能な社会を構築するうえで不足している視点を補うことを狙っている。
本書は、建築・土木学や社会学の領域のみならず、地域創生を支える行政学、地域振興を担う経営学、地域の魅力を掘り起こす観光学など、地域社会を扱うすべての学問分野において活用していただけるものであると確信している。また、地域活性化などに奔走している行政職員やコンサルタント、NPOスタッフなど、あらゆる実務家にもお役立ていただきたい。
2024年5月
小地沢将之
2005年、地方創生の実現のためには、大学と地域が連携することが重要であることについて国が初めて言及し、内閣府都市再生本部の第10次決定として「大学と地域の連携協働による都市再生の推進」が掲げられた。都市再生本部の決定を受けて結成された「大学地域連携まちづくりネットワーク」は8地域の地方自治体と大学から始まったが、わずか1年でこの組織は全国津々浦々に広がり、大学と地域は当然のように関わり合うべきとの新しい価値観が形成された。これをきっかけに、地方都市にキャンパスを置く大学を中心に、大学によるまちづくり分野への参画が進められるようになった。また各大学では地域貢献に資する学問領域として、都市や農村、地域、観光などを扱う独自のカリキュラムを発展させるに至っている。
ところで、筆者は「大学地域連携まちづくりネットワーク」の発起人である東北公益文科大学(山形県酒田市)において、地域と大学を結ぶ「共創」の拠点である地域共創センターのセンター長を担当していた時期がある。造語的な用法としての「共創」という表現は古くから存在していたが、価値を創造するという意味合いの「Co-creation」の日本語訳として大学が使用し始めたのは東北公益文科大学が最初であり、いまや全国の大学が地域と大学の連携を「共創」と称している。
この初期の共創の現場では、たびたび頭を抱えることが起きた。いままで閉ざされていた大学の門戸が突然開かれ、地域の困りごとを解決してくれる窓口ができたので、多くの人たちが大学を訪ね、さまざまな期待を大学に寄せた。しかしその多くは、「学生をボランティアに派遣してほしい」など、不足する労力(本書では第4章で「ヒューマン・キャピタル」として紹介した)を学生たちに求めるものであった。もちろんこういった期待感には1つ1つ応えていったのだが、地域の期待感と学生たちの本分である学びとの間には大きな乖離があった。その溝を埋めるためには、大学が学生たちに対して地域にまつわる専門性を身に付けてもらうためのカリキュラムを用意することが近道であったため、カリキュラム改変も私の仕事の1つになった。私が籍を置いていた大学は幸いにして、規模は小さいながらもさまざまな分野の専門家がいたため、教員個々の専門性に依存しながら、その組合せの最適解を探すような作業を行い、学生たちの専門性の獲得に資する課題解決型の学びを行える環境を整えていった。しかし、これはオムニバス科目やフィールドワーク科目にならざるを得ない側面も多く、全国多くの大学でもそのような対処に留まっている。
私の故郷の仙台が東日本大震災に見舞われたことをきっかけに、私は東北公益文科大学を離れ、地元で震災復興に奔走することになるが、そこで目の当たりにしたのは学術分野の専門性が融合する暇もなく、それぞれの論理で復興が進められていく状況であった。震災からまもない2011年6月、国の復興構想会議は「復興への提言 ~悲惨のなかの希望~」を公表し、このなかでは「新しい地域」「技術革新」「イノベーション」など、新時代を予感させるキーワードが並べられた。しかし、実際に復興に用いられた支援制度は、各省庁が平時から用いている制度のつぎはぎのようなものであった。筆者は都市計画学の専門家として、また共創のムーブメントをつくり出した一人として、復興期に分野融合・分野横断の地域づくりの素地を生み出せなかったことに、いまだ敗北感のようなものを感じている。
本書を執筆中にも、令和6年能登半島地震が発生し、その復興の道筋はまだ始まったばかりである。このたびの災害は、私がこれまで被災地で支援してきた東日本大震災や熊本地震、平成28年台風第10号などの災害とは、都市の成り立ち、人々の関係性など、異なる点は多い。すなわち、過去の災害の経験を目前の災害に無理やり適用しようとしても、部分的には正解でも、多くの部分で誤っている可能性がある。
最近の災害復興の現場では、これまでの現場での経験値の高い人たちがそれまでに培った経験則で立ち振る舞うことがあたかも正解であるようにいわれているが、これは日本人特有の職人気質の悪い現れでしかない。本来は、その経験則を専門的で体系的な知識に落とし込み、次の担い手に受け継ぐことが重要である。
本書では、複数の学問に依拠しながら、過去の経験をも学問上でどのように捉えることが可能か、丁寧に説明してきたつもりである。一方で、地域福祉学や環境学など、本書では取り扱い切れなかった学問上の知見も多い。このことを念頭に置いていただきながら、都市・まちづくりへの学びを深めていただきたい。
日本海に沈む夕陽は美しいが、奥能登では海から昇る朝陽もみられるという。少しでも早く、平穏な朝が迎えられるようになることを心から祈りたい。
本書は、私のわがままで、企画から出版までを非常に短い作業工程で進めたため、学芸出版社の松本優真さんには多大なご負担をお掛けしました。全面的なサポートをいただきましたことを、ここに感謝申し上げます。
2024年5月
小地沢 将之
開催が決まり次第、お知らせします。
終了済みのイベント
メディア掲載情報
その他、各所でご紹介いただいています
・岩手県議会「議会図書室だより」令和6年度No.5(令和6年11月26日発行)
ほか