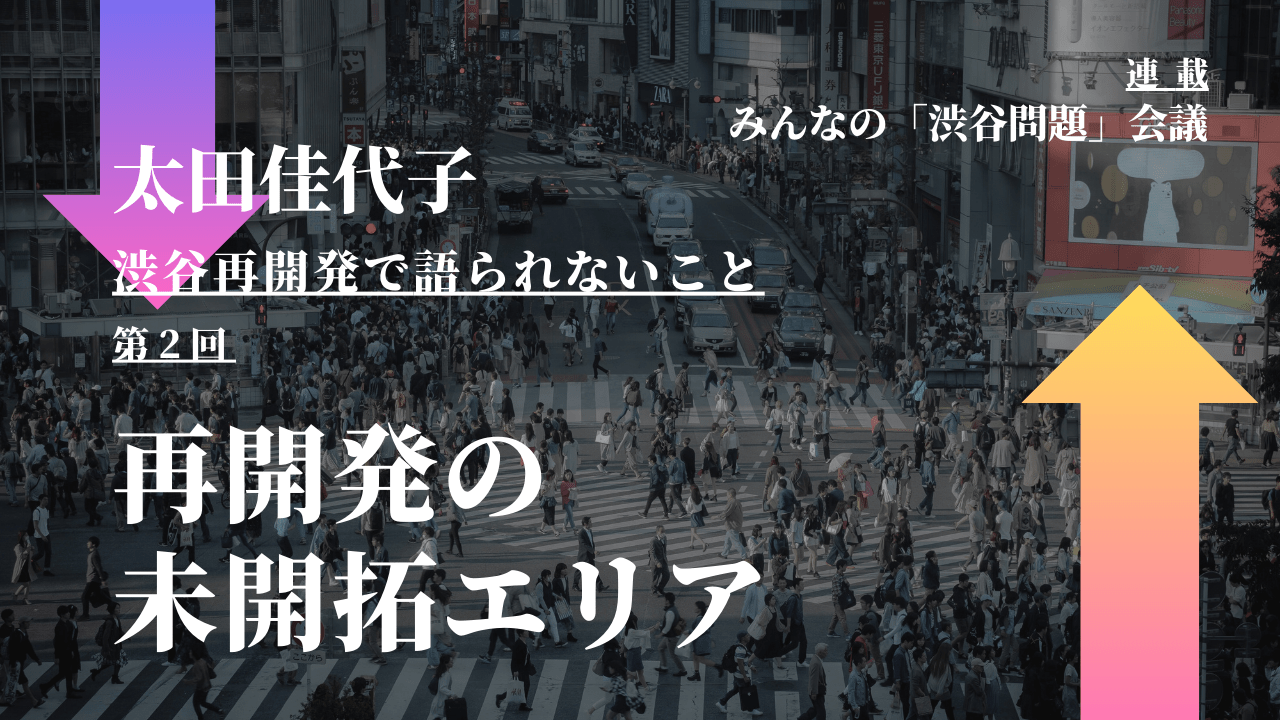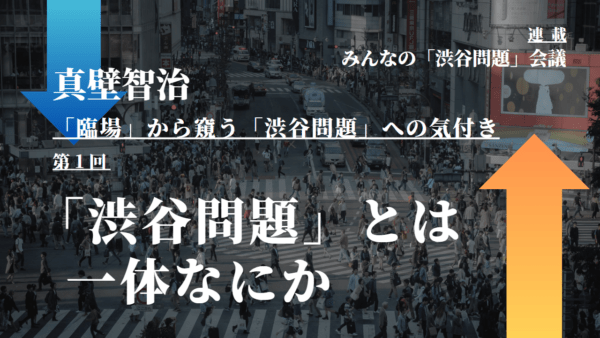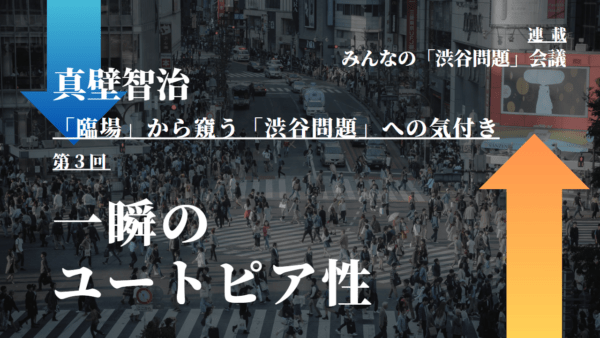再開発の未開拓エリア – 太田佳代子「渋谷再開発で語られないこと」(第2回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
太田佳代子(おおた・かよこ)
建築キュレーター、編集者。NPO法人建築思考プラットフォーム理事。ハーバード大学デザイン大学院特任研究員。2018〜21年、カナダ建築センター(CCA)特任キュレーター。2014年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館コミッショナー。2004〜06年雑誌「DOMUS」副編集長・編集委員。おもな編著に『SHIBUYA! ハーバード大学院生が10年後の渋谷を考える』(共著)など。
はじめに
都市間競争に勝たないと日本は衰退するーーというのが、都心の再開発を牛耳るオジさまたちが好んで使う決めゼリフである。マスメディアはいつもこのフレーズを素直に伝えているが、疑問はないのだろうか。社会全体にズームアウトすれば、所得格差が広がり、高齢化や孤独の問題が深刻化している。高所得者に寄り添う大規模再開発というものを、もっと相対的に論じる時に来ていると思う。
≪横にスクロールしてお読みください≫
公益性の測り方
規制緩和と引き換えに公益がオファーされた都市再生特区の再開発。そこでは、あらゆる人々に開かれた、インクルーシブな場所が作られているかどうか、公益の中身を検証し議論する必要がある。いまのところ、規制緩和を決めるプロセスを公開して公に議論するシステムはないが、それができれば、なにかと批判の多い大規模再開発にも、より多くの人が納得し、使いたくなる場所ができていくのではないか。
難しいのは、都市再生特区に想定された「公益」が妥当な内容かどうか、最初からすべてジャッジできるわけではない、ということだ。公共施設ができればいいという訳でもないし、屋外にオープンスペースがあればいい訳でもない。また、規制緩和の対象となった部分がどうデザインされるかでも、その場所に生まれる公益性の度合いは違ってくる。
そのことを示したのが、渋谷駅の南側にできた渋谷ストリームの低層部分である。設計者たちは、超高層ビルの足元部分でできることを最大限開拓し、未曾有の公共スペースを作り出した。建築のデザインが、人々の想定する「公益性」のありようを広げたと言っていい。
建築の公益性パフォーマンスを上げる
渋谷ストリームにはたくさんの出入り口がある。そのどれにも、屋内・屋外を仕切るドアはない。2階レベルでは、建物の端から端までを「ストリームライン」と呼ばれる長い通路が貫通している。あちこちで吹き抜けているこの通路は、屋外と屋内の入り混じる独特の空間だ。風が通り、光が入り、都会の音が届く。JR渋谷駅の音、高速道路の音、川の音。ここ渋谷でしかできない体験がデザインされている。
ゆったりとカーブする貫通通路に緊張をもたらすかのように、シャープな色のエスカレーターが空間を斜めに貫いている。様々な方向に向かう吹き抜けやエスカレーターは、この超高層ビルが抱える営みの多様さを示してもいる。管理され、均質化されているのが普通なのに、この屋内通路は交通動線を整理するだけでなく、都市空間の多層性を視覚化し、都会的な心地よさを作り出している。
設計者は建物低層部のあちこちに孔を通し、縦横無尽にネットワークを広げるという、建築のコンセプトを発案した。画期的なのは、超高層ビルの足元を屋外に開放し、収益性の縛りから解放し、親しみやすいインフォーマルな公共スペースにしたことだ。また、再開発で駅裏の路地が失われた代わり、細かな工夫の積み重ねによって界隈の表情をもつストリートや、路地裏風の曖昧なスペースを作り出している。
大きめの背もたれ椅子が並んだ通路がメインストリート脇にある。そこはいつも、スマホを片手に長居する若者たちに占領されている。都心の喧騒に浸りつつ一人になれる場所が、この低層部のそこここに用意されている(写真1、2)。完全な駅ビルデパートになった隣のスクランブルスクエアとは対照的だ。
大規模再開発を実験室に
本来、この超高層ビルの低層部に求められた公益は、「交通の補助」「歩行者ネットワークの整備」「渋谷川の環境整備」(*1)といった方程式のようなフレーズで表現されていた。結果、アーバンコアが作られ、渋谷川が復活し、周辺の都市インフラが接続され、新しい人の流れが生まれた。だが、注目すべきは、当初の想定を超えて多義的な公共空間となった、ビルの低層部だと思う。規制緩和で求められた公益性が、建築デザインによって高められた例として、渋谷ストリームは位置付けられるのではないか。そして、これからの大規模再開発は、この例に学ぶべきではないかと思うのである。
ここで忘れてならないのは、画期的なケースを導いたいくつかの要因である。まず、これまで都心の大規模プロジェクトからほぼ締め出されてきた中小規模の設計事務所に、わずかながら門戸を開いたこと。この「抜擢」は、大規模再開発に危機感を抱く内藤廣氏が、渋谷再開発で実験的な取組みをしようと、公共貢献の条件に加えたものだという(*2)。
渋谷再開発全体のビジョンとして、「地上階プラスマイナス2階は街のもの」という内藤氏の考え方があったことも重要だ。「公共貢献のための余剰は低層部に投下すべき」(*3)という彼の主張が、これからの大規模再開発に継承されていけば、消費だけではない多様な営みや交流を支える空間が都心に増えていくだろう。
さらに、建築、土木、都市計画のデザイナーが協力体制を組むことで、超高層ビルに文字通りの風穴を開けたことも覚えておきたい。故・小嶋一浩氏とともに設計に当たった赤松佳珠子氏は、「大都市におけるダイナミックな流動性を持つ新たな公共空間を、設計者、民間企業、行政の枠組み、そして建築と土木、都市計画の領域を横断してつくり出す」(*4)チームワークがあったと述べている。大規模かつ複雑ゆえに成立する実験があり、多様な才能を集める価値があるということではないだろうか。
渋谷の例からの学びとして、都市再生特区の設計者を公開コンペで選ぶことを求めていくことが考えられる。いまのところ大規模再開発は大企業に独占されていて、マーケットの外の人間には関心を持つのが難しいけれど、開拓する余地のある可能性は探るべきだ。それができれば、市場論理に支配される一方の都市空間にも、多少の自治力を回復できるかもしれない。
[写真1]喧騒の中で一人になれるメインストリート脇の通路(筆者撮影)

[写真2]居続けられるコモン空間(筆者撮影)

*注
- 東急電鉄広報資料「渋谷駅南街区プロジェクト(渋谷三丁目21地区)に関する都市計画の決定について」2013年6月17日付。
- 「建築雑誌」2018年5月号、内藤廣インタビュー「都市は誰のものか ––「渋谷駅中心地区」を振り返る <2>」(p.35)
- 同上(p.34)
- 「新建築」2018年11月号 、赤松佳珠子「風を感じる心地よさをつくり出す」(p.55)
(つづく)
連載記事一覧