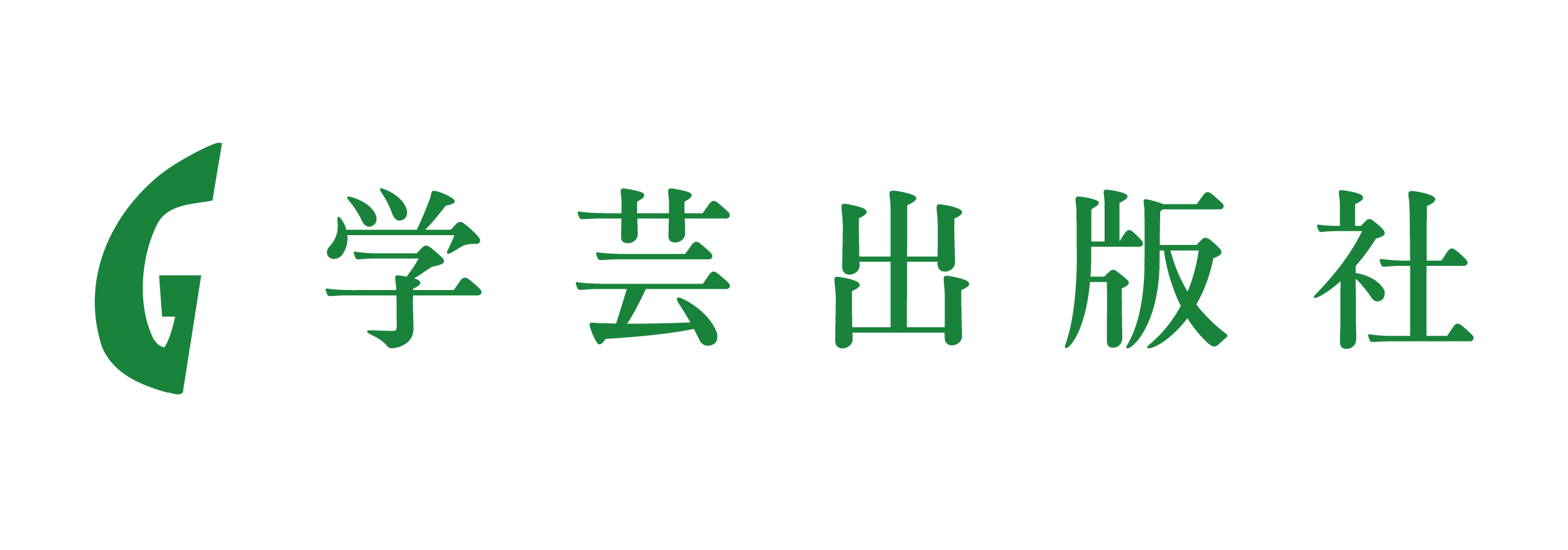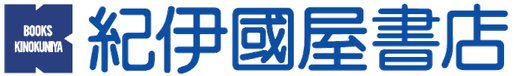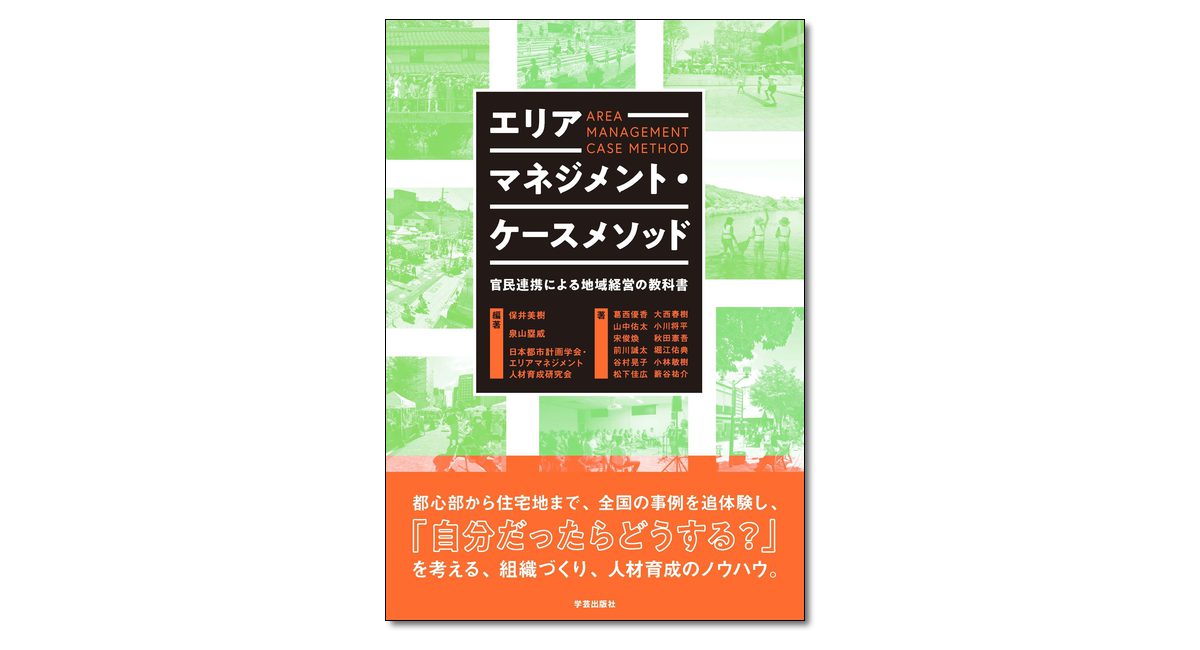ポスト2020の都市づくり

内容紹介
従来のハード開発とは違うソフト開発の分野から、まちづくりに関わる人が増えている。クリエイティブシティ、ポップカルチャー&テクノロジー、アートマネジメント、エンターテインメント、ブランディング、エリアマネジメントのエキスパートが実践に基づき提案する、ソフトパワーによるイノベーティブなまちづくり。
体 裁 四六・288頁・定価 本体2400円+税
ISBN 978-4-7615-2649-8
発行日 2017/07/05
装 丁 中澤耕平
序文「ポスト2020年」が意味するもの 水野誠一
1章 創造都市の理念と実際 井口典夫
1 創造都市とクリエイティブ資本論
2 日本の都市づくり
3 協働型まちづくりのアプローチ
4 東京都心での実験
5 今後の展開
2章 都市の創造力を高める「ポップ」&「テック」 中村伊知哉
1 創造的だが、創造的とは思っていない日本
2 創造力を発揮する都市とは
3 外国人が憧れる日本文化のクールさとは
4 コンテンツ産業を伸ばすための戦略
5 都市の成長を左右する情報テクノロジー
6 IoT、AIが日常化する社会の設計
7 デジタル・コンテンツ特区Cip
8 新しい文化・産業を生みだす超人スポーツ
3章 来たるべき計画者のために~アートプロジェクトの現場から 芹沢高志
1 計画者の矛盾
2 別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」 ─プライベートとパブリックの境界が溶ける場所
3 さいたまトリエンナーレ2016 ─柔らかな都市計画
4 三つの論点
4章 アートは地域に取り込まれるのか、地域はアートに力をもらえるのか 玉置泰紀
1 アートとローカルはどこで出会ったか
2 アートはローカルの中でいかに闘ったか
3 アートがもたらす地域のメタ化
5章 街のブランディングとソフトインフラ 小林洋志
1 都市のソフトインフラとは何か?
2 「Rising East」というまちづくりのコンセプト
3 まちづくりのパートナーとしての役割
4 エリアをプロモーションする
5 収益源としての三つのビジネス
6 エリアの価値を高めるプラットフォーム
7 まちづくりを自分事化する市民ファンド
8 ヒューマンネットワークによるブランディング
6章 動きだすパブリックスペースと運営組織のデザイン 保井美樹
1 街のガバナンスと事業のマネジメント
2 ニューヨークにおける官民連携とエリア経営組織
3 日本における官民連携の始まり
4 エリアマネジメントへ
5 パブリックスペースを育てる組織づくり
6 エリアマネジメントのチャンス到来
7章 都市開発の変化とソーシャルハブの形成 松岡一久
1 都市開発プロセスの変化
2 都市開発におけるソーシャルハブ
3 ソーシャルハブの形成に必要なこと
序文 「ポスト2020年」が意味するもの
水野誠一
2020年といえば、まず100人中99人までが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以降オリパラと表示)のことを思い浮かべるだろう。たしかに、日本にとっては重要なターゲットイヤーであることは間違いない。だが日本中が招致成功に沸いていた時点では、今回のオリパラと1964年の東京オリンピックとでは環境や条件が根本的に異なるという気づきが、当事者間のみならず国民の間でも希薄だったような気がする。それは、戦後の経済復興期を経て高度成長期の戸羽口の時代だった前回と、経済成長の果てともいえるバブル期とその崩壊を体験し、少子高齢化時代が進む今回とでは、すべての前提条件が異なるということだ。
一言でいえば、「成長期」と「成熟(化)期」の違いである。成長期に開催された前回大会では、あらゆる投資を、その後の東京あるいは日本のインフラ強化に活かすことができた。レガシー(遺産)という概念があるが、まさに大半が「正」のレガシーだった。だが、成長期を終えて成熟期に入ろうとしている2020年のオリパラでは、すでに物議を醸したメインスタジアムの設計変更と資金の見直しのように、「ポスト2020年」の姿を冷静に展望し直す必要があるはずだ。現段階では、単にオリパラにかける経費削減の議論でしかないのだが、それでもようやくその後に残される「負の遺産」という概念も語られるようになってきた。開催後は滅多に使われそうもない巨大競技場などが、赤字を垂れ流す負の遺産となるだろう。
また、オリパラ需要に間に合わせるホテルの増設も盛んだが、下手をするとその後には供給過剰になる恐れがある。訪日外国人旅行者(インバウンド旅行者)は、2016年の統計資料によると1974万人、世界ランキングでは16位だという。なにがなんでも絶対数を増やそうという政府の目論見が、団体客誘致に集中するあまり質を無視した量だけの拡大になっている。だから、現在増設されているホテルのターゲットとは必ずしも需給がマッチしない。反対に富裕層の個人客が増えない背景には、高級ホテル(ハード)がいくら建ち並んでも、それに対応する、日本独自の文化が誇る「おもてなし」サービスやコンテンツ(ソフト)に不備があるとしか思えない。
だが、コンセプトやマーケティングなどのソフトなきハードの暴走は、オリパラだけの話ではない。いやでも進行する少子高齢化時代、すなわち成長期を終えて成熟化期に入っている先進国では共通する課題だといえる。
日本には以前から「ハコモノ行政」という言葉がある。これは、公共事業をする時に、ハードウェアづくりのみに腐心して、肝心なソフトウェアやコンテンツの開発がおろそかになる現象を揶揄した言葉だ。だが、公共事業のみならず、民間主導の都市計画でも、ハードインフラを偏重してきたために、時代動向に対応できなかった事例が少なくない。そこには、消費人口を超えて供給過剰になってしまった大型商業施設の姿もある。事実、各地で大型商業施設の閉鎖の連鎖が止まりそうにもない。まさに「成長神話」の呪縛から逃れられずに、成熟化時代の到来を見誤っているのだ。だが、発想を転換さえすれば、解決不可能な問題ではないことを、この本は説こうとしている。
何事にも、成長期から次第に成熟化期に到達していく段階がある。たとえば、マズローの「欲求の五段階説」などもその一つだろう。それは、一番基本的で本能的な「生理的欲求」(食べたい、飲みたい、寝たいなど)から、安全で安心な暮らしを求める「安全欲求」段階になり、さらには、集団に属したい、仲間が欲しいという「社会的(帰属的)欲求」に進むという。ここまでは、外的充足だが、次に、他者から認められたい、尊敬されたいという内的充足の「尊厳欲求」に進み、最後には、夢の実現という創造的な活動をしたいという「自己実現欲求」に至るものだという。この内的な二段階こそが、成熟化期の欲求といえるだろう。
都市開発でも、同様な段階があり、それは以下のように説明できる。
第一段階:何でも建てればよかった段階。
「必需性充足期」。ハードのみを最重視する段階。
第二段階:商業やオフィステナント誘致などで、マーケティングが意識された段階。
「必欲性形成期」。ハードを支えるソフトの出現。
第三段階:広義のデザインによって、より大きな付加価値の創造に注力する段階。
「高付加価値形成期」。ソフト的付加価値の尊重。
第四段階:単純効率から脱して、多様な業種、地域の連携などをしくみ化する段階。
「高多様的成熟期」。ソフトと個性化の最重視。
仮にものづくりでいえば、従来の単なる品質/機能重視のハード志向から、すでにブランド力、デザイン性、あるいはライフスタイルの重視といったわかりやすい付加価値性を付与していく段階に入っているのだが、これらはいまだ「成長期」を前提とした進歩でしかない。そして一方では、ファストファッション、ファストフードに代表される価格競争商品が急成長してきた。こだわりを持った高付加価値な差異化商品との間で二極化が起きている。それによって、その間に存在する無性格で中途半端な中級品はあきらかに売れなくなった。
この現象は、先進国で叫ばれている「貧富の差」という二極化の拡大と無関係ではない。だがこれを単純な二元論として捉えているだけでは問題解決にならない。それをどう多元論的に解決していくかが問われることになる。時代は明らかに「成熟(化)期」に入っていく兆しがあるのだから、さらに多様性、地域性、個性、差異性などへの対応をしなければならないはずだ。私はそこには、従来の常識をリセットする「否常識」な思考、あるいは「逆転発想」が必要になると思っている。
最後に、「否常識思考」に必要なキーワードをいくつか掲げて、私の責めを蓋ぎたい。
その第一が、「文明から文化へ」という発想転換だろう。正確にいえば、「文明盲信から、文化の再認識へ」の転換である。20世紀の文明の進歩、すなわち経済成長、あるいは科学の発展によってもたらされた「環境的」あるいは「資源的」な矛盾を解決するためには、もはや「文明力」だけでは解決できないことは明らかだ。生活価値観や幸福感、さらには豊かさの定義を変える「文化力」を信じることが重要になる。さらに、現在世界の政治で最大のコンフリクト要因となっている「キリスト教」対「イスラム教」という宗教間対立の解消も、西洋的な文明観を一方的に押しつけるのではなく、相互の文化を認めて尊重しあうための「抗争から構想へ」の転換が必要になる。
そのためには、「進化から深化へ」という転換も重要になる。20世紀には、科学技術の進歩、それに伴う経済規模の飛躍的拡大という、人類の「進化」ともいえる成長がもたらされたわけだが、それらは表層的な進化であり、それによって物質主義や拝金主義が跋扈すると同時に、人類だけが持つ特性である思想性、哲学性、倫理性などが退化してきたのではなかろうか。これらの力を高めるためには、人間性の「深化」こそが重要になる。
それは、「競争から共創へ」という発想転換にもつながる。いつまでも競いあう「競争」ばかりではなくて、環境問題や資源問題という共通課題に対応するためには、競合相手同士が力を合わせて、共に知恵を絞る「共創」関係が求められる。
さらには「教育から共育へ」という転換も重要だ。20世紀の技法の「マニュアル教育」に代表される教育の概念では解けない問題解決のためには、共に考えヒントを共有しあう「共育」という概念が必要になる。
本書は、私が理事長を務める一般社団法人国際文化都市整備機構(FIACS)のメンバーで執筆した。それぞれ専門分野の異なる著者たちの事例研究を、こうしたキーワードのフィルターを加味しながら読み解いていただければ幸いだ。
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。