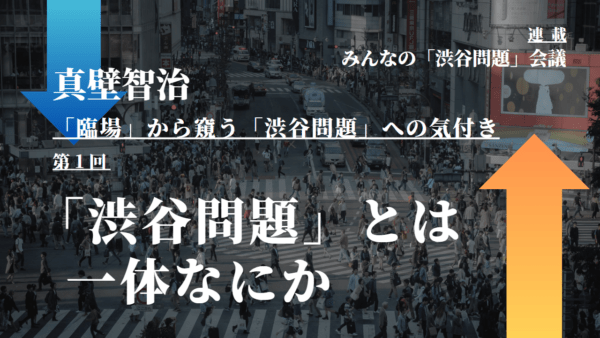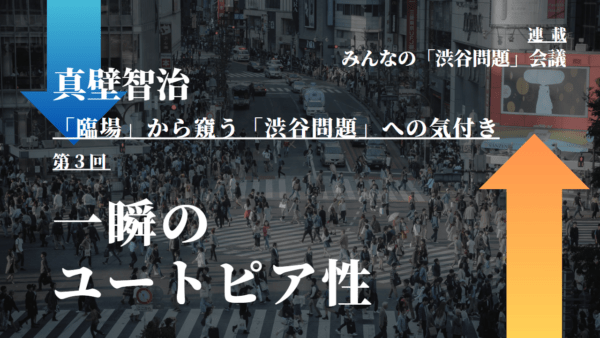用意された“公共性”を纏う都市空間の行方 – 北山恒「渋谷問題という起点」(第2回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
北山恒(きたやま・こう)
1950年生まれ。横浜国立大学大学院修士課程修了。1978年ワークショップ設立(共同主宰)、1995年architecture WORKSHOP設立主宰。横浜国立大学大学院Y-GSA教授を経て、2016~2021年法政大学教授。2021年awnに組織変更、同時にネットワーク組織AWN設立。現在、横浜国立大学名誉教授、法政大学客員教授。
はじめに 問題の所在
真壁智治さんから「みんなの渋谷問題」という提議を受けてこの文章を書くことになった。都市の巨大再開発の問題は、問題が見えないことかもしれない。というか、問題が隠蔽されている。それは意図された隠蔽ではなく、意図されない隠蔽なのかもしれない。そしてこの社会にある構造的な抑圧のなかで、「問題」が問題化していないようにも思える。問題がわかりやすく見えれば街に出てデモンストレーションしたいのだが、問題が見えないから「みんなの問題」とはならない。だから、問題がどこにあるのか考えてみたいと思う。
≪横にスクロールしてお読みください≫
17年間のパリ大改造!
東京は実経済の沈滞とは無関係に、何故か巨大開発工事の熱狂のなかにあるが、19世紀の半ばのパリも同じような開発工事の熱狂のなかにあった。オスマンのパリ大改造である。1848年の二月革命直後に書かれた『革命が不可能になる新しいパリの計画』のなかで、人口が急増し劣悪な都市環境のなかでの生活の様子が詳しく描写され、「この狭く不潔で暗い街路」には暴動が起きるたびにバリケードが築かれた。
1853年からわずか17年間でおこなわれたパリの大改造で、この迷路のような入り組んだ街区をクリアランスして、見通しの効く都市空間にしてしまった。反乱軍を鎮圧しやすくするという意図が背景にあったようであるが、産業革命以降、工場が立地する都市は地方からの都市労働者を集め、都市の空間密度が過度に上がっていた。当時、パリは産業と人口の集中によって社会様態が大きく変容しており、それに対応する都市空間が要請されていたのだ。
パリの大改造は産業革命以降のヨーロッパの文明変換点のなかにあって、都市空間の対応を示している。帝政という強大な権力が管理する壮大な公共空間が登場し、ブールバールという大通りは都市内のモニュメントを視覚的に結ぶ。この都市空間のなかで人々はパリという社会システムに日常的に包摂されているという感覚をもつようになった。パリ大改造はナポレオン三世が任命したオスマンという官吏が「超過収用」という不動産開発の手法をつかっておこなった巨大再開発である。開発利益を再投資して自律的巨大再開発を行うという近代的都市開発手法が使われたが、このような都市全域を再開発するという事業は、帝政という単一の権力支配がないと実行できない。
このパリ大改造は渋谷再開発と同じく衆人環視の下で行われる「劇場型再開発」であった。真壁さんの描く『臨場』と同様、都市の姿を変更する巨大な工事現場に出くわした作家たちがそれを報告している。エミール・ゾラは『居酒屋』のなかで、モンマルトルの労働者街を切断するマジェンタ通りの工事現場を描写し、解体工事によって通りに光が差し込む様を報告している。当時の大改造を連載雑誌でレポートしたマクシム・デュ・カンの『パリ、1870年までのその装置、その機能およびその生命』という都市論があるが、工事中の大改造に関しておおむね好意的である。それでも「われわれが習慣を狂わせ、家屋の取り壊しの埃が目に入り、(中略)都市を憂鬱に移動している」と完成に期待しながらも工事中の不便を嘆く。そして、ボードレールは『悪の華』で、改変されてしまう都市空間の喪失を嘆き、この大改造に反駁する。いずれも工事途中の反応である。
20年間かかる渋谷再開発?
権力が一方的に行う、最終のカタチが見えない再開発では様々な意見が提出される。しかしながら、パリという都市のカタチをつくる工事は強大な権力によって遂行される。民主的社会では実現できない壮大な都市の再編成、人間スケールを超越する空間操作によって卓越した権力標示の都市空間を生み出した。それに対して、渋谷再開発は私企業の再開発事業を中心とした地区整備計画である。オスマンによるパリの大改造は17年間を要したが、渋谷周辺地区再生整備計画は、私企業のビル建て替え事業にもかかわらず、それを超える20年の工事期間となっている。
パリの大改造はナポレオン三世の官吏オスマンに権限が集中していたが、現代の民主的社会で行われる巨大再開発なので、「渋谷駅中心地区デザイン会議」という会議組織が設置され、私企業の事業に公共性が持ち込まれている。この会議組織の構成は、内藤廣さん、岸井隆幸さんを中心とする4名の学識経験者、地元代表として宮益町会会長と道玄坂商店街振興組合理事長の2名、渋谷区の行政から2名、この8名の構成である。この事業運営を見ていると、情報の開示は限られ、意思決定に関して市民に開かれているわけではない。
当然のことながら、渋谷駅の問題は地元だけで扱う問題ではなく、東京という都市全体にかかわる広域の社会的共有資本だ。もし本気で公共性を導入するならば、民主的手続きによって、私企業が望む再開発の姿そのものに大きく変更を掛けることができるルートが用意されなければならない。しかし、渋谷再開発はそのような公共性はもっていない。その運営が民主的ではなく、権限を集中し情報をコントロールしているのに気づくと、用意された「公共性」は事業者が開発を前提とした事業運営するための方便なのだとわかる。権力の所在が資本に移行している。が、卓越した都市空間を生み出すために権力集中もひとつの方策なのかもしれない。この巨大再開発の評価は2027年の完成まで待つしかない。渋谷駅再開発はパリ大改造のように出来上がった時に卓越した都市空間は出現するのだろうか。
ターミナル駅の緊急整備??
しかしそもそも、なぜ渋谷駅周辺地域が「特定都市再生緊急整備地域」に指定されているのか、どのような問題があって「緊急」に整備する必要があったのか、私にはわからない。渋谷駅は東横線、井の頭線、銀座線、かつては玉川線、という分散する私鉄のターミナル駅であった。ターミナル駅は初めての人にもわかりやすく、普通と急行が選べて、座っていくこともできる。それぞれのターミナル間が離散しているので、人々は街に出てバラバラなルートを歩き、街を楽しむ。そんな余剰の時間も渋谷の都市空間を経験する身体図式として持っていた。
東横線が地下化されて副都心線と繋がったのは、利用者の利便であるよりは乗車客の獲得にあったのではないか。緊急整備?された地下駅は私にはわかりにくい。さらに問題なのは渋谷が通過駅になってしまったことである。ターミナルとは終着駅なので、渋谷という街は目的地であったことを失っている。もうひとつ、渋谷は谷底にあるので「地下鉄の銀座線が空中にある」というのも渋谷の魅力なのだが、これは都市空間の中空に明示される終着駅舎が出現し、この魅力を強化していて救われる。
この駅舎を見ていると渋谷駅の「緊急整備」とは既存の駅舎の整備だけで良かったのではと思う。多くの市民が発言できる民主的な手順がとられていれば、これほどの大仕掛けな再開発工事は必要ないという判断もあったかもしれない。駅舎の整備だけ行うのであれば了解できるのだが、高層部分を見上げると怒りがこみ上げる。そして空中レベルで歩行者ネットワークがつくられ、歩くルートが明快にされるようだが、スリバチの地形的魅力は大丈夫か。
かつて、渋谷はターミナル駅の結節した都市のノードであり、そこから街に出ると谷底にあるという感覚、高低差のある地形的特性が迷宮のような都市空間をつくり複雑なセミラチスを実体化していた。80年代には何かを表現したいという諸施設がそんな地形に貼り付いて、小規模資本の店舗や小屋がインフォーマルに集まって、まるでセドリック・プライスの「ファン・パレス」が都市にばら撒かれているような街だった。ジャンジャンやDIG、ブラックホーク、フロムダンスを知っているか? 再開発によって地形的特性は希薄になり、計画された目的空間をつなぐ街になってしまうのではないか、と気になる。この街の行方は誰が決めているのか?

エミール・ゾラは『居酒屋』のなかで、モンマルトルの労働者街を切断するマジェンタ通りの工事現場を描写し、解体工事によって通りに光が差し込む様を報告している
(出典::Xavier Lefebvre et al., “Paris, la Ville à remonter Le Temps”, StudioCanal (DVD), 2012)

(つづく)
連載記事一覧