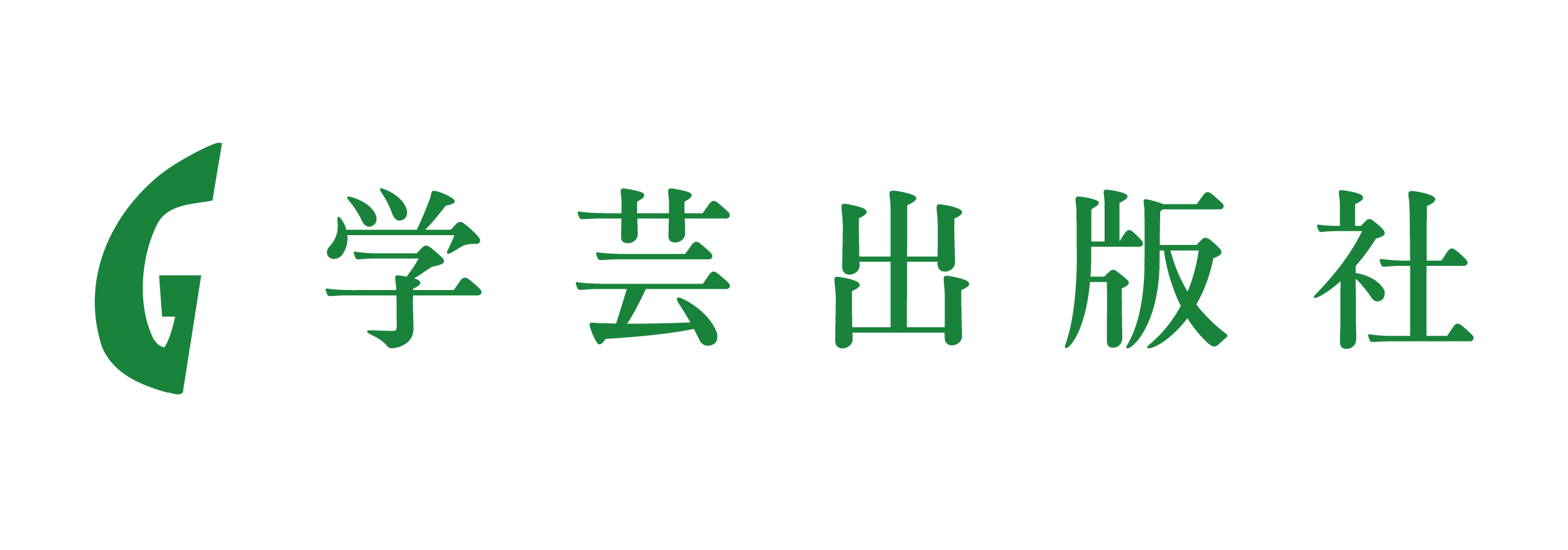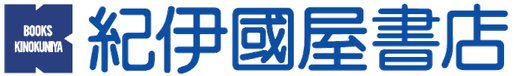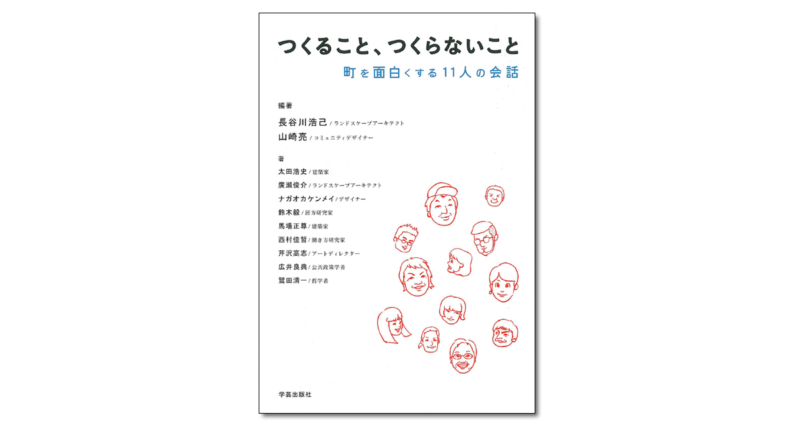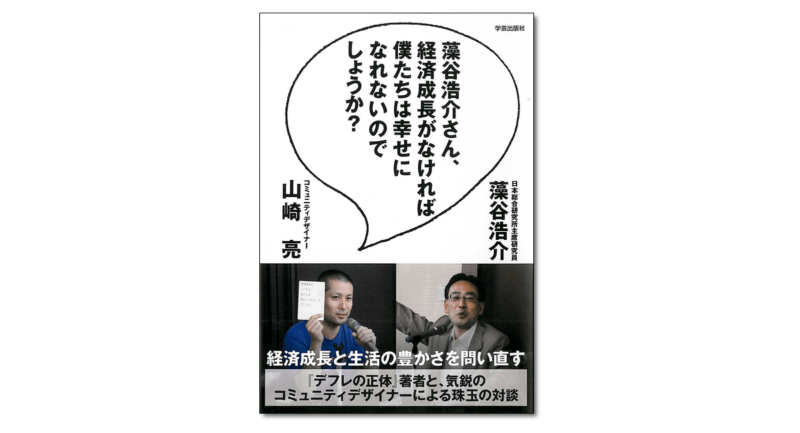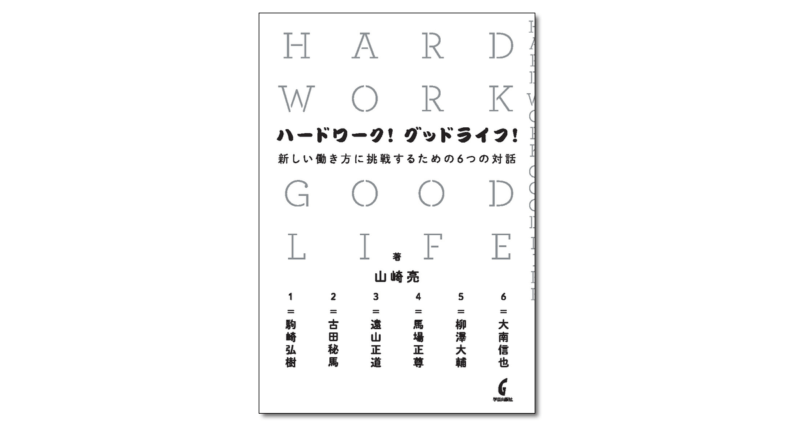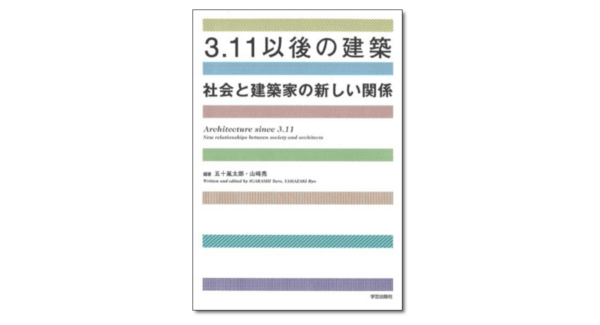コミュニティデザイン

しくみづくりの達人が仕事の全貌を書下ろす
当初は公園など公共空間のデザインに関わっていた著者が、新しくモノを作るよりも「使われ方」を考えることの大切さに気づき、使う人達のつながり=コミュニティのデザインを切り拓き始めた。公園で、デパートで、離島地域で、全国を駆け巡り社会の課題を解決する、しくみづくりの達人が、その仕事の全貌を初めて書き下ろす。
山崎 亮 著
| 体裁 | 四六判・256頁(カラー16頁) |
|---|---|
| 定価 | 本体1800円+税 |
| 発行日 | 2011-05-01 |
| 装丁 | 藤脇 慎吾 |
| ISBN | 9784761512866 |
| GCODE | 5389 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| ジャンル |
ログイン
新規登録
Part1 「つくらない」デザインとの出会い
1 公園を「つくらない」 有馬富士公園(兵庫 1999-2007)
2 ひとりでデザインしない あそびの王国(兵庫 2001-2004)
3 つくるしくみをつくる ユニセフパークプロジェクト(兵庫 2001-2007)
Part2 つくるのをやめると、人が見えてきた
1 まちににじみ出る都市生活 堺市環濠地区でのフィールドワーク(大阪 2001-2004)
2 まちは使われている ランドスケープエクスプローラー(大阪 2003-2006)
3 プログラムから風景をデザインする 千里リハビリテーション病院(大阪 2006-2007)
Part3 コミュニティデザイン──人と人をつなげる仕事
1 ひとりから始まるまちづくり いえしまプロジェクト(兵庫 2002-)
2 1人でできること、10人でできること、100人でできること、1000人でできること 海士町総合振興計画(島根 2007-)
3 こどもが大人の本気を引き出す 笠岡諸島子ども総合振興計画(岡山 2009-)
Part4 まだまだ状況は好転させられる
1 ダム建設とコミュニティデザイン 余野川ダムプロジェクト(大阪 2007-2009)
2 高層マンション建設とコミュニティデザイン マンション建設プロジェクト(2010)
Part5 モノやお金に価値を見出せない時代に何を求めるのか
1 使う人自身がつくる公園 泉佐野丘陵緑地(大阪 2007-)
2 まちにとってなくてはならないデパート マルヤガーデンズ(鹿児島 2010-)
3 新しい祭 水都大阪2009と土祭(大阪・栃木 2009)
Part6 ソーシャルデザイン──コミュニティの力が課題を解決する
1 森林問題に取り組むデザイン 穂積製材所プロジェクト(三重 2007-)
2 社会の課題に取り組むデザイン +designプロジェクト(2008-)
「コミュニティデザイン」とは聞き慣れない言葉かもしれない。新しい言葉を生み出したような響きがあるかもしれない。ところが、この言葉はすでに1960年ごろから使われていた。ただし、その意味は現在のものと少し違っていた。
50年前の日本で使われ始めた「コミュニティデザイン」は、主にニュータウン建設の過程でよく登場した。ニュータウンには、互いに結びつきのない人々が全国から集まってくる。こうした人たちが集まって暮らすなかで、良質なつながりを生み出すためにはどんな住宅の配置にすればいいのか、みんなで使う広場や集会所をどうつくればいいのか、ということを考えたのがかつてのコミュニティデザインである。このころ、コミュニティ広場やコミュニティセンターという言葉が盛んに使われた。みんなが共同して使う場所があれば、きっと自然に人々のつながりができるだろうという発想である。だから、当時のコミュニティデザインは住宅地を計画することを意味した。ある地区を設定して、その物理的な空間をデザインすることがコミュニティデザインだったのである。
一方、本書で取り扱うコミュニティデザインは住宅の配置計画ではない。50年の間に多くの住宅地がつくられた。計画的な住宅地もあるし、無計画な住宅地もある。一方では、昔ながらの中心市街地もあるし、中山間離島地域の集落もある。このいずれもが良質な人のつながりを失いつつある。100万人以上いるといわれる鬱病患者。年間3万人の自殺者。同じく3万人の孤独死者。地域活動への参加方法が分からない定年退職者の急増。自宅と職場、自宅と学校以外はネット上にしか知り合いがいない若者。その大半は一度も会ったことのない知り合いだ。この50年間にこの国の無縁社会化はどんどん進んでいる。これはもう、住宅の配置計画で解決できる状態ではない。住宅や公園の物理的なデザインを刷新すれば済むという類の問題ではなくなっている。僕の興味が建築やランドスケープのデザインからコミュニティ、つまり人のつながりのデザインへと移っていったのは、こんな問題意識があったからだ。
もちろん、ある日突然こうした問題意識に目覚めたわけではない。建築やランドスケープのデザインに携わりながら、「それだけでは解決できない何か」が少しずつ見えてきて、それが僕の中で無視できない大きさにまで膨らんできたのである。その結果、僕は設計事務所を辞めて独立した立場で仕事をするようになった。
だから僕はこの本を同じようなことを感じているデザイナーに読んでもらいたいと思っている。建築や公園を設計するだけでは解決できない課題(でも解決すべきだと感じる課題)を見つけてしまった人。「デザインにできることは売れる商品をつくること以外にもあるんじゃないか」という想いに蓋ができなくなっている人。デザイナーだけではない。行政や専門家だけが社会的な課題を解決しようとしても限界があることを実感している人。自分たちが生活するまちに貢献したいと思っているけど何から始めればいいのか分からない人。こういう人たちに本書を読んでいただき、人がつながるしくみをつくることの大切さを感じ取ってもらえれば幸いである。
都市計画やまちづくりの専門家の間では、コミュニティデザインという言葉が50年前の響きを持っているかもしれない。英語では、新しい意味でのコミュニティデザインのことを「コミュニティディベロップメント」あるいは「コミュニティエンパワーメント」と呼ぶらしい。確かに意味としては正しそうだが、いずれも日本語だと舌をかみそうな名称だ。「コミュニティデザイン」のほうがすっきりしているし、意味が通らぬわけでもない。重要なのは、かつてのコミュニティデザインが持つ印象を刷新するくらい実効性の高いプロジェクトをどんどん生み出し、コミュニティデザインという言葉の意味を自ら育てることだろう。
ランドスケープデザイン、コミュニティデザイン、ソーシャルデザイン。本書に登場するデザインはいずれもその守備範囲が広い。とてもひとりでデザインできる対象ではない。例えばランドスケープ、つまり風景は誰かひとりの手によってデザインされるものではない。コミュニティにしてもそうだ。いわんや社会をやである。
だからこそ、それらについて語ろうとする本書には、著者のほかにさまざまな人物が登場する。人名や注釈が多い点については、著者の作文能力不足が最大の理由だが、一方でそれがコミュニティデザインを語る上での特徴だとご理解いただければ幸いである。
前置きはこの辺にして、さっそく本文を読んでいただきたい。
コミュニティに興味を持った理由はいくつかあるが、そのひとつは確実に阪神・淡路大震災の経験だ。当時学生だった僕は、震災直後に現地へ入り、神戸市の黄色い腕章を巻いて現地を踏査した。全壊、半壊、部分壊を判断し、白地図に色を塗るのが役目だ。僕が担当したのは住吉区。細かい判断は必要ない。ほとんど赤鉛筆しか使わなかった。見渡す限り全壊なのである。地図上に存在する道路が判別できず、暗澹たる気持ちで川沿いを歩いていると、そこに被災者たちが集まっていた。みんなが協力して食事を作っていた。こどもを亡くした夫婦が親を亡くした家族を励ましていた。このときほど人と人とのつながりに気持ちを救われたことはない。瓦礫と化した神戸のまちに人のつながりが残っていて、そこから生活再建の芽が育っているような気がした。コミュニティの力強さを感じた。
本書の原稿を書き終わる頃、東北地方を巨大な地震が襲った。いろんなことを思い起こして原稿を書く手が止まった。原稿執筆よりもやるべきことがあるのではないかと悩んだ。しかし同時にコミュニティの力を信じた頃の自分を思い出した。こんなときだからこそ、コミュニティデザインに関する原稿を書き上げるべきだと自分に言い聞かせた。
被災地の道路や住宅はいずれ復旧するだろう。同じ場所にまちをつくるべきかどうかは検討の余地があるものの、ハード整備はそれなりに進むだろう。同時に考えておくべきなのは人のつながりだ。阪神・淡路大震災では、避難者数に対して仮設住宅の数が圧倒的に少なかった。だから高齢者や障がい者が優先的に入居した。人道的な判断だったといえよう。しかし、高齢者や障がい者は周辺に住む家族たちとつながっていたのである。夕食のおすそ分けや縁側での世間話などによって生活が支えられていたのだ。こうしたつながりが断ち切られ、高齢者や障がい者だけが集まった仮設住宅で、震災後3年の間に200件以上の孤独死が発生してしまった。
非常時には人のつながりが大切になる。言うまでもなく、それは平常時から手入れしておくべきものだ。災害が起きた後、仮設住宅を建てるように効率よく人のつながりを構築することはできない。日々のコミュニティ活動が大切なのだ。だからこそ、いまコミュニティデザインに関する書籍を世に問うべきだろう。そう考えて原稿を最後まで書き上げた。
そんな気持ちを感じ取っていたのか、編集者の井口夏実さんはいつになく原稿催促が穏やかだった。井口さんとは、僕が初めて書籍に文字を載せたときからの付き合いだからもうすぐ10年になる。初めての単著を彼女とつくることができたのはとても嬉しい。また、この本づくりを強力に後押ししてくれた学芸出版社にも感謝している。
データや図版の整理ではstudio-Lのメンバーに手数をかけた。特に、醍醐孝則と西上ありさには各プロジェクトのデータを整理してもらい、神庭慎次、井上博晶、岡本久美子には図版を整理してもらった。記して感謝したい。
東北の復興にコミュニティデザインが必要なのは言うに及ばず、無縁社会化する全国の地域にも人のつながりが求められている。非常時のためだけでなく、日常の生活を楽しく充実したものにするために。信頼できる仲間を手に入れるために。夢中になれるプロジェクトを見付けるために。そして、充実した人生を送るために。
本書がそれぞれの地域に新たなつながりを生み出すきっかけとなるとすれば、著者としてこれほど嬉しいことはない。
コミュニティデザイナー、山崎亮氏の活動報告書である。本書の全体が今日の山崎亮氏、あるいはStudio-Lの活動がいかに形づくられたのかを記録するセルフ・ドキュメンタリー的な雰囲気を持っている。公園のデザインや小さな街の総合計画、地方都市のデパートの再生など、プロジェクトごとにドラマがあり、話し合いを続け、解決策を練っていく過程で、コミュニティも、山崎氏も、周囲のスタッフも、少しずつ成長していく様子が活き活きと描かれている。都市やコミュニティ、建築や造園に関わる人たちは、本書を通じて山崎氏が格闘してきた現場の臨場感や達成感を味わい、氏のパーソナル・ヒストリーを追体験することができるだろう。
山崎氏の自分語りふうにまとめられた本書ではあるが、プロジェクトの様々なドラマの背景を読みこんでいくと、山崎氏はやはり時代の申し子なのだと思う。氏は1973年という団塊ジュニアのピークに生まれ、転校生として全国を転々としつつ育ち、1995年の阪神大震災の経験を転機にコミュニティに関心を持ち、やがてコミュニティデザインという職能に出会う。そのプロセスは、1970年代という開発主義絶頂の時代からポストモダン的な価値の多様化へ、さらに1995年という転機を経て地方分権とともに地方都市のコミュニティがクローズアップされる時代へと至る、日本社会全体の大きな変化のプロセスと完全にシンクロしている。つまり、本書は山崎亮というひとりのデザイナーの歴史であると同時に、時代を語る本でもある。
ただし、意外と読み方の難しい本でもある。本書では「コミュニティデザイナー」という職業がどのようなかたちで機能しているかというロールモデルは示されているが、誰もが使えるようになるような、いわゆる方法論としては何も示されていない。また、「コミュニティデザイナー」の明確な定義とか、歴史的な位置づけ、批判的な検討など、いわゆる理論的な部分もない。つまり、これを読んだ人がどんなに山崎氏の活動に共感してコミュニティデザイナーを志したとしても、実際にその夢を果たすための具体的な道筋は示されていない。先輩の合格体験記を読んでも志望校に受かるための勉強にはならないのと同じで、本書はコミュニティデザインの体験記ではあっても、教科書ではない。
本書の後、山崎氏は多様な実践を重ねるとともに自らの職能を理論的に位置づけ、方法論を明らかにする、つまり、教科書を書くという段階に進むだろう。もちろん、山崎氏も推薦書に掲げる『まちづくりの方法と技術 コミュニティ・デザイン・プライマー』(ランドルフ・T.ヘスター/土肥真人, 1997)など、先行例は豊富にあるので、私たちが山崎氏の手によるコミュニティデザインの「教科書」を手にするのも時間の問題であろう。それが編まれていくプロセスで、なぜ今の日本にソーシャルデザイナーが必要なのか、コマーシャルなデザイナーとソーシャルデザイナーの違いは何か、どのようにすれば実際にソーシャルデザイナーの職能を拡大できるか、より多くの議論が巻き起こっていくだろう。
山崎氏の提唱する「コミュニティデザイナー」を目指すにせよ、異なる職業を目指すにせよ、山崎氏と同じ時代に生きる私たちにとって、本書が今という時代をつかみ、デザイナーという職能、あるいはデザインの役割の今後を考える上で大きなヒントになることは間違いない。若い世代には特に読まれたい。ただし、合格体験記と同じく、読み方には気をつけられたい。
(建築家・東洋大学専任講師/藤村龍至)
担当編集者より
昨年末から始まった山崎さんとの本づくりは、短期集中型のスリリングな体験でした。
「今までのまちづくりの本とは違うものにしたい」「(僕の仕事の)どこが面白くて、どこが面白くないかを聴かせて欲しい」と何度となく問われ、それに応えるうちに、目次や口絵諸々、本の形がはっきりしてきました。やりとりをし続けた数ヶ月、とても楽しかったです。
装丁は、「コミュニティデザイン 山崎亮」と、著者名までがタイトルに見えるものを目指したのですが、実際、この著者だからこその内容が語られていると思います。シンプルで印象的なフレーズも、几帳面な不断の観察があってこそ力を持つ。地域との地道な関わりを大事にする山崎さんの仕事ぶりが伝えられていれば嬉しいです。
(Ino)
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。