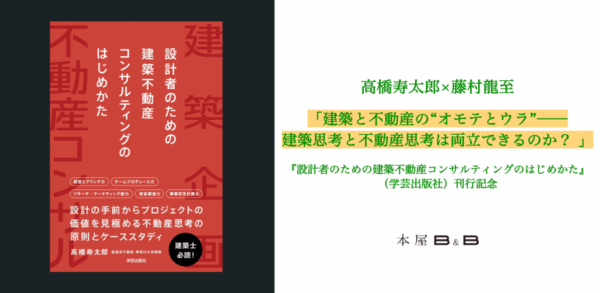設計者のための 建築不動産コンサルティングのはじめかた

真に事業主に愛される建築を生み出す企画力
今、設計者に求められるのは不動産コンサルの視点を踏まえた、設計の前段階での建築企画力=「建築不動産コンサルティング」だ。建築デザインと不動産を掛け合わせた集合住宅や店舗、オフィス等の事業用建築を実践例に、その方法論を解説。真の建築/事業企画を提案し事業主に愛される建築を生み出すためのロードマップ。
高橋 寿太郎 著

ログイン
新規登録
プロローグ 「設計の前段階」ですすみゆく変革
あいだの「壁」はいまだに残る
「建築企画」と「不動産コンサルティング」のあいだ
設計者にとっての明らかな転換点
これからの総合窓口は誰なのか?
自らの専門性を再定義するために
「設計の前段階」の様相を俯瞰せよ
1章 なぜこれからの建築に不動産思考が必要なのか ―建たない時代に抗う、あるいは抗わない方法
1‒1 インフレ時代の地殻変動はどこで起きているのか?
30年ぶりのインフレーションの行く先
まずは海外のインフレを振り返る
資金調達難が建築計画数を減らす
建たない時代の建築家たちによる無数の胎動
さらに進化を求めるビジネスモデル
図面を描くだけでは完結しない建築プロジェクト
1‒2 事業主側でプロジェクト実現のカギを探せ
新中間層がいなくなる?
ダブルインカム世帯がつくっていた住宅需要
デフレ・低金利・新中間層
建築の「起こり」への解像度を高める
1‒3 「事業主の時代」に求められること
事業主である不動産オーナーに向き合う
アパートを建てたいオーナーにヒアリングをする
築古ビルのリノベオーナーの「資金調達」に向き合う
店舗を出したいオーナーの「立地」に向き合う
中規模な企業の「経営」や「マネジメント」に踏み込む
1‒4 「建築と不動産のあいだ」にある壁とチャンス
隣あわせだけどまったく異なる二つの領域
多数の小さな会社による市場分散型市場
互いの誤解や偏見こそが壁を生む
結局、損をしているのは建て主だ
事業系プロジェクトの「建築と不動産のあいだ」
1‒5 不動産コンサルティングの技能と歴史
「設計の前段階」で活躍する多様なスペシャリストたち
高度成長期~バブル期 売り込み型の建築企画
不動産コンサルティングの仕事と資格
バブル期に生まれた不動産コンサルティング会社
混ざり合うことで危機を乗り越える
地方へと視線を向ける必然性はあるのか?
1‒6 お金や不動産や事業はデザインできる
多品種少量生産業界で戦略をつくる方法
領域を「拡大すること」と「特化すること」は矛盾しない
あくまで多角経営ではなく集中戦略をめざせ
2章 クリエイティブな建築不動産コンサルティングの方法論 ―事業系プロジェクトを動かす設計者のイニシアチブ
2‒1 事業系VFRDCM
メンタルブロックを越えて読み進める
建築不動産コンサルティングのトライアングル型
建て主のための建築不動産フロー「VFRDCM」とは
設計の前段階で大切な、事業系のV・F・R
企画で陥りがちなミスを回避するための道筋
2‒2 事業系V(ビジョン)フェーズ
事業主のお客さまとライバルを特定せよ
「未条件」を発見しよう
バリューチェーンを図示してみよう
プロジェクトの羅針盤となるロードマップ
チームメンバーのプロデュース
2‒3 事業系F(ファイナンス)フェーズ
ひたすら聞く ―お金についてのヒアリング術
お金に苦手意識がある本当の理由
土地があっても借りられない?資金調達の常識
お金が潤沢にあれば大丈夫?資産マネジメントの基礎知識
建築費用だけではなく事業費用をトータルに説明せよ
事業のキーパーソン ―銀行と税理士
最低限必要な収支計画書を読む知識
類似事例ではなく普通の競合物件を巡るツアーの意味
2‒4 事業系R(不動産)フェーズ
少し異なる建築と不動産のエリアリサーチ
半径500mのすべての道や路地を実際に歩け
「うまくいく事業を提案してくれないか?」
みんなが言う共通認識を発見し、それだけはやるな
ペルソナ待ち、でもやってこない
床面積を最大限確保しなければならない時代ではない
設計要綱で事業の戦略を描き尽くす
2‒5 事業系D(設計)・C(施工)・M(マネジメント)フェーズ
建築設計に集中しているあいだにやるべき三つのこと
設計の決まりきったワークフローを疑おう
「伝える仕組み」を建築プロジェクトに組み込め
運営に参加する本当の理由は、企画にもどってくるため
ローカルに参入するのは将来のため
2‒6 建築不動産コンサルティングの契約と見積り
不動産コンサルティング業務委託契約書
不動産コンサルティングの見積書
設計の前段階で建築と不動産のあいだの壁を超えよう
3章 建築家×不動産コンサルタント 四つのケーススタディ ―無数の「問い」がひらく設計者の選択肢
ケーススタディ1:イマケンビル ─建て替えか?リノベーションか? 築55年の空きビルを再生させる
カフェ×ランドリー空間=「?」
築古一棟リノベーションの「建築的」な課題は検査済証
築古一棟リノベーションの「不動産的」な課題は資金調達
知名度がない「森下」
建築家のビジョン・まちの記憶・オーナーのリーダーシップ
感性だけでは実現できない
子どもたちと地域に託す
店舗にするなんてとんでもない!
グランドレベルの「1階づくりはまちづくり」
ランドリー需要は確かにある
ケーススタディ2:REDO神保町 ─古書の町でどんな企画を? 再生のプロフェッショナルたちの協力体制
神保町での新たな挑戦
神保町の現実を知る
耐震補強の専門家からの依頼
再生建築を担う若手建築家
先入観を捨てて真のニーズを探る
事業主の事業目的から捉えなおす
実行可能な事業案
独自性を持つ空間の創造、再生建築のデザインアプローチ
企画と設計と施工の一体化
再生の突破口は?
ケーススタディ3:オーレック・グリーンラボ ─設計要綱に書くべきことは? 良いプロジェクトにするための十分条件
企業理念を体現するデザインを考える
機械メーカーから、食と農をまもる企業へ
ショールームと営業所を兼ねた、ブランド発信拠点をつくる
発注側にプロジェクトを束ねる人材が必要
長野の「アップルライン」沿いに見つけた土地
建築家の答えは、情報を共有する場でいきなり生まれた
つくり込みすぎず、情報共有のための環境をつくる
全国へ展開していく設計思想
答えのない企画中のプロジェクト三題
ケーススタディ4-A 敷地を広げるために買い増しすべきなのか?
都市の住宅地は、小さくなっていくしかないのか?
建築で「都市」にどう向き合うか?
事業主と建築家のビジョンは住まい手を選ぶ
ケーススタディ4-B 保存か?再生か?歴史的建築物のコンサルティング
築90年の木造モダニズム建築「三岸アトリエ」
関係者が注目する保存活用
蘇らせていくチームビルディング
ケーススタディ4-C 巨大な築33年SRC造ビルを、どう生まれ変わらせる?
スピードとバランスが求められる「サウンディング」
未条件から新たな軸が現れる
様々な問いに総合的に向き合い、決断する
参考文献
エピローグ
索引
「設計の前段階」ですすみゆく変革
「建築と不動産のあいだには壁がある。しかし、建て主にとっての本当の価値は、そのあいだに隠れている――」
私が不動産コンサルタントの立場から、業界の構造や商慣習を多面的に触れた書籍『建築と不動産のあいだ』を2015年に出版してから、はや10 年が経ちました。
果たして、そんなテーマに関心を持ってくれる人がいるのかどうか、当時はまったく予想もつきませんでした。しかし、日本中の建築と不動産の専門家たち、中でも建築設計事務所のみなさんに支えていただき、刊行後、多くの方に読まれ、版を重ねることができました。
そしてこの10年間は、私たちも含めた日本各地の多くのプレイヤーが、その「壁」を跳び越えようとする実践を積み重ねてきたのです。
あいだの「壁」はいまだに残る
かつての、建築設計は建築設計、不動産は不動産と、明確に分業されていた時代から、近年では住宅、店舗、オフィスといった用途を中心に、建築と不動産を一体的に捉え、企画やデザインが統合的に進められる実践が、全国で広がっています。両者を混ぜ合わせて、もしくはそれぞれの専門家がタッグを組んで、新しい価値を生み出していくことの可能性を、目の当たりにしてきました。
基礎的な技術や根本的な価値観を、建築と不動産の双方が互いに理解し合い、協働して建て主に貢献する。そうすることで建て主が得る価値、成果、そして利益の大きさ。その可能性を、私は様々な現場で伝えてきました。そして確かな成果が少しずつ形になってきたと感じています。
だからこそ、こうした実践をもっと広げていきたいのです。むしろ日本は、「小規模な建築と不動産のチームがうまく連携し、力を発揮している国なのだ」と諸外国から参考にされる存在になっていける、私はそう考えています。
ただし、そうした協業がすでにスタンダードになったかというと、おそらく全体の1%にも満たないでしょう。建築と不動産のあいだには、依然として決定的な「壁」が存在しており、特に中小規模の事業者において、その傾向は顕著です。
この業界は「市場分散型」で、大手による寡占化が進みづらいという特性があるため、構造的に建築と不動産のあいだの溝が埋まりにくいのです。
しかしいま、様々な経営環境の変動を背景に、その「あいだ」に新たなターニングポイントがやってきました。それが一体どのようなものであり、なぜいま起きているのか。それは本書を読み進めていただければ、はっきりと見えてくるはずです。
「建築企画」と「不動産コンサルティング」のあいだ
「寡占化されない市場分散型の業界」をポジティブに捉えるならば、建築設計業界には、大手企業だけではなく、小規模、または個人の設計者が日本各地のエリアに存在し、地域住民や企業にとっては、相談できる窓口が多数ある、ということでもあります。建築設計から建物に関わる日常的な相談まで、対応できる人が身近にいるという状況は、日本ならではの良さだと、私は感じています。
確かに海外と比較し、また他の士業に比べると、日本には設計者の数が非常に多く、競争が激しく感じられ、「持続的に稼ぐのが難しい」とネガティブに捉える意見も聞かれます。ですがその一方で、設計者が身近だからこそ「設計の前段階」からプロジェクトに関わることが増えている、という実感があります。
ここで改めて、建築と不動産の「あいだ」をよく見てみましょう。本書が扱うのは、集合住宅や商業施設、企業のオフィスといった、事業系建築の「設計の前段階」です。そこに位置する、「建築企画」と「不動産コンサルティング」という二つの領域を結びつけるための方法論です。
本来、この二つは突き詰めればかなり似通った領域です。にもかかわらず、なぜこれまで同時に語られてこなかったのか。その理由は、いまだ明らかにされていません。ただ、両者のあいだには確かに「壁」が横たわっています。
そしてこれらが結びついた職能、またはチーム、あるいは横断的にプロジェクトを成功に導こうとする意思を持つ者を、本書では「建築不動産コンサルタント」と呼んでいます。これが本書のテーマです。
聞きなれない方には、やや難解な専門技術のように感じるかもしれませんが、決してそうではありません。新しい技術が発見されたわけではなく、10年前と変わらず、やはり「すでにあるものを角度を変えて見ている」だけのことなのです。
つまり、建築設計と不動産取引、それぞれのごく基本的で当たり前のことについて、少し視点を変えるだけで、これからの時代に必要とされるスキルとして、実務に生かせるようになります。
設計者にとっての明らかな転換点
21世紀が四半世紀過ぎ去ったいま、設計事務所は大きな転換点に立たされています。これまでの新築住宅ニーズは減少し、マンションのリノベーションも減少、そして様々なプロジェクトが「企画段階」でストップする、という状況が頻発しているのです。こうした事態は、設計事務所の存続そのものを揺るがすほど深刻です。
一方で、都市部の中~大規模の設計事務所やゼネコンでは、インフレーションをものともせず大規模再開発の受注は継続しているものの、人材不足や流出により、案件の継続や遂行が難しくなるという別の課題が顕在化しています。
こうした不安定な状況の背景には、設計事務所を取り巻く経営環境の激変が、現在進行形で進んでいることがあります。設計事務所のビジネスモデルの刷新をテーマに論じた『建築と経営のあいだ』の刊行からわずか5年の間に、世界は大きく揺れ動きました。
新型コロナウイルスのパンデミックの結果、地球規模でのインフレーションが起こり、ロシア・ウクライナ侵攻やイスラエル情勢の悪化がそれに拍車をかけ、そして円安バブルが起きました。これらが複合的に深刻な影響を与えています。
もともと建設業界は、平成時代から構造的な課題を抱えていました。そこに、さらなる建設費の高騰が加わったことで、住宅建築の需要は大きく後退し、集合住宅や商業施設も利回りが回らず、事業計画が成り立ちません。
さらに空き家が900万戸を越え、空きビルや空き施設を加えると、日本は「使われていない建物だらけの国」として、いよいよ海外にも知れ渡りつつあります。
加えて、経済学や社会学の分野で指摘されるように、日本も欧米の後を追い、格差社会が本格的に拡大していくことが予測されます。つまり、設計事務所の経営環境が変わるのは、まだまだこれからが本番なのです。
その変化を「難しい障壁」と捉えるのか、それとも「千載一遇のチャンス」と捉えるのか。本書では、その分かれ道に立つ感覚を養っていただきたいと考えています。経営理論の視点から見れば、自らが置かれた外部環境に対してどのようなスタンスを取るのか、それこそが、経営戦略の第一歩なのです。
これからの総合窓口は誰なのか?
「設計の前段階」に視点を戻すと、現在、プロジェクトマネージャー、コンストラクションマネージャー、事業プロデューサー、クリエイティブディレクター、経営コンサルタント、そして不動産コンサルタントといった様々な前段階のプレイヤーが、台頭しています。
彼らは、建築事業が当たり前に成立しない時代に、既存市場や新しい市場で、従来の設計事務所では実現できなかった「価値提供」を実現しようと試みています。
しかし、この建築設計の前段階は、まだ確立された方法論が存在せず、混沌としていると言っていいでしょう。本書はそこをくわしく深堀りしています。
また事業主が「建物を建てたい」と思ったとき、最初に誰に相談してよいかわからない、という話をよく聞きます。不動産会社に相談すればよいのか、銀行などの金融機関か、税理士または中小企業診断士か、あるいは設計事務所なのか、と。いまだに、最初の一歩を踏み出すための相談先が整備されていないのです。
ここでのポイントは、設計事務所と不動産コンサルタントが、そのあいだの壁を越えタッグを組み、プロジェクトの企画段階から「総合的な相談窓口」として機能すると、事業主にとって大きなメリットになるということです。
さらに、新たなオフィスや店舗をつくることは、事業主にとってワクワクする未来に向けた取り組みである一方で、慎重に進まなければならない、危ない橋渡しでもあり得ます。
設計事務所と不動産コンサルタントが、領域の壁を越えて組むことは、事業主にとって偏りの少ない、より機能的なチーム編成を可能にします。それにより、事業主のリスクを低減し、プロジェクトのパフォーマンスを高めることができます。
自らの専門性を再定義するために
設計事務所にとっても、このタッグは大きな可能性があります。本書のテーマの一つでもある「設計の前段階」、つまり建築の与条件をつくるところから業務が開始される、ということは大きなメリットです。
また、単なる受託待ちの状態ではなく、前述したような異なる専門家との連携を経験する中で設計の前段階で、積極的に事業主の事業自体をコンサルティングしていく能力が磨かれていくでしょう。
さらに、他業種との連携は、設計事務所が過去の業界慣習によらず、自らの専門性を再定義することが可能になります。それが何よりもメリットかもしれません。
不動産コンサルタントにとっても、建築設計事務所と連携することは、仕事をする上での戦略的価値を高めます。本書は、不動産コンサルティングの視点や方法論を建築設計業に従事している方々に紹介するものですが、逆の意図もあります。
不動産業界では、この令和の時代になっても、まだ建築設計事務所の技術や能力が、十分に理解されていない実情があります。
だからこそ、ものづくりやクリエイティビティ、そして地域文化の理解を強みにする建築設計事務所とタッグを組むことで、不動産コンサルタントも、より地域に根差し、社会的価値のある存在に近づくことができるでしょう。
言い換えれば、設計事務所と不動産コンサルタントは、その壁を越えて互いに補完しあう親和性を持ったパートナーになれることは、もはや間違いありません。
「設計の前段階」の様相を俯瞰せよ
これらを総合して、本書は、『建築と不動産のあいだ』(2015)の続編と言えますし『建築と経営のあいだ』(2020)を加味した、完全版とも言えます。
『建築と不動産のあいだ』では、主に住宅土地の「売買仲介」と「建築設計」が連携するケースが扱われていましたが、本書『設計者のための 建築不動産コンサルティングのはじめかた』では、集合住宅、自社オフィス、商業施設など、「事業系建築」において、建築家と不動産コンサルタントが、どのようにして価値を生み出していくのかを、以下の順番で論じています。
1章「なぜこれからの建築に不動産思考が必要なのか ―建たない時代に抗う、あるいは抗わない方法 」では、なぜいまこの本を建築設計業界に従事している方々に読んで欲しいのか、その理由と時代の移り変わりについて書いています。不動産コンサルティングの必要性が増している時代背景と変化を、多面的に分析し、論じています。
2章「クリエイティブな建築不動産コンサルティングの方法論 ―事業系プロジェクトを動かす設計者のイニシアチブ」では、実務での具体的な方法論について書いています。実務で陥りがちな落とし穴を多数テーマにし、具体的にイメージしやすく、感覚的に習得できるようにしました。さらに本書の一つのゴールである「建築企画」と「不動産コンサルティング」を融合させた「建築不動産コンサルタント」については、ここで解説しています。
3章「建築家×不動産コンサルタント 四つのケーススタディ ―無数の「問い」がひらく設計者の選択肢」では、私が経営する創造系不動産が実際に事業主と建築家と共に取り組んだ事例を、当時を振り返り、臨場感をもって紹介をします。
また本書は1章から3章を通じて、単なる知識の集積にとどまらず、実際に行動したいと考える方に向けた、実践のためのロードマップとなることを目指しました。1章では、建築士が、本書で得た不動産コンサルティングの視点や知識を、実務で顧客に提供するための書籍や資格などを紹介し、2章では、創造系不動産が実際に用いている見積書のフォーマットや、不動産業団体による不動産コンサルティング契約書のひな型なども掲載しています。さらに3章では、事例は「答え」よりも、正解のない状況の中で「問い」を立てることを重視した構成になっています。
また本書では、住宅や建築・不動産の実務に携わる建築家や設計士の方々が、全体像をテンポよく把握できるよう、細かな情報、個別の知識、関連図書や動画資料などは、すべて欄外に注釈にまとめて補足的な解説を記載しました。必要に応じて参照するものですので、それらは読み飛ばしても支障ありません。
建築設計の前段階での「建築企画」と「不動産コンサルティング」の融合。その視点と方法を知ったみなさんが、実際のプロジェクトにおいて、異業種の専門家とタッグを組み、より社会的価値を高め、事業主に愛される建築を生み出していく。その一助になることができれば、著者としてこの上ない喜びです。
創造系不動産 代表取締役 / 神奈川大学建築学部 教授
高橋寿太郎
「建築企画」という領域がもつ魅力は、1980年代から変わらず、それはときにおぼろげでつかみどころのないものに感じられながらも、建築設計に携わる人々を長年にわたって惹きつけてきました。一方で、私たちが日々実務として取り組む「不動産コンサルティング」という領域は、建築設計から見ると、より泥臭く、別次元にあるようにも映ります。偶然の出会いでもなければ、仕事として関わることすらありません。
しかし、もしこの二つが時代とともに接近し、気付けば「すでにほとんど同じもの」になっていたとしたら――。本書を執筆するきっかけは、そんな小さな発見でした。
設計の前段階へと流れをさかのぼり、同時に建築と不動産を隔てる「壁」を越えていくと、その先には、両者が融け合った世界の景色が広がっています。それを事業主のために、そして自分たちの建築のために見つけ出すことができれば、建築と不動産の未来は確実に変わるはずです。
1章で紹介したイノベーターたち、そして本書で紹介しきれなかった多くの設計事務所や事業主たちは、すでにそれを実現させはじめています。社会が大きく揺れ動くとき、私たちは「変えてはならないもの」を守り抜くためにこそ、「変わるべきもの」を選び取らなければなりません。変化は恐怖を伴い、抵抗も生まれますが、それは後退でも妥協でもなく、次の時代へ進むための一歩なのだと、私は信じています。
そして最後に、本書の執筆に際し、多くの方々からお力添えをいただきました。この場を借りて、心から感謝を申し上げます。
創造系不動産を長年にわたって支えてくださっているエイトブランディングデザインの西澤明洋さん、スタッフの渡部孝彦さん、杉江萌子さんには、これまでの著作に続き、本書でも表紙デザインからすべての図版作成まで、多大なご協力をいただきました。
学芸出版社の井口夏実社長、安井葉日花さんにも、やはりこれまでの著作と変わらず、本書を最後まで温かく導いていただきました。
神奈川大学の浅川果音さん、高橋美莉さんには、3章のケーススタディの執筆で大きな助力をいただきました。創造系不動産の斎藤美冬さんには、膨大な情報の整理と、四十社を越える引用先への内容確認作業で尽力していただきました。
また、その引用を快くご承諾くださった皆さま、そして事例掲載に惜しみなくご協力くださった事業主と建築家の皆さまにも、改めて深く感謝を申し上げます。
さらに私たちの取り組みに共感し、これまでともに歩んできた多くの建築家の皆さま、そして苦楽を共にする創造系不動産のメンバー、創造系OBの仲間たちにも、心から御礼を伝えたいと思います。
本書が、設計事務所の未来を切り拓くための一助となり、皆さんの背中をほんの少しでも押すことができたなら、これ以上の喜びはありません。
高橋寿太郎
※SNS等にて公開投稿されていた読者の皆様のレビューを、埋め込み表示させていただいております。不都合がございましたら、お手数ですがページ末尾のご意見・ご感想フォームよりご連絡をお寄せください。
高橋寿太郎著『設計者のための建築不動産コンサルティングのはじめかた』通読。
建築企画と不動産コンサルティングのあいだを領域横断的に橋渡しする存在を「建築不動産コンサルタント」と定義したことが発明。これまで建築・不動産のあいだで不明瞭だった与条件、未条件をいかに整理するかが肝心。
→ pic.twitter.com/ClVfrLS8oP— 若林 拓哉|Wakabayashi Takuya (@takuya_wakaba) December 1, 2025
創造系不動産の高橋寿太郎社長より
『設計者のための建築不動産コンサルティングのはじめかた』をご献本いただきました。ありがとうございます。最近、個人事務所を経営していると不動産事業者からの「設計なのか企画相談なのか曖昧な案件」が増え、建築と不動産の関係性を強く意識していました。… pic.twitter.com/SfmhJtROWM
— Kiichiro Usami / 宇佐美喜一郎/OFA (@UsamiKiichiro) December 10, 2025
公開され次第、掲載します。
開催前・開催中のイベント

メディア掲載情報
| 日付 | タイトル |
|---|---|
| 2026年2月2日 | 『設計者のための 建築不動産コンサルティングのはじめかた』が「商店建築」(2026年2月号)で紹介されました |
| 2026年1月13日 | 【全文閲覧可】『設計者のための 建築不動産コンサルティングのはじめかた』が不動産投資と収益物件の情報サイト「建美家」で紹介されました |
| 2026年1月13日 | 『設計者のための 建築不動産コンサルティングのはじめかた』が「月刊不動産流通」で紹介されました |
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。