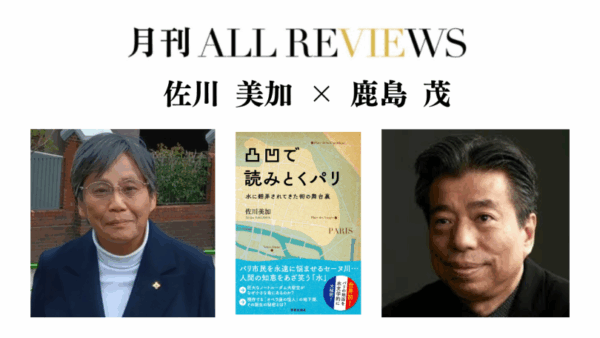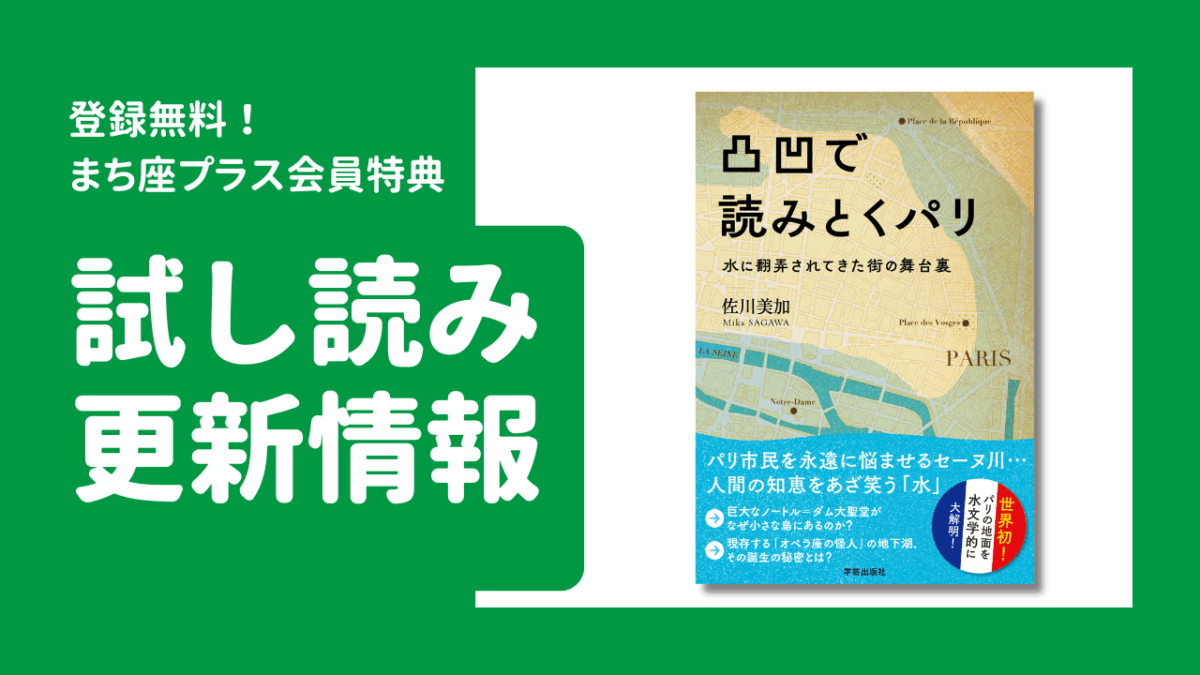凸凹で読みとくパリ

図版約160点を掲載!パリの街がよくわかる!
フランス・パリを「地面の凸凹と水」で読みとく土木史ガイド。具体的状況を示す約160点の豊富な図版とランドマークを紐づけた解説で、実際確認しづらい地面の上と下両方の水の動きがよくわかる。古代から現代までの史実を交え、自然地形や人工構造物がセーヌ川などの水とどのように影響し合い街が変化してきたかを解明する。
佐川 美加 著

ログイン
新規登録
目次
・本書に登場する凸凹が潜むエリア図
・はじめに
・本書の読み方
序章 優雅でなだらかな地形はどうやってできた?
0-1 パリの凸凹を決定づけた太古のセーヌ川
0-2 川と地形を変化させる地上と地中の「水のやりとり」
プラス解説-0 「モンソー」の尾根=「ビュアッシュの分水嶺」
1章 敵の侵略が自然地形を変えた?! 人工改変の始まり
1-1 水の流れを変えたローマ帝国による征服
1-2 シテ島の城砦化でセーヌ川の水位が上昇!
1-3 ノルマン人との攻防で姿を変えた川岸
プラス解説-1 中心軸「7度」のズレの謎
2章 敵去って地固まる?! 地面を変えたセーヌ川の水位差
2-1 上流を潤し下流を乾かす橋と水車
2-2 セーヌ川の流量と水位を一変させたビエーヴル川の付け替え
2-3 地面の乾燥が進んで島の面積拡大! ノートル=ダム大聖堂の建設開始
2-4 湿地を農地に変化させる修道士たちの地道な排水
プラス解説-2 「サンジノサンの墓地」「シャンポーの市場」から学ぶ地表と地下の水の影響
3章 水の流れを変え続ける防衛施設「市壁」
3-1 パリに建設された八つの「市壁」
3-2 敵だけでなく地面を流れる水をも阻んだ「フィリップ・オーギュストの市壁」
3-3 悪臭を放つドブに変わった「エティエンヌ・マルセルの市壁」
3-4 中世ヨーロッパ最大級の濠を持つ「シャルル5世の市壁」
3-5 水質汚染と疫病の蔓延! 市壁に阻まれない排水ルートの確立
プラス解説-3 パリの「市壁」が生み出した直線道路
4章 壁外に積み上がりすぎた「ゴミの山」が建設資材へ
4-1 ジャンヌ・ダルクの陣地は「ゴミの山」!?
4-2 粉挽風車は町を見下ろす丘の上に
4-3 ゴミと排出土を最大限活用した巨大インフラ「フォセ・ジョーヌ」
プラス解説-4 古地図に描かれたゴミ捨て場
5章 国王の都市計画と新しい下水システム
5-1 急速に進む宅地整備とインフラの増強
5-2 市壁撤廃と排水溝ネットワークの再整備
5-3 徴税のための市壁建設と民衆の怒り
6 章 近代都市化の波に削られる天然の凹凸
6-1 広くて平らな馬車道の建設
6-2 「ティエールのバスチオン」と「オスマン男爵の大改造」
6-3 セーヌ川旧河道が生んだ名作「オペラ座の怪人」
6-4 テクノロジーが支えた印象派の水面
終章 再び変わろうとするセーヌ川
おわりに
参考文献
1 パリ市の紋章に船が描かれている理由
図1はフランス国立古文書館に所蔵されている1412年の公文書に残されたパリ市の印章のレプリカである。中央に帆船、その舳先と艫にフランス王室を象徴する百合の花があしらわれている。この水に浮かぶ船を中央に大きく描くデザインは1210年以来、21世紀の現在まで変わっていない。
船が描かれている理由を解き明かすヒントは、周囲に刻まれた文字にある。ラテン語で “SIGILLUM MERCATORUM AQUAE PARISIUS”=「パリの水の商人の印」という意味である。当時、パンの原料の小麦、ワイン、チーズ、野菜やくだもの、そしてパンを焼く薪でさえもパリの上流にあるブルゴーニュ地方からセーヌ川を下ってきた。荷を運ぶ舟(船)、舟が到着する港、港で開かれる市(いち)、市で繰り広げられる取引、これらすべてを取り仕切っていた水の商人組合の力は絶大であり、十字軍から戻ってきた国王ルイ9世は1263年、パリの町の実質的な行政権を「水運業者親方組合」に譲り渡し、セーヌ川を職場とする「水の商人たち」の代表が参事会員に、そして商人頭がその長となった。川岸こそがパリの玄関であり、町の顔だったのである。河岸の一角にあった水運業者親方組合の寄合所は、パリ初の町役場になり、現在はパリ市庁舎になっている。図2は16世紀半ばの「トリュシェとオヨーのパリ図」で、右からセーヌ川、船着き場、広場、町役場(LOSTEL DE LA VILLE)が描かれている。
2 頻繁にあふれるセーヌ川との攻防の歴史
パリの人々にとって唯一の自然災害は「洪水」である。冬、上流で雨が続き、しばらくするとパリのセーヌ川の水面が上がり始める。川にとって、雨が降り、流れる水が増え、水面が上がり、岸から溢れるということは当たり前の自然現象でしかない。しかし、このような川のほとりに人が住み、そこでの生活が始まったとき、「洪水による被害」が新たに加わる。今も冬のセーヌ川の増水は季節の景色のひとつで、市民はそれを知っており、共存している。
図3はアルマ橋の上流側の旧橋脚に取り付けられている高さ5mを超える「ズワーヴ兵」の石像で、毎日数多くの観光船がすぐそばを通過している。この像は市民にとっての水位計の役目を果たしており、川が増水し始めると町の人々がこの像のどこまで水が上がってきているかを見にくる。図3には過去の大規模な洪水の西暦と、そのピーク時の水位を加筆している。1658、1910、1740年は水位が8mを超え、パリ三大洪水といわれている。日本の川と比較してセーヌ川全体の傾斜は緩やかで水位の上昇も下降も非常に緩やかであるため、川から溢れ地面に広がってしまった水がなかなかひかない。1910年の大洪水のときは、パリ市のすべての機能が回復するのに半年を要したほどだ。
パリにおけるセーヌ川の水位はパリ植物園近くのオーステルリッツ橋で観測しており、その値が上がるにしたがって川沿いの交通に安全のための規制が加えられる。水位が3.2mに達すると川岸の道がふさがれ始め、3.4mに達すると船が航行禁止、5.75mになると川のすぐ脇を通過している鉄道RER(地域圏国鉄急行網)のC線が予防的に運行停止、6.2mになると川岸の道路の完全封鎖、7.13mに達するとRERのA線、B線そしていくつかの地下鉄区間が運行停止になる。ちなみに平常値は1m未満で、このときの川のそのものの水深は約3.5mである。かなり細かく具体的なルールが設定されている。
洪水被害に見舞われる川沿いの町には「水防施設」は欠かせない。川から溢れる水への対策として「堤防」は最初に考えられることであるが、パリにはこれがない。あるのは「河岸(かし)」=「ケ:quai」である。人工的な構造物の影響をすべて排除した「自然本来の川」には「限界」があり、パリを流れるセーヌ川の水面は海抜35mより上がることはない。川沿いの土地をこの高さまで一斉に嵩上げし、いわば「スーパー堤防化」した結果が現在私たちが見ている「河岸」なのである。その最上部は川の水面から約8m高く、パリ市のすべての河岸が完成するのには1000年もの年月がかかっている。
3 様々なインフラ整備で一大都市へ
安全に対岸へ渡れる橋がパリに登場したのは紀元前1世紀、古代ローマ帝国の支配下に入った時期だと考えられる。ローマ人たちが「パリシイ人」と呼んだ人々は川のほとりの低地に住み、小舟に乗って自由に川面を行き来していた。彼らの住む場所に頑丈な木造の橋を建設し、ローマ式の舗装道路をそれにつなげた。その橋の上を渡り、ローマ人たちはさらに北を目指して進んでいった。
時代が下り、橋の材料が木から石に代わると、頑丈さを増した橋には川を渡る以外の様々な要素が付加されていく。橋の下には小麦を挽くための水車が設置され、大きな橋の上には「橋上家屋」が建つようになった。図4を見ると、シテ島(右)とセーヌ川右岸(左)を結ぶ3本の橋の上すべてに列をなして家屋が建っていることがわかる。高いものは4階建てにもなり、橋を通る人々からは全く川の姿が見えず、川を渡っている感覚はなかったという。また、下二つの橋の橋脚の間に描かれた格子が水車である。太い石の橋脚とその間をふさぐ水車が川の水が流れることができる場所をかなり狭めていた。橋や水車が増えるにつれて増水時の水位上昇は早くなり、上がってきた水が橋桁の上を通過しようにも橋上家屋が壁となって立ちはだかって橋はダムと化した。さらに水位を上げながら押し寄せる水の圧力に耐えられなくなった橋はすさまじい轟音と共に崩れ落ち流されていったが、人々は試行錯誤を重ね、また新たな橋を建設したのである。
また、パリで忘れてはならない重要なインフラといえば「市壁」である。フランス語の単語本来の意味は「市域を囲み、その内側を守り、その外側の地域との境界をなすもの」で、いわゆる「城壁」の形をとるものばかりではなく、パリのものには「市壁」という日本語を充てることが多い。12世紀末、セーヌ川右岸に初めて「フィリップ・オーギュストの市壁」が誕生すると、その後、王都防衛や徴税のための壁が新たに加えられていった。市壁は日常生活に様々な不都合を引き起こし、その新たな問題を解決するために人々は知恵を絞った。外に向かって拡大を続ける市域を守るために一回り大きな市壁を建設することが繰り返され、それと同時に用済みとなった古い市壁は街区の屋並みの中に埋もれていった。姿が見えなくなり、人々の記憶から消えていった市壁であるが、今、私たちが目にする「華の都」パリの現代の美しい町並みの中に、実は、ひっそりとその名残を留めている(図5)。
4 地面の凸凹から街を読み解く
人々の暮らしを文字どおり足元から支えている地面。そこにある凸凹は地表面を流れる水の動きを支配している。水は低い場所に向かって流れ、周辺で最も低い場所に留まる。凸によって流れの行く手が阻まれるとき、水はその手前に溜まる、あるいはより低い場所を求めて向きを変える。流れの前に凹があれば、水はその中にまっすぐに落ちていく。
現在私たちが踏みしめているパリの地面は、自然本来が持つ「天然の凸凹」の上に人間の営みの結果生まれた「人工の凸凹」が加えられたものである。新たな凸凹が増えるたびに水の流れは姿を変え、その思いもかけない動きに人々の暮らしは翻弄された。
一方で、恩恵も受けた。パリの町のすぐ外側にかつて広がっていた湿地(太古のセーヌ川が流れていた天然凹)では、ある作物がよく栽培され、国王や町の人々の食を支えた。それを伝える道が今でも残っている。「ポント・シュー通り(rue Pont aux Choux)」、直訳すると「キャベツ橋通り」は、かつて両側にキャベツ農地が広がる道であった。成長に多くの水が必要なキャベツは、水はけの悪い場所に最適な作物とされている。図6の左下から右上に向かって描かれている太さの異なる2本の川のようなもの、右側の細い方はドブ、左側の太い方は「濠」である。また、2本の流れにはさまれるように描かれたものこそ前述した市壁である。セーヌ川につながっているため常に水を蓄え、天然の濠となっていた湿地を利用し14世紀半ばにつくられた中世最大級の市壁で、時の国王の名前をとった「シャルル5世の市壁」である。
図7は1910年1月に起きたパリ大洪水の記録写真はがきである。中央奥がサン=ラザール駅の駅舎で、水没したパリからの脱出を図っている人々が小舟に乗って湖と化した駅前広場の水面をわたっている。水に覆われたこの場所こそ、太古のセーヌ川とそのほとりの湿地だったところである。最先端技術を用いたインフラも整っていた「華の都」パリであったが、よみがえったセーヌの力に抗うことはできなかった。パリにおけるセーヌ川の水は海抜35mより上にはこないと前述したが、駅舎左手に見える緩やかな上り坂の始点となっている水際のラインは海抜35mの等高線と一致している。
これから、自然が与えてくれたパリの地形=天然の凸凹を復元し、そこに人々が築いていったインフラ=人工の凸凹がその場所にどのような影響を与え、地面を変化させていったかを検証する。主役は「水」。それが何処にあり、どの方向に流れているのかを地図、文献から丹念に拾い上げていく。水が語る「パリの地面の物語」である。
パリに到着した翌日は夜明け前に目が覚める。空腹と時差が原因である。空港で買ったパンと飲み物で軽い朝食を済ませても、日の出までには時間があり、まだ町は眠っている。街灯は灯り、冬であれば道は凍っている。私の「凸凹調査」が始まる時間である。セーヌ川、街の通りには営業時間も、入場料もない。
ひたすら歩き、突然現れる階段の高さをメジャーで測り、見た目には平らな道の真ん中で「そんなはずはない」と日本から持っていったパチンコ玉を転がして傾いていることを確かめた。現場、地図、文献の間を何度も行き来し、凸凹に忠実な「パリの地面の水」が「その場所でどうなっていたのか」を、考え続けた。
・
「なぜ、ノートル=ダム大聖堂はすぐ水に浸かってしまうシテ島に建てることができたのか?」
・
10年以上持ち続けていた疑問であった。これまで、その答えが書かれたものは皆無だった。なぜなら、大聖堂が建つ島の「地面より上の事」しか論じられなかったからである。セーヌ川が増水すればあっという間に水に覆われてしまう地面が「どのように変化し」、そして「なぜ、その変化は生まれたのか」。本書で私はそれを明らかにし、ずっと抱えていた疑問に答えを出すことができた、と自負している。
「昔のパリの道はぬかるみ、不衛生だった」と数えきれないほどの文献に書かれているのに、「なぜ、そうなってしまうのか?」について納得のいく説明も見当たらなかった。しかし、姿を消した「市壁」とそれが水に与えた影響を明らかにすることでその答えも導くことができた。
「天然の凸凹」に「人工の凸凹」が複雑に絡み合ったもの、それが「パリの地面」であった。必要に迫られて人間がつくったインフラストラクチャー、それにいち早く、そして最も敏感に反応したのが「水」。低いところに向かって流れ、低いところに溜まる水によって激変した場所を目の当たりにし、あっけにとられ、そして翻弄された人々は試行錯誤を重ね、知恵を絞り、時には行き当たりばったりで凌ぎながらその地面の上で暮らし続けた。
・
パリの「扉」を開いてくださった早稲田大学小林茂名誉教授、地名をはじめ様々な固有名詞の正しい発音を教えてくださり、時には現地ガイドまでしてくださったパリ歴史研究の権威アルフレッド・フィエロ氏、パリ歴史図書館で文献探しを助けてくださったジュヌヴィエ―ヴ・マドール女史、私の研究ノートを1冊の本にするために学芸出版社につないでくださった早稲田大学佐々木葉教授、そして、辛抱強く私の原稿を編集してくださった学芸出版社の古野咲月さん、たくさんの図を丁寧に仕上げてくださった村角洋一さん、ミステリアスな魅力ある装丁をデザインしてくださったテンテツキの金子英夫さんに心からの敬意と感謝をささげます。
Merci infiniment pour tout!
・
写真は、ローマ人のカルド「サン=マルタン通り」とナポレオンの「リヴォリ通り」の交差点、そこから一つ東に寄った細い「サン=ボン通り」である。奥にサン=メリ教会が見える小路の中程に階段がある。のぼった先を横切るのがローマ人も歩いたデクマヌス「ヴェルリ通り」。この通りが「ビュアッシュの分水嶺」の上に載っている。比高わずか0.96mの1本の微高地。そこへ登る小さな7段。ここが、私の「パリの凸凹論」の原点である。
2025年8月15日 ノートル=ダム(聖母マリア)の祝日に
著者 佐川美加
公開され次第、掲載します。
メディア掲載情報
| 日付 | タイトル |
|---|---|
| 2026年1月5日 | 『凸凹で読みとくパリ』(佐川美加)が「毎日新聞」で紹介されました |
| 2025年11月17日 | 【全文閲覧可】『凸凹で読みとくパリ』(佐川美加)が「週刊エコノミスト」で紹介されました |
| 2025年11月17日 | 『凸凹で読みとくパリ』(佐川美加)が「週刊文春」内の鹿島茂さんによる連載「私の読書日記」で紹介されました |
| 2025年10月6日 | 【全文閲覧可】『凸凹で読みとくパリ』(佐川美加)が「産経新聞」で紹介されました |
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。