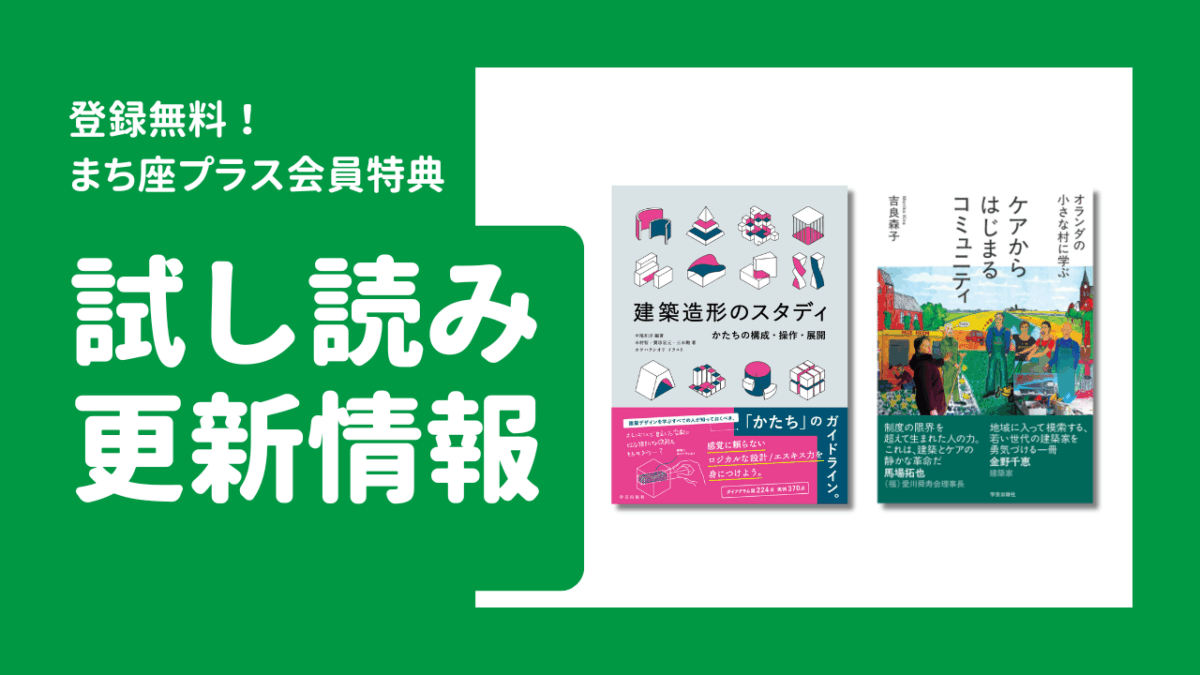建築造形のスタディ
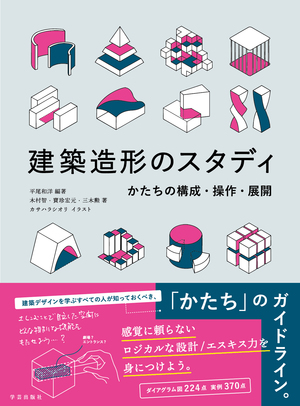
感覚ではないロジカルな設計力を身につける
建築のすべての構成要素の基本となる「かたち」についての入門書。かたちの図形的特徴やプロポーションの扱い、かたちの組み合わせ方や配置と変形技法、それらをひとつの建物としてみた時の空間の効果を、古代~近代・現代の豊富な実例とともに図解する。建築的な考え方が身につき、感覚に頼らないロジカルな設計を促す。
平尾和洋 編著/木村智・寶珍宏元・三木勲 著/カサハラシオリ イラスト

ログイン
新規登録
はじめに 「デザイナーの頭をつくろう! かたちのシンタックス」
1部 かたちの基本構成
01 線
1-1 かたちの基本要素
1-2 直線・柱の集合体
1-3 懸垂曲線/カテナリー/サイクロイド
1-4 曲線・円錐曲線・放物線
02 面
2-1 空間を仕切るもの
2-2 平面
2-3 曲面
2-4 円錐曲面・双曲面
2-5 シェル
03 ヴォリューム
3-1 プラトン立体
3-2 立方体のフレームと表層
3-3 立方体/キューブ
3-4 球体
3-5 錐体
3-6 円柱・シリンダー(円筒)・ヴォールト
3-7 家型
04 単体のかたち
4-1 円/サークル
4-2 断面的な円弧
4-3 円弧とその組み合わせ(自由曲線)
4-4 楕円/オーバル
4-5 ロの字形/コートハウス
4-6 多角形
4-7 らせん形/スパイラル
4-8 パラレル
4-9 コの字形
4-10 L 字形
4-11 放射形
4-12 風車形
4-13 門型/ゲート
05 比例するかたち
5-1 黄金矩形・黄金分割・黄金比
5-2 人体寸法システム「モデュロール」
5-3 ル・コルビュジエの分割比「8,5,3」
5-4 ルート矩形・白銀比
2部 かたちを操作する
06 かたちの基本操作
6-1 分割する
6-2 引き算・足し算
6-3 回転する
6-4 内包する
6-5 重ね合わせる=重合
6-6 重層する/オーバーレイ
6-7 平行を崩す/パースペクティブ(遠近法)
6-8 さし込む=貫入・挿入
6-9 孔をあける=穿孔
6-10 宙に浮かせる=浮遊
6-11 掘削する
6-12 積み重ねる=スタッキング
6-13 折り曲げる・ひねる=ベンディング
6-14 ずらす
6-15 ちりばめる=パラパラ
6-16 模倣する/アナロジー
6-17 ヴォリュームを変える
07 かたちの組織化
7-1 直交グリッド
7-2 斜交グリッド
7-3 放射グリッド
7-4 反復
7-5 並置と対比
7-6 対称(シンメトリー)と非対称(アシンメトリー)
7-7 軸線の関係性
7-8 近接・雁行・連結
7-9 入れ子= Box in box
3部 かたちから空間への展開
08 部分の集まり方
8-1 単一中心の建築
8-2 外なる囲い
8-3 内なる囲い
8-4 リニアな配列
8-5 ストライプ
8-6 立体パズル
8-7 群としてのクラスター
8-8 ヴォリュームの解体
8-9 部分と全体の相補性
8-10 建築の内と外/中間領域
09 分節化
9-1 分節の定義/面と線の分節
9-2 ヴォリュームの分節/プログラム別の分節
9-3 構造の分節/スキンとボーン
9-4 表面・ファサードの分節/スキニング
9-5 力の流れの分節
9-6 明暗・高低による内部空間の分節
9-7 コア(タテ動線設備)の分節
10 都市と建築の見え方
10-1 都市のかたち
10-2 図と地
10-3 景観と距離
10-4 風景の切り取り
10-5 アプローチとエントランス
10-6 空間の開閉性= D/H
10-7 基壇による高さ効果
問題集
デザイナーの頭をつくろう! かたちのシンタックス
この本は建築設計・デザインの初学者にむけて、「かたちの基本」とその「操作・配置」「空間展開」を伝えるために編まれたものです。彫刻とならんで3 次元芸術である「建築」は、最終的に「立体」として人間の様々な要求に応える実用物ではありますが、その製作過程では「紙の上にスケッチ・図面を書き、模型をつくり、それを見て評価し、コンセプトをまとめる」など、3 次元のみならず、2 次元ツールやことばも使って試行錯誤(スタディ)することが一般的です。ただし、プロのデザイナーともなれば、どの段階で、どのツールを使おうとも、頭の中では常に3 次元を中心とした「かたち」がイメージされています。
1部/
つまり建築の設計思考には、「思考の道具」としての「かたち」が必ず存在するということです。必然、かたちを数多く、きちんと整理・イメージして設計思考できる人は、様々な組み合せを試すことで、柔軟に建築をつくっていくことができるようになります。まだたくさんのことばを知らない赤ちゃんよりも、たくさんのことばを身に着けた詩人の方が、巧みな構文を紡ぐことができるのと同じことです。
2部/
他方、仮に「かたち」をたくさん知ったとしても、時に複雑な要求に応える必要のある建築では、それを自在に「組織化する」「変形する」「組み合わせる」ことが求められることがしばしばです。こうした「操作」する力を養うために、デザイン教育の現場では、課題を与えて設計をする練習、つまり「演習」が行われます。そこでは学生のエスキス(esquisse:スケッチ、素描、建築分野では設計の構想を進めるためのスケッチ。あるいはその構想を意味する)に先生が批評やアドバイスを加え、様々な操作や配列法を伝えていきます。言葉としての「かたち」をどう加工し、どう配列すればいいのか? つまり「シンタックス」と呼ばれる統辞・修辞技法(syntax:人間の自然言語において文が構成される仕組み)の感覚を学ぶのです。
3部/
もちろん、エスキスは他者から評価されるものでもあります。たくさん描いたスケッチを組み合わせ、統合化して、案の全体像(プレゼン・ボードや模型)へと「展開」するのが最終段階です。自分ひとりなら、クライアントになった気分で「空間効果や状態・見え方」を確認します。ダメだと思ったところは修正して、発展・代替案を作ってみます。この時に、集まったかたちの状態や見え方についての基本フレームも知っておくと有効でしょう。
不思議なことに、現在の教育現場では「かたち」も「操作」のやり方も、特に初学者に対して、体系的に伝えることは行われていないようです。むしろ演習の現場で、先生の経験的な知識が、「暗黙知」として、時間をかけながら学生に伝授されている、といったところでしょうか。
この本はその暗黙知を「形式知」に置き換える試みです。かたちにせよ、操作にせよ、これが全てではありません。この本を手に取るみなさんが、自ら作品研究を通して「あれもあるし、これもあるよ」と本のスキマにスケッチや写真・図面を加えて頂ければ、貴方だけのスクラップ・ブックが出来上がることでしょう。
読者の編集作業はこれからも続くものであることを期待しつつ、本書の編集では、紙面構成を含め学芸出版社 安井葉日花さんにお世話になりました。この場を借りて著者を代表し謝意を表したいと思います。
2025年9月 編著者 平尾和洋
公開され次第、掲載します。
開催が決まり次第、お知らせします。
メディア掲載情報
公開され次第、お伝えします。
※SNS等にて公開投稿されていた読者の皆様のレビューを、埋め込み表示させていただいております。不都合がございましたら、お手数ですがページ末尾のご意見・ご感想フォームよりご連絡をお寄せください。
建築学生のときにこの本があったら絶対買ってたな〜と思う一冊が出ました✍🏻
かたちのネタがたくさんあるので、設計課題に役立つこと間違いなしの造形スタディの教科書です。
いや〜いい教科書。 pic.twitter.com/olJcF0O4r5
— 編集部Y (@henshubunowai) October 16, 2025
おもしろいいいいい…! pic.twitter.com/xB8S68lWx6
— 菊池駿一@まるもり (@kiku5445) October 18, 2025
めちゃくちゃいい!
一回生の時欲しかったなー
手を動かしながら読むといいかも pic.twitter.com/2DHzA13NZe— たか (@anktaka245) October 19, 2025
教科書をお探しの先生方へ
採用検討用見本ご請求フォーム
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。
ご提供にあたってのご注意
提供はオリジナルデータ(筆者作成・撮影のもの)に限りますのでご了承ください。 また使用に際しては下記の注意を遵守いただきますよう、お願いいたします。ご提供の条件について
データの提供先は「授業で本書を履修者数分教科書としてご採用いただける先生」「直接弊社にデータ提供希望をお申込みいただいた先生」に限り、また原則として10名以上の受講(10部以上の注文)があった場合に限らせていただきます。著作権遵守/出典・クレジット表記のお願い
著作権を遵守してご使用ください。「オリジナル図表のデータ」については、スライド上映用資料データへの掲載、配布資料への印刷、オンライン講義での配信に限り、著作権者からのご許諾をいただいております。必ず図版の直下に出典(著者名、書名、出版社名)を明記してください。また、一部の画像の下部についているクレジットもカットせずに使用してください。出典の表記例
橋口新一郎 編『実践につながる インテリアデザインの基本』学芸出版社
データの管理について
データの管理には十分ご注意ください。出版物等への無断転載や、授業とは無関係の第三者への配布はもちろん、お知り合いの先生への個人的な提供も禁止します。採用特典ご請求フォーム
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。