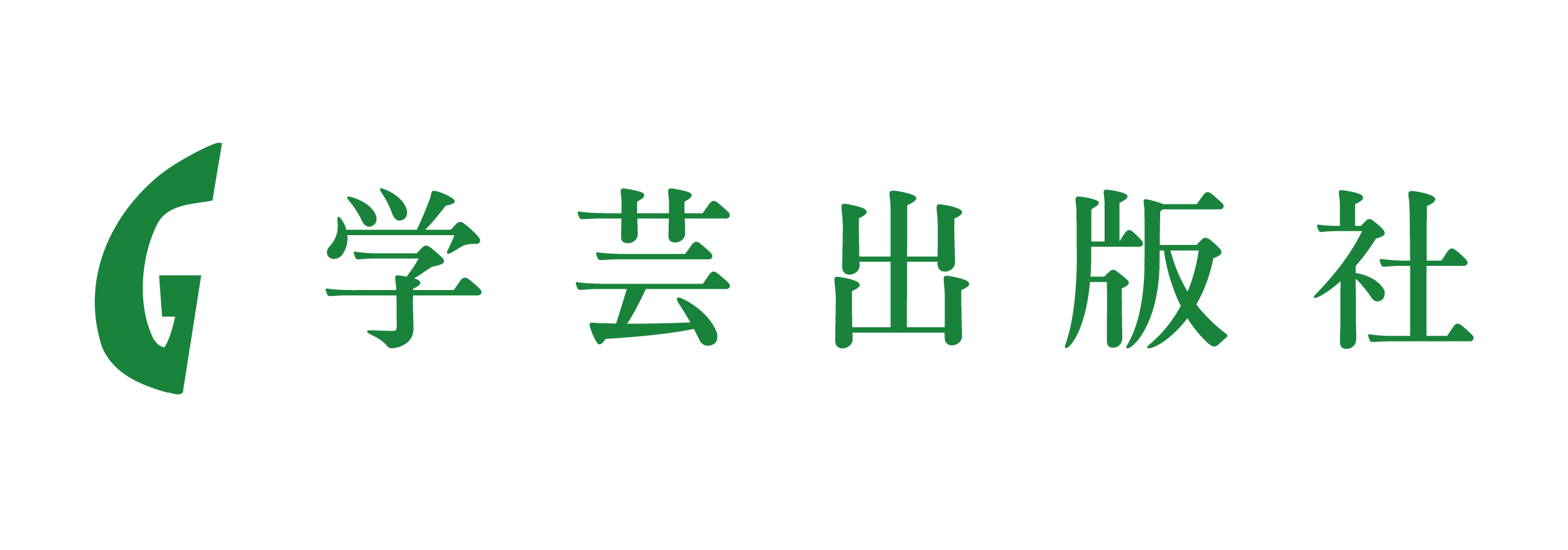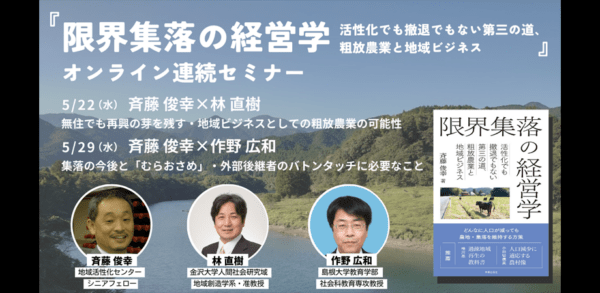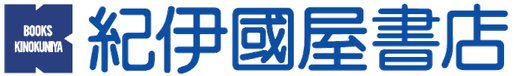限界集落の経営学

人口が減っても農地・集落を維持する方策
広がる廃村危機。活性化か撤退かの二択では国土も食料も維持できない。住民主体の手づくり重視から、PPPによる経営力導入と中規模の加工工場への国の直接投資へ。人口が極限まで縮小しても小さな予算で農地と農村を維持する道は開ける。肉牛の放牧、受精卵、大豆ミート事業など先進事例もすでにある。今こそ決断の時だ。
斉藤 俊幸 著
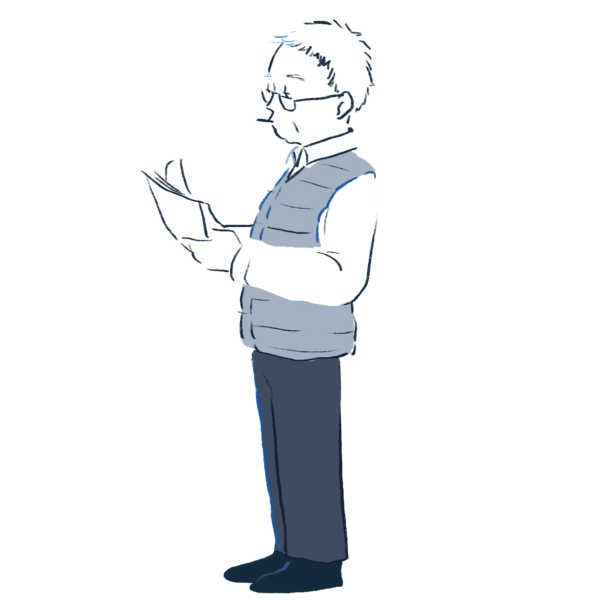
| 体裁 | 四六判・220頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2200円+税 |
| 発行日 | 2024-05-15 |
| 装丁 | ym design(見増勇介・鈴木茉弓) |
| ISBN | 9784761528928 |
| GCODE | 5689 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| 関連コンテンツ | 試し読みあり レクチャー動画あり(全2件) |
| ジャンル |
ログイン
新規登録
序 章 限界集落の経営学
①地域とビジネスのイノベーション
②イノベーションを誘発する
③現場・現実から現物を差し出す
第1部 粗放農業によるむらつなぎ
第1章 活性化でも撤退でもない第三の道
1 粗放農業の延長線上に集落が荒廃しない道筋がある
2 放牧をやりたい若者は必ずいる
第2章 適正規模の農業を目指す若者たち
1 適正規模の農業とは何か
2 適正規模の牧場経営の旗を振る先駆者
3 粗放農業と相性が良い新規参入者の非競争性
第2部 新規参入者の受け入れと土地利用型地域ビジネス
第3章 後継者は長老組織からの存在承認を得る必要がある
1 「池田暮らしの七か条」が示唆する地域の思い
2 固い結束に基づく集落組織からはイノベーションは起きない
3 棚田の草刈りで存在承認を得る
4 若者が黙々と働く姿に長老組織が大規模投資を決断
5 むらつなぎ実現のための条件
第4章 イノベーションを決断できるリーダーの育成は難しい
1 多くの集落で地域ビジネスのリーダーと後継者がいない
2 組織が生き残るためにイノベーションがどれだけ重要か
3 衰退と発展の分かれ目にある浜中町農業協同組合
4 イノベーションを理念として引き継ぐ木次乳業の新リーダー
5 イノベーションを起こす当事者がいないと事業の継続は難しい
第5章 地域ビジネスを継承できるリーダーは外にいる
1 「投資と経営の分離」と「経営とオペレーションの分離」がポイントだ
2 経営リーダーは外部人材でも良いのではないか
3 弱いつながりの組織をつくれ
第6章 土地利用型地域ビジネスの実践・計画例
1 土地利用型地域ビジネスとは
2 土佐あかうし牧場クラスター ─ 適正規模農家の誘致
3 受精卵ビジネス ─ 遠隔地からのリーダーの招聘
4 子牛放牧ビジネス ─ 地域商社と牧草栽培農家の連携
5 和牛肉輸出ビジネス ─ 海外に向けたオペレーション
6 大豆ミートビジネス ─ ベンチャー企業の誘致
7 米焼酎ビジネス ─ 酒造専門家を招聘
8 農家独自流通ビジネス
第3部 国の直接投資と公民連携による所得向上
第7章 農村における公民連携
1 民間が主導せざるを得なかったまちづくりの経験
2 農家に投資を決めた大企業
3 資金調達の課題
4 土地利用型地域ビジネスによる所得向上
第8章 国の投資と地域ビジネスによる農地・農村維持
1 内発的発展論の今日的解釈を試みる
2 国も適切なリスクを負い所得倍増を果たす仕組み
3 毎年数十億~百億円の予算枠でむらつなぎは実現できる
4 むらつなぎ実現のための方策
あとがき
序章 限界集落の経営学
①地域とビジネスのイノベーション
組織の変革と所得向上から考える
人口減少社会に入り、農地と農村集落に関する地域政策の分野で活発な議論が起こっています。主なものを紹介すると、農村撤退論、むらおさめ論、農村たたみ反対論、食料安全保障論などです。本書は農村の消滅危機を煽るものではありません。農地と農村を二分する議論に、第三の道として放牧と地域ビジネスの現場から具体的に地域活性化政策の方向性を提案したいと考えています。
加えて農地と農村の存続に関する最大の問題点は、結束の固い長老組織にあると考えています。固い結束の組織からはイノベーションは生まれません。これでは地域が持っている地域ビジネスを後継者にバトンタッチすることができず、集落は無住化を待つばかりです。
また農地と農村を維持するためには、大都市と地方の所得格差を解消し、後継者の所得の向上を図る必要があります。大都市と地方の所得格差の拡大が無策のまま今後も続くと、やがて政治問題化します。所得格差に対する不満から紛争へとつながる現象は世界の各地で起きています。日本が例外であることはありません。この紛争を回避するためには、地域ビジネスによる所得の新たな配分方法を考える必要があります。ここでも社会的価値を市場価値に変換できる地域ビジネスによる所得配分が有効です。
土地利用型地域ビジネスとは
では地域ビジネスとは何か。それはイノベーションを生むことができる土地からの産物を活かした中量生産のビジネスです。生産工場から毎日同じ商品を10トン車で搬送するのが大量生産です。農家の手作りにより、農家が住んでいる市町村を対象として農産加工品を販売するのは少量生産です。工場が立地する都道府県を主な対象として営業車によって商品を供給するのが中量生産です。
2000年代に入り、地域再生事業の時代に突入しました(注1)が、支援が少量生産に偏っていました。現在にいたるまでの20年間の地域ビジネスに対する国の助成は職業訓練、商品開発、販路開拓に関わる外部専門家の人件費に集中していたのです。農業分野においては六次産業化政策により、優れたレシピで作られた商品や高級感あふれる包装デザインの商品を多く生みだしましたが、商品が手作りであるため、販路拡大や収益に限界があり、その多くが農家所得の向上に寄与しませんでした。
例外を除いて、農家は消費者に対して直接的な販路を持たず、生産規模の拡大へ向けた投資に手を出すことができなかったのが実情です。この結果、六次産業化によって次の時代を切り拓くようなイノベーションは生まれなかったのではないでしょうか。このため、内発的発展論で重要視される地域の「自立更新」につながることはありませんでした。〝失われた30年〟とは、日本がバブル崩壊という経済的な破綻に直面し、企業も政府も大規模な投資意欲に後ろ向きになり、イノベーションの機会を失い、地方は自己破壊を起こしていたのではないかと筆者は考えます。
では、農地を維持するために、どのような地域ビジネスが良いのでしょうか。それは粗放化(粗放農業)によって農地を維持できる地域ビジネスです。集落や集落住民が所有する農地だけではなく、同じような空間を共有する複数の集落が広域的に連携して、粗放的な生産(粗放農業)を行い、それを束ね、市場価値へと変換できる地域ビジネスが求められます。筆者はそれを土地利用型地域ビジネスと定義しました。
代表的な土地利用型地域ビジネスとしては、乳業会社があります。乳業会社は牧草を栽培し、乳牛を飼養し、生乳を生産する酪農家を束ね、市場価値に変換しています。ただ乳業業界は飽和状態なので、本書では、肉用牛繁殖農家が放牧で飼養する和子牛を生産するための受精卵ビジネスや大豆の粗放的生産を束ねる大豆ミートビジネスなどを例として取り上げています。
今さらなぜものづくり産業なのかの問いに対しては、農地を引き継ぐ地域ビジネスでないと長老組織からのバトンタッチが成立しないからと答えたいと思います。集落に住む人がいなくなり、所有者が都会にいるような土地に不動産会社が入る事態が予想されます。不動産会社はその土地を安価で購入し、外部の企業に売り渡すのであれば、たとえそこで地域ビジネスが誕生したとしても、それは内発的発展と言えません。もうあまり時間は残されていないのです。このため、現実的に実現可能な土地利用型地域ビジネスをスタートしイノベーションを継続することで、次のイノベーションを誘発することしか選択肢は残されていないのです。そのため5年以内に各地で具体的に実現できるような土地利用型地域ビジネスを提案しようと考えています。
粗放農業と地域ビジネスの先に創発が起こりうる
筆者は青森市や高松市の中心市街地がコンパクトシティの代表例として脚光を浴びた時期に、中心市街地に「買い物難民」が取り残されているのではないかとの問題提起をしました。硬直した地域に外部専門家が入ることが有効であることが分かり始めた時期に、住み込み型の外部人材がさらに有効であることを筆者自らがモデルとなり示したことで、住み込み型の「地域おこし協力隊」が誕生しました。その後、「地域おこし協力隊」制度は創発的な展開を示し、移住制度の切り札として飛躍的な発展を遂げました。
農村撤退論のなかには農地の粗放的管理(粗放農業)が段階的な撤退の選択肢としてあり、この段階をへて農地を森に帰すというシナリオがありますが、筆者は農地の粗放農業には、ビジネスチャンスが存在するのではないかと見ています。筆者はこの小さな隙間の向こうに、人口減少で苦戦する日本を救う大きなビジネス領域が隠されている可能性があると注目しています。「買い物難民」や「地域おこし協力隊」の制度化に共通する小さな隙間が見えます。「買い物難民」がそうであったように、「地域おこし協力隊」がそうであったように、この先の展開は、シナリオどおりにはいかず、まったく分からない状況であると思います。つまり創発が起きるということです。
粗放農業の適任者はすでにいる
本書では、適正規模の経営を提案する酪農家を追いました。北海道の三友盛行氏のリラックス農業と岩手県の中洞正氏の山地放牧です。それぞれ多くの若者が共鳴し、適正規模の農業を追随しています。三友氏は主に北海道において、若い新規就農者に大きな影響を与えました。また中洞氏は北海道以外の日本の各地に実践者を生みました。筆者はこれらの実践者を中心にヒアリングしました。若い新規就農者はみな、仕事は生きていける目途が立つのであればそれでよく、仕事より家族を大切にしたいと話していました。地元出身の酪農業や肉用牛繁殖農家が大きな投資を進め、成長を目指す姿とは異なるものでした。
こうした非競争性とも言うべき特徴は、これからの日本にとって重要な存在となるのではないでしょうか。人口減少社会に突入し、すべてが規模や効率性の競争ではなく、粗放農業で価値を生むことができれば、人口減少社会だからこそ実現できる新たな日本の姿を生むことになるでしょう。そして農地の粗放農業の適任者はすでに存在しているのです。
②イノベーションを誘発する
広域農地を対象としたプッシュ型支援
本書で伝えたいことを冒頭で簡単に説明します。まずは農村集落の組織と農地のビジネスとしての活用を分離し、農地の活用を考えるということです。集落の組織は選択肢がないまま追い込まれており個々に解決策を見出すことが難しい状況です。まさに集落は思考停止状態にあります。このため筆者は広域で農地の維持を考えることを問題提起し、適正規模の農業の戦略的な集積を農地・農村維持の解決策として提案しています。
これは一集落から見るとボトムアップではなく、広域からのトップダウンだとの批判もあるかと思います。しかしその批判は当たらないと考えています。今、集落は消滅という危機に直面しています。これは国家的な危機であり、国が中心となってこの危機を回避するというミッションが優先されるべきであると考えるからです。このため集落政策においては、災害時に発動される国からのプッシュ型支援への転換を提言します。
投資と経営とオペレーションの分離
筆者は都市整備や景気浮揚を名目とした旧来型の建築・土木投資と、地域ビジネスにおいてイノベーションを誘発するための設備投資とは分けて考えるべきであると主張しています。では誰が土地利用型地域ビジネスのリーダーとなりうるのでしょうか。
まず誰が設備投資のリスクを背負うのか? 集落住民は高齢化し、借金を背負って中量生産規模の工場の設備投資を実施することは難しいことが多いでしょう。この答として、筆者は設備投資のリスクは国が担うべきであると主張しています。設備投資に関わるリスクと土地利用型地域ビジネスの経営とが分離できれば、外部からの経営人材の招聘と集落住民によるオペレーションで十分です。
また投資リスクがなければ、事業に参入する経営人材も飛躍的に増えるのではないかと考えます。国の重点的な設備投資により、経営に関する新たなビジネス領域が誕生するのではないでしょうか。土地利用型地域ビジネスは単に商品を生産することではなく、イノベーションを起こすことが使命となるという新領域です。このような地域ビジネスの萌芽を本書で紹介しています。
所得倍増を目指す
前述のとおり本書では、農地と農村を維持するためには、大都市と地方の所得格差を解消し、後継者の所得の向上を図ることが必要であると述べています。このため具体的な政策に関して言及しています。
一つは国の直接投資により投資リスクがなくなることや国家財産であるため固定資産税が免除されることにより、収益向上が可能となります。この収益向上を人件費に充当すれば、人件費はアップできます。
また、地方公務員の月12日勤務を提案しています。これは消防署の勤務体系です。人事院が国家公務員の週休3日制の導入を勧告しており、地方自治体でも試験的運用が始まっています。これを踏まえ、1日おきの勤務体系とし、休日となる時間に、集落住民と協働して土地利用型地域ビジネスを起業することを提案しています。これにより、農地が活用され、所得の向上が見込まれるのであれば、地域に定住する根拠も明確となると考えています。
③ 現場・現実から現物を差し出す
本書では公害を蒔き散らした重化学工業が登場します。集落の長老組織に対してモノ申しています。所得格差を解消するため、設備投資を解決策としています。おまけに地域外の経営人材による遠隔操作まで登場します。SDGs、サステナブル、ウェルビーイング、共創が求められる時代なのにそんな話は一つとして出てきません。この地域活性化論は大丈夫だろうかと筆者も心配です(笑)。
しかし筆者は実務家研究者として、実際にある地域の「現場」から、「現実」を理解したうえで、「現物」を差し出すという姿勢を貫きたいと思います。地域活性化政策もみな地域の「現場」「現実」「現物」から生まれるものであって、それを横展開するために制度化されてきました。
限界集落は大丈夫です。農地は機能します。チャンスです。みんなで地域の「現場」「現実」「現物」を世界に向け差し出そうではありませんか。どうかご一読ください。
2024年3月
斉藤俊幸
注
1 なお、国からの支援の代表的な事業には、地方創生事業があります。安部首相から岸田首相に代わり、地方創生交付金事業の名称がデジタル田園都市国家構想交付金事業に変更となったため、本書においても新しい事業名で書くべきですが、長期間にわたり、地方創生事業と称呼されてきたため、読者は新しい事業名では事業全体の構造がイメージしにくいのではないでしょうか。このため本書では、国の事業名として安倍首相の時代の呼び名である地方創生事業という称呼を採用しています。
筆者は適正規模化を志向する若い新規就農者の意見を追いかけてきました。彼らは成長、大規模投資、大量生産を志向する従来型の酪農家、肉用牛繁殖農家とは異なる志向を持っていました。非競争性という志向です。
2023年7月に国立青少年教育振興機構がまとめた『高校生の進路と職業意識に関する調査報告書―日本・米国・中国・韓国の比較』の調査結果を読みました。この調査では注目すべき結果が出ています。仕事や生活に関する意識において、日本の高校生は、「暮らしていける収入があればのんびりと暮らしていきたい」が、49%であり、米国(42%)、中国(29%)、韓国(36%)と比較して最も高い数値を示しているのです。「社会に役に立つ仕事をしたい」「仕事よりも、自分の趣味や自由な時間を大切にしたい」も同様に最も高い数値を示しています。日本は非競争性の特性を持つ世代の後を継ぐ高校生においても、非競争性を特徴とした若者が育っている証拠ではないでしょうか。
バブル崩壊により就職氷河期世代が生まれ、この世代を起点に、終身雇用、年功序列の安定した仕事に従事することがすべてではないという意識を持った後継者が生まれています。長期的な人口減少社会のなかで、日本のすべての分野で競争だけを続けることが果たして良いことなのか、もっと違う生き方があるはずだという大きな流れは必ずやってきます。そして、こうした動きに親和性を持つ若い世代がすでに日本に生まれているのです。日本が受けたバブル崩壊という経済的なショックは、日本人の心の深層部にまで影響を与え「失われた30年」となってしまいました。しかし、日本は「瓢箪から駒」や「怪我の功名」や「思惑倒れ」といった創発を繰り返すなかで、偶然にも素晴らしい後継者を育てていたわけです。
とはいえ競争ばかりを強調する社会にウンザリして別の生き方をしている人たちが、再び競争社会に引き返すことはあるのでしょうか。地域ビジネスとは言え、会社に従属することを選ばないのではないかという疑念があるでしょう。ここは、大切なポイントです。
岡山県美作市で草刈りをする移住者グループは午前6時から活動を開始し、午前8時には解散します。彼らが兼業によって生きていることは紹介したとおりです。しかし、みな20~40代の独身の若者です。結婚し、子どもが生まれるとなると、兼業で稼ぐ収入だけでは家族は養えない場合も出てくるのではないでしょうか。
地元出身の農林漁業者も生活費や子どもの教育費の捻出に苦労しています。久賀島のある漁師は中学校を卒業後、高校へは行かず漁師となられ5トン未満の小さな船で刺し網漁をして生計を立てておられました。息子二人は学校の成績がよく、将来を期待され日本のトップといわれる私立大学と旧帝国大学をルーツに持つ国立大学に進学されました。この漁師は子どもが島外の高校に入学し、大学を卒業するまで時化のときも漁に出たそうです。
山内道雄らによる「未来を変えた島の学校」(2015年)には「島前高校が廃校になれば、島の子どもたちが自宅から通える高校はなくなる。寮や下宿生活に伴う仕送りなどの負担は重い。3年間、一人の子どもを本土の高校に通わせると400万円から450万円になるとの試算がある。家計には大きな負担で、経済的にゆとりがない家庭や、子どもの数が多い家庭ほど、島外に出てしまう」と書かれています。こうした現象は島嶼部だけではなく、山間部の遠隔地でも起きています。
地域で安定した生活を営めるのは、地方公務員、金融機関、新聞記者だけだと聞いたことがありますが、適正規模の農業や粗放農業を営む人が安定した生活が営めないのはおかしい。そのために筆者は土地利用型地域ビジネスを提唱しています。
雇用されること、従属性への嫌悪があるのであれば、いかに本人がワクワクできるか、意義を見付けられるかが大切です。
日本が持っている競争と非競争の二刀流は実は強い競争力を持っています。非競争性志向の人たちを競争社会に引き戻すのではなく、適正規模の農業や粗放農業の社会的価値を市場価値に変換することが必要なのです。市場価値に転換する地域ビジネス領域の開拓や深化は始まったばかりです。
なお、これはブランド化で稼ごうという話とは違います。ブランド化を否定するつもりはありませんが、ブランド化は競争社会のなかで勝ちにいくことを目指しています。本書で提案している土地利用型の地域ビジネスは、むしろ市場での不当な扱いを改め、望むなら子どもを育て、教育を受けさせることもできる程度の収入を確保できる道をつくることです。
農地・農村の荒廃だけではなく、所得格差が広がり、分断が深まっています。人口減少のなかで、価値の創造を個人頼みだけで行うことはできないでしょう。放置すれば紛争になりかねません。所得格差の拡大に歯止めをかけられるのは国だけです。土地利用型の地域ビジネスが日本全体の安定にもつながるのです。
国は、ムラの空洞化が始まった時点が地域ビジネスによる「むらつなぎ」のチャンスであると捉え、土地利用型地域ビジネスへのイノベーションに関与し、非競争性を持つ若者に着目し、彼らが活躍する場をつくってください。若者は後継者として現場で汗を流してください。その関係づくりが必要です。日本の農地・農村は非競争性の最先頭にいます。チャンスです。
筆者は実務家研究者です。大学の研究者が、学問的背景や知見に基づき、学術的な新知見を論考することで新たな理論を見出すのに対して、実務家研究者は、研究者の新しい理論を引き継ぎ、実行、達成、解決する手法を現場から組み立てるのが任務です。実務家研究者が、先行する理論をベースに地域の現場に具体的につないでゆく。研究者と実務家研究者が協働して、地域に研究成果を着地してゆくことが、これからのアカデミズムに求められます。筆者は、大学の研究者の理論や提言を引き継ぎ、まさに具体的に地域に成果を着地できる存在でありたいと考えています。
日本が持っている非競争性は、逆に強い競争力を持っているという書き出しから分かるとおり本書は競争論がベースとなっています。こうした競争論の視点を筆者に与えてくれたのが、経営学者の藤本隆宏先生(東京大学名誉教授)です。筆者がここにいるのは小学校の同級生である藤本先生をずっと見上げていたからです。藤本先生の前でいち早く本書の内容を話させていただきました。この本は限界集落に踏み込む新しい経営学の領域にいるのではないかと二人で話し合いました。藤本先生のおかげでここまで来られました。ここに改めて御礼申し上げます。
また本書は筆者の博士論文がベースとなっています。博士論文の指導教員である那須清吾先生(高知工科大学教授)に改めて感謝申し上げます。那須先生からは大学の研究者と実務家研究者の役割に関して深い示唆をいただいてきました。
地域活性化センター常任顧問(前理事長)の椎川忍氏および明治大学教授の小田切徳美先生に本書の推薦文を書いていただきました。椎川氏からは筆者が地域の現場に入るなかで、多くの示唆に富むご指導をいただき、現在にいたっています。総務省の地域力創造アドバイザーや地域活性化センターのシニアフェローとして活動できるのは椎川氏のおかげです。筆者はまた、小田切先生の足跡を見つめ現在にいたっています。感謝申し上げます。
なお、「プッシュ型支援」の地域への導入の是非に関しては法政大学の図司直也先生にご指導いただきました。畜産業のイロハも分からない筆者に畜産業の現場でご教示いただいた鳥取県伯耆町の獣医師木嶋泰洋氏にも感謝いたします。木嶋氏からは、畜産業に関する多くの知見をいただくとともに、熱い情熱を持って、日々努力する姿を見させていただきました。本書を博士論文から読み物に書き替えるために、拙文を読み、貴重なご意見をいただき、あるいは、励まし続けていただいた大学の先輩である高橋文男氏にも感謝申し上げます。
最後になりますが、編集の力をまざまざと見させていただきました学芸出版社の前田裕資氏に感謝申し上げます。みなさま、ありがとうございました。
2024年3月 斉藤俊幸
開催が決まり次第、お知らせします。
終了済みのイベント
メディア掲載情報
| 日付 | タイトル |
|---|---|
| 2024年11月7日 | 『限界集落の経営学』(斉藤俊幸 著)が「西日本新聞me」および「九州経済調査協会月報」で紹介されました |
| 2024年10月8日 | 『限界集落の経営学』(斉藤俊幸 著)が、季刊「しま」(2024年9月、279号)で紹介されました |
| 2024年9月11日 | 『限界集落の経営学』(斉藤俊幸 著)が「季刊ritokei」(No.46)で紹介されました |
| 2024年7月8日 | 『限界集落の経営学』(斉藤俊幸 著)が、日本農業新聞(2024年7月7日)で紹介されました |
| 2024年7月4日 | 『限界集落の経営学』(斉藤俊幸 著)が「月刊ガバナンス」(2024年7月号)で紹介されました |
| 2024年7月1日 | 『限界集落の経営学』(斉藤俊幸 著)のダイジェストが、書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」で公開されました |
| 2024年6月10日 | 『限界集落の経営学』(斉藤俊幸 著)が、日本経済新聞(2024年6月8日付)で紹介されました |
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。