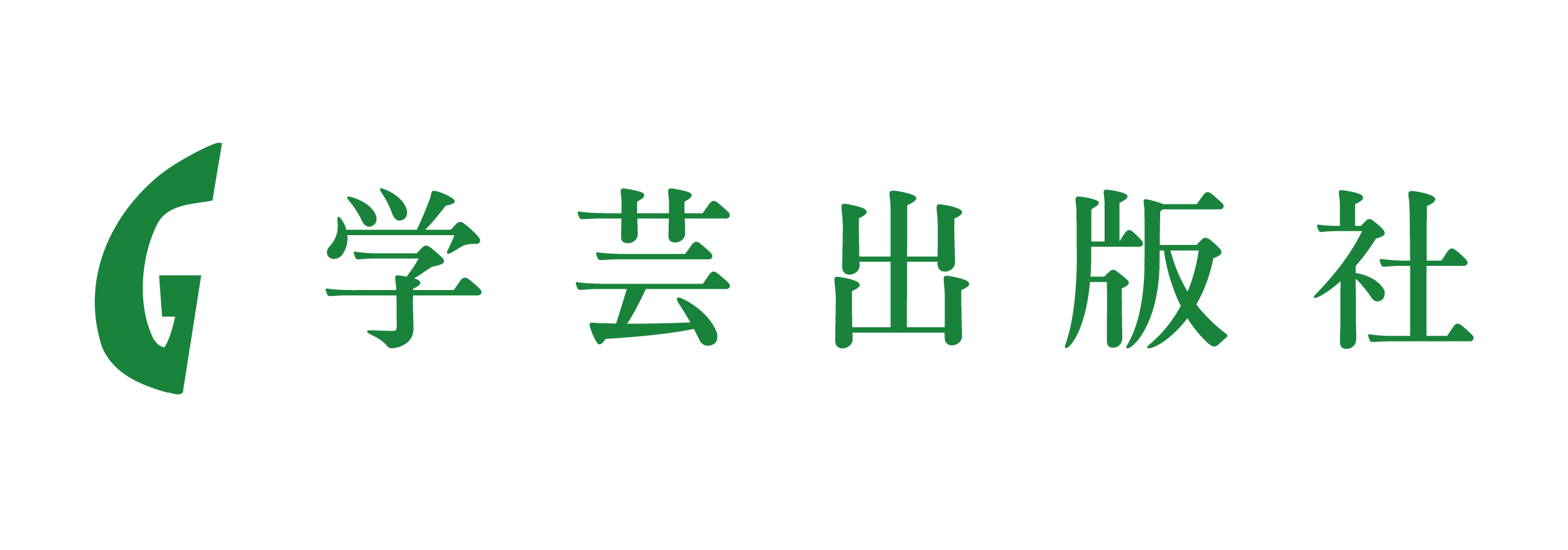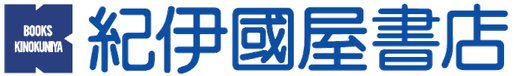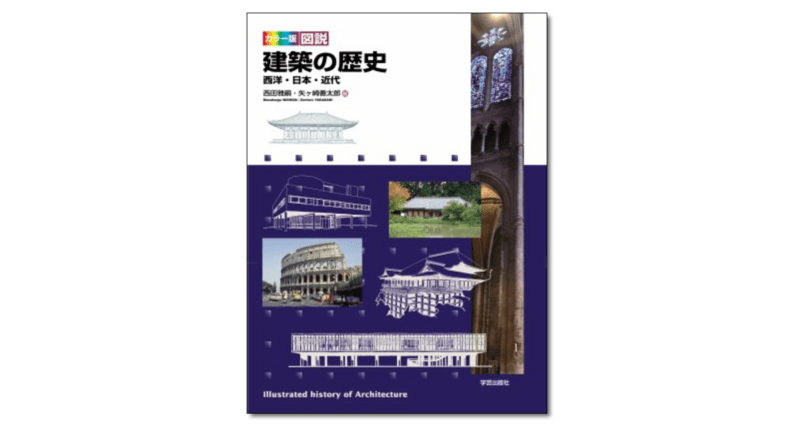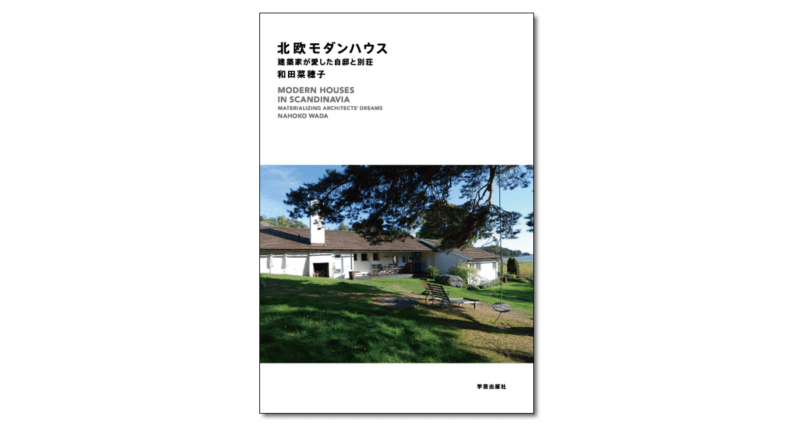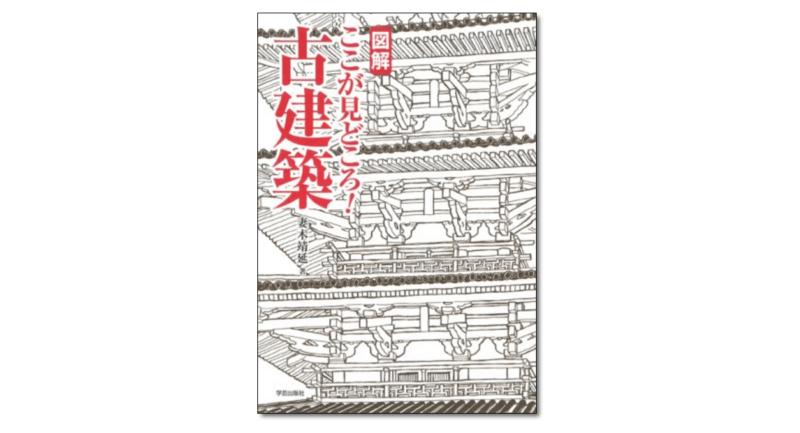(仮)建築小説集
内容紹介
実在の建築を舞台にした10編の短編小説集。舞台となる建築にまつわるキーワード(風土・建築家・時代背景など)に紐づけて、過去・現在・未来における人間の選択や決意の瞬間を描く。
体 裁 四六判・252頁・予価 本体2000円+税
ISBN 978-4-7615-1377-1
現在、鋭意制作中です!
本書の最新情報をお知らせ!お気に入り登録はこちらから。
瞳の天蓋(六一〇年、ローマ、パンテオン)
ローマは摩耗した都市だ。
数カ月にもわたる馬上での旅を経て、古都に降り立った男はまず第一にそう思った。
乾いた盛夏の空気の下、往来の少ない埃っぽい街路の両脇には、石と煉瓦の塊が密集している。小さな窓を備えた四、五階建ての集合住宅(インスラ)。アーチ状の開口の奥に黒々とした日陰を抱えた商店の数々。
馬を引いてそのまま進むと、広場に出る。深い庇を持ち、仰々しい碑文が壁面に刻まれた巨大な公会堂(バシリカ)が、呆けたように口を開けていた。
かつては几帳面な鋭角に満ちていたであろうそうした建築群は、長年の風雨に晒され、今や曖昧な丸みを帯びている。街路や区画の整然とした構造は残っていても、栄華の時が遠くなれば細部は茫とする。そして街全体も、凡庸な地方都市の様相を呈するようになる。公文書に書かれない、人々の欲望の歴史に酷使され続け、その結果として摩耗しきってしまった都市だと、男は思った。
男の名をここでは〈犬〉としよう。それはもちろん、彼の本当の名前ではない。東ローマ帝国皇帝フォカスの忠臣である彼は、フルネームも、二、三の立派な肩書も持っていた。しかし、帝国の首都コンスタンティノポリスでは誰もが陰で彼を犬と呼んだ。そのことに彼自身も気づいていたが、苛立つどころか、その渾名を気に入ってすらいたのだ。
中年を目前にした犬は、これまで旅の多い人生を歩んできた。小アジアのとある都市で生まれ、貧困の中で育ち、若くして東ローマ帝国軍の兵士となった。そして数年間、国境防衛のために辺境の属州を渡り歩いた後、成り行きで軍によるクーデターに参加することになった。
犬の所属する部隊を率いていた下士官は、気性が荒く残忍な煽動者だった。彼は当時の皇帝が処刑された後、兵士たちに推されて皇帝フォカスとなった。フォカスの忠実な部下だった犬は、図らずも皇帝付きの官僚として、独特の地位を与えられることになった。
犬がローマを訪れるのは初めてのことだった。自ら足を向けたいと思ったこともなかった。喜んで諸国を漫遊するような趣味は彼にはなかったし、宗教も歴史も彼の専門外だった。彼が得意なことは別にあった。だからこそ、彼がわざわざローマに派遣されたのだった。
長旅を無事に終えたばかりの犬は、疲れと安心感から、一刻も早く眠りたかった。帝国の輝かしい首都コンスタンティノポリスから、かつての首都ローマへの旅は、決して容易な道のりではなかった。
バルカン半島を東から西へと横断し、アドリア海に臨む諸都市を巡りながら雑用やこまごまとした使いを済ませ、ヴェネツィアからは南に進路を取る。
ラヴェンナにしばらく滞在し、ところどころ断絶したローマ街道の石畳を馬上から脇目に見ながら、さらに南下してようやくローマに到着した。常に野蛮人や盗人に脅かされる、危険で過酷な旅だった。
そのため犬は市内での仕事は翌日以降に回して、この都市で彼の面倒を見る、とある役人のもとに向かったのだった。
その役人にももちろん本名と肩書があったが、ここでは〈驢馬〉と呼ぶことにしよう。
驢馬は太った男だった。年齢は犬よりも十歳は上で、目元の皺には老いの片鱗も見え隠れする。しかし頬の皮膚は赤っぽく膨らんで光沢を放ち、彼が笑うと、富を脂肪に変えて蓄えた二重あごがぶるぶると震えた。
「この家の中は安全だ。私の名誉にかけて保証するよ」
市街の中心部から少し外れた通りに面した邸宅(ドムス)のアトリウムで、驢馬は犬にそう言った。犬のローマ滞在の面倒を見る庇護者であり、この街の高級官僚の一人でもある彼は、裕福だった。邸宅は何人もの衛兵に守られていた。
「皇帝の使いで来た客人に、不便な思いはさせない。危険な事態や困ったことがあれば、いつでも知らせてくれ」
「この街はそんなに治安が悪いのか」と犬は尋ねた。
「良からぬ連中はどこの街にでもいる」
そう驢馬は答えた。
「廃れた街なら尚更だ。明るいうちはごろつきに絡まれる程度だが、暗くなれば追い剥ぎや夜盗が湧いて出る」
天窓から差し込む夕方の光の下で自慢気に調度品を撫でるその男こそ、ローマの治安維持を監督する立場の一端を担っているのだが、その口調はまるで他人事だった。
犬の視線にそんな非難を感じ取ったのか、驢馬は言い訳のように付け加えた。
「なにしろ、ラヴェンナの総督府がコンスタンティノポリスに代わってローマの内政を司るようになってから、まだ日が浅い。我々も難儀しているのだ。君にはその点でも助言をもらえるとありがたいのだが」
驢馬は犬を客室に案内した後、去り際に意味深げに付け加えた。
「とにかく、日が落ちてからはあまり出歩かないことだ。何より、君はきっと常人よりも敵が多いだろうからな」
彼の含むところは犬にもよく分かった。フォカスは皇帝の座の簒奪者であり、対立する者を次々と処刑する暴君としても知られている。現皇帝に反抗し、その治世を一刻も早く終わらせようとする気運は民衆に根強い。その命を受けて単身はるばるローマを訪れた素性を知られれば、市内で厄介事に巻き込まれる可能性は否定できなかった。
中庭に臨んだ二階の客室は、犬には十分な広さだった。なにしろ、イタリア半島に入ってからの旅路は街道沿いの安宿で寝られれば良い方で、野宿も珍しくなかったのだ。柔らかい寝床があるだけでも天国のようだった。
犬は手早く荷を解き、翌日からの仕事の準備を始めながら、いつの間にか眠りに落ちていた。
次の日も、夏の日差しは強烈だった。犬は驢馬の邸宅を出ると散策に出かけた。それも仕事のうちだ。ローマを一度も訪れたことのない皇帝に代わって市内の様子を見聞し、コンスタンティノポリスに戻った後に治安維持や風紀の取り締まりについて進言しなければならない。楽しみのために市場を冷やかしたり、歴史的な遺構を見物したりという発想は彼にはなかった。
驢馬は犬に護衛を付けることを提案したが、犬は断った。彼は見知らぬ他人に行動を監視されることを好まなかったし、皇帝もそれを望まない。
通りには召使いや奴隷がうろつき、屋内からは職人たちのぼそぼそとした話し声が聞こえてくる。彼らは質素で劣悪な多層集合住宅に住み、労働に命をすり減らしている。そのほとんどは、都市の戸籍にも載ることはない。まともな名を持つことすらない。
彼らを使役するのは、貴族や裕福な商人や役人、有力な手工業者といった上級市民だ。夏の日差しを避けてそれぞれの邸宅に閉じこもり、古美術や調度品に囲まれて暮らしている。郊外には農地を持ち、そこでも小作農や奴隷たちを働かせている。
出自の知れないごろつきが、犬に鋭い目を向ける。彼が腰に提げた剣を値踏みしているのだった。
この街に生きる人々はまるで鼠だ、と犬は思った。
その点に貧富の差は関係ない。ローマ人が築き上げた栄光の廃墟の隙間に入り込み、権力者の目を逃れてこそこそと生存する。街路も室内も変わらず俗悪で、浅はかな欲望が詰まっている。驢馬の言う通り、邸宅を一歩外に出れば、何が飛び出してくるか知れない。
犬は、寂しくすり減ったローマを不快に感じ、到着時に内心で味わった落胆を反芻した。
大帝国の首都として栄華を極めたこの街は、およそ三百年前のローマ分裂以降、じわじわと重要性を失ってきた。政治と商業の中心はラヴェンナなど周辺の諸都市に分散し、人口は減って市民文化も衰えた。残ったのは、聖職者と古教会の威厳ばかりが残る鈍重な都市だ。そんな権威すらも、強力な騎馬隊を持つゲルマン人諸民族の度重なる侵攻と略奪によって、さらに失墜した。五十年ほど前に改めて東ローマ帝国の支配下に戻った後も、ローマにはいち宗教都市以上の存在価値は戻らなかった。
今や皇帝によるイタリア半島支配は虫食い状態だ。帝国の行政機構や軍の警備が行き届く範囲は群島のようにばらばらになった。街を出て馬を走らせれば、そこはもはや異国という有様だ。ローマは今、ラヴェンナの総督府が管理する辺境の地方都市の一つにすぎない。
犬がラヴェンナに立ち寄り、皇帝からの書簡を携えて総督に謁見した際も、彼の関心事にローマの発展や繁栄などまるでないようだった。皇帝や総督の望みはただ、自らの威信の後ろ盾として、宗教都市ローマを安全かつ無害に保つことだけだ。
そして、犬はそのためにこそローマに送り込まれたのだ。
街路をしばらく歩くと、ふいに視界が開けた。そこは広場だ。すり減った石の舗装の上に種々雑多のごみが散らばり、物乞いや小商いが茣蓙を敷いて声を張り上げている。
そんな場所の奥にある巨大な建築物が、皇帝が犬に命じた今回の旅の、最も重要な目的地だ。
ずんぐりとした鍋のような建物の正面を、古い様式(オーダー)の列柱と、それに支えられた巨大なペディメントが覆い隠している。そしてペディメントと列柱の交わる梁の部分には、こんな文字が刻まれていた。
――M. AGRIPPA L. F. COS TERTIUM FECIT(ルキウスの息子マルクス・アグリッパが三度目のコンスルのとき建造)
それはローマ帝国のかつての繁栄を示す遺構の一つ、パンテオンだった。
広場を抜けて建物の真下に着くと、犬はその大きさに圧倒される。閉鎖的でみすぼらしい周囲の古教会や商店、住宅と比べると、その外観はおおらかで大胆な印象を与える。列柱空間は開放的で、夏の空の下に荘厳な日陰を湛えていた。
しかし、彼の用事があるのは建物そのものではない。どれだけ巨大で威厳に満ちていようと、建物はただの建物だ。美に打ちひしがれて使命を忘れるほどナイーブな心象は、彼にはなかった。
犬の仕事はこれまでもこれからも、第一に人と会って話すことなのだ。
階段の上では数人の職工が休んでいた。
犬が近づくと、彼らはじろりと目を向ける。それを無視してアーチの下の入口に進むと、そこに若い男が立っていた。
紛れもなく聖職者だ。痩せた身体に簡素な黒いローブを身にまとい、頭頂を円形に剃り上げている。
「何かご用でしょうか」
聖職者は言って、一瞬で犬の全身に視線を走らせる。その結果、問題がないと判断したようで、その後の口調は柔らかだった。
「お見かけしたところ、コンスタンティノポリスからいらっしゃったようだ」
「パンテオンの改装の状況を見届けに来た」と犬は言った。
聖職者の、彫りの深い眼窩に光が差し、目が影の中できらりと光った。彼はおお、と言って、犬の名を口に出した。あだ名ではなく、彼の本当の名前だった。
「あなたが皇帝の遣いの方ですね。司祭から伺っていました」
そこで彼は自分の名を名乗った。しかし例によって、ここでも〈鹿〉という渾名を用いることにする。
「私は教皇と司祭たちに命じられて、サンタ・マリア・アド・マルティレスの工事を取り仕切っています。工事といっても、簡単なものですが」
「サンタ・マリア?」と犬は聞き返した。
「おや、お聞きではありませんか。この建物――教会の新しい名前ですよ。皇帝が我々の教皇、ボニファティウス四世に寄進されたパンテオンは、教皇によって聖母とすべての殉教聖人たちに捧げられました。パンテオンなどというのは今や古い名ですよ」
取り澄ました鹿の顔に、うっすらと誇りが、高慢の香りが交じった。
「名前のことなどどうでもいい」
犬は撥ね返した。
「俺の関心は、皇帝がお前たちに与えた建築物が好き勝手に改築されていないかどうかを確かめ、その姿を記録することだけだ」
犬がそう言うと鹿は余裕のある笑みを浮かべた。青年というには年重の男だが、少しでも表情を崩すと子どものような無防備な甘さが現れる。
その表情の裏には、今のところ不安や緊張は感じられない。いけ好かない相手だ、と犬は思った。
「ご心配なく。この建物は大胆な改築など受け付けません。中に入ってみれば一目瞭然ですよ」
鹿はそう言って、薄暗い内部へと犬の視線を誘った。入り口の幅は二人が揃って両手を広げられるほどの尺で、高さは身長の四、五倍ほどもある。その奥は列柱に支えられた影の中から見ても暗く、よく見えなかった。
しかし、鹿の背中を追って進むにつれ、犬は息を呑んだ。
無意識のうちに、彼の視線は上方へ惹きつけられた。
目の前に広がっているのは円形の大空間と、パンテオンの中心をなす大円蓋(クーポラ)だった。列柱やペディメント装飾に満ちた壁の上から、緩やかな曲線が頭上へとせり出し、中央で一つに閉じてドーム状の天井を形作っている。ただし、それは犬が諸国で見たどんな教会の、どんなクーポラとも違った。
何よりも、桁違いに巨大だ。驢馬の邸宅どころか、そこそこの大きさの集合住宅すら丸ごとすっぽりと包み込めそうな高さと広さがある。まるで空気が膨れ上がり、石の中に巨大な泡を作り上げたかのようだった。
天井面には正方形の凹みが整然と連続していた。クーポラにはそれ以上の装飾はない。全面に、褪せた白灰色の地が見えている。
そして、何よりも犬の目を釘付けにしたのは、天蓋の中心に開いた光の穴だった。
建物全体が大きすぎて、穴の直径が上手く掴めない。少なくとも、大の大人の身長でも二、三人分以上の大きさだ。
真円の天窓から、正午近い日の光が床に真っ直ぐに落ちている。石張りの床にその光が反射し、大空間全体を明るく照らしている。天井面の凹凸がその光によって、不思議に軽やかな立体感を帯びていた。
犬は自分の体重がなくなってしまい、宙に浮かび上がるかのような感覚にとらわれた。
「おわかりでしょう」
そう言う鹿の声には、どこか自慢するような響きがあった。
「この建物の作りは、市内の公会堂や教会とは全く違う。壁から異教の痕跡を剥がし、教会の認める彫刻や装飾を施すことはもちろんできます。実際、内部に残る異教の象徴は、ほとんど消し去ることができました」
鹿の話す通り、周囲を円形にめぐる壁面には教会式の装飾が施され、聖母像や聖人像がすでに備え付けられていた。
「しかし、この建物の根幹をなす、あのクーポラには誰も手がつけられない」
彼はそう続けた。
「彫刻はもちろん、絵画を描くこともはばかられます。下手に手を加えれば、建物全体の価値が著しく損なわれてしまう。どんな塗料でどのように塗り直すかということですら、非常に難しい問題なのです。コンクリートでできていますから」
「コンクリート?」
「火山灰に砕石やレンガの破片を混ぜ込んで固めた建築材料のようです。この建物は石を積んで作られたのではなく、いわば灰を水で捏ねて作られた。しかし、詳しいことは分かりません。これは古代ローマ人が開発し、数百年の混乱の中で我々が忘れてしまった技術なのです」
犬は建築技術の専門家ではなかった。彼がどれほど熱心にクーポラを眺めても、その構造の秘密を解き明かせそうにもない。
しかし、彼は人の表情の奥に潜む心理の構造にかけては、コンスタンティノポリスでも右に出る者のない専門家だった。
「クーポラを除けば、もう工事は終わったということか」と犬は鹿に尋ねた。
「あとは、建物全体の掃除や補修が残っています。長年、大した手入れもされずに放置されていましたから」
「天井の色は」
「私が決めることではありませんが、おそらく、このままの状態で残されるでしょう」
犬は鹿の顔をじっと見たが、その表情に嘘は読み取れなかった。少なくとも現在の計画では、皇帝の預かり知らぬところでパンテオンが好き勝手にいじくり回されるということはない。今日のところはそれが確認できれば、犬としては十分だった。
犬は、数十年前に書かれたパンテオン内部の見取り図を携え、現物を確認して回った。果たして鹿の言うとおりだった。細かい装飾を付け替え、彫像を新たに置き直した形跡はあるものの、建物の形態に関わる大きな変更は全く見られなかった。
「この光を見ていると、神を感じませんか」
確認作業が終わりに差し掛かったところ、鹿が頭上を見上げてそう言った。日は傾き、天窓が投げかける光輪は壁を上って天蓋の凹凸模様の上に落ちて、複雑に変形していた。
「当時のローマ人は多神教を信仰していたといいますが、本当は我々の神をよく理解していたのではないかと思わざるを得ません。天上のある一点から降り注ぐ光が、この世界のすべてを照らす。この空間のいかなる場所においても、あの光の目(オクルス)から逃れることはできない。サンタ・マリア・アド・マルティレスの性質は、我々の生きる世界の性質をよく表しています。だからこそ、この建築は混乱の時代を生き延び、我々にもたらされたのではないでしょうか」
鹿はそのような持論を滔々と語った。オクルスに向けられた彼の目は光を帯び、表情は恍惚としていた。
犬は宗教家が嫌いだというわけではない。しかし、彼らが限られた理屈で世界を語りつくそうとする際の物言いを、彼は好まない。ふと、意地の悪い発想が浮かんだ。
「この空間にも、あの光が十分に届かない場所はある」
鹿は訝しげな顔をした。
「それは、一体どこでしょうか」
「俺たちの背後だよ。俺たちの影が落ちる場所だ。俺が後ろ手にナイフを持って、今まさにあんたを刺し殺そうとしていたとしても、あの目には見えやしない」
「しかし、反射光はあなたの背後にも届いていますよ。神の目を騙すことはそう甘くない」
「なら、閉じた目蓋の下はどうだ。この頭の中、あるいは腹の中は」
犬の予想に反して、それでも鹿はうろたえず、むしろ彼を憐れむような表情になった。
「神はそんな暗闇も見ておいでですよ。目を閉じてみれば分かります。暗闇の中に、微かに光が残るでしょう」
「それが神の光だっていうのか」
「私はそう考えています。もちろん、我々の正式な教義の中に含まれてはいませんが」
この男とこれ以上話しても意味はない、と犬は思った。鹿は若い宗教家らしく浮世離れした男だ。すべての事象を単純な図式で理解したい、そうしなければならないという情熱に動かされている。
「宗教の形を借りて勝手な持論を築くのは勝手だ。だが、話す相手には注意することだな。俺が誰の遣いでここに来たか、よく思い出すことだ。この世界で何が正しい考えで、何が異端の考えか。それを最終的に決めるのは、教皇ではない」
口をつぐんだ鹿をその場に置いて、犬はパンテオンを後にした。
列柱を抜けて、明るい陽光の下に出ても、彼は目の前に見える埃っぽい街が現実であると信じがたいような、妙な気分だった。いつまでもオクルスの光に照らされているような気がしてならなかった。街を歩いていると、背後に視線を感じることが度々あった、
太陽は激しく、石と灰の廃都ローマを照らしていた。あの燃える一点に発する光がすべてを照らし、都市に影や形を与えている。目を閉じても、外の光をたしかに感じる。人の目蓋は薄く、完全な暗闇を作ることはできない。気に入らない考えではあるが、あの助司祭の言うことは的を射ている部分もあると犬は思った。
しかし犬は、そんな概念の遊びによって価値観を揺さぶられるほど幼くはなかった。皇帝に命じられた仕事は、まだ二割も済んでいない。
仮に、この世界に満ちる光が神の視線で、善事も悪事もすべて見つめられているのだとしても、その視力が弱まる条件はある。夜になれば月や、無数の星々が大地を覆う。窓のない屋外では、今まさに秘密が育っている。そんな大いなる影の中こそが、犬の本当の仕事場なのだ。
翌朝は時間があったので、犬は驢馬と遅い朝食を共にすることになった。
「よく眠れたかな」と食卓で驢馬が尋ねた。
食卓には種々の肉や果物が並び、朝食としては多すぎるほどだ。いずれも、精巧な作りの骨董品めいた皿に山盛りになっている。コンスタンティノポリスでもなかなかお目にかかれない、豪勢な朝食のテーブルだった。
「ああ、おかげさまで」
「しっかり鍵をかけて、物音一つ立てずに熟睡していたようだ。パンテオンの視察はそれほど大変だったのかな」
「長旅の疲れが残っているんだ。鍵をかけて寝るのは、日頃の癖だ」
「もちろん、構わないよ。ゆっくりと休んでくれ」
そう言って驢馬は豚肉のソテーをほうばった。太った顎が震え、白い歯で肉を咀嚼するのが見える。地方役人のくせにまるで貴族のような贅沢だ、と犬は思った。
「随分と豪勢な食事だな」
「私の土地で採れたものだ。近郊に広い農地があってね」
「奴隷は何人だ」
「奴隷は少ないが、土地を農民に貸している。彼らの善意によって、その作物の一部を分けてもらっているというわけさ」
「まるで、租税のようにか」
犬がそう言うと驢馬の表情にさっと陰が差した。葡萄酒で口内の咀嚼物を流し込み、反論するように彼は言った。
「人聞きの悪いことを言わないでくれ。私は領主気取りの付け上がった役人ではない。総督府に認められて、ローマ近辺の行政に関わっているだけだ。ささやかな土地を祖父の代から受け継ぎ、少しずつ増やしてきた。農民も適切に扱っている。それだけだ」
「俺は別に、変な疑いをかけようとしているわけではない。ほんの冗談だよ。ただ最近は身分を世襲し、領民や兵まで従えて地方の支配者を気取ろうとする輩が多いからな」
犬はそう取り繕ったが、彼の目には驢馬の表情の細かい変化がすべて見えていた。
驢馬は用心深い男だ。簡単にはぼろを出さないし、後ろ暗いことなど何もないと自分に言い聞かせて行動している。だからこそ総督府にも信用され、皇帝の権威を辺境のローマにまで行き渡らせるための役人たちの網に加えられているのだ。
驢馬はその後、口数がやや少なくなった。それを気取られまいと意識する様子も、犬には手に取るように分かった。
北方から押し寄せる騎馬民族にイタリア半島を虫食い状に侵略された現状を先々代の皇帝が認め、ラヴェンナ総督府に軍事と行政の権限を移譲してからというもの、地方の役人は次第にコンスタンティノポリスの軛を逃れて勝手な振る舞いをするようになっている。遠く離れた首都や、まだ体制の整っていない総督府の目を盗み、土地所有を加速して支配者気取りをするようになっているのだ。
しかし、激烈な性格で知られる皇帝フォカスはそんな勝手は許さない。数カ月前には、皇帝の逆鱗に触れた高級役人のうち数人が城壁に吊るされたばかりだった。
「ローマでは君が来る前日に、役人が殺された。家族ともども皆殺しだ」
驢馬は食事の手を止めずに言った。
「下手人は誰だ」
「分からないが、その辺りをうろつく夜盗でないのは確かだ。戸締まりをしたドムスの中で、ほとんど物音も立てずに全員が一刃でやられていた。おそらく、この街出身の者ではない。殺しの訓練を受けた人間だ」
「では、どこ出身だと?」
その問いに驢馬は答えない。
「コンスタンティノポリスか」
「やめてくれ。この話は終わりだ。君もあまり挑戦的な物言いをしない方がいい。自分の立場を勘違いするな。事態が変われば正しさも変わる」
「カルタゴ総督の反乱のことを言っているのか」
またも驢馬が答えないので、犬はそのまま続けた。
「たしかにカルタゴは危機を迎えている。しかし、皇帝はもう二年近くもその動きを抑え込んでいる。首都も混乱しているが、統治は揺るがないはずだ」
「たしか、君は現皇帝とともに首都に入ったんだったな」と驢馬が言った。
「そうだ」
「なら、簡単に楽観はしないことだ」
犬が外出する頃には正午を過ぎていた。屋外は暑い。滞在中の仕事はまだたっぷりと残っている。彼は胸のうちに残った不安の種を、その日のうちに忘れた。
日が傾く頃、犬はまたパンテオンを訪れた。職人たちは相変わらず、だらだらと仕事を続けていた。薄暗い屋内に入り、再びオクルスを見上げていると、鹿が犬をみとめて声をかけてきた。
「今日もいらっしゃったのですね。随分お仕事熱心なことだ」
「絵描きは来ているか」
「ええ、そこにいます」
鹿は大空間の隅の薄暗い一角を指差した。そこには汚れた身なりの男が、画架に向き合って座っていた。
聖職者をその場に残して、犬は黙々と仕事をする絵描きに近寄った。鹿はそんな様子を遠巻きに眺めている。その視線を背に感じながら、犬は低い声で絵描きに話しかけた。
「首尾はどうだ」
絵描きはちらりと犬に目をやり、無言のまま、また手元に目を戻した。近くで見ると、その顔には深い皺が無数に刻まれている。
画布には木炭でパンテオン内部の素描が描かれている。犬は芸術を解さないので、それがよく描けているのかどうかは判断できない。しかし、彼の仕事にはこの絵描きが必要なのだ。
「仕上がるまでどのくらいかかる」と犬は尋ねた。
「どちらの話だ」と絵描きは聞き返した。
「両方だ。絵も、殺しも」
「絵の方は、必要であれば今日中にでも仕上げられる。しかしそれではお前が困るだろう。儂がここにいる口実がなくなるからな」
「その通りだ」
「殺しの方は、昨夜までに下見は済んだ。今夜、月が雲に隠れていれば決行する」
「くれぐれも気をつけろ。役人どもはお前の最初の仕事で怯えている」
「儂は失敗を犯してはいない。約束通り、お前がこの街に入る前に済ませた。ある程度目立つ殺し方もしたじゃないか」
「それは分かっている。悪いが、第三の獲物も教えておく。十分に時間を取ってから、殺れ」
犬は低い声で、市内のとあるドムスの場所と、その家の大まかな部屋の配置、そして周辺の警備の情報を呟いた。絵描きはそれを聞きながら、画布の上に奇妙な記号を書き留めていく。それが彼なりの備忘録なのだ。
「いつ訪問した」と絵描きが尋ねた。
「つい先ほどだ。主人は初めは警戒していたが、途中からは俺を見くびってぺらぺらと話してくれたよ。もちろん言明はしないが、奴は反皇帝派だ。領主を気取って私腹を肥やし、おそらくカルタゴにも協力している」
「本当に、表情からそこまで読み取れるのか」
絵描きは初めて、微かに笑った。
「それとも犬と呼ばれるだけあって、鼻が利くのかな」
「無駄口はやめろ。昼に俺が判断し、夜にお前が殺す。それが皇帝の命令だ」
「今回も、家族全員を殺すのか」と絵描きが訊く。
「お前に任せる。状況に応じて判断しろ」
「儂は何も決めない。判断しない。それが儂だ。お前が決めろ」
犬は半ば無意識に背後を振り返ったが、鹿はいつの間にかいなくなっていた。ふと頭上に目を向けると、オクルスがこちらを見つめていた。
「ならば、殺せ」と犬は言った。
絵描きは正確に、第二の仕事をした。その日の夜、月も見えない曇りの空の下で、ある役人とその家族が死んだ。それによって、皇帝フォカスに反抗する不届き者の勢力が少しだけ削がれることになった。
夜盗の仕業に違いないと多くの人々は考え、夜は衛兵が廃れた古都を隅々まで歩き回ったが、手がかりはまるで見つからなかった。
そんな日々が二月以上も続いた。犬は皇帝とラヴェンナ総督府の証書を持って淡々と役人を訪ね、その中から生きるべき者と死ぬべき者を選別した。そして、視察と称してパンテオン内部の薄暗がりを尋ね、絵描きに絵の進捗と殺しの進捗を訊き、オクルスに見つめられながら次の仕事を発注し続けた。季節は盛夏から晩夏になり、初秋に入った。日の勢いは弱った。
そしてある日、コンスタンティノポリスからローマへ、ある噂が流れてきた。
皇帝フォカスが処刑されたという情報は、瞬く間に街中に広まった。
「どうやら噂は本当らしい。首都は混乱しているが、じきに正式な知らせが来るだろう」
驢馬はアトリウムで調度品を撫でながら、犬にそう告げた。
「カルタゴ総督の息子、ヘラクレイオスが艦隊を率いてコンスタンティノポリスを襲撃した。首都は二日で陥落したそうだ」
「皇帝は」と犬は尋ねた。
「ヘラクレイオスが即位を宣言した」
「違う、フォカスのことだ」
「まだ確認できていない。しかし噂通りなら、殺されただろう。私もその可能性が高いと考えている」
驢馬は犬を真正面から見据えた。犬が見つめ返すと、驢馬の表情の奥には、安堵と不安が綯い交ぜになっているように見えた。
「君の主は死んだ。世界は変わるぞ」
驢馬はそう言った。それ以上、言葉を交わすべき内容はなかった。数日か数週間か。しかるべき時間が経てば新皇帝の誕生がローマにも正式に伝わる。そうなればおそらく、犬は後ろ盾を失うだろう。ヘラクレイオスがフォカスの忠臣を引き続き登用するとは考えにくい。驢馬が犬を庇護し、安全な客室を与えている理由もなくなるのだ。
翌日、パンテオンのクーポラの下へ、犬は絵描きを尋ねた。数カ月をかけて描かれた絵は、犬の目にもなかなかの出来だった。
「いずれにしろ、お前と儂の仕事はもうほとんど終わった」
絵描きはそう言った。
「お前の話では、残るは小役人ばかりだったろう。続けろと言うのであれば殺すが、生かしておいても仕事の失敗とはとられない」
「そういう問題ではない。皇帝が死んだんだぞ。俺たちの後ろ盾はなくなった」
犬は思わず声を荒げた。その声はパンテオンの静かな大空間に微かにこだました。幸運にも、他には誰もその場にいなかった。
「次の皇帝が即位したのだろう」
絵描きの口調は淡々として、焦りも不安もどこにもないようだった。
「誰かがまた儂を必要とするのであれば、お前ではない誰かが獲物を伝えに来る。そうでなければ儂はただの絵描きとして生きる。それだけだ。三代前の皇帝から、そのように仕えてきた。お前はこの絵と、殺しの報告を持って、首都に帰ればいい」
絵描きが挑発しているのかと思い、犬は激昂しかけたが、どうにか踏みとどまった。彼が本心からそのように言っていると気づいたからだ。そのとき初めて、犬は自分と絵描きの立場がまるで違うことを悟った。
犬はフォカスの忠実な部下だった。諸都市を巡り、皇帝派と反皇帝派を嗅ぎ分けて、必要であれば暗殺者に依頼して殺してきた。旅ばかりで疲労の絶えない人生だが、世界のどこに行っても丁重に扱われてきた。殺される側や野垂れ死ぬ側ではなく、殺す側、追放する側として生きていられた。
なぜなら、それが正しいことだったからだ。皇帝の権威に覆われた地中海世界では、その秩序の維持こそが平和への貢献だった。好き勝手に人民や土地を酷使する地方の支配者を帝国に平伏させることが世界を守ることだと、犬は信じてきた。
しかし実のところ、犬は帝国に従っていたのではなく、フォカスという一人の王、やがて首を刎ねられる王に従ってきただけだったのだ。フォカスなき今、犬は仕事を失い、正義を失い、存在の基盤さえも失いつつある。
急に、オクルスから降り注ぐ光が眩しく、犬は目を開けていられなくなった。
「逃げるなら早くしたほうがいい」と絵描きは言った。
「逃げるだと。俺は帝国のために働いてきた。他の人間にはない能力もある。新皇帝が俺に価値を見いださないことはあり得るだろう。しかし後ろ暗いことなど何もない」
「本気でそう思っているのか。フォカスが先代から皇帝の座を簒奪したとき、何が起こったか、お前は覚えているはずだ」
何も答えられず、犬はパンテオンからふらふらと歩み出た。列柱の間で職人に指示していた鹿が呼び止めたが、彼には聞こえていなかった。
日は傾き始めていた。犬は寂れたローマ市内を闇雲に歩き回った。この街に来る前、彼は実はローマに期待を抱いていたのだ。ローマには千年の歴史があり、この世界を支える価値の根幹があると。
現在のパンテオンを建造した皇帝ハドリアヌスは、自分の名前でなく初代パンテオンの建造者アグリッパの名前をペディメントに刻んだ。そのように名誉を重んじ、唯一絶対の価値のために働く。それがローマ帝国の人間の理想だと、犬は思っていた。自分たちが簒奪者であることを都合よく忘れて。
しかし実情は違った。ローマは遺跡と塵芥だらけの廃都となって、忘れ去られようといている。自分たちはクーデターによってのし上がった不安定な権力者に過ぎず、再びのクーデターで排斥される。昨日までの善行は今日からは悪行となり、遡及的に裁きが下る。同じ太陽で照らされていても、善悪は簡単にひっくり返るのだ。どんなに明るくても、この世界は実際には一寸先も見えない暗闇だ。
そして日が落ち、街が夕闇に沈む頃、犬は寂れた街路で襲撃を受けた。いつの間にか黒衣の男が周囲を取り囲み、剣を取り出して彼に襲いかかった。
犬はもう諦めていた。暴漢たちの出自や、自分を殺そうとする理由は幾通りも思いついたが、どれであっても結果は大差ない。ここで生き残っても、最終的には新皇帝が自分を殺すだろう。すべてはもう終わったのだ。
しかし、犬は死ななかった。
物陰から現れたもう一人の男が、鮮やかな身のこなしでナイフを躍らせて、男たちを次々と倒してしまったからだ。
「どうして俺を助けた」
犬は呆然として、絵描きに尋ねた。
絵描きはナイフの血を拭き、四人の死体を物陰に隠すと、平静に返事をした。
「今のところはまだ、お前が儂の司令役だからだ。正式な知らせが来る前にお前が殺されては、儂の仕事が失敗とみなされる。クーデターがあろうがなんだろうが、誰の命令を聞くべきかという正式な指令なしには、儂は行動を変えない。だからこそ機械として信用されるのだ」
そうして絵描きは、死体の被った頭巾を取り払った。
「この顔に見覚えはあるか」
犬はすぐに理解した。暴漢の一人は、驢馬の邸宅を守る衛兵の一員だった。
夕刻のパンテオンに入るのは、犬にとって初めてのことだった。驢馬の邸宅を離れ、安心して一夜を過ごせる場所は、ローマには他に思いつかなかった。
たどり着くと、ちょうど鹿が建物の扉を閉めようとするところだった。彼は犬の乱れた身なりを見て、何かを察したようだった。
「奥に、まだ磨いていない床の一角があります。寝るのであればそこにしてください」
鹿はそう言って、扉の隙間を少し大きくした。
「俺は追われる身だ」
犬は思わずそう言った。
「今は正式には罪人でなかったとしても、いずれ罪人として殺される。そんな人間が、この建物を頼りにしていいのか」
「我々は皇帝に、帝国に仕えているのではありません。教皇に仕えているわけですらない。神に仕えているのです」
鹿は暮れかけた街を見渡して、余裕の笑みを浮かべた。
「日が昇る限り、神の目は遍在します。そして夜には、私の内部の光が外部を照らす。目から入った神の奇跡の光は、私の内部に火を灯す。暗くてもこの火を頼りに、なすべきことを判断できる」
鹿が扉を閉めると、パンテオンの内部はほとんど真っ暗になった。しかしオクルスが切り取る紺の空からわずかに光が入り、目が慣れれば自分の横たわるべき場所を見つけることができた。
じきに完全な暗闇が辺りを満たし、孤独で不安な夜が始まった。犬はその中で息を潜め、静かに横たわっていた。しばらくすると雨が降り始めた。天窓から水が落ちる音だけが静かに聞こえ、床は濡れていった。彼の衣も濡れ、乾いた肌に水が染み入った。しとしとという雨音に浸りながら、犬は思いを巡らせた。
驢馬が自分を殺そうとしたのは、おそらく独断だ。正式な処刑の命を待たずに帝国の敵を討ち、手柄を立ててさらなる権限を得ようと画策したのだろう。奴は自分が殺した役人たちより一枚上手だ。コンスタンティノポリスやラヴェンナに従いながら、器用に領主への道を歩んでいる。奴には信念がない。信念がないからこそ、混乱したこの世界で成り上がることができる。
あの絵描きにも信念はないが、代わりに規則がある。彼の中はからくり仕掛けで満たされていて、余計な感傷や恐れが入り込む隙間などない。だからこそ信用され、皇帝がどれだけ変わっても仕事人として生き続けることができる。
しかし、鹿は自分の内部に光があると言った。そこには空間があると。たしかに彼には、外部の状況に左右されない内面がある。聖書に書かれていなくとも、内心で従うべき基準を持っている。
どいつも気に食わない男だが、俺にはないものを持っている。
俺はどうだ。フォカスの事情によって生きてきた人間でしかない。帝国のために働いてきたつもりだったが、実際には一人の独裁者の下で力を振るっていただけだ。驢馬よりも愚鈍で、絵描きのように正確でもなく、鹿のように温かい心臓を持たない。
「俺は、このまま死を甘受するのだろうか」
犬は口の中で小さくつぶやいた。
そして、一睡もできないまま朝が来た。
パンテオンの内部に光が差し始めた。
オクルスから注がれた光によって、空間が生まれる。巨大な容積が生まれ、浮遊感が生まれ、精神の宿る場所が生まれた。
そこで初めて犬は理解した。建築は、こんな瞬間のためにあるものなのだと。
外界がどれほど野蛮で残酷で、移り気で、不条理に満ちていても、この空間は朝が来ればこれほどの美しさを確実に見せる。この空間は、この世界で最も確実で、信用に足るものを写し取ったものなのだ。それは、人の内面だ。
人は自分の内部に空間を作る。つまり、小宇宙を。揺れ動く世界で生き続けるために必要な秩序を。鹿はそれを火と言った。絵描きはそれを規則というだろう。
犬は思った。俺の中には蝋燭もからくり仕掛けもない。俺は空っぽのまま、フォカスの影として生きてきた。しかし、今はこうして自問自答するだけの隙間が、光の差し込む隙間がある。それがつまり、空間というものではないか。
そして俺の空間はまだ、満たされることを求めている。
パンテオンの扉が開く。そこには鹿がいた。
「よく眠れましたか」
「ああ、生き返った気分だ」
そして犬は立ち上がった。
「どこかで、馬を得られる場所はないか」
「貧しい人々が集まる市場が南の街外れにあります。あなたの装飾具のどれか一つでも金に変えれば、弱い馬が買えるでしょう。――逃げるのですね」
「俺は、生きるのだ」
そう犬は言った。
「俺は空っぽだった。自分が空っぽだということすら分からなかった。しかし今は、空間を見つけた。この空間を膨らませたい。意味のあるもので満たしたい。いや、満たされなくても、この身の奥に開いた空間を守りたいのだ」
オクルスの光が次第に強まり、パンテオンの中は明るくなった。犬は扉の外に踏み出した。外は明るいが、引き続き一歩先も見えない暗闇の世界だ。しかし彼の中には空間が、光が、新しい目があった。
犬は振り返らずにパンテオンを後にした。
少しでも本書に興味を持たれた方は、ぜひご登録ください。
※2022年1月からnoteにて連載予定!
※()内は物語上の設定と舞台となる建築です。
「瞳の天蓋」(610年、ローマ、パンテオン)
西洋史の古代が終わり、中世の動乱が高まっていく最中の7世紀ローマ。パンテオンはキリスト教の聖堂へと転用され、破壊と殺戮の時代を生き延びていく。その空間に魅せられ、不条理な世界で神の存在を問い始める兵士の物語。
「草と土くれ」(1599年、京都、妙喜庵待庵)
江戸幕府成立前夜、秀吉亡き後の政治的混乱の渦中にある16世紀末の京都。千利休が結んだ待庵は一度解体され、妙喜庵へと移築されて侘び茶の精神を後世に伝える。その土壁を塗る中で人生への悲観から立ち直り、次世代に残せるものを見出す職人の物語。
「火の鳥の鉄の骨」(1906年、奈良、東大寺金堂)
西洋文明との衝突により文化・社会が大きく揺れ動き始めた明治時代の奈良。歴史上2度の再建を経た東大寺大仏殿は、西洋式の鉄骨トラスにより倒壊の危機を免れる。その不完全な姿を憎み、3度目の炎上と再建を妄想してしまう学生の手記。
「白い方舟」(1940年、ポワシー、サヴォア邸)
ドイツ軍に侵攻・占領され、日常を脅かされる第二次世界大戦中のポワシー。サヴォア邸はドイツ軍の倉庫などとして使われ、荒れ果てた姿で戦後まで生き延びる。その誕生から荒廃、そして復活に至るまでの経緯を半ば呆れつつ眺めた修理工の物語。
「怪獣たちの夜」(1963年、東京、代々木競技場)
東京五輪を間近に控え、活気と欲望に満ちた高度経済成長期の東京。日本の建築デザインと建設技術の粋を集めた代々木競技場は、今まさに建造されている。夜中もその現場で働く父を訪ね、巨大な仕事の美と暴力性を同時に感じる少年の物語。
銀の祈り(2001年、ウィチタ、ウィチタハウス)
好景気が続き、国際化と多様化の時代を本格的に迎えつつある21世紀初頭のウィチタ。フラーによる未完の発明住宅ウィチタハウスが近代建築愛好家グループにより復元される。その懐古的な未来のイメージに浸り、社会の多様化に戸惑う白人中高年グループの物語。
「幻野の家」(2002年、東京、自由学園明日館)
雑居ビルと住宅が立ち並び、どこか猥雑な雰囲気が漂う1970年代の東京・池袋。60年前の緑豊かな田園地域は今や完全に都市化し、自由学園明日館だけが往時を忍ばせる。その場所で少女時代を過ごし、震災や戦争で変わる街を見つめ続けてきた老女の一人語り。
坂道の詩人たち(2025年、シアトル、シアトル中央図書館)
アメリカ全体で保守化が進む中、不法移民を保護する聖域都市であり続ける現代のシアトル。市民サービスの中核を担うシアトル中央図書館は、移民に働き口や学習機会を提供している。そのプログラムによって生計を立て、英語を学びながら居場所を獲得していく移民の物語。
星々の卵(2032年、大阪、ニュートン記念堂)
公共施設や自治体の統合整理が進み、公的な新築プロジェクトが激減した近未来の大阪。VRで再現されたニュートン記念堂の中には、実現しなかった設計案が蓄積されている。その中で無数のアンビルトに触れながら、社会的な建築家を志し続ける若者たちの物語。
水面(2053年、ヴェネツィア、サン・ジョルジョ・マッジョーレ聖堂)
海面上昇と異常気象により、街路や広場がほとんど水没してしまった近未来のヴェネツィア。サンジョルジョ・マッジョーレ聖堂も床まで浸水し、水上に浮かぶような姿を見せている。永遠不変だったはずの地面を失ったその姿に思いがけない美を発見する文化財修復士の物語。
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。