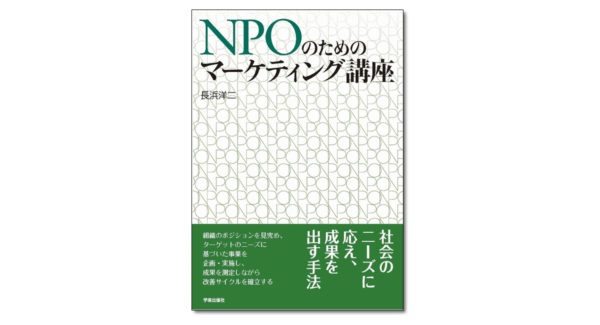公務員のためのマーケティング講座
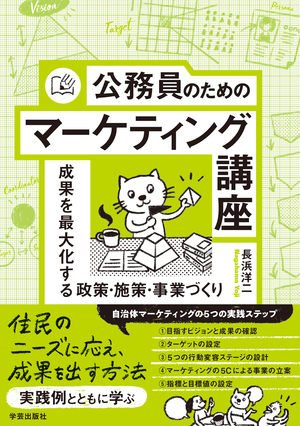
内容紹介
5つの実践ステップを実例と共に学ぶ入門書
厳しい財政状況や人手不足の中、限られた経営資源をもとに、実施する事業の成果を高め、多様化した住民ニーズや災害に迅速かつ柔軟に対応していくための有効な手段が「マーケティング」だ。マーケティング戦略の5つの実践ステップと、マーケティングの実効性を高めるためのコーディネーションを実例とともに学ぶ入門書。
長浜 洋二 著
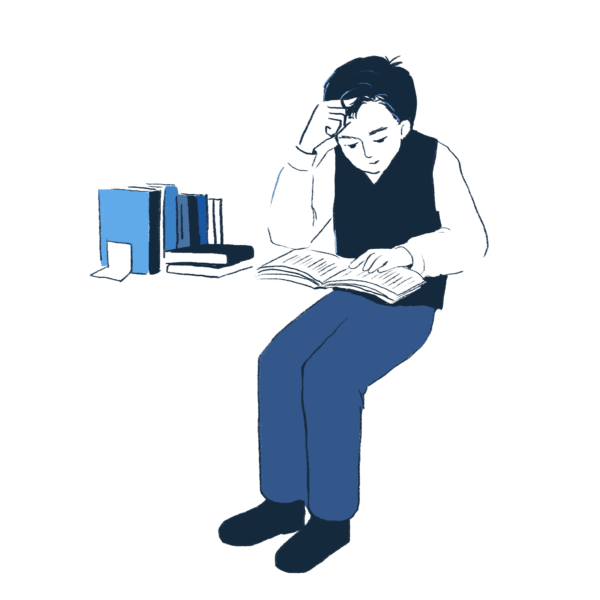
| 体裁 | A5判・200頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2400円+税 |
| 発行日 | 2025-05-25 |
| 装丁 | テンテツキ 金子英夫 |
| ISBN | 9784761529314 |
| GCODE | 5711 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| 関連コンテンツ | 試し読みあり |
| ジャンル | 自治体・自治・都市政策 |
ログイン
新規登録
まえがき
第1章 公務員にとってのマーケティングを理解する
1.公務員にもマーケティングが必要な理由
2.企業との違いにみる自治体の特徴と社会的役割
3.自治体マーケティングの4つの特徴
4.自治体が目指すのは住民のウェルビーイング
5.公務員にとってのマーケティングの定義
6.自治体マーケティングの5つの実践ステップ
<Tips>京都市:観光需要を抑制するディマーケティングの実践
<Tips>横瀬町:「ひと」を中心としたウェルビーイング指標の設定
第2章 自治体マーケティングの5つの実践ステップを学ぶ
◎ステップ1 目指すビジョンと成果の確認
1.「北極星」の役割を果たすビジョン
2.ビジョンの実現に向けた目的と手段の整合性を確認する
3.ビジョンの実現には住民の関わりが不可欠
〔ポイント解説〕政策体系の目的と手段の整合性を押さえる!
<Tips>町田市:多様な切り口の市民参加によるビジョンづくり
◎ステップ2 ターゲットの設定
1.ターゲット=「全住民」では誰にも伝わらない
2.ターゲット設定における4つの特徴と留意点
3.ターゲットの絞り込みとペルソナの作成
〔ポイント解説〕ペルソナを作成してターゲットの解像度を上げる!
<Tips>和気町:移住サイトを活用したターゲットとの関係構築
<Tips>福山市:人口減少対策に向けた9つのペルソナ設定
◎ステップ3 5つの行動変容ステージの設計
1.行動変容を描いてゴールへの道筋を明確にする
2.基本となる5つの行動変容ステージ
3.行動変容ステージ設計の留意点
〔ポイント解説〕成果を生み出す主体になりきって行動変容を描く!
<事例>春日部市:シビックアクションの推進に向けたステージ設計
◎ステップ4 マーケティングの5Cによる事業の立案
1.事業づくりの枠組みとなる「マーケティングの5C」
2.マーケティングの5Cで行動変容を後押しする
3.価値(Customer Value):機能・感情・社会的価値を提供する
4.コスト(Cost):行動を阻害する負担を軽減する
5.コミュニケーション(Communication):双方向を意識する
6.利便性(Convenience):手段や方法、時間や場所を工夫する
7.快適さ(Comfort):人・物的環境・プロセスに配慮する
〔ポイント解説〕相手の反応を見ながら、タイムリーに背中を押す!
<Tips>千葉市:呼び出し番号のプッシュ通知で時間コストを削減
<Tips>鴨川市:使いやすさを追求したホームページのユニバーサルデザイン
<Tips>甲府市:ひきこもり相談におけるメタバースの活用
<Tips>葉山町:公式Instagramの活用を一歩進めた関係づくり
<Tips>宇都宮市:AIを活用した暮らしに関する質問の自動応答
<Tips>今治市:移動市役所の巡回で交通アクセスの不便を解消
<Tips>川崎市:出前講座で住民との顔の見える関係づくり
◎ステップ5 指標と目標値の設定
1.目標・現状・ギャップの考え方
2.自治体におけるマーケティングの目標と指標
3.目標値の設定により到達地点を明確にする
4.指標と目標値の設定における課題
5.SMARTゴールを活用した指標と目標値の設定
6.行動変容とマーケティングの5Cとの関係性
〔ポイント解説〕納得感のある指標と目標値がヤル気を高める!
<Tips>世田谷区:バックキャスティングで活動と成果の指標を設定
第3章 マーケティングに不可欠なコーディネーションを学ぶ
1.自治体マーケティングに求められる協働と連携
2.公務員は多様な主体をつなぐ「コーディネーター」
3.PDCAサイクルを活性化するコミュニケーションの実践
4.公務員に不可欠なファシリテーションスキル
5.実務に活かすファシリテーションの基本的な技法
6.ファシリテーターの「やり方」と「あり方」
〔ポイント解説〕相互理解の促進により協働や連携を実現する!
<Tips>高島市:寄付金付き商品を媒介とした官民連携の取り組み
<Tips>豊明市:ビジョンと課題の共有による協働のチームづくり
<Tips>生駒市:住民主体のまちづくりを促す戦略的ワークショップ
<Tips>豊田市:対話を可視化するグラフィック・レコーディング
【参考】 自治体マーケティングの5つの実践ステップ作成例
1.地方創生における移住定住の促進【連携:空き家バンク】
2.経済活性化に向けた観光客の誘致【連携:民泊】
3.若者の就労支援と自立の促進【連携:引きこもり家族支援】
4.青少年育成と非認知能力の向上【連携:高齢者の生きがいづくり】
5.住民主体の景観まちづくり【連携:観光まちあるき】
6.協働による防災まちづくり【連携:親子向け防災啓発】
あとがき
21世紀に入り、社会全体の価値観が経済成長や物質的な豊かさではなく、自分らしさや個人の幸せなどの精神的な豊かさや自然環境との調和へと大きく変わりつつあります。このことを裏づけるかのように、書店にいけば資本主義のもたらした弊害とともに、その限界や代替システムを訴える著作がずらりと並ぶようになりました。日本だけでなく世界全体でみても、時代が大きな転換点を迎えていると言っても過言ではありません。
こうした現代の状況を別の角度から捉えたのが、VUCA(Volatility[変動性]、Uncertainty[不確実性]、Complexity[複雑性]、Ambiguity[曖昧性])という言葉。もともと米陸軍で使われ始めた造語で、先行きが不透明で将来の予測が困難な状況を表したものです。つまり現代社会は、未来のことが予測できない、これまでの解決策や事例が通用しない、問題の把握や問題構造の見極めが難しい、関係者間で見解がズレるといった特徴があり、結果として利害対立は大きくなり、合意をつくりながら解決に向かっていくことが非常に難しい時代だということです。実際に、2019年末に発生した新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナへの侵攻、世界全体に大きな影響を及ぼしている中国の経済政策や安全保障政策、気候変動や相次ぐ大規模自然災害など、VUCAの時代であることを実感するような出来事が世界の至るところで発生しています。まさに世界的規模で、先が見通せず、非常に不安定な時代に私たちは生きているのです。
課題先進国と言われる日本に目を転じてみると、諸外国に先駆けて人口減少や少子高齢化が進んでおり、貧困問題、教育格差、自然災害、労働問題、多文化共生、デジタル化など、様々な社会課題に溢れています。平成のバブル崩壊から「失われた30年」と言われる経済停滞が続いており、2024年の世界時価総額ランキングでトップ50入りしているのはトヨタ自動車のみという結果で、企業もその存在感を大きく失っています。また、日本はG7先進国中で自殺死亡率が最も高く(『令和5年版自殺対策白書』参照)、世界幸福度ランキングでもG7先進国中で最下位の51位となっており(『World Happiness Report 2024』参照)、社会全体が自信や活力を失っているようにもみえます。このように、決して先行きが明るいとは言えませんが、世界に先駆けて高齢化し、もがきながらも様々な社会課題の解決に向き合い続けている日本だからこそ、「社会課題解決先進国」になれるのではないでしょうか。そして、その中心で舵取り役を期待されているのが自治体であり、公務員なのです。
とはいえ人口減少や少子高齢化、長引く不況の影響は自治体においても例外ではありません。税収の減少や社会保障費の増加、公共施設の老朽化対応などによる厳しい財政状況や、職員定数の削減による慢性的な人手不足という課題を抱えています。さらに社会の価値観やライフスタイルの変化により多様化した住民のニーズや、自然災害などの不測の事態への迅速かつ柔軟な対応が求められており、従来と同じ感覚ややり方で自治体を経営することはできません。こうした状況の中、限られた経営資源を基に実施する事業の成果を高め、自治体が社会や地域のニーズに応えていくための1つの有効な手段が本書で解説する「マーケティング」なのです。
〈本書の構成〉
本書は3章で構成されています。第1章では、公務員にとってのマーケティングについて、その概要を解説します。マーケティングは一般的に企業における経営実務であり、自治体の業務には関係ないものと思われがちです。あらためて、マーケティングとはどのようなもので、公務員の日々の業務にどのような意味をもたらすものなのか、どのように実践していけば良いのかなどについて理解を深めていきます。
第2章は本書の中心をなすもので、具体的なマーケティング戦略の企画立案を5つの実践ステップに分けて解説していきます。自治体が掲げる地域の将来像であるビジョンや政策分野ごとの目指す成果を確認した上で、ターゲット(対象者)を設定し、その意識や行動の変容を描き、具体的な事業とその指標や目標値を企画立案していくという、一連の流れを学びます。
第3章では、マーケティングの実効性を高めるために公務員に求められるコーディネーションの重要性について触れていきます。一般的なマーケティング書籍ではあまり取り上げられることがない視点でしょう。VUCAの時代を迎え、協働や連携による社会課題の解決が求められる中、どのように自治体内外の利害関係者と意思疎通を図っていくのかは、マーケティング戦略の計画から実行に至るまで、その成否に直結する極めて重要なポイントです。日々の業務におけるコミュニケーションやファシリテーションスキルの向上は公務員にとっても関心が高いのではないでしょうか?
マーケティングに馴染みのない公務員には最初から順番に読み進めていくことをお勧めしますが、気になったところから読んでいただいても構いません。自分の担当業務と照らし合わせながら、どのようにマーケティングの視点を取り入れることができるか、新たな気づきや学びを得たり、既に実践していることを確認しながらお読みいただければと思います。
〈本書を読み進めるにあたっての注意点〉
タイトルにある「公務員」は幅広く捉えることができますが、本書では基礎自治体の市町村を中心に、広域自治体の都道府県に従事する地方公務員までを主たる対象として想定しています。総務省の『令和6年地方公共団体定員管理調査』によると、令和6年4月1日現在、地方自治体に従事する公務員の数は市町村等が約138万人、都道府県が約143万人の合計約281万人で、そのうち約94万人が一般行政職です。これだけの数の公務員がマーケティングの考え方を理解し実践するようになったとしたらどのような社会が実現できるのか、想像しただけでワクワクしてきます。
より具体的な読者ターゲット層としては、「働き始めてから10年程度が経ち、異なる部署を3つ程度経験し、地域や所属する自治体の実態を俯瞰的に捉えられるようになり、主担当者としてさらに責任ある立場で活躍することが期待されているような公務員」を想定しています(個人差がありますので、この定義に捉われる必要はありません)。
このことを踏まえ、本書では、地方自治体が策定する総合計画の中でも、大半の公務員の日々の業務に直接影響のある「実施計画(事業)」のレベルを中心に取り扱っていきます。自治体によってこの3つの階層の解釈や整理の仕方は異なりますので、それぞれの実態に合わせてご理解ください。
なお、本書で解説するマーケティングの基本的な考え方やその実践は、地方自治体の公務員に限らず、国家公務員や自治体の外郭団体などでも活用できる内容になっています。是非、最後までお読みいただければ幸いです。
本書が、自治体が実施する事業の効果や効率をこれまで以上に高めるとともに、地域や社会の課題を解決し、新たな未来を創造していくための道標となることを心から願っています。
長浜洋二
開催が決まり次第、お知らせします。
メディア掲載情報
公開され次第、お伝えします。