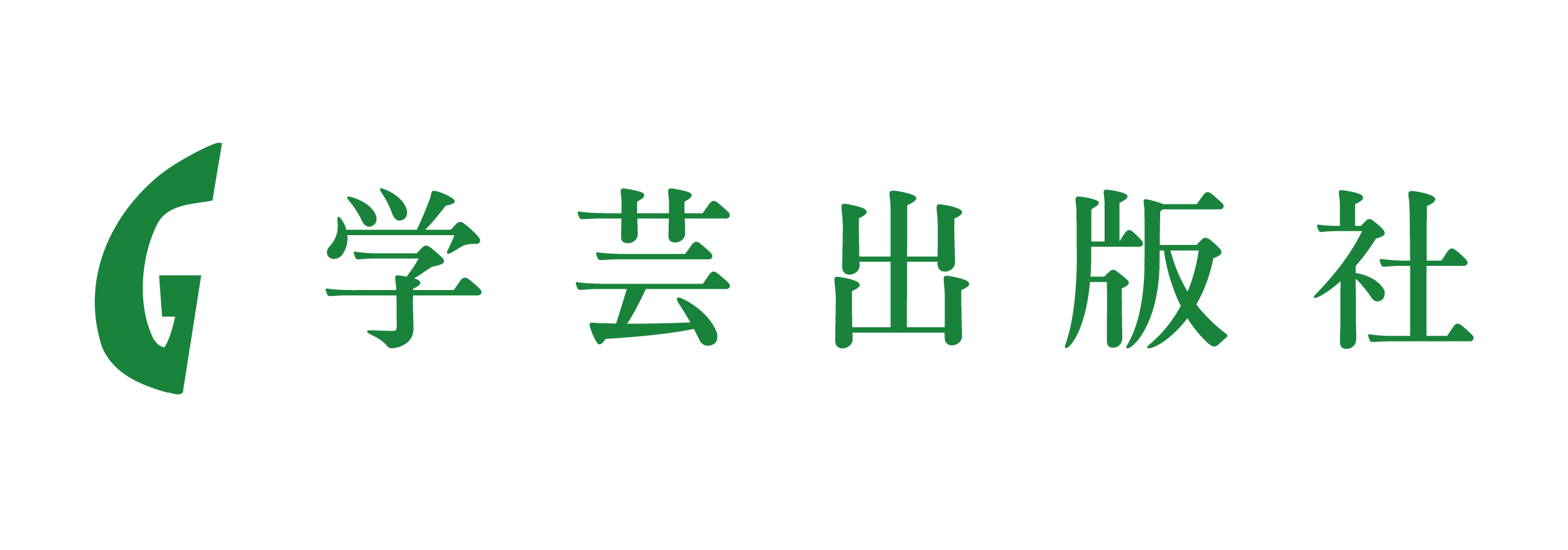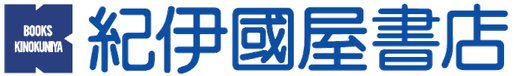ソーシャルアート

内容紹介
障害のある当事者、福祉施設スタッフ、アーティスト、プロデューサー、音楽家、ダンサー、演出家らが実践する「アート×福祉×コミュニティ×仕事」25の現場。アーティストの原動力、スタッフによる創作のサポート、表現の魅力を発信する仕掛け、新しいアートの鑑賞法、創造的で多様な仕事づくりなど多彩に紹介。
体 裁 四六・304頁・定価 本体2400円+税
ISBN 978-4-7615-2630-6
発行日 2016/10/01
装 丁 藤田康平(Barber)
はじめに ─社会を変えるアートの実践 森下静香
1章 障害のあるアーティストはなぜ表現するのか
1 見えない世界を面白くするアート 光島貴之×吉岡洋
2 自分の身体を再発見するダンス 森田かずよ×大谷燠
3 自分らしく社会とつながる思考と表現 ウルシマトモコ×中津川浩章
4 山野将志を表現へ導くもの ─欲求・チャレンジ・プライド 中島香織
2章 日常がアートになる場のつくり方
1 生き方はひとつじゃないぜ。─スウィング 木ノ戸昌幸
2 生きることのおかしみを語りあえる場所 ─ハーモニー 新澤克憲
3 セルフトートが生まれるアトリエの日常から ─やまなみ工房 山下完和
4 すべての人が歓待されるホーム ─カプカプ 鈴木励滋×栗原彬
3章 違いの共存から生まれる身体のアート
1 境界を消し共鳴を起こすダンス 佐久間新×大澤寅雄
2 生き(き)るためのアクション 五島智子×富田大介
4章 新しい関係を生みだすアート
1 異質な価値観を楽しむ即興音楽 ─音遊びの会 沼田里衣
2 ひとりひとりの物語を回復する舞台 ─みやざき
まあるい劇場 永山智行
3 障害者とアーティストが共振する ─アートリンク・プロジェクト 田野智子
column 社会を包摂するアーツマネジメントへ 中川真
5章 地域とつながるサードプレイスの運営
1 障害の価値観を超えるオルタナティブな場 ─たけし文化センター 久保田翠
2 多様な人のやりたいことを形にする ─片山工房 新川修平
column サード、セーフ、そしてノープレイス ほんまなおき
6章 自由な感性でアートを見る
1 目の見える人と見えない人の鑑賞の場で発見されること─視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ 林建太
2 障害者アートで開く共創の学びの場 川上文雄
3 アートをもっと身近にする ─プライベート美術館 岡部太郎
column すべての人に美術館を開く ─アクセシブル・ミュージアム 井尻貴子
7章 アートで新しい仕事をつくる
1 福祉と社会の関係を多様にする ─工房まる、ふくしごと 樋口龍二
2 社会に新しい仕事をつくる ─Good Job!プロジェクト 森下静香
3 アートによる復興支援 ─Good Job!東北プロジェクト 柴崎由美子
column 初期の障害者アートを支えた企業の支援 若林朋子
おわりに ─アートもいろいろ、社会化もいろいろ
播磨靖夫
はじめに ─社会を変えるアートの実践
一人一人の可能性に光をあてること。関わりあうなかで生まれる楽しさ、存在の不思議さ、生きることの重みを伝えること。そして、私たちを取り囲む常識や一方的な見方を変えていくこと。
ここに集まった25の現場からの報告は、アート、福祉、仕事、関わり、場のあり方を表現と身体を通して考え、自分のなかにある境界を越え、周囲の世界をも変えていく実践のドキュメントである。どの活動も最初から明確に目指す姿があったわけではなく、伝えたい、この状況を変えたい、なんとかしたい、という切実なニーズや希望から始まり、人を巻き込み、つながり、また実践していくという試行の繰り返しから生まれている。
「障害者アート」という時、結果としての作品が注目されることが多い。しかし、本書で紹介するように、障害のある人とアートの活動に取り組んでいる人の多くは、豊かに生きること、幸福であることへの願いや、それを実現できる環境や社会はどうあるべきかという問いと、アートの活動を決して切り離してはいない。「障害」という窓を通して、既成の概念を疑い、社会を変えていく、アートの実践が、本書における「ソーシャルアート」である。
本書には多様な担い手が登場する。障害のある当事者、社会福祉施設の施設長、NPOの代表、アーティスト、アートプロデューサー、音楽家、ダンサー、演出家、研究者。彼らは、一つの肩書きにとどまらず何役もの役割を担っている。そして分野も、福祉、アート、音楽、ダンス、演劇、デザイン、ソーシャルビジネスと多岐にわたりかつ横断している。今、障害のある人のアート活動はジャンルを越えて、社会のなかでさまざまな役割を果たしている。
本書で紹介する実践には、いくつかの核心が基調としてある。
第一に、障害のある人と共に、福祉の概念を編み直す実践である。根底にあるのは、それぞれの現場や地域で、目の前にいる障害のある人や家族、支援者、ボランティア、アーティストらとの関わりのなかで、自分たちの概念や表現が絶えず更新されていくことを(時には格闘しつつも)楽しむ姿勢である。それは、アートという技術を通して、人が生きることの原点に立ち返ることでもあり、社会全体の価値観や意識を問い直すことでもある。
第二に、現場で発見したヒント、または現場にあるさまざまな課題を個人的な関心や自分たちの世界にとどめずに、表現や発信することを通して「社会化」することを目指している。共通するのは、障害は個人に属するものではなく、その人が社会に出ていく時に感じる障壁であり、人と人、人と社会の間にあるという感覚であり、変わらなければならないのは、既存の制度や社会の側であるという意識である。
第三に、それぞれの専門性、領域を越えて異なる文化や慣習を持つ人と果敢に対話し、学び直し、活動を変化させていくことを厭わない。アートであっても、福祉であっても、その専門性を棚にあげて、自分の言葉、自分の表現、自分の行動で関わっていく。ケアする人/ケアされる人、アートをつくる人/鑑賞する人、障害/健常などの二分法、境界を越える挑戦でもある。
第四に、何より現場にいる人たちの存在や思いがエネルギーとなって活動を後押しする力となっている。そこに必要としている人がいるからこそ、当事者、そしてその必要性に気づいた市民が起点となり、活動が始まる。そして、信頼をベースとしたつながり、コミュニティが生まれ、活動が継続している。
そして第五に、多くの活動が現在進行形で、活動の途上にある。社会に向きあう活動も、アートの実践も、関わる人や社会の変化のなかでかたちを変えていくだろう。
本書は、それぞれの活動の実践のノウハウや一つの方向性を示すことを目的とはしていない。常に新しい表現を求め、葛藤しながらも前に進む表現者。表現すること、存在することが歓待され、多様な人に開かれた地域の居場所。価値観を揺さぶられる主体的な鑑賞の方法。「モノ、カネ、制度」ではなく、「人、生活、いのち」から発想する新しい仕事や働き方。こうした実践者たちの考えや経験知を自らの活動のきっかけにしてもらいたいと考え、編んだ本である。
改めて思う。「福祉」も「障害」も、その社会的なイメージを変えなければならない。その既存の概念も偏見も、領域も越えていかなければならない。そのために、アートの「想像する力」と「創造する力」を活かしていきたい。本書にあるような一つ一つの小さな実践が積み重ねられ、今はまだない道を切り拓く。そのことが新しく道を拓いていく人のヒントになればと思う。
一般財団法人たんぽぽの家 森下静香
おわりに ─アートもいろいろ、社会化もいろいろ
いったい幸福とは何か。豊かさとは何か。価値ある生き方とは何か。私たちは今立ち止まり、考え直さなければならない。
今日の最大の問題は、貧富の格差が開く経済的貧困、弱者が排除される社会的貧困、中央文化が支配する文化的貧困、他者の痛みに向きあわない精神的貧困である。
これらの貧困は社会を分断し、対立を生み、人々を孤立させている。これらを解消するためには「ソーシャル・チェンジ」を図らなければならない。
だが、どんな理想も実現のプロセスが示されないものはむなしい。ところが、今やアートがそれを示し始めている。それもハイアートから離れた「遠いところ」「弱いところ」「小さなところ」で存在感を増している。
私たちは1995年に「アートの社会化」「社会のアート化」を掲げ、ABLE ART MOVEMENT(可能性の芸術運動)を提唱した。
まず手がけたのは価値が低く見られていた「障害者アート」を新しい視座で見直すことだった。そして障害のある人たちの能力を高めると同時に、社会的イメージを高める取り組みを始めた。
今や日本では「障害者アート」はブームのように盛り上がっている。それは「アールブリュット(生の芸術)」として国が推進していることがからんでいる。
「障害者アート」は「アールブリュット」と決めつけ、一部の美術館の学芸員、美術記者、大学の研究者までもが何の疑いもなく追随している。アートの社会化にもいろいろあるということか。
私たちが「違って独特」の表現に強く惹かれるのは、理解ができない部分(語りえぬもの)にある。だが、西欧の美術(史)しか学んでいない人たち、つまり「知っているアートしか知らない」人たちは、その美術観が揺らぎ、美術の見方が根底から怪しくなっている。
障害のある人たちの生き方、その表現を長く見てきた経験から言えば、岡倉天心の「東洋の美は不完全の美である」というのに共感を覚える。「望月よりも欠けたるがよし」とする日本人の美意識に由来するからだ。
また、民芸の思想家、柳宗悦の「不完全を厭(いと)う美しさよりも、不完全をも容(い)れる美しさの方が深い」にも共鳴する(柳宗悦「美の法門」)。この不完全さが未知の衝動を与え、一つの美術システムに安住している人たちを突き動かしている。
「アールブリュット」の動きはグローバリゼーション(世界化)の流れと言えるだろう。私たちがABLE ART MOVEMENT を始めた1995年といえば、ユネスコが文化のグローバル化に対して勧告を出した年でもある。それは文化の画一化を危惧したもので、多様性、身体性、地域性の尊重を訴えている。
障害のある人たちの表現をカテゴリー分けするのはなんでも二分する近代の名残でもある。
それには次のような問題点がある。いったん一つのカテゴリーに入れられると、そこから出られない。それぞれのカテゴリーは独立した別個のものと見なされる。時間とともに変化するものが扱えない。カテゴリー間にまたぐような事物の扱いが不得意である…など。
「存在が違って美しい」という言葉があるが、障害のある人たちの表現の特徴は多様であるということだ。一つのカテゴリーのなかに囲い込むのは、多様性を殺すということでもある。
哲学者の鷲田清一さんは朝日新聞のコラム「折々のことば」(2015年10月30日掲載)で多様性についてこのように言っている。
多様性の尊重には、一人ひとりが異なる存在であることが前提となる。人びとが数で一括りにされるところに多様性はありえない。人はその個別性においてこそ輝く。20世紀フランスの哲学者(エマニュエル・レヴィナス)は、だれかを別のだれかで置き換え可能と見るのは、人間に対する「根源的不敬」であるという。
「障害者」と一括りにし、個性ある表現を一つのカテゴリーに囲い込むのはまさに「根源的不敬」ではないか。
アートには人間の痛みに想像力を働かせ、生きる意味を考えるきっかけをつくる役割がある。それに気づいた人たちが今、日本でも活躍し始めている。彼らに共通しているのは、ロック世代かその影響を受けている世代。テクノロジーが社会を画一化していく時代にあって、ロック音楽が生まれた時代から変わらないもの、自分らしい生き方をしたい、という思いを持つ世代だ。
音楽を愛する若い世代が、自分らしい生き方の追求を根拠に、障害のある人たちの表現と向きあっている。生き方の画一化を拒む精神が「障害者アート」の新しい可能性を切り開いている。
2016年8月
一般財団法人たんぽぽの家理事長 播磨靖夫
評:細馬 宏通
(滋賀県立大学人間文化学部教授(コミュニケーション論))
「自分の知らない、自分のバリアを知ることから始まる」
知らないことだらけだ。
わたしはこの『ソーシャルアート』で紹介されているいくつかの活動は拝見したことがあるし、「音遊びの会」のメンバーでもある。実は、「障害のある人とアートで社会を変える」という本書のサブタイトルを見たとき、おおよそわかっていることを確認するつもりで読み始めた。しかし、それは全くの思い上がりだった。知らないことだらけなのだ。
たとえば、最初の光島貴之×吉岡洋の対談からしてそうだ。そこで、光島さんは、作品を作っていくうちにだんだん「目が見えない」ということ自体を押し出すやり方や「障害者アート」や「アール・ブリュット」という枠組に、違和感を感じるようになったのだという。それで、吉岡さんと考えるうちに「バリアフリー」ではなく「バリアコンシャス」ということばにたどりついた。それは単なるフリーからコンシャスへのことばの言い換えではなく、障害というバリアを取り除くという一方的な見方から、誰もが知らず知らずのうちに持っているバリアを意識する見方へという、いわばバリアを感じている主体の変更を促すような視点だ。
この本が次々と知らないことを提示してくれる要因のひとつは、執筆陣のバランスの良さだ。自ら動く人もいれば、共に動いている人、動く場所を作っている人もいる。動こうとするまさにそのときについて書いている人もいれば、動くまでに至るさまざまな生活の営みを書いている人もいる。動く場所をとりまく地域について考えている人もいる。絵画、音楽、演劇、ダンス、どんな動きに結実するかはそれぞれの人がどんな生き方を発見していくかによって違ってくる。多様性、というと収まりがよすぎる。わたしたちは何をやってもよいのではなく、何をやっても自分のバリアを意識することになる。自分の知らない自分のバリアがあること、しかしそこから始まる何かがあることを、この本は教えてくれる。