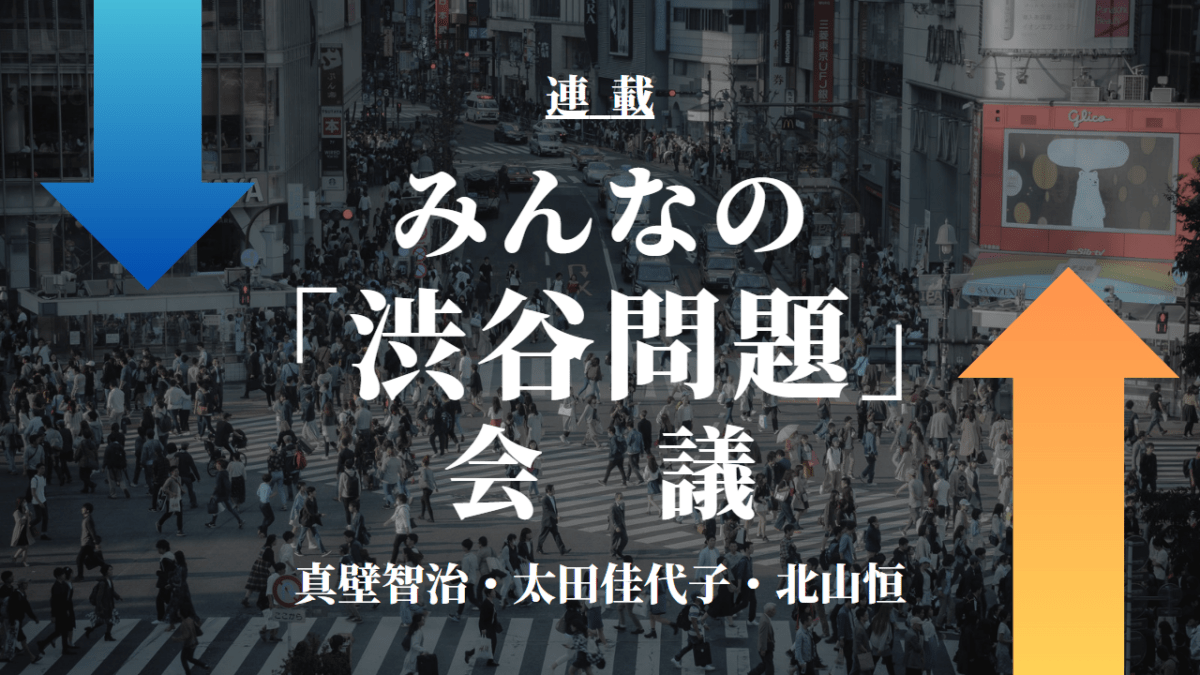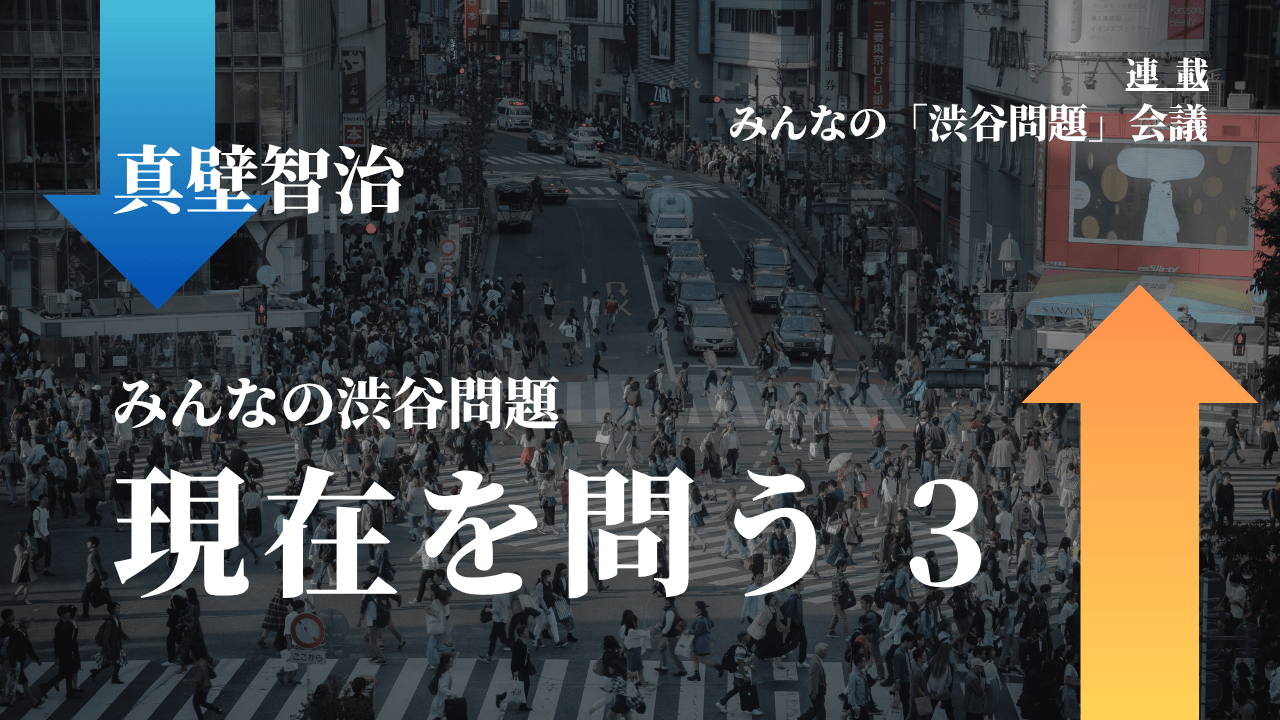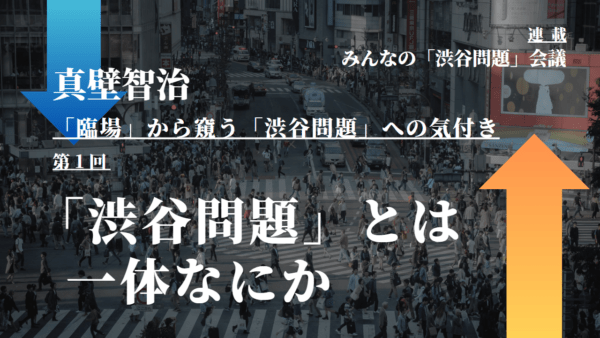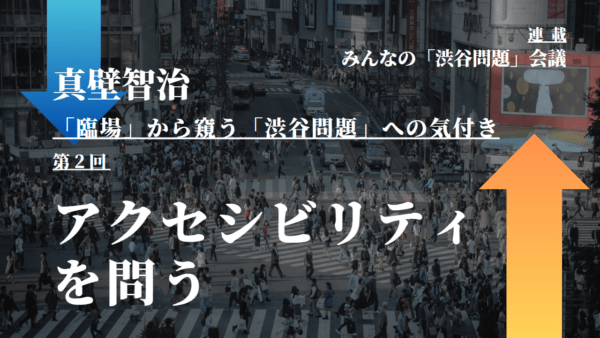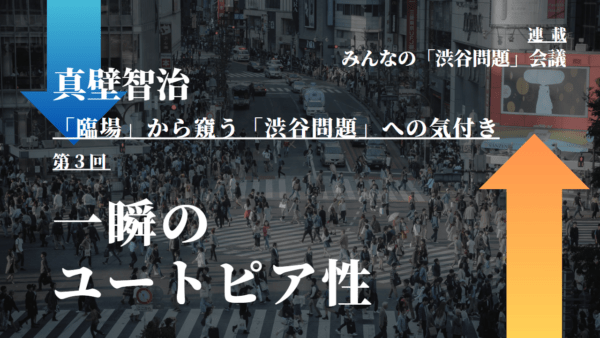みんなの渋谷問題 現在を問う3|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。
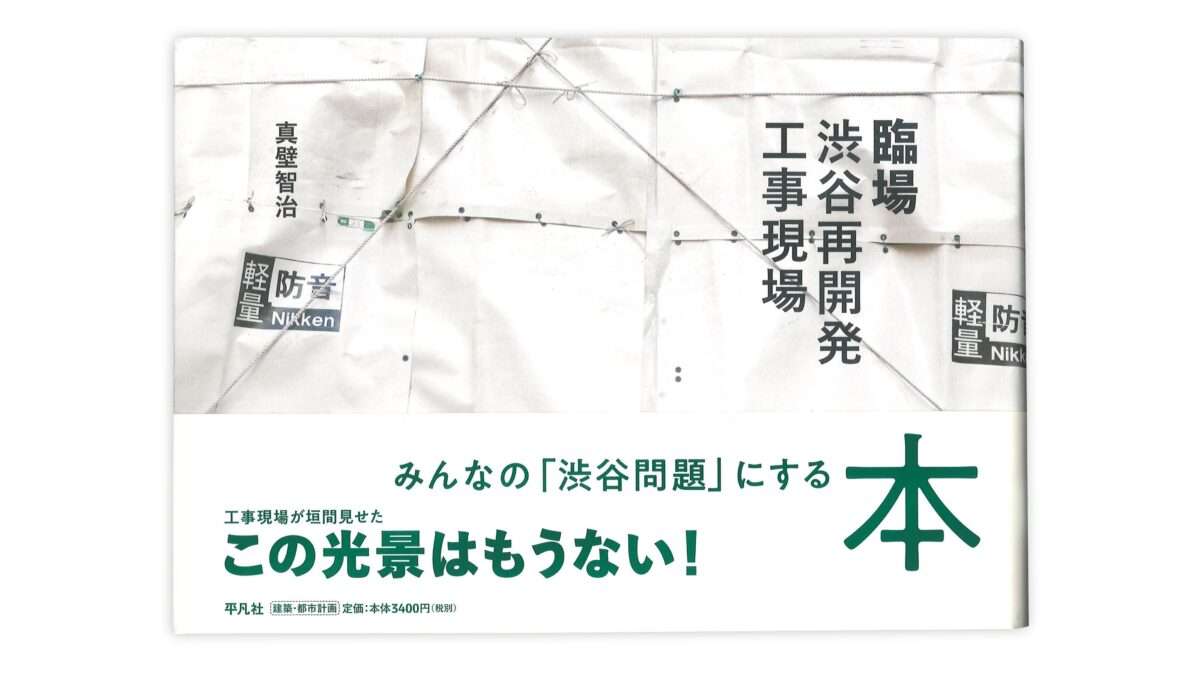
≪横にスクロールしてお読みください≫
谷底底部のウォイドインフラの行方
渋谷再開発には対象地域内での「アクセシビリティ」に於いて解決すべき大きな課題が二つあった。この二つの課題が渋谷に求めているものは極めて対照的で、象徴的なものになる。一つは国道二四六号線による渋谷の南北の分断化への改善。もう一つは渋谷の谷底底部地形を埋め尽していたJRと百貨店からの解放。いずれの課題も生来からの地形・地勢に対して人為的に加えられた構築物に依って生じて来た課題となるものであった。
前者は渋谷再開発での重点的な歩行インフラの整備として挙げられ、「アーバンコア」(垂直移動)と「スカイウェイ」(空中水平移動)の都市歩行装置が渋谷の南北分断化解消への切り札として展開される。
基本的に前者の課題は開発主体側にとっても、都市生活者側にとっても分り易く、改善への余地は納得のいくものであった。とりわけ渋谷を構成する地域の人々にとっては渋谷の南北分断化は致命的で一刻も早い改善が求められていたものだった。
その課題をクリアーにする為に歩行インフラとしての「アーバンコア」と「スカイウェイ」が設置される。そのいずれの都市装置も空中移動の為のものになり、渋谷での地上性も喪失してゆく。
それらは民間主導型都市開発に在っては公共貢献として規定され、渋谷再開発の正当性の最大の根拠となるものになっている。
それに引き換え後者は渋谷再開発が担うべき課題としての意識が前者よりは遥かに稀薄に感じられるのである。つまりは、公共性のある課題解決としての優先順位が前者よりも低いということなのであろうか。
そもそも後者の課題意識とは一体どの様なものであったのか。
なによりも後者の課題意識は前者のような目の前の公共性の改善、というものとは異なり生来の「渋谷らしさ」の根本となる都市資源、あるいは都市アイデンティティに連なる地形的資質の回復とその為の解放なのであった。当然この課題意識は最終的には渋谷の公共性を象徴するものになるのだが、開発主体側の問題意識が捉える「公共性」とはレベルが異なる。少なくともそれは目の前の利便さに貢献する公共的な共通利益を示すものではなく、渋谷がこれからも永く語られてゆく上での基盤となる公共的な資源(素地)を意識していて、渋谷の地上性とカオス性の象徴となるべきものなのだ。
現状では「スクランブル交差点」がインバウンド層などに観光化して注目されているが、本来的には谷底底部が担うべき地形の回復を基にした地上性とカオス性の獲得こそが渋谷再開発が自覚的に取組む計画的課題であったのではないだろうか。
以上述べてきた渋谷再開発が解決すべき二つの課題の所在を示したが、これらに取組んでこその都市緊急特区としての渋谷再開発なのである。
JR渋谷駅更新工事はこれまで改札の一括化が集中的に進む3Fに注目が集まってきたが、漸く接地階での工事の様態が活発になり始め、関心はもっぱら駅を巡る地上の在り様にフォーカスが移ってきた。
私たちが「工事」を通して期待する「計画」はやはり谷底を四方から自由自在に通り抜けられる駅舎の地上の「構え」なのである。それが窺えるのか。
そこに渋谷の地勢とパノラミックに繫がる新たな光景から皆が渋谷にいる、という共通利益を感じるに違いない。
現在は接地階の改札を出ると、南口・東口・ハチ公口への三方向の出口までのアプローチが分かり易くなり、各々の出口間を通り抜けられるようになってきた。
この事態は仮設工事中とは言え、四方から通り抜けられる駅舎の接地階計画を確信させるに充分なものがある。
しかも抜けられる通路が「コンコース」的な扱いに成るのが仮設工事からも読み取ることが出来る。
工事中の渋谷駅接地階の臨場からその様な手応えを感得していた矢先に、ネット上に渋谷再開発工事の日程がいよいよ終章へ、として開示された(完成予定の二〇二七年から大幅に遅れることになる)。
•渋谷の東西南北が地上やデッキ階でつながる歩行者ルートが完成→二〇三〇年
•「渋谷スクランブルスクエア」中央棟と西棟が完成→二〇三一年
•「ハチ公広場」の整備が完了→二〇三四年
私は渋谷再開発の早い段階から当該立地が谷底底部に位置するので、更新される駅舎そのものが接地階の四方への往来の障害になることなく、自由に四方に通り抜けが出来る駅舎の地上部の在り方が本計画の要になると再開発計画が話題になる時から常に思って工事現場を臨場してきたのである。いわば予断として「計画」を臨場してきたのである。
そうすることによって街の四方への移動が容易になり公共的利便性が高まるだけでなく、なによりもそれは谷底地形の本来の姿を目に見える形に還す、あるいは戻すことに最大の意味があると考えてきたからだった。それこそが地形のまち渋谷に於ける公共的アーバニズムの象徴となるものではないか。
その為には渋谷の本来の地形と共に東西南北に地上で自由に向え、そこにサイトスペシィフィックなパブリックライフが創出されたら素晴らしいと考えてきた。それこそが世界に誇れる地形を活かしたアーバニズムが体現することになる。
その為には如何に渋谷駅舎の接地階をどの様に抜き、ウォイドをつくるのかが計画上の重要な課題となってくる。これまでの工事現場の臨場からは接地階のピロティ空間化は粗ほ無い。
当初から駅舎更新計画に在って接地部・地上部の通り抜け方や四方への拡がり方が十全に計画としてスタディされていたとは思えないのである。
本来この場面ではデザインアーキテクトのヴォイド・インフラデザインへの手腕に期待したいところだが、この段階を見ても彼らが手を付け得る余地が在ったようにはまず思えない。
谷底底部から四方八方に拡がり、生来の地形が成りでパノラミックに蘇生するのを望んでいたから、本来は渋谷駅舎だけでなく、「渋谷スクランブルスクエア」を含んだ地上部のヴォイド・インフラが全体的に体現するのを期待するが、果してどの様になるのか。
「渋谷スクランブルスクエア」東棟は既に建設され稼働していて致し方がないが、せめて「アーバンコア」の接地部と駅舎のヴォイド・インフラとが軸線上に繫がるシークエンシャルなデザインが渋谷らしさの大きなポイントになってくる。
その為には駅舎のヴォイド・インフラの出入り口となるスキマとしての開口が都市に開かれたスキマとしてどの様にデザインされるのかに興味を覚える。
同様に、これから建設される「渋谷スクランブルスクエア」中央棟及び西棟の接地階でもどの様なヴォイド・インフラを構築しえるのか、デザインアーキテクトの関わりを見守ってゆくことになるが、そこでの主題はあくまで谷底底部への自覚的問題意識とその解放なのである。
駅舎接地階のスキマを通して渋谷を見通す、都市を見透す。生来の渋谷の谷底地形がたとえ「トリミング」された状態としてもスキマから窺う見透しの利いた視線の計画は渋谷のアイデンティティには不可欠な「アーバンデザイン」となるもので、それは決定的な渋谷の体験を形成するものとなる。
こんな重大なテーマをJRはどこまで認識しているのか。2Fのホームの整えや、3Fに集中する改札から再開発他施設への接続には極めて熱心だが肝心な駅舎と地上での接続意識は薄い。もっともこの問題は上位な計画意志決定機関であるデザイン会議(座長内藤廣)の見識にかかってくるべきものになるのだが。
私は渋谷再開発で特に問題だと強く感じてきたのは「デザイン会議」自体が極めて渋谷の谷底底部の地形の貴重な都市資源としての認識の低さであり、更にはそれを活かすアメニティデザインへの志向が欠如していることだ。この問題は渋谷の再生と共に再開発が取組むべき地形・地勢の再生なのである。(唯一の例外が「渋谷ストリーム」の接地部での渋谷川及びそれに面する建物裏側のエイジングした壁面の様相を借景にリバーサイドの小路と店舗が共振する谷底底部の地上性には渋谷再開発唯一のカオス感が漂っている)
こうした渋谷の地上性や接地性を全く欠く再開発はまさに地に足がつかない計画展開となっているのではないか。地に足がつかない都市再開発が示すものはなにか。
建築がその地上性や接地性を欠くと、そこでの場所性は周辺のコンテキストとは縁が切れ、不明にならざるをえなく、賑わいが得られたとしてもそこには場所性は定着しない。
大地から離れ上へ上へと床を拡張させるビッグネスには到底場所性の余地は接地階以外にはありえないのである。
つまりは渋谷再開発は過半が地上性との関わりを欠く為、場所性の創出が極めて困難な計画となっているものなのだ。施設内のコンテンツだけで場所が生まれるかのような幻想が吹聴されるが、とても長く根付く場所性を形成するものにはなりえないのは明らかだろう。
場所性を生まない渋谷再開発が渋谷にもたらす「渋谷らしさ」とは一体なんなのか、根本的に問わねばなるまい。


谷底底部とJRをつなぐヴォイド
(おわり)
連載記事一覧