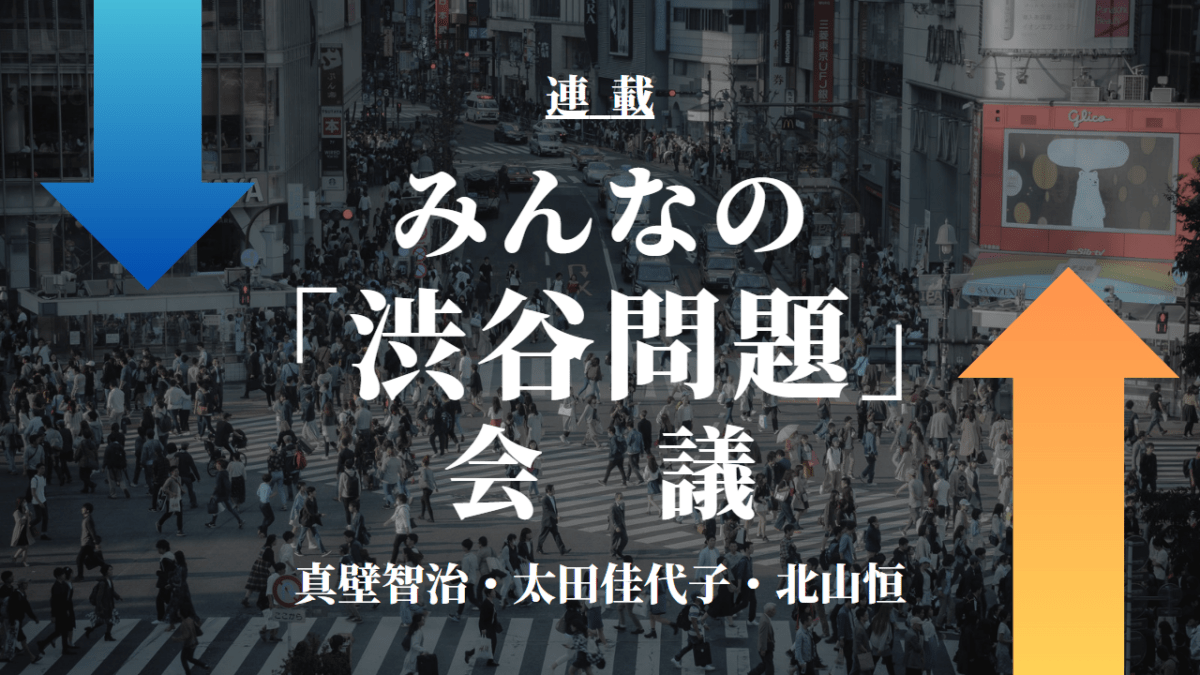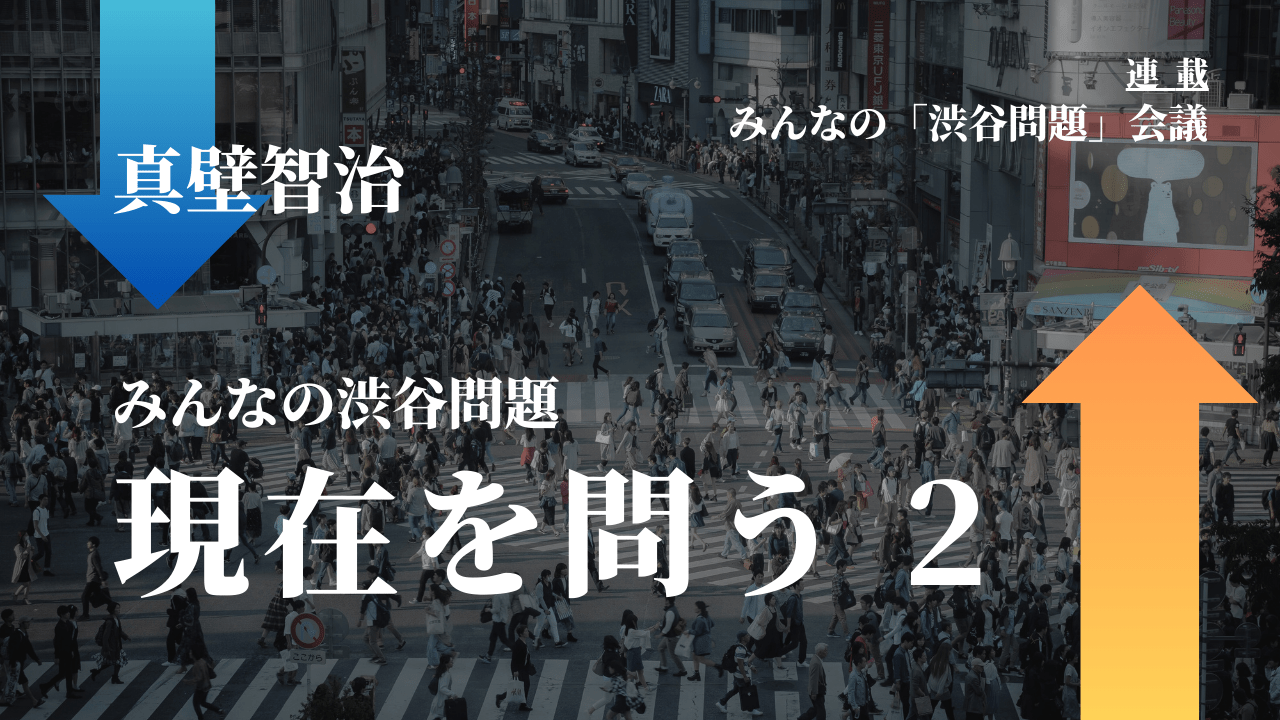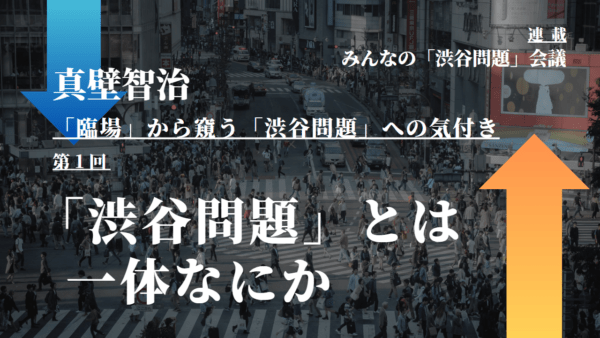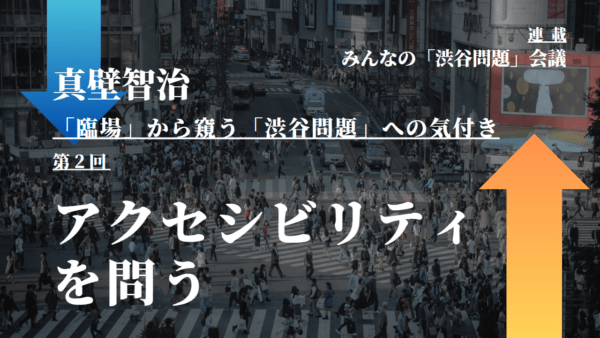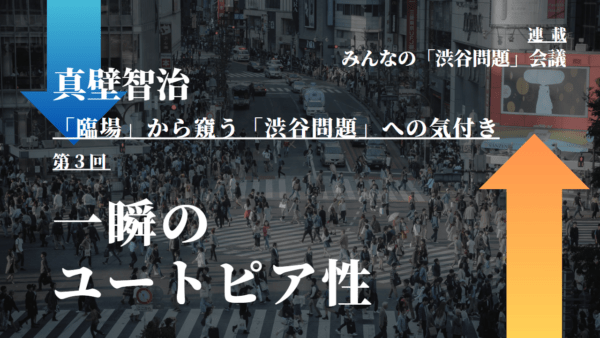みんなの渋谷問題 現在を問う2|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。
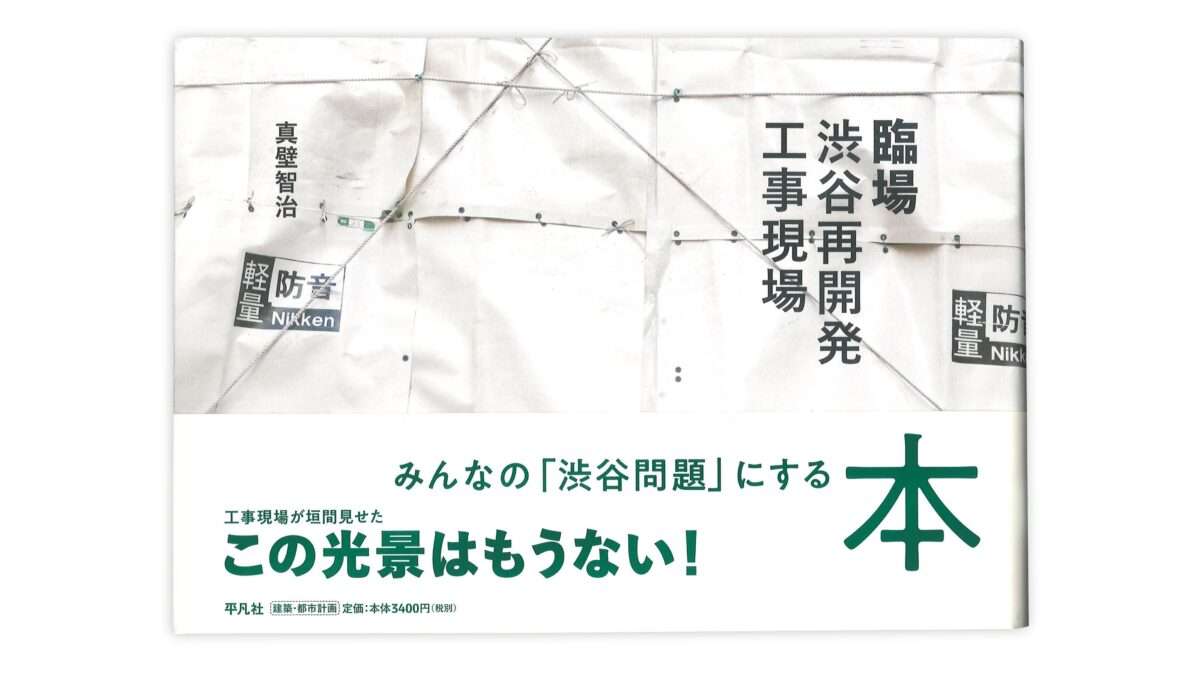
≪横にスクロールしてお読みください≫
「計画」を窺う臨場という方法
渋谷再開発工事現場も着工から一五年以上が経ち、計画予定の七・八割程が完成してくると、工事現場からの臨場の対象や主題も次第に違うものになり、渋谷問題の全体の輪郭が少しずつ見えだしてくる。臨場は再開発工事現場を事件現場と見立て、当初から民間主導型都市再開発計画が充分に開示・衆知されていない裡で、その工事現場から「計画」を窺ってゆくことがその最大の根拠となるものであった。従って、計画を事件として読み解いてゆく臨場は極めて身体的思考を伴うことでもある。
計画が生み出すメガ・スケール感を躯体が立ち上がる段階でいち早く実感することも工事現場の臨場が担う重要な課題でもあった。計画のスケールを事件として身体的に感得することである。
ここまでを渋谷再開発工事現場から臨場する第一ステージと捉えることが出来る。
これまでの官主導型の都市再開発では、計画の事前公開・事前検討が市民社会に対する義務として課せられてきた。一方、昨今多発する民間主導の都市再開発では、こうした計画に対する義務への意識が極めて薄いのが大問題である。
この臨場第一ステージでの衝撃はメガ・スケールの体感に加え、多くの仮設空間に出会えたことだった。そのどれもがブリコラージュな技術秩序が生み出す空間となるもので、新鮮な建築的解像として臨場される主題となった。
こうした仮設空間は工事計画への対応として生まれてくる暫定的で、極小な仮のミニマル空間となるものであり、ジェネリックなXLの相貌を示すビッグネスのメガ・スケールとは全く対比的に、仮設空間はどこまでもヒューマンスケールを示すXSの世界となるものだった。
そして、なによりも臨場第一ステージでは、この民間主導型都市再開発の体質を探る上からも、計画の根拠となるものや、そのアウトラインを工事現場から如何に少しでも窺い、探るか、にかかっていた。
特にこの第一ステージでの圧巻は、再開発桜丘地区での既存建物解体工事の様態であった。小さな施設・小さな土地が解体・整地を通して大きな土地に改編されてゆく様は重大事件で、渋谷再開発計画の「ビッグネス」を象徴的に示唆していた。
次いでの臨場は、工事進行につれ、複数の施設工事が同時多発に立ち上がってくるので、計画としての施設の関係性を工事現場を介して読み解いてゆくことが主題となってゆく。これが臨場第二ステージと呼ぶもので、ここでは複数の「ビッグネス」がどの様に繫がるのかをいち早く窺うことが重要な感得になってくる。
それは同時に「ビッグネス」群の関係性だけでなく、再開発にかかわる多くの開発主体者の関係性についても計画を支えるスキームとして窺ってゆくことが肝心になってくる。
つまりは臨場第二ステージが明らかに第一ステージと異なる主題は、単体施設の様態を窺うのではなく複数の工事の進行を通して新たな再開発計画の統合化を推察するものになる。それは不連続で、関係も無さそうな複数の工事が示す各々の骨格から新たな関係性を読み解こうとするものなのである。
それらの解像から描き出されるものは国・区・公共交通を含むディベロッパーによる資本主義プラットフォームと化す渋谷再開発のリアルな姿なのである。
こうした資本主義プラットフォームはどこまでも都市の内に超メガ・ネットワーク(関係性)を構築しながら街に対して囲い込み化を強固に図ってゆく。街に人を流す建前と、人を囲い込んでゆく本音との自己矛盾を渋谷再開発は根本的に抱えているのである。
従って、再開発工事現場の臨場第二ステージは都市緊急再生特区としての渋谷が示す施設間の関係性とその統合性を注視することに尽きる。そこにこそ資本主義プラットフォームの野心が露見されるからである。
そして、その野心がどの様な渋谷の再生をもたらすものになるのか、を再開発工事現場から鋭く問うことを「演習」(プラクティス)として臨場第二ステージで行う。演習は単なる観察ではない。この演習は開示されない計画への洞察・解釈となるものでみんなで議論し合うことが新しい論点を探る意味からも望まれるものだ。
更に、渋谷再開発工事現場からの臨場では、この計画そのものが渋谷とどの様な連携を示唆するのかを窺うことになる。これが臨場第三ステージになり、現在の工事進行からはこのステージでの観察が可能である。
ここでの臨場のポイントは、再開発計画が渋谷に対してどの様な役割りを担うことが出来るのかを改めて推察することだ。
この裡で、街との共存性について吟味することがポイントになる。
街に対して効率よく人を流すことを再開発の大義としている以上、人の流れ方を窺い、再開発地域や街との接点(境目)にどの様な親和性が育ち得るのかを推察してゆく。その先に境目の公共性の余地を精査し、感じとってゆくことになろうか。
再開発地域と周辺地域との共存は接続点である境目の様態の如何が深く関わってくる。そこに皆が共通利益として感得される公共感覚がどの様にデザインされているか、それが親和性を生むか否かの岐点になる、と考えるからだ。
渋谷再開発の特性の一つに、再開発地域の背後に多くの奥性を抱えていることが挙げられる。再開発地域がスリバチ地形の底部に当る為、そこから四方に延びる街の奥性が歴史的・文化的に形成されてきて、そこに独特の「テリトーリオ」を織り上げてきたのである。
従って、再開発地域とその周辺地域との境目が渋谷再開発に於いてはもう一つの重要なポイントだ、と私は考えてきていた。そこには固有な境目が幾つも認められる。•宮益坂方面との境目。•道玄坂方面との境目。•桜丘方面との境目。•金王坂方面との境目。•並木橋方面との境目。などがそれで、各々の境目には各々に固有な地域コンテキストを有する奥性が備わっている。渋谷再開発に在っては境目は各様の奥性が示す異界への入口となるべきもので、「歩行のまち渋谷」に在っては貴重な歩行の為の起点であり、都市資源となるべきものなのである。
この奥性を各々の境目がどの様に映し出せるのか。これも重要なデザイン課題になろう。
境目は資本主義プラットフォームと固有な周辺地域との接続点となるもので、本来的にはデリケートなものになる。「街に人を流す」観点からも境目の様態には無関心ではいられないはずである。
この境目を再開発地域側から見るのか、周辺地域側から見るのかでも接続点の眺めが全く変わってくるのが如実だ。従って、どの境目もその流れの力学がスムーズな接続となるものばかりではなく、「街に人を流す」とは本来、再開発地域と周辺地域との人の流出と流入を同時に視野に入れるべきなのが境目なのであるが、もっぱら再開発地域から周辺地域への流入のみが主題になっている。
それは周辺地域を支えてきた商店街からの強い要請もあったであろう。周辺地域への人の流入が都市再生のハブと把握され、合意形成されているようだ。
しかし、周辺地域は各々に独自の奥性を抱えていて、その奥性に当る地域からの再開発地域への流入(あるいは交流)は境目からは窺うことが出来ない。奥から人が出てくる必然性が通勤・通学のルーティン行動以外にも当然あろう。
特に、奥に住む高齢者が再開発地域にアクセスする折の境目がなんとも曖昧で味気ないのである。あるいは境目自体がどこに在るのか分からない。
これは、再開発地域と周辺地域との境目に、なんらかの公共性の余地を欠落させているから生起してくる問題なのであろう。
私はこの境目という「小さな場所」からも渋谷再開発が担う都市の公共性を議論する機会になると考えているが、開発側には境目への自覚が極めて薄い。
都市に入用なのは一律の公共性ではない。
場所に応じた公共性やアーバニティが必要な時代に在るのではないか。この局面からすると、民間主導の都市再開発は明らかに公共性に偏向が見られる。公共性に絶えず商業主義が絡んでいて、エリアマネージメントの対象として境目も管理され、極めて限定的な公共性と映る。都市生活者にとって境目が身近な公共性を体現する「小さな場所」に一切成っていないのではないか。「渋谷サクラステージ」西側デッキの境目に建つ「キュービック施設」が周辺地域に示すものが一体ナニなのか。それが表象するものが不明なのだ。
ここで指摘した都市の「小さな場所」に育まれる公共性は、むしろ「公共感覚」とした方が相応しいものになる。一律的な制度としての公共性ではなく規範や約束事としての公共感覚の自生的醸成が現在の都市に極度に不足しているものではないか。
こうして育成される「小さな場所」での公共感覚を私は「小さな公共性」と呼ぶ。これこそが下からの公共性であり、一律な上からの公共性とは遥かに異なる人と場所との繫がりをそこに生み出し、コモンの萌芽へと向かうものになる。都市のコモンは、この様な「小さな公共性」を皆が共通利益として実感し、それを維持しようとする自生的な自治の在り様から引き出されるものになるのであろう。
この「小さな場所」での「小さな公共性」を体現させる上ではデザインの力が初動のテコとなり、皆が共感し合える公共感覚を醸成させてゆく。
こうした公共感覚を誘導するデザインとして「アーバンデザイン」を再定義してゆくことが肝要なのである。アーバンデザインは究極的には景観を整えるものだけではなく、公共感覚を生み出すものでなければならない。それこそがこれから求められる「パブリックライフ」であり「アーバニズム」となるものであろうから。従って、民間主導で開発される場所の公共性をどの様に捉えて問題とすべきなのかを問うことが臨場第三ステージでの重要な観測になる。
民間主導型都市再開発では容積緩和の旨味と引き換えにしきりと「公共貢献」が唱えられる。公共貢献とはナニか。
それは開発可能な容積を割いて公共に依する場面(空間や機能やサービス)を提供することを「公共貢献」としているようだ。
が、しかし、この公共貢献は公共に供する「場面」をつくっているのであって、それはそれで意味あることなのだが、そこに豊かな公共性が育ち、根付くのか、新たなアーバニズムを創生しうるのか、そこは不明なのである。公共性の醸成を図るよりも、それを管理しようとする対応が民間主導型都市再開発では強いと映る。とりわけ渋谷再開発での公共貢献は歩行インフラの整備、と言うことに尽きようか。
私たちが渋谷再開発に望む「公共貢献」には資本主義プラットフォームを結果的により強化させている歩行インフラの先に小さな場所による「小さな公共性」と言う公共感覚を感得したいものだ。その為の下からの公共性となる「小さな公共性」を引き出し、醸成させるにはデザインの力に依る所が大きいが、それをスタディするのもデザインアーキテクトの主要な仕事であったのではないだろうか。この公共感覚をデザインすることはデザインの差異を打ち出すミッションだけからでは生まれてこない。
今、渋谷再開発は想定外のオーバーツーリズムの余波を受けて、「公共性」、「パブリック・スペース」のお粗末さが一気に露呈し出しているのは皮肉だ。それは流すことだけで、溜まることへの関心の無さが一気に噴き出してことでもある。観光への対応は流すだけではなく、溜まることの対応が強く求められる。
インバウンド層を百貨店に呼び込むのが目的としても、渋谷に降り立った期待感を鼓舞する豊かな公共性を体現するパブリック・スペースの体がどこにも見当たらないのだ。
ベンチや公衆トイレ一つない渋谷の「玄関」の構えがどの様に渋谷再開発では構想されていたのか、全く不可解であり、不明なのが現実である。
渋谷再開発では、元々公共性の強い広場の概念のない我が国に在って、容積率緩和と引き換えに公共貢献があざとく図られたとしてもそこに十全で十分な公共性を体現しえている、とは端から思えない。
こうした公共的な整えや公共感覚の創出は計画サイドがより強い自覚を持たない限り生まれえないものなのだ。この視点を欠如している「流すだけの公共性」の空疎さが強く感じられるのが渋谷再開発での公共貢献の実態なのだ。
その意味からも渋谷再開発で最大に公共感覚をデザインが創出し醸成させているのが「ヒカリエ」に通じる「ブリッジ」(デザイン内藤廣)になる。
そこが国道上に架かる公共空間だから公共性を感じるのではなく、そこにデザインとしての公共感覚が下から打ち出されているから公共性を私たちが共通利益としてそれを感得する感覚回路が私たちの内に備わっていることが良く分かるのである。
これまで工事現場を介して計画を窺う臨場を重ねてきたが、工事個所も縮小し、限定的になり、次第に臨場の対象も工事から出来上がった施設に移ってゆくことになる。
そこでの臨場は計画を窺う域から更に、出来上がった施設に対面し、それが意図している計画を吟味することが臨場の主題になってくる。この様に臨場の対象が工事中であれ、竣工後の施設であれ、いずれの場面もその場を「現場」として捉え渋谷再開発の計画の所在をあぶり出す為に臨場は行われているもの、と言っていい。従って臨場は現場主義が前提となる。
臨場第二ステージでは出来上がりだした施設間の関係性の計画を吟味することが主題であった。
臨場第三ステージは出来上がった施設と周辺地域との境目を臨場する。そこにどの様な配慮が計画に介在しているのか。そして、そこで育てようとする公共性とはどの様なものなのか。そしてその境目の後背地である「奥」となる固有な地域との繋がりをどの様に構築しようとしているのか、などを検証することが主題となってくる。
なによりも渋谷に在っては、その谷底地形の中心から四方に延びる奥性の固有性・稀少性は有徴な都市資源であり、環境資源となるものだからである。これらへの対応が渋谷再開発の視座からは、どの様に捉えられているのか。
これまで見てきた様に、緊急性を要する都市再生特区としての渋谷再開発を日常的な都市現実を生み出す現場として捉え、そこに密着して一五年以上に渡って臨場してきた。完成予定(二〇二七年)よりも更に延びる眺めにあり、まだまだ臨場は続く。
渋谷再開発は全てが竣工し、出来上がってもその状態がゴールでは無論ない。その時点で明らかになる都市生活者にとってのダメージをよりシビアに糾弾し、異議申し立てをし、事態を変更するように仕向けてゆかなければならないのではないだろうか。民間主導の都市再開発であればなお更である。計画そのものが充分に広く討議されることなく進展し、当事者意識を持つことなく、いつの間にか完成してしまうから、ここからの臨場がより肝心になってくる。渋谷再開発を生き、向き合ってゆくのが臨場第四ステージとなるもので、計画が描き出し、誘導しているものらと現実との軋みを臨場してゆく。特に臨場に際しての特異な与件は若者たちの新たな動向と急激なオーバーツーリズムの動向・動態である。彼らの「渋谷」への興味・関心もこれからの臨場に際しては無縁ではない。
臨場は計画を窺い、実感し、批評するだけではなく、計画された実感に対しての提案も臨場のステージが進むにつれ次第に重要な主題になってくるのである。
直近のSNSで渋谷再開発の完成予定が七年先に送られ、二〇三四年完成予定、とある。
これからが渋谷再開発の臨場も正念場を迎える。

(おわり)
連載記事一覧