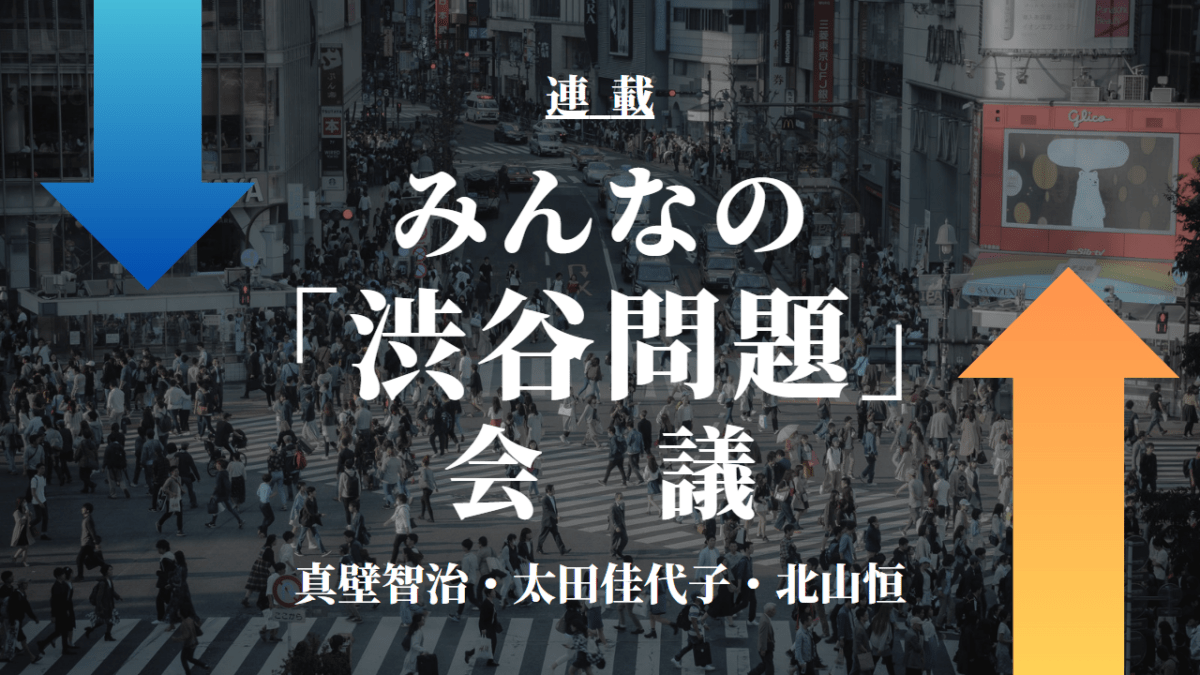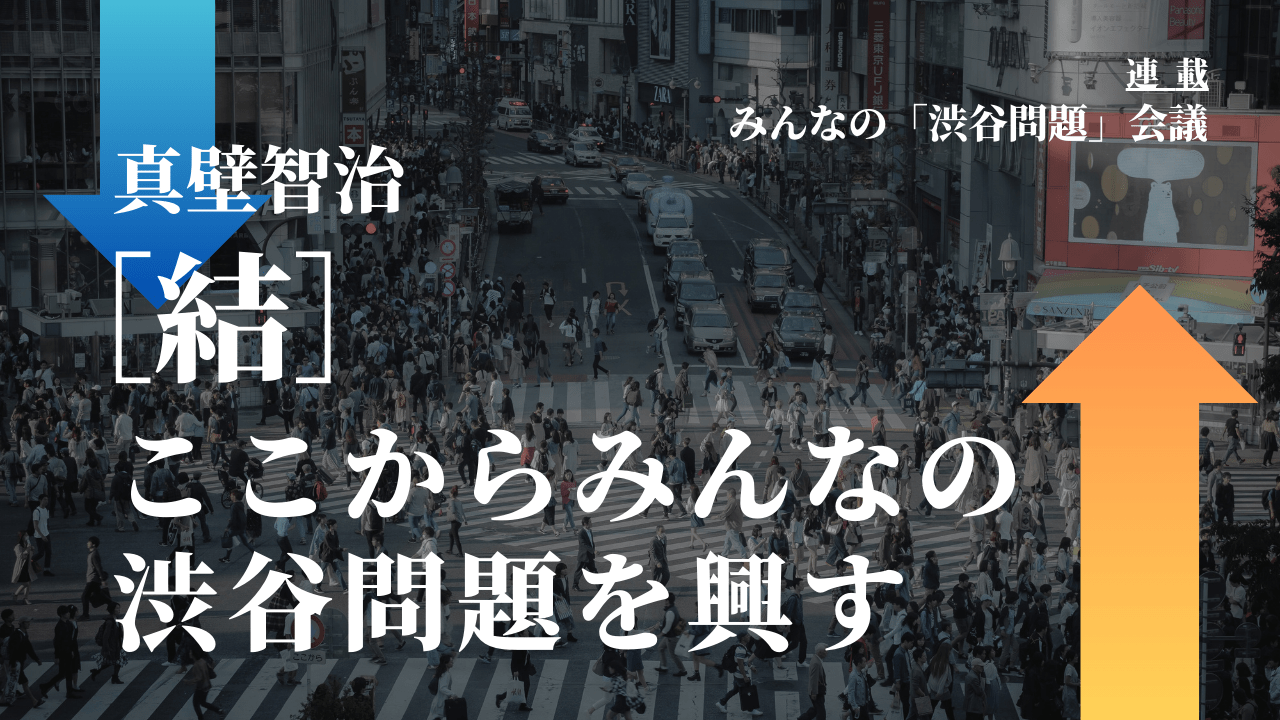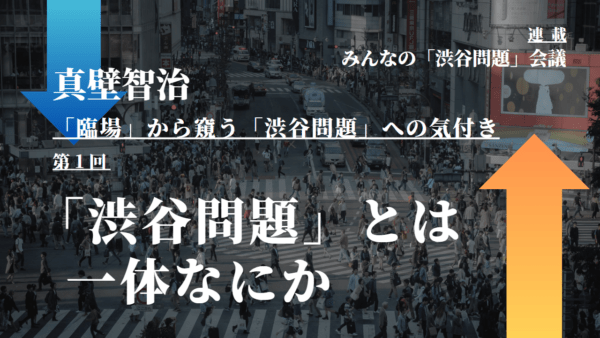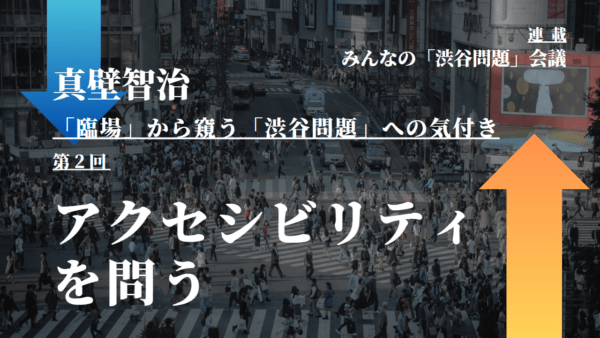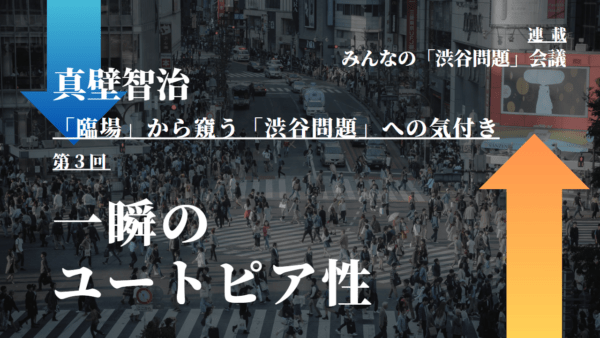[結]ここからみんなの渋谷問題を興す|連載『「みんなの渋谷問題」会議』
渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。
真壁智治(まかべ・ともはる)
1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。
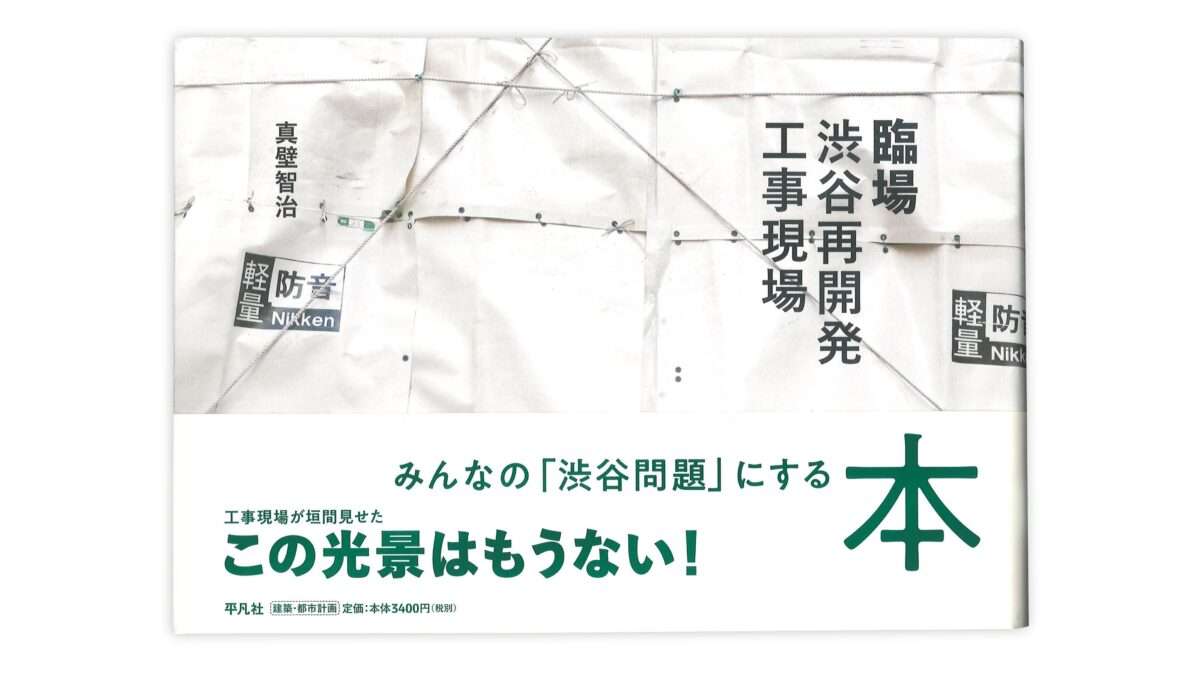
≪横にスクロールしてお読みください≫
なぜ渋谷問題なのか
百年に一度の巨大大都市開発と言われる渋谷再開発をもっと身近に、そして、もっと当事者意識を持って広く議論したい、とする意図で学芸出版社ウェブサイト「まち座」から真壁智治・北山恒・太田佳代子の三名に依る「みんなの渋谷問題」会議として議論の為のベースメントになるべく基調論考を発信することとなった。
今回予定通り三名の基調論考を発信し終え、そこを起点にあらためてみんなの渋谷問題への議論を活発に図ってゆきたい。
なぜ、いま渋谷問題なのか、なぜそれへの議論を尽くさなければならないのか。
それは百年に一度の大規模な民間主導の渋谷再開発が次第に顕在化させている開発の構造やスキーム、更にはデザイン・管理、更には人の振る舞いなどをそこに見るにつけ、これは戦後日本の都市史上、最大級の危機をもたらし始めている事態と思えるからだ。
なによりも、そこでは都市は一体誰のものなのか、が深刻に問われなければならない。
言うまでもなく、都市の主役は消費者ではなく、市民であるべきだ。
たとえ都市がディベロッパーの手により開発されたとしても市民こそが主役でなければならないのは当然である。
しかし、これまでの所、開発された都市の主役としての市民度を計測し、評価する術は開発主体にも都市生活者にも共有された指標は一切ない。
都市再開発で市民が主役に、と言うことは市民に提供される共通利益としての公共性が再開発された環境に担保されているのか、と言うことになる。その上で、それを互いに計測し合う術が全くないことからその認識にズレが生じている。
このことが都市開発や都市再開発の推進の仕方の如何を問わず、根本的な大問題なのではあるまいか。開発された都市環境の公共性からの評価こそがとりわけ都市再生特区には充分に課されるべきだ、と考えるからだ。
渋谷再開発に於いて、開発主体側は「公共貢献」として都市インフラの整備を図ってきた、と主張するだろう。
確かにハードとしての都市インフラは河川改修や「アーバンコア」・「スカイウェイ」などの都市装置に依る歩行インフラ整備が図られている。
しかし、それらが十全に都市の主役としての市民に向けた「共通利益」と呼べるものか、と吟味すると極めて危うさもそこには見えてくる。
「アーバンコア」としての眺めを持つJRとメトロの改札が合流する「渋谷スクランブルスクエア」東棟2Fの大空間やその地上部にはどこにも渋谷の玄関口としてのゲート機能もロビー機能もなく、ましてやベンチや公共トイレなどはどこにもない。
つまりはハードとしての都市インフラは整備されても、市民が「共通利益」として感じ易いソフトが付帯する公共空間にはなっていないのである。
それを民間主導型都市開発の限界だ、と言ってしまえばそれまでだが、どこまで行っても市民を徹底対象とすることが出来ずに、消費者を念頭に誘導する都市インフラ開発になっていることは否めない。
特に渋谷再開発での「スカイウェイ」と言う開発施設を架け渡す空中通路(ルビ:ブリッジ)の解釈の拡張化が目に余り、「人を街に流す」を掛け言葉に、渋谷の谷底地形を跨ぐかたちで、開発施設間のネットワーク化を図る為に架橋させている。この眺めを渋谷全体から見ると都市の再開発を手段に消費者の回遊化・誘導化・滞留化の促進策と一面から見れば映ろう、と言うものだ。つまりは人の移動の寡占化である。
ただ、確かに再開発での「アーバンコア」と「スカイウェイ」の設置で渋谷駅周辺地域へのアクセシビリティや回避性は遥かに高まったことは評価されよう。積年の谷底地形とそれを横断する道路インフラによる街の分断化が解消されてきている。
しかし、こうした極めて不充分で片寄った公共性が規制緩和とバーターされて実現し出した渋谷再開発での公共貢献の事態に対して、私たちはどの様に向き合い、それに対抗してゆくべきものなのだろうか。
渋谷が畏縮しだしている
渋谷再開発で生まれている公共性の高いオープンスペースや開発施設内貫通通路での私たち(市民)の振る舞いはどの様なものになるのか。そしてどう在ることが私たちの共通利益とも符合する新たな公共性をそこに獲得しうるのか、をみんなの渋谷問題として活発に議論すべき局面が切迫している。
この局面こそ戦後日本の都市史上最大の危機的ターニングポイントと私が指摘する根拠となるものなのだ。
「みんなの渋谷問題」会議での太田佳代子さんから示された基調論考に見られたように、近年の都市開発では、公共性の高い場所での市民の和やかな振る舞いや都市を生きる喜びを包摂するような新たな対応の公共性の創出よりも消費者を前提とする購買・消費を促進させる意図が全面化する公共性もどきの公共貢献が跋扈してはいないか(それを「公共空間の商空間化」という言われ方が一部にある)。
これでは都市が誰のものなのか、極めて際どい事態に私たちは危機感を強く覚えざるを得ない。特にその場に付帯する管理の在り方については大いに疑問を感じるし、ホスピタリティや寛容さが全く欠如していて健全なアーバニティを享受出来る域には程遠い。
私たちが資本の論理で蹂躙されている、と感じざるを得なく、それが特に都市の開かれた場所で在るべき広場や公開空地がどれもが畏縮・萎縮している、と映っていないだろうか。
覇気のない公共貢献に依る公共空間が占有する渋谷駅周辺地域の現在の様態はこのままでは全くマズイ。人々が、特に若者がどんどん離れてゆく。市民を畏縮させ、シラケさす要因がそこには在るはずだ。
こうした場所の管理の在り方については、お役所・行政のそれよりも民間の方がより狡猾で、質が悪いからこそ市民の畏縮が余計目に付くのである。
その一方で、開発主体側は、エリアマネージメントを駆使して、公共空間(広場やデッキ・通路等)の活性化を図る、としている。
しかし本来、ここで求められるエリアマネージメントには、地域全体の公益性の向上や、場所や地域へのコモン意識を育成し根付かせる為のものとして行使されたい。
その為には開発主体の顔色を窺っているような小手先だけの「エリマネ」では無理だ。
公共貢献となる公共性の高い場所を、主体的に名実ともに公共空間としてゆくことこそが渋谷再開発に於ける「エリマネ」に強く求められるものではないだろうか。
そしてこの局面への「エリマネ」の方策についてもみんなの渋谷問題として議論を深められたらいい。
なによりも「エリマネ」が目指すべきは、開発主体の利益に反してまでも市民が感じ取れる共通利益としての有益性を醸成させてゆく中立的、主体的な立場のもので在って欲しい。
それらは目前の渋谷再開発への具体的なコミットメントの一歩になってゆくに違いなく、渋谷再開発での流れを変えてゆく方策はそれしかないのかもしれない。
どちらかと言うと、その様な局面からの渋谷再開発に切り込もうとする「エリマネ」の態度は、小さなコモン・小さな自治をそこに獲得しようとする開発主体から自立する動向となるものだ。
渋谷再開発に課すべきもの
同時に私は渋谷再開発の公共性の高い場所に対して「独り」と言うシチュエーションからの検証を加え、それについても広くみんなの渋谷問題として議論してゆきたいと考えている。
「独りのためのパブリックスペース」は建築家・槇文彦に依って動議された指摘であった。言うまでもなく、近代民主国家に於いては個人の権利は尊重され、守られる建前になってはいるが、個人が「独り」と言う行動形態を採ることには世間が、社会が然程、寛容にはならない。独りのパブリックスペースが消費者ではなく市民に保証され、配慮され、確保されるアーバニティこそが魅力的なパブリック・ライフを生み、大人の都市への成熟を可能にしてくれるのである。しかし、現状の都市の過半は防犯カメラが張り巡らされ、公開空地は無論、その他の都市に生まれるオープンスペースでの「独り」に対する監視・管理体制が強まってきてはいないか。市民が安全に、安心して豊かに過ごせる独りのためのパブリックスペースこそが保証されなくてはならない。
渋谷再開発では「華やかに群れる」ことが誘導されているが、その対極の「豊かな独り」を可能にする公共空間を期待したいものだが、現状・現実にはその様な配慮は少なく、デザインアーキテクトもその主題に対して自覚的に手を付けてきてはいない。
そして、最大の議論の焦点は、この規模の都市再開発に対して、特に低層部にどの様な条件・規制・課題を解決義務として提示すべきか、を先に触れた公共性の指数化(市民主役度)の議論と共に、みんなで検討し合うことが、今起きている都市最大の危機を乗り越えてゆく道となるのではないか、と考えている。その視点無くして、小手先の「エリマネ」で済む話ではない。その為には渋谷再開発が「まちづくり調整部会」(座長岸井隆幸)と「デザイン会議」(座長内藤廣)の二頭体制の主導に依り推移してきたのだが、そこから明らかに欠落している公共性の在り方とデザイン及び管理についてもっと議論と提案を立ち上げてゆく。それ在っての「渋谷らしさ」の追求ではないのか。
どうやら渋谷再開発は当初の完成予定年二〇二七年がもう少し延長され、二〇三〇年に及びそうな事態になってきた。
実に二五年にも渡る「都市をつくる」と言う一大事業が辿ってきた経緯をあらためて振り返りながら、そこで失ってきたもの、生み出されてきたもの、育ててゆかなければならないもの、修正すべきものらへの渋谷問題として議論を重ねてゆかねばならない。
議論の渦中から渋谷再開発への当事者意識を強く共有化してゆけたら、と思う。
そして、なによりも渋谷再開発が体現している様態を生きられた都市として感応する私たちの都市的日常性を注視し続けてゆくことが、みんなの渋谷問題に取組む根本にならなければならないのは言うまでもないことである。
再開発は計画が完了しても終りではない。いや、むしろそこから新たに手を入れるべき課題を私たちが開発主体に付きつけなくてはならない。
その為の精査こそがみんなの渋谷問題の真の主旨なのである。
(おわり)
連載記事一覧