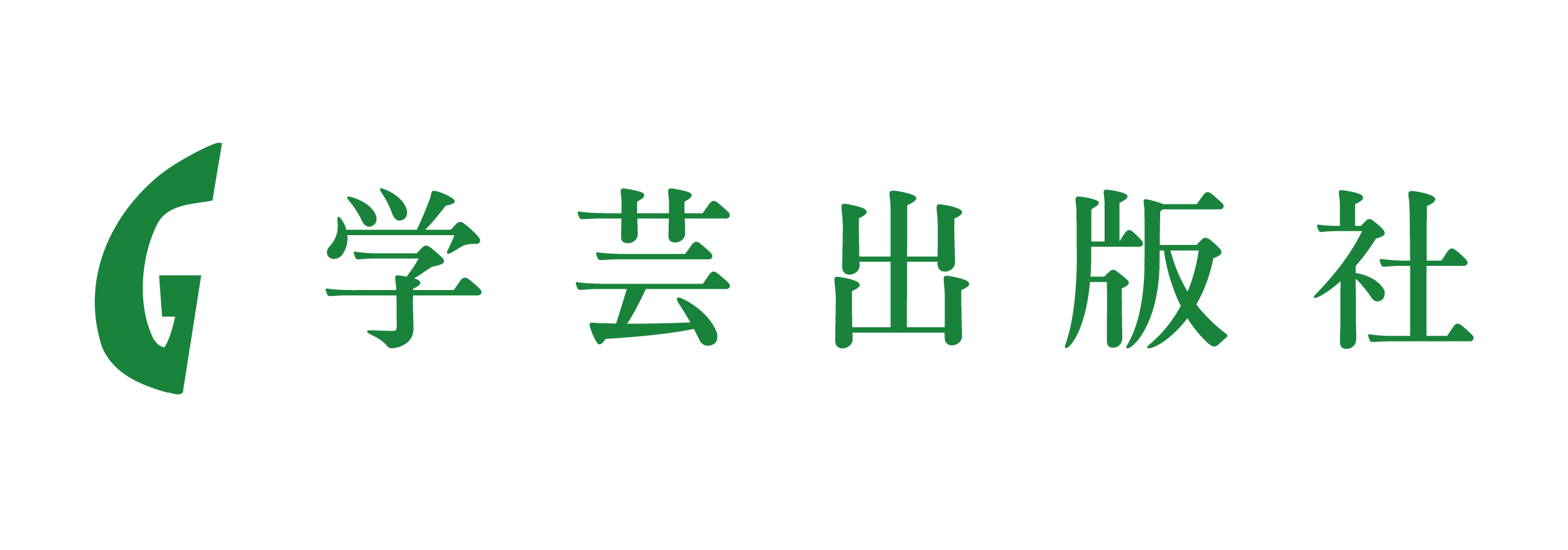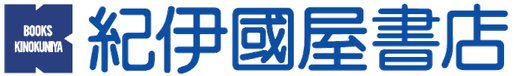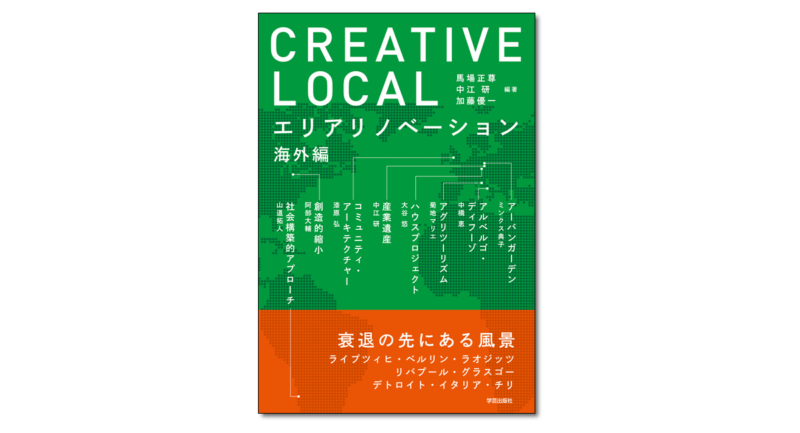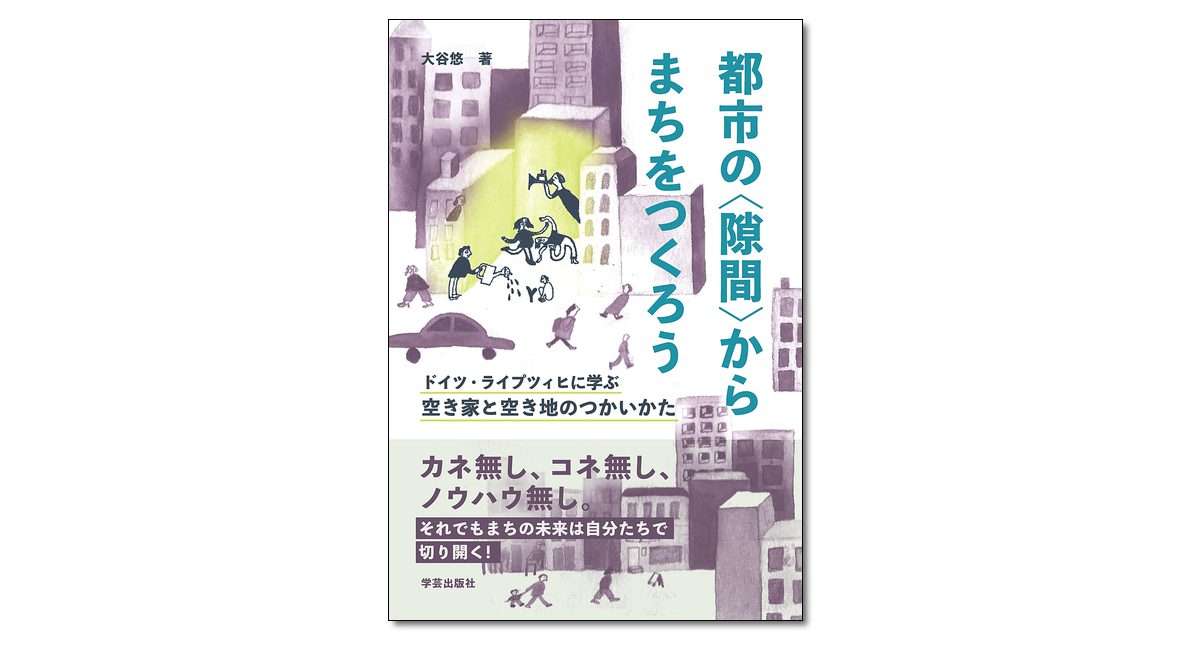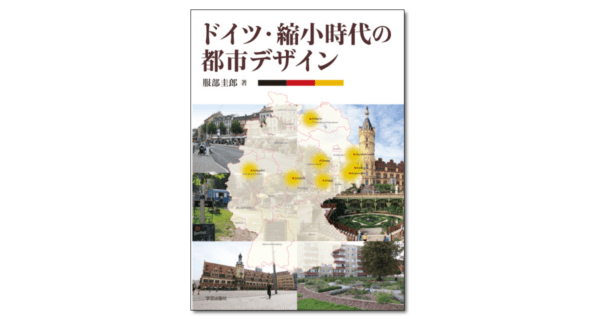負の資産で街がよみがえる

内容紹介
街の資源を蘇らせるアートによる地域再生論
人口が減り、空洞化する街の中で余剰資産となった工業化時代の建築物。それを廃棄するのではなく、未来の資源として有効活用する術が求められている。木密地区や過疎地の空き家や廃校等を舞台に、リノベーションと文化的仕掛けを施すことで、街の魅力が再発見される。街の資源をアートの力で蘇らせる、縮小時代の地域再生論。
体 裁 A5・208頁・定価 本体2200円+税
ISBN 978-4-7615-2466-1
発行日 2009-08-30
装 丁 上野 かおる
序章 都市のアグリー・ダックリンたち―不幸な国の新たな主役
第1章 文化資源を利用した地域の再生
1 文化資源論の系譜
2 表の文化、裏の文化
3 アートと街のマッチング
4 ビエンナーレ/トリエンナーレの効用
5 地域資源の再発見
第2章 アーティスト・イン・空き家
1 ソーホーの神話
2 都心を占める木造住宅密集市街地
3 京島に住む
4 「アーティスト・イン・空き家」の実施
5 過疎地でも「アーティスト・イン・空き家」
第3章 多文化が交わる都市社会
1 多文化共生の枠組み
2 もうひとつの木造住宅密集市街地、横浜鶴見
3 南米人が街を元気にする
第4章 廃校がミュージアムに
1 小学校がなくなる
2 学校はアート・スペースになるか
3 D─秋葉原テンポラリー
終章 縮小時代の価値創造
1 「負の資産」を「正の資源」に置き換える
2 デザインの四面体
3 クリエーターと地域性
あとがき
序章「都市のアグリーダックリンたち―不幸な国の新たな主役」
冒頭から少々暗い話で申し訳ない。何よりも日本の都市を眺めていると、心が晴れないのである。それを象徴的に示すのが、最近話題となっている幸せの度数なるものだ。最近イギリスで実施された調査によると、日本はどうやら世界のかなり下位にランクされているようで、大変寂しい。先進国として勤勉さを売り物にして築いてきた国家と社会に対して実はまったく満足しておらず、不幸を背負った国民ということなのだから、日本の近代とは一体何だったのか、改めて問い直さざるをえないだろう。住まいそのものをとってみると、かつては「ウサギ小屋」とまで揶揄された日本の住宅も、最近は充実度を増し、アメリカにはかなわないものの、平均面積はヨーロッパ諸国とあまり変わらない。都市計画も住宅づくりも目標を設けて一生懸命行っているにもかかわらず、それが人々の満足度とか幸せ度に結びついていないという現実がある、ということだ。
筆者自身、この四半世紀、つまり1980年代から現在に到る我が国の都市状況をずっと観察してきたが、本来なら向上すべき都市の住み心地の良さが、実はそれほど向上していないという事実を突きつけられると、返す言葉がない。時代は速いテンポで動き、政局も経済も流行もファッションも、どんどん変わっている。経済の動向がどうかといえば、バブル、不況、そして束の間のミニバブルに続くサブプライム・ショック、大不況という具合に、短いスパンで景気の浮き沈みが激しいために、どうも落ち着いた気がしない。というよりは、毎日の為替の相場、株の動きに翻弄され、じっくりと腰を据えて物事を考えようという気になれない。足もとがそんな感じだから、生活感から見た都市環境なるものが、どうみても地につかないというところが本音だろう。
この四半世紀に何が起こったかといえば、科学技術の面では大変なことが起きている。コンピュータが当たり前となり、インターネットや携帯電話の方面では飛躍的な進化を遂げているのだ。ところが、自身の身の回りと切っても切れない関係にある住まいや都市の話となると、どうみても以前とそれほど変わっていないのだ。ほとほと困った事態である。空間を必要としないコミュニケーションが飛躍的な発展を遂げているのに対して、都市空間に対する「空間音痴」とでもいうべき症状が目立つのである。むろん、進歩がないわけではない。環境やエネルギー消費に対する人々の意識は確実に変わっており、一昔前では考えられなかったエコ思考が人々を捉えている。ところが、環境を考える上で本流であった都市づくりや街並み整備となると、これといった確信がないままその場その場の判断で右左に舵を切っているようなものだ。一貫性が感じられない。霞が関に行っても地方都市の市役所に行っても、元気であるべき若手官僚たちはもっぱらリスク回避を考えるようになって、物事がどんどん小さくなっていく。
翻って、1980年当時、日本は空前の好景気に沸き、欧米の都市が遅れて見えたものだ。その頃、アメリカもヨーロッパも、長い不況が続くなかで都市の綻びが目立ち、すさんだ中心市街地のイメージが強くて、その分日本の都市がまぶしく輝いていた。グラスゴーやジェノヴァに行って、昔栄えた都市が衰退するというのはこのようなことかと、妙に納得した記憶がある。都市の劣化現象というべきだろう。その頃、筆者が仕事をしていたのが東京の芝浦地区で、一昔前は単なる埋立地として何の文化もないところとされていたのが、ジュリアナ旋風とでもいうのだろうか、東京の最新ファッションをリードするホットな場所として認知され始めたのである。倉庫地区であって変に色がついていなかったのが、逆に幸いした。東京のこんなところから世界に文化が発信できるのだ、と誰しも妙に舞い上がったものだ。
ところがこの20年の間に、形勢はすっかり逆転してしまった。日本はバブルがはじけて、世に言う「失われた10年」の時代に入り、人々の思考は日に日に内向きとなっていった。それに対して欧米は大きく変化した。何よりも、欧米、特にヨーロッパの都市が本当にきれいになった。都心部も郊外も、古い建造物と新しい建物とが混じりあい、それまでに体験したことのないほどの活気が出てきたのである。イギリスのマンチェスターをとってみれば、そのことがよくわかるだろう。一九世紀の産業革命の都市が20世紀になって時代遅れとなり、煉瓦積みの大ぶりな工場と倉庫が、産業の衰退にともなって無用の長物となり、しかもクリーンで明るいモダニズムの価値観とは相容れなかった。だから20世紀の進歩史観からは、排除されるべき対象と見なされたのだ。ところが、20世紀も終わりになると、そのような価値観はすっかり影を潜めて、もう少し文明を大所局所から見るようになった。20世紀文明に対して別の価値観が登場してきたのである。都市政策に関しても、文化や創造性の問題が前面に掲げられ、新たな試みを大胆に行う下地ができてきた。マンチェスターの場合は都心部の文化に着目した新たな都市活性化の政策が功を奏し、人々が戻ってきたのである。語の本来の意味で、人間にやさしい都市が復活したといってよい。
フランスでいえばリールやルーベがそうである。特に小マンチェスターと呼ばれたベルギー国境の町ルーベは、第二次大戦後になって繊維産業が日本、次いで中国にとって代わられた後、ほとんど過去の遺物のようになっていたと聞く。筆者も1970年代から80年代にかけてパリに住んでいたが、その頃、この町のことなどまったく話題にならなかった。人々の記憶からすっかり忘れ去られていたといってよい。ところが、フランス北部のベルギーと国境を接するあたりの人口稠密地帯で、リール都市圏という地の利を生かして、国の文化施策をうまく導入し、国や県の文化施設を積極的に誘致して多くのプログラムを導入することに成功した。そのための場所として、過去の産業建築をリノベーションして用に供す。つまり、大きな手をかけなくとも、街の表情を変えることが可能であることを身をもって示したのである。小さな町だからこそ切り替えが早くうまくいったということもあるだろう。何よりも無用の長物のように見えた過去の建築が、実は新たな価値を生む資産になりえたという事実が、都市の再生に大きく寄与しているのだ。
こうした都市の再生事例は、今日のヨーロッパでは事欠かない。都市が革命的に変わったという状況ではなく、既存の都市的コンテキストをうまく活用し、過去の資産を巧みに利用して、新たな価値を生じさせているのである。バブル的なニュアンスをもつ「打ち出の小槌」というよりは、まさに都市に暮らし日々の生活を享受している人々が、都市の新しい価値に「生き甲斐」のようなものを感じるようになり、楽しく美しく暮らすことが本当に幸せだと思うようになったからである。しかも自然体で。失礼な言い方だが、今世界でもっともホットな中国では、世界に追いつき追い越せとの号令で、皆しゃかりきになって仕事をしているようで、これでは大変だろうなと思ってしまう。日本が頑張っていた時代、最近では1980年代だが、この頃の日本人は評価額が額面以上となったことに気がつかず、思い上がりが甚だしかった。だから落ちるのも早いのである。
つまるところ、今の日本はある種の閉塞状況にはまっているように見える。超高齢化といわれる時代を迎えるようになり、国民の活力が落ち、将来への展望が描けないまま、自己嫌悪に陥った状態といえるだろうか。先進的な文化施策を打ち出して都市の新たなヴィジョンを描くヨーロッパを遠く眼にして、自虐的に「日本は駄目だ、若い世代もだらしない」と愚痴をこぼすのが精一杯で、世界のあちこちがきらびやかに見える分だけ、自身がみすぼらしく感じる。何事にも対応が遅い日本に対して世界の評価も日増しに厳しくなっているようだ。しかし、本当に日本の国力は落ちているのだろうか。傍目には日本人は結論を急ぎすぎ、長期的に物事を考えようとしないように思えて仕方ない。「失われた10年」を含めて過去15年ほどをこれだけ苦労して過ごしてきたのだから、日本人ももう少しヨーロッパ的スタンダードを意識して、自分のペースに見合った仕事と、その分、クリエーティブであるような生活を送ってもよいのではないだろうか。自分なりの生き甲斐をはっきりと見据え、社会のイノベーションを何かひとつでも行えばそれでよしとして、あまり無理をしないでゆったりと四半世紀程度単位の計を立てればよい。それならばそう困難なことではないはずだ。社会の蓄積という観点から見ると、日本も人々の知恵とノウハウを生かす社会に大きくシフトしていて当然おかしくない。なぜ、欧米でできることが、日本人にできないのであろうか。
このような昨今の日本人の動向を、アンデルセンの童話を借りて「アグリー・ダックリン」(みにくいアヒルの子)と表現してみたい。実は将来に向かって大きな可能性があり、まもなくその時期が訪れようとしているのに、そのことに気がつかず、周囲との交流を避け、ひとり自身の醜さを卑下するところが、今の日本人の置かれた状況をよく物語っているのだ。今日の日本の問題は、自閉的になり、海外への関心を以前より失い、自信をなくしている点にある。しかし、我が国をよくよく見ると、実は日本人は相当程度頑張っているということが改めてわかってくる。実際、日本各地を訪れてみると、町おこしや町並み再生というのが今や合言葉になって、本当にさまざまな試みがなされており、改めて都市の再生などというのがおこがましい。地元のNPOや自治体、住民組織がいろいろな努力をしているのは確かである。筆者の限られた経験でも、地域レベルで街を見れば見るほど「日本は意外と面白い」と間違えなく言えそうで、その点は自信をもってよいだろう。ただ、日本のケースが欧米と決定的に異なっている点があり、それが今の元気のなさの元凶ではないかと私は密かに思っている。それは、リスクをとることに今の日本人が消極的であるということだ。市民運動をしている人たちは、元気がよい。特に女性や定年後の人たちが積極的である。しかし、実際に資金を出し、事業を起こす人たちが、そういう決断をしてくれない。優柔不断というか、自信がないというか、歯がゆい限りである。リスクマネージメントは重要であるが、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」といった勢いで動く人たちに対して支援を出し惜しむ傾向がある。日本の企業はどうもその傾向が強く、特に大企業はいけない。それに比べて中小企業の方が、世界の荒波を受けながらも、果敢に新規事業を起こし、イノベーションに盛んに取り組んでいるようにも思えるのだ。
日本の現状を指して「アグリー・ダックリン」と呼ぶのには、もうひとつ理由がある。日本の街は汚い、雑多であると海外から言われ続け、都市のあり方に対しても自信を失っている。20世紀に入って日本人は性急に都市をつくり続け、急成長を達成し、スクラップ・アンド・ビルド方式の建設サイクルを実現させてきた。そのことが、環境が変わり縮小の時代に入ると逆に多くの不要な施設や住宅を生み出してしまうのである。だから現在の街並みの中には古く役に立たないということで見捨てられた建築が山のように放置されている。俗に20世紀の負の資産と呼ばれる都市環境や施設群である。20世紀の工業化時代に成長を合言葉につくられた産業施設や高密度の住宅地が、今となっては邪魔物として煙たがられているわけだ。一昔前であれば、それらをきれいさっぱり取り壊して、新しいビル群に置き換えるというのが再開発の定石であったが、ここで強調したいのは、そうした邪魔物が実は新たな可能性を有した宝の山であるということである。遊休化した「みにくい」建築が新たな価値を帯びて未来にはばたく日が近い、と言い換えてもよい。「アグリー・ダックリン」は我が国が今後都市の活力の回復にむけて動きだすためのキーワードなのである。
本書を書き始めたきっかけはそのような問題意識にある。リスクに対して消極的な国や大企業といった枠組みではなく、進取の精神をもって都市や地域の問題に果敢に取り組んでいる人たちを対象に、暗く曇りがちな我が国の都市状況をめぐって、元気の出る、面白いまちづくりの仕組みを提案したいと思ったからである。その背景には、私たちがこの十年来、みずから「アグリー・ダックリン」を自認して国内外で取り組んできたいくつかのアクションがあり、ここでは失敗事例も含めて紹介し、今後の都市づくりの一助としたいと考えている。都市には必ず主人公がいるもので、主体が見えない運動は成功しない。その意味で、やや手垢がついた「都市再生」といった決まり文句ではなく、人と場所(ロケーション)と状況(シチュエーション)を介してこれらの活動を見てみよう。ある種のパフォーマンスを含んだ文化の仕掛けのための一助としたい。
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。