ここが知りたい 木造住宅の構造設計Q&A
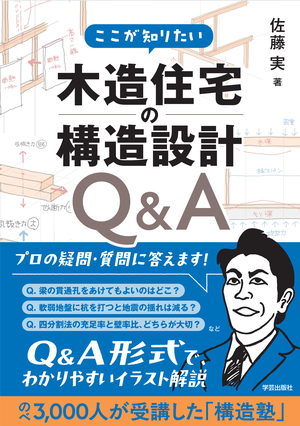
著者主宰の塾に多く寄せられた疑問に答える
2025年の建築基準法改正により、木造住宅の新築時に構造計算書の提出が必須となるなど、設計実務者への影響が大きくなっている。本書は、著者が主宰する延べ3000人以上が受講の「構造塾」に多く寄せられる実務上の疑問に答える形で、木造住宅の設計に必要な構造知識をQ&A形式で構成した、実践的な手引きである。
佐藤 実 著
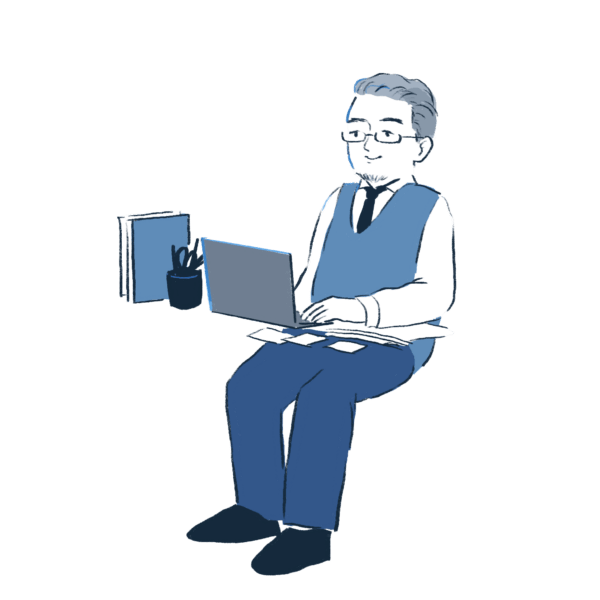
| 体裁 | A5判・176頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2300円+税 |
| 発行日 | 2025-09-30 |
| 装丁 | 美馬智 |
| ISBN | 9784761529512 |
| GCODE | 4076 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| ジャンル |
はじめに
第1章 耐震基準
Q001 木造住宅の構造安全性検討方法はどのようなものがありますか?
Q002 構造安全性検討方法の違いが、間取りの制約につながることはありますか?
Q003 耐震等級3の先を目指すには、何がオススメですか?
Q004 どうして耐震等級3が必要なのか? 耐震等級1ではダメなのですか?
Q005 耐震等級3「相当」について、「良い」と「悪い」がある?
Q006 構造安全性検討方法により計算内容の違いはありますか?
Q007 構造計算(許容応力度計算)を覚えるにはどうしたらよいですか?
Q008 耐震等級3をお施主様に納得してもらうための伝え方は?
Q009 新耐震基準は最新の基準なのですか?
Q010 新耐震基準の耐震性能は?
Q011 新耐震基準の木造住宅の地震被害状況は?
Q012 全国の木造住宅の耐震化率が9割近いですが、ホントですか?
Q013 瓦屋根は地震に弱いのですか?
第2章 構造計画
Q014 構造計算するとコストアップになるのはなぜですか?
Q015 力業(ちからわざ)の構造計算とは、どういうことですか?
Q016 構造を考えて間取りを作るには?
Q017 構造を考えて間取りを作ると、間取りの制約やデザインの弊害になりませんか?
Q018 耐力壁はどのように配置したらいいですか?
Q019 そもそも水平構面って何ですか?
Q020 べた基礎のスラブ区画はどこに作ればいいですか?
Q021 スラブの大きさの基準について教えてください。
Q022 ダメな基礎を見抜くポイントを教えてください。
Q023 ダメな間取りの見抜き方は?
Q024 パネル化をしてもコストダウンしないのはなぜですか?
Q025 木造住宅でスケルトン・インフィルをやる意味と方法は?
第3章 地 盤
地盤調査
Q026 スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)はどのような調査ですか?
Q027 住宅にはどの地盤調査方法がオススメですか?
地盤判定
Q028 構造計算していない木造住宅でも地盤判定できますか?
Q029 構造計算(許容応力度計算)で地盤の安全性は確認できていますか?
Q030 地盤判定による地盤改良判定が覆ることは問題ないのですか?
Q031 液状化判定は行うべき?
Q032 液状化判定による液状化の危険性が確認できた場合どうしたらよいですか?
地盤補強
Q033 木造住宅では、なぜ杭による地盤補強も「地盤改良」と呼ぶのですか?
Q034 建物重量が不明なのに地盤改良設計ができるのはなぜですか?
第4章 基 礎
コンクリート
Q035 コンクリートの設計基準強度とは何ですか?
鉄筋の基準
Q036 木造住宅の基礎で使う鉄筋はどの太さまで?
Q037 定着長さの取り方はどうやって決めますか?
Q038 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは?
Q039 継手長さと継手位置を決めるときの注意点は?
Q040 鉄筋と鉄筋のあき(間隔)はどのくらいあければいいですか?
基礎設計
Q041 べた基礎と布基礎の併用はできないの?(異種基礎禁止)
Q042 基礎の接地圧とは何ですか?
Q043 べた基礎のスラブを厚くすると強くなりますか?
Q044 布基礎、べた基礎を選ぶ基準とは?
Q045 なぜ、べた基礎が増えてきたのですか?
Q046 べた基礎は安心ですか?
Q047 独立基礎はどのように設計するのですか?
Q048 袖壁の基礎はどう考えればいい?
Q049 そもそも地中梁とはどういうものですか?
Q050 スラブを補強するだけの仮想地中梁とは?
Q051 基礎立上り縦筋のフックをなくす方法はありますか?
Q052 基礎梁の主筋は何本まで縦に配置できますか?
Q053 なぜ、決まった根入れ深さが必要なのですか?
Q054 基礎の立ち上がりがほぼ無いフラットなスラブ基礎は構造的に大丈夫?
Q055 基礎の人通口はどこに取るべきですか?
Q056 杭があれば基礎断面は小さくできますか?
Q057 コンクリートブロックは基礎になりますか?
第5章 耐力壁
Q058 耐力壁の幅、高さなどの決まりはありますか?
Q059 耐力壁の構成で実際の設計で押さえておくポイントはありますか?
Q060 91cm+45.5cmの壁は耐力壁にできますか?
耐力壁の基準
Q061 開口部に掛け張りする面材は耐力壁になりますか?
Q062 面材耐力壁の穴あけ基準を教えてください。
Q063 水平構面の穴あけ基準は?
Q064 面材耐力壁の入り隅対策とは?
Q065 面材耐力壁の仕様とは?
Q066 面材耐力壁と筋かい耐力壁の併用は可能ですか?
Q067 面材耐力壁と筋かい耐力壁、耐震性能はどちらが上ですか?
Q068 面材を選ぶ基準を教えてください。
Q069 面材耐力壁をビス留めしても大丈夫?
Q070 筋かい耐力壁はなぜ左右交互に配置するのですか?
Q071 面材耐力壁のへりあきはどのくらい?
Q072 筋かいプレート2点留め、3点留めどちらが良いですか?
耐力壁の設計
Q073 計算方法によって壁量に違いはありますか?
Q074 建物重量が大きいと壁量が多くなるのはなぜですか?
Q075 2025年建築基準法改正による新たな壁量計算とは?
Q076 2025年建築基準法改正による新たな壁量計算により耐震性能は向上する?
Q077 準耐力壁等は、壁量計算に算入した方が良いですか?
Q078 多雪区域でも壁量計算で問題ないですか?
Q079 高さの低い耐力壁は計算に算入できますか?
Q080 建物端部の筋かいの向きは?
Q081 風圧力に対する壁量計算、1.35mの意味は?
Q082 平面上の斜め壁の壁量計算方法を教えてください。
第6章 壁の配置バランス
Q083 壁の配置バランスはなぜ重要なのですか?
Q084 四分割法の充足率と壁率比、どちらが大切ですか?
Q085 偏心率とはどのような計算ですか?
Q086 効率のよい壁の配置バランスはどのようにすればいい?
Q087 壁の配置バランスを整える方法を教えてください。
Q088 偏心率と四分割法の関係性とは?
Q089 一面開口をつくる方法とは?
Q090 太陽光パネルを載せるときの偏荷重設計について教えてください。
第7章 柱頭・柱脚の接合
Q091 下階の柱がズレているとき引抜力はどうなるの?
Q092 なぜ柱頭・柱脚の接合設計が必要なのですか?
Q093 N値計算はどのような計算ですか?
Q094 土台設置型引抜き金物を使うときの注意点は?
Q095 出隅柱の金物はなぜ大きくなるのですか?
Q096 斜めに地震力が来るときのN値計算はどう考える?
Q097 筋かい補正値は何の計算に使いますか?
Q098 通し柱にも金物は必要ですか?
Q099 上下階の金物整合は必要ですか?
Q100 N値5.6を超えた場合はどうしたらいいですか?
Q101 ホールダウン金物は足し合わせをしても大丈夫?
第8章 仕様ルールほか
令42条2項関係
Q102 アンカーボルトはどこに取り付ければいいですか?
Q103 アンカーボルトの役割は何ですか?
Q104 ホールダウン金物用のアンカーボルトがあれば、 土台設置用のアンカーボルトは不要?
令43条関係
Q105 横架材間垂直距離とはどこの距離ですか?
Q106 柱の有効細長比とは何ですか?
Q107 横架材や基礎のスパン表を使うときの注意点は?
令44条関係
Q108 通し柱は必要ですか?
Q109 梁の間柱欠きこみは危険ですか?
Q110 梁の貫通孔をあけてもよいのはどこですか?
令46条3項関係
Q111 添え梁と、同断面の梁はどちらが強いですか?
Q112 火打ちの設置基準はありますか?
Q113 そもそも火打ちはなぜ必要なのですか?
Q114 火打ちと構造用合板、どちらが強いですか?
Q115 勾配天井の斜め部分に火打ちを設置しても大丈夫?
第9章 構造計画の目安・地震ほか
Q116 柱の直下率の目安は?
Q117 木造住宅で柱を鉄骨柱にすると混構造になる?
Q118 木造住宅に取り付ける制振装置、どれがオススメ?
Q119 吹き抜けはどこまで大きくできますか?
Q120 安全な吹き抜けの目安は?
Q121 窓はどこまで大きくできますか?
Q122 スキップフロアーの構造上の注意点を教えてください。
Q123 出隅部分のコーナー窓は構造的に問題あり?
Q124 大屋根の構造はどのように設計しますか?
Q125 オーバーハングの注意点とは?
Q126 セットバックの注意点とは?
Q127 無垢材と集成材、どちらがオススメですか?
Q128 合板は剥がれないのですか?
Q129 基礎下に敷きこむボード系断熱材は、家の重さでつぶれませんか?
Q130 基礎下に敷きこむボード系断熱材と、杭の取り合いはどうする?
Q131 震度7以上の地震は無いのですか?
Q132 軟弱地盤に杭を打つと、地震の揺れは減りますか?
Q133 地盤に柔らかいものを入れると免震効果がありますか?
Q134 耐震等級3でも地盤が弱いと意味がない?
Q135 キラーパルスはなぜ木造住宅を倒壊させる?
Q136 津波に耐えられない木造住宅に耐震性能は必要ですか?
Q137 多雪区域の雪の重さはどの程度ですか?
Q138 マグニチュードと震度の違いは?
Q139 地震地域係数Zとは?
あとがき
本書は、木造住宅の構造設計に関する「ここが知りたい」を分野ごとに整理し、Q&A方式でまとめた一冊です。対象は構造設計の実務者に限らず、これから構造を学ぶ学生や若手設計者、間取りを作成する意匠設計者、現場監督や施工技術者、さらには営業担当者まで、木造住宅に関わるあらゆる立場の人に読んでいただきたいと願っています。木造住宅の構造を理解することは、誰にとっても共通の基盤となり、日々の業務や判断の質を大きく高めてくれるからです。
私が「構造塾」を立ち上げたのは2010年のことです。当初は、木造住宅業界における構造知識の不足を痛感し、基礎から学べる場を提供したいとの思いから始めました。あれから16年、執筆時点の2025年までに延べ3000名以上の方々が受講し、その中から多くの構造計算技術者が育ちました。2019年には全国28会場で年間150回以上の講座を開催しましたが、2020年以降はコロナ禍の影響によりすべてオンラインに移行しました。現在は、毎週月曜日の「基本コース」と、月・火・水の3日間で実務者向けに学ぶ「マスターコース」の二本立てで運営しています。そのなかで寄せられた多くの質疑を整理し、代表的な139項目をまとめたのが本書です。
構造設計は、一度覚えれば終わりというものではありません。実践を重ねれば重ねるほど「さらに知りたい」が増えていく奥深い世界です。私自身、構造設計に携わって30年以上になりますが、初歩から体系的に学べる教材が少なく、また相談できる環境も整っていなかったため、多くの遠回りをしながら歩んできました。だからこそ、本書は「当時の自分が一番欲しかったもの」を形にしたつもりです。読者の皆さまが効率よく学び、現場で活かせるよう願っています。
本書は最初から順に読む必要はありません。疑問が浮かんだとき、目次から関連する項目を探し、答えを見つける。そんな辞書的な使い方を意識しています。もちろん通読すれば構造設計の全体像がつかめますが、日々の実務の中で困ったとき、迷ったときに気軽に開いていただければ幸いです。
木造住宅に携わるすべての方へ。本書が構造の理解を深め、より安全で安心できる住まいづくりにつながることを願っています。
本書をご覧いただき、本当にありがとうございます。ここまでお付き合いくださった読者の皆さまに、まずは心から感謝申し上げます。
本書は、本文の執筆はもちろん、解説のためのイラストやキャプション(注釈)に至るまで、すべて私自身が手掛けました。イラストを描く経験はこれまでなく、正直かなり苦労しましたが、言葉だけでは伝わりにくい部分を補い、より理解していただけるようにとの思いで、一枚一枚心を込めて描き上げました。伝えたいことを自分の手で表現できたことは、大変でしたが、とても貴重な経験になりました。
今回の執筆にあたり、編集担当である知念靖廣さんから「イラストもぜひご自身で描いてほしい」と声をかけていただいたことが、すべての始まりでした。うれしさと同時に大きな戸惑いもありましたが、実は以前、別の著書制作の際にイラストレーターさんへ依頼するために大量の下絵を描き、それをインスタグラムに投稿していました。それを知念さんに偶然見つけていただいたことがきっかけとなり、今回の挑戦へとつながったのです。
当初の出版予定からは、私自身の怠慢もあって大幅に遅れてしまいました。その間も知念さんは辛抱強く待ってくださり、イラスト制作に取り掛かってからも進行は決して早くありませんでした。数ページ描いては送り、また数ページ描いては送りという状況で、なかなか前に進まない中、それでも毎回「いいですね」「とても分かりやすい」と励ましの言葉をかけていただきました。その度にやる気を取り戻し、またペンを握ることができました。
発売日が決まったときは、さすがに背中を押される思いでした(笑)。ギリギリのスケジュールの中でありながら、クオリティを落とさず描き切れたのは、編集のサポートと寛容なお心遣いのおかげです。完成した本を手に取り、自分の言葉と絵が一体となって形になったことを誇りに思います。
本書を通じて、木造住宅の構造設計の面白さと奥深さを少しでも身近に感じていただけたなら、著者としてこれ以上の喜びはありません。そして本書が、これからの学びや実務に向かう皆さまの背中を、ほんの少しでも押すことができれば幸いです。
公開され次第、掲載します。
開催が決まり次第、お知らせします。
メディア掲載情報
| 日付 | タイトル |
|---|---|
| 2025年10月17日 | 『ここが知りたい 木造住宅の構造設計Q&A』(佐藤 実)が「新建ハウジング」で紹介されました |
| 2025年10月6日 | 『ここが知りたい 木造住宅の構造設計Q&A』が著者・佐藤実さんのYouTube「「構造塾」チャンネル」で紹介されました |
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。







