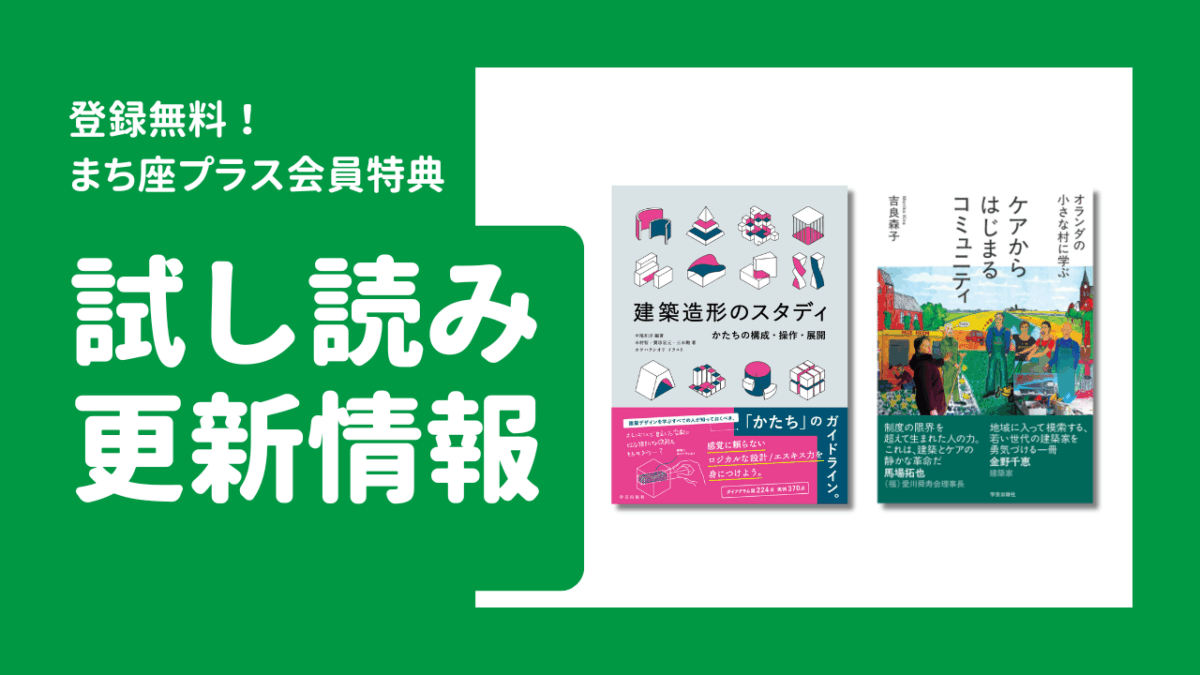オランダの小さな村に学ぶ ケアからはじまるコミュニティ
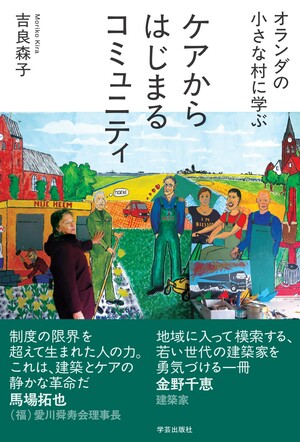
住民がつくる多世代共生、地域ケアの実践
オランダの小さな村で、住民たちが老人ホームを買い取り、多世代共生の場へと再生した物語。障害者のデイケアや地域活動を通じて培われた「住民が育てるコミュニティ」の軌跡。その具体的なプロセスを建築家である著者が10年間の密着取材から紐解く。ケア、福祉、まちづくりに携わる人、暮らしのつながりを育てる全ての人へ
吉良 森子 著

ログイン
新規登録
まえがき 0歳から100歳まで、誰もがケアし合うコミュニティ
第1章 オルドヘームの一日──近隣の暮らしの場に変わった老人ホーム
オルドヘームの朝
障害者のグループホームを見守るメンターたち
近隣をサポートする、障害者デイケアのメンバーたち
朝のコーヒー、午後のバックギャモン
オルドヘームの夕べ
第2章 オルドヘームで暮らす人たち──人生の様々なステージに応える拠点
ほどよくつながり心地よく離れる
機能の余白がある、緩やかな建築
「人それぞれ」を受けとめられる場所
88歳の地元っ子、ゲルトさん
老人ホーム時代から住んでいるザウドマさん
アトリエと住まいを借りたアーティスト、ヨハネカさん
シングルマザーのカルラさん
ひとりではないと感じながら暮らせる場
第3章 住民が描いた村の将来──老人ホームを買い取ったコミュニティ
集落に背を向けていたオルドヘーム
未来を予想して牽引した、アナさん
日本の学生たちには見えた、オランダの小さな村の可能性
将来のアトリエ──みんなで構想する村のこれから
対話と模索を重ねて
コミュニティとしての決断
いろんな世代が集う場に生まれ変わった
第4章 オランダ福祉政策の変容──コミュニティの力なしにはもう成立しない
壁画が伝えるメッセージ──等身大のメンバーたち
一人ひとりのウェルビーイングを支えるもの
住民が育てる、誰もが参加できるコミュニティ
大規模化する福祉事業──人に寄り添うケアの喪失
オランダならではの「変化する」文化
コミュニティが主体となる仕組みへの転換
第5章 活動から事業へ──「自分たちの答え」にたどり着くまでの10年
見えてきたのは、自主事業という形
自治体・企業・コミュニティ、三位一体の時代
障害者だけでなく、地域にとって意味のある活動に
ビジョンの共有、事業計画の完成、プロジェクト開始(2006.2009)
あっけなく挫折、そして再スタート(2009)
「ケアから始まるコミュニティ」の本当の始まり(2009.)
事業者たちの限界
住民主体でなければ成り立たない
コミュニティ活動から事業への脱皮(2017.)
自治体と住民の対等な関係
第6章 変化し続けるコミュニティ 岐路で自分たちのビジョンに立ち返る
コーディネーターとマネージャー
管理するというより、家族のように見守る
状況と向きあいながら形づくられたオルドヘームの運営
コミュニティ事業ならではの持続力
隙をついた乗っ取り事件
事件を乗り越えて生まれた仕組み
活気ある集落に投資したい──ニコレットさん
役に立つことが何よりも大切──コニーさん
集落と農地と北海を、子どもたちの世代に──ベンさん
変わり続けるオルドヘーム──熱心なのは中高年層ばかり、というジレンマ
コミュニティがパートナーとなる時代
あとがき クロースターブールンが教えてくれたコミュニティの力
まえがき 0歳から100 歳まで、誰もがケアし合うコミュニティ
アムステルダムから車で北に向かって2時間余り、北海のすぐ近くにクロースターブールンという小さな村がある。この辺りはオランダでも有数の農業地帯で、水平線の彼方まで麦やジャガイモ畑が広がっている。クロースター(修道院)という名前の通り、12世紀に 設立されたカトリックの修道院がこの村の起源だ。しかしオランダがプロテスタントの国として建国された16世紀に、修道院は破壊されてしまう。その跡地に農家や民家が肩を寄せ合うようにして集落が形成され、クロースターブールンという村が生まれた。修道院時代の唯一の名残はニコラス教会の塔だ。小ぶりな煉瓦が積み上げられ、 どっしりとした三角屋根の塔はこの村のシンボルで、広大な畑の向こうに塔が見えてくると、アムステルダムからの車の旅も終盤だ。
クロースターブールンとその周辺に住んでいる人の数は800人余り。この小さな集落のコミュニティ活動が近年オランダで注目を浴びている。古くからこの集落にある老人ホームを、住民たちが買い取って「コミュニティ・ハウス」として運営を始めたのだ。2008 年以来、オランダでは政府による福祉政策の転換の結果、全国で小さな集落の老人ホームの閉鎖が起こり、 社会問題となっていたため、多くの新聞がこのことを取り上げた。クロースターブールンを密着取材したテレビ番組も話題になった。2018年には、小さなコミュニティのサポートをライフワークとするオランダ国王アレキサンダーが視察に訪れ、その年のクリスマスのスピーチでクロースターブールンの住民の活力を讃えたほどだ。
こうしてクロースターブールンは、一躍オランダのコミュニティ活動のトップランナーとして注目されるようになった。だが、彼らはいきなり老人ホームを買い取ったわけではない。長い間の活動の積み重ねがあった。高齢化と地方の人口減少が社会問題として認識され始めた2000年ごろから、住民有志が色々なコミュニティ活動を起こしてきた。クロースターブールンが属するフローニンゲン州は、州都以外はたくさんの小さな集落で構成されていて、すでに州都への人口集中が顕著で、周辺集落の人口減少と高齢化が他の地方よりも早く始まった。ここでは集落の将来への危機感がもともと強かったのだ。
なかでもコミュニティ活動がはっきりと形になったのは2006年につくられた障害者のデイケアセンター「ミンテゥンチェ」の発足だ。通常、障害者のデイケアセンターでは農園の手伝いやお菓子づくりなど1箇所で誰もが同じ作業を行うが、ここでは一人ひとりの希望や特性を考慮しながら、近隣住民から必要とされている作業を請け負っている。活動内容は、農家や施設での作業、高齢者のサポートなど多岐にわたる。
イニシアチブをとったのは障害者の保護者たちだ。彼らはクロースターブールンのような小さな集落であれば、住民に見守られながら、障害者もコミュニティの一員として暮らせるのではないかと考えた。最初は8人のメンバーで、ボランティアに支えられて始まったデイケアセンターも30名余りのメンバーに増え、今では安定した収入のある組織に成長した。
さらに2013年には、障害者のグループホームが老人ホームの一角につくられた。デイケアを設立したメンバーは当初、障害者の仕事の場だけでなく、暮らしの場もつくろうと、集落の中に新しくグループホームを建設しようと自治体・住宅協会との話し合いを行った。しかし2008年の経済危機の影響もあって叶わず、老人ホームの一角を使うことになった。その後コミュニティ活動は徐々に幅を広げていく。カトリック教会の庭を使ってコミュニティ菜園をつくったり、礼拝が行われなくなったニコラス教会を引き取ってコミュニティの集会所に改装したり。一部の住民のイニシアチブで始まった、初夏のバザーにも次第に近隣住民の出店や参加が増え、障害者や高齢者だけでなく、多様な世代の住民が参加できる活動を展開しながら、クロースターブールンの住民にコミュニティ意識が醸成されていった。
2015年に福祉事業者が老人ホーム「オルドヘーム」から撤退を決めた時、60室余りからなる老人ホームが空き家になれば、集落にとって大きな負のインパクトになると多くの住民が声をあげた。オルドヘームで終末期を迎えようと考えてきた集落の高齢者たちは慣れ親しんだ土地を離れて遠くの老人ホームに入所しなければならなくなる。せっかく軌道に乗ってきた障害者のグループホームを継続することもできない。集落の中心に大きな空き家を抱えることになる。有志による住民組合設立の声に200名を超える住民が応えて参加し、全員一致で組合による老人ホームの買い取りが決まった。
住民組合がオルドヘームの運営を始めると、徐々にいろんな世代の住民が暮らし、訪れる場所に変わっていった。自立して暮らしていけるけれど、一戸建ての家を持て余していた高齢者たちが最初に引っ越して来た。しばらくすると、新しい家を探す親子や、安価な住まいを見つけられない若者も移り住んだ。若い保育士さんたちが保育園を開設し、放課後の学童保育を併設した。日常品を売る小さな店はボランティアが引き継いで運営し、設備の整った大きなキッチンがあると聞いて、デリバリーのケーキ屋さんがやって来た。関係者以外は入りにくい雰囲気があった老人ホームが、自然にコミュニティの暮らしの場に変わっていった。
とはいえ、運営が安定するまでには色々なことがあった。光熱費を抑えるために、フローニンゲン州からお金を借り、運営しながら設備を更新し、全ての窓を三重ガラスに替えた。保育園の許可を取るための整備にもお金がかかった。当初運営を担っていた人たちがオルドヘームを乗っ取ろうとしたこともあった。一つひとつの問題を乗り越えながら、住民組合は自分たちならではの運営方法を模索していった。
私がこのクロースターブールンを知り、通うようになったのは2013年ごろからだ。きっかけは「住民を主体とした住環境づくり」をテーマとしたフローニンゲン市のシンポジウムにパネラーとして登壇したことだった。そこで、クロースターブールンのコミュニティ活動を牽引してきたアーティスト、アナ・ヒルブリンクさんに出会った。アナさんは、前述の障害者のデイケアセンター、ミンテゥンチェ設立を働きかけた人だ。彼女はそれ以来、村のコミュニティ活動の中心となって、専門家や住民を巻き込んでワークショップを何度も開き、人材を発掘し、自治体や住宅協会との交渉を繰り返して、グループホーム、コミュニティ菜園、 住民組合の設立へとコミュニティの運営力を高め、発信してきた。アナさんは元々、場の潜在力を形にするパブリックアートをつくってきたアーティストだ。クロースターブールンの地勢と文化の力を見極め、活動していく信念や実行力も、彼女の創作力とつながっている。
私は建築家として、住民が主体となって計画する共同開発の住宅や集合住宅の設計をテーマとして日本とオランダで活動してきた。住民が力を合わせて共に暮らす場所をつくることがこれからの高齢化、人口減少の時代に求められている。どうすれば、集まって住む場所が単なる家の集合体ではなく、コミュニティとして近隣との関係をつくりながら、育っていくのか。家の集合体をデザインするのではなく、将来そこで暮らしていく人たちのつながりをデザインしていくことはできないのだろうか。そんな曖昧な疑問を抱えていた私は、アナさんとの出会いや、クロースターブールンのコミュニティ活動との関わりを通して刺激を受けてきた。住民それぞれが暮らしを営みながら、お互いの存在が日々の暮らしを豊かにしていく場をつくっていくことができる。クロースターブールンでそれを確信することができた。では、ここ以外の場所でそんなコミュニティを形成していくにはどうしたら良いのだろう。誰がイニシアチブをとって、どういう手順で進めていけば良いのだろう。なぜクロースターブールンでは可能だったのだろう。
1歳から100歳の住民誰もが参加し、自ら様々な活動を運営するクロースターブールンのようなコミュニティはオランダでも他にまだ例はない。でも少しずついろんなところで住民が集まって自治体や事業者にはできないケアや活動を通して、顔の見えるコミュニティ事業を展開し始めている。住宅・環境・食・貧困・孤独、テーマは様々。クロースターブールンのような小さな集落だけでなく、ロッテルダムのような大都市でもいろんなイニシアチブがコミュニティ事業のネットワークを形成し始めている。そういうつながりと仕組みを21世紀に生きる私たちは必要としているのだ。
私がアナさんと出会って、10年余りが経った。私もクロースターブールンの住民組合のメンバーとなり、 建築の専門家として、ひとりの市民として関わってきた。多くの学びがあった以上に、私はここで過ごした時間と人々とのつながりをかけがえのないものだと感じている。クロースターブールンで起こったことは、奇跡ではないし、ここでしか起こり得ないことでもない。
日本もオランダも、高齢化や過疎化、社会システムの複雑化といった課題を共有している。制度や文化は異なるが、クロースターブールンのように長い歴史とともに地域の文化を育んできたコミュニティは日本各地にたくさんあり、多くの人たちが様々なイニシアチブを起こしている。オランダ北端の小さな村の発想や取り組みが、そうした活動への刺激や参考になれば──そんな思いでこの本を書いた。
公開され次第、掲載します。
開催が決まり次第、お知らせします。
終了済みのイベント
メディア掲載情報
※SNS等にて公開投稿されていた読者の皆様のレビューを、埋め込み表示させていただいております。不都合がございましたら、お手数ですがページ末尾のご意見・ご感想フォームよりご連絡をお寄せください。
吉良森子『オランダの小さな村に学ぶ ケアからはじまるコミュニティ』学芸出版社2025は実に良い本。拙著『未来のコミューン』の最終章で書いた住み方のヴィジョン。20年前から彼女は地道にやってた。自然にしっかりと描いたレポート。そして彼女の建築家の定義が素晴らしい。#通勤書評 pic.twitter.com/ikGj8rSqjK
— 中谷礼仁NorihitoNAKATANI (@rhenin) October 29, 2025
『オランダの小さな村に学ぶ ケアからはじまるコミュニティ』(吉良森子、学芸出版社、2025年9月)を読み終える。たいへん良かった。「近隣」にケアしあう関係性をつくるためのヒントが。著者は建築家で、適量のケアを調整しやすい空間という視点も。ケアを閉じ込めず開いていくことで安心が育まれる。
— 長久啓太(岡山県学習協) (@okayamagaku) September 24, 2025
吉良森子『オランダの小さな村に学ぶ
ケアからはじまるコミュニティ』学芸出版10日間かけて読破。
住民主体のコミュニティ形成。その中には福祉も内包する。
「超高齢社会」「2025年問題」「介護人材不足」「限界集落」そのような課題に直面する日本にとっての処方箋となる1冊だと感じました。 pic.twitter.com/mdkrTmZvpE
— M.H. (@mi_hayashi0528) October 4, 2025
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。