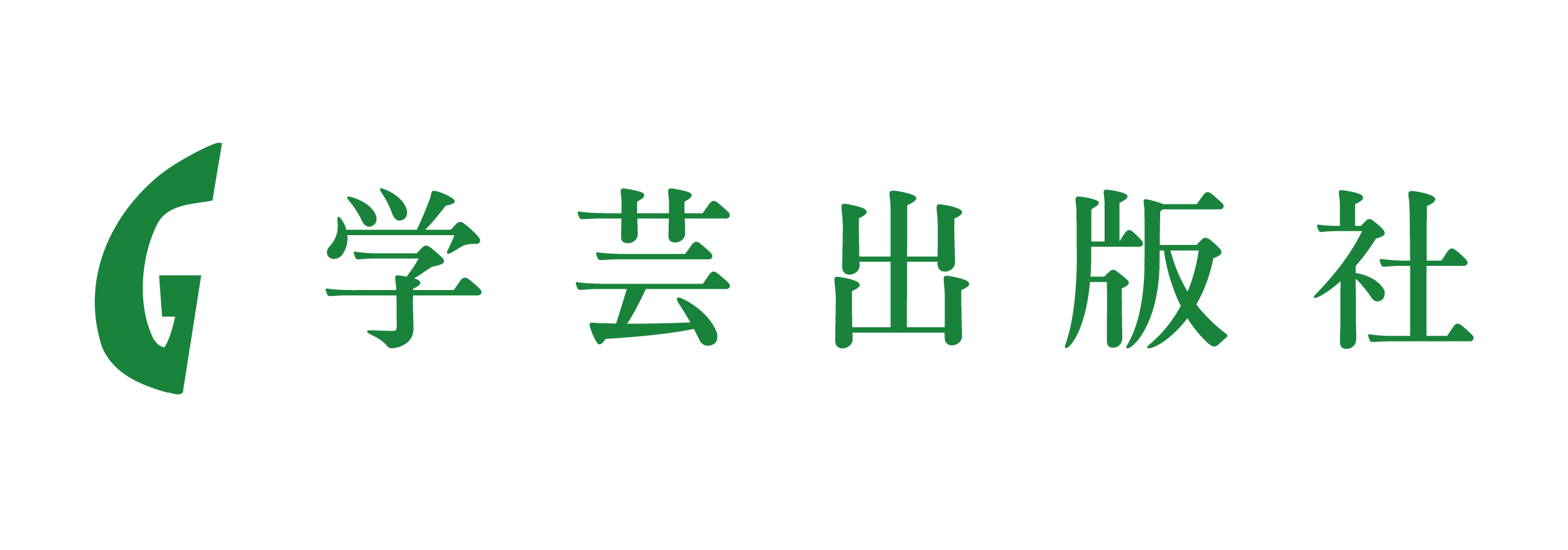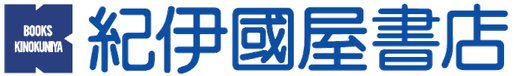図解 庭師が読みとく作庭記・山水并野形図

現場で使える秘伝書の読み方をやさしく解説
日本庭園愛好家や造園関係者に好評を博したロングセラー『図解 庭師が読みとく作庭記』をバージョンアップし、『山水并野形図』を新たに増補。独自の段落分けとわかりやすい小見出し、作庭経験を踏まえた現場で使える図解・訳注で、従来の抽象的な解釈を超えた、秘伝書の読み方を提示。日本庭園史の二大古典をこの一冊で。
小埜雅章 著
| 体裁 | 四六判・268頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2500円+税 |
| 発行日 | 2016-11-01 |
| 装丁 | KOTO DESIGN,Inc. 山本剛史 |
| ISBN | 9784761526344 |
| GCODE | 2267 |
| 販売状況 | 在庫×・重版未定 |
| ジャンル |
作庭記
一、石立ての心構え
二、池庭づくりの留意点
三、池庭の構成
四、遣水を流す
五、石を立てる
六、木を植える
七、泉を構える
八、雑部
山水並野形図
一、石の五色と相生
二、庭の三要素―山・水・石
三、庭づくりの勘所―一口伝授
四、池庭
五、施主と庭づくり
六、庭の観賞心得
七、庭石の起源
八、石の据え様(一)
九、庭木の扱い
十、石の据え様(二)
『作庭記』について
『作庭記』は、寝殿造建築に対応する庭のために書かれた庭づくりの秘伝書であり、日本最古の作庭書である。内容は専門的、かつ、具体的で、体験を踏まえた上で勘所だけを示した、高度な技術書となっている。口伝を必要とする書とし、かつ、重要な部分は漢字ではなく平仮名とすることで(例えば、避き、良き)、解る者には解るように、解らない者には、それなりに解るように工夫をこらしたのである。
ほとんどの『作庭記』註釈書の底本となっているのが、谷村家所蔵の『作庭記』である。ただし、この巻物に『作庭記』という書名はない。「群書類従」の中に、ほぼ同一内容のものが『作庭記』として収められていたので、後世、拝借したに過ぎないのである。
所蔵系路により、『作庭記』は、『園池秘抄』、『前栽秘抄』とも呼ばれるが、少しだけ内容の異なったものに『山水抄』という異本がある。恐らく『作庭記』が纏め上げられるまでには、絵師の巨勢家や宋人などからの伝承、延円からの伝承等々、幾つかの秘伝書があって、これを集約したのが『作庭記』ということになるのであろう。その際、それぞれの編者、あるいは書写した人物が、自己の関心事に応じて、多少とも取捨選択したのは、想像に難くない。ただ、何れにしても、谷村家本ほど、秘伝をよく理解した上での表記となっているものは他にないと、私などは思っている。
『作庭記』の著者を考える上で、見落とせないのが、同書の「高陽院殿修造の時も、石をたつる人みなうせて~それをバさる事にて、宇治殿御みづから御沙汰ありき。その時には常参りて、石を立る事能々見きき侍りき」という文章である。高陽院の修造は、数度あるけれども、宇治殿こと、藤原頼通の死(承保元[一〇七四]年)以前では、長暦三(一〇三九)年の炎上による長久三(一〇四二)年の再建と、天喜二(一〇五四)年の焼亡による康平三(一〇六〇)年の再建がある。『百錬抄』によると、長暦三年は炎上で、天喜二年は焼亡である。つまり、長暦三年の際は、三年ばかり後に早くも行幸がある程の再建がなっている。ごく小規模の被害で庭の修造までは必要なかったのではないか。しかし、天喜二年の焼亡の折は、その再建は六年後のこととなっている。恐らくこの工事こそ、『作庭記』の著者が、「石を立てること、能々見きき侍りき」した時であろう。①宇治殿のすぐそばで、石立てのことを見聞きできる人物、②延円阿闍梨以後の人物、③巨勢弘高とほぼ同年代、もしくは以後の人物、④蓮仲法師による東北院石立て以後の人物で、その石立てを「禁忌を犯している」と判断できる作庭力の持主であるとともに、それを公言できるだけの地位の人物。
このようなことを考えていくと、頼通の子で、「伏見修理大夫と号し、水石風骨を得たり(『尊卑分脈』)」と評された橘俊綱が、著者として浮かび上がってくる。俊綱の自邸伏見殿の庭も、「風流勝他、水石幽奇也(『中右記』)」と賞されている。俊綱は長元元(一〇二八)年生まれで、嘉保元(一〇九四)年に六七歳で亡くなっている。長暦三年の高陽院炎上の折は、俊綱一二歳、天喜二年の高陽院焼亡の折は、俊綱二七歳、再建なった康平三年は三三歳である。天喜二年に俊綱宅の寝殿が、仮御所(頼通第四条宮)の南殿として移築されている(『百錬抄』)ほどであったから、天喜から康平年間にかけて、俊綱は作庭にも充分活躍した時期であろう。しかし、承保元(一〇七四)年の頼通の死、俊綱四七歳。承暦四(一〇八〇)年高陽院焼亡、俊綱五二歳。寛治七(一〇九三)年俊綱伏見殿焼亡、俊綱六六歳、と立て続けに不幸が続く。恐らく、頼通の死後、自己が相伝した文書などを後世に残す責任を感じ始めたのではないだろうか。
因みに高陽院創建は治安元(一〇二一)年。東北院落慶は長元三(一〇三〇)年。延円阿闍梨の死は長暦四(一〇四〇)年。東北院焼亡は康平元(一〇五八)年、東北院再建は康平四(一〇六一)年である。延円の死後東北院に蓮仲が立てた石というのは、東北院焼亡後、康平四(一〇六一)年の再建の折だとすると、この年、俊綱三四歳、嘉保元(一〇九四)年、六七歳で死亡するまでの間に『作庭記』は成ったことになる。
庭づくり、石組の特殊性
石組は、自分で施工できない。石組を指図する者は、石と対峙する側から、石と石との関連性、石の立ち具合、石の表情を常に見ていなければならない。三又など(今日ではクレーン)で吊り上げられた石は、三次元で千変万化する。その内の一瞬を捉えたまま、そのまま地上に根ざしてもらうべく、工人に指図しなければならないからである。石組の際は、石組を指図する者と工人とは、石を挟んで対極の位置にある。もし、大所高所から庭を沙汰するオーナーがいるとすれば、指図者はオーナーのすぐ近くにいて、沙汰をよく聞きとり、工人に指図しなければならない。『作庭記』に、高陽院殿修造に際して、「宇治殿御みづから御沙汰ありき。其時には常参て、石を立る事能々見きき侍りき」とあるのも、このことを言っているのであって、単に傍観者的に遠くから眺めていたわけではない。『作庭記』異本の『山水抄』が、同一内容の文章の中で、「予ヒトリ一向奉行シ侍ヘリキ」と述べているのも、沙汰をよく見聞きし、工人に指図しているのであって、要は両書とも同じことを言っているのである。沙汰(選び分ける)、能々(十二分に)、奉行(上命を奉じて、事を執行)、などの言葉は、石組における分業を如実に示している。指図する者は、施工するわけではないので、「予ヒトリ」で充分である。また、石組というものは、その日によって入れ替わり立ち替わり、別の人物がするものではない。故に、「常に参る」必要がある。
作庭記の底本と校訂の方針
本書は谷村家蔵本を底本とする。『作庭記』は『群書類従』にも収められているが、底本の緻密さは『群書類従』の比ではない。とは言え、不明、欠字の場合は、『群書類従』に拠った。底本の誤りとして、後世、文字の削除や訂正が行われているが、そのほとんどは秘伝を理解できないための苦肉の曲解である。底本そのままが、もっとも秘伝を心得た者による表記であることを知るべきである。
私が多少とも『作庭記』に関わるようになったのも、語句の正確な内容が把握できない限り、全体の内容が映像として、脳裏に浮かんでこないからであった。その端的な例が、本書〔19〕中「遣水の石を立つるにハ」の「つめ石」と「水こしの石」である。詳しくは本文に譲るが、平仮名に正解の漢字を当てることで、これらの石が池底から水面に向かって、高さ順に列挙されていることがわかる。ひいては、個々の石の特徴、役割も、明解に思い描けることになるのである。
『山水并野形図』について
『山水并野形図』は、奥書にある通り、美馬入道浄喜が相伝した増円以来の書や、秘事相承等が基となっている。これに浄喜自身が書き加えたものも含めて、全てを増悟上人に相伝させるにあたって、文安五(一四四八)年に纏めたのが本書である。したがってその成立は、室町頃と考えていいのであろう。本書には茶道の影響が微塵も見られないので、少なくとも桃山期以前の成立とも言える。むしろ「鏡石」や「曲木」などは、茶の世界でいう「蹲踞の後石」や「袖摺の松」を髣髴せしめる。「生本の二字にかえる」なども同様である。
また〔7〕に、「壷を構えつれば、壷故に難を除く」とある。後者の壷は、鎌倉から室町期にかけて流行した犬追物(悪霊である白狐代用の犬を射る)の矢壷のことを指している。したがって本書は、鎌倉期を遡り得ないことも、また確かなのである。
日本庭園の根源的な精神は、自然、草木、石に対する畏敬の念である。この精神的核心をついているのが『山水并野形図』である。「名石、無名石」などと、方便的に石を区別しているけれども、要は庭石に平気で腰を掛ける、その「心」を厳しく警告するのである。今日でも日本人が、深妙に庭に対座できるのも、この頃からの躾が効いているのであろう。
『作庭記』と『山水并野形図』の秘伝書二篇は、真摯に庭のことを知りたいと思っている人には、是非とも揃えてほしい書物である。この度、出版社に無理を聞いてもらって、二篇を合冊していただけることになった。長年の思いが叶えられて本当に嬉しいかぎりである。
お求めのご案内
本書は紙版品切れ・重版未定の商品です。紙版のお求めは、中古書店や図書館にお問い合わせください。
また、新版・改訂版が出ている可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
図書館蔵書横断検索
検索する- 「国立国会図書館サーチ」のページに遷移します。
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。