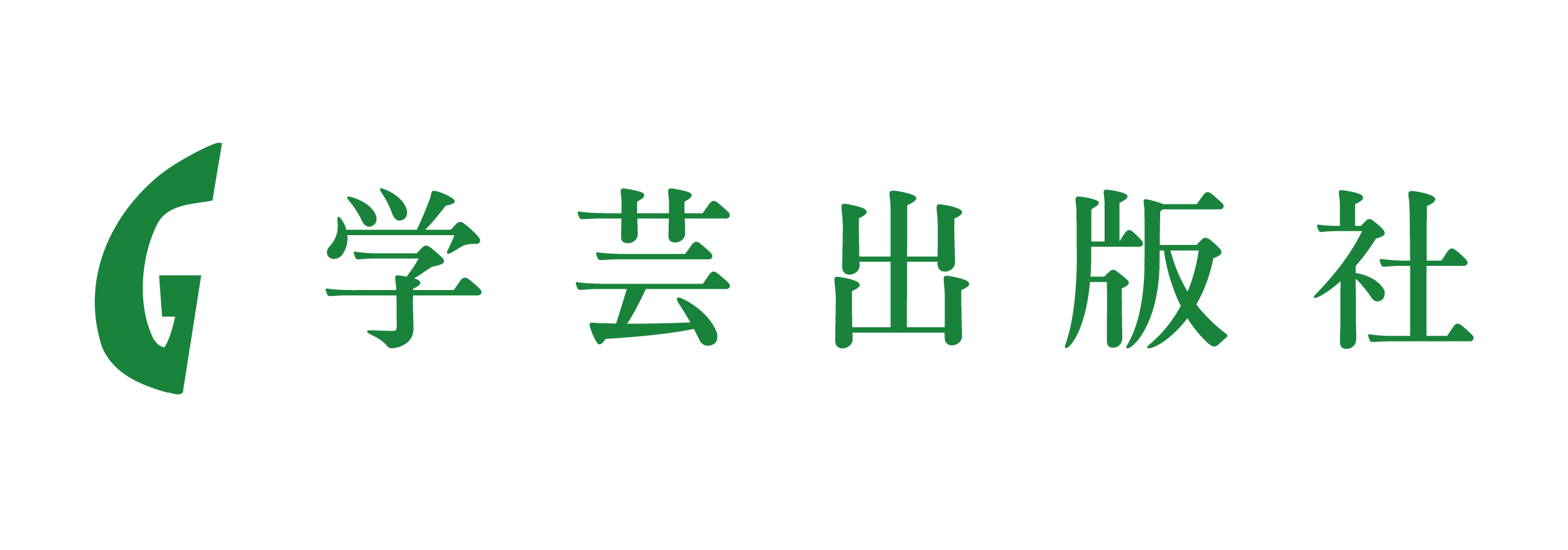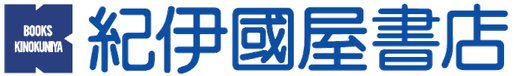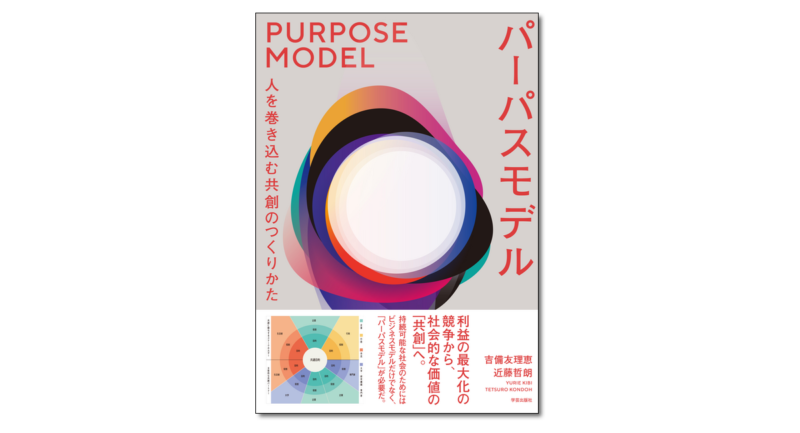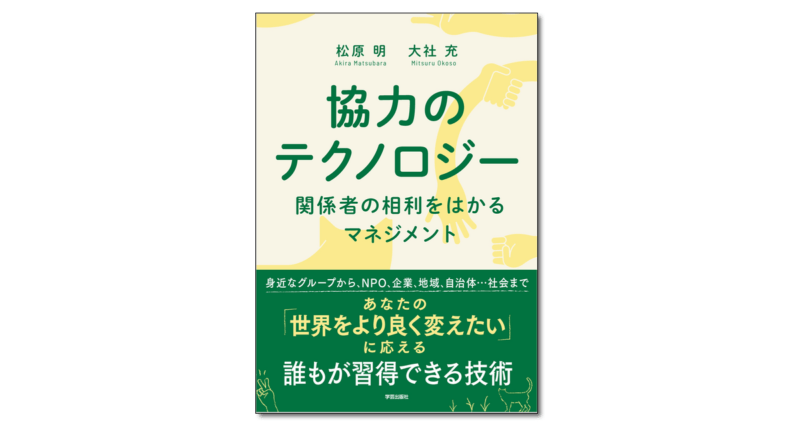未来に選ばれる会社
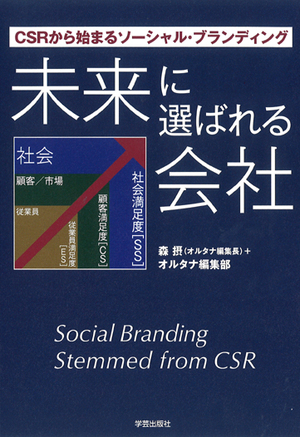
内容紹介
会社にとっての最大のミッションは組織や事業を永続化すること。その実現には、営利の追求だけでなく、社会全体から支持されることが必須だ。社会満足度を上げ、企業価値を高める「ソーシャル・ブランディング」という戦略。その方法論を、国内外30社以上の成功例から実践的に解説。未来を志向する会社の誠実な強さを探る。
体 裁 四六・224頁・定価 本体1800円+税
ISBN 978-4-7615-1353-5
発行日 2015/10/01
装 丁 安保 瑞枝
『日本でいちばん大切にしたい会社』坂本光司教授推薦!
利他経営、すなわち「社会を幸せにする会社」でなければ、ビジネスを続ける意味はない。その条件を満たしてこそ、企業が未来に選ばれる、つまり社会に存続を許されるのである。
50年後、100年後でも芯がブレずに成長していて、存在感があり、社会のためになっている会社を目指すためにも、本書は参考になるところが多い。坂本光司・法政大学大学院政策創造研究科教授
まえがき
第1章 いま改めて企業に必要なCSRとは
1 CSRは責任だけではなく「社会対応力」
2 ES×CS×SSの効用とは
3 CSRで株価を上げる(IR×PR×CSR)
4 必要なのは「広義のコンプライアンス」
5 儀式化してしまった「ダイアログ」
6 CSRはルール、CSVは競技
7 消費者も国際ルールも進化
8 最大のグローバルCSR課題は「人権」
[インタビュー Ⅰ] 坂本 光司(法政大学大学院政策創造研究科教授)
「企業の最大使命は社員を幸せにすること」
第2章ソーシャル・ブランディングの構造
1 ソーシャル・ブランディングの構造
2 マーケティングの「4P」も「4C」もソーシャルに
3 ソーシャル・ブランディングの7つの類型
4 ソーシャル・ブランディングの8つのステップ・27のポイント
5 ソーシャル・ミッション(企業の社会的使命)を作る
6 社会的課題を自社製品で解決する─ソーシャル・プロダクツ
7 ソーシャル・ブランディングの広報は「引き算」で
[インタビュー Ⅱ] 松本 晃(カルビー会長兼CEO)
「多様性なき企業に明日はない」
第3章 ソーシャル・ブランディングの実践 大企業編
「真のグローバル企業」には攻めのCSRが不可欠 [味の素]
トップの決断で始まったCSV [キリン]
「竹紙」「里山物語」で社会的課題を解決する [中越パルプ工業]
ストーリーでCSR/CSVを伝える [伊藤園]
創業者の思いをソーシャル・ブランディングに生かす [森永製菓]
CSR/CSV活動で沿線の価値を上げる [阪急阪神ホールディングス]
[インタビュー Ⅲ] 増田 典生(日立製作所 情報・通信システム社CSR部担当部長)
「『B2B2C2S』というアプローチ」
第4章 ソーシャル・ブランディングの実践 中堅企業編
子どもの成長を支援し、会社を次世代へつなぐ [ギンザのサヱグサ]
CSR/CSVで新マーケットを開拓 [山陽製紙]
「ついでに」「無理なく」「達成感」のCSR [石井造園]
地域の情報発信が自社の生き残り戦略 [シーズクリエイト]
違法木材は使わない、フェアウッド100%の家具 [ワイス・ワイス]
紅茶で地元・宇都宮を元気にする [ワイズティーネットワーク]
社員を「サーフィンと田植え」に行かせよう [白井グループ]
[インタビュー Ⅳ] 黒川 光博(虎屋社長)
「創業500年、『人を大切にする』経営哲学」
第5章 ソーシャル・ブランディングの実践 海外企業編
競争への危機感がCSRの原動力 [英国総論]
CSV元祖の最大目標は資源の調達 [ネスレ]
責任と良心ある経営の先駆者 [ザ・ボディショップ]
世界一サステナブルな小売業を目指す [マークス&スペンサー]
米国「社会的企業」の草分け的存在 [ベン&ジェリーズ]
企業使命としてのエシカル経営 [アヴェダ]
現地での信頼がブランド価値を高める [アメリカン・ホンダ・モーター]
[インタビュー Ⅴ] イヴォン・シュイナード(パタゴニア創業者)
「社員をサーフィンに行かせる本当の理由」
あとがき
本書のタイトル「未来に選ばれる会社」の「未来」とは、「未来の顧客」であり、「未来の社会」であり、そしていまはまだ生まれていないかもしれない「未来の従業員たち」という思いを込めた。結局のところ、会社にとっての最大のミッションは組織や事業を永続化することであり、これらは「サステナブル(持続可能な)」や「レジリエント(しなやかで強い)」という英語でも説明されてきた。
しかし、「企業が永続的になるためにはただ営利だけを追求すれば良いのではない」という当たり前のことが、現代社会では置き去りにされがちだ。顧客のすぐ後ろには社会があり、後述の「社会満足度」を高めることが企業の寿命を左右する。社会への取り組みを通じてレピュテーション(評価)を高め、企業の発展性を高めることこそが、地域・グローバルを問わず、企業間競争を生き抜くための強力な推進力になるはずだ。
「当社がCSR活動をやらないと、他社に先を越される。そうなれば競争で生き残れない」。CSV(共通価値の創造)の草分け企業として知られるネスレの担当者も、英国の大手小売業マークス&スペンサーの担当者も、異口同音にこう語った。カルビーの松本晃・会長兼CEOは「CSRはロングターム・インベストメント(長期投資)だ」と言い切った。
このように「顧客だけでなく社会全体から支持される」ことにより、「未来の顧客」に選ばれるための「強み」を作り上げる作業を「ソーシャル・ブランディング」と本書では定義する。
この場合の「ソーシャル」とは、「社会と対話する」「何らかの社会的課題を解決する」という意味だ。社会的課題の解決を企業のコア・バリューの中心に据え、あらゆるビジネス判断の場面において、ソーシャルな要素を重要視するブランド戦略を指す。
CSR活動は決して余剰利益を使ってお付き合いでするものではなく、企業の組織力向上や、経済的・社会的価値創造のために不可欠であり、企業経営と表裏一体であるべきである。
そしていま、ソーシャルな概念とブランディングは急速に融合しつつある。ブランディングはこれまで製品やサービスの質の向上を通じて顧客に新たな感動を呼び起こすための仕組みづくりだった。しかし海外では、企業のソーシャルな活動に対して「共感」が広がる事例が増え、それは日本にも波及し始めた。
ソーシャル・ブランディングというと、フェイスブックやツイッターなどソーシャル・メディアを駆使したブランディングやマーケティングと誤解される向きがあるかもしれないが、そうではない。「CSRを起点にして」「CSR活動を通じて」のブランディングであることは、本書で詳しく述べる。
この本は「企業がCSRをスムーズに導入する」ための手引きでもある。
日本でCSRは「企業の社会的責任」と訳されてきた。企業も2003年ごろから導入し始め、CSRレポートを発行する企業の数も増えてきた。だが、そのスピードは決して速くなかった。
その理由は、CSRを「責任」と訳したために「誰かから押し付けられる」感覚が強くなり、反発すら感じる企業人も少なくなかったことにある。どの会社でも、常にどこか他人事のような感覚が付きまとった。
経営者も例外ではない。CSRは大事だという一方で、多くはそれを神棚にたてまつったままで、日本でCSRを正しく経営に統合できた企業は少ない。CSRの社内浸透も最重要事項だが、これも多くの企業で手付かずのままだ。
その理由は、3つある。1つ目は、企業で「CSRとは何か」(what)を議論することが少なかったこと。2つ目は、「なぜ重要なのか」(why)が伝わらなかったこと。3つ目は、「では、どうすれば自社で展開できるか」(how)というノウハウに欠けていたことだ。
この3つの問いに対する答えを描き出すことが、本書の最大の目的だ。1つ目の問い「CSRとは何か」に対する答えは、単なる「社会的責任」というよりは、「社会からのさまざまな要請に対する対応力であり、社会的課題を解決する力」と定義したい。
2つ目の問い「なぜ重要なのか」に対する答えは、「その企業の価値を高め、未来の顧客を創造し、自社をより永続的に存続させるための重要な手段の1つ」と考えたい。
3つ目の問い「どうすれば自社で展開できるか」に対する答えは、まずは徹底的にステークホルダーと対話(ダイアログ)をすることに尽きる。
「寄付やボランティア活動、植林やゴミ拾いをすれば、それがCSRだ」と考えるのではなく、まず社会が何を求めているのかを知り、それに対応すること、つまり法令遵守だけではない「広義のコンプライアンス」である。
こうしたプロセスを社内に組み込んでいくことこそ、「未来に選ばれる会社」になるための王道である。この本を手にされた皆さんの会社が、本当の意味で「未来に選ばれ」、持続可能な組織として永続していくことを願ってやまない。
2015年8月
株式会社オルタナ代表取締役/『オルタナ』編集長 森 摂
2007年3月、私たちはビジネス情報誌『オルタナ』を立ち上げた。オルタナとは英語の「alternative」から採った誌名で、「もう1つの選択肢」という意味だ。
創刊したのはリーマン・ショックの直前だったが、すでに世界の資本主義はところどころで「綻び」を見せていた。エンロン事件やワールドコム事件などの金融スキャンダル。日本でも企業による犯罪や法令違反が少なくなく、しかも定期的に起きていた。
売上高や利益はもちろん大事だが、それと同じくらい大事な「何か」、もう1つの選択肢があるのではないか。正直に言うと、その「何か」はよく分からずに創刊したのかもしれない。「大事な何か」とは─。その命題に対する答えは、創刊から8年の間に、次第にくっきりと浮かび上がってきた。
最近話題のトマ・ピケティ『21世紀の資本』が指摘する通り、長期的には資本収益率(r)は経済成長率(g)よりも大きいため、富の集中が起こる。これによる所得格差や貧富の問題がいまや大半の国で深刻化した。日本も例外ではなく、子どもの貧困率は6人に1人に達した。
このように「20世紀型の資本主義」が内包する矛盾や課題は、あらゆる国で深刻な社会的課題となった。なかでも途上国の児童労働や労働者の職場環境など「人権」の問題は、いまや世界で最重要のテーマである。地球温暖化や気候変動など地球環境の変化も、私たちの社会や経済に大きな影響を与え続けている。毎年のように世界中のどこかで、洪水によって地域の交通が分断され、グローバル企業の生産活動を止める。食品企業にとっては、穀物の出来や水問題が本業を大きく揺るがす。
こうした社会的課題を解決するために、企業が社会の声を聞きながら、さまざまなステークホルダーとともに努力すること。これがCSRの本質である。CSRはこれまで「企業の社会的責任」と訳されてきたが、「レスポンシビリティ=レスポンス+アビリティ」という意味において、「企業の社会対応力」と訳す方が正しい。
この社会対応力こそが、実は企業をリスクから守り、従業員の満足度を高め、生産性を良くし、企業の価値を高めることが分かってきた。私たちが創刊時に意識していた「大事な何か」とは、このことだったのだ。
『オルタナ』創刊後、私たちは一貫して企業の環境・CSR活動やソーシャル・ビジネス、NGO/NPO活動、社会的課題への取り組みなどを取材し続けてきた。
株式会社オルタナとしては2011年に企業のCSR担当者向けセミナー「CSR部員塾」を、2012年にはCSR専門のコンサルティング部門「オルタナ総研」を立ち上げた。それ以来、多くの企業向けコンサルティングに関わるとともに、多数のCSR担当者と情報を交換してきた。
こうした取材や、オルタナ総研のコンサル活動を通じて得た知見やノウハウを、今回、一気にまとめた。いわばオルタナ8年の集大成でもある。
この本は、企業規模を問わず、あらゆる企業の経営者、経営幹部、そして社員の皆さんのために書いた。すべてのビジネスパーソンがCSRに対する理解を深め、日本企業が国際競争や国内市場の縮小に負けない、本当の意味で「未来に選ばれる会社」になるための参考になれば、筆者にとって最高の幸せである。
最後に、本書の執筆と編集に協力いただいた下田屋毅さん(在ロンドン)、藤美保代さん(在米カリフォルニア州)、冨久岡ナヲさん(在ロンドン)、吉田広子(オルタナ副編集長)、池田真隆(オルタナS副編集長)、佐藤理来(オルタナ編集部)、佐藤綾子(オルタナ経営企画室長)、安保瑞枝(デザイナー)、そして学芸出版社編集部の宮本裕美さんにも深い謝辞を表したい。
2015年8月
株式会社オルタナ代表取締役/『オルタナ』編集長 森 摂
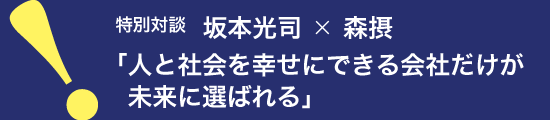
坂本光司(法政大学大学院教授)×森摂(オルタナ編集長)
会社は誰のものですか?
100年後も輝き続ける会社にするために大切なことは何ですか?
7000社以上の企業をみてきた経済学者と、企業経営の本質を取材する経済記者が語る、未来に選ばれる会社とは。
 |
 |
会社は誰のものですか?
森 『オルタナ』という雑誌を2007年に創刊してから8年が経ちまして、今回初めて単行本『未来に選ばれる会社』を出版しました。
私は、前職で日本経済新聞の記者を20年やっておりまして、その当時から、会社は誰のものか、会社を永続的にするものは何か、ということを考えていました。例えば、日経新聞的にいうと、会社は株主のものなんですね。ところが、本当にそうなのかなという思いが在職中からあったのが、この『オルタナ』という雑誌をつくる一つのきっかけになりました。その後独立をして、小さいながらも自分の会社(株式会社オルタナ)をつくりました。
会社をつくってみて、会社は誰のものかという命題は簡単に解けました。その答えは、会社は誰のものでもないということです。つまり、会社は経営者のものでも、株主のものでも、社員のものでも、顧客のものでもない。結局、みんなのものであるということが、自分で会社をつくってすごくよくわかったんですね。
次に解きたかった命題は、会社を永続的にするために必要ものは何かということです。これは結構難しかったのですが、その後、私なりにいろいろ調べていくうち、従業員満足度、顧客満足度、そして社会満足度が必要だと考えるに至りました。
新聞記者をやっていた当時から、企業の経営者に取材で会うと、決まって最後に、「社員と株主と顧客、どれが一番大事ですか」と尋ねていました。当時はお客様が第一と答える経営者がほとんどでした。
そのなかでとても印象に残っている経営者がいました。当時の株式会社カトーデンキ、現在の株式会社ケーズホールディングスの加藤修一社長(現会長)です。加藤さんにも同じ質問をしたところ「社員が一番大事ですよ」とすばり言われたんです。当時、この答えを聞いたのは加藤さんが初めてでした。この加藤さんの言葉はそれ以来20年、頭から離れない。
家電業界は競争が熾烈です。加藤さんの会社はそのなかでよく生き残っておられて、売上げも20年以上、増収増益だと思います。おそらくその秘密は、社員を大事にするという、加藤さんのポリシーにあるんじゃないかと思います。
この従業員満足度が一番で、その次に顧客満足度がきて、最後は社会満足度が必要になるというのが、私の仮説です。
従業員満足度も顧客満足度も数値化できますが、この社会満足度だけはまだ数値化できません。これが数値化できれば、ひょっとしたら世の中を動かすことができるかもしれないと思っています。
人を幸せにする仕事、人を不幸にする仕事
森 坂本先生に初めてお会いしたのは、多分4年くらい前だったと思います。そのときに坂本先生から「私は約7000の会社をこれまで見てきて、どんな会社が強く、どんな会社が100年、200年と続いていくのかがわかった。それは社員とその家族を大事にする会社だ」と言われました。それが大変印象に残っています。
坂本 ご紹介いただいたように、私はこれまで40年以上、7300社の中小企業を調査・研究してきました。その中でぜひ皆さんに紹介したいという会社が400~500社あります。その中で数社ずつ『日本でいちばん大切にしたい会社』という書籍にまとめてきました。来年1月に5巻目の『日本でいちばん大切にしたい会社5』が出版されます。
今日はその中から1社、社会福祉法人北海道光生舎という会社を紹介したいと思います。この会社は北海道赤平市で、今から60年前に髙江常男さん(故人)がご夫婦で起こされたクリーニングの会社です。現在、従業員が1300人まで増え、北海道の主要都市に拠点を持つまでに成長しています。
髙江さんは会社を大きくしたいという思いはまったくなかったそうですが、大きくせざるをえない事情がありました。それは、この会社で雇ってほしいと希望する障害者が次から次にこの会社の門戸を叩いたからです。現在1300人の社員のうち、およそ半分は障害者の方です。
なぜ、この会社がこんなに障害者雇用に力を入れているかというと、髙江さんご自身が想像を絶する障害者だったからです。10歳の時に片目を失い、19歳の時に両腕を付け根から失ったそうです。髙江さんを雇ってくれる会社はなく、結果的に自分で会社をつくること以外に職を得る方法はなかったんです。人間は働かなければ幸せになれませんから、髙江さんは自分で会社をつくったことでようやく幸せになることができわけです。
当時、赤平は炭鉱町で、炭鉱事故で怪我をした障害者がたくさんいて、十数名の障害者が就職し、会社はスタートしました。クリーニング業を選んだのは、作業がたくさんの工程に分けられ、片手のない人、足の悪い人、それぞれの障害に合った作業に就くことができると考えたからだそうです。
私の本は涙が出るような経営学書と言われますが、夢と希望のある苦しみはどんな苦しみでも耐えることができるけれども、夢と希望の失われた苦しみは耐えることができません。
森 今、日本の企業の障害者雇用率は徐々に上がってきていますね。
坂本 上がったといっても、日本の企業の障害者雇用率(2015年11月、厚生労働省発表数値)は、まだ1.88%なんです。民間企業の法定雇用率は2.0%ですので、法律を守っていない会社が53%あるということです。
今、障害者の方は、人口比でいうとだいたい6%、800万人弱くらいいます。そのなかで、実際に民間企業で働いている人はわずか45万人くらいしかいないわけです。
大学で教えるべきは、人を大切にする経営学
森 坂本先生の著書『日本でいちばん大切にしたい会社』のシリーズは、たくさんの人に読まれているわけですが、なぜこの本を書こうと思われたのでしょうか。
坂本 私も、最初から人を大切にする経営論をやってきたわけではありません。大学で経営学を勉強しましたが、当時の経営学では、会社の目的は業績を極大化するとか、いかに社員の効率を高めるかとか、経営の成果は利益であるといったことを教えられました。会社にとって一番大切なのは株主である、あるいは顧客であるという視点で企業を見ていました。
しかしいろいろな企業の経営者にお会いして、自分のそれまでの常識を覆されたのです。業績を求めていない会社の方が、好不況にかかわらず業績を伸ばしていて、業績を求めている会社の方が業績はぶれまくっていることに気づいたんです。
森 なるほど。
坂本 実はそれに気づいたのは十数年前なんです。私が教わってきた経営学は間違っていたわけです。だから私は今、大学人として経営学を破壊したいんです。
現在の経営学で教えられるのは業績論で、それを学んだエリート学生たちは大会社に就職し、やがて社長なります。このサイクルを変えない限りは難しいと感じています。
これは私の力不足ですけれども、人間本意の経営学、経営の目的は業績を高めることではなく、人を幸せにすることだということを教育している先生が、残念ながらあまり広がりを見せていません。
森 そう言えば、大学でもそういうことを教える先生はあまりいませんね。
坂本 そこで「人を大切にする経営学会」をつくりました。学会員は600人いるんですが、普通、学会というと大学の先生が圧倒的多数ですけれど、この学会は珍しくて、大学の先生は50人くらいしかいないんですよ。でも、若い先生が随分入ってくれて、そこには希望を見ています。
なぜ、人を大事にする会社は強いのか
森 社員を大事にする会社は強くなるということは、確かに頭の中ではわかるんですが、明日からすぐ行動に移すのは大変そうだと考える経営者も多いと思います。明日から変わるためには、どこから変わっていけばいいのでしょうか。
坂本 「社員を大事にする会社は強くなる」というのは理想でも理論でもなく、シンプルな現実なんです。自分が所属する組織に不平、不満、不信感を持っている社員は、組織の業績を高める努力はしないからです。自分が所属する組織や上司に不満のある社員は、必ずその足を引っ張ろうとします。これは当たり前です。
ですから、会社の業績を上げようと思えば、まず社員が不平、不満、不信感を抱かない環境をつくるのが最善最短の方法です。
経営者がやるべき大きな仕事は三つしかありません。方向を明示すること、決断をすること、社員のためにいい職場環境を準備すること。売上高を高めるとか、新商品をつくるというのは経営者の仕事じゃありません。
そして大事なのは、決断をする、方向を明示するときの物差しです。その物差しは、二つの物差しを使いましょうと言っています。一つは、会社に関係する人々の幸せづくりにとって「正しいか、正しくないか」。もう一つは、「自然か、不自然か」という物差しですね。
森 なるほど。ただ、実態として全国400万の会社があるなかで、どれくらいの社長さんがこれをわかっておられて、実際に行動に移していらっしゃると思われますか?
坂本 そうですね、そういう社長さんは、残念ながらおよそ1割くらいではないでしょうか。しかし、大学に比べると、企業の方が少し変わりつつあると感じています。
そういう企業の動きを後押しするために、私たちは2010年から「日本で一番大切にしたい会社大賞」という賞を毎年募集しています。これまで6回開催してきましたが、この賞の応募条件は厳しく、過去5年以上にわたって、以下の五つの条件にすべてに該当していることが必要です。①リストラをしていないこと、②仕入先企業へのコストダウンを強制していないこと、③障害者雇用率は法定雇用率以上であること、④黒字経営であること、⑤重大な労働災害がないこと。
森 確かに、一昔前までは顧客第一主義という経営者が圧倒的に多かったですが、今は、意識が高い経営者の中には、お客様より社員が大事だと考える方々が少しずつ増えてきたように感じます。
坂本 私が教鞭をとる法政大学大学院創造研究科の学生は60数人いるんですが、そのうちの7割くらいは現職の社長さんで、残りの3割は士業の仕事をしている方々です。
現職の社長さんは2年で修士課程を修了すると、自分の会社経営の現場に戻るわけですが、90%以上の人が障害者雇用に取り組んでくれます。また以前はリストラをやっていた会社が一切リストラをやらなくなります。
では一体どんな教育をしているかというと、院生たちを「人を大切にする経営学」を実践している会社に年間100社くらい、連れて行きます。そこで訪問先の経営者といろんな議論をするなかで、いろいろなことに気づきます。
森 古今東西、人や社会を大切にしてきた会社は多数存在し、そういう会社は長生きしているのではないでしょうか。
たとえば、インドの三大財閥の一つ、タタ・グループの創業者はゾロアスター教を信仰するペルシャ人で、インドのヒンズー教社会では完全なマイノリティでした。しかし、世界で初めて1日8時間労働制や本格的な企業年金制度、労災補償、出産交付金を導入し、社員満足度を高めるとともに、インド人の教育機会の拡大や奨学金の創設など類まれな社会貢献を続け、「善良すぎて潰せない」と言われるくらい、インド社会で認められる企業になりました。
一方、日本でも、近江商人の「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)は商いの美徳として語られることが多いですが、その神髄は「他国商い」にあります。近江商人は近江国(現在の滋賀県)で商いをしたのではなく、江戸をはじめ全国に商いの拠点を広げました。進出先の地域に商売を認めてもらうための極めて戦略的な経営理念が「三方よし」だったのです。
最近はブラック企業など、働き方をめぐる暗いニュースが多いですが、結局そういう会社は淘汰され、人と社会を大切にする会社だけが長生きします。企業経営の本質は実は凄くシンプル。さまざまな企業を取材したり自分で会社を経営する経験を経て、それを実感しています。
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。