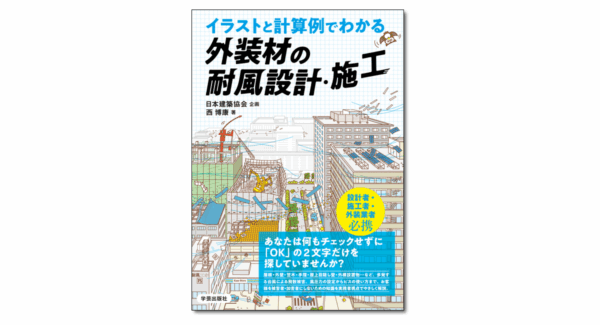イラストと計算例でわかる 外装材の耐風設計・施工
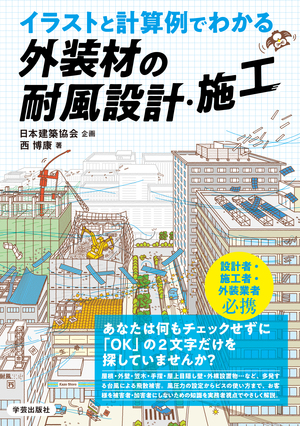
お客様を被害者・加害者にしないための知識
屋根、足場、庇、シャッター、防水、笠木、外壁、手すり、屋上設置物の飛散など、台風等による飛散被害が頻発するなか、すべての建物の設計・施工管理業務において耐風圧対策の重要性が高まっている。お客様を被害者・加害者にしないために、また生産者責任を追及されないために必要な知識を、実務者視点でやさしく解説。
西 博康 著 日本建築協会 企画
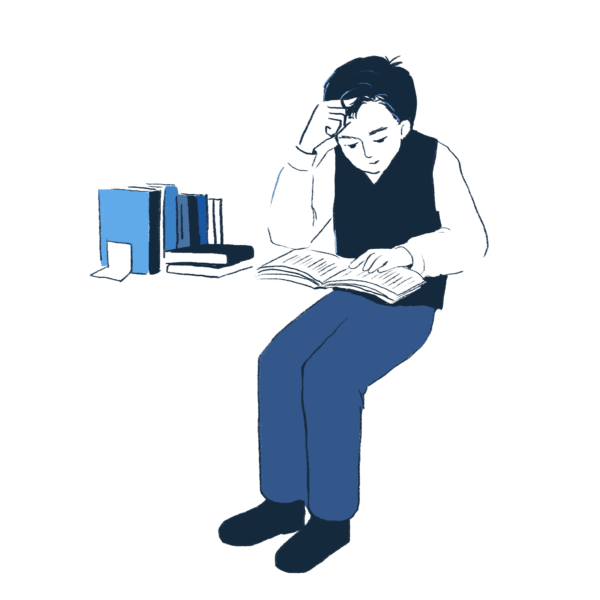
| 体裁 | A5判・256頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2700円+税 |
| 発行日 | 2025-09-15 |
| 装丁 | テンテツキ 金子英夫 |
| ISBN | 9784761529413 |
| GCODE | 8273 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| ジャンル |
外装材の耐風設計・施工の大切さがわかる映像
●風工学の研究者より
建築物の耐風設計で最も重要なのは外装材です。事故も多いです。関係者は事故を公にするのを避けたいため、一般の方々は事例を目にすることができません。本書では筆者の経験からイラストを通じて風による事故とそのメカニズムを分かり易く伝えています。設計者は勿論のこと、施工者や外装材メーカーにとっても間違いなく有益なものとなります。
株式会社風工学研究所会長 中村修
●構造設計者より
外装材の耐風設計を扱った参考書はこれまでありませんでした。本書は重要なポイントを豊富なイラストや図表、計算例により、わかりやすくかつ網羅的に解説されています。今後、台風の大型化に伴って構造設計者のさらなる関与が求められることから、実務に役立つ一冊として強く推薦いたします。
株式会社安井建築設計事務所 山浦晋弘
●意匠設計者より
近年自然災害が甚大化し、台風時の強風による建物被害が発生しています。建築に携わる者として建物の安全性を確保することは責務ですが、外装材や手摺など非構造部材の風圧力については様々な基準が散在し分かり難いものでした。本書ではイラストを交えて要点が解説されており、構造のみならず意匠、監理、施工に携わる方々にも手に取って頂きたい実務書です。
一般社団法人日本建築協会会長 指田孝太郎
本書(第1版第1刷)につきまして、編集作業の過程で以下の誤植がございました 。
読者の皆様にお詫び申し上げますとともに 、以下に訂正いたします。
正誤表(第1版第1刷)
【最終更新日:2026年2月16日】
目次
はじめに
本書の活用マップ
第1章 なぜ耐風圧設計は必要かつ重要なのか
1.1 被害者が加害者になる現実
1.2 台風で被害を受けた人が、法的に加害者になるのか?
1.3 大きな被害の台風は、想定内の台風であった?
1.4 外装材・屋根ふき材などの非構造部材はチェックの穴!?
1.5 建築基準法では屋根ふき材や外装材の風圧検討を義務付けている
第2章 政令や告示に示される耐風圧設計の基本
2.1 風圧力を求める基本となる式
2.2 「構造骨組部材」と「外装材等」 風圧力の影響の違い
2.3 「構造骨組部材」と「外装材等」の計算式とその違い
2.4 平均風速・最大瞬間風速とガスト影響係数
2.5 基準風速V0と再現期間・・・国土交通省が決めた値
2.6 非超過確率と再現期間換算係数・・・「50年間吹かない」ではない!
2.7 地表面粗度区分・・・周辺の状況により計算方法は分類される
2.8 地表面粗度区分Ⅱとは・・・Ⅱを理解するのが早道!
2.9 速度圧qと平均速度圧q(qに上線)・・・平均速度圧を知れば答えは近い!
2.10 EとE r 風速の鉛直分布係数・・・高さで風速は異なる
2.11 風圧力計算用の高さHとは・・・高さの概念を知ろう!
2.12 平均速度圧q(qに上線)の計算方法・・・風圧力計算の出発点
2.13 ガスト影響係数Gf と速度圧 qの計算方法
2.14 風力係数 Cf ・・・構造骨組部材に使う係数
2.15 ピーク風力係数Cf(Cに^)・・・外装材等に使う係数
2.16 風圧力・・・それは、q(qに上線)×Cf(Cに^)
2.17 外装材等の耐風圧検討手順
第3章 例題でわかる!告示に示される耐風圧設計の要
3.1 金属折版屋根を例に基本を知ろう!
3.2 機械固定式塩ビシート屋上防水・・・安全率についての一つの考え方
3.3 サンドイッチパネル・・・負圧をビスに依存する外装材の例
3.4 サッシとガラス
3.5 シャッター・・・実は落とし穴だらけ、間柱の強度にも注意
3.6 瓦屋根(参考)
第4章 告示に具体的な記載がない耐風圧設計の具体例
4.1 告示に具体的な記載がないものとは
4.2 屋上目隠し壁と屋広告板・・・部材の大きさでCf(Cに^)が異なる!?
4.3 屋上パラペット笠木・・・飛散しやすい部材の代表格
4.4 手摺(中高層建物)・・・コーナー部とルーフバルコニーは注意!
4.5 バルコニー隔て板(中高層建物)・・・外端の固定が重要
4.6 庇・・・頂部の剥離流と下部の吹き下ろしに注意!
4.7 フィン、竪樋、袖看板・・・外端部は剥離流の影響に注意!
4.8 軒天井・ピロティ―・・・検討しないと破損します
第5章 局地的な地形と地物の影響
5.1 法令上の扱い・・・検討が求められます
5.2 小地形による風速の割り増し・・・風速割り増し係数を知ろう!
5.3 地物の影響(ビル風の影響)・・・風速増減率を知ろう!
第6章 外構の耐風圧検討
6.1 フェンス・・・条件で大違い!基礎にも配慮を
6.2 自転車置き場・カーポート・・・住宅用製品には注意が必要
6.3 防風林・植栽・・・強風に身をさらす防風林の対策とは
第7章 チェックの要 締結部材
7.1 ボルト・ナット・・・外装材は振動で緩みます!
7.2 「タッピンねじ」と「ドリリングタッピンねじ」・・・抜けと破断
7.3 スタッド溶接・・・溶接安全性の確保と安全率の設定が重要
7.4 あと施工アンカー…2023年から学会指針が厳しくなっています!
コラム1 工事用足場にも風は吹きます 台風対策は一苦労!
コラム2 設備施設にも風は吹きます 屋上設置機器類にも注意を!
コラム3 設備施設にも風は吹きます 外部のダクトも強風対策を!
おわりに
はじめに
強風による建築物への被害は、台風時のみならず、春一番他、思わぬところで生じており、予てより建築技術者における外装材等の耐風圧検討能力の向上が課題と感じておりました。2018年関西を直撃した台風21号の被害を目の当たりにし、強風による被害者及びその関係者が次の瞬間に加害者となりえる現実を思い知らされ、また近年の台風の大型化の傾向を踏まえ、耐風圧検討能力向上が急務であると痛切に感じました。私たち建築技術者は、お客様を被害者にも加害者にしてもいけないと強く思います。
外装材の風圧力に対する計算方法について、これまでわかりやすい専門書がありませんでした。告示を読みこなし業務を行うことは必須のことですが、理解し適切に業務に織り込むことは容易ではないと感じます。また、風圧力に関する専門書は構造系技術者向けの専門性が高いものが多く、意匠設計者や現場の技術者には難解なものと感じます。その上、構造用の風圧力の考え方と外装材等の風圧力の考え方の違いがまず理解されにくく、更に、法令や告示等と日本建築学会とでは、用語の使い方に違いがあり、より複雑にわかりりにくくなっているものと思います。外装材メーカーが作成する風圧力の検討書も、これらの違いによる誤記はもとより、そもそも正しい理解がなされずに作成されているものも散見します。更には、ピーク風力係数「Cf(Cに^)」という記号も、文字化けして頭の「 ^ 」がなくなると全く意味が異なるものとなり、風圧力の記号には、頭にアクセントが付いたものが多数あることより、読み手も誤植から生じる誤認もあろうかと思います。
これらのわかりにくさが背景にあり、設計者・監理者・施工者・外装材等のメーカー並びに工務店は、適切な風圧力の設定・適切な検討書の作成・適切な伝達と解釈・適切なチェック行為、更には検討書どおりの施工を行うことに苦労されているものと感じます。本書は、これらの問題に応えるべく、本書のそれぞれの読者層に対し、わかりやすく解説を行うものであります。
本書を読んで頂きたい方とその趣旨
意匠設計者(電気設備・給排水衛生設備 設計者)・監理者
・各部それぞれの適切な強度設定のあり方の理解
・施工者から提出される検討書への適切なチェック能力向上
・提出された施工図の妥当性の確認
構造設計者
・非構造部材について、意匠設計者への適切な支援の理解
施工管理者
・設計要求事項の理解
・外装等メーカーの検討書のチェック能力育成・向上
・検討書どおりの施工管理とそのポイントの理解
外装等メーカー及び施工店
・正しい検討書の作成
・検討書の適切な理解と検討書どおりの施工の実践
わかりやすく伝えるための工夫
わかりにくい風圧力検討を本書では次のような工夫で解説しています。
・用語の定義について図などを併記し、わかりやすく解説
・構造用の計算方法と外装材等の計算方法の違いを解説
・計算例を多用し、実例をたどりながら解説
・安全性についての考え方を事例で解説
・どこで壊れやすいか、計算書のポイントと現場の管理の要を解説
・特に重要なポイントは、フクロウマークで明示。
本書の活用により、強風に対し安全な建物が作られることに寄与できることを祈ります。なお、実務への適用に際し、条件の確認・引用文献の原文確認・法令等の改訂確認を含め利用者の責任でお願いしますことを申し添えます。
おわりに
強風の飛散防止をテーマに掲げれば、枚挙に遑がありません。汎用性が高いものに絞った積りでしたが、無心に書いたら優に300頁を超えてしまい、出版社から絞るように言われ、現在の形になりました。外にあるものは全て風を受けますので、その検討対象や形状は無数です。しかし、本書を活用し基本を理解していただければ、応用ができるものと思います。
風の影響について、先人の方々が数多くの研究を行ってこられており、現在も多くの方が研究を重ねておられます。感謝の念に堪えません。しかしながら、設計者や施工者がそのような研究成果を目にしたり、活用することが少ないのはとても残念に思います。本書を切っ掛けに、風圧力に関する専門書や研究論文の原文を是非とも確認いただきたいですし、活用方法を身に付けていただければありがたいと感じます。また、研究者の方々は、継続して成果を発表されていますので、有益な情報に注目いただければと感じますし、更には本書を上書きする状況や政令等の改訂により、本書の内容が追い付かなくなることもあろうかと思います。本書は執筆時の状況における情報とご認識いただければと存じます。
本書では、設計・施工を行う側の検討事項を中心に記載していますが、風圧力という繰り返し荷重を受ける部材は、疲労・緩み・腐食といった問題を常に受けている部材です。そのため、安全率に対する考え方や疲労・緩み・腐食といった問題を併記しています。設計者・施工者の皆様におかれては、建築主や建物の保全・管理者に、外装材等の維持管理とメンテナンスという視点でもご説明いただければと切に願います。そのことが、お客様を加害者にさせないために重要なことです。
本書を作成する傍ら、一般社団法人日本建築協会・出版委員会のメンバーから、もっと設備のことを、仮設のことも…などとリクエストをいただきましたが、紙面の関係でこの内容とさせていただきました。しかしながら必要なエッセンスを凝縮させたつもりですので、是非とも皆様のお役に立つと幸いです。
最後になりますが、本書の作成に当たり、これまでに賜りました数多くの専門業者や建築関係団体のみなさまからのご支援・ご教示に感謝申し上げます。
また、長きにわたり風圧力の基本をご指南くださいました清水建設株式会社技術研究所 菊池浩利様、資料の掲載等にご理解・ご支援を賜りました風工学研究所 中村修様・株式会社数値フォローデザイン 日比一喜様(元株式会社清水建設技術研究所フェロー)をはじめ多くの研究者のみなさま、更には構造設計者の観点でアドバイスをくださいました株式会社安井建築設計事務所 山浦晋弘様、意匠設計者として総合的な見地からご助言を頂きました一般社団法人日本建築協会 指田孝太郎会長並びに日建設計株式会社 勝山太郎様に厚く御礼申し上げます。本書の企画段階からご支援くださいました一般社団法人日本建築協会・出版委員会のみなさま、株式会社学芸出版社 岩崎健一郎様に深く感謝申し上げます。
令和7年9月吉日
西 博康
公開され次第、掲載します。
メディア掲載情報
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。