身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規
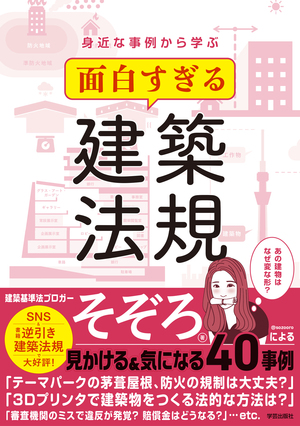
そぞろが解説!見かける&気になる40事例
「テーマパークの茅葺屋根、防火の規制は大丈夫?」「あの建物はなぜ変な形?」大好評の建築基準法ブロガーが、街で見かける建物や、有名建築家の設計作品、話題のトピックや実際の事件などを建築法規の視点でマニアックに解説。難解な法規も「面白い」に変わる、身近で気になる40事例。楽しく読めて設計にも役立つ一冊。
そぞろ 著

| 体裁 | A5判・220頁(2色刷) |
|---|---|
| 定価 | 本体2300円+税 |
| 発行日 | 2025-08-10 |
| 装丁 | 美馬智 |
| ISBN | 9784761529345 |
| GCODE | 2355 |
| 販売状況 | 在庫◎ 電子版あり |
| ジャンル |
はじめに
Introduction
第1章 防火:適用除外、性能規定・・・自由な計画実現の秘策
1.ディズニーシーに「茅葺き屋根」をつくるための法適合のひと手間
コラム:他にもまだある!テーマパークに隠された建築法規
2.隈研吾が手がけた「TOYAMAキラリ」──斜めの吹抜けをつくる上での意外な問題とその対策
コラム:建築基準法が難しいのは「性能規定」のせい?
3.「京都駅」のコンコースと空中歩廊の大空間、面積区画はしなくていいのか
コラム:旧38条認定を取得した建築物は、増改築が困難に?その理由と救済措置
4.どうして一部だけ網入りガラスを使った?「LINKS UMEDA」のスターバックス
5.「笠間保育園」全焼は建築基準法の想定範囲内?建材や内装に木を使用する燃えしろ設計
コラム:「60分耐火構造」VS「75分・90分準耐火構造」、どちらの方が優れている?
6.木現しの「日刊木材新聞社新社屋」──隣地側に開口部がつくれなくても、準延焼防止建築物を計画するメリット
コラム:今話題!木を活用するための建築法規について徹底解説
7.「糸魚川市大規模火災」から生まれた建ぺい率の緩和。なぜ緩和を追加したのか
第2章 避難:非常時には安全に。平常時には溶け込むように
1.階段をあえて表につくった日建設計「荒川ビル」。実は、ただの階段ではない
2.商業施設の階段はどうして広くつくられているのか
3.「メゾネット式のホテル」がつくりづらい理由とは?
4.安藤忠雄設計「こども本の森」の絶妙な、デザインを損ねない非常用の進入口
コラム:探してみよう!街に隠れた非常用の進入口・代替進入口
5.隈研吾設計「One 表参道」──ルーバーの外観に非常用の進入口がない理由
6.「北新地ビル放火殺人事件」──建築基準法は犯罪行為に対しても有効なのか
第3章 集団規定:地域の中で上手く建築物を建てるための、創意工夫
1.実は「東京駅」は自身の容積率を売っていた!
2.大きな建物を建てるための奥の手・公開空地
3.道路幅員4m未満の京都市「昭和小路」。接道義務はどうなっているのか
4.2m接道しているのに、共同住宅が計画できない!用途の工夫で条例に対応
コラム:法規制を逆手に取って、コンセプトに昇華させた建築物
5.道路斜線が目に見えるビル
6.「神保町シアタービル」の形と法規の関係──なぜ、周辺の建築物より大きな建築物をつくれたのか?
コラム:他にもまだある!高さ制限が適用されない建築物
7.どうして下階がえぐれている?日影規制に適合しやすくするための手段
8.スカイツリーの高さは、634mではなく約470m!建築基準法上の高さの算定方法
9.安藤忠雄設計「六甲の集合住宅」──斜面を有効活用して、中層に見える低層建築物を計画
コラム:建築法規に登場する数値はなぜ中途半端なのか
第4章 一般構造:よく考えると不思議?身近な建築物の疑問
1.住宅によく納戸・サービスルーム・備蓄倉庫が設けられる理由とは?
2.サウナ室は本当だったらつくれない?無窓居室をつくる難しさ
コラム:知っておきたい!採光義務と無窓居室の違いとは?
3.2階建ての建築物には、法的には階段は不要?
4.申請先によって、判断が異なる?法に明文化されていない内容の扱い
5.階段に手すりを設けなくとも、違反建築物にならないことがある!?
6.今話題の3Dプリンタ、どうやって建築基準法に適合させるの?
7.建築基準法の想定外!台風と地震の同時発生
8.多雪区域「以外」の建築物に、積雪荷重の割り増しが定められた理由とは?
第5章 手続き:建築基準法の手続きはブラックボックス?
1.豪華客船は「建築物」と言える?船でも建築基準法の適用を受けるケース
コラム:他にもある!建築物に該当するか悩ましい事例
2.再建された「旧国立駅舎」は建築基準法に適合していない!?
3.ひと昔前の建築物は、検査済証を取得していない「違反建築物」だらけ
4.ついに、確認申請の特例が受けられる建築物の範囲が縮小、その理由とは?
5.確認済証の交付後に違反部分を発見!どうなるのか?
6.検査済証取得前に、荷物の搬入を行うのは可能か?
7.地域のルール「建築協定」は確認申請の審査対象になるのか?
第6章 その他:意外と関わる、建築基準法以外の建築法規
1.SNSで話題の建築物「高円寺酒チャンス」──誰でも「設計者」になれるのか?
2.ディズニーシーの「タワー・オブ・テラー」の高さはなぜ59mなのか
3.隣地境界線からの距離が矛盾?「建築基準法vs民法」、どちらが勝つのか
索引
早いもので、こうして建築法規の文章を書き始めて、もう6年も経過しました。ここまで続けてこられたのは、私自身が「建築法規が好き」というのが一番大きな理由のような気がします。
建築法規が好きと公言していると、「どうして好きになれるの?」とびっくりされることが多いです。確かに、建築業界の方とお話ししていると、建築法規が苦手、嫌いと感じている方はかなりいらっしゃる印象です。
正直、私も最初から建築法規が好きだったわけではありません。実務でも、建築士試験対策でも、建築法規の勉強といったら、法文を読むことから始まります。もちろん私もそうでしたが、最初はまともに読むことすらできません。そして、苦労して読めるようになって、内容を理解したとしても、自分の仕事に関係が薄いものについては「そんな規定・緩和があるんだな、私には縁がなさそうだけど…」と、他人事のようにしか感じることができませんでした。特に、建築士試験の勉強などでは、こんなの絶対使わないだろう、というマニアックな内容も学習しなければならないので、同じことを感じてしまう方が多いのではないでしょうか。
そんな私が建築法規を好きになったキッカケは「巧みに建築法規に適合させた建築物」の存在を知ったことです。私は指定確認検査機関に勤務していたので、設計者さんが考えた建築物の計画を見る機会が多かったです。そんな中、マニアックな建築法規を巧みに使いこなし、自分のやりたい設計を実現させる設計者さんに出会いました。自分には関係ないと思っていた規定・緩和はそんな使い方ができるのか!と感動した記憶があります。
そこに気がつくと、とたんに建築法規がどんどん面白く感じるようになり、好きになっていきました。街なかの建築物を見ては、「もしかして、この緩和規定を使って適合させているのかな…」とか、「あえて建築物を歪な形にして工夫しているのかも…」などと予想して楽しむことができるように。
そこで、本書では私が厳選した「巧みに建築法規に適合させた建築物」を中心に、どのような法規が適用されているかや法改正の原因となった事故・事件などをわかりやすく解説し、みなさんに建築法規って面白い!と思ってもらえるようにまとめました。正直、普段の設計ではあまり触れたことがない内容や、実務に応用できない内容もあると思います。でも、「机上の建築法規の内容」と「現実の建築物の計画」の結びつきを感じることで、私のように建築法規を好きになってくれる方がいるのではないかと思い、このような本を出そうと決心しました。
どうか、みなさんが建築法規を面白いと感じ、少しでも好きになってもらえますように。
2025年7月 そぞろ
公開され次第、掲載します。
開催が決まり次第、お知らせします。
メディア掲載情報
| 日付 | タイトル |
|---|---|
| 2025年11月27日 | 『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』著者・そぞろさんへのインタビューが「日経クロステック」で公開されました(会員限定) |
| 2025年11月5日 | 【全編視聴可】『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』(そぞろ)がYouTubeチャンネル「FM アーキチャット」で紹介されました |
| 2025年8月8日 | 『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』(そぞろ)が「新建ハウジング」で紹介されました |
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。












