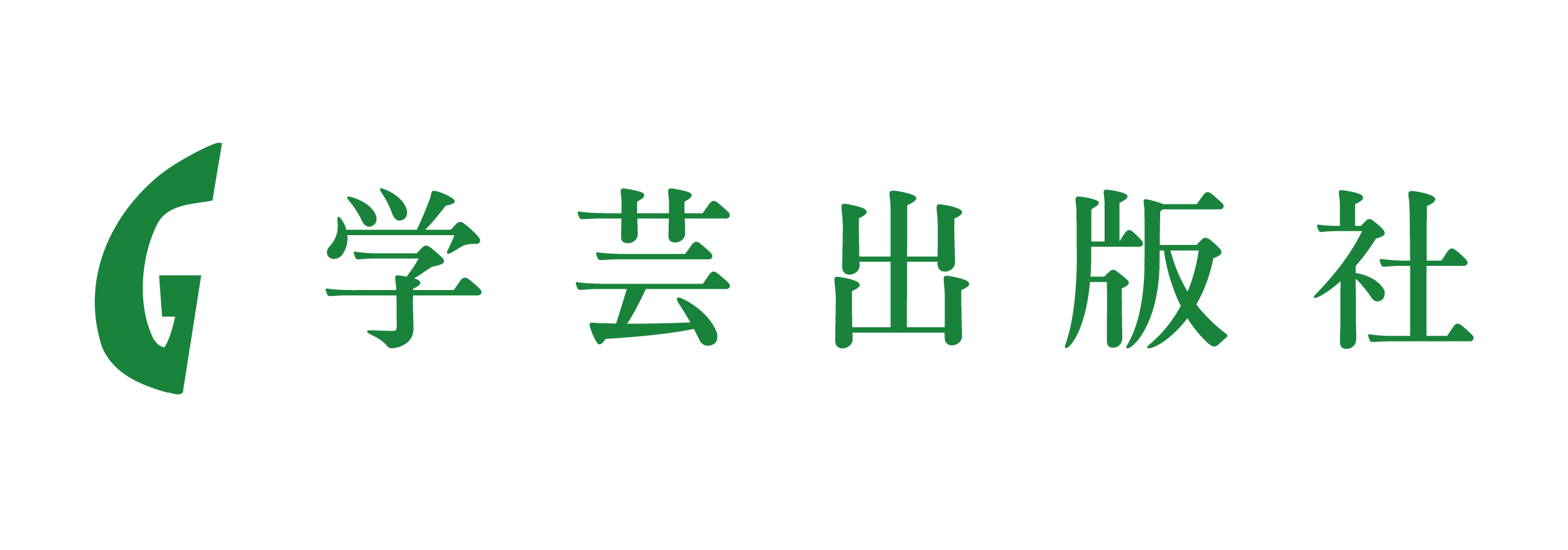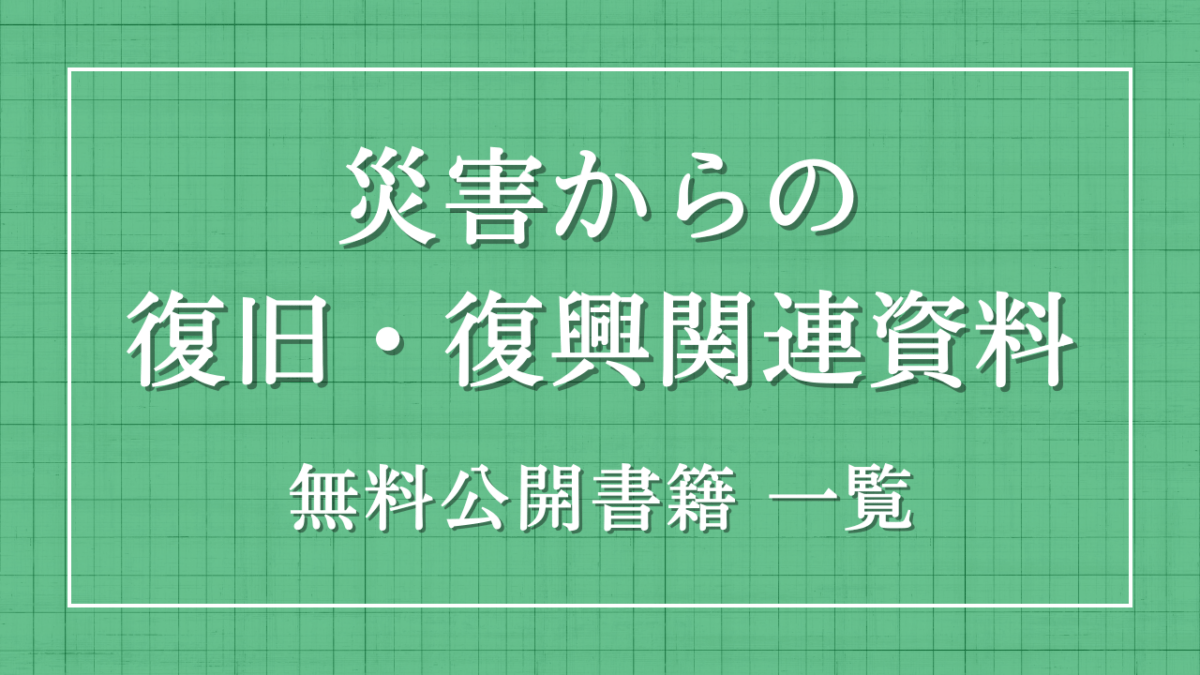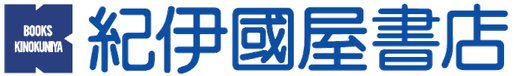地域が主役の自治体災害対策

ボトムアップ型で災害を乗り越えるために
想定外の災害を地域主体のボトムアップ型で乗り越えるには「連携」と「協働」、組織をつなぐ「コミュニケーション」が不可欠だ。自治体の業務マネジメント、応急対策、避難所運営を、阪神・淡路、東日本、熊本、能登半島の地震、西日本豪雨の経験から語る。今後、起こりうる南海トラフ地震を乗り越えるために求められることは何か。
阪本 真由美 著
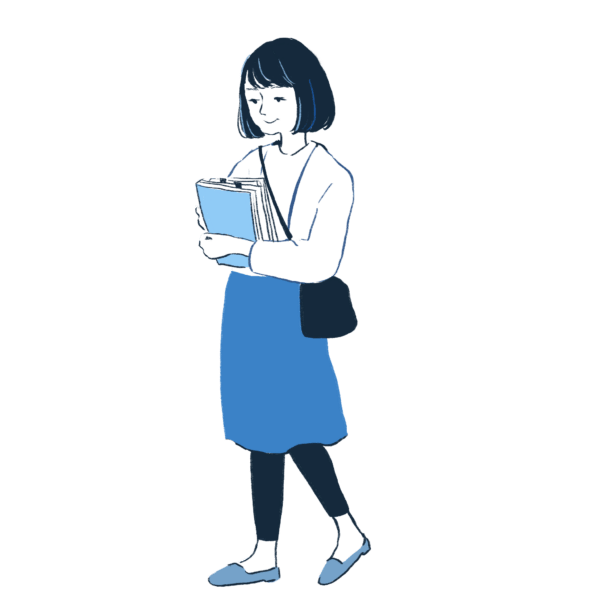
| 体裁 | 四六判・216頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2500円+税 |
| 発行日 | 2025-01-20 |
| 装丁 | 美馬 智 |
| ISBN | 9784761529185 |
| GCODE | 5707 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| ジャンル |
はじめに
第1章 市町村の災害対策を機能させる
1. 日本の災害対策システムの特徴と課題
2. 災害対策システムができるまでの動き
3. 災害が起きた時の対応体制
4. 確立されていない災害対策本部の設置基準
5. 災害対策本部の設置から運営まで
6. 想定外の災害に備えるための組織マネジメント
7. 災害マネジメント人材を育成する
第2章 被災市町村の災害時業務マネジメント
1. 熊本地震(2016年)にみる益城町の対応
2. 住民の目線で考える業務継続計画
3. 阪神・淡路大震災(1995年)で被災した芦屋市の窓口業務再開
4. 東日本大震災(2011年)で被災した釜石市の窓口業務再開
5. 窓口業務再開の手順と工夫
6. ワンストップ窓口の設置と被災者支援の質の向上
7. 災害時の行政サービスの継続
第3章 大規模広域災害を乗り切る自治体間連携―2011年東日本大震災
1. 重要な役割を担う自治体間の応援協力
2. 宮城県にみる県域の受援情報把握の課題
3. 自治体の自主的な連携による支援
4. 被災地支援のためのロジスティクス
5. 大規模広域災害時の受援体制構築に向けて
第4章 避難所運営―災害関連死を防ぐ
1. 災害時の避難所運営をめぐる課題
2. 避難者数と避難理由を把握する
3. 避難所生活における災害関連死
4. 「動かない」と「動けない」
5. 避難所の衛生環境をめぐる課題
6. 優先されるべきなのは「公平性」よりも「必要性」
7. 多様な人との協働による避難所運営
第5章 避難情報と住民の避難行動
1. 市町村が発令する避難情報
2. どのタイミングでどの避難情報を出すのか
3. 西日本豪雨(2018年)における住民の避難行動
4. 避難スイッチをオンにするための取り組み
5. 避難情報を住民の身近な情報とするために
第6章 地域住民と自治体によるコミュニケーション型防災
1. 誰が主役となり防災を進めるのか
2. 災害時の地域コミュニティの役割
3. 地区防災計画により地域コミュニティを活性化する
4. 住民参加型の防災と市町村の役割
5. 共助により地域の災害対応力を高める
おわりに
1 日本の災害対策システム
日本の災害対策システムは、世界でも他に類をみないユニークな仕組みとなっています。その一方で、複雑でわかりにくいところもあります。私は大学で防災を教えていますが、講義で学生に「日本の災害対策を統括している省庁はどこでしょう」と質問すると、「国土交通省」(30%)「環境省」(17%)「防衛省」(12%)「厚生労働省」「気象庁」(各10%)「復興庁」(7%)「内閣府」「金融庁」(1%)というように多様な省庁名が挙げられます(%は回答者の割合)。なかには、「防災省」「防災庁」「減災復興庁」と存在しない省庁名を挙げる学生もいます。日本では、毎年のように災害が発生していますが、それにもかかわらず災害対策を統括する省庁がどこなのかを知らない大学生が多数いるくらいわかりにくい仕組みです。
このように、学生が日本の災害対策システムを知らないことはやむを得ないことだと思います。なぜなら、災害にどう対応しているのかを、学校教育ではほとんど教えていないからです。小学校・中学校・高等学校の教科書をみても、台風・地震・津波・火山などの災害をもたらす(ハザード)現象がどのように発生するのかというメカニズムの解説や、阪神・淡路大震災、東日本大震災などの自然災害による被害、避難・避難生活などについては記載されていますが、災害対策システムに着目した単元は見当たりません。私自身も、本当のところ、東日本大震災(2011年)の対応に関わるまでは、大規模災害時に国や地方自治体がどう対応しているのかを理解していなかったように思います。
2 地域が主役のボトムアップ型災害対策
日本の災害対策システムがわかりにくい要因は、日本の災害対策が都道府県や市町村などの地方自治体の役割が大きい仕組みになっている点にあります。世界をみると、アメリカには「連邦緊急事態管理庁(FEMA)」が、ロシアには「民間防衛問題・非常事態・自然災害復旧省(EMERCOM)」が、インドネシアには「国家防災庁(BNPB)」がというように、名称は「緊急事態」「非常事態」「防災」と異なるものの、国から被災現場レベルに至る災害対策実務を統括する省庁があります。
このような災害対策を統括・実施する独立した省庁は日本にはありません。防災計画の立案や災害時の省庁間の調整事務は「内閣府」が行っていますが、内閣府は他にも多様な業務を統括しています。
これは、災害対策で最も重要な役割を担うのが国ではなく地方自治体(都道府県・市町村)だからです。災害がおきると、地方自治体が被災者を支援し、国はそれをサポートします。国が中心となり災害対応を行う体制を「トップダウン型」とすると、日本は地方自治体を中心に災害対応を行う「ボトムアップ型」の仕組みです。
かつては、日本でもトップダウン型で災害対応を行っていた時代がありました。現在のようなボトムアップ型の体制に転換するきっかけとなったのは、1959年の伊勢湾台風です。伊勢湾台風は、愛知県・三重県・岐阜県に大きな被害をもたらした台風でした。被災した愛知県には災害対策本部(中部日本対策本部)が設置され、国が被災現場で災害対応にあたりました。しかし、被災した地方自治体は復旧・復興に関する事務手続きや予算交渉を各省庁と行わなければならず、被災自治体の声が政策に反映されにくいという課題に直面しました。伊勢湾台風の経験を踏まえて災害対策システムは見直され、1961年に災害対策システムを定める「災害対策基本法」が制定されました。被災した地域が主役となり災害に対応できるように、地方自治体の権限が大きくなりました。
3 組織転換による災害対応
地方自治体を中心とする災害対応において、被災住民を支援するという最も重要な役割を担うのは市町村です。それにもかかわらず、市町村には災害対応を専門とする職員はほとんどいません。災害対応を担当する職員の多くは事務職であり、人事異動により配置され2年程度で異動します。市町村がどのように災害に対応しているのかというと、災害が発生する、もしくは発生するおそれがある時には組織全体を「災害対策本部」という体制に転換させ、全職員が災害対応業務に従事します。このことは、地方自治体には、平常時業務/災害時業務という二つの業務モードがあり、災害業務モードに切り替わると、特定の職員だけでなく、全職員が災害対応に参画しなければならないことを示しています。全組織が一丸となって対応しなければならないほど、災害対応は大変な業務です。
組織体制を転換させて災害に対応するには、そのための特殊な組織マネジメント能力が求められます。災害時にどのように業務を進めるのかは、計画に定められています。国は「防災基本計画」を、地方自治体は「地域防災計画」を策定します。ところが、災害は不確実な事象ですので、災害が発生すると、これらの計画に記載されていないような事象が発生します。とはいえ、計画を見直している時間はありません。その場で状況を判断しながら、対応を進める必要があります。つまり、災害に対応するには、計画を策定するだけでは十分ではなく、計画外のことが発生した時に、的確に状況を判断し対応する能力が必要です。
また、全ての自治体職員が災害対応に従事するわけですから、職員全員が災害対応の知識を持っておかなければなりません。それにもかかわらず、そのための人材育成の仕組みが整っていないという課題もあります。なぜなら、日本全体でみると災害は毎年のように起こっていますが、個々の市町村が大規模な災害を経験する頻度はさほど高くないからです。台風の接近や豪雨に伴い2~3日間、避難所を開設するという程度の被害であれば、全職員を動員しなくても、防災担当部局の職員だけで対応できます。そのような経験を積み重ねるうちに、災害対応は防災担当部局がするものだ、という思い込みがうまれてしまいます。地方自治体を基盤とする災害対策には、他の地域で起きた災害対策のノウハウが伝わりにくいという課題もあります。
その結果、大規模な災害が発生すると、災害対策本部へ組織体制を切り替えられない、災害対策本部を機能させることができないという課題が続出します。災害対応は待ったなしです。災害が起きた瞬間から、市町村は、避難所の開設・運営、被災者への食料・物資の提供、被災家屋の被害認定や罹災証明の発給、災害廃棄物の処理、被害額の算定などの膨大な業務に追われます。これらの業務の多くは、平常時には実施することのない業務です。目の前にある問題への対応に忙殺され、急がなければならない重要な課題が先送りされてしまうケースもあります。そうすると、復旧・復興が遅れていきます。災害対策を迅速かつ的確に実施するには、応急対策から復旧・復興に至る災害対策の全体像を把握しつつも、その場の状況に応じて的確に状況を判断して業務を進めなければなりません。
4 組織間連携のためのコミュニケーション
日本の災害対策システムが、地方自治体の役割を重視しているのは、被災した地域住民のニーズに寄り添い対策を進めるためです。ところが、大規模な災害が発生すると、市町村の災害対応を統括するトップ(首長)が命を失う、災害対応の戦力となる職員が命を失う、市町村の本庁舎が被害を受けて使えなくなるといった被害が発生し、行政機能の維持さえ難しい過酷な状況に陥ることがあります。市町村を主体とする災害対策は、市町村の行政機能が維持されるような局所的な災害には効果的ですが、阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)のように、市町村自体が被害を受ける大規模・広域災害には対応できないという弱点があります。
そのような弱点を補完するには、国、他の地方自治体、民間組織などの組織間の「連携」と、連携を機能させるための「調整」が不可欠です。また、行政を中心とした公的セクターによる支援(公助)だけでなく、民間セクター(NGO / NPO、企業など)や、地域コミュニティによる相互支援(共助)が不可欠です。そのために求められるのが、組織間をつなぐコミュニケーションです。
コミュニケーションを効果的に行うには、それぞれの組織が何を目標として行動しているのか、自分の所属する組織との考え方の相違がどこにあるのか、表からは見えにくい組織的な制約を知ることも大切です。互いの組織に対する理解を深めることは、考え方のギャップを埋め連携を容易にします。
5 本書の構成
本書では、以上に述べた地方自治体の権限が強いボトムアップ型の日本の災害対策システムの特徴を踏まえたうえで、どうすれば災害対応を機能させることができるのかを、近年発生した災害の事例分析から検討します。
第1章では、日本の災害対策システムにはどのような特徴があるのか、どのような経緯で現在の仕組みになっているのかを概観するとともに、どう想定外の災害に対応するのかを災害対応の鍵となる災害対策本部の設置と運営に着目して検討します。そのうえで、災害対策本部を機能させるために必要な「状況判断」を、ジャズをモチーフとした「即興」という概念から考えます。
第2章では、「即興」による状況判断の事例として、災害発生時の市町村の業務継続に着目します。
災害により被害を受けた状況で、行政サービスをどのように継続するのかを災害時の業務と平常時の業務のバランスから検討します。災害が発生すると、市町村は様々な業務に追われます。災害対応に追われるなかで継続しなければならない業務が、市民への行政サービスの提供と長期的な復興につながる業務です。災害に直面した状況で、これらの業務を継続しつつ即興でどのように業務全体の立て直しを図るのかという、災害時の業務マネジメントの方策を示します。
第3章では、自らの対応力を超える災害に対応するための自治体間の組織連携に着目します。災害対策基本法では、災害の発生により、市町村がその業務を行うことができない時は、他の市町村に職員の「派遣」や「応援」を要請すること、市町村長などが実施すべき応急措置を都道府県知事が実施することを定めています。つまり、災害後に増大する業務については、他の市町村との連携が不可欠です。実際に東日本大震災では、日本全国の自治体から被災自治体に対し支援が行われました。しかし、支援を受け入れる「受援」の仕組みが確立しておらず、支援調整が難しいという課題に直面しました。そこで「受援」をどのように機能させるのか、そのための方策を示します。
第4章では、市町村の災害対応でも難しい避難所運営に着目します。災害で一命をとりとめても、その後の避難生活の環境が良くなく、それが原因で「災害関連死」に至る事例があります。行政は避難所を開設するものの、長期にわたりその避難所運営にかかわることは困難です。とはいえ、被災して住まいを失い、生活の立て直しを強いられている被災者に、自主的に避難所を運営するよう依頼することも容易ではありません。そのような時に行政と住民をつなぐ役割を担うのが、非営利組織(NPO)などのボランティア団体です。ここでは、熊本地震や西日本豪雨(2018年)における避難所運営の事例分析から、避難生活の質をどう改善させ災害関連死を防ぐのかを示します。
第5章では、住民の状況判断に着目し、豪雨災害時の避難をめぐる行政と住民との認識ギャップを考えます。行政は、災害時に住民の避難を促すためにハザードマップを配布するほか、「警報」「注意報」「避難指示(緊急)」などの災害情報を発出しています。それにもかかわらず避難しない人は多数います。そこで、住民がどのように行政による避難情報を捉えているのかを、平成30年7月豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町で実施した調査結果から検討します。
第6章では、防災における地域コミュニティの役割を考えます。現在の防災施策の多くは行政が中心となって実施されており、そこに住民があまり参画していないという問題があります。もともと日本では地域住民が中心となって災害に対応してきました。どうすれば住民が再び主体的に災害対策に取り組むようになるのかが問われています。そのために、2013年の災害対策基本法の改正により、新たに導入された仕組みが「地区防災計画」です。地区防災計画は、住民が防災計画を策定し、市町村防災会議にそれを提案することができる住民提案型の制度です。本章では地区防災計画の実践事例から、地区防災計画を通して、どうすれば住民が防災の主役になっていくのかをみてみます。
以上の議論を通し、地域を主役とするボトムアップ型の災害対策システムの特徴・課題を明確にします。そして最後に、現在の災害対策システムで南海トラフ地震のような大規模災害を乗り越えることができるのか、乗り越えるには何を強化しなければならないのかを考えます。
1 連携と協働のためのコミュニケーション
本書を読んで、市町村の災害対策がどのように動いているのか、災害時の避難所運営がなぜ上手くいかないのか、避難情報がどのように出されているのか、おわかりいただけたでしょうか。
日本の災害対策は、地方自治体の権限が強いボトムアップ型のシステムですが、これは被災した人に寄り添い命を守ることを重視しているためです。住民を大切にシステムが構築されている点と、災害の状況に応じて柔軟に組織体制を変化させることができる点に優れた、ユニークなシステムだと私は考えています。想定外の災害でも即興でも対応しやすい仕組みです。とはいえ、ボトムアップ型の災害対応体制で災害を乗り越えるには、組織マネジメント能力が不可欠です。また、自分の自治体だけで対応することは難しく、連携と協働も必要です。それを進める鍵となるのがコミュニケーションです。最後に、連携のためのコミュニケーションのポイントを整理しておきます。
市町村間の連携においては、それぞれの組織内の上司・部下の関係、指示系統、役割分担が市町村により異なっていることを理解しておく必要があります。組織間連携を効果的に行うために、アメリカでは災害対応に関わる自治体の組織構造をインシデント・コマンド・システム(ICS)に基づき標準化し、指揮命令系統を明確にすることで外部からの支援調整を行いやすくしています。ところが、日本ではICSのような標準化という考え方は浸透していません。災害対応のための組織体制は市町村により異なります。唯一共通しているのは、「災害対策本部」という体制です。従って、災害対策本部を機能させることが大切です。本書で取り上げた災害対策本部をどう設置して運営するのか(第1章)、災害対応業務と平常業務のバランスをどう取るのか(第2章)、自治体間の支援をどのように災害対応に組み込むのか、情報をどのように共有していくのか(第3章)はいずれも即興で対応が求められるポイントです。組織体制を柔軟に変えて対応することに加えて、被害が大きい時は、他の組織との連携は不可欠です。即興で対応しなくてもよいように相互応援協定などを通して関係を構築することや、大規模な支援を想定した受援訓練を実践しておくことも大切です。
行政と住民が連携するには、コミュニケーション・ギャップを知ることです。災害時に用いる「言葉」をとっても、行政と住民とではコミュニケーションがうまく取れていません。その典型的な事例が第5章で述べた避難情報です。市町村は、被害が発生しないよう、住民の立ち退き避難が必要なタイミングで「避難指示」を出していますし、「避難指示」を的確に出せるよう様々な取り組みを行っています。けれども、「避難指示」を発令するためにどれほど情報収集をして、工夫しているのか、情報を出すための努力と情報に込められた「避難してほしい」という強い思いを住民は知りませんし、それを伝えるための取り組みもほとんど行われていません。
行政は責務として災害対応を行い、その責務が行き届かないところを共助が補完することを期待しています。これに対し、住民にとっての共助は責務ではなくボランタリーな活動です。そのような共助を機能させるには、ボランタリーな活動を活性化するための取り組みが大切になります。市町村がどれほど頑張ったとしても、肝心の住民が主体的に行動しない限り災害対応は機能しません。そう考えると、日本の災害対策システムは、住民・地域・行政が、互いが「できること」「できないこと」に対する理解を深め、他者を信頼し助け合ってこそ機能する、いわば信頼と連携に基づくシステムです。そのためにも、互いの考え方を知る「場」を設置し、コミュニケーションを通して信頼を育むことが大切です。
私たちの暮らしを支える最小単位は地域コミュニティです。東日本大震災では壊滅的な被害を受けた地域を訪れた時に、人々が互いに声をかけあって避難し、その後の生活を互いに支え合っている姿が印象的でした。そこには「支援する人」「支援される人」、「行政」「住民」の区分はなく、人として支え合っていました。首都直下地震、南海トラフを震源とする地震、日本海溝・千島海溝を震源とする地震のように、複数の大規模災害が想定されています。どれほど大きな災害であっても暮らしを支えるのは、常に人でありコミュニティです。大災害を乗り越えるには、いざという時に一人一人が主役として行動し、支え合うことができる地域づくりを行うことこそが、災害への最大の備えです。そのような人やコミュニティへの信頼に基づく災害対策システムを構築することが、自治体に求められています。
2 過去の災害対応に学ぶ
私自身の減災復興研究の原点となっているのは阪神・淡路大震災です。阪神・淡路大震災が起きた時、私は神戸大学の大学院生でした。住民の立場からは、行政の災害対応に対してたくさんの不満と疑問がありました。なぜ大規模な火災を鎮火できなかったのか。六甲の水は商品化されて販売されているほど地下水で有名な地域なのに、なぜ飲料水を住民に提供できなかったのか。なぜ神戸で地震が起きないと思い込んでいたのか。なぜ学校が避難所となることを私たちは知らなかったのか。なぜ避難所はあれほど混雑して食事や物資が行き届かない状況が続いたのか。それらの疑問への答えを模索し防災研究者になりました。
2011年の東日本大震災が起きた時は、阪神・淡路大震災後に設置された研究機関である人と防災未来センターの研究員であり、災害発生直後から災害対応に関わることになりました。災害発生直後から、宮城県の災害対策本部において、命を守るには何が求められるのか、次にどのような対策を取らなければならないのかを必死で考えました。自然の猛威を目の当たりにするとともに、刻一刻と状況が変わる現場において、災害対応がいかに難しいものなのかを実感しました。研究者としては、それまで自分の専門領域の研究さえしていればよかったものが、防災研究者であるからには、あらゆる分野における専門知識が求められることを思い知らされました。そのような状況において支えとなったのは、阪神・淡路大震災をはじめとする過去の災害対応の経験のある行政職員の方々や先輩の研究者のアドバイス、そして人と防災未来センターにある膨大な資料でした。過去の災害の知見を蓄積し、それを災害対応に活用することができることは何よりも大切であることを実感しました。
本書は、災害対策システムの理解を深めるとともに、災害現場での対応に悩む自治体職員の皆様の業務の参考になればという思いから執筆しました。本書を構成する各章には、新たに執筆したものや、これまで執筆した学術論文、その他の原稿を大幅に修正したものがあります。研究を進めるにあたり、協力してくださった自治体職員の皆様には心より感謝しております。
執筆にあたっては、学芸出版社の中木保代さんの手厚い支援を得ました。倉敷市真備町でのワークショップにも足を運んでいただき、アドバイスをいただいたことに心より感謝しています。江藤洋平さんには、私の拙い説明をわかりやすいイラストに仕上げていただきました。原稿を繰り返し読み、アドバイスをしてくれた家族にも感謝しております。
日本の災害対策システムは、過去の災害対応の知見を経て変化してきています。これからも変化し続けることでしょう。本書を手にしていただいた皆様が、これまでの取り組みを参考にさらなる改善策を考え、実践していただけると嬉しいです。私も一緒に考え、取り組んでいきたいと思います。
公開され次第、掲載します。
開催が決まり次第、お知らせします。
終了済みのイベント
メディア掲載情報
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。