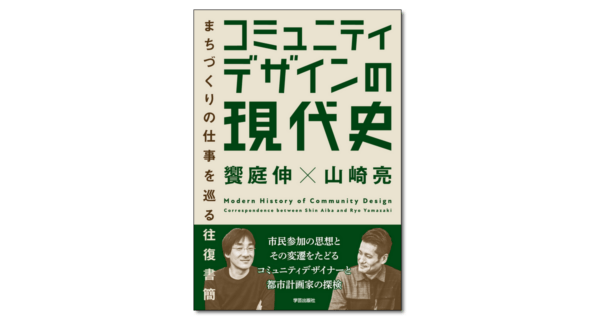コミュニティデザインの現代史
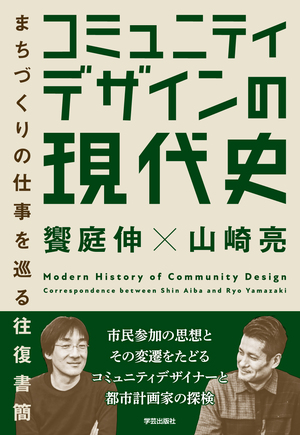
コミュニティデザイナーと都市計画家の探検
コミュニティデザイナーと都市計画家が「まちづくりの仕事の歴史が知りたい」と始めた文通。「どうも70年代の世田谷で、面白そうなことが始まっている」「地縁型まちづくりを辿ると神戸が気になる」「まちづくりに最適なスケールって何?」「事務所の経営とは?」と広がり続ける話題から参加を巡る思想の変遷が見えてくる。
饗庭伸・山崎亮 著

| 体裁 | 四六判・288頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体2400円+税 |
| 発行日 | 2024-09-05 |
| 装丁 | 題字・アートディレクション:春井裕(paper studio)、装丁デザイン:美馬智 |
| ISBN | 9784761529000 |
| GCODE | 5680 |
| 販売状況 | 在庫◎ |
| ジャンル |
1章 コミュニティデザインの歴史が気になる
1 往復書簡のきっかけ(山崎)
2 参加型デザインの原体験(饗庭)
2章 パイオニアたちに会いに行こう
3 気になるパイオニアたち(山崎)
4 見取り図を描いてインタビューに臨もう(饗庭)
パイオニア訪問記1 林 泰義さん
3章 70年代、町田や世田谷で起こっていた面白そうなこと
5 林泰義さんから派生するさまざまな話題(山崎)
6 いくつもの流れが生まれた(饗庭)
7 アメリカのコミュニティデザインを振り返る(山崎)
4章 コミュニティ計画を突き詰めた神戸へ
8 知られざる真野地区のまちづくり(饗庭)
9 地縁型コミュニティを考える(山崎)
パイオニア訪問記2 乾亨さん
5章 コミュニティ計画が描いたもの
10 コミュニティ計画をめぐる3つの論点(饗庭)
11 実践のなかの能動態・中動態・受動態(山崎)
パイオニア訪問記3 小林郁雄さん
6章 まちづくり事務所の経営について考える
12 コミュニティ計画の方言
13 URの経営スタイルから学ぶこと(山崎)
14 NPO法制定時代、80年代のワークショップ(饗庭)
15 NPO価格──studio-L設立時に考えたこと(山崎)
パイオニア訪問記4 浅海義治さん
7章 何のためのワークショップ?
16 コミュニティデザイン教育と都市(饗庭)
17 スチュワードシップと民主的な計画づくり(山崎)
18 3つのプランニング(饗庭)
19 木下勇さんのワークショップに惹かれる理由(山崎)
20 いいデザインのため? 公正なプロセスのため? 人が育つため?(饗庭)
パイオニア訪問記5 木下勇さん
8章なぜ僕らはワークショップをするんだろう
21 人が育つためのワークショップ(山崎)
22 1人からの都市計画(饗庭)
ある都市や村にこれがあったら、もっとみんなが豊かになれるんじゃないかとか、みんなが抱えている問題が解決できるんじゃないか、といったことを考える。自分が権力を持っていたり、大金や土地を持っていたりするわけではないので、都市や村の人たちが持っているものを出し合ってもらい、それらを組み合わせたり混ぜたりしながらそれを実現する、この本を手に取って下さった人は「そんな仕事」をやっている人ではないだろうか。
「そんな仕事」は、大昔から存在する。人々がバラバラに、自分が必要とするだけの住まいと生業の空間だけをつくっていたら、都市や村は成立しない。住まいと仕事場をつなぐ道路、水路や港といった生業のための施設、モノとモノを交換するための市といったものは、誰かが「そんな仕事」をしたからこそつくられたものである。ちょっと大袈裟に言うと、「そんな仕事」こそ、都市や村をつくってきた、とも言うことができる。
この本は、「コミュニティデザイン」と呼ばれたり、「まちづくり」と呼ばれたりする「そんな仕事」の歴史を少しばかり辿ってみようと考えた本である。
2つの言葉の歴史はそれほど古いものではなく、「コミュニティデザイン」は1970年代から、「まちづくり」は1950年代から使われ始めた言葉である。日本の近代化が明治維新から始まったとすると、150年にわたる近代化の後半期の「そんな仕事」をあらわす言葉として使われてきた。どちらが新しい、どちらが正統だ、どの定義が正しい、誰が正しい、という不毛な議論を展開するつもりはない。いずれの言葉であっても、人々の気持ちが動いたり、納得がつくられるのであれば、その言葉を使えばよい。大切なことは、どちらの言葉を使っても、「そんな仕事」の本質を外すことなく、うまくやり遂げることである。
山崎亮さんは「コミュニティデザイン」という言葉を、饗庭は「まちづくり」という言葉をよく使いながら、「そんな仕事」をやってきた。2018年に2人で上海でワークショップを開いた時のちょっとした空き時間に、2つの言葉の歴史についてあれこれと議論したことが、この本ができるきっかけになっている。もちろん2人が「コミュニティデザイン」や「まちづくり」を初めて提唱したわけではない。詠み人知らずのようになっていたこの2つの言葉が、近代化の後半期に「そんな仕事」をする人たちの中で、どのように使われ、育てられてきたのかを、何人かの先駆者にインタビューし、「そんな仕事」の本質を探っていこうと考えたわけである。
ちょうどコロナ禍が始まった2020年の春から冬にかけて、林泰義さん、乾亨さん、小林郁雄さん、浅海義治さん、木下勇さんへのインタビューをお願いし、その間に22回の書簡のやりとりを重ねたものを本書に詰め込んだ。歴史を大きな軸においているので、時間の流れにあわせるようにして、最初から順番に読み進めていただくことがよいと思う。この本を手に取って下さった人の、「コミュニティデザイン」であったり、「まちづくり」であったりする「そんな仕事」の展望を描く1つの助けになればと考えている。
饗庭伸
日本におけるコミュニティデザインやまちづくりの先輩たちから話が聞きたい。そう思い始めたのは2015年頃のことだった。当時、「コミュニティデザインの源流をたどる」という雑誌の連載で、19世紀のイギリスにおける思想や運動を調べていたので、その反動がきっかけだったのかもしれない。比較的身近な、つまり日本の戦後くらいからの出来事が知りたくなったのだ。 2016年、私は林泰義さんと延藤安弘さんとで鼎談する機会をいただき、「日本の、戦後以降の」まちづくりやコミュニティデザインについて話を聞くことができた。「さて、次の世代の話を聞きたいな」と思っていたところ、上海で饗庭さんから「その世代の話なら20年前に聞いたよ」と伝えられて驚いた。これが本書の冒頭に記したことである。
そこから往復書簡が始まった。主に私が饗庭さんに教えを請うというやりとりである。個人的には、往復書簡という形式が気に入っている。対談だと相手の話にすぐ答えなければならないため、質問も返答もじっくり考える余裕がない。また、記憶を頼りに話を進めるので、情報が不正確になってしまうことが多い。その点、往復書簡ならじっくり考えて手紙を書くことができるし、不確かな情報は調べてから返信できる。それでいて、相手からの手紙に刺激されて伝えたいことが生まれてくる気持ちよさがある。単に複数人で執筆分担した書籍ではこうならない。往復書簡ならではの掛け合いを本文から感じ取ってもらえれば幸いである。
本書が特徴的なのは、往復書簡で歴史を振り返りつつ、その登場人物に直接会って話を聞いていることだろう。インタビューに応じてくれた林泰義さん、乾亨さん、小林郁雄さん、浅海義治さん、木下勇さんに感謝するとともに、2023年に亡くなられた林さんに本書の完成を報告できなかったことを悔やむ次第である。
往復書簡という形式の書籍をつくるのは2回目である。建築家の乾久美子さんとの往復書簡に続いて、今回も編集を担当してくれた井口夏実さんに感謝したい。彼女は本書をつくっている間に学芸出版社の代表という重責を担うことになったため、編集のための時間を捻出するのが難しくなったと推察する。その状況を乗り越えて刊行まで導いてくれたことに敬意を表したい。
装幀を担当してくれた春井裕さんは、本書に登場する先輩方と同時代を生きたデザイナーである。だからこそ、狭義の装幀の枠を超えて、多くの情報や図版を提供してくれた。ありがたいことである。
そして、往復書簡の相手である饗庭伸さんには格別の謝意を表したい。大学の研究者であり、現場での実践者でもある饗庭さんだからこそ、知り得たり感じ取れたりすることがあるのだろう。それらを余すところなく伝えてくれたことによって、現代のコミュニティデザインがどんな流れのなかにあって、どういう特徴を有しているのかが明確になった。加えて、インタビュー先への連絡においても饗庭さんの人脈に助けられたし、本書に掲載された図版についても饗庭さんが保管していた資料に助けられた。改めて感謝したい。
本書に登場した先輩たちが活躍したのは、1970年代、80年代、90年代の約30年間である。その後のことについてはあまり語られていないが、すでに2000年代と10年代の約20年間が過ぎている。2030年以降に21世紀最初の30年間を振り返ったとき、コミュニティデザインやまちづくりの歴史に少しでも貢献できるよう実践に取り組み続けたい。また、同じように取り組む人たちにとって、本書で示した時代の潮流が今後の方向性を示すものになれば、著者の一人として嬉しく思う。
2024年7月 山崎亮
公開され次第、掲載します。
開催が決まり次第、お知らせします。
終了済みのイベント
メディア掲載情報
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。