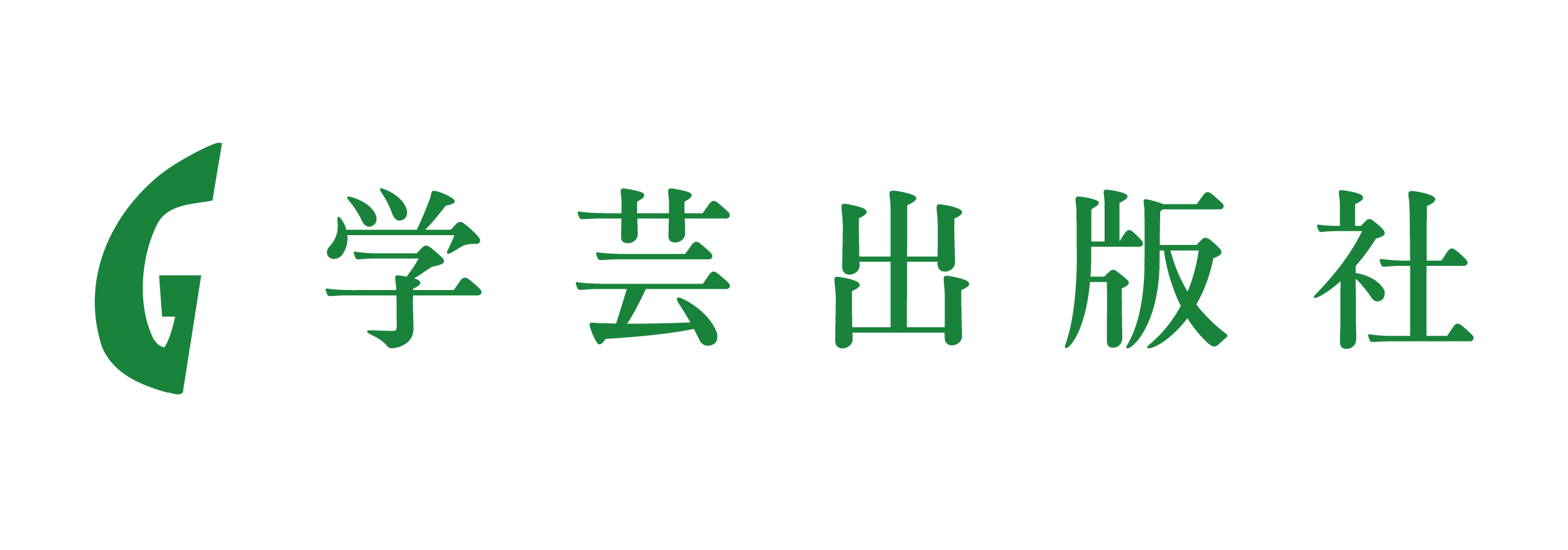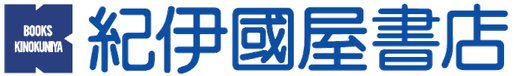コミュニティと共生する地熱利用

内容紹介
規制緩和や技術革新により各地で導入が進む地熱発電。本書は地熱資源の基礎解説に始まり、優れた合意形成で地域と共生する国内事例から、事業化を支える制度設計に踏込む海外事例まで、エネルギー自治の為のプランニング手法を網羅。開発有望地の自治体、温泉事業者、開発業者や研究機関まで、あらゆる当事者に役立つ入門書
体 裁 A5・240頁・定価 本体2500円+税
ISBN 978-4-7615-2678-8
発行日 2018/05/31
装 丁 美馬智
序 進化し続ける日本の地熱利用
第1章 いま、なぜ地熱発電か
1.1 エネルギー資源としての地熱
1.2 地熱資源利用の基本的な仕組み
1.3 欠かせないコミュニティづくりと合意形成
第2章 地域の挑戦に見る、持続可能な開発の道筋
2.1 これまでの日本の地熱発電
2.2 制度改革と技術開発
1 地熱発電を後押しする制度改革と支援策
2 地熱利用を後押しする技術開発
2.3 事例編Ⅰ:地域主導の小型地熱開発
1 小浜温泉バイナリー発電所
未利用温泉熱を活用した地域活性化
2 土湯温泉バイナリー発電所
震災復興から域内経済循環へのリーダーシップ
3 わいた地熱発電所
合弁会社設立による地域自治の明確化
2.4 事例編Ⅱ:地域と共生する大型開発
1 上の岱地熱発電所
地元企業と地域の信頼関係が可能にした新規開発
2 山葵沢地熱発電所計画
地熱開発における環境アセスメントの適用
2.5 事例編Ⅲ:自治体が主導する大型開発
1 八丈島地熱発電所
地熱利用により加速する島の持続可能性
2 自治体が地域とともに創る地熱発電
第3章 共生に向けたコミュニティづくりの手法
3.1 実践を後押しする制度づくり・人づくり
1 社会のリスク認知とコミュニケーションの重要性
2 環境省地熱ガイドラインを越えて
3 計画の担い手づくり:多様な主体の関与を促す協議会
4 市民参加と合意形成のプロセス
5 環境アセスメントを応用したリスクコミュニケーション
3.2 海外のプランニングと合意形成からビジョンを描く
1 アイスランド
オイルショックから地熱へ。地域社会と共生する地熱利用大国
2 ニュージーランド
効率的な合意形成を可能にするプランニングシステム
3 アジア諸国
問われる政府のリーダーシップ
3.3 「地熱立国」へ向けて
1 人をつくる制度づくり
2 多様な主体の協働による持続可能な地熱資源利用の実現
あとがき
用語解説
進化し続ける日本の地熱利用
1.今、地熱を再発見するということ
(1)地熱発電の「第一印象」
わが国では、2011年3月11日の東日本大震災の発生と〈福島第一原子力発電所〉事故以降、確実に再生可能エネルギーへの関心は高まった。しかし、よほどエネルギー関連の情報に詳しくない限り、再生可能エネルギーにはどのような種類があるか、網羅的に挙げることは難しいようだ。試しに、「再生可能エネルギーとして思いつくものは?」と大学生に聞いてみよう。返ってくる答えは、「太陽光発電」「風力発電」「水力発電」、ニッチなどころで「バイオマス発電」、ときて最後にやっと「地熱発電」が出てくるのが大体のパターンではないだろうか(再生可能エネルギーについては、1.1節で詳しく説明)。
「地熱発電」。まず字面に華が感じられない。地味の「地」に「熱」。全体的に画数も多い。地「熱」というのに「発電」がついている。しかも発電だけでなく「熱利用」も同時に行うらしい……もうこうなると熱なのか電力なのかよくわからない。
日本は火山国だ。火山やマグマ、温泉はおそらく諸外国よりも馴染み深いが、実際のところ地熱発電を身近に感じる機会はあまりない。ではどうして、地熱発電は知名度が低いのだろう? 「どうせ、コストが高いから普及していないとか、そんなところだろう。やはり再生可能エネルギーとか地熱発電などではなく、今までどおり火力や原子力に頼るのがエネルギー安定供給というものではないだろうか」……大学でエネルギー政策を教えると、このような保守的な考えの学生に遭遇することがある。確かに、地熱はその性質上山間部に資源があるため、都会の人間からは距離があり、身近にその存在や意義を感じるきっかけは少ないかも知れない。しかし、地熱はとても理解しやすいエネルギー利用方法である。壮大な惑星の成り立ちをベースにしていながらも、その原理は唖然とするほどシンプルだ。
詳細は第1章で扱うが、基本的に、地球という惑星内部にエネルギーが蓄積される宇宙物理学的現象を基に、熱(マグマ溜まり)、器(地熱貯留層)、水(地熱流体)の三要素で蒸気発電を行うのが地熱発電の最もポピュラーな構図だ(1.2節に詳しい)。
(2)国内外で進む地熱発電の再発見
再生可能エネルギーというと、太陽光発電や風力の変動性が問題視されることが多い。しかし地熱は地下に蓄えられたエネルギーを利用するため、天候や季節に左右されない安定電源である点が、ほかの再生可能エネルギーと大きく異なる。また、ライフサイクルCO2排出量注1は原子力以下である。
地熱は、建設コストが他の電源よりも比較的高い。しかしトータルで見た発電コストは再生可能エネルギー中で最も低いレベルであり、クリーンかつリーズナブルな発電方法だ。
また、日本はエネルギー資源小国と言われるが、それは化石燃料に由来した表現であり、化石燃料以外のエネルギー資源は決して少ないわけではない。こと地熱エネルギーに関しては、日本は世界でもインドネシア、アメリカに次いで世界第3位の資源量があるとされる(村岡ほか、2008)。このような豊富な資源量を背景に、特に東日本大震災以降、地熱発電にはあらためて期待がかかっている。また、純粋な電源として以上に地熱のエネルギーを自らの生活に利用してゆきたい、と考える人々も増えつつあり、地域活性化に役立てる動きが見られている。
(3)地熱エネルギー利用を契機とした「まちづくり」へ
例えば、長崎県雲仙市小浜では、2010年ごろから地熱を中核に据えた地域づくりが始められ、「小浜温泉エネルギー」という事業主体が立ち上がり、未利用の温泉熱水を利用した発電が事業化されている(2.3節1項に詳しい)。もともと小浜では2000年に温泉利用の検討が始まったが、開発ありきの事業計画への反発から、事業自体が中止になっていた。しかし今、その小浜でも、地域の人々が主体となる温泉熱水利用や発電事業が本格化するという非常に興味深い状況が起こっている。また、地熱エネルギー利用という枠組みを活用しながら、まちづくりや農業ビジネスとの連携などの新たな分野への拡大が企画されている。
2.新たなエネルギー源、地熱
目を海外に転じれば、2000年代以降、地熱はさまざまな国で大きな伸びを見せ始めている。アメリカやアイスランドは地熱開発の歴史が長い国だが、これら以外でもアジア・オセアニアではフィリピン、インドネシア、ニュージーランド、また昨今ではケニアなどのアフリカ諸国や、コスタリカ、エルサルバドルなどの中南米諸国でも開発が進められている。
地下資源の探索や掘削に巨額の初期投資が必要な地熱でも、これらの国々では政府の前向きな政策と民間の開発投資意欲を組み合わせて、着実な地熱開発が進められている。例えばニュージーランドでは、2005年ごろから現在にかけて、地熱開発件数が大幅に伸びを見せている。この背景には、より効率的でシステマティックな地熱探査方法の開発(2.2節2項)や環境アセスメント手続きの整備を中心に、科学的データに基づいた地域関係者と合意形成を図る取り組みがある(第3章)。このように、世界の国々では地熱開発を、温暖化対策とエネルギー安定供給、そして新たなビジネスチャンスとして捉えており、政策・制度を整えることで急速に発電量を増やしているのだ。
3.日本における地熱研究会の発足と目的
(1)地熱開発を巡る環境整備と残された課題
一方、わが国の地熱発電は火力や原子力といった多様な電源(発電方法)の中ではわずか約0.3%の発電量でしかなく、国民への浸透も十分とはいえない。なぜだろうか? その背景には、これまで何度も政策的に梯子を外されたり架けられたりした紆余曲折の歴史がある。
例えば、地熱技術開発は1990年代後半から費用対効果が薄いという理由で縮小され、2003年には政府の地熱技術開発予算は終了させられている(當舎・内田、2012)。また、地熱を含む再生可能エネルギーの普及促進を目的としていた1997年制定・施行の「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネ法)」では、事実上バイナリー発電のみが対象とされ、蒸気を用いる一般的なタイプの地熱発電が除外されていた。
加えて、日本の地熱資源の約8割が国立公園などの自然公園内にあること注2も、自然保護の観点から、開発の足枷であった(2.2節1項に詳しい)。しかし、2010年ごろから一部の規制緩和が行われるなど、少しずつではあるが規制の問題は改善されている。ほかにも、温泉法による掘削許可の迅速化など、地熱に関連した規制の緩和が段階的に行われつつある。
これら制度的な問題が(十分ではないものの)ようやく解決しつつあるなか、もう一つの大きな問題として残されているのが、本書で取り上げる“地域の共有資源(ローカル・コモンズ)”としての地熱の位置付けと、「利害関係者(ステークホルダー)」との“コミュニケーション”である。地熱開発に際しては、掘削によって温泉資源枯渇などといった悪影響が出るのではないか、という懸念が温泉事業者たちや地域の関係者に見られることがある。地熱開発において、利害関係者(ステークホルダー)間におけるコンセンサス(合意)を得る努力は必要不可欠なのだ。そもそもの話をすれば、地熱発電は原子力発電のように、万が一の事故時においても放射性物質拡散のリスクを伴うような発電方法ではない。しかし、だからといってそのリスクを全く無視してよいということではない。国民全体に対しては良いものであると考えられても、開発現場の住民に説明なく押しつけられてはならない。地熱発電の便益とリスクをきちんと理解してもらい、コミュニティと合意形成をしていくにはどうしたらいいのだろうか。小浜の例に見られるように、地域の人々が主体となって地熱を利用していく事例が増えるためには、何が必要だろうか。
(2)研究会発足の目的
そうした問題意識から、私たちは「地熱ガバナンス研究会」を発足した。この研究会は、環境アセスメント学会の会員を中心とした有志のメンバーで成り立っている。私たちは、地熱の持つエネルギー資源としてのポテンシャルを地域に理解してもらい、その資源が有効に活用されることで、さらなる発展を見込むことができると考えている。これが、環境アセスメントの専門家である研究会メンバーが最も期待する点である。
研究会ではこれまで、地熱技術の専門企業へのヒアリング、地熱技術に習熟する国立研究開発法人産業技術総合研究所や、リスク分析などに実績のある一般財団法人電力中央研究所との連携をはじめ、国内外の現地調査、学会発表などを通じて地熱発電を取り巻く社会的文脈を把握してきた。そのなかで、地熱発電に関して技術的な解説を行う書籍はあるものの、地熱発電の導入にまつわる社会的側面に関する知見をまとめた文献は非常に限られていることを痛感するに至った。
(3)制度的・社会的障壁を克服する
例えば、地熱開発をする際、地熱発電によってどのようなメリットが地域住民にあるのだろうか。ともすれば疲弊しがちな地域コミュニティに、地熱発電はいかに貢献できるのか。そしてその一方で、万が一のリスクに備え、どのタイミングでだれが何を保障すべきだろうか。リスクコミュニケーションはどのようになされるべきか。東日本大震災以降の日本で、ベースロード電源としてエネルギー供給を支える再生可能エネルギーの一つとして、地熱エネルギーには期待がかかっている。しかし当然、新たなエネルギー源の開発には、コストも時間も必要となる。さまざまな制度的・社会的障壁もある。今後は、そのような障壁を認識し、克服するために、地熱エネルギーのみならずその他のエネルギー源開発とともに、国・地方自治体・開発者・利用者などの異なる関係者間の合意を得て、開発を促進する規制再構築を行っていく必要がある。こうしたいわゆる“社会科学”の側面に関する問いに対して、包括的に応える書籍をつくるべく、本書をまとめることとなった。
本書の目的は、三つある。一つは、地域住民の主体的な地熱開発へ取り組みを促進すること。もう一つは、温泉事業の歴史的経緯と権利を尊重し、かつ冷静な議論の土台となる開発事例・情報を提供し、地域と共生できる開発を実現すること。最後に、再生可能エネルギーを生活の一部にしてゆきたいと考える人に、広く地熱発電導入の実践手法を伝えること、である。
4.本書の構成
第1章では、地熱技術に関する基本的な説明(発電の原理、種類、その他利活用例、発電量による設備の違いやメリット・デメリットなど)を踏まえたうえで、これまでの国内外の地熱開発の歴史を俯瞰し、技術・制度・社会的制約などがどのように地熱開発の障壁となってきたかを理解する。第2章では、制度の整備や技術の進歩がどこまで進んでいるかを解説し、これまでわが国で起きた地熱開発の紛争・失敗から、どのような政策・制度が必要かも考えてゆく。
さらに、地熱発電がどのように地域コミュニティに貢献しうるか、事例を基に検証する。特に、各事例における事業者・住民・行政らの関係やコミュニケーションのあり方について丁寧に考察しているのが本書の特色である。
第3章では、これら事例から得られた知見を基に、今後考えられうる地域コミュニティとの共生のあり方について考察する。これまで地熱発電とコミュニティに関しては、環境省の「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」注3が示されてきたが、これは主に温泉資源の枯渇を未然に防ぐための技術的な指針であって、必ずしも地域住民・資源との共生を探る枠組みを提示したものではない。本書では、さまざまな選択肢を議論できる土台づくりへ向けて、紛争を解決する制度づくり・自治体の関与・適切な対話のプロセスの制度化を提言する。
また、コミュニティや地域地熱開発を支える教育・キャパシティの充実と発展についても考察する。再生可能エネルギーが根本的に問いかけている分散型エネルギーの実現可能性を高めるためには、需要家(電力消費者)自身に「エネルギーを創り出す」という新たな役割を求める必要がある。消費者の立場を超えた“エネルギー生産者”を増やすためには、いかに新たなエネルギー源の開発・利用を阻む多くの障壁を取り除くか、新たな政策を培っていくかといった発想が重要であり、当然そのような努力を可能とする知識・教育も求められる。今後エネルギー「政策」が、学問として成立し、社会知として定着し、新たなエネルギーシステムを生み出すために、今後の地熱やエネルギー教育のあり方についての提言を以って総括としている。
それでは次章から、そうした新たなエネルギーシステムを生み出すきっかけを見ていきたい。
[注]
注1 ライフサイクルCO2排出量
エネルギー源となる燃料や、その他エネルギー源に関わる生産・輸送・発電などをトータルで見たときに発生するCO2の排出量。
注2 自然公園内の地熱資源
本書では、国立公園の他、国定公園や道府県指定の公園を含むものとする。
注3 温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)
温泉資源の保護に関するガイドライン(2009年)の分冊として地熱発電関係に特化して発行されたもの。2014年に改訂され、その後2017年に再改訂されている。詳細は3.1節2項で扱う。
[参考文献]
- Bertani, R. (2016) “Geothermal Power Generation in the World 2010-2014 Update Report”, Figure taken from Renewable Energy World HP
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/01/2016-outlook-future-of-geothermal-industry-becoming-clearer. html - JOGMEC HP
http://geothermal.jogmec.go.jp/information/geothermal/mechanism/mechanism2.html - 今村栄一・井内正直・坂東茂(2016)「日本における発電技術のライフサイクルCO2排出量総合評価」『電力中央研究所研究報告書』Y06
- 小浜地熱エネルギー HP
http://obamaonsen-pj.jp/kyougikai.html - 環境省(2012)「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」
http://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/chinetu_guideline.pdf - 當舎利行・内田洋平(2012)『トコトンやさしい地熱発電の本』日刊工業新聞社
- 日本地熱協会 HP
http://www.chinetsukyokai.com/information/nihon.html - 村岡洋文・阪口圭一・駒澤正夫・佐々木進(2008)「日本の熱水系資源量評価2008」『日本地熱学会平成20年学術講演要旨集』B01
日本の再生可能エネルギーは、確実に新たな段階に入っている。かつての「再生可能エネルギーを導入するべきか」という議論は、今や再生可能エネルギーを「いかに導入するか」という議論になってきている。
電力会社に発電の多くを任せていたころ、都市でも地方でも、一般に人々はエネルギー「消費者」であって、エネルギーの生産に携わることは極めて稀であった。しかし、再生可能エネルギーの本質は「分散型」である。つまり、大手電力会社が戦後長きにわたって行ってきたエネルギーの生産は、分散し、生活圏(コミュニティ)の近くにやってくる。
地熱利用に関しても各地で計画が立ち上がっているが、それらの地域がこれまでエネルギー生産には縁遠かったとしても全く不思議ではない。日本のエネルギー需給構造そのものが、長らく「分散した」エネルギー生産と無縁だったからだ。しかし、生活する人々の理解と協力を得、人々の生活に資するエネルギーたることが、再生可能エネルギーに期待されている点である。それぞれの地域に経済的・社会的便益をもたらしてこそ、再生可能エネルギーの「健全」な導入と言えるし、日本でそのような導入をいかに進めていくかを広く考えていくことが社会的要請となりつつある。
本書は地熱利用を扱ってきたが、再生可能エネルギーとわれわれの関わりは今後深くなることはあっても、その逆はあり得ないはずで、本書の提起した地熱や再生可能エネルギーの社会的側面やより良い導入に今後さらにスポットがあたっていくことを祈念している。
なお、さまざまな制約のなか、本書で扱うことができた事例に限りがあったこと、技術的な面については、国内外の他書に譲らざるを得ない面もあったこと、ビジネスとしての地熱プロジェクトの難しさと可能性について扱えなかったことなど、反省は多い。しかし、地熱技術や社会制度について習熟している国内外の多くの専門家を会して本書を世に出すことができたことは、望外の喜びである。
本書の刊行は、地熱利用に関係する多くの方々のひとかたならぬご協力・ご尽力の上に成り立っている。ときに山深い、または雪多い地域にあって、難しい地下のエネルギーに向き合い、軌跡と今後の指針を示してくださっている皆様に心からの敬意と感謝を申し上げたい。また、本書の執筆に参加してくださった著者の方々、特に全体について多くのアドバイスをいただいた安川香澄さん、企画から刊行に至るまで万般の配慮をいただいた学芸出版社の方々と岩切江津子さんに、深くお礼申し上げたい。
2018年3月 編者を代表して 諏訪亜紀
本書の出版に際し、京都女子大学から平成29年の出版助成を受けた。執筆者一同、記して謝意を表したい。
お問い合わせ
ご入力前にご確認ください
- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。
- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。