復興まちづくりまつり 第1回世界鷹取祭
世界の人が支えている。
町よ、 よみがえれ。
人よ、 集え。
21世紀の神戸へ。
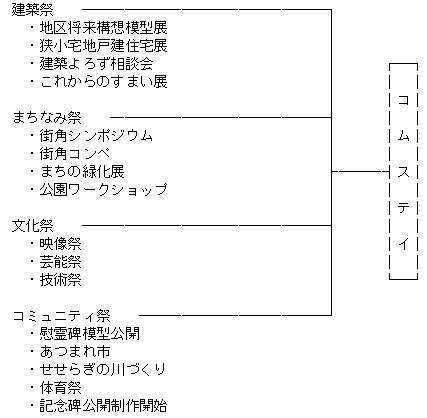
世界の人が支えている。
町よ、 よみがえれ。
人よ、 集え。
21世紀の神戸へ。
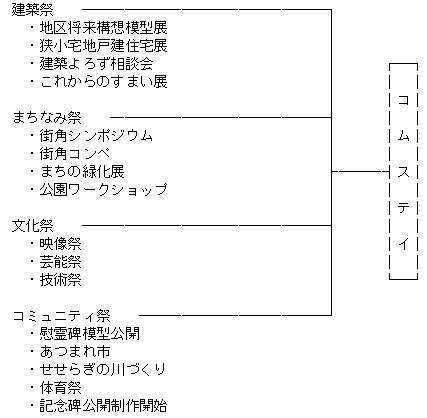
まちづくりには終わりがありませんが、 まちづくりを通して、 当面は自分たちのまちを考え、 そして物理的にも、 人間的にもコミュニティを復興することを目的としています。
被災されて今まで住んでいたコミュニティから遠く離れている人々も、 お祭りの間は地域に帰って来て、 地区の中に泊まって再会を喜び、 また地震で亡くなった人々のためには鎮魂祭を、 これからまちづくりを再建して行こうとする人々のためには、 まちづくりの新たな展開への祝祭として盛り上げて行けたら幸いです。
祭りの内容は上記の通りですが、 まちづくり計画が進み、 道路や公園が整備されていく中で、 これからは個々の建物をはじめ、 立体的なまちの景観がどうなるのかが問題となります。
まちの景観としても、 まちづくりにも大切な街角空間をどうするのか、 人間も自然の一部なのだとの考えからエコロジーとしての自然、 即ち緑や水辺をどのように命につないで行くのかが課題となります。
そこで街角、 緑、 水をキーワードとして祭りを盛り上げて行きたいと考えています。
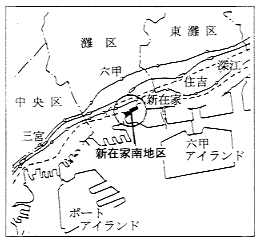
(その2)の報告以降、 また約半年が経過したが、 この間、 “後興まちづくり”としては、 懸案の「まちづくり協定」が神戸市長と縮結され、 まちづくり協定委員会の運営がはじまった。
一方、 “復興すまいづくり”としては、 住民と市の供働による特目賃事業と住市総の補助事業としての共同建替え事業が着工した。
本稿では、 これらの新在家南地区における続その後の復興まち・すまいづくりの進捗状況を報告する。
この事業は、 権利者が両地区合わせ34人と比較的多かったこと、 公道の移設を神戸市にお願いしたこと等により時間がかかったが、 地権者の我慢強い協力とディべロッパー及びコンサルタント集団の汗と努力の結晶といえる。
今後は既に着工した事業を啓発材料として、 下図に示すような復興状況の詳細な把握に基づき、 新しい共同建替え等の計画的建替え車業を掘り起していきたい。
3月17日の兵庫県都市計画審議会の約1週間前の出来事である。
それ以降、 震災からおおよそ18ヶ月が経過した現在まで、 24回の会合を積み重ねてきた。
均すと、 月当たり1.3回の開催と言うことになる。
同じような名前が多いのでやや紛らわしいが、 連絡会は3月17日の都市計画決定に反対する各地区の住民の会の、 連絡・交流・学習の会として発足した。
被災により住民がいないことをよいことに、 建設省の主導による非民主的な再開発・区画整理などの都市計画がかけられようとした。
それに対して住民主体の立場から民主的なまちづくりを進めようとする各地区の住民やそれを支援する専門家・研究者が参加している。
発足時には、 宝塚(中筋)・西宮(北口、 森具)・芦屋(中央、 西部)・神戸(森南、 六甲、 新長田、 西須磨)・北淡町等の住民が危機感を持って集まり、 基礎自治体での都市計画の縦覧の取組や都市計画審議会への働きかけを各地区ごとに行った。
さらに県の都計審にも様々な取組を行った。
しかし残念ながら都市計画決定がなされてしまったのは周知の通りである。
都市計画決定後は、 都市計画の変更や事業計画の民主的転換を目指し、 様々な学習や情報交流を行ってきた。
節目節目には、 シンポジウムや合宿を行って総合的な活動方針を検討したり、 個別の具体的な問題の掘り下げなども行っている。
この8月11日には、 7時間に及ぶシンポジウムを、 予想を超える220名の参加で開催し、 今後の運動の展望を語り合った。
連絡会における今回の区画整理や再開発などの評価は、 基本的には×である。
区画整理の根本的な目的は、 以前から計画決定されていた(大)幹線道路を通すことであり、 住民説得の理由として述べられている、 「復興のためのまちづくり」などは、 概ね、 おためごかしに過ぎないというのが、 大方のメンバーの判断である。
もちろん今回の区画整理でも建築基準法上の接道条件が改善されるなど利益を得ることのできる住民はいるだろうが、 大多数の人が、 被災にプラスする被害を被ることは間違いないと思われるからである。
再開発の場合はもっと悲惨であると思われ、 大幅な改変が必要であると連絡会では考えている。
西宮北口でも六甲道でも新長田でも、 これまでと同じような制度条件で事業が進めば、 借家人などの零細権利者はもちろん、 持地持家の人でも商売や居住の継続が極めて難しい事態になることが、 明白に予想されるからである。
さらに根本的には、 建物は完成してもその後の維持管理が順当に進むかといえば、 この点での事業のまっとうな成立は絶望的であると推測される。
西日本で最も経済ポテンシャルの高い大阪梅田の再開発が非常に苦闘している現状では、 今回の被災地の大規模な再開発がまともに成立することは予測の以前であり、 住民がすべて追い出されたガラガラの幽霊ビルに、 多額の市税を投入してかろうじて維持するという将来の筋書きが目の当たりに見えると言って言い過ぎではないであろう。
現在各地区の都市計画・まちづくりは圧倒的に優勢な行政に押しまくられているように見えるが、 事態は必ずしも行政の意図するようには進んでいない。
大方の行政の側の施策や論理には住民の意向を無視またはないがしろにするという根本的な矛盾があるからである。
行政の支援が極めて乏しいいわゆる白地地区の復興も含め、 住民・市民の総合的な力量を強め、 本当に住民・市民本位の復興まちづくりや住宅づくりが進むような状況を作り出す必要がある。
そのための一歩として、 少しでも多くの都市計画の専門家やコンサルタントの方々が、 夜間のボランティア活動でもよいから、 住民本位のまちづくりを目指す自主的な住民・市民の運動を支援してくださることを要望して、 この小稿を閉じることとする。
(9月1日 記)
復興まちづくり
まちづくり協定を神戸市と締結
懸案であった「新在家南地区まちづくり協定」は3月の臨時総会で住民周知が不充分のため延期となり、 まちづくりニュース等の発行による周知徹底の後、 6月の総会において可決承認され、 平成8年6月26日に神戸市と締結(神戸市公告第25号)された。まちづくり協定委員会が始動
その後、 7月より11人からなるまちづくり協定委員(総会で選出)により1ケ月に1回の日程で協定委員会を開き、 届出案件について審議を行っており、 7月、 8月、 9月の3ケ月で下図に示す9件の審議を行った。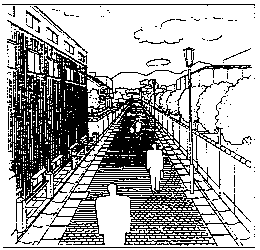
啓発イメージ図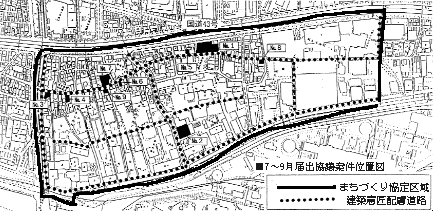
7〜9月届出案件位置図
(*ワンルームで敷地300m2以上)
(*事業所部分が1,000m2以上)
(*敷地面積300m2以上)
但し、 *は協議、 無印は図面審議
まちづくり協定に沿った塀の設置
まちづくり協定の協議期間中に建設された住宅で、 本体はプレファブ住宅であるが、 勾配屋根、 色調に加え、 まち並みを配慮した塀を設置した例が出来ている。
まち並を配慮した塀の設置例
復興まちづくり
住宅復興率は約32%
新任家南地区の全住宅地面積(工場等を除く)は約47,000m2で、 このうち約32,500m2(約70%)が今回の震災で更地化したが、 震災1年8ケ月後の平伐8年9月現在で約10,500m2の住宅地において再建済み又は工事中であり、 住宅地復興率は32%である。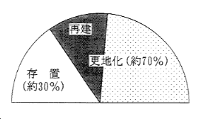
更地化率特目賃住宅が6月に着工
神戸市の災害復興特定目的借上公共賃貸住宅制度(特目賃)を活用した地域貢献型共同住宅の起工式が、 去る6月22日(土)に建築主の見掛家をはじめ、 まちづくり協議会や自治会代表が出席して行われ、 地域の期待のもとに、 来年3月の竣工を目指して7月から工事が始まっている。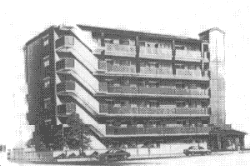
特目賃共同住宅完成予想図
3丁目A・B共同建替が合同で起工式
震災直後からまちづくり協議会の支援を得て取り組んできた3丁目10―A地区と10―B地区の住市総補助事業による共同建替え事業が、 1年半を要して、 ようやく去る9月25日(水)に合同で起工式を行い、 10月から来年8月の竣工を目指して工事が始まった。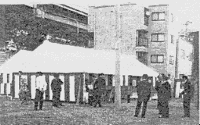
3丁目A・B地区合同の起工式
今後の展開
あと2件の権利者の合意が出来ている共同建替え案件については、 法的、 開発手続き関係で遅れているが、 弁護士等の専門家の協力を得て解決し、 年内着工を目指している。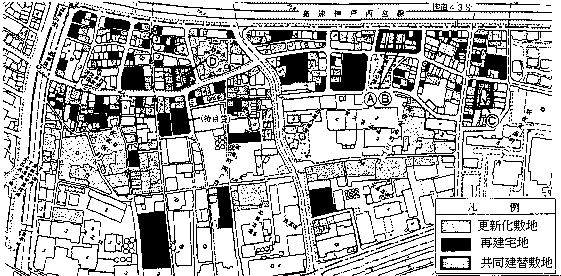
居住ゾーンの住宅債権復興状況図
住民本位の復興を目指す「復興市民まちづくり連絡会」
「復興市民まちづくり連絡会」事務局・神戸松蔭女子学院短期大学教授/竹山 清明
「復興市民まちづくり連絡会」(以下、 連絡会)は、 1995年3月9日に発足した。INFORMATION
震災復興・実態調査ネットワーク/第5回交流会
※以前に10月5日と連絡しておりますが、 日が変わっておりますのでご注意ください
阪神グリーンネット/第13回定例会議

生垣・緑化推奨看板をたてました。
'96.8/26灘区楠丘町3丁目
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい37号へ
きんもくせい37号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ