職能の原点に立ち返ること
都市計画の原点は、 人が集まり住むところから始まっている。そして都市計画とは、 集まり住む人々が都合よく生活できる仕組みを〈個〉のレベルから〈全体(社会)〉へと構成させることと考えられるが、 手法的には便宜的に〈全体〉的発想からこれを行っていた。
しかし、 現在の日本における都市計画は、 そのコンセプトまで〈全体〉からのスタートになってしまっている。
街の人々の存在すら意識しているかどうかあやしいものである。
〈個〉そのもので成立している街は、 その協力者としての都市計画家に委ねてしまうには、 大いに危惧される。
一方、 建築家もその職能の原点に立ち返る必要がある。
その職能は次の4点につきる。
(1)個人の利益の保全、 育成 (2)社会の利益の誘導 (3)個人と社会の矛盾の相克 (4)次代への継承 である。
現在の日本の建築家の多くは、 〈個人の利益の保全、 育成〉のみにその重点を置き、 〈個〉からのスタートした〈社会〉にその職能性があることを横に置いてしまっている。
今、 〈まち〉にとって求められているのは、 建築家と都市計画家の中間の領域を持ち、 地区に密着したコミュニティ・アーキテクトである。
〈個〉からの〈社会〉を形成させうる誘導的整備手法を持ちえるまちづくり専門家(コミュニティ・アーキテクト)である。
為に、 専門家は地域社会の中で密接にそのコミュニティとかかわり、 自らの社会性を日頃から鍛え、 自分の身は自分で守るという地域社会の大切さを見直さなければならない。
そこで、 まちづくりの視点をもう一度検討する必要がある。
高齢者を地域が支えてきたコミュニティがあったことを認識し、 いろんな生活が街に顔を出すようなまちづくりの必要性を感じなければならない。
そして、 それがまた街を楽しくしたり豊かにすることの仕掛けともなっていることに気づかねばならない。

まちづくり会議(日本建築士会連合会主催.1/20神戸市)での
森崎氏の講演
新しいパラダイムでの役割
震災以前、 職人達の業界全体に対して、 都市・建築家がその権利を守ったり、 技術のレベルアップを図ったりすることは殆どなかった。このことは〈まち〉が形づくられている構成そのものにあまり関心が向けられていなかったことを物語っている。
今、 地域社会に対しても建設業界に対しても、 新しい専門家としてのスタンスが必要となっている。
新しい住宅のあり方の提唱、 神戸らしさと経済性という観点から、 新しいパラダイムで設計基準を語る時期に来ており、 地震後(ポスト・アースクェイク)の都市・建築の新しいパラダイムの提案をすべきである。
徒歩圏で行動できる都市づくりによって、 都市部においてのインフラの根本にまで至る変革の提案である。
残せるものはできるだけ残す、 残せないものはそのイメージを継承する。
これは、 都市と建築を造る思想にとって重要なことに思える。
モダニズムという免罪符を打破し、 その経済性、 機能性を第一義におくのではなく、 建築は都市の中の構成部位であるという認識にたって、 リフォームする技術、 リニューアルの思想を育ませ、 より高度な建築を生み出す力を持たねばならない。
都市計画にとって次に掲げることを今一度再認識しておく必要がある。
神戸には神戸のスケール感があるのでこれを大切にすること、 プライベートな空間とパブリックな空間の仕組みについて再考すること、 等が必要である。
そして、 各々に多様な問題点を抱えた中で、 独自のまちづくりを行おうとしている。
それを可能にするには、 地域に密着した専門家の支援が不可欠である。
一方、 専門家にとっては個人としての活動の範囲は、 いろいろな要因によって困難な状況に取り巻かれている。
その問題点打破のためにもまちづくりのためのNPO(非営利組織)の設立を実現し、 その組織化による支援体制の確立も急務である。
〈まち〉に対する(1)人的支援、 (2)情報協力、 〈専門家〉に対する(3)組織的協力、 (4)財政的支援、 等その役割は多岐にわたる。
しかし、 まちづくりの緊急性はそれらを短時間で解決しなければならないことぐらいは誰もが認識している。
〈まちづくり〉はその実現性にこそ意味を持っているのだから。
(上記レポートは、 足立祐司氏、 三好庸隆氏との対談からの引用を含んでいます)
p1,4
出席者は地震前まで長田区久二塚地区の借家に住み続けてきた人たちで、 72歳〜85歳までの女性11名と地区の世話役の方々である。
以下にその日の話を再現してみよう。
聞き手は森崎、 太田、 小林、 石東である。
自分の住宅は小さいけど台所やお便所もついていて、 共同の大きめの台所、 食堂や談話室、 お風呂などがあるという共同住宅で、 住む人がみんなで共同部分を使って、 管理していくという住まい方です。」
理想的や。」
そこをみんなで掃除できるか。」
できんようになったらどうしたらええんやろか。」
高いので入りにくい。」
人と知り合える。」
参加したいけど、 何もできなかったら人にしてもらう方が多くなって気兼ねする。」
ひとりやと同じもんを何日も食べなあかんし、 自分の好きなもんしかつくらへんので、 栄養がどうしても片寄る。」
一週間分のメニュー考えたらええねん。」
テレビ見てても考え方がいろいろ聞けてええ。」
お正月を前にして、 孤独に耐えられない被災者は少なくなかっただろう。
記事によると、 震災後の自殺者は6月以降は仮設住宅居住者が目立っているという(毎日新聞によると、 1月半ばで、 自殺者33名、 独居死51名、 室内で意識不明に陥った人12名)。
一日中誰ともふれ合わんと、 部屋の中で孤独に過ごすのはあかん。
明日への気力がわいてけえへん。
《いつでも誰かと会えるし、 いつでもひとりになれる》、 《ひとりで食事するよりも、 たまには大家族のように集まって食べよう》というコレクティブハウジングが理想的やと思う。
今、 仮設住宅に住んでいる人の中には、 自力で住宅を確保して移り住む人もいるけど、 多くの高齢者や母子世帯などは災害公営住宅の入居を待たざるをえない。
そうすると災害公営住宅では、 今の仮設住宅よりももっと高齢者や母子世帯などの割合が多くなるだろう。
行政としてはいろんな懸念もあると思うけど、 とにかくモデル的にコレクティブハウジングの供給を早急にやってみて!長田区のしたたかなおばあちゃんたちの応援があるやん。
初期に建てる住宅に実験的にとりくんでみて、 問題点があれば修正していけばいい。
躊躇していると孤独に耐えきれないで、 人知れず亡くなっていく人の記事が、 今後何年も何年もの間報じられて胸を締めつけられる日々が続くよ。
被災した人たちは人間が変わった。
変わろうとしている。
変わって新しい生活を始めようとしている。
行政システムも変わってほしい。
人々が仲良くしていける地域をつくることが防災である。
《共に住む、 共に生きる、 共に創る、 相互扶助の暮らし》、 《集まって住む安全性と安心感、 集まって暮らすことの楽しさをもつ住宅》の供給が、 待たれている。
昔のように元気な生活をとりもどした下町のニュースを、 一日も早く目にしたい。
そして、 そこから、 本格的なコレクティブハウジングが発展していくのを願っています。
p2
そのためにはいろいろなことが考えられますが、 わたしたちはささやかながらブロック塀を生垣に変えることを考えたいと思います。
緑は堅い都市空間をやわらかい素材で包むとともに、 都市に間隙をつくりだします。
一人ひとりつくりだせる緑はわずかなものですが、 「住民自らが自らの手で自らの暮らしを守るという基本」にもあっています。
それに、 なによりわたしたちに四季を教え、 自然と共生する生活のゆたかさをもたらしてくれます。
垣根から始める安心環境づくりを応援するために、 垣根づくりのノウハウと情報を紹介したパンフレットをつくりました。
ご希望の方は、 返信用切手(270円分)を同封の上、 下記までお申し込み下さい。
一つは「阪神・淡路震災復興支援10年委員会」(代表:安藤忠雄氏)が進めようとしている「ひょうごグリーンネットワーク」の取り組みで、 もう一つは「環瀬戸内海会議」の3人のメンバーの運動です。
実は、 ネットワークでも「阪神市街地緑化再生プロジェクト」の第2段階として「家に苗木を」(『きんもくせい』第10号、 '95.6.6参照)ということで、 苗木づくりの準備を始めていました。
今後、 こういった方々とも連携して緑豊かなまちづくりを進めていきたいものです。
朝日新聞・朝刊 1/6付 毎日新聞・朝刊 1/20付
「復興まちづくり講座」として「区画整理・再開発」、 「共同建替・マンション建替」、 「都市オープンスペース・防災」、 「復興市民まちづくり計画」のテーマで講演及び分科会の討論を行いました。
最終日は全体のまとめとして、 分科会の報告並びに参加者100数十名が約十数グループに分かれての討論が行われ、 被災地の実状をふまえた専門家としての多彩で貴重な意見、 提案等が出されました。今後これらの具体的推進が望まれています。
075-342-2600)
またTシャツ等「ガレキに花を咲かせましょう」グッズも販売しています。
震災以後、 神戸大学重村研究室等で定期的に行ってきた被害状況や復興状況の調査結果や、 復興モデルプラン等の展示が行われました(住吉地区の詳しい状況は『きんもくせい』15号参照)。
「阪神淡路ルネッサンスファンド」(HAR基金)は、 主にこの「白地地区」の復興まちづくりを支援するものです。
このほど、 HAR基金の自動引き落としがほとんどの銀行及び郵便局でできるようになりました。
詳細は事務局までお問い合わせ下さい。
また、 新しいパンフレットもできましたのでご利用下さい。
2月5日(月)必着分までを掲載します。
1月中にページ数等確定しますので、 早めに事務局までご連絡下さい。
P.4
文化・環境
モノを造ることと残すことは、 そう違ったものではない。
環境の認識とその質の向上をめざすことが都市計画の役割である。
組 織
まちづくりは、 地元住民による自発的な取り組みが基本となることは言うまでもない。(1)人的支援
(2)情報協力
(3)組織的協力
(4)財政的支援
以上、 まちづくり専門家とその組織の役割、 支援についての提案を述べたが、 当面の検討課題は多い。
(1月17日 記)
「そんな住宅、 理想的や。
そやけどわたしら5年も待たれへん!」
長田区のひとり暮らし高齢者のすまいを考える集い
(被災地にコレクティブハウジングを!/その5)コレクティブハウジング事業推進応援団 石東 直子
12月半ば、 長田区二葉老人いこいの家で、 仮設住宅に住むお年寄りの“ひとり暮らし高齢者のすまいを考える集い”が久二塚6まちづくり協議会・住宅部会によってもたれた。
(1月20日 記)
あなたの家の垣根からはじめよう。
安心な環境づくり
兵庫県立人と自然の博物館 田原 直樹
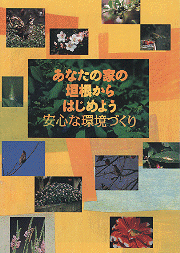 安心環境づくりは、 広幅員の道路や広い公園があればよいというのではなく、 ふだんの暮らしの場をゆとりあるものにすること、 いわば基礎体力をつけることが大事だ、 とたびたび指摘されています。
安心環境づくりは、 広幅員の道路や広い公園があればよいというのではなく、 ふだんの暮らしの場をゆとりあるものにすること、 いわば基礎体力をつけることが大事だ、 とたびたび指摘されています。
申込み・連絡先:ヒューマン&ネイチャー・ネットワーク
〒669-13 三田市弥生が丘6 人と自然の博物館内
TEL.0795-59-2018 FAX.0795-59-2029
INFORMATION
てんさいコーナー/第2回
今回は、 被災地に苗木を配り、 街を緑化しようという取り組みを紹介します。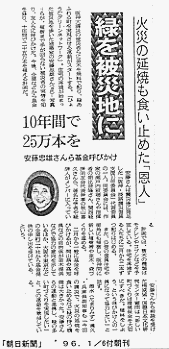

 朝日のより大きな画像43K
朝日のより大きな画像43K
 毎日のより大きな画像83K
毎日のより大きな画像83K
まちづくり会議(第5回)開催される
日本建築士会連合会まちづくり委員会主催の「第5回まちづくり会議」-阪神淡路大震災のまちづくりから学ぶ-が1月19〜21日の3日間にわたり、 神戸で行われました。
グループごとの討論風景・3日目メモリアル1・17展
*ネットワーク事務局からも資料提供をしています。
 メモリアル1・17展へのリンク
メモリアル1・17展へのリンク
展示風景住吉地区震災復興パネル展 開催される
震災1年目に当たる1月17日から21日までの5日間、 住吉地区復興支援グループによりパネル展が開かれました。
パネル展全景(神戸市東灘区・コープこうべシーアにて)ネットワーク事務局より
HAR基金自動引落システムができました
被災地の復興まちづくりはまだその歩みを始めたばかりで、 特に「白地地区」といわれている被災地の約8割を占める広大なエリアは自力再建を余儀なくされており、 取り組みは遅れています。まちづくりニュースを至急送って下さい
好評につき『復興市民まちづくり』VOL.4を2月下旬に刊行します。ネットワーク会議等
「神戸東部市街地白地対策会議」
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい24号へ
きんもくせい24号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ