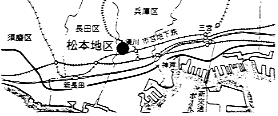
松本地区位置図
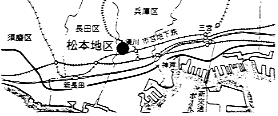
3月17日、 約8.9haの土地区画整理事業区域と地区内の幹線道路(松本線・17m)が都市計画決定された。
地区周辺は、 神戸の市街地でよく見られる条理制遺構にもとづく直交道路パターンで画された市街地で、 震災前の土地利用は戦前からの建物が残る下町的住宅地で、 住宅を主として一部に商業施設、 食品工業施設等も立地していた。
震災後地元住民から火災保険の支払いを求める運動が始まり、 これが母体となって「松本地区復興委員会」が結成された。
復興委員会は、 焼け跡にいち早くコンテナを利用した事務所を設置し、 火災保険に加えガレキの撤去や行政への仮設住宅建設要望など応急的対策を中心に活動していた。
都市計画決定を経て復興のための活動への本格的取り組みとして、 復興委員会を発展させて「松本地区まちづくり協議会」が5月7日に結成された。
この協議会は松本地区全域を対象としたもので、 被災住民が地元にほとんどいない中、 約260名の集会により承認されたもので、 役員は暫定的なものであるとの認識のもとにまちづくり活動を行なっている。
コンサルタントによるまちづくり支援は、 まちづくり協議会結成直後から開始された。
我々の支援活動は、 当初は毎土曜日に開催される協議会役員会での土地区画整理事業や建物共同化等まちづくりの基本とする内容の説明を行ないつつ、 「まちづくり協議会ニュース」の作成、 避難所や仮設住宅等に避難している住民の居所の把握、 従前の権利関係の復元、 今後の計画検討に必要な地形模型の作成等の作業を行なった(模型の一部は、 東京理科大学の学生諸君によるボランティア活動の成果でもある)。
復興まちづくりの目標は、 一日も早い住宅や店舗の再建、 快適な居住環境の創出、 豊かなコミュニティの回復であり、 その手段としての区画整理事業の早期実施でもあるといえる。
事業計画の作成にあたっては街区ごとの詳細な住民意向の集約が必要である。
このため、 まちづくり協議会では現在、 全力をあげて下部組織として街区ごとの「まちづくり小委員会」づくりをめざした活動を展開しつつあり、 その最初の会合が9月10日に開催される予定である。
いずれにせよ、 松本地区のまちづくりはその端緒についたばかりである。
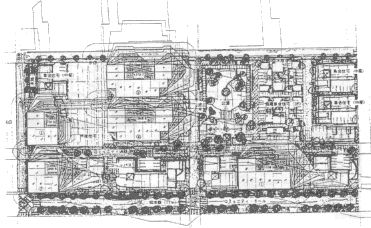
住吉地区(旧住吉村)はその中央に位置し、 独特な歴史的背景を持っている。
神戸大学重村研究室と、 いるか設計集団のボランティアグループは、 3月から本格的な調査、 提案活動に入った。
この調査は、 緊急調査であることの本質的問題を抱えている以上、 復興のために必要な様々なデータの経時的な変化を追っていない。
せめて住吉の百数十haだけでも、 との発案からこの定期的詳細調査を始めた。
このような被災と復興の方法を研究するための計画調査には、 戦略的な調査目標が必要である。
私達の調査では以下の四つの計画目標のもとに、 これに必要な調査項目を設定した。
2)避難所避難者数の推移 避難所避難者数は、 6月中旬以降横這いとなっている。
地域の賃貸住宅居住者に、 適切な価格、 位置や条件の避難先が乏しいことをうらづけている。
3)撤去と仮設、 新築等の進行状況を見ると、 8月現在空地が大規模に広がって、 風景が喪失されてきた状況が良くわかる。
また撤去優先の政策の可否も問われる。
4)賃貸住宅居住者等への集中した被害
木造長屋は、 持ち家をも含んでいるが、 103棟中72棟が倒壊し、 42 5世帯中316世帯が被災している。
これらの家主に、 適切な住宅の再建のインセンティヴを与える方法、 従前居住者の戻り入居を可能にする方法が課題である。
5)その他の共同住宅 RC共同住宅の内39棟が倒壊している。
このうち、 いわゆるマンションの課題には、 良く指摘されている既存不適格問題や、 ダブルローンの問題に加えて、 ローン完済の高齢者が戻り入居できるかという問題が出てきている。
6)街区の空間整序課題 未接道宅地や、 過小宅地を含む街区が多く存在する。
協調建替えや、 共同化、 ミニ区画整理など、 どのような再建手法がふさわしいか、 街区ごとにデータ化し、 問題モデルを選んで解決策のオプションを作成中である。
7)被災前の住吉の環境について研究した論文と現在のフィールドをもとに、 住吉の環境資源を調査し、 長期の理想目標を、 生活産業、 自然、 歴史文化環境の観点から描いておく必要がある。
豊かな目標を持たないと復興は応急の域を越えないだろう。
直接問題を抱える被災住民、 権利者に投げかける方法と、 かすかに残った地域組織を通じる方法、 展覧会などのイベントを仕掛ける方法を模索している。
(8/29記)
7月末の炎天下、 芦屋市呉川町のケア付き仮設住宅を訪ねた。
ここ呉川町には8棟(95戸)の仮設住宅が軒を接して建てられている。
その一角の3棟がケア付き仮設住宅で、 平屋建ての1棟に14人(14居室)が共に住まうコレクティブハウジングである。
わが国ではケアを必要とする人たちが共に生活する場をグループホームと呼び、 福祉施策にもり込まれた施設だが、 北欧諸国のコレクティブハウジング(多世代の多様な家族が集まって住む共同住宅)の親戚みたいなものである(芦屋市では呉川町の3棟と高浜町の1棟のケア付き仮設住宅の運営を、 「尼崎喜楽苑」の市川禮子苑長に委嘱している)。
1居室は16m2の広さで、 6帖(和室と洋室があり選べる)にトイレと洗面スペース、 押し入れ、 ゆったりした入口スペースである。
それに14人の共同生活のためのダイニングキッチン(約45m2)、 2つの浴室と職員詰所がある。
一人に一室なので二人世帯の場合は二室が使える。
居住者の多くが住宅が全壊し、 長時間倒壊家屋の下に埋もれていた人たちで、 極限の恐怖を体験している。
中には、 1938年の阪神大水害と第2次大戦をも体験している人もあり、 “わたしの一生は何だったんだろう”と呆然としていたという。
入居当初は話を始めると、 すぐ涙がふきでてくる人たちばかりで、 生きる気力もなく一日中自室に閉じこもりがちの人も多かったそうだ。
市川さんをはじめとするスタッフ13名が、 昼間は各棟に1〜2人、 夜間は4棟で2人になって、 24時間勤務している。
スタッフの主な仕事は、 入浴介助などを必要とする人の手助けで、 通常は目配り、 気配りでもって話し相手や生活相談にのり、 買い物や通院への付き添いなどと、 てんてこ舞いである。
食事は原則として自炊ということだが、 希望者には月、 水、 金の昼食づくりはボランティアの支援があり、 居住者やスタッフも一緒になって食事を作る(居住者は食材の実費を負担する)。
夕食は31人が芦屋市福祉公社の配食サービスを利用している。
スタッフは、 居住者が生きる気力を取り戻すために何をしたらいいか頭を痛めているというが、 時間が経つにつれて、 気力の蘇りを確実に感じているという。
各室に閉じこもりがちだった人が、 談話室に出て来て交流することにより、 入居当初ひどかった精神障害が落ち着き、 ここまで良くなるとは思わなかった程に快方に向かっているという。
また、 沈みがちの日々を送っていた人が、 夕涼みパーティの後、 「わたし自分の家を建て直すわ」と言い出し、 皆を驚かせたという。
刺しゅうの得意な85歳の婦人は見事な作品を仕上げて、 額に収め談話室に飾った。
市川さんは浴室の前に吊るす「ゆ」の暖簾の制作を頼んだ。
わたしが訪れた木曜日は、 特別のボランティアが来て、 ザルソバ、 わらびもち、 煮豆の昼食を全員のために用意された。
自室で食べる人、 食堂でみんなで一緒に食べる人、 好き好きである。
かいま見た居住者たちの生活の一部であるが、 共に住まうという楽しさと安心感、 人に対する優しさが育まれているのを感じた。
冒頭に記した市川苑長が開口一番に発した「楽しい」というのは、 協同居住の確かな手ごたえを得ることの充実感と自信だと思う。
協同居住の確かな手ごたえが日を追うごとに、 居住者の生活に現れてくる。
居住者の多くは避難所や福祉施設の一時入所、 一般仮設住宅、 親戚宅などから移ってきたが、 ここに入居してみたら案外このような住まい方もいいものだと実感しつつあるという。
このケアつき仮設住宅の入居対象者は、 入浴、 炊事、 衣服の着替えなどに一部の手助けを必要とする程度の高齢者であるが、 一般の仮設住宅も同様な手助けを必要とする人は少なくない。
また身体的に元気であっても、 生きる気力も失せて途方に暮れている人、 将来の生活に不安を持つ人が多い。
仮設住宅の中で孤立無援の状態におかれていることが一番つらい。
生きる気力を取り戻すには、 この共に生きるコレクティブハウジングの住まい方が適しており、 日本の土壌にも育まれつつあることが、 ここを訪ねて実証された思いである。
それぞれ独立した住戸で暮らしながら、 コモンルームを核に協同生活を展開していくことは、 安全性、 共に住む楽しさ、 心理的な安心感が生まれる。
わが国にも少し前から北欧のコレクティブハウジングの先進事例が紹介され始め、 そのニーズの社会的気運も出てきつつあるが、 震災というつらい体験を得て、 そのニーズの加速度が増したといえよう。
今、 阪神間の復興まちづくりのために、 コレクティブハウジングを供給する時が来た!
兵庫県が事務局を設立し、 庁内プロジェクトチームなどでサポートしています。
現在以下の4つの活動を行っています。
(1)“土曜いどばた会議”の開催
2)ふれあいセンターの早期開設と100戸未満の小規模団地への追加設置を是非とも実現すべきである。
3)応急仮設住宅で生活環境改善(雨水排水対策、 案内標識・案内板の設置)を早急に実施する必要がある。
4)心のケアについては、 専門家による対応の一層の充実を図るとともに、 被災者同士がふれあいを深め「心を癒しあう」機会の創出、 コミュニティづくりが急がれる。
5)行政の被災者に対する情報、 あるいはミニコミ紙等の民間情報を含め、 総合的かつ一元的な最新情報を速やかに提供する仕組みが必要である。
連絡先:事務局・県民会館6階 TEL.078-321-2994 FAX.078-321-3099
しかも雷雨。
翌日9月の声を聞くなり朝晩はうそのように涼しく、 花にとってはようやく一息という思いのことでしょう。
芦屋市朝日丘町の方から突然お手紙を頂戴し、 お叱りとばかり思っていたところ、 『こんなにすばらしいプレゼントを…(中略)…これをステップに頑張る勇気がわいて参りました。』
この方の土地に撒いた人達にもコピーをお配りしました。
この手紙が私たちにも“一息”となりました。
秋の準備に向けて頑張ります。
10月の第2週に撒けるよう各地域の準備をお願いします。
今、 花が咲いている地域はそれを耕してからということになります、 初めての場所は前回と同じ要領ですが、 面撒きを優先したいと思います。
9月中旬に花の種類をお知らせしますので住民の方々でご検討いただく会もご準備願います。
vol.1に比べページ数が約1.5倍になり、 復興まちづくりの地元の活動がしだいに活発化していることを物語っています。
大都市大手書店で発売中。
事務局までまでアクセスを!。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
P.4
1.調査の目標
震災の被害については三学会の緊急調査があるものの、 本格的な統一調査はその後ほとんどなされていない。
2.現在までの成果と概要
1)倒壊及び使用不能建物の件数は、 30%を越す地区が、 20町丁目数のうち12に及び、 あらためて住吉の被害の大きさと人口流出が明らかになった。
いわゆる文化住宅(木造賃貸アパート)では113棟中75棟が倒壊し、 725世帯中約500 世帯が被災している。3.どのように住民に投げかけるか
人々がいなくなり、 地域組織が崩壊した今、 最大の難問である。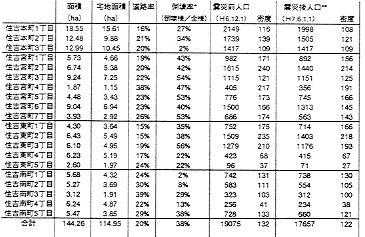
町丁別面積・人口・倒壊率(6/10調査時点)
**震災後人口は区役所に転出入届の集計に基づいており実態とは異なる。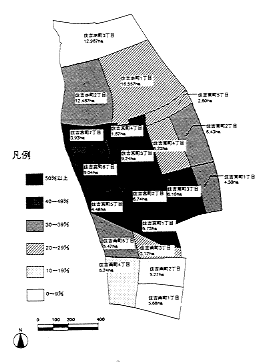
町丁別倒壊率(倒潰棟/全棟)
コレクティブハウジングが根づく確かな芽が育まれつつある(その2)
芦屋市ケア付き仮設住宅訪問記
石東 直子(石東・都市環境研究室)
「今、 この仕事をしていて、 本当に楽しいんよ」と、 のっけからに市川禮子さんは言う。
(8/20記)
共同リビングでの食事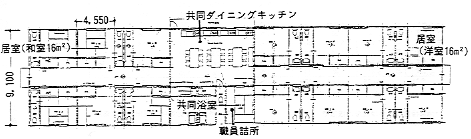
芦屋市呉川町ケア付仮設住宅平面図
INFORMATION
「被災者復興支援会議」の活動状況
被災者復興支援会議(7月17日発足)は、 各界の専門家12人で構成され、 被災者と行政の間に立って被災者の生活再建の支援策等を提案、 助言することを目的としています。
被災者復興支援会議第1回提案・8/28
1.基本的考え方
1)「被災者」の復興に向けて―「被災地」の復興と「被災者」の復興は表裏一体
2)被災者は今を生きている
3)分かち合いともに生きる社会
4)将来の展望を開く
5)復興への国家的取組み
2.当面取り組むべき課題
1)恒久住宅の具体的建設計画を速やかに住民へ提示するとともに、 応急仮設住宅の入居期間を明らかにする。花咲かだより・その5
連日の炎天下に息もたえだえの花たちでしたが、 8月最後の日に待望の雨。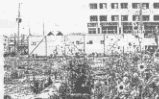
一面焼け跡となった鷹取地区(長田区)に
咲いたヒマワリ
鷹取商店街の仮設店舗も建ち始めた。ネットワーク事務局より
「復興市民まちづくりvol.2」発刊
多くの方々のご支援により「復興市民まちづくりvol.2」(学芸出版社、 253ページ W゛、 2,060円)を発刊できることになりました。
「復興市民まちづくりvol.2」表紙「きんもくせい」の発行状況など
ネットワーク会議等
第9回東部市街地連絡会(毎月第3火曜)
日時:9月19日(火)18:30〜
場所:神戸富士バンクビル
コレクティブハウジング事業推進応援団・第1回ミーティング
日時:9月21日(木)14:00〜17:00
場所:神戸富士バンクビル
問合せは当ネットワーク事務局まで
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい16号へ
きんもくせい16号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ