 図1:ラプラドが基本計画を構想したカルチェ・レゼルヴェ(カサブランカ)
図1:ラプラドが基本計画を構想したカルチェ・レゼルヴェ(カサブランカ)■ 第6回 パリのモロッコ ■
モロッコという国は、確かに北アフリカの国であり、またイスラーム世界に属する国である。しかし、北アフリカや中東の中でも、とりわけ地中海に接するあたりの国々は、古くからヨーロッパ諸国との交易によって栄えてきた歴史がある。たとえば、マルセイユ石鹸とアレッポ石鹸、リカールとアラク(アニスの香りのする蒸留酒。水で割ると白く濁る)などは、そうした交易と文化交流の中で育まれたフランスとアラブの共同の産物である。さらにフランス植民地主義の全盛期に入ると、パリで大掛かりな植民地博覧会が開催され、モロッコを含む非ヨーロッパ世界の文化が展示され、市井でもてはやされた。フランスは古くから、世界中の文化の理解者でありたいと欲し、実際にその受容をはかってきたと同時に、一方でフランス語・フランス文化の各国への普及を熱心に推進してきた国である。モロッコの建築・都市文化もまた、様々な形でパリに持ち込まれ、多文化の首都の一画を担っているのだ。今回は、そうした形でパリに息づいているモロッコについて、歴史もささやかに踏まえながら見ていこう。
1931 年に開催されたフランス植民地博覧会では、本書でも登場したリヨテ将軍(博覧会時には元帥)が総括となって、自らの「旧領」モロッコを盛大にアピールしていた。会場の設計は、やはりリヨテ時代のモロッコで活躍した建築家、アルベール・ラプラドであった。ラプラドは、モロッコの歴史的な都市空間を模倣し再現することに情熱を傾けた都市デザイナーであり、その作風は中庭や狭い街路、袋小路といった、典型的なモロッコ都市のボキャブラリーを多用するものであった(図1および図2)。この植民地博覧会の会場設計者として、まさにうってつけの人物だったのである。 図1:ラプラドが基本計画を構想したカルチェ・レゼルヴェ(カサブランカ)
図1:ラプラドが基本計画を構想したカルチェ・レゼルヴェ(カサブランカ)
 図2:カルチェ・レゼルヴェ現況。設計はカデ&ブリオン
図2:カルチェ・レゼルヴェ現況。設計はカデ&ブリオン
残念ながら、博覧会の終了とともに、ヴァンセンヌに設営された会場も建築物も取り壊された。しかし、ここでいくらかの写真を紹介しておきたい。図3から図6は全て、会場内に設営されたモロッコ・パビリオンである。中庭、馬蹄型の入口、スーク(市場)といった、モロッコ建築・都市の特徴的な要素を再現している(図版は全て、パトリシア・モルトン 長谷川章訳『パリ植民地博覧会 オリエンタリズムの欲望と象徴』ブリュケ、 2002 年、 pp.219-226 からの孫引きさせて頂いた)。
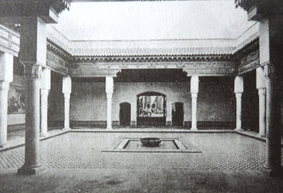 図3:モロッコ・パビリオン中庭
図3:モロッコ・パビリオン中庭
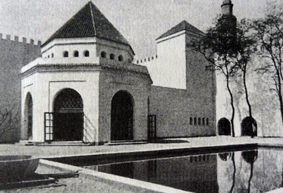 図4:同入口
図4:同入口
 図5:同スーク
図5:同スーク
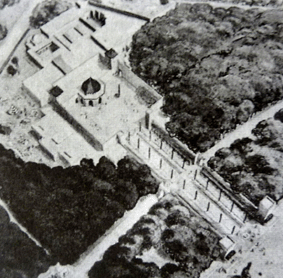 図6:同鳥瞰図
図6:同鳥瞰図
そして、パリにおけるモロッコ建築は、博覧会が全てではなかった。イスラーム教徒にとってもっとも大切な、他ならぬモスク建築が、パリのカルチェ・ラタンに建設されていたのである。現代でもフランスで最も重要なモスクであるとともに、文化発信、観光の拠点でもあるパリ・モスク(5区)である。建設年は、博覧会よりも5年早い1926年である。設計はロベール・フォルネ、モーリス・マントゥーのフランス人2人である。最大の特徴は、フェスのカラウィーン・モスクを範に取ったデザインである。四角平面のミナレット(図7)や、細やかなゼリージュ(モザイクタイル)を貼りこんだ壁や柱の装飾(図8および図9)などは、全くもってモロッコのものである。 また、モスクを運営するための伝統的な寄進の制度「ハブス」(正則アラビア語でワクフ)も、このモスク建設とともにフランスの承認の下で整備されていった。
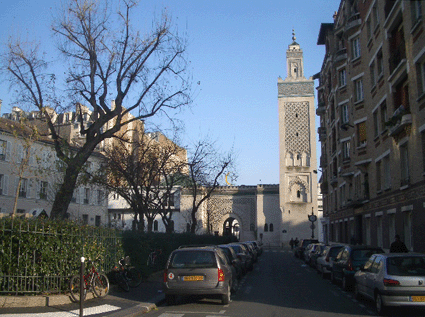 図7:ミナレットの写真
図7:ミナレットの写真
 図8:壁のゼリージュ
図8:壁のゼリージュ
 図9:柱のゼリージュ
図9:柱のゼリージュ
〔パリ・モスクURL〕
http://www.mosquee-de-paris.org/
もっとも、壁を共有するフェスの旧市街のカラウィーン・モスクが密集市街地の中にピッチリと埋め込まれているのに対し、明晰なアパルトマン街のブロック上に立地するパリ・モスクは周辺を武家屋敷のように白壁で囲われている(図10)。そうすることで外部に対して閉鎖的となる一方、敷地の内部に本格的な中庭を複数配置できているのだが、これは本ブログの第二回「モスクの話」で述べた、フェスの新市街のモスクと極めて似ている現象である。
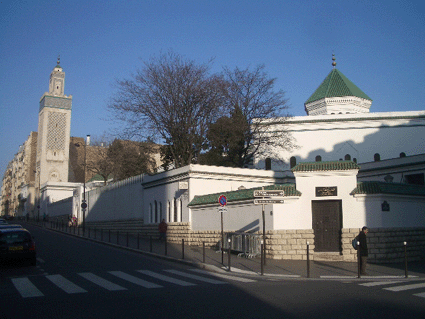 図10:モスク外壁
図10:モスク外壁
馬蹄型のアーチをくぐって中に入る。ただちに目に飛び込んでくるのは、中庭の緑と噴水だ。もっともこの中庭はもっぱら庭園形式で、そこから更に奥へと進んだところに、メインの中庭がある(図11)。こちらは一面タイル張りだ。更にその奥に礼拝室。モスクには一応の基本形式があって、入口から入ってまっすぐ中庭を通過し、噴水で沐浴してから礼拝室に入り、そのままメッカへと向かって礼拝をする。ミフラーブとよばれる窪みがメッカの方向(キブラ)を指し示す。というわけで、入口からミフラーブ、更にその先にあるメッカのイメージまでが、直線上に配置されるのが基本なのだ(第二回参照)。
 図11:メインの中庭
図11:メインの中庭
もちろん、敷地の形などによって変形されることも多いし、また、必ずしもミフラーブが正確なキブラをさしているとは限らないこともある(多くの場合は学派ごとのキブラがある)。また、キリスト教会との区別のため、キブラの方向に沿って縦長となるのは忌避されるとも言われる。
パリのモスクも、航空写真から判断する限り、長方形の敷地の中にあって、礼拝室はみごとに45度ほど傾斜して計画されていることが、はっきりとわかる(図12)。実際、礼拝室の入口から見ると、お祈りの方向は斜めにずれているのがわかる。(図13)ここまでやるからには、キブラの方向も正確に算出されているのだろう。幸いなことに、パリ・モスクは一般公開されている。今度測量してみることにしたい。
 図13:礼拝の方向(キブラ)は入口に対して斜め
図13:礼拝の方向(キブラ)は入口に対して斜め
このパリ・モスクの近所には、ジャン・ヌーベル設計のアラブ研究所がある。ヌーベルといえば、建築界に関係のある方なら知らない人はいない巨匠であり、フランス人である。そんな彼の設計になるアラブ研究所は、フランス人によって解釈された、モロッコ建築なりイスラーム建築なりの現代版の系譜に連なるものだ(図14)。ここでは、壁のモザイク・タイルは自動開閉式に変換され、中庭はガラスに覆われている。お祈りスペースはスロープ状の階段の踊り場だ。このアラブ研究所のソフトもまた興味深いが、研究者にとっての拠点でもあるので、またの機会に改めて触れることにしたい。
 図14:アラブ研究所概観
図14:アラブ研究所概観
一方、パリ市内にモロッコ文化、あるいはアルジェリアやチュニジアなどのマグリブ文化が根を下ろしている地区は他にも存在する。モンマルトルの丘の東側、シャトー・ルージュやバルベス通り界隈が、そうした地区にあたる。移民、すなわちマグレブ系、黒アフリカ系の人々が多く住むところなのだ。
街を歩けば、アラビア語も頻繁に目にするし、肉屋はほとんどがハラール肉屋(ムスリムの作法に従って絞められた肉を扱う)だ。アルジェリア製や中国製の安い洋品、雑貨、携帯電話等の店が多いが、他にも、よくわからないアフリカ物産の店とか、焼トウモロコシを売る露店がひしめいていて、平日・土日を問わず大変な活気となる。
そうした中、モスク建築も存在する。パリ・モスクほどかっこよくはない。かつては普通のアパルトマンが建っていたであろう街区の角地が、モスク用地として提供され、2層程度ながらかなり広いモスクとされたもの(図16)。敷地一杯がブロック塀で囲われており、安普請な感じが漂っている(図17)。ミナレットが無いのも残念だが、壁に貼られた「Aidez la Mosquee(浄財求む)」のフランス語が痛々しい。近くにいたアルジェリア人風の紳士に話しかけたところ、モスクは20年程前の創建という。名前はマスジド・ル=ファタハと大書されている(図18)。
 図17:モスク外壁
図17:モスク外壁
 図18:モスク名を示す看板はアラビア語とフランス語の併記形式
図18:モスク名を示す看板はアラビア語とフランス語の併記形式
フランス人によって精巧にデザインされたパリ・モスクと、20世紀も終わり近くに、恐らくは移民自身の手によって建設されたモスク。その意味の違いについては、本書中で私なりの意見を述べておいたつもりである。
更に話しかける相手を物色していると、いい感じの初老の男性を発見。こういうとき私はアラビア語を使うのが怖い。アラビア語が下手だからというより、移民のうち、アラビア語を話したがらない人が、少なからずいるからだ。「ボンジュール」という私の問いかけに、むこうも「ボンジュール、ムッシュウ」と答えてくる。名前と建設年、どれくらいの人が礼拝に来るのか、などが最初に知っておくべき事項だ。最後だけアラビア語で、「シュクラン・ジャジーラン(どうもありがとう)」と礼をいうと、「ラーシュクラン・ルワージブ(どういたしまして)」と笑顔でかえってきた。こういうのはちょっと嬉しい。
嬉しいから帰りにみつけたクスクス屋で食べた。ハラールだからビールは飲めないが、とてもおいしくて6ユーロ。このへんも、住めば楽しい地区なのだろう。