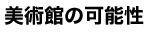
『デザイン理論』(意匠学会編集委員会) 2007.No.50
「美術館という空間の役割は芸術作品を見えるようにし、美術館自身を見えないようにすることに他ならず、作品の可視性の中で忘却させる」とは1970年の『CRITIQUE』の論文である。そこに展開する論理は美術館=額縁論に他ならない。当時、美術館は作品を保存することにある、と考えていた。ところが40年近い時間は、美術品=芸術作品という関係を変化させ、その概念規定も揺れだし変貌させた。
芸術作品を蒐集保存することが美術館の役割であろうか、いや美術館そのものが役目を終了したのではないか、という疑問すら起きている。そこで「美術館の可能性」を真正面から取り上げ、真剣に論及する両氏に敬意を表しておきたい。
美術作品の歴史を研究する並木と、それらを収納・展示する建物の歴史を研究する中川との共同作業が本書を他の類書とは異なる著作に仕上げている。学問分類では異分野となってしまった美術史と建築史からの考察は、美術館を腑分けし、複雑な社会状況における問題点を多視点から捉えている。
歴史現象としての美術品と建物を取り扱わなければならない両者に、社会の動きが速く、次から次へと自己存在を主張し始めた美術品と建物との関係は実に厄介な問題が突きつけられる。美術館・博物館に勤務する学芸員を養成するコースが大学に設置され、美術館・博物館に関する学問的研究から始められたのは極近年のことで、前世紀の後半から陽の目をみる学問領域であり、様々な補助学の助けを借りて初めて成立する学問領域としてやっと市民権を得ている。その研究領域は美術史学・建築史学より広く、その学としての蓄積のお寒いことも認めねばならない。
Museology=博物館学では美術館を美術品の蒐集・保管(含育成)・展示・調査研究する施設と位置づけている。社会教育法の中にある博物館法の規定に従えばそうなる。しかし、現実社会の動向はこの法律より速く変化し、美術品の概念もデュシャンの便器を持ち出すまでもなく、拡大し収拾がつかない状況に立ち至っている。便器を国民の税金で国立国際美術館が蒐集・購入せねばならない状況が発生し、日本の美術館はまさに熱力学のエントロピーそのものになっている。人間という動物の欲望そのものがエントロピーであり、それが美術館を増殖させている。
この現象は序章「美術館で起こっていること」(中川)第一章「概念のあやうさと制度のゆらぎ」(並木)第二章[「モノ」をめぐる場のあやうさ](並木)第三章「美術館は建築表現の課題か」(中川)第四章「まちづくりから求められる美術館」(中川)という各章のタイトルに用いる言葉が示している。「あやうさ」「ゆらぎ」は、今日の美術館の置かれた状況、美術の置かれている位置を明瞭に表現する。ここに明治の文明開化以来、西欧先進国の跡を追い続け、近代化が達成出来ると夢想してきた現代日本がある。
『輸入学問の功罪』で鈴木が述べるように、近代の大規模な異文化受容の過程において受けた呪縛があり、その一つに「美術」を加えることができる。「外からの近代化」を代表する訳語としての「美術」があり、この「美術」が高尚な芸術であり、規範とせねばならないという意識を国民に与えてきた。本来「工藝」であったものが、150年余りの時間の中で変容し、工藝と美術とに分離し、さらにデザインまで成立させてしまった。美術館もその一現象であり、現在の美術館がこの柵から脱却できるのだろうか?という問題を孕む。
第二章の「モノ」を前提とした美術館をみてゆく。国立国際美術館の「便器」は本物ではないが美術品とされ、本物とレプリカ問題が起きる。本物はある種の力を保持しており、鑑賞者は「美」を体験できるとする立場に立つのか、それともレプリカでも「美」を体得できるとする立場に立つのかにより状況が変わる。ここでも美学が問われるのだが、解答は簡単に出せない。
「モノ」としての作品は本来存在した場所にあってこそ雄弁に語りかけてくるのだが、本来の「場」を離脱し展示会場に持ち込まれた時点から「本物」ではなくなる、と考える場合はどうなるのか? 絵画であっても本来の場所から離脱すれば、「本物」ではなく参考品に過ぎなくなる。
事例として、レプリカのみの美術館として大塚国際美術館を挙げ、『……あくまでも美術館にあるのは慎重に取り扱われるべき「本物」であることを前提に話を進めるべきであろう。そうでないと、以降の展示や建築の問題は意味をなさない。レプリカは無限に再生産可能なのだから』と並木はいう。確かにレプリカは再生産可能な存在であるが、実物大の再生であることが、成功の鍵を握っている。シスチン礼拝堂を実物大に再現しており、空間の高さ大きさを実体験できることは重要な意味を持つ。現地では、多数の参観者に取り囲まれ、ラッシュ・アワーの電車の中で天井画を見上げ、ミケランジェロが体感したであろう空間を味わうことが出来ないのだから。
第Ⅲ章で美術館の建築表現に就いて論じられている。現代の消費社会やグローバリゼイションの展開により、「趣味や美的感覚が見えない権力・階級化原理」に基づいて制作された美術作品を鑑賞する能力が限定された階層のみとなる状況に抵抗感が強まり、美術館が「不合理」な存在となりつつあることを前提にし、中川は美術館建築を論じる。「新しい社会の方向性を導くための積極的な提案を行うことも、建築家の重要な職能となってきた。その提案には、建築家の構想力、つまり作家としてのフィクション」が含まれ、その結果「美術館の変革は、主に建築家の作品性の中に問われる事態」が続出していると指摘する。
04年に開館し、様々な建築賞を受賞した金沢21世紀美術館を事例に「最も注目しておきたいのは建物の開放性を見事に実現」し、この美術館のキャッチフレーズ「公園のような美術館」を具現化した、と中川は肯定的だ。「美」の神殿ではない建物が美術館になったと位置付け、「美」=ミューズではなく「遊」=アミューズの『場所を開く』ことが建築家の役目と解することになる。その例証に77年のポンピドゥ・センターと90年の水戸芸術館を挙げる。
ポンピドゥ・センターはグロテスクそのもので「美」の神殿ではないことは明白である。しかし『場所を開く』ための水戸の場合、薄暗く開放感がなく閉塞感を感じる。「芸術」を看板に挙げねばならない柵が建築家を呪縛している、と評者には思える。 |

 |
 |


|