<街の復興カルテ>の目的とそこから学ぶこと
大阪大学工学部環境工学科教授 鳴海 邦碩
はじめに
「被災地は、 人間に例えれば、 怪我人である。 人間と同じように、 回復の程度に応じながら、 段階段階を追って、 治療を行っていく必要がある。 そのために、 復興の各段階で<復興地区カルテ>を作成し、 地区診断をしながら、 計画の目指すべき方向を常に再確認し、 復興計画を進めていかなければならない。 そして<復興地区カルテ>はそのまま、 復興の貴重な記録ともなる。 」震災発生後、 学会を中心として行った緊急被害実態調査が一段落したあたりから、 都市環境デザインに関わる有志が集まり、 『震災復興まちづくりへの提言』を取りまとめた(注)。 上記はその中の一文である。 この考えに基づき、 筆者等は、 緊急被害実態調査で担当した芦屋市について定期的に復興実態調査を進めてきた。
その後、 兵庫県が設置した震災復興調査研究委員会に加わり、 災害復興誌等の企画編集に携わることになった。 その検討経過において、 <街の復興カルテ>の作成の必要性を提案した結果、 取り組んでいただけることとなったのである。
(1)今回の震災では被害がきわめて広域にわたっており、 復興の全体像をつかむためには統計的な数字によるしかない。 そこでいくつかの地区を選び出し、 そこの復興状況を詳細に調査しそれを分析することによって、 リアリティのある復興状況が把握できる。
(2)複数の地区を同時間的に調査し分析することによって、 被災地の全体的な復興がどこま続き で進んでいるかを、 推測することができる。
(3)さらにその分析結果から読み取とれる問題点に関する考察から、 復興への新たな課題を発見できる。
(4)この継続的になされる調査の結果は、 復興の貴重な記録ともなる。
委員会事務局の方から、 この調査への参加を呼びかけていただき、 下記の担当者で作成チームが編成された。
(1)長田区・須磨区/齋木崇人 (2)三宮周辺地区/角野幸博/山本俊貞 (3)東灘区/重村力 (4)灘区/平山洋介 (5)芦屋市/鳴海邦碩/小浦久子 (6)西宮市/田端修 (7)一宮町/田原直樹/三谷哲雄 (8)仮設住宅1/大西一嘉 (9)仮設住宅2/松本滋 (10)仮設住宅3/石東直子
東西の違いは、 空地の状況にもある。 西では、 比較的狭い空地がフェンスで囲まれて残存しているのに対し、 東では、 比較的大きな敷地が空地で残り、 ミニ開発やマンション化の進行が予想される。
震災後およそ1年半の時点における定点調査対象地区の復興状況を取りまとめた報告書が、 近々兵庫県から刊行される予定である。 この調査の結果が、 復興推進に少しでも役立つことを、 調査担当者一同、 切に願っている。
(5月8日 記)
(注:『震災復興まちづくりへの提言』ASHIYA倶楽部、 1995年7月)
p1
3つの協議会でそれぞれ方法は異なるが可能な限り住民の総意が表れる努力がされた。 ・役員会で施設配置計画案を一つに絞った後、 住民集会、 ニュースで周知をはかり、 アンケート調査を行い、 その結果を住民集会で承認し決定した。 (桜備4ブロック)
杯まで使うと高層にならざるを得ないことは理解されたが南面住宅を増やすこととな
る。
それにしても「きんもくせい」と「復興市民まちづくり(学芸出版社)」は六甲道南地区のコンサルをしていく上でも、 他の地区はどうなっているのだろう、 他のコンサルは着々成果を上げているのだろうかとその情報は常に励みになりライバル意識と頑張る意欲をかき立ててくれるものであった。 心より御礼申し上げると共にここまでやってきていただいたスタッフの皆様に衷心より敬意を表します。 本当にありがとうございました。
(5月11日 記)
しかしながら、 海外へ発信する情報はさほど多くなく、 また海外との都市計画事情の違いなどにより、 現在進められている我が国の復興の状況がなかなか伝わりにくいといった状況も生じています。
そこで、 この「きんもくせい」をなんとか海外に紹介できないかをこの間ずっと模索してきていましたが、 六甲アイランド基金の助成を契機に、 やっと“KINMOKUSEI” INTERNATIONAL PROJECTを開始することができました。
現在数名のプロジェクトチームを組み、 翻訳家の参加も得ながら作業を始めています。 まず最初に行っていることは復興まちづくりに関する辞書づくりです。 たとえば、 “まちづくり”の一言をとってみても使われ方、 内容は多岐にわたっており、 単純に翻訳できる代物ではありません。 我々の最初の関門は、 これはこれで一大作業であり、 多方面の方々から適切なアドバイスをいただかなければできないものと考えています。
辞書が完成すれば、 各報告のタイトル・見出し等の翻訳→本文の翻訳、 というふうに順次進めていき、 この夏の終わりぐらいを目途に全体の完成を考えています。 インターネット等の活用については、 タイトル・見出しの翻訳が出来次第ホームページを開設する予定です。 このプロジェクトに是非参加したいという方は、 下記事務局までご連絡ください。
震災後幹線道路の事業計画決定が行われた神戸市西須磨地区において、 住民主体のまちづくり運動を活発に展開している西須磨まちづくり懇談会が、 震災後の活動記録として詳細にまとめた力作です。 (A5版、 ¥1,200、 エピック社)
5月より10月まで各月1回、 共に暮らす意味や中庭などの共用空間の使い方や維持管理について考えていきます。
<第1回/暮らしのワークショップ>
―「育む」をテーマに共に暮らす意味を考える―
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
復興カルテの目的と作成メンバー
この<街の復興カルテ>の作成の目的については、 以下の事項があげられた。 復興の概況
復興の全体的な状況を見ると、 被災地の西で遅く、 東で早いという一般的な傾向がある。 住宅の新設着工戸数や復興住宅の供給計画をみると、 西では推定滅失住宅戸数になかなか届いていないのに対し、 東では、 震災前を上回る住宅が供給されつつある。 しかし、 中には建築確認申請なしで建築されている住宅も少なからずあるように見受けられ、 復興状況を正確に把握することは難しい。 <街の復興カルテ>から読み取れる主な復興
今回の定点調査の結果から学ぶべき主な課題と、 それを示唆する具体現象を例示的に示しておきたい。 (1)復興停滞空地(震災空地)の課題
*“原っぱ”化した市街地は少しずつ復興に向かってはいるが、 地震発生から2年経過した時点になっても、 住宅再建は順調に進んでいるとはいえず、 “原っぱ”の部分が残っている。 (神戸市:灘区)(2)景観形成上の課題
*住宅ではプレファブ住宅による再建が目立つ。 小規模宅地ではプレファブ住宅による再建が多く、 町並みの変化が大きい。 (神戸市:長田・須磨区、 芦屋市:竹園地区)(3)住宅のニーズと供給とのミスマッチ解消の課題
*震災前の戸建て住宅宅地に非木造共同住宅が建つ例があり、 一般的な住宅市場内での供給であり、 震災前に長屋・木造共同住宅が地域の住宅構成の中で果たしていた役割を新たに担うものではない。 (神戸市:東灘区)(4)応急仮設住宅の解消上の課題
*仮設団地に何とか復興住宅を建ててくれないかという声が上がり、 仮設住宅自治会で2,900もの署名を集め、 兵庫県や神戸市に要請している。 (東加古川仮設住宅団地)(5)事業所再建支援上の課題
*盛り場であるにもかかわらず沿道全体の80敷地中、 空地が20敷地(放置1を含む)もある。 裏通りにはさらに空地が目立つ。 土地、 建物、 テナントの所有者がそれぞれに異なる複雑な権利関係のもとでは、 再建の合意を得ることが難しい。 (神戸市:東門街)
まちづくり提案(街区別施設配置計画)を終えて
―六甲道駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業の報告・第3回――
(株)環境開発研究所 大阪事務所長 有光 友興はじめに
「きんもくせい」第27号で報告したとおり昨年(1996年)3月17日に公園・道路の配置計画案が決まった。 その後3つのブロック協議会はまちづくり提案に向けての作業に入った(もう1つの深田4南ブロックはすでに事業計画決定済み)。 そして2つのブロックは昨年12月16日に、 残り1つのブロックは約3ヶ月遅れたがそれぞれ神戸市長宛に「まちづくり提案」を提出した。 本稿ではこの間の経緯と震災後から関わってきコンサルタントとして約2年間を振り返って感ずるところを報告する。 1.まちづくり提案に至るまでの経緯
公園・道路の配置案が連合協議会で決定したとき、 公園の規模は概ね1haということであった。 各街区の施設配置計画と残存マンション住民意向により最終形を決めようとするものである。 3つのブロック協議会は、 これを念頭に役員会、 住民集会を繰り返し合意形式をはかっていった。 (1)合意形式(案の絞り込み)の方法
―詳細日程は省略―
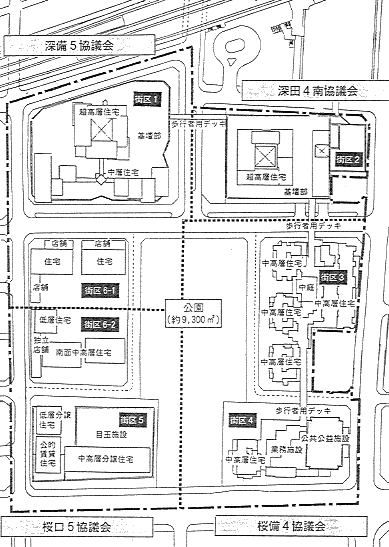
各協議会のまちづくり案の概要(2)合意形成過程での論点
2.まちづくり協議会のコンサルタントを担 当しての所感
震災直後から六甲道南地区の復興計画には関与していたが、 市の住民への説明会に立ち会ったのが1995年3月5日、 解体したメイン六甲B.C棟の区分所有者集会でコンサルとして選任されたのが3月26日、 3つのまちづくり協議会が設立され(6月18日)そのうちの1つ深備5ブロックのコンサルに選任され役員と顔合わせしたのが7月1日、 それから今日まで六甲道南地区と徹底的に付き合ってきた。 これからも続くがまちづくり提案の段階を終えた機会にこれまでのことをコンサルタントとして整理しておく。 (1)地元住民の思考の変化
(2)コンサルとしての充足感
おわりに
「きんもくせい」はまもなく第50号で終刊されるというので、 本誌読者へはこれが最後の報告となるが、 本事業の経緯については今後も色々な機関を通して報告し、 ご批判を得たいと思っている。 
六甲駅南地区街区別計画模型
“KINMOKUSEI”INTERNATIONAL PROJECT START!
未曾有の被害をもたらした大都市型災害である阪神大震災は、 海外でも非常に関心が高く、 震災後早くから海外(とくにアメリカ西海岸)の専門家、 行政関係者らが多数被災地を訪れており、 被災地の復興まちづくりに関わる人たちとの交流が行われてきています。 また、 最近では被災地から海外へ出向いた交流も多くなってきています。 復興まちづくり書籍の紹介
=「住民主体への挑戦-被災地須磨のまちづくり」=
本の表紙INFORMATION
南芦屋浜/暮らしのワークショップ開催 のお知らせ
南芦屋浜地区では、 平成10年春の入居までの期間に、 入居予定者を中心にボランティアや周辺住民と環境形成にかかわる専門家との協同で暮らしのワークショップを行うことになりました。
このワークショップに興味を持たれた方、 参加したい方は下記まで申し込んで下さい。
<応募先・問い合わせ先> まちづくり(株)コー・プラン/吉川健一郎
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
NHKテレビ『未来潮流』<都市をみる目>
ネットワーク事務局より
神戸復興市民まちづくり支援ネットワーク/第19回・西部市街地連絡会
<報 告>
「新長田駅南再開発事業における住宅」/太田尊靖(都市・計画・設計研究所)
「六甲道駅南再開発事業における住宅」/有光友興(環境開発研究所)
「久二塚6再開発のコレクティブハウジング」/石東直子(石東・都市環境研究室)
<コメント>
茗荷 修(神戸市長田南部再開発事務所)
p3,4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい48号へ
きんもくせい48号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ