復興3年目に改めて被災地の街づくりの課題を考える
神戸大学工学部教授 室崎 益輝
さてもう1つの視点、 それは、 涙ぐましい努力がもたらしつつある大きな成果に確信をもつ、 ということである。 被災地では、 被災者を先頭にして血の滲むような努力が日々重ねられている。 復興には矛盾が山積しており、 被災者やまちづくり関係者の努力が、 報われる状況にないことも確かである。 そのなかで、 否定的な側面にのみ目が向けられる傾向が生まれている。 これだけ努力してもの思いがあることも否定できない。 しかし、 その努力が無駄であったかというと決してそうではない。 まちづくりへの胎動など、 明日につながる希望の芽が無数に生まれつつあることも確かである。 大切なことは、 この新しい芽を見逃さず、 大きく育てる努力を怠らないことである。
個を全体につなげるというのは、 個別改善というミクロな努力を都市復興というマクロな視点から問い直すということである。 防災まちづくりということでは、 個別に住宅を耐震化したり不燃化するといった努力も大切だが、 家並を揃えるとか緑のインフラを共有するとかいった、 相隣関係に配慮したまちづくりの取り組みも欠かせない。
震災の教訓の1つに、 1人ではどうにもならない、 お互いに助けあわないといけない、 というのがあった。 まちづくりとて同じである。 集まって住み共に助け合うということを意識した空間形成の取り組みが、 ここでは求められよう。 かって、 わが国の都市は大火の経験の中から、 「うだつ」という相隣空間技術を生み出した。 現代にはどのような「うだつ」がふさわしいかを考えてみることである。
全体からみることを協調するのは、 個の限界を知っているからである。 個の足りないところを全体でカバーする、 それが都市計画でありまちづくりである。
阪神淡路大震災では、 河川沿いの緑地や学校に隣接した公園が火災抑制や応急避難のために機能し、 私たちの命を守ってくれたことを思い出そう。 この河川緑地や学校公園は戦災復興のなかで先輩たちが苦労して残してくれた防災遺産なのである。 とすれば、 我々は子孫の命を守るために何を残すべきなのか?
今回と同じような巨大地震は何時起こるかもわからない。 被災地では、 しばらくは大地震は起きないといって、 安心しきっている人も少なくない。 こうした人の多くは、 安全な街をつくることも災害に強い住宅をつくることにも、 消極的である。 しかし、 自分たちだけのことを考えていてよいはずはない。 子孫のことや地球のことをも考えなければならないのである。 子孫にどのような環境や文化を残すべきなのかを、 震災体験を踏まえて考えてみることである。 仮に巨大地震が1000年後にしか発生しないとしても、 それと戦うための文化は、 被災後の今つくりあげなければ、 つくりあげる時がないのである。
被災地における防災遺産を後世に残す取り組みは、 被災地以外の震災予備軍的な都市に対しても、 大きな刺激と励ましを与えることになろう。 シカゴ大火後のパークシステムを軸とした都市復興が、 世界の都市計画をリードしたように阪神淡路大震災後の都市復興が、 世界の防災計画をリードする役割を果すために、 我々は努力しなければならないと思うのである。 (6月4日 記)
p1
(その3)の報告以降、 また8ヶ月が経過したが、 この間、 “復興まちづくり”としては、 「まちづくり協定」の運営が本格的にはじまり、 平成8年度で計16の案件を審議した。
“復興すまいづくり”については、 新在家南町4丁目で共同建替え事業1件が着工し、 去年の6月に着工していた特目賃→民借賃住宅がほぼ完成し入居を待っている。
本稿では、 これらの新在家南地区におけるその後の復興まち・すまいづくりの推進状況を報告する。
また、 まちづくり協定を一般の人々に知ってもらうため、 新在家福祉センターの前に平成8年度の予算で、 まちづくり協定の看板を設置した。
このプロジェクトにおいても、 旧西国街道沿いの建物として、 勾配屋根や1〜2階のデザイン等に留意して計画した。
p2,3
当日は、 まず延藤安弘先生の「住まいを育む」幻灯会に始まり、 グループで自己紹介、 南芦屋浜での新しい暮らしについての「夢紙芝居」づくり、 これから話し合いたいことについてなど、 3時間半にわたって行われました。 現時点では南芦屋浜についての情報がほとんどないため新しい生活についての不安は持ちつつも、 一年後に始まる南芦屋浜で始まる暮らしについて、 「農園をつくって、 みんなで育ててみんなで食べよう」「団地内に温泉を掘って銭湯をつくる」「ふれあいセンターのようなおしゃべりできる場所がほしい」など、 さまざまな期待を盛り込んだ夢紙芝居が発表されました。
次回のワークショップは以下の通り行われます。
今回の作品は96年1月から3月までの記録で、 震災1周年の地区の状況、 区画整理事業凍結期の様子、 東京の狛江高校の修学旅行生が野田北部・鷹取地区を訪れたことなどが映し出されています。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
はじめに
被災地の復興を山登りでたとえると、 4合目までどうにか辿りついたかな、 というのが私の印象である。 もっとも目指す山頂をどこに設定するかで、 残された道程が違ってくるので一概に何合目といえないが。 いずれにしろ、 いままで辿ってきた道筋を振り返ることも、 これから目指す道のりを見通すこともできる、 中間地点に差し掛かっていることだけは確かてある。 中間点にあって再確認すべきこと
これからの復興のあり方を考えるとき、 見落としてならない視点が2つある。 1つは、 言うまでもないことであるが、 被災者の悲しい現実から目をそらしてはいけない、 ということである。 いまだ災害は進行形で、 生活の再建の展望が得られないままに、 満身創痍の状態で苦しんでいる被災者が少なくない。 そのなかで復興という山登りから脱落していく人がいるという悲しい現実がある。 ところで、 1人の犠牲者も出さずに全員が登頂に成功すること、 それが山登りの理想であるといわれる。 このことは、 復興とて同じことである。 被災者のすべてが生活再建を果たしてこそ、 真の復興が成しえたということができ、 そのために最後まで被災者が協力しあわねばならない、 といえよう。 共働と協力の関係を空間化すること
復興のいままでの努力を無駄にせず、 復興をより確かなものとするために、 以下の2点に留意すべきではないかと考えている。 それは、 個を全体につなげることと、 今日を明日につなげることである。 安全のための文化を未来に残すこと
今日を明日につなぐということでは、 被災地の復興への努力のなかで生まれてきた新しい芽を育て、 それを将来の財産として定着化させることが、 大きな課題となる。 コレクティブハウジングやエコロジカルストラクチュアなど、 その実現は容易でないにしても、 将来のためにそれを根づかせることが求められるのである。
新在家南地区復興まち・すまいづくりの実践報告(その4)
(株)ジーユー計画研究所 後藤 祐介
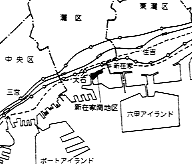
新在家地区位置図○それから
本稿は「きんもくせい」第12号(1995年7月11日)と第24号(1996年2月9日)、 第36号(1996年9月30日)記載事項の続編であり、 できれば旧稿と併せて見てほしい。 復興まちづくり
まちづくり協定委員会の運営
新在家南地区まちづくり協定は、 平成8年6月に神戸市と締結し、 その後、 まちづくり協定委員会を月に1回開催し、 案件の審議を住民の手で行なっている。 これまでの案件は右表に示すとおりで、 平成8年度(6月〜3月)は31件の届出件数のうち16件を審議案件として審議し、 数件について設計の改善を施主と調整した。
届出件数 審議件数 H8.6 2 2 7 3 3 8 5 3 9 4 3 10 3 2 11 1 1 12 6 0 H9.1 1 1 2 0 0 3 6 1 合計 31 16 パンフレットの作成・看板の設置
平成9年2月には、 まちづくり協定の内容を住民の皆さんにより深く知ってもらうため、 新在家まちづくり協定パンフレット(A4・カラー8ページ)を作成し、 全員に配布した。 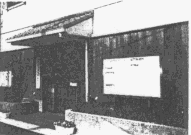
福祉センター前に設置した協定看板
まちづくり協定パンフ表紙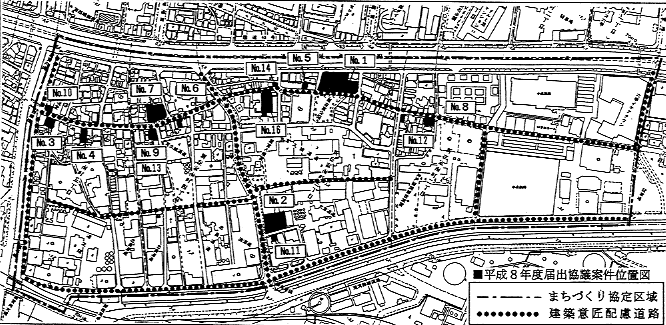
まちづくり協定区域における平成8年度届出協議案件位置図復興すまいづくり
住宅の共同化事業の推進状況
新在家南地区において、 住宅の共同化事業等のこれまでの取組み状況は下表に示すとおりで、 平成9年5月末現在で3件の住宅の共同化事業と3件の公的支援賃貸共同住宅建設事業が着工し、 3件が事業化を計画・調整中である。 1),2),3)の3件は地権者全員の合意が得られず、 事業化を断念した。 3件目の共同再建事業が着工
前号で3丁目A・Bの共同再建事業の着工を伝えたが、 今年の4月に入って、 4丁目-C街区の住市総による共同化補助事業がようやく着工した。 この共同建替えについては、 24号でもお伝えしたように、 公道の付け替えを行なっており、 このための手続きで手間取り、 着工が大幅に遅れてしまった。 
3件の公的支援賃貸住宅の建設
新在家南地区では、 2件の民借賃と1件の特優賃の建設が進んでいる。 このうち、 S)4丁目-Eは、 竣工目前で、 現在入居者募集中で、 計画戸数24戸のうち、 4戸は従前居住者が入居するので残りの20戸に対し5月現在約60世帯、 3倍の応募がある。 あとがき
これまでの成果
新在家南地区のまちづくりについては、 住民の共同再建手法等の早期説明会にはじまり、 新在家らしい復興を誘導するため「まちづくり協定」を締結し、 官民供働によるルールづくりとすまいづくりをリンクさせて推進してきた。 現在の状況
震災後2年と数ヶ月の現在で、 人口、 世帯数の回復率は52%と約半分で、 土地利用の回復率も49.2%で半分である。 人口、 世帯数については、 今後、 現在進行中の共同住宅が出来ることによって、 その回復が見込めるが、 土地利用については採算面から見ても極めて難しい面がある。 今後の課題、 展開方向
従って、 新在家南地区の今後の復興まちづくり課題は、 地区の1/4にあたる約5haの空地の有効活用が上げられる。 このためには、 まちづくり協議会の立場からの利用検討が必要である。 この他、 当地区まちづくりの展開方向としては、 まちづくり協定を生かした、 より積極的な魅力あるまち並み環境整備事業の促進が期待される。
敷地面積 権利者数 事業種別 計画戸数 進捗状況 1) 3丁目10-A 約720m2 20人 住市総共同化 32戸 工事中 2) 3丁目10-B 約650m2 10人 住市総共同化 32戸 工事中 3) 4丁目 -C 約500m2 5人 住市総共同化 15戸 工事中 4) 4丁目 -D 約650m2 1人 民借賃 24戸 竣工、 入居 5) 3丁目 -E 約450m2 1人 特優賃 16戸 工事中 6) 3丁目 -F 約550m2 1人 民借賃 14戸 工事中 7) 2丁目 -G 約720m2 13人 住市総共同化 28戸 計画推進中 8) 4丁目 -H 約440m2 3人 住市総共同化 18戸 計画検討中 9) 5丁目 -I 約960m2 1人 民借賃 26戸 計画検討中 10) 3丁目 約260m2 4人 住市総共同化 8戸 事業化断念 11) 2丁目 約360m2 2人 民間賃 16戸 事業化断念 12) 4丁目 約920m2 8人 住市総共同化 20戸 事業化断念 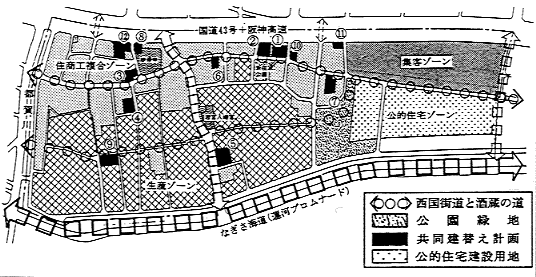
新在家地区復興まちづくり構想と住宅の共同再建事業等プロット図
第1回 南芦屋浜/暮らしのワークショップ開催される
前号でお知らせした南芦屋浜/暮らしのワークショップが、 5月25日に開催されました。 入居予定者・入居希望者26名を含む74名の参加がありました。 
グループごとの「夢紙芝居」の発表風景。
5/25.芦屋市立美術館にて
TEL:078-842-2311 FAX:078-842-2203
「人間のまち、 野田北部・鷹取の人々/「第6部」完成
長田区野田北部・鷹取地区で震災直後から復興映像を撮り続けている青池憲司監督の第6作目となる「人間のまち、 野田北部・鷹取の人々」がこのほど完成し、 上映会とシンポジウムが6月3日、 こうべまちづくり会館において行われました。 
地元の方から震災の話を聞く修学旅行生('96.2/12)INFORMATION
防災家づくりセミナー
第2期コレクティブハウジング事業推進 応援団/第7回ミーティング
阪神グリーンネット報告会/in沖縄
※緑の専門家の集まりである阪神グリーンネットは、 これまで全国の方々から多くの花や苗木などの提供を受け、 被災地並びに被災地の人々にうるおいとやすらぎをもたらす活動を続けています。
沖縄からは、 ヒカンザクラやキバタイワンレンギョウなど多くの花や苗木を継続的に提供していただいており、 お礼かたがた報告会を行うものです。
HAR基金第4回公開審査会
※助成申請受付は6月10日締切です! ネットワーク事務局より
西宮復興まちづくり支援ネットワーク/情報交換会
神戸復興市民まちづくり支援ネットワーク/東西合同連絡会
・7/6シンポジウムについて
・ネットワークの今後の進め方について、 他
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい49号へ
きんもくせい49号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ